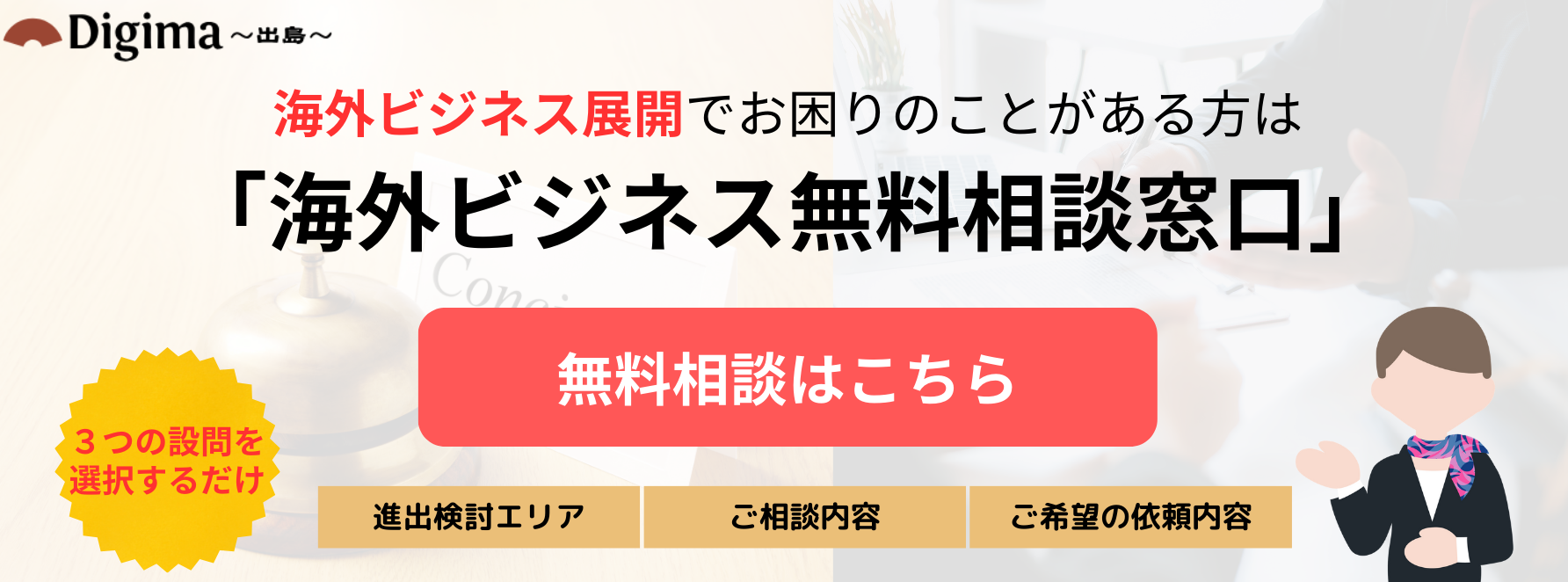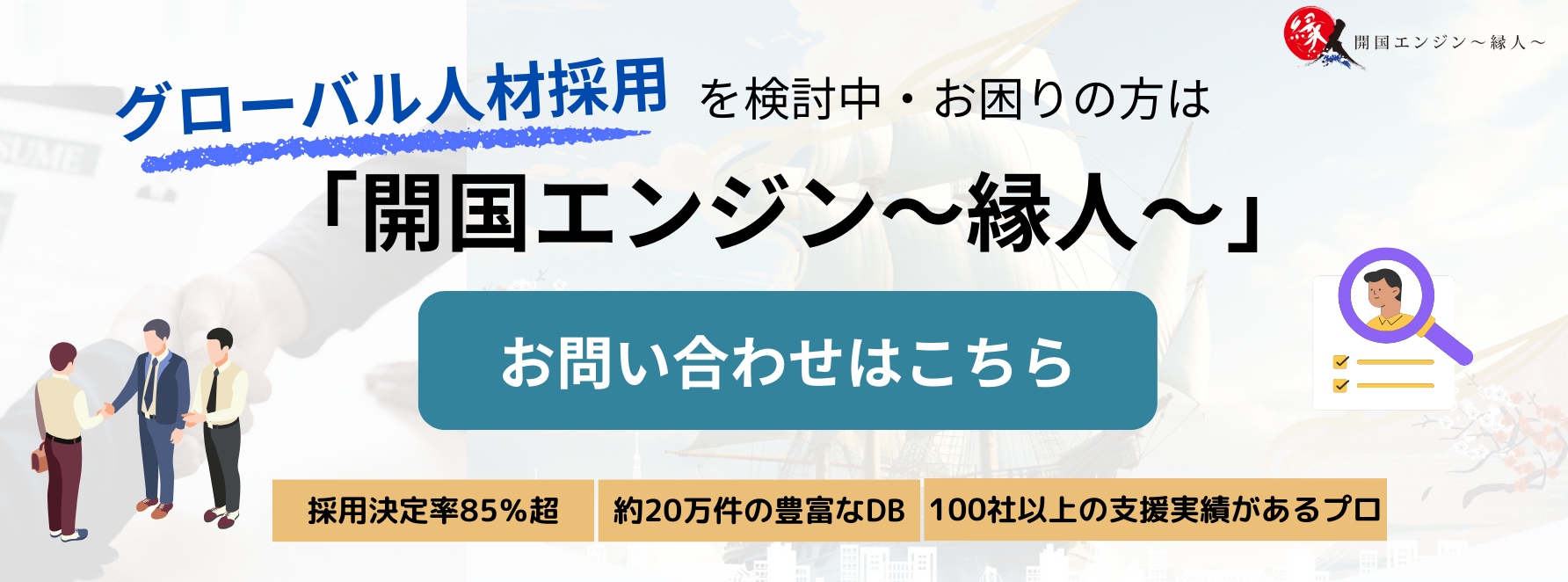- ホーム
- アメリカ
- アメリカ進出インタビュー
- 福岡発のグローバルIT企業「ヌーラボ」が掲げる「海外進出」という名の「世界平和」
同僚にいろんな人がいるっていうのは、とても幸せなことだと思うんです
橋本さんは、自社の海外進出について、どのような感覚でとらえているのでしょうか?
インターネット圏内っていう感じですね。正直、海外進出って言うと、ちょっと変な感じがしちゃうかもしれません(苦笑)
僕らみたいな人って地球上にいっぱいるわけで、そんな自分たちに似た人たちに、自分たちがいいと思うサービスを提供しているっていうだけであって、特別に「海外に進出している」という感じでもないんですよねぇ。う〜ん、なんていうんだろう…?
遠くにいる近い人…みたいな?
そうそう! そんな感じです(笑)。言ってみれば、インターネットっていうもうひとつの国があって、そこに進出しているような感じですね(笑)
それこそ物理的な距離はあるけど、マインドは近いというか?
僕自身が物理的な距離を余り分かってない人なんですね。自社プロダクトの「Cacoo(カクー)」(※オンライン作図・共有サービス)を携えて、初めてニューヨークに行ったときも、一緒にいた役員に「NYの仕事が終わったら、このまま車でAppleの本社まで行ってみよう」って提案したんですけど、「車じゃ無理…」って言われて(苦笑)
僕としては「ちょっとそこまで」って感覚だったんですけど、普段からインターネットで過ごしていると、リアルでは距離がすごくあったとしても、ものすごく近く感じているケースが多々あって(笑)
オンラインならではの独特の感覚ですよね。さきほどのお話にも出ましたが、ご自身はプライベートも含めて、初めての海外がニューヨークだったんですよね?
そうですね。「WordCamp」というWordPress(※世界的なシェア率が高い、オープンソースのソフトウエア)のイベントに企業として出展しました。
そのきっかけも、たまたまカンファレンスの後の懇親会で知り合った、高野直子さんというWordPressの開発をしている会社の方から、近々ニューヨークで開催される「WordCamp」でスピーカーをやるって話をきいたんですね。それで「応援しに行きたいなぁ」って言ったら、「じゃぁ行けばいいじゃん」と背中を押され、行くことが決まりました(笑)
実際に参加してみていかがでしたか?
すごいびっくりしたのが、「当たり前だろう」って言われるんですけど、周りがみんな外国人なんですね。
そうですよね(笑)
それで通貨も違う。
当たり前ですよね(笑)
こっち(ニューヨーク)は昼なのに、日本は夜だったり。
それが普通ですよね(笑)。ただ当たり前のことが新鮮に感じられますよね。
その通りなんですよ(笑)。知識としては分かっていても、実際に体験するのとは違いますよね。改めて「地球って丸いんだなぁ」って体感しました。
現在「Cacoo」ユーザーは、すでに世界中で280万人を超えていて、その約90%が海外ユーザーだとうかがっています。
もともと当時から英語対応だったので海外での反応もよかったんですが、さきほど話した高野さんが、あるブログで紹介してくれて、それがSNSなどで拡散され、さらにlifehacker.comで取り上げていただいたことで、一気に口コミで拡がっていったイメージですね。
もともとCacooって名前を決めるときも、彼女に相談してみたり、僕たちのホームである福岡の街を歩いている外国人の方に感想を聞いたりもしていました。
そもそも自社プロダクトを開発するにあたって「海外仕様」という考えが元からあったと?

はい。「Cacoo」と連携して国内外で展開している「Backlog(バックログ)」(※プロジェクト管理ツール)や「Typetalk(タイプトーク)」(※ビジネスディスカッションツール)も含めてそうですね。
まぁもともとは…憧れから始まっているというか、行ってみたいなぁって気持ちがあって、それから…売ってみたいなぁって気持ちに変化していった感じですね。
ローンチ後、口コミで自社プロダクトが世界に拡散していくことは想定内だったのでしょうか?
そうですねぇ。想定内っていうと頭のいい人みたいな感じになっちゃうので、僕の中では妄想内…妄想圏内っていう感じですかね(笑)
(笑)橋本さんは、普段からよく妄想をされるんですか?
普段からよく妄想してますねぇ。誰かとシェアしたりもしますが、そもそも僕自身はほぼ妄想と衝動で動いてるようなものなんで(笑)
昨年、とある大手IT企業で海外事業に尽力されていた方とお話しさせていただいたんです。彼いわく、ある外国の都市でいい感じのカフェに入って、そこでコーヒーなんかを呑んでると、ふと「ここに子会社つくりたいなぁ…」って気持ちになると。で、「それは気をつけた方がいいよ」って言ってましたね(笑)
危ないぞと?
そう。お店の雰囲気がよかったり、風景が素敵だと、かなり危険らしいですねぇ。だから最近では、自分の衝動に対して、少し距離を置くようにしていますね。
国内(福岡・東京・京都)に加えて、すでにシンガポール、ニューヨーク、アムステルダムに拠点を構えていますが、それこそ妄想ではないにしろ、各都市を選択した根本的な理由には何があるのでしょうか?
そうですねぇ。個人的に何らかの物事を決める場合、まずはファーストインプレッションがあって、その後にロジックをつけていくパターンは多いですね。ですから…直感という意味では、ウチの海外担当者が何かを感じて、その直感を活かしてロジックを組んで…という線はあり得るかもしれません(笑)
まずは直感が働いた後に、例えば「シンガポールに子会社を作りたいです。なぜなら“人・モノ・金が集まる東南アジアのハブ都市”だからです」というビジネスロジックの理由付けをしたとか(笑)
もちろん、日本→シンガポール→ニューヨーク→アムステルダムと順番に拠点を作っていったのにはちゃんとした理由がありまして、各都市の稼働時間がシームレスにつながることで、プロダクトのアップデートや新機能の開発、さらにはユーザーサービスにおいても、より迅速かつ効率的に対処できるというのがあります。
ただ、基本的に僕は「承認係」なので、自分のアイデアではなく誰かのアイデアに対して「うん、いいんじゃない?」って決まっている感じはありますね。
最新の情報ですと、シンガポールにて新たなコミュニティスペースをオープンしたとうかがっています。

はい。シンガポール社のオフィスと兼用で、ヌーラボユーザーだったら誰でも無料で利用できるアジアンコミュニティスペース「NuSpace(ヌースペース)」をオープンしたんです。
他のASEAN諸国と比べて、シンガポールにはミートアップ系のイベントやコミュニティでの交流が盛んな国なんですね。僕らが提供しているプロダクトを通して、ユーザー同士のコラボレーションや新しい仕事が生まれてくれたら嬉しいですね。
ではアムステルダムとニューヨークについてもうかがいたいのですが、まずは今年(2018年)の2月にオープンしたばかりのアムステルダム社について。そもそもなぜアムステルダムだったのでしょうか?
まず前提として次の拠点がヨーロッパである必要があったんです。なぜヨーロッパなのかと言いますと、もちろんヨーロッパにもたくさんユーザーがいますし、さきほどもお話しましたが、日本を含むアジア圏と、北米であるNYの拠点間には、仕事時間のかぶりがないので、その中継地点が欲しいというのが、ヨーロッパに拠点を設立した理由のひとつではあります。
ただ、なぜアムステルダムにしたのかと聞かれると、そこはもう誤差になってくるんですね…。
誤差とは?
もともと選択としては、ベルリン、パリ、アムステルダムがあったんです。ただ、ベルリンの場合だと、近年世界中のスタートアップ企業から注目されているだけあって、地代家賃も次第に上昇しているんですね。
パリにしても、MicrosoftやFacebookが支援している「Station F」がスタートアップ施設として話題になっていて、それをきっかけにたくさんの企業やお金が現地に流れているので、これもまた地代家賃が高くなるなぁって思って。
だから…じゃぁアムステルダムかな? って感じですね(笑)
アムステルダムも次世代のスタートアップ都市として話題になりつつありますよね。では現地ではどのような業務を?
現状では、まだ登記が済んだばかりなのですが、マーケティングに関わる開発がメインとなる予定です。例えばランディングページを作ったりとか、それ周りのマーケティング要素も盛り込んだ業務になると思います。
続いてはニューヨークですが、そもそも IT系企業なら普通なら西海岸辺りかなと思うのですが…失礼ですが、逆張りとか…?
そうですね。逆張りですね(笑)。僕らが本社をずっと福岡に置きっぱなしなのも、ある意味、逆張りなところもありますし。それこそシリコンバレーやサンフランシスコだったら、「ふ〜ん」だったと思うのですが、ニューヨークとなると「お?」ってなると思うんですよ。
確かに(笑)。ではニューヨーク社の規模や様子は?
20名くらいが入るオフィスです。ちょっとだけ改装して、それなりにオシャレな感じではありますね。マーケティングスタッフや開発者がいて、Cacooのフロント側の開発はニューヨークでしています。
日本人は2名だけで、ほかは現地の方々という構成になっています。ただ、ニューヨークの場合、現地の方々といっても、大体がローカルではなかったりするので、多様性はありますね。
とてもニューヨークらしいですね。加えて「多様性」というワードこそが、ヌーラボという企業にとって、もっとも重要なキーワードのひとつだと思うのですが?

確かに。サービスのグローバル展開と合わせて、メンバーも多国籍化が進んでいます。社内の行動規範である「NUice Ways (ヌイス・ウェイズ)」の中にも、あ…「NUice」というのは、あくまで社内の造語で「Nice」と「Nulab」を混ぜた単語なんですが(笑)…、その中でも「ちがうことは、すばらしい」と掲げています。
そもそも、同僚にいろんな人がいるっていうのは、とても幸せなことだと思うんです。
ヌーラボにはそれに幸せを感じる人たちが集まっている?
…だといいなぁって思ってます(笑)
今回橋本さんに取材をお願いした理由のひとつが、「なぜ、世界に進出するのか?へ対しての僕の回答」というブログエントリーに感銘を受けたからなのですが、そこに書いてある回答にもつながりますよね?
「結果的に「世界平和のためだなぁ」という考えに至りました」ってやつですよね(笑)。もうね、やっぱり結局そうなっちゃうんですよ。
なぜ海外進出が世界平和のためになるのか? 改めて教えてくれますか。
例えば、ある国のことが嫌いな人がいたとしますよね? でもその国に自分の会社の同僚が働いていたら、単純に嫌いとは言えなくなると思うんです。
少し前に台湾で大きな地震があったときも、実際に現地でリモートで働いてくれているメンバーがいたり、僕らのサービスを使ってくれてるユーザーさんもたくさんいらっしゃるので、本当にリアルな心配事として心が痛むんですね。
人ごとじゃないですもんね。
そう、まったく人ごとじゃないんですよ。
あるいは以前に博多駅前の路上に大きな穴が空いたときがあったじゃないですか? あのときは逆にニューヨーク社の人たちから、ものすごく心配されたんですね。
だから彼らにとっても、それが人ごとじゃなかったりする。
ただ知ってる人がそこにいるってだけで、世界の出来事がまったく違ったとらえ方になる。とたんに自分ごとになる。
あるいはLGBTなどに関しても、身近にそのような方がいるといないとでは、まったく考え方も違ってきますよね。
だから、そういった多様性みたいなものが、組織としてどんどん混ざっていくと…なんていうか…幸せだよなぁみたいな(笑)
それこそ組織として圧倒的な多様性を極めるってことは、とても労力がかかることだし、商売として考えた場合でも、意味があるのかどうかわからないですけど、ひとりの人生としてとらえたら、とても大きな意味があると思っているんです。
確かに、世界平和を実現するには、仲の悪い国同士こそが積極的に貿易を行って、相互依存を高め合って、お互いになくてはならない関係になるのが一番の近道だっていう話もありますもんね。
そうですよね。だからあとは、海外に拠点を作ったから商売的にも意味があったね…ってストーリーにしていかないとですね(笑)
最後に、今後の海外事業についてのビジョンを教えてください。

これは昔からの妄想なんですけど…外国のバーに入って、カウンター席でビールとかを呑んでいて、ふと隣の席に座っているお客さんの話が聞こえてくるんですけど、彼らがヌーラボプロダクトの話をしているという…いや、日本では結構あったりするんですよ(笑)
あとは…ヌーラボっていう名前が世界中で知られるようになるのが希望ではありますね。さらに名前だけじゃなくて、ウチの仕事のやり方とか、企業としてのマインドとかが伝わってくれると嬉しいなと。
やっぱりウチの道具を使ってくれるってことは、そのプロダクトの背景にあるマインドや哲学を、ほんの少しでも取り入れてくれたってことだと思うんです。そういう人たちが少しでも増えてくれれば嬉しいですよね。