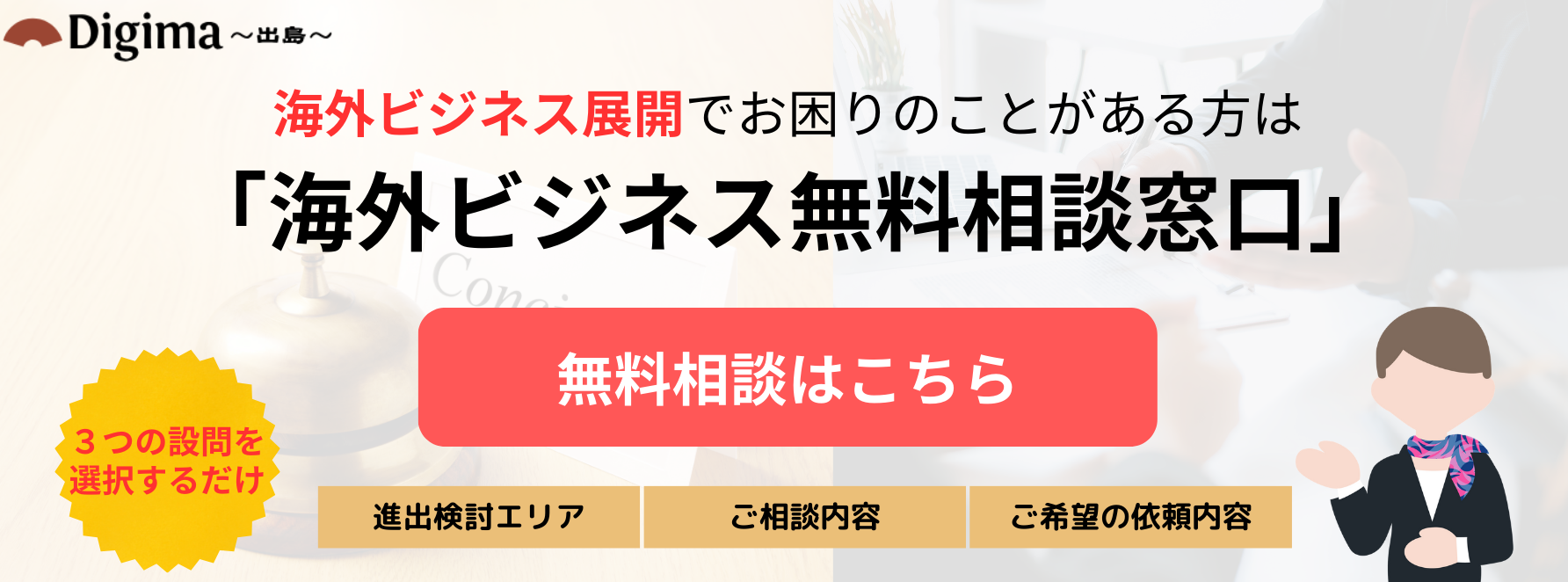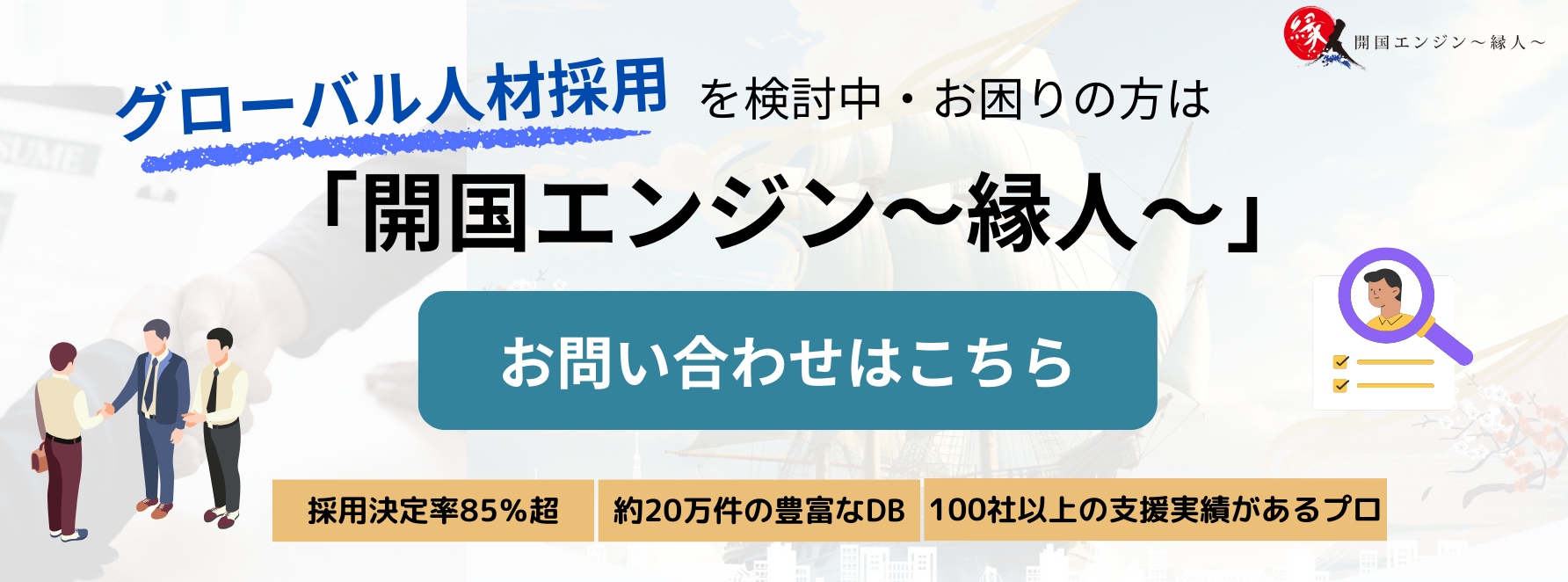- ホーム
- ベトナム
- ベトナム進出インタビュー
- 海外の人的ネットワークを活かした提案型オーダーメイドユニフォーム事業
「国内の海外化」で「技術の集約と移転」という課題を解決
まずは菅沼さんの自己紹介からよろしくお願いします。
オーダーメイドのユニフォームを手がける株式会社ソーイングボックスの菅沼と申します。創業約70年の菅沼縫製所グループという縫製業に特化した会社の3代目になります。
菅沼さんは、以前は医療・介護系コンサルティング会社に勤めていらしたんですよね?
はい。元々家業を継ぐ気はなかったのですが、2011年の東日本大震災を契機に実家に戻りました。簡単に言えば、経営が危うくなったからですね。
具体的にどのように危うくなったのでしょうか?
当時は婦人服ブランドのOEM(Original Equipment Manufacturer=他社ブランドの商品を製造すること)事業がメインでした。婦人服ブランドの多くが海外向け製品を主力としていので、日本があのような災害に見舞われてしまった為に受注が激減してしまいました。さらに弊社の従業員の半数以上は外国人スタッフだったのですが、彼らの多くが帰国せざるを得なくなってしまったんです。
そのような危機的状況の中での再建を余儀なくされたと?

はい。そもそもの会社の成り立ちを申し上げますと、菅沼縫製所は祖父が戦中に始めた会社で、パンツの縫製から始まりました。当時は1ヵ月で10何日程度稼働すれば、従業員の50人は食べられるような時代でした。
次に先代の父の代になると、衣料業界は本格的な大量生産の時代となり、たくさんの量販メーカーさんが市場に参入されました。そんな中で先代はあえてオートクチュールに可能性を見いだして、大手の婦人服トップブランド向けのOEM事業をスタートさせたんです。
ISSEY MIYAKEさんや、コム デ ギャルソンさんといった一流ブランドのOEMですね。
ありがたいことに、当時は大手ブランドさんからのOEMだけで、充分に事業として成立させることができていました。ただ、時代が変わるにつれて、縫製業も含め、日本のモノ作り産業における「技術の集約と移転」という課題が浮き彫りになっていったんです。
具体的に「技術の集約と移転」とは何を表す課題なのでしょうか?

“若年層労働者の不足”をいかに解決するかということですね。製造業と一口に言ってもその中身は多岐に渡り、他の業種と比較すると縫製業にはなかなか人材が集まりにくい。先代の頃はちょうど高度成長期の後期でしたが、その頃から慢性的な人手不足状態は続いています。
我々のケースだと、婦人服ブランドのOEM事業は通常の縫製よりもより高度な技術が求められます。製品単価の高さに比例して服の構造が複雑になったり生地の種類が違ったりして、縫製の複雑性が増していく。その結果、モノ作りにおける構造化の労力も比例して高くなっていく。つまり、それまでの技術と経験に加えて頭の柔軟性も必要とされるんです。
あえて言うならば、熟年労働者の持つ経験だけではカバーできない領域が次第に拡がっていくものの、それをカバーするのに必要な若い人材が国内では慢性的に不足している。そういった「技術の集約と移転」という課題を解決するために、我々が選択した解決策のひとつが「国内の海外化」というものでした。
具体的には、外国人のスタッフを国内の工場で雇うということですね。
そうです。菅沼縫製所グループの特徴のひとつがその「国内の海外化」になります。現在では、スタッフの7割が外国人で残り3割が日本人という割合になっています。
外国人の従業員を採用する際は、ご自身で現地へ赴くのでしょうか?
はい。しょっちゅう行ってますね(笑)。ここ半年に関してはほぼ半分の割合で海外にいます。飲食業や介護事業向けユニフォームの場合はアジアがほとんどですが、アパレル事業だとニューヨークやL.A.にも行くことも度々ありますね。
昨日まではハノイにいたのですが、現地の(就職)説明会には4~50名の方に集まっていただきました。最近弊社を“卒業”したベトナム人の子も来てくれて…、あ、我々は以前日本で一緒に働いてくれていたスタッフを“卒業生”と呼んでいるんです(笑)
そういった海外の“卒業生”の方々が採用のハブになってくれている?

そうですね。外国人スタッフを採用する際、今はどの国もインターネット環境が整っているのでSKYPE面談とかが普通らしいですが、僕らからすれば実際に会うことが当たり前なんです。だって国内で新卒スタッフを雇う場合は、必ず事前に直接会うじゃないですか? それと同じ感覚です。
加えて、外国からわざわざ日本に来てもらうからには、その方のご家族ともちゃんと会っておくべきだと思ってます。何百人採用したいというのではなく、十数人の採用なのですから、そこは丁寧にというか普通のことだと思うんです。
それと、卒業生たちが我々の求めるクオリティを理解してくれているので、技術的にも精神的にも一緒に働けそうな人たちを事前に集めてくれているというのも大きいですね。ここ20年で特にベトナムには、卒業生たちが経営する会社もできていて、現地でのネットワークが次第に拡がりつつあるんです。
海外で人材採用をする場合、海外に派遣する機関、いわゆる送出し機関が存在していて候補者集めは彼らに一任して、日本側はノータッチっていうケースが多いのですが、我々はそれは制度的に使うだけであって、基本的には自分たちで採用しに足を運ぶっていう感覚を強く持って行動しています。
ですから、実は弊社の採用はかなりの倍率ですよ。普通、採用面接するといっても4〜5人集まればいいほうで、我々の場合はその十倍の候補者が集まってくれる。そこが優秀な外国人スタッフが採用できている理由のひとつだと思っています。
外国人スタッフの出身国の割合は?
今は半分以上がベトナムですね。技能実習制度も使っているので、採用する年によって変わりますが、韓国の方も増えています。少し前までは中国、インドネシア、スリランカなどアジア諸国の方が在籍していましたね。
先ほど説明していただいた「国内の若年層労働者不足」以外に、積極的に外国人スタッフを採用しようと決断した大きな理由はなんだったのでしょうか?
ここ4〜5年かけて、生産拠点をいかに海外に移すかというテーマで動いているんです。
実際に、我々の事業規模もかなり大きくなってきていて、今や国内顧客向けの商品販売の多くが海外生産です。それだけでなく、海外顧客向けの商品販売を現地で行うようにもなっています。例えば、ベトナムで生産した商品をベトナム現地やカンボジア、香港で売るということが既に出てきています。この流れは、次世代事業として拡大していくのかなとは思っています。
ここまで「国内の海外化」についてお聞きしましたが、ここでソーイングボックスさんの事業における、もうひとつの大きな特徴である、「オーダーメイド」について聞かせてください。介護事業や飲食業向けユニフォーム産業において、ソーイングボックスさんが手がける「オーダーメイドユニフォーム」の強みは、どこにあるのでしょうか?

前職の医療・介護系コンサルタントをしていた際、行く先々の病院や介護施設でユニフォームに関する不満を耳にする機会が多かったんです。
例えば病院のユニフォームで言えば、既存メーカー4〜5社でシェアの90%を占めている状態だったんですが、単純に「国内に160万人以上いる看護師さんが着る制服を、たった4〜5社でしか作っていないってどうなんだろう?」と。
つまり、ユーザーからしてみると選択肢が限られている。だから本当に着たいと思う服と、実際に作られている服の間にはギャップがあるんだろうなと思って。だったらオーダーメイドの需要があるはずだと。
そこで、「フルオーダー」「セミオーダー」「イージーオーダー」といった、デザイン性と機能性と価格のバランスを考慮したオーダーメイドの提案を始めたんです。現場の皆さんは新鮮に感じていただいたみたいで、大きな反響をいただきました。弊社が今の事業スタイルに舵を切って6年目になりますが、お陰様で順調に事業規模は拡大し続けています。
さらに、ソーイングボックスさんが他のユニフォーム会社と差別化できるポイントは、その「オーダーメイド」をベースにした、新たな「提案」という付加価値、具体的には「コンサル」を加えるということにあると思います。
そうですね、ざっくり言いますと僕らは「ユニフォームを作る会社」ではなく「変化を助ける会社」を目指したんです。
ユニフォームを売る会社は世の中にたくさんあって、オーダーメイドというのは僕らのひとつの武器ですが、もうひとつ「課題解決」という武器もあるんです。
自社のブランド力を強化したい、他社と差別化したい、離職率を下げたい、採用を増やしたい…といったお客様それぞれ抱えている課題の解決を、ユニフォーム作りでやりましょう!っていう会社なんですよ。そこが他社との大きな違いですかね。
もちろん、ユニフォームだけでなく、カバンや帽子といった服以外の製品を提案する時もありますし、最近だと店舗内装やメニューのデザインとか、いろんなものを手がけています。それこそ企業ロゴやCI(コーポレート・アイデンティティ)まで一緒に考えたりもするケースもあるんです。
以前の医療・介護系コンサルティング会社での経験も反映されている?

はい。ベースにある考え方は当時から変わっていません。それをユニフォームでやっているという感じです。昔も今も、病院や介護施設・飲食店にとって、従業員が着用するユニフォームは重要なアイテムですし、自社ブランドのアピールや他社との差別化にも作用するものなんですね。
ですから、会社の従業員の方がステージに立ってファッションショーを開催したり、フランチャイズ展開をしている会社様の組織力を高めるためにユニフォームをお披露目するイベントを企画したり、あるいは地元と密接に関わっているお客様だったら、新規施設を建設する町のイベントに参画することを提案したりなど、ユニフォーム+αの何かを提供することを心がけています。
そのような「総合的な課題解決」を含めた提案をするユニフォーム会社さんは他に存在するのでしょうか?
う〜ん…あまり聞いたことはありませんね。かなり特殊なんじゃないかなと(笑)
今回の「国内の海外化」と「課題解決」というふたつのテーマは、どのように繋がってくると思いますか?
やっぱり国内だけだと、どうしても生産力の広がりに限界があるということですね。僕が家業に参画した6年間で、周りの縫製会社さんの1/3が廃業しているんです。協力し合っていたパートナーがいつまで生存できるかわからない状況で、ずっと国内ばかりに執着してはいけないのではないかという思いがありましたから。
その答えが、海外で日本のブランド力を維持した生産力を持てればいい、ということでした。飲食業の会社さんの多くが、日本国外にマーケットを見いだしている時代ですから。そもそも、新参者がなにかをやろうと思ったとき、今までと同じ流れでモノを作って売ってもしょうがないと思ってますから。
では、国ごとの人材や生産については、どのような内訳で考えているのでしょう?
自分としてはポートフォリオ(組み合わせ)が大事だと思っています。要はバランスをどうとるのかってことですね。
どこかの国に固執するのではなくて、それぞれの国の経済特区の可能性から見たら、どこで作ったら一番利益がでるのかとか、あるいは人材のマネージメントの面で見た時のバランスの良さを考えています。
現在の拠点にしても、今ブームだからベトナムって訳じゃなくて。原材料は中国で調達して、生産はベトナムとか、もしくはミャンマーで作るとか、各工程から導き出した総合的なパワーバランスを見ながらやっています。
アイテムによっては作ることができない国もありますし、例えばカバンだったら韓国では作れるけど、バングラデシュでは難しいかなとか。その国の生産性や商品特性に合わせて選択しないといけないですよね。
縫製作業だけでなく、デザインや+αの提案に関しても、外国人スタッフの方が活躍されている?
そうですね。今一番活躍しているのが韓国人のデザイナーなんです。日本人に限定してデザインを担当してもらう必要もありませんから。現在のファッション系大学やデザイン系専門学校にはたくさんの外国人留学生がいて、成績優秀な生徒さんも日本人じゃないケースが多いんです。
柔軟になりますよ。あるデザインひとつを巡っても、韓国人の当たり前と僕らの当たり前って違うことが実感できますからね。美しいと感じる視点も異なりますし。
お客様に変化を届けるという意味では、色々な見え方や考え方があったほうがいいんです。ある程度作業上の指針を決めて効率良く進めたほうが、生産性という意味では良いかもしれませんが、自分たちはデザインを含めた、新しい発想やアイデアを届けることを大切にしています。
そういった外国人スタッフさんは、大体何年くらいで卒業されるのですか?
平均すると3年くらいですね。技能実習生制度の年数がその要因のほとんどを占めています。
会社としては当然、もっといてほしい、5年でも10年でもいてほしいという声もあります。ただ個人的には、その位の期間でも充分だと思っているんです。基本的にデザイナーとは個人プレイヤーであって、熱意のあるプレイヤーが活躍できる場を提供するのが、自分たちの役割だとも思っていますから。
ウチでの仕事…ある病院のユニフォームをデザインしたり、ある飲食店の内装を手がけたりといった様々な経験を積む中で、さらに自分が追求していきたいことが見つかったら、新しい場所で新しい経験を積んでいってほしい。
我々はデザインを軸とする会社ですが、そもそもデザインのトレンドは時代によって変化していきます。並行してテクノロジーも進化していきますし、人材もさらにグローバル化が推進されていくはずです。あらゆるものが変わっていく中で、当然会社自身も変わっていかなければならないですし、良い意味で一人一人に固執する必要もないと僕自身は思っています。
卒業した子たちが、自分の国に戻ったり、日本以外の国に行って、そこで自分のやりたいことを見つけてさらに成長した後に、また僕たちと一緒に新しい事業を始めてくれている。そんな流動性を保ちながら、全員がハッピーになれればいいなと思っているんです。まぁ、スタッフの子たちの結婚式にもかなり出席してますからね(笑)。みんな家族みたいなものですよ。
昔ながらの伝統的な価値観と、現代のグローバルな価値観が自然に融合しているのが、ソーイングボックスさんならではと思います。最後に将来的なビジョンを教えてください。

1952年の創業なので、恐らく僕の代で100年の会社になるんです。と言いますか、しなきゃいけないと思っていて(笑)。だから100年企業にするには、どういうことをやっていけばいいのかってことだけを考えています。
逆に、そういう視点の方がやりやすく感じています。ユニフォーム業界における自社のシェアを30%に上げるよりも、あと30年継続していこうと考えると、自然となにか楽しいことがしたいなって思うようになるんです。
だからこそ、自分達のように海外への視点を持って、常に変化しようとしている企業の方々と、もっと出会いたいと思っています。もしこの記事を読んで、興味を持っていただけたらぜひお声がけくださると、大変嬉しく思います。