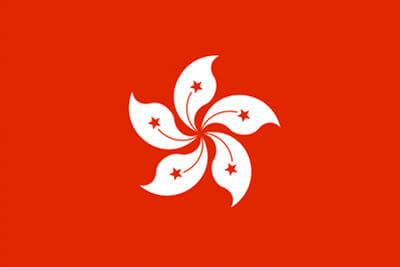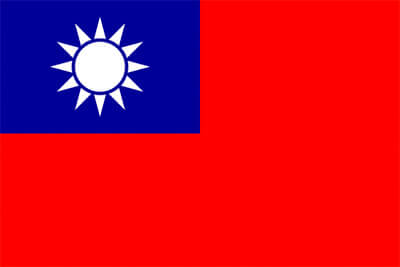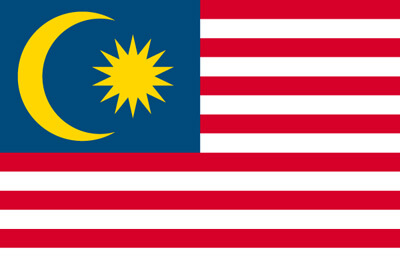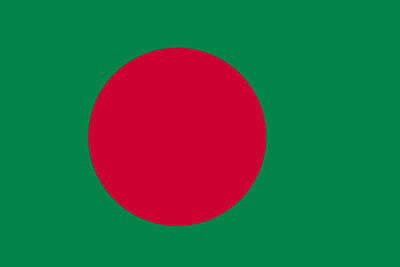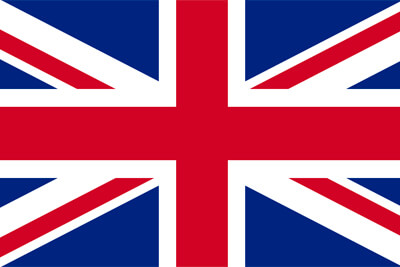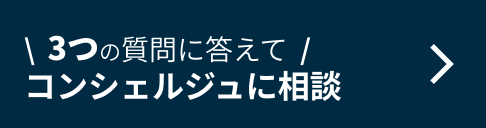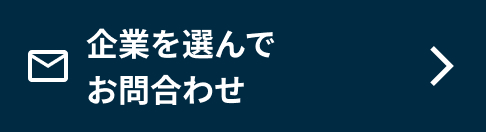海外販路開拓モデル⑥|海外営業DXモデルの構築法|“つながる仕組み”が営業を進化させる【2026年版】

「海外販路を拡大したいが、現地に拠点を設けるのは難しい」「代理店が動いてくれない」「展示会も予算が限られている」──こうした悩みを抱える企業にとって、海外営業DXモデルは新たな突破口となり得ます。
海外営業DXとは、単に越境ECで物を売る仕組みではなく、デジタルチャネルを通じて海外の見込み顧客とつながり、商談の起点を築くB2B型の営業手法です。自社サイトや業界ポータル、オンライン広告、SNSなどを組み合わせ、現地に物理的な拠点がなくてもリードを獲得できるこのモデルは、初期投資を抑えつつグローバル市場へのアクセスを可能にします。
さらに、生成AIや自動翻訳、CRMといったツールの進化により、多言語対応やデータ活用も格段に容易になりました。人材や予算が限られる中堅・中小企業であっても、適切な設計と体制を整えれば、「海外営業を仕組みで回す」時代がすでに現実となりつつあります。
本稿では、海外営業DXモデルの基本構造・導入メリット・現実的な課題・成功に向けた実行設計を多角的に解説します。従来型の営業手法とどう組み合わせるべきかを含め、海外展開の“実践的な一歩”としての活用方法を探っていきます。
▼ 海外販路開拓モデル⑥|海外営業DXモデルの構築法|“つながる仕組み”が営業を進化させる【2026年版】
第1章|海外営業DXモデルとは?──非対面で“商談の起点”をつくる新たな販路戦略
従来型モデルからの転換:物理チャネルの限界とデジタルの台頭
これまで海外販路開拓といえば、現地法人設立や販売代理店の起用、あるいは展示会出展といった「物理チャネル」が主流でした。しかし、これらの方法には拠点構築や人的ネットワーク形成に多大な時間とコストがかかるという制約がつきまといます。加えて、パンデミック以降は対面営業の制約や移動制限が常態化したことにより、非対面でいかに顧客接点を持つかが、企業戦略の新たな軸として注目されるようになりました。
非対面でも“営業が動く”仕組み:海外営業DXモデルの正体
このような変化の中で登場したのが、「海外営業DXモデル」と呼ばれる新しい販路戦略です。これは、SEOやオンライン広告、業界ポータル、SNSなどを駆使して海外企業の意思決定層からの問い合わせや見積依頼を引き出し、営業活動につなげる非対面型の営業手法です。ECサイトのようなB2C販売とは異なり、B2B領域での商談獲得にフォーカスした仕組みであり、製品の比較検討や相談、個別対応など“商談の起点”をデジタル上で創出するのが特徴です。
初期投資を抑え、柔軟に市場検証ができる“入り口戦略”
営業DXモデルの大きな魅力は、現地拠点を構えずに市場ニーズを測定できる点にあります。広告やコンテンツ発信によって集まった問い合わせを分析することで、「どの国で、どの製品に、どんな業種が関心を持っているか」といった一次情報が得られます。これにより、大規模な投資を行う前に有望な市場や製品領域を特定できるため、戦略的な“スモールスタート”が可能になります。特に中堅・中小企業にとっては、リスクを抑えながら海外展開を実現する現実的な手法といえるでしょう。
デジタルと人の連携が成否を分ける
ただし、海外営業DXモデルは単なるリード獲得装置ではありません。問い合わせの質を見極め、商談へとつなげるには人的対応が不可欠です。また、海外営業を加速させたい現場部門と、ガバナンスやセキュリティを重視する管理部門との連携も求められます。こうした前提のもとで、営業・マーケティング・管理の各部門が連動し、運用体制を設計してはじめて、海外営業DXは“販路開拓モデル”として本領を発揮します。
第2章|海外営業DXモデルの4つのメリット──“攻め”と“効率”を両立する営業モデル
1. 現地拠点なしで商談機会を継続創出できる
海外営業DXモデルの最も大きな利点は、物理的な拠点を構えることなく、海外の企業から引き合いを獲得できる点にあります。従来のように展示会や現地出張に頼らずとも、WebサイトやSNS、業界ポータル、広告などを通じて24時間365日、自動的に問い合わせを受け付けることが可能になります。たとえ日本の営業時間外でも、世界中の見込み客が製品情報を閲覧し、関心を示せる仕組みが整うことで、営業活動の間口が格段に広がります。特に人的リソースや予算に限りがある中小企業にとっては、こうした常時稼働型の営業チャネルを確保できること自体が、海外展開の現実的なスタートラインになるのです。
2. 顧客の関心・ニーズを「見える化」できる
営業DXモデルを活用することで、自社への関心がどこから、どのような目的で寄せられているのかを定量的に把握できるようになります。たとえば、どの国・地域からのアクセスが多いのか、どの製品ページが閲覧されているのか、どの業界ポータルから問い合わせがあったのか──こうしたデータはすべて「市場の声」として分析可能です。加えて、問い合わせ内容に目を通せば、製品の用途や調達背景、価格感度など、従来の市場調査では得がたい実務的なインサイトも浮かび上がってきます。このように、実際の顧客接点を通じて得た情報を営業・マーケティング施策にフィードバックすることで、戦略の精度を高めていくことができるのです。
3. 運用を続けるほど、営業資産として蓄積される
展示会や訪問営業は、開催日や訪問先ごとに「単発」で終わる傾向がありますが、営業DXモデルは中長期的に資産化していく特性を持ちます。ウェブサイトやコンテンツは一度整備すれば、情報発信を継続しながら検索経由での流入を生み出し続けます。問い合わせ導線やデータ収集の仕組みも、自社にとって価値ある情報を着実に蓄積していきます。時間とともにWeb上の信頼性やSEOスコアが高まり、広告効果やコンバージョン率も向上していくという好循環が生まれるのです。こうした“仕組みとしての営業チャネル”を構築していくことで、単発的な活動では得られない持続的な販路形成が実現します。
4. 他チャネルとの連携で、ハイブリッド型営業を強化できる
オンラインで得たリード情報を、オフラインの施策と連動させることで、営業活動全体を一段階引き上げることができます。たとえば、海外展示会に出展する前にWeb広告やメールマガジンで来場予定者へアプローチすれば、当日の商談化率を高めることができます。また、Web経由で接点を持った見込み客を現地代理店に引き継ぐことで、よりスムーズに販路構築へとつなげることも可能です。営業DXモデルは、単独で完結するものではなく、従来の営業活動を支援し、連携を通じてその価値を最大化する“プラットフォーム”としての役割を担っています。特に営業部門とマーケティング部門の連携が整っていれば、デジタルとリアルを融合させたハイブリッド型営業によって、海外販路開拓の効果を飛躍的に高めることができるのです。
第3章|4つの課題──「リードは来るが、成果にならない」構造的ボトルネック
1. 数は増えても質が伴わない──“ノイズ”リードへの対応負荷
海外営業DXに取り組む企業がまず直面するのが、「問い合わせの質のばらつき」です。広告出稿やSEO強化によってWeb経由のリード件数が増えても、それが有望顧客であるとは限りません。ときには単なる情報収集や競合調査目的の問い合わせ、あるいはターゲット外の業種・地域からの連絡も含まれるため、リード全体に対する営業の打ち手が見えづらくなるのです。特に社内に“スクリーニング”の体制が整っていないと、対応の優先順位が曖昧になり、営業担当者の負担が無駄に増大します。こうした「ノイズリード」への対応を漫然と続けていると、営業現場の疲弊やROIの低下を招き、せっかくのDX施策が逆効果になりかねません。
2. 商談化に向けた組織体制が構築されていない
Webを通じて得たリードを、具体的な商談へと展開していくには、明確なプロセスと担当体制が不可欠です。ところが、マーケティング部門が問い合わせ対応を担っていたり、営業部門がデジタルリードの扱いに不慣れであったりする企業では、「誰が、どの段階で、どのように」対応すべきかが不明確なままリードが放置されてしまうことがあります。また、初動対応のスピードやメッセージの質がばらつくことで、見込み顧客の関心が失われるという課題もあります。こうした状況を防ぐには、マーケティングと営業が一体となった連携体制の整備と、業務フローの標準化が急務です。
3. 専門知識の欠如──デジタル運用を担える人材不足
営業DXの推進には、SEOやリスティング広告、アクセス解析、MA(マーケティングオートメーション)ツールの運用など、さまざまな専門スキルが求められます。しかし、従来のB2B企業では、こうした知見を持つ人材が社内にほとんどいないというのが現実です。そのため、最初は手探りで施策を進めざるを得ず、思うように成果が上がらないケースも少なくありません。加えて、外部パートナーに業務を委託した場合も、B2C向けのテンプレート的な運用になってしまうことがあり、B2Bならではの商流や意思決定プロセスへの配慮が欠けてしまうリスクがあります。こうした“知見の断絶”が、DX推進のボトルネックになっているのです。
4. 本社と現地、部門間の連携不全が成果を分断する
営業DXを機能させるためには、本社のマーケティング部門だけでなく、現地の営業拠点や販売代理店、さらには社内のIT・管理部門との連携が不可欠です。しかし実際には、部署ごとに目的やKPIが異なっており、得られたリード情報が有効活用されないケースも多く見られます。たとえば、マーケティング部門が収集したリードを営業側が「温度感が低い」と判断し放置してしまったり、逆に営業が活用したい情報をデータベースから引き出せなかったりするなど、意思疎通の断絶が機会損失につながるのです。また、ガバナンスを重視する管理部門が外部ツールの使用に制限をかけた結果、現場の施策スピードが落ちるといった事例もあります。このように、組織間の足並みが揃わなければ、せっかくの営業DXも十分に成果を発揮できません。
第4章|成果を最大化する4つの対策──“仕組み”としての営業DXを設計する
1. 「リードの質」を起点とした設計に切り替える
営業DXの成果を最大化するには、まず「量より質」の発想へと切り替えることが重要です。アクセス数や問い合わせ件数をKPIとする運用では、ノイズリードに振り回され、現場の対応力が疲弊してしまうリスクがあります。そこで必要なのは、自社にとって有望な顧客層──業種、企業規模、担当職位、課題傾向など──をあらかじめ定義し、そのセグメントに向けたチャネル戦略やコンテンツ設計を行うことです。広告やSEOのキーワード設計、資料ダウンロードのCTA(Call To Action)、問い合わせフォームの項目設計など、あらゆる接点において「絞り込み」の設計を行うことで、より精度の高いリードが集まりやすくなります。
2. 商談化までの「対応プロセス」を明文化する
問い合わせがあったリードを確実に商談へと転換するためには、初動対応から営業引き渡しまでのプロセスを、あらかじめ社内で標準化しておくことが求められます。たとえば、「初回返信は●時間以内」「対応内容の記録はCRMに統一」「商談判断の基準は●●」といったルールを設けることで、属人化を防ぎ、抜け漏れのない運用が可能になります。特にB2Bの場合、見込み顧客は複数のサプライヤーを比較しているケースが多く、初期対応の品質がその後の信頼構築に大きく影響します。マーケティングと営業が連携し、対応状況をリアルタイムで共有できる仕組みを整えることが、コンバージョン率の向上につながります。
3. 外部パートナーを「仮想チーム」として活用する
営業DXの立ち上げにおいて、最初からすべてを内製化しようとするのは非現実的です。SEOや広告運用、コンテンツ制作、CRM連携など、各領域には専門性が求められるため、初期は信頼できる外部パートナーの協力を得ることが現実的な選択となります。ポイントは、委託先を「外注先」ではなく、「仮想チーム」の一員と捉えることです。自社のビジネスモデルやターゲット顧客の理解を共有しながら、週次・月次での定例ミーティングを通じて方針をすり合わせ、ノウハウを社内に移管していく設計が望まれます。いずれは社内で内製化できるよう、運用とナレッジの両面から「育てる」視点を持つことが、持続可能なDXの推進につながります。
4. 「営業インフラ」としての社内連携体制を築く
海外営業DXは、特定の部門が独立して担う一時的な施策ではなく、営業活動そのものの「基盤」として全社で取り組むべきプロジェクトです。そのためには、マーケティング・営業・IT・管理部門の三者が共通の理解を持ち、それぞれの立場からリスクと機会を共有できるガバナンス体制が不可欠です。特に、外部ツールの利用、個人情報保護、クラウド環境の構築などに関する運用ポリシーは、社内全体で合意形成を図る必要があります。このような「組織間の橋渡し」こそが、海外営業DXを一過性の試みではなく、長期的に改善・拡張できる営業インフラへと昇華させる鍵となるのです。
第5章|営業DXは「自走する仕組み」づくりから始まる
「仕組み化」が成果の持続性を左右する
海外営業DXを単なるキャンペーンや短期施策と捉えるのではなく、「仕組み」として構築することが成功の出発点となります。たとえば、リード獲得から商談化、そして受注・顧客化に至るプロセスを一連のフローとして定義し、社内で共通認識を持つことが重要です。そのなかで、役割分担、KPI設定、進捗共有のルールなどを明文化し、属人的な判断や対応を排除することで、安定した成果を上げ続ける体制が整っていきます。属人性を脱し、再現性を持たせたプロセス設計こそが、営業DXを“インフラ”として機能させる鍵になります。
データと現場をつなぎ、戦略をアップデートし続ける
営業DXが優れている点は、「すべての営業活動をデータとして可視化できる」ことにあります。たとえば、どの国のユーザーがどのページを多く見ているのか、どの製品の資料請求が多いのか、どの導線から商談につながっているのか──こうした情報を一元的に分析することで、顧客ニーズや市場傾向をリアルタイムで把握することができます。重要なのは、その分析結果を営業戦略や製品開発にフィードバックし、PDCAを高速で回していく体制を築くことです。データと現場をつなげることで、戦略の精度とスピードの両立が可能になります。
「成功体験の言語化」でチームの成熟度を高める
営業DXを通じて得られた成功事例は、属人化させず、必ず「言語化」してチーム全体に展開することが求められます。たとえば、「●●業界・●●国ではこの訴求が効果的だった」「このキーワードで問い合わせが増えた」「こういう初動対応が商談率を高めた」など、具体的な経験則をナレッジとして共有すれば、担当者ごとのバラつきが減り、全体の営業力が底上げされていきます。こうした文化が根づけば、営業DXは単なるツール運用ではなく、組織の学習・成長サイクルそのものを支える基盤へと変わっていきます。
まとめ|海外営業DXは「仕組み進化型」の販路開拓モデル
海外営業DXモデルは、単なるオンライン化ではなく、「営業という営み自体を再設計する」ことにその本質があります。現地にオフィスや人員を置くことなく、見込み顧客と接点を持ち、興味関心を可視化し、商談へと導く──この一連のプロセスを少人数で、かつ継続的に回せることは、中堅・中小企業にとって非常に大きな武器となります。
一方で、このモデルは「デジタルを導入すれば成果が出る」という単純なものではありません。問い合わせ対応の体制やリードの質を見極める目、社内外の連携設計、顧客データの活用、そして何より「営業という活動を仕組み化する」視点がなければ、短期的な反応だけに一喜一憂して終わってしまうリスクもあります。
大切なのは、オンラインとオフラインを分断するのではなく、相互補完的に設計することです。展示会で得た名刺からオンラインでの情報提供へつなぎ、デジタルで獲得したリードを現地代理店と共有して商談につなげる。営業DXは、販路開拓チャネルを単線的に使うのではなく、「編み合わせる」ことで真価を発揮します。
海外展開の第一歩を踏み出す方法として、また既存施策を強化する仕組みとして──営業DXモデルは今後、あらゆる企業にとって不可欠な選択肢となっていくでしょう。重要なのは、テクノロジーを“手段”として捉え、自社の強みをどう届け、どう深めるかという「戦略」として設計し続けることです。
営業活動を“点”から“面”へ、そして“仕組み”へ。海外営業DXは、その変革を加速させる起点となるのです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談