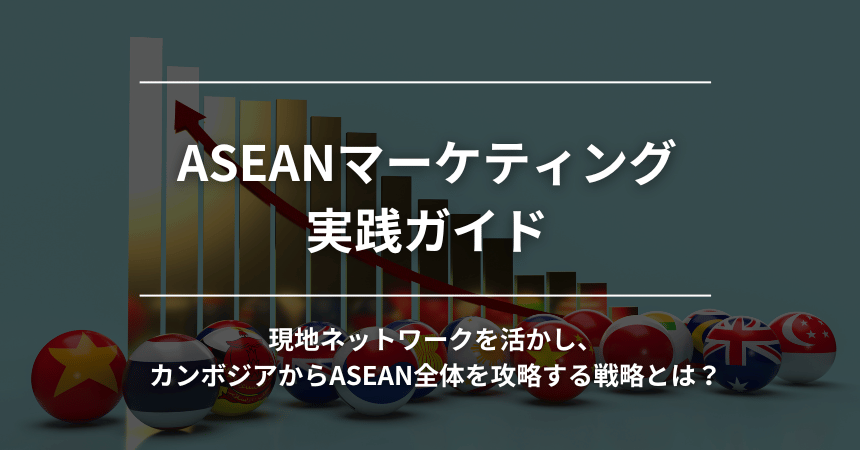海外向け営業資料の作り方|事前準備が9割!商談を成功に導くプレゼン資料のポイントとは?

海外企業との商談において、「何を伝えるか」と同じくらい重要なのが、「どのように伝えるか」です。とりわけ海外営業の現場では、言語や文化、商習慣の違いがある中で、営業資料やプレゼン資料が果たす役割は、日本国内の商談以上に大きくなります。
本記事では、「海外営業」「プレゼン資料」「営業資料」などのキーワードを軸に、海外企業との商談で成果を上げるための営業資料の作り方をわかりやすく解説します。構成・表現・デザイン・翻訳といった各要素に触れながら、資料作成における実践的なポイントを紹介し、さらに改善によって成果を上げた企業事例もご紹介します。
とりわけ海外向けの資料では、言語の問題を補完する「論理性」「視覚性」「簡潔性」が重視されます。日本のように言葉の行間を汲み取ることが難しいからこそ、営業資料には一貫したメッセージと明確な価値提案が求められるのです。また、初回商談では相手企業にとっての「第一印象」としても機能するため、資料の完成度がそのまま信頼度を左右することも珍しくありません。
つまり、商談の成否はプレゼンそのものではなく、事前の資料準備によってほぼ決まっている──そんな実感を持つ営業担当者も少なくありません。「事前準備が9割」といわれる理由を、具体的な内容を通じて解説していきます。是非、参考にしてください。
▼ 海外向け営業資料の作り方|事前準備が9割!商談を成功に導くプレゼン資料のポイントとは?
海外企業との商談に求められる営業資料の特徴とは?
「情報が多い=伝わる」ではない、という視点
日本国内では、詳細な情報を網羅した資料が「丁寧で信頼できる」と評価される傾向があります。しかし、海外企業との商談においては、その常識が必ずしも当てはまりません。特に欧米やアジア諸国の多くでは、短時間で要点を把握できるシンプルな構成が好まれる傾向にあります。情報を多く載せすぎると、かえって読み手にとっては「結局何を伝えたいのか分からない」という印象を与えてしまいかねません。
また、海外のビジネスパーソンは「結論から聞く」姿勢が強く、プレゼン資料にもそのスタイルが求められます。ですので、日本語でよくあるような背景や前提から話を始める構成よりも、まず結論、次に根拠、というロジカルな流れが望ましいと言えるでしょう。
ロジカルで視覚的に整理された資料が信頼を生む
海外の商談では、プレゼンターの話す内容と並行して資料を読み進めるスタイルが一般的です。そのため、資料単体でもある程度内容が理解できるように作ることが重要です。文字情報は簡潔にまとめつつ、図表・アイコン・写真などの視覚的要素を活用することで、伝わりやすさと信頼感が格段に高まります。
たとえば製品の特長を説明する際も、文章で羅列するのではなく、箇条的に整理し、図解や写真を添えることで、「直感的に理解できる構成」にすることが求められます。また、文字サイズや余白の使い方にも配慮し、読み手がストレスなく視線を移動できるレイアウトを意識すると、伝達力が高まります。
日本企業にありがちな“失敗パターン”とは
実際の現場では、日本企業が海外商談用に作成した資料が「丁寧すぎるがゆえに伝わらない」というケースが見受けられます。たとえば、1ページに複数の情報を詰め込みすぎて読みづらくなったり、文化的背景を共有していない相手に前提知識を省いた表現をしてしまったりすることが挙げられます。
また、日本語から英語への直訳によって、不自然な表現や曖昧なニュアンスが残ったまま使用されていることも少なくありません。こうした細部の違和感は、相手に「この企業は海外向けの対応に慣れていない」という印象を与えてしまう要因になりかねません。
商談の場では、資料が企業の姿勢を映す鏡でもあります。「準備不足」や「視点のズレ」が感じられると、信頼構築の妨げとなることもあるため、資料づくりの初期段階で、相手目線・海外基準を意識することが欠かせません。
事前準備から逆算する営業資料の構成とストーリー設計
相手企業の立場に立った「構成設計」が第一歩
海外向けの営業資料を作成する際に、最も重要なのは「自社が伝えたいこと」ではなく、「相手が知りたいこと」を中心に構成を組み立てることです。たとえば、商談相手がパートナー企業なのか、バイヤーなのか、技術担当者なのかによって、関心を持つ情報や評価基準は大きく異なります。
そのため、資料づくりは単なるテンプレート作業ではなく、相手の立場や背景、商談の目的を踏まえて構成を逆算していくプロセスが欠かせません。相手の課題や期待を見据えた上で、「まず何を伝えるべきか」「どこで信頼を得るか」「どのように次のアクションへつなげるか」を設計していくことが、営業資料の成功に直結します。
海外向けプレゼン資料の基本的な構成例
一般的に、海外向けの営業資料では以下のような流れが好まれます。
- 会社概要(企業理念・規模・実績などの要点)
- 相手企業の抱える課題や市場背景(共通認識の提示)
- 自社のソリューション提案(提供できる価値や強み)
- 実績・導入事例・エビデンス(第三者評価や数字の裏付け)
- 実行計画や価格の概要(初期提案レベルでも構いません)
- コンタクト情報・次のステップ
このように、「まず信頼を獲得し、次に価値を伝え、最後にアクションへ導く」構成が基本となります。いきなり製品スペックから話を始めるよりも、相手に寄り添いながら全体像を描く流れが効果的です。
ストーリーテリングで「記憶に残る提案」を目指す
営業資料は情報を整理するだけでなく、一貫性のあるストーリーで相手の印象に残すという役割も担います。製品やサービスの説明を単体で提示するのではなく、「なぜこのサービスが必要なのか」「なぜ当社なのか」「この提案によって相手にどんな未来が開けるのか」といった流れを意識することで、提案が“納得”から“共感”へと変わります。
たとえば、環境対応製品を提案する際には、規制動向→市場課題→製品の特長→他社比較→導入後のベネフィットという流れにすることで、相手企業の課題感とシンクロしやすくなります。事実を並べるのではなく、相手の関心軸に沿って構成することが、伝わる営業資料づくりの核心です。
プレゼン資料の英語表現と翻訳の注意点
直訳ではなく「伝わる英語」を意識する
海外向け営業資料を英語で作成する際、単純な直訳だけでは相手に真意が伝わらないことがよくあります。特に日本語特有の曖昧な表現や丁寧語、婉曲的な言い回しは、英語に変換した際に誤解を招く原因になりかねません。たとえば「前向きに検討します」という表現を直訳すると、実際のビジネスシーンでは相手に期待を持たせてしまうことがあり、慎重な表現が裏目に出ることもあります。
そのため、翻訳においては「意味が通じること」だけでなく、「意図が正確に伝わるか」という視点が重要です。自社内で翻訳する場合でも、ネイティブまたはビジネス経験のある翻訳者によるチェックを挟むことで、資料の信頼性と読みやすさが格段に高まります。
専門用語や業界用語は、相手の理解度に応じた調整を
技術資料や製品仕様を含むプレゼン資料では、専門用語や業界固有の表現を使うことが避けられません。しかし、相手が必ずしもその分野の専門家とは限らないため、専門用語をそのまま使用するか、あるいは簡単な英語に言い換えるかの判断が必要です。
また、同じ言葉でも国や地域によって受け取り方が異なるケースもあります。たとえば「eco-friendly」や「sustainability」といった言葉も、欧州では法律やSDGsに関連する文脈で用いられるのに対し、アジア圏ではやや曖昧に理解されることもあるため、補足や注釈を加えると丁寧です。
数字・単位・言い回しにも文化差がある
英語化において意外と見落とされやすいのが、単位表記や日付の形式です。たとえば、寸法や容量を表す際、日本では「㎡(平方メートル)」や「cc(シーシー)」といった略語がよく使われますが、英語圏ではそれぞれ「square meters」「cubic centimeters」など、略さずに綴るのが一般的です。また、重さや長さについても「kg」「cm」など国際単位系(SI単位)は基本的に通じますが、アメリカではポンドやインチなどの単位を使用するため、相手国に合わせて併記する配慮があると親切です。
また、日付の表記方法にも注意が必要です。たとえば日本で一般的な「2025/03/25」という形式は、英語圏では解釈が異なる場合があります。アメリカでは「March 25, 2025」あるいは「03/25/2025」と表記するのが一般的ですが、イギリスなど他の国では「25/03/2025」と日と月が逆になります。これを誤解されると、商談日や納期に混乱が生じる恐れもあるため、日付は「25 March 2025」のように月名を英語で明記するのが最も確実です。
こうした細かな配慮が、「この企業はグローバル対応に慣れている」という印象を与える一因となります。資料全体の完成度を高めるには、こうした基本的な形式の選び方も重要なポイントです。
海外営業で成果を出すためのデザインとビジュアルの工夫
「読みやすさ」と「伝わりやすさ」は別物と考える
海外向け営業資料では、内容が正しく書かれているだけでは十分とは言えません。伝えたい情報をいかに素早く、正確に理解してもらうかという点で、資料のデザインと構成が大きな役割を果たします。とくに海外企業との商談では、相手に与える第一印象の多くが資料によって決まるため、見やすく、ストレスなく読めるレイアウトを意識することが重要です。
資料が読みづらい原因の一つが「情報の詰め込みすぎ」です。1枚に情報を多く載せたくなる気持ちはわかりますが、情報が散漫になると理解が追いつかず、印象に残りにくくなってしまいます。むしろ、1枚1メッセージの原則で情報を整理し、余白を適切に使いながら視線の流れを設計することが、資料の伝達力を高めるポイントです。
視覚的要素の活用で「記憶に残る」資料をつくる
日本企業の資料では、文章中心の構成がまだまだ主流ですが、海外では図表やアイコン、写真を活用して視覚的に訴える資料のほうが高く評価される傾向があります。製品の仕様やサービスの流れを説明する場合は、表形式やフロー図、ピクトグラムを用いることで、言葉の壁を超えて直感的に理解されやすくなります。
また、ブランドのイメージを伝える上でも、写真やビジュアルの質は重要な要素です。例えば自社工場の外観、現場の様子、製品が使われているシーンなど、具体的なビジュアルを挿入することで、信頼感と親しみやすさが生まれます。特にオンライン商談では、こうした視覚情報が対面での印象に代わる役割を果たすこともあります。
フォント・色使い・レイアウトの基本を押さえる
意外と軽視されがちですが、フォントや色使い、レイアウトの整合性も資料のプロフェッショナル感に直結します。フォントは読みやすさと統一感を優先し、タイトル・本文・注釈などで大きさや太さを適切に使い分けましょう。また、企業カラーを使った配色はブランド認知を高める効果もありますが、派手すぎず、背景とのコントラストを考慮して読みやすさを損なわないよう配慮が必要です。
さらに、段落間の余白や配置バランスなどにも意識を向けると、全体として洗練された印象を与えることができます。海外では「細部に気を配れる企業」は高評価を受けやすく、資料のデザインひとつ取っても、その企業の姿勢や品質へのこだわりが伝わるのです。
成功事例|営業資料を改善して成果を上げた日本企業のケース
製造業(部品メーカー)|図解中心の資料で商談化率が大幅改善
ある中堅の部品製造メーカーでは、以前より海外展示会に出展していたものの、「資料を配ってもその場で終わってしまう」「商談につながらない」といった悩みを抱えていました。従来の資料は、日本語のものを単純に英訳したA4数ページの説明書で、技術用語も多く、相手にとっては読みづらいものでした。
そこで、営業資料を全面的に見直し、「製品の特長を視覚的に伝える」ことを重視したスライド資料に刷新。製品の用途や強みを図解やイラストで紹介し、導入後の効果や実績データもグラフで示すようにしたところ、展示会後の商談化率が以前の3倍に増加しました。また、オンライン送付時にも好反応が得られ、「説明がなくても資料を見れば十分理解できた」との評価が寄せられました。
ITサービス企業|英語資料の構成改善で欧州進出の足がかりに
国内向けに業務システムを提供していたITベンチャー企業が、欧州進出を目指してプレゼン資料を英語化しましたが、現地商談では「わかりづらい」「資料の構成が合っていない」といった反応が多く、成果が出ない状態が続いていました。
そこで、専門の翻訳者とともに、資料の英語表現だけでなく構成そのものを欧州流にリライト。冒頭で顧客課題を明確に示し、その後にソリューションの概要、導入効果、価格体系、導入フローをわかりやすく整理しました。併せて、デザインもシンプルでスタイリッシュなトーンに変更。結果として、商談後のフォロー率が向上し、初年度で2社との契約を獲得することができました。
食品系メーカー|ブランド価値を伝えるビジュアル設計で信頼感向上
和菓子や調味料など、日本の伝統的な食文化を取り扱う食品メーカーでは、海外でのブランド訴求に苦戦していました。とくに商品の“品質の良さ”や“歴史のある企業姿勢”が文字では伝わりにくく、価格競争に巻き込まれてしまう状況でした。
そこで、英語資料に商品が使われている風景写真や工場の衛生管理体制、長年の取引先実績などを丁寧にビジュアル化し、資料のトーンを高品質・安心感が伝わるものに調整しました。また、ストーリーテリングの手法を取り入れ、「日本の味を世界へ届ける」理念も資料に盛り込んだ結果、現地バイヤーの信頼を得やすくなり、価格よりも価値で評価される商談が増加しました。
まとめ|“言語”ではなく“準備”が海外商談の成功を決める
海外企業との商談において、言語の壁や文化の違いに不安を感じる日本企業は少なくありません。しかし、商談の成否を分けるのは、語学力ではなく「どれだけ事前に準備された営業資料を用意できているか」にあります。的確に構成された資料は、企業の信頼性を示す“看板”であり、言葉では伝えきれない価値を明確に示すツールです。
本記事では、海外向け営業資料の構成、英語表現、デザイン、翻訳時の注意点など、実務に即した観点から資料づくりのポイントを解説しました。さらに、営業資料の改善によって成果を上げた企業の事例からも、資料の力がいかにビジネスの結果を左右するかが見えてきたのではないでしょうか。
今後の海外展開を見据える企業にとって、営業資料の整備は「後回しにできない最初の一歩」です。伝わるプレゼン資料は、貴社の価値を正しく、魅力的に届けてくれる最強の営業パートナーです。まずは資料から、海外営業の成果を変えていきましょう。
なお、「Digima~出島~」には、優良な海外販路拡大の専門家が多数登録されています。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
本記事が、海外市場への参入を検討している企業にとって有益な情報となり、現地での成功につながることを願っています。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談