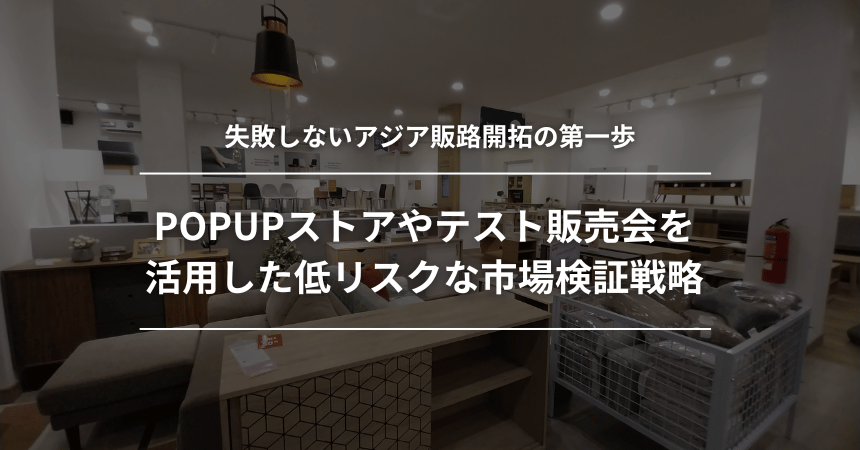高度人材制度とは?ポイント制の仕組み・在留資格・メリットをわかりやすく解説

国内の人材不足が深刻化するなか、専門性を持つ外国人材への注目がますます高まっています。特に、技術・研究・経営などの分野で活躍できる外国人を受け入れるために整備された「高度人材制度(高度専門職)」は、企業にとって有望な採用選択肢の一つです。これは、学歴や職歴、年収、日本語能力などをポイント制で評価し、一定の基準を満たす人材に対して在留資格を付与する制度であり、通常の就労ビザに比べて多くの優遇措置が用意されています。
この制度は、国際競争力のある人材を呼び込むための政策的な枠組みであり、日本での永住や家族帯同、柔軟な就労形態など、外国人にとっても魅力的な内容となっています。その一方で、制度の仕組みが複雑に感じられることや、どのように活用すればよいか分からないという声も少なくありません。
本記事では、高度人材制度の概要からポイント制の評価項目、企業側のメリットや実際の活用事例、さらに導入にあたっての実務的な注意点までを体系的に解説します。外国人材の採用を戦略的に進めたいと考える企業の皆様にとって、制度理解の第一歩としてご活用いただければ幸いです。
▼ 高度人材制度とは?ポイント制の仕組み・在留資格・メリットをわかりやすく解説
高度人材とは? 制度の目的と対象者のイメージ
高度人材=高度専門職という特別な在留資格
高度人材とは、法務省が定める「高度専門職」という特別な在留資格に基づいて認定される外国人のことを指します。これは、特に専門性が高く、日本社会や経済への貢献が期待される人材を対象とした制度であり、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)とは異なる枠組みで運用されています。高度専門職の在留資格は、「1号」「2号」の2段階に分かれており、まず1号の認定を受けた人材が、日本での活動実績や在留年数などの条件を満たすと、より自由度の高い2号へと移行できる仕組みです。
この制度の導入目的は、日本がグローバルな人材獲得競争の中で、より優秀な外国人を呼び込みやすくすることにあります。そのため、高度人材に該当すると、在留期間の優遇や永住権取得の迅速化、配偶者の就労許可など、多くの優遇措置が設けられています。企業にとっても、これらの人材を積極的に採用することで、国際展開や研究開発の推進、新規事業の立ち上げといった分野で大きな戦力となる可能性があります。
特定技能や技能実習との違いとは?
高度人材制度は、技能実習制度や特定技能制度と混同されることもありますが、その性質は大きく異なります。技能実習はもともと「技能移転」を目的とした制度であり、受け入れ企業側は教育・監督責任を負う立場にあります。一方、特定技能は労働力としての受け入れに近く、対象職種や業種が明確に限定されています。どちらも一定の技能や試験合格が要件ですが、業務の内容は比較的現場・作業系の分野に寄っています。
これに対して高度人材制度は、いわば“企業の中核を担う人材”のための枠組みです。大学卒業以上の学歴や高い年収、専門的な職歴など、総合的に評価される属性を持った外国人が対象で、技術者、研究者、経営者など、高度な知識や経験を活かして企業活動に貢献することが期待されています。また、制度上も就労内容や在留の柔軟性が格段に高く、経営の中核に据えたい人材の採用に適しています。
どのような分野の人材が対象になるのか?
高度人材制度が想定している職種や分野は多岐にわたります。大きくは、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3類型に分類されており、それぞれに適した評価基準が設けられています。たとえば、大学や研究機関での研究者は「研究活動」、エンジニアやデザイナー、財務専門家などは「専門・技術活動」、企業の経営者や役員クラスは「経営・管理活動」に該当します。
近年では、特にITやAI、バイオテクノロジーといった分野において、海外からの高度人材に対する需要が高まっており、これらの分野では採用事例も増えています。また、海外子会社との連携や国際展開を視野に入れた経営戦略を持つ企業にとっては、語学力や異文化理解を持つ外国人材が非常に貴重な存在となります。高度人材制度は、こうした戦略的な人材獲得を実現する上で、制度的な後押しとなるのです。
ポイント制の仕組みと評価項目
ポイント制の基本:70点以上で高度人材に認定
高度人材制度の中核となるのが「ポイント制」による評価システムです。この制度では、外国人が高度専門職として認定されるために、学歴や職歴、年収、日本語能力など複数の項目において一定の点数を獲得する必要があります。合計で70点以上を取得した場合に「高度人材」として認定され、該当する在留資格(高度専門職1号)が付与されます。
ポイントは、たとえば大学院卒業で20点、年収1,000万円以上で40点、日本語能力試験N1合格で15点など、個別の条件に応じて加算される仕組みとなっており、年齢が若いほど加点される仕組みもあります。また、対象となる分野に関連する資格や職歴、論文実績なども評価の対象となるため、特定の分野で専門性を積んだ人材が有利になりやすい設計です。
このスコアリング制度は非常に透明性が高く、あらかじめ自社の候補者が70点を超えるかどうかを見極めやすい点も、企業側にとって活用しやすいポイントです。なお、ポイントの計算は法務省や出入国在留管理庁の公式ガイドラインを基に算出できますので、導入を検討する際には事前に候補者のスコア試算を行っておくとスムーズです。
高度専門職の3類型(研究/技術・人文知識/経営管理)
高度専門職の在留資格は、活動内容に応じて大きく3つの類型に分かれています。第一に「高度学術研究活動」では、大学や研究機関などでの教育・研究に従事する人材が対象となります。博士号の取得や論文発表、研究実績などが評価の中心です。第二に「高度専門・技術活動」では、民間企業等において技術職・事務職・専門職として働く人材が対象となり、学歴や職歴、年収のバランスが求められます。もっとも活用範囲が広く、ITエンジニアや経理、デザイナーなどが該当します。
第三に「高度経営・管理活動」は、企業の役員や経営者として事業運営を担う外国人が対象です。起業家や外資系企業の代表などが該当し、高額年収や事業運営経験などが評価されます。これらの類型ごとに評価項目の重みづけが若干異なるため、自社が採用したい外国人材の役割に応じて、どの類型での申請が最適かを検討する必要があります。
それぞれの類型において、ポイントを構成する基本軸は共通していますが、職種や業務内容によっては要件を満たさない場合もあるため、事前に類型ごとの要件を確認しておくことが重要です。
制度改正(J-Skip・J-Find)の概要と影響
2023年に導入された新たな制度「J-Skip(Japan System for Special Highly Skilled Professionals)」および「J-Find(Future Creation Individual Visa)」は、高度人材制度のさらなる活用を促進する目的で設けられた新制度です。特にJ-Skipは、高度専門職の中でもとりわけ年収や学歴などの条件が高い外国人を、より迅速かつ簡易に受け入れる枠組みとして注目されています。
たとえば、J-Skipでは年収が2,000万円以上であることや、修士号以上の学位を有することなどが基準となり、これを満たせばポイント制のような細かい評価を経ずとも、高度専門職としての在留資格が付与される仕組みです。これにより、より即戦力となる外国人材の採用がスピーディーに進められる可能性が広がっています。
また、J-Findは主に外国人留学生や起業志望者など、将来的に日本での活躍が期待される層を対象とした制度で、一定の条件を満たすことで在留資格の取得や滞在延長が可能になります。企業としては、これらの制度も視野に入れることで、高度人材の採用戦略をより柔軟に設計できるようになるでしょう。
高度人材という在留資格のメリット
永住権取得の優遇・長期雇用が実現できる
高度人材制度の大きな特徴の一つが、「永住権取得における優遇措置」です。通常、外国人が日本で永住権を申請するには10年以上の継続的な在留が必要ですが、高度人材として認定された場合は、最短でわずか1年(原則は3年)で永住申請が可能になります。これは、高度専門職1号としての活動実績と安定した生活基盤が評価されるためです。
この優遇措置は、外国人本人にとって大きな魅力であると同時に、企業側にも間接的なメリットをもたらします。長期的に日本に定着する意思を持つ人材を確保できることで、継続的な雇用と育成への投資が可能になるからです。採用と退職を繰り返すことなく、中長期的な戦力として活躍してもらうことができ、特に技術継承やマネジメント層の構築を視野に入れる企業にとっては、安定した組織づくりに貢献する制度といえます。
家族帯同・配偶者就労・家事使用人の雇用も可能
高度人材制度では、本人だけでなく、その家族にも柔軟な在留と活動の許可が認められています。たとえば、配偶者には日本国内での就労が認められており、一般の就労ビザ保持者の配偶者が原則として就労できないのとは大きな違いがあります。さらに、年収基準を満たしていれば、自身の親を日本に呼び寄せることや、家事使用人の同伴も可能になる点も注目されています。
こうした制度設計により、本人が安心して日本での生活・キャリアに集中できる環境が整うため、定着率が高まり、企業にとっても人材流出のリスクを軽減する要素となります。特に海外からの人材は「生活の安定」が雇用の持続に大きく関わるため、家族のサポート体制が整っていることは、採用時の大きなアピールポイントにもなり得るでしょう。
就労範囲が広く、副業・兼業も認められる
高度専門職に認定された外国人は、就労内容の柔軟性においても大きなメリットがあります。通常の就労ビザでは「活動内容(職種)」が厳密に制限されており、在留資格に記載された業務以外に従事することは原則として認められていません。しかし、高度人材の場合、一定の関連性がある業務であれば複数の職務や事業への従事が可能であり、副業や兼業も柔軟に認められている点が特長です。
これは企業にとっても、業務範囲や役割設計において高い自由度を確保できるという意味で有利です。たとえば、専門職とマネジメント業務を兼務させることや、新規事業への横断的な関与を任せるといった対応が、制度上も現実的になります。こうした柔軟性により、変化の激しい業界においても戦力としての適用範囲が広がり、より戦略的な人材活用が可能になるのです。
どんな企業が活用している? 活用事例と向いている業種
IT・製造・研究など専門性が求められる業種で導入拡大中
高度人材制度は、特に専門的な知識や技術力が必要とされる業種で積極的に活用されています。たとえば、IT業界ではエンジニアやデータサイエンティスト、AI開発者など、国内での人材確保が難しい職種を中心に、多くの企業が海外人材に目を向けています。また、製造業においても、高度な機械設計や品質管理、国際調達などの分野で、高度人材の活躍が期待されています。
さらに、大学や企業の研究所などにおける理系分野の研究職、ライフサイエンス、エネルギー開発といった高度な専門性を必要とする分野では、博士号取得者を中心に制度の活用が進んでいます。これらの業種に共通するのは、求めるスキルや知見が日本国内では供給不足に陥っているという点です。高度人材制度は、こうした“人材ギャップ”を埋める現実的な選択肢として、各業界から注目されています。
スタートアップやグローバル展開企業の活用事例
高度人材制度の活用は、大企業だけにとどまりません。最近では、スタートアップ企業や中小規模でもグローバル展開を目指す企業による活用事例も増えています。特に、設立間もないスタートアップでは、創業チームの一員として外国籍のエンジニアやマーケティング人材を招くケースが多く見られ、事業スピードを加速させるうえで制度の利点が活かされています。
グローバル市場をターゲットにしたサービス開発や海外向けのプロダクト設計を行う企業にとっては、多様な価値観を持つ高度人材の存在が、単なる労働力ではなく“共創のパートナー”として機能します。また、グローバル採用を通じて企業文化の柔軟性を高め、社内における国際対応力の底上げにもつながる点が、制度導入の副次的なメリットとして注目されています。
中堅・中小企業もポイント制で採用チャンスが広がる
「高度人材制度は大企業向け」と捉えられがちですが、実際には中堅・中小企業にも活用の余地が十分にあります。ポイント制の仕組みは、個人の属性(学歴・職歴・年収・日本語力など)によって認定されるため、企業規模が大きくなくとも、条件を満たした人材であれば制度を活用できます。特に、国内での採用が難しいポジションや、技術継承・新規市場開拓といった“成長投資”の文脈では、中小企業にとっても重要な選択肢になります。
また、自治体や中小企業庁などが提供する外国人材受け入れ支援制度と併用することで、ビザ取得から生活支援、職場環境整備まで、伴走的なサポートを受けることが可能です。すでに高度人材制度を活用して成功している中小企業の事例もあり、他社との差別化や成長戦略の一環として制度を位置づける動きが広がっています。
高度人材制度を活用するための実務ポイント
まずはポイント計算とポジション設計から始めよう
高度人材制度の活用を検討するにあたり、最初に行うべきは、候補者が制度の基準を満たすかどうかを確認することです。これは「高度専門職ポイント計算表」を用いて、学歴、職歴、年収、日本語能力などのスコアを事前に試算することで可能です。70点以上であれば制度の適用対象となるため、候補者のスキルや経歴をもとに丁寧に確認しておく必要があります。
同時に重要なのが、受け入れるポジションの設計です。高度人材は、単なる労働力としてではなく、専門性を活かす前提で在留資格が認められているため、業務内容が制度の類型(研究・技術・経営管理など)に合致している必要があります。たとえば、エンジニアとして採用する場合でも、技術的な判断や設計業務を伴うポジションであることが求められます。したがって、求人票や職務定義において制度との整合性を意識することが重要です。
申請書類の整備とタイミング管理が肝心
高度人材制度を活用するには、申請に必要な各種書類を正確に準備することが欠かせません。必要書類には、在留資格認定証明書交付申請書のほか、企業概要書、雇用契約書、職務内容の詳細説明書、ポイント評価資料(学歴証明、職歴証明、年収証明など)があります。これらは法務省や出入国在留管理庁が定める形式に則って作成する必要があり、特に「職務内容と類型の整合性」は審査において非常に重視されます。
また、申請から在留資格交付までには一定の期間(通常1~2か月程度)を要するため、採用スケジュールとの調整が必要です。急な人材補充では制度の適用が難しくなるため、あらかじめ候補者の選定と申請準備を並行して進めることが理想的です。採用計画に制度の申請リードタイムを組み込んでおくことで、事業への影響を最小限に抑えることができます。
採用後のフォロー体制(生活支援・キャリア支援)も準備を
高度人材の受け入れは、単にビザを取得させれば終わりではありません。日本での生活に慣れてもらい、長期的に活躍してもらうためには、受け入れ後の支援体制が重要な鍵を握ります。たとえば、住居探しや行政手続き、日本語学習のサポートといった生活面のフォローが整っていることで、本人の安心感や定着率が大きく向上します。
また、キャリア形成の面でも、定期的な面談やキャリアパスの提示、社内での成長機会の提供が不可欠です。特に異文化で働く外国籍人材は、評価や期待が見えにくいと不安を感じやすいため、フィードバックや評価基準を明確に伝える仕組みも効果的です。こうしたフォロー体制が整っていれば、高度人材が本来の能力を発揮し、企業の中核人材として成長していく土台を築くことができるでしょう。
まとめ|高度人材の活用は“制度理解”と“企業の姿勢”が成功の鍵
高度人材制度は、日本企業が国際的な競争力を高めるうえで、非常に実効性の高い制度です。専門的な知識や経験を持つ外国人材を受け入れやすくするための枠組みが整っており、在留資格の優遇、永住申請の迅速化、家族の帯同や就労支援など、従来の制度と比べて柔軟性と利便性が大きく向上しています。企業にとっては、国内で確保が難しい高度人材を戦略的に採用することができ、技術力の強化、新事業の創出、国際展開など、さまざまな局面で新たな推進力を得られる可能性があります。
ただし、この制度を効果的に活用するには、制度そのものへの理解に加えて、候補者の条件評価、在留資格申請、受け入れ後の支援までを一貫して設計・運用することが求められます。形式的な採用にとどまらず、高度人材が組織の中で活躍し続ける環境を整えるという視点が不可欠です。
今後の人材戦略において、多様なバックグラウンドを持つ人材を活かす姿勢は、企業の価値や魅力を大きく左右する要素となっていくでしょう。高度人材制度はその入り口に過ぎませんが、活用のあり方次第で、企業の成長に長期的かつ本質的なインパクトを与えるものになるはずです。
なお、海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima~出島~」の運営する「開国エンジン~縁人~」のようなグローバル人材マッチング支援サービスを活用することで、自社に最適なエージェントと出会うことが可能です。是非、お気軽にご相談ください。
本記事を参考に、自社に最適な高度人材の採用戦略を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談