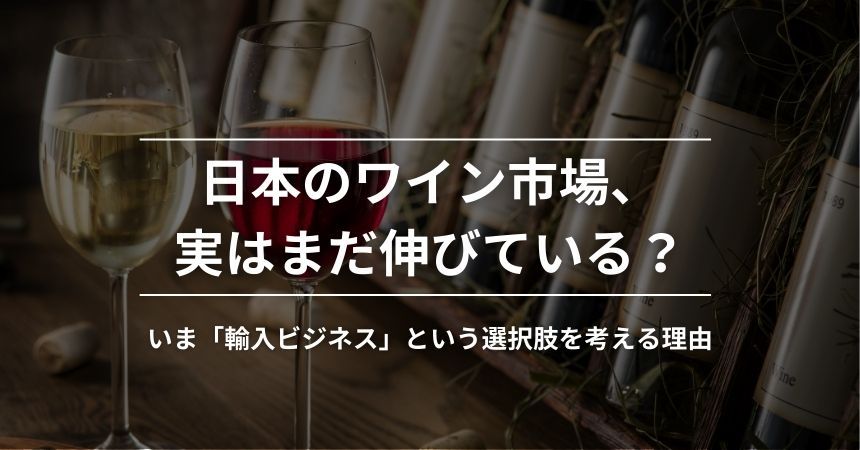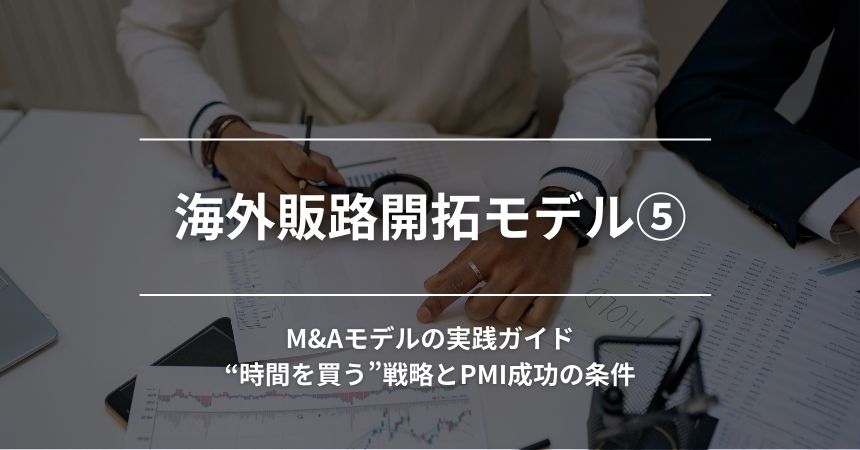個人輸入での輸入販売ビジネスの始め方-海外から買い付ける4つの方法

海外から商品を(個人)輸入して「輸入販売ビジネス」を始める際の基礎知識について解説します。
「輸入販売ビジネス」とは、海外から個人輸入した商材(商品)を日本で販売して、その差額で利益を得るというシンプルなビジネスです。しかしシンプルといっても、海外の仕入れ先とのやりとりが発生するビジネスなので、日本におけるいわゆる〝せどり〟や〝転売〟とは異なり、通関や税率さらには輸出規制といった、輸入ビジネスならではの最低限の知識が必要になります。
本テキストでは、そんな「輸入販売ビジネス」を検討している海外ビジネスパーソンに向けて、輸入販売ビジネスの利益の出し方、最低限必要な4つの知識、基本的な5つのビジネスモデル、海外から日本へ仕入れる「輸入商品」をセレクトする方法、海外から「輸入商品」を買い付ける方法…など、懇切丁寧にレクチャーしていきます。
▼個人輸入での輸入販売ビジネスの始め方-海外から買い付ける6つの方法
- 1. 海外から日本へ商品を仕入れる「輸入販売ビジネス」とは?
- 2. 輸入販売ビジネスには2つの利益の出し方がある
- 3. 輸入販売ビジネスに必要な最低限の4つの知識とは?
- 4. 輸入販売ビジネスにおける5つのビジネスモデル
- 5. 「個人輸入」と「一般(商業)輸入」と「小口輸入(商業輸入)」の違いとは?
- 6. 海外から日本へ仕入れる「輸入商品」をセレクトする6つの方法
- 7. 海外から輸入商品を買い付ける4つの方法
- 8. 日本企業の「輸出入・貿易・通関」に関する最新トレンド
▼ アナタの海外ビジネスを成功させるために
1. 海外から日本へ商品を仕入れる「輸入販売ビジネス」とは?
海外から仕入れた商品で利益を得る=「輸入販売ビジネス」
「輸入販売ビジネス」とは、海外から仕入れた商品を日本で販売して利益を得るビジネスです。
具体的には、海外の販売サイトや、直接海外に買い付けに行って商品を仕入れて、国内のネットショップや店頭販売、あるいはオークションなどで商品を販売し、その差額で利益を得るビジネスモデルとなります。
基本的に輸入販売ビジネスの利益は、売値から仕入れ価格(コスト)と経費を引いた額となります。
経費は運送費や海外への支払手数料など仕入れにかかる費用のほか、販売にかかる費用なども含まれます。仕入れ価格や経費は、為替相場や仕入れの金額・荷物の大きさなどにより、毎回変動するのが普通です。
2. 輸入販売ビジネスには2つの利益の出し方がある
「薄利多売」と「厚利少売(高付加価値ビジネス)」
輸入販売ビジネスには2つの利益の出し方があります。
ひとつめは「薄利多売」です。これは一つ一つの利益額は低くても販売量を増やすことで利益を上げる方法です。資金力がある強者の戦略であり、誰でもできることではありません。
ふたつめは「厚利少売(高付加価値ビジネス)」です。少量で多くの利益を得るビジネスです。これは一つ一つの利益を大きくとり、量を減らすという方法です。個人事業主や小さな法人は大体、この高付加価値戦略で利益を上げるのが通常です。
3. 輸入販売ビジネスに必要な最低限の4つの知識とは?
このセクションでは「輸入販売ビジネスに必要な知識」について解説します。
それこそ輸入販売ビジネスに必要な知識は様々ですが、ここでは最低限知っておくべき4つの知識について簡潔に解説します。
① 関税に関する知識
1つめは関税に関する知識です。海外から商品を仕入れる際は、「関税」と呼ばれる税金が発生します。具体的には「商品の課税価格×関税率」となります。よって、価格が高い商品ほど、あるいは関税率が高い商品ほど、納める関税の額が大きくなります。
20万以下の少額の輸入ビジネスの場合、「簡易税率」と呼ばれる税制が適用されます。ちなみに簡易税率は、20%、15%、10%、5%、3%、無税、重量税の7つに分かれており、輸入する商品によって税率が変わってきます。
また課税価格が20万円を超えてしまう場合は、一律15%の関税率が適用されます。
さらに自分が輸入した商品の関税率が分からない場合は、税関の「事前教示制度(税関に関税率を問い合わせること)」を利用することをオススメします。
② 「フォワーダー」などの通関サービスに関する知識
2つめは、実際に商品を海外から輸入した際に、あなたが利用するであろうサービス(具体的には「フォーワーダー/通関業者などの代行サービス」)についての知識です。
結論から言ってしまえば、海外の販売サイトから仕入れる、いわゆるDoor-To-Doorでの輸入の場合は、特別に通関業者などを利用する必要はありません。
しかし、コンテナなどを使用する一般商業輸入の場合は、フォワーダーやコンテナ輸送会社などの「通関業者」のサービスを利用する必要があります。
そもそも「フォワーダー」とは、海外で商品を販売したい企業と現地の販売会社を仲介する事業者のことを指します。その基本的な役割としては、荷主と実運送人の間での国際輸送に関する業務となり、自らは運送手段を持たないものの、依頼者と運送手段を持つ運送業者との間に立って、様々な通関業務を代行してくれます。
フォワーダーの業務は多岐に渡り、物品の運送、混載、保管、荷役、包装、配送に関する業務、さらには通関手続きや納税のための申告も、その業務に含まれています。そういった業務を、ワンストップでアウトソーシングできるのがフォワーダーや通関業者に依頼する際のメリットと言えるでしょう。
③ 「輸入原価」の算出に関する知識
3つめは、輸入の際の経費を計算して「輸入原価を算出する」ための知識です。海外から商品を輸入した場合、下記のような費用が必要になります。当然ですが、せっかく海外から商品を仕入れても、利益が出なければ、輸入ビジネスをする意味がありません。
下記の費用をすべて計上して「輸入原価」を算出しておく必要があることは心に留めておきましょう。
1: 商品の価格
2: 国際輸送費
3: 海上保険料金
4: 日本側の通関費用
5: 関税・消費税
6: 国内配送料
7: 貨物保管料
8: 販売費用
9: 人件費
10: 信用状(L/C)開設費用 ※
11: 輸入者側の利益
※ 信用状とは銀行が輸入者の代わりに商品代金の支払いを保証するために発行するもの。L/C(Letter of Credit)とも呼ばれる
これらの費用をすべて計上して「輸入原価」を算出することが重要です。
④ 「海外送金」に関する知識
4つめは、海外送金に関する知識です。輸入ビジネスを行う際には、海外へ支払うために海外送金が必要になります。海外送金を行う際には、以下のポイントに留意する必要があります。
1. 為替レートの把握
海外送金では、日本円を外貨に換算する必要があります。その際には、為替レートを確認し、最適なタイミングで送金することが重要です。為替レートは日々変動するため、市況や外国為替市場の動向を注視する必要があります。
2. 送金手数料の確認
海外送金を行う際には、送金手数料がかかる場合があります。送金手数料は送金額や送金先の国・地域によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。また、送金手数料が高い場合には、他の送金方法を検討することも重要です。
3. 送金先の口座情報の正確性
海外送金を行う際には、送金先の口座情報を正確に入力することが重要です。誤った口座情報を入力すると、送金が遅延したり、送金先が間違ったりする可能性があります。送金先の口座情報を入力する際には、何度も確認し、慎重に入力することが必要です。
4. 法規制の遵守
海外送金には、国内外の法規制を遵守する必要があります。特に、資金移動に関する法律や規制が厳しい国・地域では、送金手続きや報告が必要となる場合があります。適切な手続きを行うことで、法的なトラブルを回避し、円滑な送金を行うことができます。
これらのポイントに留意することで、海外送金を効率的に行い、輸入ビジネスの運営をスムーズにすることができます。
4. 輸入販売ビジネスにおける5つのビジネスモデル
一般的に輸入販売ビジネスには5つの方法があります。

以下より順を追って見ていきましょう。
① 無在庫販売
このモデルでは、商品を事前に在庫として持つ必要がありません。販売者は商品をオンラインで販売し、注文が入った後に、海外のサプライヤーやメーカーに直接発注します。この方法は初期投資が少なく、リスクも低いですが、納期の遅れや在庫管理の問題が生じる可能性があります。
② 海外通販サイトからの輸入再販
既に市場に存在する商品を、海外のオンライン通販サイトから輸入し、日本で販売する方法です。この方法は商品の種類や量に応じた柔軟性がありますが、競合との差別化が難しい場合があります。
③ 海外の卸業者からの輸入販売
既存商品を海外の工場や卸業者から直接輸入し、日本で販売する方法です。大量購入による単価の削減が可能ですが、大量の在庫リスクや品質管理の問題があります。
④ 海外製造のオリジナル商品の自社輸入販売
自社ブランドのオリジナル商品を海外で製造し、それを輸入して日本で販売します。ブランド価値の向上が期待できますが、製品開発、品質管理、ブランド構築には高い専門知識と資金が必要です。
⑤ 海外製造のオリジナル商品の国内流通販売
自社製品を海外で製造し、それを日本の小売業者や実店舗に卸す方法です。幅広い流通ネットワークを通じて販売が可能ですが、販売チャネルの確立と維持には大きな労力と関係構築が必要です。
ビジネスモデルとしては、後の方法になるにつれて難易度が高くなり、資金力やノウハウなどが必要とされます。これらの方法は、それぞれ異なるリスク、利益、資本、専門知識を必要とします。自分のビジネスに適したモデルを選ぶ際には、それらを事前に考慮することが重要です。

5. 「個人輸入」と「一般(商業)輸入」と「小口輸入(商業輸入)」の違いとは
輸入販売ビジネスがどのようなビジネスモデルか理解できたところで、このセクションでは、「輸入販売ビジネスの3つの形態」について解説します。
一口に「輸入販売ビジネス」といってもその形態はさまざまですが、本稿では以下の3つに定義で解説します。
①「個人輸入」
②「一般(商業)輸入」
③「小口輸入(商業輸入)」
ただ、①「個人輸入」と③「小口輸入(商業輸入)」の線引きが難しいため
■①「個人輸入」と②「一般(商業)輸入」の違い
■③「小口輸入(商業輸入)」と②「一般(商業)輸入」の違い
…という2つのテーマにわけて解説します。
具体的には、①「個人輸入」と③「小口輸入(商業輸入)」のそれぞれを、②「一般(商業)輸入」と比較した際の違いについて解説した上で、①と②の違いについて解説します。
ではさっそく〝①「個人輸入」と②「一般(商業)輸入」の違い〟から見ていきましょう。
①「個人輸入」と②「一般(商業)輸入」の違いとは?
「輸入販売ビジネス」に関して調べていると、「個人輸入」や「一般(商業)輸入」といったワードを目にすることが多いと思います。
結論から言うと、上記2つは、個人使用と商売目的を区別するための言葉であり…
①「個人輸入」:
個人使用目的で輸入すること
②「一般(商業)輸入」:
商売目的で輸入すること
…という区別となります。
③「小口輸入(商業輸入)」と②「一般(商業)輸入」の違いとは?
続いては「小口輸入」と「一般(商業)輸入」の違いについて見ていきましょう。
先述したように「一般(商業)輸入」とは商業目的で輸入することを指します。
対する「小口輸入」とは、先述した「個人輸入」における〝商売目的の輸入〟を意味する言葉で、「第三者に販売する目的で小規模の量の商品を輸入すること」を指します。コンテナなどを利用して大量の商品を輸入する「一般的な商業輸入」と区別する際に、「小口輸入」というワードが使われるケースが多いです。
それらをまとめると以下のようになります。
③「小口輸入」:
(おもに個人で)商売目的で輸入すること
②「一般(商業)輸入」:
商売目的で輸入すること
「小口輸入(商業輸入)」と「個人輸入」の違いとは?
前項までを踏まえて③「小口輸入(商業輸入)」と①「個人輸入」の違いについて解説します。
ときどきネット上で〝個人輸入は法律に反する…〟などという文言が見受けられることがありますが、これは誤りです。正しくは〝個人使用目的で輸入したものを販売するのは違法〟となります。
つまり、先述したように「小口輸入」とは「販売目的で商品を輸入した個人輸入」を意味します。
したがって、たとえ少量での輸入といえども、輸入したものを販売することは商業輸入ですので、法規制などのルールに従って輸入販売を実施しなければなりません。
また両者では関税の計算率も異なります。
■個人輸入の関税の計算率:
「海外の市場価格×0.6×関税率」で計算(課税対象額が1万円以下であれば関税と消費税は免除)
■小口輸入の関税の計算率:
商品の市場価格の100%に関税率をかけた方式で計算(送料や保険費用なども含まれる点に注意)
税関における「個人輸入」と「小口輸入(商業輸入)」の判断基準とは?
最後に、税関における「個人輸入」と「小口輸入(商業輸入)」の判断基準について見ていきましょう。
結論から言うと、個人利用と商業利用の目的は、それらを明確に区別することは非常に難しく、税関と見解が異なるケースが多々あります。
「個人輸入」と「小口輸入(商業輸入)」の違いには、明確な判断基準がなく、税関がその場で実施する検査結果で左右されるのです。
税関における判断材料とされているのが、価格・数量・頻度などです。
それらが個人が利用する範囲を超えていると税関が判断すれば、商売目的の「小口輸入(商業輸入)」となる可能性が大きいということです。
先述したように、個人輸入と小口輸入では関税の計算方法が異なるので、販売目的の個人輸入を行う場合には、あらかじめ小口輸入として一連の作業を行う必要があるのです。
6. 海外から日本へ仕入れる「輸入商品」をセレクトする6つの方法
顧客のニーズを理解してセレクトする
輸入ビジネスに限らず、ビジネスの基本は「顧客が必要としている商品・サービスを提供する」ことです。そのためには顧客のニーズを理解しなければなりません。
さらに「仕入れ値」や「売値」や「利益率」はもちろん、「競合商品」や「ブランド力」なども併せて考慮する必要があります。しかし先述の「ニーズ」がもっとも重要であることは言うまでもありません。
そのような「顧客ニーズのある商品をセレクトする方法」を6つピックアップしました。

下記よりそれぞれの方法を見ていきましょう。
① 大手通販サイトのランキングを参考にする
Amazonや楽天などの大手通販サイトのランキングは、現在市場で人気のある商品やトレンドを把握するのに役立ちます。これらのランキングは、現在市場で何が人気か、どのような傾向があるかを把握するのに役立ちます。特に新商品や流行している商品の情報を得るのに適しています。
② メルカリなどのフリマアプリで売れている商品をリサーチする
メルカリなどのフリマアプリでは、個人が所有する商品が販売されており、ここでの売れ筋は市場の需要を反映しています。また、中古市場での人気商品は、新品市場でも需要がある傾向が高いため、販売戦略に応用できます。
③ 日本で販売されていないブランドをセレクトする
日本市場に未導入の外国ブランド商品を選ぶことで、新鮮さと独自性を提供できます。これにより、市場に新しい選択肢を提供し、競合との差別化を図ることができます。
④ 日本から撤退したブランドをセレクトする
日本市場から撤退したが、以前は人気があったブランドの商品を取り扱うことで、特定の顧客層の関心を引きつけることができます。これらの商品は特定のファンやコレクターにとってはアイテムとなります。
⑤ 各メディアで紹介されている商品をセレクトする
テレビ、雑誌、オンラインメディアなどで取り上げられている商品は、一般的な認知度が高く、市場での受け入れが早い傾向にあります。これらの商品をセレクトすることで、広告やプロモーションの影響力を利用した販売促進が可能になります。
⑥ 著名人が愛用している商品をセレクトする
有名人やインフルエンサーが使用している商品を選ぶことで、彼らのフォロワーやファンにアピールできます。この方法は特にファッションやライフスタイル関連の商品で効果的です。
7. 海外から輸入商品を買い付ける4つの方法
日本のユーザーがどのような商品を求めているのかを理解したら、そのニーズに対応できる商品を海外から仕入れます。
ここからは、海外から輸入商品を買い付ける方法について解説します。
おもな輸入商品を買い付ける方法は以下の4つになります。

それぞれの方法を順番に解説していきます。
① 海外通販サイト・海外仕入れサイト
英語に自信がない方や、仕入れの時間がとれない方でも、もっとも手軽に利用できるのが「海外通販サイト」です。ひとくちに「海外通販・仕入れサイト」といっても、その種類は様々です。
代表的な「海外通販サイト」だとAMAZONが思い浮かぶ方も多いと思いますが、実際に世界14ヵ国でAMAZONは展開しており、各国のAMAZONサイトから商品を仕入れることが可能ですし、英語を始めとする外国語に自信がない方でも、Google Chromeにある翻訳機能を使えば、大体の意味は理解できるはずです。
またAMAZON以外でも、卸業者によるインターネット上の卸サイトや卸業者を集めたサイトなど、インターネット上にはたくさんの卸サイトや問屋があります。
代表的なものだと、小売店や個人事業主などが自分の店舗で販売するための商品を、サイト内の問屋および卸売を行う企業から仕入れることができるオンラインサイト「NETSEA(ネッシー)」などがあります。
② 海外展示会・見本市
国内の展示会や見本市と同じように、海外でも展示会や見本市が開催されています。こちらも日本と同様に各業種ごとに分かれており、同業者が集まって展示を行います。
いわゆるBtoBの場であるケースがほとんどで、来場者も一般消費者ではなく、その業界のバイヤーであることが多いとされています。
商談のスタイルも、国内の展示会や見本市と同じように、出展企業のブースをバイヤーが訪れて商談するというのが一般的です。ただ、海外での展示会や見本市なので、英語でのやりとりは必須です。
各見本市・展示会の情報を知りたい方は、国内外の国際見本市・展示会の有益な情報が掲載されている、JETROのデータベース「世界の見本市・展示会情報(J-messe)」を参考にするとよいでしょう。
③ 海外へ買い付けに行く・海外のメーカーや販売店と直接契約をする
実際に海外に渡航して、現地で買い付けをする場合、多くのケースで、現地の雑貨店で購入したり、メーカーや問屋に赴いて、直接商品を購入したりすることが多いです。
現地で開催されている蚤の市や、たくさんの店舗が集まっているマーケットで、掘り出し物を購入するという手もあります。
そのような足を使った買い付けが厳しい場合は、現地のショッピングモールやスーパーで気になった商品のラベルを確認して、現地のメーカーに直接問い合わせをしてみるのもよいでしょう。
あるいは海外現地に知人や信頼できるディーラーがいる場合は、彼らにマージンを支払って、買い付けを依頼することも可能です。その場合は、きちんとした信頼できる相手でないと、損をしたり詐欺にあったりなど、トラブルに巻き込まれる可能性も想定しなければなりません。
また海外に赴かなくても、日本から海外のメーカーや販売店と契約して、直接海外からの商品を仕入れる方法もあります。ただ、最低限のロット数の問題や、複雑な通関業務を通さなければいけないというデメリットも存在します。
④ 各国大使館の商務部
各国の大使館には、日本への輸出の窓口となる「商務部」が設けられている場合があります。欧米諸国では州政府単位で在日事務所を設けているところや、貿易振興機関の事務所を開設している国もあります。
ただし、業務内容は国ごとに異なりますので、事前に電話などで問い合わせをしておくことをおすすめします。
8. 日本企業の「輸出入・貿易・通関」に関する最新トレンド
「輸出入・貿易・通関」に対する相談が急増
最後に本稿のメインテーマ「輸入販売ビジネス」の補足情報として、「日本企業の輸出入・貿易・通関に関する最新トレンド」をご紹介します。
毎年、海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima~出島~」では1年間の進出相談と海外進出企業ならびに、海外進出支援企業を対象に実施したアンケートをもとに「海外進出白書」を作成しています。
下記は「Digima〜出島〜」に寄せられた、海外進出を検討する企業の相談内容のランキングを示したグラフになります。

結論から言えば、アフターコロナにおいて、もっとも件数を大幅に増やしたのは「輸出入・貿易・通関」に対する相談でした。また、コロナ禍で減少傾向にあった「会社設立・登記代行」も増加に転じました。
その背景には近年の「円安」があり、その結果として「輸出入・貿易・通関」および「販売代理店探し」に関する相談が増加したことがうかがえます。
これは輸出産業にとってのチャンスという側面だけでなく、「外貨を獲得することが重要だ」といったような危機感の広がりもあったはずです。単純に円安による輸出チャンスの拡大だけを考えれば、「輸出入・貿易・通関」や「代理店探し」「越境EC」が増加するというのはわかりますが、「会社設立・登記代行」も増加しており、これはコスト面を考えると逆行しています。そういった意味で、「外貨獲得の必要性」という危機感を持って海外進出への取り組みを強化している企業が多いのではないかと推測しています。
単純に円安による輸出チャンスの拡大だけを考えれば、「輸出入・貿易・通関」や「代理店探し」「越境EC」が増加するというのは当然ですが、「会社設立・登記代行」が増加するというのはコスト面を考えると逆行しています。
そういった意味で、「外貨獲得の必要性」という危機感を持って海外進出への取り組みを強化している企業が多いのではないかと推察されます。
…上記の内容をさらに深掘りした日本企業の海外進出動向を「海外進出白書」にて解説しています。
日本企業の海外進出動向の情報以外にも、「海外進出企業の実態アンケート調査」「海外ビジネスの専門家の意識調査」など、全117Pに渡って、日本企業の海外進出に関する最新情報が掲載されている『海外進出白書(2023-2024年版)』。
今なら無料でダウンロードが可能となっております。ぜひ貴社の海外ビジネスにお役立てください!

9. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
貴社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
今回は、海外から商品を仕入れる「輸入販売ビジネス」を始める際に必要な知識について解説しました。
『Digima〜出島〜』には、厳正な審査を通過した優良な輸出入・貿易・通関のサポート企業が多数登録しています。当然、複数の企業の比較検討も可能です。
「海外から商材を輸入したい」「通関や輸出入許可の申請をサポートしてほしい」…といった、多岐に渡る海外資材・材料調達におけるご質問・ご相談を承っています。
ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、貴社にピッタリの輸出入・貿易・通関の支援企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
もっと企業を見る