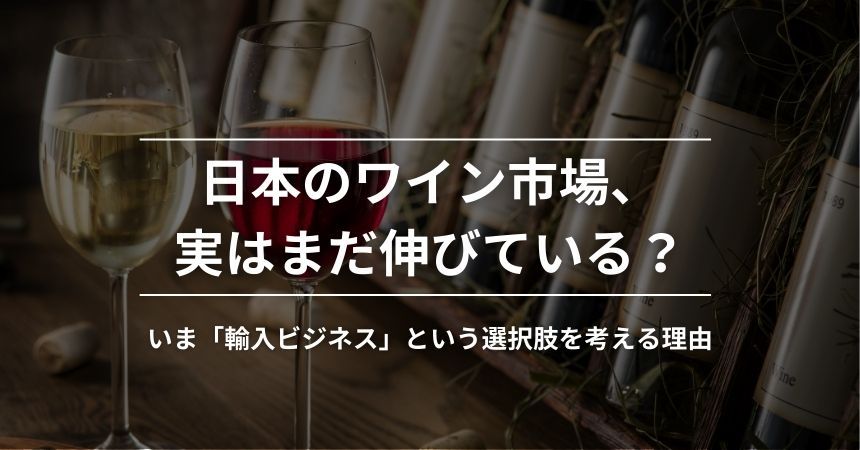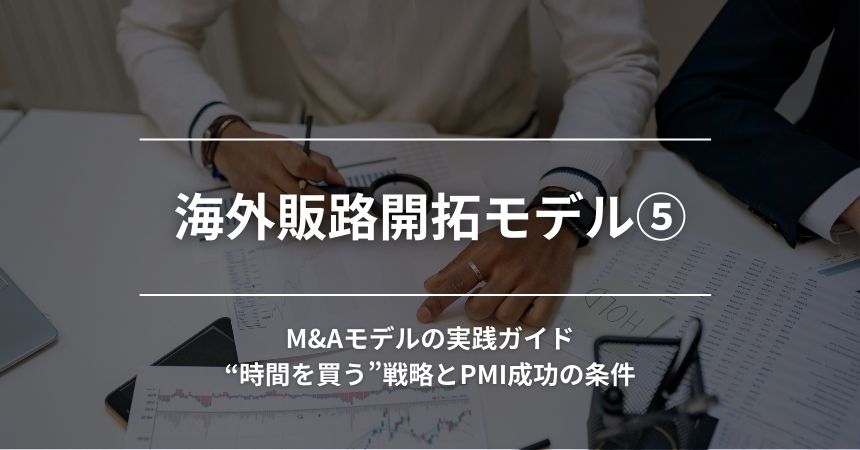サプライチェーン再設計時代の現実解ーーリスク分散から始めるASEAN戦略

世界経済が不確実性を増す今、企業にとって柔軟かつ強靭なサプライチェーンの構築は喫緊の課題となっています。特にここ数年、地政学的リスクの表面化が著しく、グローバル企業の間では生産・調達拠点の多極化が進んでいます。
中でも注目されているのがASEAN諸国。その背景には、米中対立、ロシア・ウクライナ戦争、エネルギー価格の高騰、そしてパンデミックといった外的ショックが重なり、かつてのように「中国一国に依存する体制」では企業の継続性が保てないという現実があります。
本記事では、ASEAN戦略の鍵を握る「柔軟なサプライチェーン再設計」の考え方と、進出ハードルを下げる手法として注目を集めるEOR(Employer of Record)の活用法に焦点を当て、今こそ見直すべきグローバル展開の現実解を提示します。是非、参考にしてください。
▼ サプライチェーン再設計時代の現実解ーーリスク分散から始めるASEAN戦略
世界経済の不確実性とサプライチェーン再設計の必要性
グローバル企業が直面する地政学的リスク
世界経済はいま、長期的な安定成長の前提を失いつつあります。新興国の台頭や人口動態の変化といった構造的要因に加え、近年では地政学的リスクの顕在化が企業活動に直接的な影響を及ぼしています。米中の覇権争いは関税政策や技術覇権争いに発展し、ロシア・ウクライナ戦争はエネルギー供給と穀物流通に混乱をもたらしました。さらに、コロナ禍によって露呈したサプライチェーンの脆弱性は、企業にとって「安価で効率的な調達・物流」よりも「持続可能性と柔軟性」を重視すべき時代への転換を強く印象づけました。
その結果、製造コストや輸送費、納期の信頼性といった従来の指標だけでは、企業の競争力を担保できなくなっているのが現実です。加えて、特定地域への依存度が高い企業ほど、為替の変動、政情の悪化、貿易障壁の変化といった「非経済的要因」による影響を大きく受けやすくなっていることから、地政学リスクを戦略的にマネジメントする視点が欠かせません。
特に製造業や消費財業界では、供給が滞れば顧客ロスや売上損失だけでなく、ブランドの信用失墜にもつながりかねません。こうした状況下で、企業のグローバル調達・生産・販売体制は、改めて見直しを迫られているのです。
生産・調達拠点の多極化が進む背景
こうしたリスクを踏まえ、多くの企業が従来の「一極集中型モデル」から脱却し、「多極分散型モデル」への移行を本格化させています。特に中国に集中していた生産拠点や調達ルートを、ASEANやインド、メキシコ、東欧諸国など他の地域へ分散する動きが加速しています。この「拠点の多極化」は、単なるリスクヘッジにとどまらず、各国の市場成長力・FTA適用・物流の利便性・人件費水準といった複数の要因を踏まえた、より戦略的な意思決定へと進化しています。
加えて、近年では脱炭素やESG(環境・社会・ガバナンス)経営の観点からも、持続可能なサプライチェーンをどう設計するかが問われています。たとえば、カーボンフットプリントの削減を前提に、調達・生産・輸送を最適化する必要性が生じており、これもまた拠点多極化の後押しとなっています。
また、テクノロジーの進化もこの動きを支えています。生産工程の自動化やロボット技術、サプライチェーンマネジメントにおけるAI・IoTの導入により、以前よりも遠隔での運用・管理が可能になったことで、複数拠点を一元的にコントロールすることへのハードルも下がってきています。
つまり、生産・調達拠点の多極化は、コスト・リスク・成長・持続可能性という複合的な観点から見ても、今やグローバル企業にとって“避けては通れない戦略課題”となっているのです。
トランプ関税が突きつけた「中国リスク」
米中摩擦が与えた構造的インパクト
2018年から始まったトランプ政権による対中追加関税政策は、グローバル企業にとって「中国リスク」の現実性を強く印象づける転機となりました。特に最大25%にもおよぶ関税措置は、従来のコスト計算を大きく覆し、多くの企業が急速に「脱・中国依存」を検討するきっかけとなったのです。
2025年4月に発表された「相互関税政策」も、こうした流れを一段と加速させています。この新たな政策では、日本やASEAN諸国からの輸入品にも高い関税が課される方針が示されており、中国一極集中の体制に加え、第三国を経由した調達戦略のリスクも露呈しています。
こうした事態を受けて、日系企業やグローバルブランドは「チャイナ・プラスワン」戦略を明確化。コスト面だけでなく、地政学的な安定性、サプライチェーンの回復力(レジリエンス)を加味した多拠点展開が急速に進んでいます。
代替地としてのASEAN:注目される「戦略的分散」
中国に代わる製造・調達拠点として注目を集めているのがASEAN諸国です。その理由は単なるコストの安さにとどまりません。ASEANは、成長市場としてのポテンシャルに加え、FTA(自由貿易協定)ネットワークの広がり、豊富な労働力、輸出志向の産業政策など、外資誘致のための条件が整っているのです。
例えば、ベトナムでは韓国・日本企業をはじめとする外資製造業の進出が加速し、サプライチェーンの再設計拠点として存在感を高めています。またタイやインドネシアも、電機・自動車部品・食品加工など多様な業種において強固な製造基盤を築いています。
さらに、RCEPやAFTAといった多国間協定の恩恵により、域内での関税優遇やスムーズな物流も実現されており、ASEANを起点とした国際展開が現実的な選択肢となってきています。今やASEANは「代替拠点」ではなく、「主力の柱」として再評価されているのです。
とはいえ「拠点設立」はリスクも高い
中小企業にとっての“進出コスト”の重み
たしかに、ASEANは地政学的リスクの回避や成長市場へのアクセスという観点から非常に魅力的なエリアですが、現地に製造拠点や営業所を設立するとなると、決して簡単な話ではありません。特に日本の中堅・中小企業にとっては、初期投資の負担が大きな壁となります。現地法人の設立登記、会計・法務対応、不動産のリース契約、設備の購入、ITインフラの構築といった「目に見える」コストに加え、現地スタッフの採用・教育・定着支援などの「目に見えにくい」コストも無視できません。
さらに、進出後に万が一撤退することになれば、設備資産の処分、スタッフとの契約解除、顧客・取引先との関係清算など、多大なコストと労力を要します。進出の成否が企業の財務体質や信用に影響を与えかねない現実を前に、躊躇する企業が多いのも無理はありません。特に国内マーケットでのリソースが限られる中小企業にとっては、「撤退できる仕組みを最初から設計する」という視点が不可欠となります。
雇用・労務・法規制の“見えない壁”
また、ASEAN各国では表面的には外資受け入れに積極的な姿勢が示されている一方で、実際の現地運営には多くの“見えない障壁”が存在します。たとえば、国によっては現地雇用率の規制や外国人就労ビザ取得の要件が厳しく、思うように人材が確保できないケースもあります。さらに、各国で異なる労働法規や退職金制度、労働組合対応など、日本とはまったく異なる制度運用が求められます。
こうした法規制の違いを理解せずに、見切り発車で現地採用を行った結果、従業員とのトラブルに発展したり、当局との交渉に時間を取られるケースも少なくありません。また、文化的な違いによるマネジメント上の摩擦、価値観の相違からくる職場離職の頻発なども、多くの企業が進出後に直面する“現地運営の難しさ”です。
このように、拠点設立には明確な資本コストと同時に、“制度面・人材面の不確実性”というコストが付きまといます。単に「現地法人をつくれば現地で商売が始まる」というわけではなく、あらゆるリスクとコストを見積もったうえで、持続可能な戦略としての現地進出かどうかを判断する必要があります。
その解決策が「EOR(Employer of Record)」の活用
法人設立なしで海外人材を活用できる柔軟な仕組み
こうした現地拠点設立に伴う高いコストと複雑な手続きへの懸念に対し、いま注目を集めているのが「EOR(Employer of Record)」という雇用代行モデルです。EORとは、企業が海外で現地法人を持たなくても、現地のパートナー企業(EOR代行会社)が法的雇用主として人材を雇用し、その人材を実質的に企業の指揮命令下で業務に従事させるという仕組みです。
EORを活用すれば、企業は現地の労働法や税制に煩雑な対応をせずとも、スピーディに人材を確保し、現地市場での事業検証を開始できます。たとえば、ベトナムやフィリピンに数名の営業・マーケティング担当を置いて、市場の反応や文化的な適合性をテストする、あるいは顧客ヒアリングや業界調査などを現地で進める、といった実践的なステップが低リスクで可能になります。
「おためし進出」から「本格展開」への橋渡しに
EORの最大の利点は、まさに“撤退の自由度”です。仮に現地市場で期待した成果が出なかった場合でも、法人設立と異なり、雇用契約を終了することで比較的スムーズに現地からの撤退が可能です。この柔軟性は、特に海外展開に不慣れな中堅・中小企業にとって、大きな心理的・財務的ハードルを取り除く存在になります。
一方で、EORによって現地業務が軌道に乗り、商談数や案件化が一定の成果を見せ始めた場合には、正式に法人を設立し、よりスケーラブルな事業展開へと移行することも可能です。つまりEORは、単なる一時的な雇用手段ではなく、「本格展開前の市場テスト」あるいは「撤退リスクを最小化した探索的進出」として活用できる実践的なステップなのです。
このように、EORはこれまで“進出か、しないか”という二択しかなかった海外戦略に、新たな選択肢をもたらす存在として注目されています。進出の柔軟性とスピードを高めながら、現地のリアルな声をつかみ、確実な戦略判断につなげる――。今後の不確実性の時代においては、EORのような可変性の高い戦略が、企業の競争力を大きく左右する鍵となるでしょう。
結論:激動の時代こそ「柔軟性」が最大の武器に
ここまで見てきたように、グローバル経済の不確実性が増す中で、サプライチェーンの再設計はもはや一部の大企業だけの課題ではなく、すべての企業にとって現実的かつ喫緊の経営テーマとなっています。特に製造業や流通業をはじめとする企業では、かつてのように「中国一国依存」型のサプライチェーンは明らかにリスクの高い戦略となっており、地理的・政治的に分散したネットワークの構築が不可欠です。
この文脈において、ASEAN地域は単なる“中国の代替地”にとどまらず、今後の企業成長を支える「攻めの製造・調達拠点」としての存在感を強めています。安定した経済成長、豊富な労働力、FTA・RCEPによる貿易優遇、さらに急拡大する内需市場など、ASEAN各国の魅力は枚挙にいとまがありません。
一方で、現地拠点の設立には多額の初期投資と法制度への対応などの障壁が存在し、特に中堅・中小企業にとっては容易に踏み切れないという現実もあります。こうした中で、EOR(Employer of Record)のように、進出と撤退の柔軟性を担保した雇用モデルを活用することは、リスクを抑えながら機動的に海外展開を進めるための有力な手段となるでしょう。
今後、企業がASEAN戦略を進めるうえで最も重視すべきは「柔軟性」と「スピード」です。市場の変化に迅速に対応し、小さく始めて、大きく育てる。EORのような選択肢を戦略的に活用することで、激動の時代にも自社の成長と競争力を持続的に確保できるのです。慎重でありながらも大胆に。これが、サプライチェーン再設計の時代における日本企業の次なるスタンダードと言えるでしょう。
なお、ASEANでの事業展開にあたり、EOR(Employer of Record)サービスを活用することで、法人設立を行わずに現地での人材採用・雇用管理が可能になります。弊社では、現地の法規制に準拠した給与計算、社会保険手続きなどを一括でサポートし、スムーズかつ効率的に事業を開始できる環境を提供しております。
ASEANでの採用や人事・労務に関するご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談