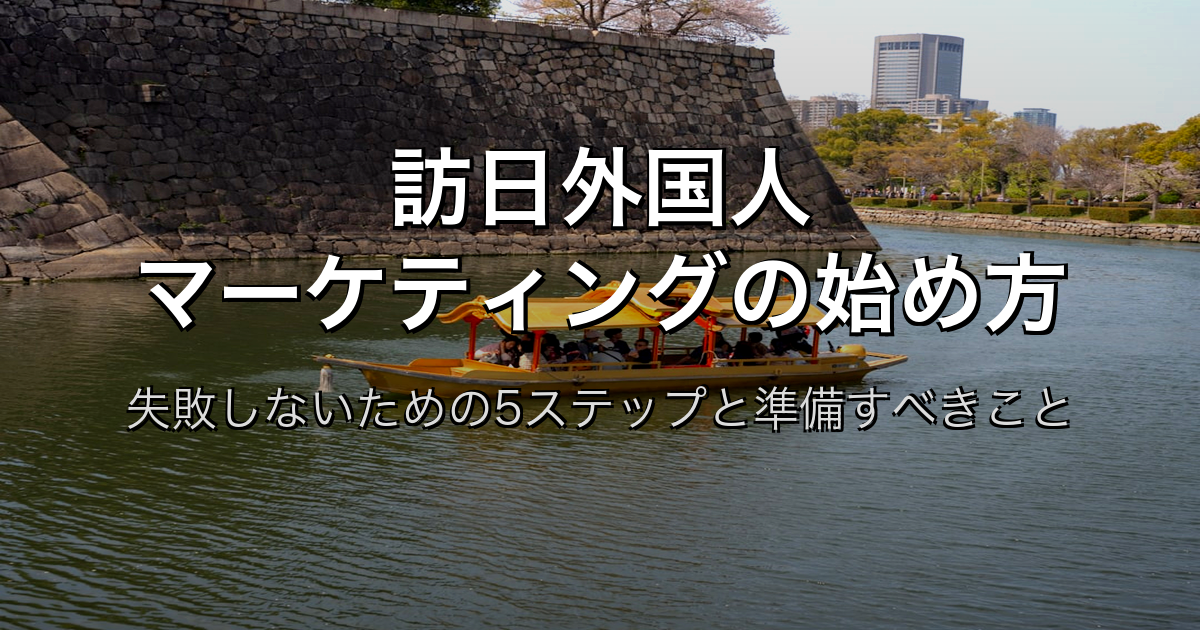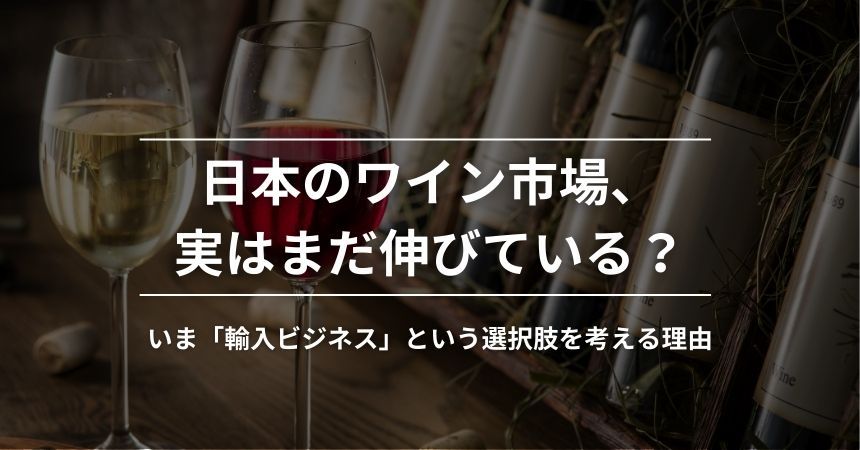越境ECとは? 成功のポイントはハイブリッド型とインバウンド対応! その他、始め方・市場選定まで徹底解説

「越境EC(Global E-Commerce)」とは、国や地域の境界を越えて、インターネット上で商品やサービスを販売・購入する取引形態を指します。すなわち、日本の企業や個人が、自国以外の消費者に対してオンラインで販売する行為がこれに該当します。EC市場のグローバル化が進む中で、越境ECは企業にとって「国内需要の限界を超える販路拡大策」として注目されており、コロナ禍を契機にその流れはさらに加速しました。
背景には、海外消費者の購買行動のデジタル化と、日本製品に対する高い信頼性、そして円安傾向による価格競争力の向上があります。加えて、現地にリアル店舗を構えずともテストマーケティングが可能であることから、スタートアップや中小企業にとっても導入ハードルが下がりつつあります。
なお、越境ECは一般消費者を対象としたBtoCだけでなく、企業間取引のBtoB領域でも活用が広がっています。部品や原料の供給、OEM製品の発注などもオンラインで完結する流れが進んでおり、業種を問わず戦略的なチャネルとして導入が進んでいるのが現状です。
本記事では、越境ECの基礎から始め方、注目の市場動向、販路の選び方、成功に向けた実務対応、そしてインバウンドとの連携まで、網羅的にわかりやすく解説してまいります。越境ECを今後の成長戦略のひとつとしてご検討中の方にとって、実務的なヒントとなれば幸いです。
▼ 越境ECとは? 成功のポイントはハイブリッド型とインバウンド対応! その他、始め方・市場選定まで徹底解説
越境ECの市場動向と注目の国・地域
世界で拡大する越境EC市場と日本企業への追い風
世界の越境EC市場は年々拡大を続けており、経済のデジタル化とともに今後も成長が見込まれています。国際的な調査によれば、2027年には世界の越境EC市場が5兆ドル規模に達するとも予測されており、これはグローバルEC市場全体の大きな割合を占める数字です。インターネットと物流の整備により、消費者は海外製品を以前より手軽に購入できるようになり、日本企業にとっても“距離”はもはや参入障壁ではなくなりつつあります。
特に日本製品は「高品質」「安心・安全」「洗練されたデザイン」といったイメージが海外でも浸透しており、越境ECを通じてブランド価値を高めやすい状況が整っています。伝統産品から美容・ヘルスケア、アパレル、アニメ・キャラクター商品まで、ジャンルを問わず「日本ならでは」の強みを活かせる分野は少なくありません。
注目される海外市場:東南アジア、中国、北米、中東など
越境ECのターゲットとして特に注目されるのが、東南アジア諸国(ASEAN)、中国、北米、そして中東圏です。たとえば東南アジアでは、スマートフォン利用率が高く、EC普及率も上昇傾向にあります。若年層の購買意欲も旺盛で、日本製品への関心も高いため、価格帯や訴求方法を最適化すれば有望な市場といえます。
中国市場は競争が激しいものの、日本ブランドへの信頼性は根強く、TmallやJD.comを活用した公式出店などにより安定的な売上を構築する企業も存在します。一方、アメリカをはじめとする北米市場では、プレミアム製品やライフスタイル商品への評価が高く、ECインフラが整備されているため、継続的な運用がしやすい利点があります。
また、中東やインドといった新興市場も近年注目度が上昇しており、文化や決済の違いへの対応を前提としつつ、早期参入のチャンスが広がっています。
越境ECの始め方と販売チャネルの選び方
販売チャネルの基本:独自ドメイン型とモール出店型
越境ECを始める際には、まず「どのようなチャネルを使って販売するか」が重要な検討ポイントとなります。大きく分けて、ひとつは自社でECサイトを構築・運用する独自ドメイン型、もうひとつはAmazon、Shopee、Tmall Globalなどの海外ECモールに出店するモール出店型の2つが存在します。
独自ドメイン型は、自社のブランディングや自由なデザイン・プロモーションが可能な反面、集客や決済、言語対応、物流設計などを自力で行う必要があります。一方、モール型は既に集客力や決済インフラが整っており、販売開始までのスピード感や信頼性の面で優位です。特に現地での認知が低い段階では、モールを起点にスタートしやすいという利点があります。
両立が主流:成功企業はハイブリッド型を選ぶ傾向に
実際に越境ECで成功している企業の多くは、独自ドメイン型とモール出店型の両方を併用する「ハイブリッド戦略」を採用しています。モールでの出店は顧客との最初の接点となり、そこから自社サイトへ誘導することで、より深いブランド体験を提供するという形がよく見られます。
このように複数のチャネルを持つことで、リスク分散にもつながり、モール側のルール変更や手数料体系の変更にも柔軟に対応できる体制を構築できます。また、モールで得た顧客データを自社サイトのマーケティングに活かすこともでき、チャネル間の相乗効果が事業成長を後押しします。
SNSや動画を活用した越境プロモーションの拡張
販売チャネルと連動する形で、SNSや動画プラットフォーム(Instagram、TikTok、YouTubeなど)を活用したプロモーションも、越境ECにおいて極めて重要です。現地言語での発信や、インフルエンサー(KOL)とのコラボレーションは、商品理解や信頼感の形成に直結します。
近年は、SNSから商品ページに直接誘導する「ソーシャルコマース」も広がっており、販売チャネルはECサイトだけに留まりません。越境ECでは「どこで売るか」だけでなく、「どのように見つけてもらい、どう伝えるか」が売上に直結するため、チャネル戦略とプロモーション戦略は切り離せない存在となっています。
越境EC成功に向けた実務上のチェックポイント
決済・為替対応と多通貨処理の整備
越境ECにおいて、最初のハードルのひとつが「決済環境の整備」です。海外の消費者が購入をためらう最大の理由のひとつが「使い慣れた決済手段が使えないこと」です。したがって、対象とする国・地域の主流決済手段に対応することが不可欠となります。クレジットカード、PayPal、Alipay、LINE Pay、GrabPay など、地域ごとに異なる決済文化に柔軟に対応できる仕組みが求められます。
また、通貨の違いも考慮が必要です。訪問者のIPアドレスやブラウザ言語に応じて通貨を切り替える「多通貨対応」は、ユーザーの離脱防止に効果があります。為替の変動にともなう価格調整や決済時の為替手数料にも注意を払い、価格設定の戦略に組み込むことが、信頼性と利益率の両立に貢献します。
海外配送・通関・返品対応の体制構築
物流もまた、越境ECの成否を大きく左右する要素です。配送方法は、EMSや国際宅配便(DHL、FedEx、UPSなど)、越境EC向けの物流代行サービスなど複数の選択肢があります。配送スピードやコスト、追跡の有無などを総合的に考慮し、顧客の期待に合った配送体制を整えることが重要です。
さらに、国によっては輸入関税や通関書類の要件が異なるため、通関に強い物流パートナーの選定や、商品のHSコード管理といった実務面での準備も不可欠です。返品対応についても、あらかじめ明確なポリシーを提示しておくことで、トラブルの未然防止と顧客満足度の向上につながります。
カスタマー対応と文化・言語の壁を越える工夫
海外顧客とのやり取りにおいては、言語・文化・時差という3つの“壁”が存在します。特に購入後の問い合わせ対応において、顧客の言語に対応できないことで機会損失や信頼の低下を招くことも少なくありません。そのため、多言語対応のカスタマーサポート体制の整備、もしくは外部委託の活用が効果的です。
時差に関しても、リアルタイム対応が難しい場合は、24時間以内に返信するなど一定の対応基準を設けておくと良いでしょう。また、FAQページやチャットボットの導入も、文化の違いによる問い合わせのパターンに対応する手段として有効です。ローカルの期待に応える対応品質は、リピーターの獲得やブランドロイヤルティの醸成につながります。
越境ECのメリット・デメリットとリスク対策
越境ECのメリット:市場拡大とブランド価値の向上
越境ECの最大の魅力は、言うまでもなくグローバル市場へのアクセスです。国内需要が飽和傾向にあるなかで、新たな成長の場として海外に目を向ける企業が増えています。越境ECであれば、現地に拠点を持たずとも、海外の消費者に自社商品を届けることが可能であり、低コスト・低リスクで海外市場への足がかりを築けるのが特徴です。
また、日本製品の持つ「高品質」「信頼性」といったイメージは、多くの国で好意的に受け入れられており、越境ECはそのブランド価値をさらに強化する手段にもなります。とりわけ、丁寧なつくりやパッケージデザイン、ストーリー性を重視する消費者層には、EC上の情報発信やSNSを通じて価値を深く伝えることができます。
デメリットと実務的課題:物流・規制・文化差への対応
一方、越境ECにはいくつかの注意すべきデメリットや実務課題も存在します。まず挙げられるのは、物流コストと配送遅延のリスクです。とくに遠距離配送の場合は送料が高額になるだけでなく、通関の遅れや現地配送業者の対応品質によって、到着までの日数が読みにくくなる場合があります。
また、輸出入に関わる各国の規制や法制度への理解も欠かせません。例えば、食品・化粧品・医療機器などの商材は、販売国によって許可制や成分規制が異なるため、事前の確認と制度対応が求められます。さらに、文化や習慣の違いから、マーケティング表現や顧客対応にずれが生じることもあります。翻訳や広告の表現が現地の感覚と合わないケースでは、ブランド毀損につながるリスクも否定できません。
リスク対策:現地目線の準備と外部パートナーの活用
こうした課題を乗り越えるためには、現地視点を持った設計と、外部パートナーとの連携が重要です。たとえば、物流面では国際配送に強いフルフィルメントサービスを活用したり、法制度に関しては現地の法務・税務に詳しい支援会社のサポートを受けたりすることで、自社単独での限界を補完できます。
また、進出前に「どの国のどの層に届けたいのか」を明確に定めることも、不要なリスクを回避するうえで極めて重要です。ターゲットを絞り込んだ上で、その国の文化や言語に配慮した商品紹介・接客を心がければ、越境ECは単なる販路ではなく、“海外ファン”を育てるためのブランド戦略ツールとして大きく機能します。
インバウンドと越境ECの相乗効果|訪日客を“越境ファン”に変える戦略
越境ECにおいて、インバウンド消費との連携は極めて有効な戦略のひとつです。訪日外国人観光客が日本国内で商品やサービスに実際に触れ、その品質や使い心地を体験したのち、帰国後にオンラインでリピート購入するという流れが定着しつつあります。これにより、「旅先での体験」を起点とした継続的な購買行動が生まれ、越境ECのリピート率やブランド認知度の向上につながるのです。
たとえば、旅館で使用された日本製の化粧品、レストランで提供された食器や調味料、土産店で購入されたスナックや和菓子といった商品は、「体験に紐づいた記憶」として消費者の心に残ります。その後、越境ECを通じて同じ商品を再購入したり、SNSでシェアしたりすることで、インバウンド体験が越境販売の起点となる“ストーリー”に昇華されていきます。
このような流れを促進するためには、リアル店舗での多言語案内や越境ECサイトへのQRコード掲示、SNSアカウントのフォロー促進などを通じて、訪日中から越境ECへの導線を設計しておくことが鍵となります。とくに訪日外国人が多い地域の小売店・観光施設・ホテル・交通機関などと連携し、購買体験をオンラインに接続する仕掛けを設けることで、越境ECの成長を「国内観光の延長線上」に位置づけることが可能になります。
また、訪日前・訪日中・帰国後という3つのタイミングを通じた一貫したコミュニケーション設計を行うことで、越境ECは単なる販売チャネルではなく、「日本ブランドとの継続的な接点を生み出す顧客体験の場」として進化していきます。
越境ECの成功事例から学ぶポイント
越境ECは、業種や企業規模にかかわらず、明確な戦略と準備を整えれば着実に成果をあげることができる取り組みです。ここでは、実際に成果を上げている企業の事例をもとに、成功の要因を整理していきます。
たとえば、日本茶を扱うある老舗企業では、海外の日本文化愛好家に向けた発信をSNSで丁寧に行い、自社ECサイトを多言語対応で整備。最初は個人向けの小規模販売から始め、顧客のレビューや動画投稿をきっかけに話題となり、台湾やアメリカを中心に安定的な売上を確保するに至りました。この企業は、同時にAmazonやShopeeといったモールにも出店し、複数の販売チャネルを柔軟に組み合わせるハイブリッド戦略を展開しています。
また、地方の伝統工芸メーカーでは、訪日観光客が工房を訪れる体験型コンテンツを提供し、帰国後に越境ECで商品をリピート購入できるよう導線を設計。現地言語での商品紹介や、使用シーンを伝える動画などを活用することで、「体験を思い出に変えるEC」の形を確立しています。
さらに、ストーリーテリングを重視したある和菓子ブランドは、商品の背景にある地域性や季節感、作り手の想いを海外向けに丁寧に発信することで、「日本らしさ」を価値として届け、価格競争に巻き込まれずに安定したブランド力を構築しています。
こうした企業に共通しているのは、単に「商品を並べて売る」のではなく、ターゲットに合わせた文脈づくりと、継続的な顧客接点の設計に力を注いでいる点です。特にSNS活用やローカル文化との接点を重視した表現によって、ブランドへの共感と信頼を築く姿勢が印象的です。
越境ECは、ただ越境して販売するのではなく、「ブランドごと海外に届ける」ことを意識することで、中長期的に成長を続けるビジネスへと発展させることができるのです。
まとめ|越境ECは一過性ではなく“事業戦略”として設計する時代へ
越境ECは、単なる「海外でモノを売る手段」ではなく、今や企業にとって中長期的な成長の柱となり得る戦略的チャネルです。インターネットを介して国境を越えた取引が当たり前になった現在、国内市場に依存せず、世界に広がる顧客層へと視野を広げることは、持続的な企業競争力の確保にもつながります。
その一方で、越境ECは準備と実行において非常に多面的な要素が求められます。販売チャネルの選定、現地ニーズへの対応、決済・物流・カスタマー対応、そして現地文化を尊重したマーケティングなど、どれも手間のかかる取り組みですが、それぞれを丁寧に設計することで大きな成果へと結びついていきます。
とくに重要なのは、モールと独自ドメイン、自社と外部パートナー、オンラインとオフライン(インバウンド)を組み合わせるハイブリッド戦略です。一つの手段に依存するのではなく、複数の接点を立体的に構築することで、リスクに強く、再現性のある事業モデルをつくることが可能になります。
また、越境ECは「一度つくって終わり」ではありません。顧客の反応をデータとして捉え、改善を繰り返し、継続的な運用を行うことが信頼の積み重ねとなり、海外ファンの獲得やブランドの国際的成長へとつながっていきます。
グローバル市場に対する扉はすでに開かれています。越境ECを単なる挑戦で終わらせるのではなく、自社のビジネス成長を支える「基幹戦略」として位置づけることこそが、これからの時代に求められる発想です。
なお、「Digima~出島~」には、優良な越境ECの専門家が多数登録されています。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
是非、本記事を参考に越境EC事業に取り組んでみてください。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談