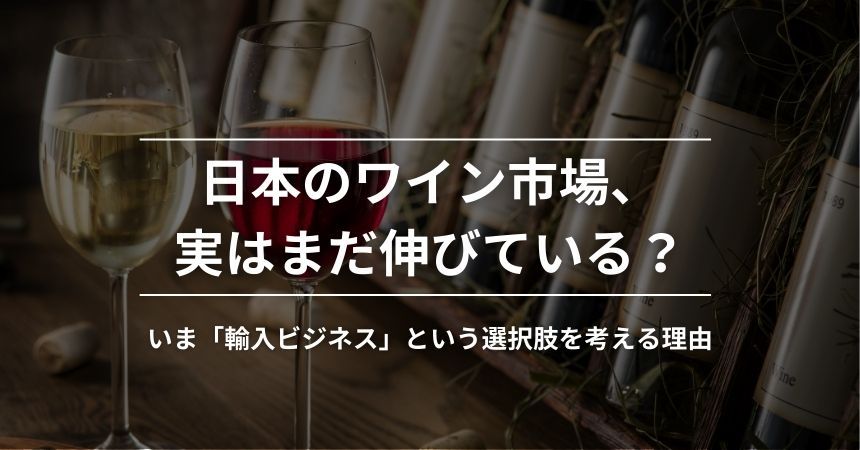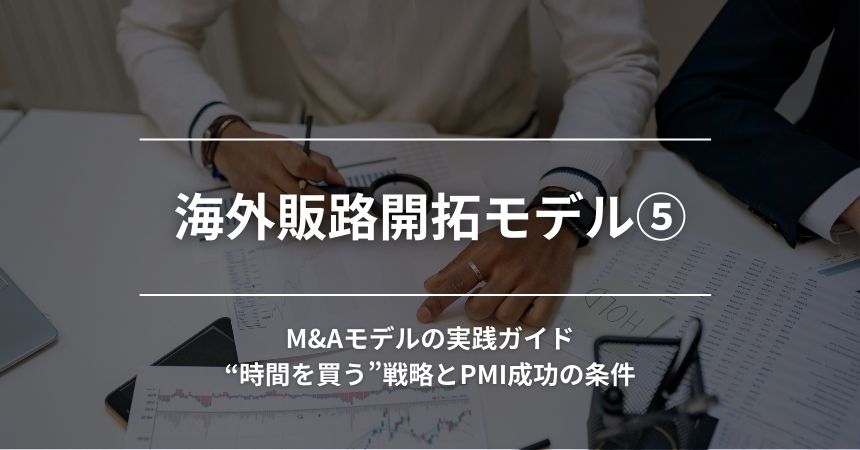AI翻訳で“伝わる”はつくれるか? 海外ビジネスに必要なトランスクリエーションの現在地

AIの進化は、翻訳・通訳の在り方を大きく変えつつあります。ChatGPTをはじめとする生成AIや、多言語対応の翻訳エンジンの登場により、誰でも手軽に多言語対応が可能となり、国境を越えた情報発信のハードルは大きく下がりました。ビジネスの現場でも、資料作成やチャットのやり取りにAI翻訳が活用されるケースが増え、翻訳コストの削減やスピード向上といった恩恵を実感する企業は少なくありません。
しかし、果たしてAI翻訳は「伝わる言葉」を生み出しているのでしょうか。海外ビジネスにおいて、翻訳や通訳に求められるのは単なる言語の置き換えではなく、相手の文化・価値観・感情に沿った“伝え方”です。とりわけ広告や販促、商談の場面では、言葉が「刺さるかどうか」が成果を左右します。ここで重要になるのが、「翻訳」ではなく「トランスクリエーション」という考え方です。
本記事では、AI翻訳の進化と活用法を押さえつつ、トランスクリエーションの意義、そしてAIと人間、どちらにもできること・できないことを整理します。さらに、現地スタッフや専門家の関与がなぜ不可欠なのか、具体的な場面に即して解説し、これからの海外ビジネスにおける言葉の使い方のヒントを提示します。
▼ AI翻訳で“伝わる”はつくれるか? 海外ビジネスに必要なトランスクリエーションの現在地
AI翻訳・通訳の進化と限界
生成AIで翻訳のスピードと低コスト化が進む
AI技術の進展により、翻訳・通訳のスピードとコストパフォーマンスは飛躍的に向上しました。ChatGPTやDeepLといった先進的なAIツールは、文脈をある程度理解しながら自然な翻訳を生成できるようになり、従来の直訳型翻訳とは一線を画す精度を実現しています。特に、業務メールの多言語化、Webサイトの多言語展開、社内マニュアルの翻訳などにおいて、AI翻訳は即時性と柔軟性を提供し、海外業務の初動段階を大幅に効率化しています。
また、リアルタイム翻訳機能の搭載された通訳アプリや、オンライン会議での字幕翻訳サービスの普及により、言語の壁そのものが以前よりずっと低くなりました。こうした進化により、海外展開のハードルが下がり、多くの企業がスモールスタートでグローバル化を志向できるようになったのは間違いありません。
「意味は通じても、伝わらない」AIの落とし穴
一方で、AI翻訳には限界も存在します。たしかに文意を把握し、正確に訳す技術は進んでいますが、「その言葉が相手にどう響くか」までを読み解くことは、依然として難しいのが現実です。特に広告コピーや製品説明文、商談での発言など、相手の感情に訴えかける表現においては、AIの翻訳が空虚に感じられることがあります。
たとえば、日本語では丁寧で自然な表現が、英語に訳すと冗長に映ったり、曖昧で信用を損なう可能性もあります。また、敬語のニュアンスや謙譲表現が文化的に異なる背景を持つ相手には伝わりづらく、結果的に誤解を招くリスクもあるのです。こうした「微妙なズレ」は、AIが文脈や感情を完全に理解するにはまだ遠いということを物語っています。
通訳も“伝える技術”が問われる時代へ
会議や交渉の場で用いられる通訳においても、AIの導入は進んでいます。リアルタイムの音声認識と翻訳が可能になった今、機械による同時通訳も実用化されつつあります。しかし、通訳には言葉を訳す以上の役割が求められます。たとえば、相手のトーンや感情、発言の意図を汲み取り、適切に言い換えるといった“間の取り方”や“配慮”は、現在のAIには困難な領域です。
また、文化的な禁忌や背景知識を知らずに直訳してしまうと、意図せず不快感を与えたり、ビジネスチャンスを損ねることもあり得ます。特に国際的な商談では、「言葉の正確さ」以上に「伝え方の繊細さ」が成否を左右します。ここにこそ、人間による通訳や現地スタッフの重要性が残る理由があります。
「翻訳」ではなく「伝える」が成果を分ける
文化・文脈を踏まえた「トランスクリエーション」とは
トランスクリエーションとは、単なる直訳ではなく、翻訳対象の背景にある文化、価値観、目的を理解し、相手に「刺さる」ように言い換える手法です。特に広告やマーケティング、商品コピーなど、受け手の感情に訴える表現では、直訳では意図が伝わらないことが多々あります。たとえば、日本で「安心・安全」と謳われる製品が、海外では「挑戦心のない製品」と見られることすらあります。このような感性のギャップを埋めるためには、現地文化や消費者心理に対する深い理解が不可欠です。
AIが翻訳の質を高めているとはいえ、現地の流行語やニュアンス、社会的背景を織り込んだ表現にはまだ対応が不十分です。こうした言語と文化の“翻訳を超えた調整”が求められる場面でこそ、トランスクリエーションの重要性が際立ちます。
刺さる表現に変えるには“現地目線”が欠かせない
本当に相手に響く言葉を生み出すには、「誰に、何を、どう届けるか」を徹底的に考える視点が必要です。その際に重要なのが、“現地目線”です。現地の人々の価値観や感情、生活文化を理解しないまま発信された情報は、いくら翻訳が正確でも受け手には届きません。
たとえば、日本企業がよく使用する「高品質」「安心」「真面目さ」といった価値は、日本国内では訴求力がありますが、国や地域によっては他の要素――たとえば「革新性」「スピード」「自己表現」――の方が購買行動に直結するケースもあります。言い換えれば、翻訳文に“現地らしさ”がなければ、その商品やブランドは「外国のもの」という距離感の中でしか評価されないのです。
AIと人間、両者の特性を活かすハイブリッド体制へ
AI翻訳が飛躍的な進歩を遂げた一方で、「翻訳に意味を持たせる」段階では、依然として人間の関与が必要です。今後の海外ビジネスにおいては、AIのスピードと正確性を活かしつつ、人間の感性や現地経験を活かして最終調整を行うハイブリッド体制がスタンダードになるでしょう。
たとえば、一次翻訳をAIで行い、その内容を現地に精通した翻訳者やマーケターがチェック・リライトするという流れです。このような分業体制により、コストを抑えながら質の高いアウトプットを実現できます。また、現地スタッフの協力を得ることで、言葉だけでなく、文化や感覚に即した表現の微調整も可能になります。
AIの翻訳が“基礎工事”を担い、人間の知見が“仕上げ”を担う。そうした分業の意識こそが、これからのグローバルコミュニケーションの質を決定づけるのです。
トランスクリエーションの現場で起きていること
AIの進化で“誤訳”は減ったが“響かない”翻訳は増えた
AI翻訳の進化により、以前のような致命的な誤訳は大幅に減りました。文法の整合性や単語の選定も、非常に高い水準で自動処理されるようになっています。しかし、そうした“正しさ”が増す一方で、“心に響く表現”が減っているという声も現場からは聞こえてきます。
特に、マーケティングやプロモーションの分野では、文章の温度感やユーモア、文化的な含みといった要素が購買行動に大きく影響します。たとえば、「あなたにぴったりの一品です」という表現も、英語でそのまま「Perfect for you」としても機械的に見えてしまい、心に残りません。こうしたニュアンスの差こそが、ブランドの印象や商品イメージに直結するのです。
AIは「間違えない」翻訳には強くなりましたが、「刺さる」翻訳、つまり読み手の感情を動かすような言葉選びには、依然として人間の役割が重要であることが現場では実感されています。
業界・商材によって求められる翻訳はまったく違う
トランスクリエーションの難しさは、業界や商材ごとに“伝え方”が大きく異なる点にもあります。たとえば、医療機器のマニュアル翻訳では正確性と法的適合が最重視される一方で、化粧品やアパレルのマーケティングでは、感性やライフスタイルに訴える表現が求められます。
また、食品業界では「味」や「安心感」「原産地」といった表現が、国によって好まれる言い方が大きく異なります。日本では「無添加」「素材の味を活かした」という表現が好まれる一方で、欧米では「高たんぱく」「植物由来」などの機能性や倫理性が重視される傾向があります。
このように、商品ごと、業界ごとに最適なトーンやワーディングは異なり、AIでは判断が難しい領域も多く残されています。現場では、AIで生成された文章を、業界特有の言い回しや文化的適合性を持たせるために、人の手で繊細に調整する作業が日常的に行われています。
“正しさ”より“伝わりやすさ”を優先する視点
翻訳作業において、しばしば「正確さ」が最も重要視されがちです。しかし、実際のビジネスの現場では「伝わるかどうか」が成果を左右する場面が少なくありません。ときには、あえて直訳を避けて意訳した方が、相手の心に届くこともあります。
たとえば、日本語の「おもてなし」を英語に直訳すると「hospitality」になりますが、それだけでは日本的な心配りや細やかさは伝わりにくいかもしれません。むしろ、その背景や価値観を補足した文章に変えることで、初めて「おもてなし」の本質が伝わるのです。
このように、トランスクリエーションにおいては「原文に忠実であること」以上に「目的に適った表現になっているか」が重要です。AI翻訳ではまだ困難な、この“目的ベースの翻訳”という視点が、現場ではますます重視されるようになっています。
海外ビジネスにおけるAI翻訳活用の実践ポイント
AI翻訳の活用シーンと“向いている作業”を見極める
AI翻訳は、正しく使えば非常に効率的なツールとなりますが、すべての翻訳作業に適しているわけではありません。たとえば、社内資料やメールの下訳、ウェブサイトの一次翻訳、リサーチ資料の概要把握といった、構造が明確で言葉選びにそこまで繊細さを求めない作業では、AI翻訳のスピードとコストメリットを最大限に活かすことができます。
一方で、広告コピー、企業メッセージ、商品説明文のように感情に訴えかける表現が求められる場合や、現地の文化・価値観を汲み取った文章を求められる場面では、AIのみの翻訳では限界が生じます。翻訳の目的や使用する場面を見極め、「AIに任せるところ」「人が仕上げるところ」の線引きをすることが、ビジネスの成果に直結します。
“その翻訳は本当に刺さっているか?”の確認ステップ
AI翻訳を導入した後に見落としがちなのが、成果物が「現地の読者に本当に響いているか」を検証するステップです。表面的には整っている文章であっても、文化的に誤解を招く表現や、違和感を与える言い回しになっていることもあります。
そのため、現地に精通したネイティブスタッフやパートナーによるレビュー工程は欠かせません。可能であれば、実際の消費者や営業先など、想定読者に近い立場の人に目を通してもらい、フィードバックを得ることが理想的です。翻訳の最終目的は“通じること”ではなく、“伝わること”であるという原点に立ち返る必要があります。
AI×人間の最適バランスで成果を最大化する
海外ビジネスにおける翻訳・通訳の現場では、AIと人間の役割をどう分担するかが、今後の大きなテーマとなります。AIには、圧倒的なスピードとコストパフォーマンス、そして多言語への瞬時対応という強みがあります。一方で、人間は文化的文脈や感情、ブランドイメージの調整といった「空気を読む」能力に優れています。
最も理想的なのは、AIを翻訳の起点として活用し、そのうえで人間が仕上げをする“ハイブリッド運用”です。この体制を構築することで、コストを抑えつつも品質を担保することが可能になります。特にマーケティングやクリエイティブ領域においては、この“AI+人間の協業体制”こそが、グローバル市場で成果を生む鍵となっていくでしょう。
翻訳・通訳の未来と、日本企業が今取るべきアクション
トランスクリエーションもAIに置き換えられる時代は来るのか?
近年のAIの進化はめざましく、翻訳だけでなくトランスクリエーションの領域にまで応用が広がりつつあります。たとえば、文脈や感情を加味し、より自然でターゲットに響く表現をAIが出力できるようになってきました。実際、広告コピーや製品説明文の試作段階では、AIが生み出す候補が参考になるケースも少なくありません。
しかしながら、ターゲット市場ごとの宗教・文化的背景、感情のニュアンス、消費者インサイトに応じた表現の調整といった「人間ならではの嗅覚」が必要とされるシーンでは、依然として人の力が求められます。つまり、トランスクリエーションが完全にAIに置き換わる未来はしばらく訪れないと考えるべきでしょう。むしろAIは、作業の「起点」として活用し、人間がその文脈を調整・洗練させるという使い方が、今後も主流になっていくと見られます。
AI翻訳を活かす組織的な運用体制づくり
AI翻訳を本格的にビジネスで活用するには、単発的に使うだけでは成果につながりません。重要なのは、社内に明確なルールや運用フローを整備することです。たとえば「どの言語ペアならAI翻訳を使用可」「対外資料には必ずネイティブチェックを入れる」など、リスク管理と品質担保の仕組みをあらかじめ構築しておく必要があります。
また、AIツールの選定やカスタマイズ、使いこなしのための教育も欠かせません。翻訳ツールは進化し続けるため、継続的なアップデートと運用の最適化が求められます。これらを一企業でまかなうのが難しい場合には、専門家や翻訳会社と連携した運用も現実的な選択肢となります。AI活用を“戦略の一部”として定着させる視点が、いま問われています。
“現地の目線”をもつパートナーとともに進む
AI翻訳の可能性を最大限に活かしながらも、最終的に成果を出すために欠かせないのが“現地の目線”です。どれほど高精度の翻訳であっても、現地消費者の感覚、文化的背景、言葉のトーンに寄り添っていなければ、伝えたいメッセージは届きません。
この点で、日本企業が取り入れるべきは「現地パートナーとの協業」です。現地のマーケターやコピーライター、翻訳チェックを担うネイティブスタッフなど、ターゲット市場に根差した人材のサポートを得ることで、AI翻訳の“精度”に“共感”や“深み”が加わります。AIと人間の協働、そして“現地の人間の視点”を組み合わせることで、グローバルに通用するコミュニケーションの質が一段と高まるはずです。
まとめ|AI時代にこそ問われる「翻訳の本質」と“現地目線”の価値
AI翻訳の進化は、かつては専門家の手を借りなければ困難だった多言語対応を、驚くほど身近なものに変えました。短時間で高精度な翻訳が可能になり、ビジネスのスピードとコストパフォーマンスは格段に向上しています。加えて、近年では文脈や感情まである程度くみ取った「トランスクリエーション的翻訳」も登場し、AIの可能性は広がり続けています。
しかし、だからこそ見失ってはならないのが「翻訳とは伝えることであり、伝わることである」という原点です。どれだけ技術が進んでも、相手の文化、価値観、期待に合致した言葉でなければ、伝わったことにはなりません。そこに必要なのは、現地の空気を読み、言葉の裏にある感情や背景までくみ取る“人間の感覚”です。
日本企業がグローバルに展開するうえで重要なのは、AI翻訳を活用して業務効率を高める一方で、最終的な表現の質を左右する「現地目線」と「共感の力」をしっかり担保すること。AIと人間、そして現地パートナーの協働こそが、真に伝わるグローバルコミュニケーションを築くカギとなるのです。今後の海外ビジネスでは、このバランス感覚が大きな競争力となるでしょう。
なお、「Digima~出島~」には、海外マーケティングの専門家が多数登録されています。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
本記事が、海外展開を検討される日本企業の皆様にとって、実務の一助となれば幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談