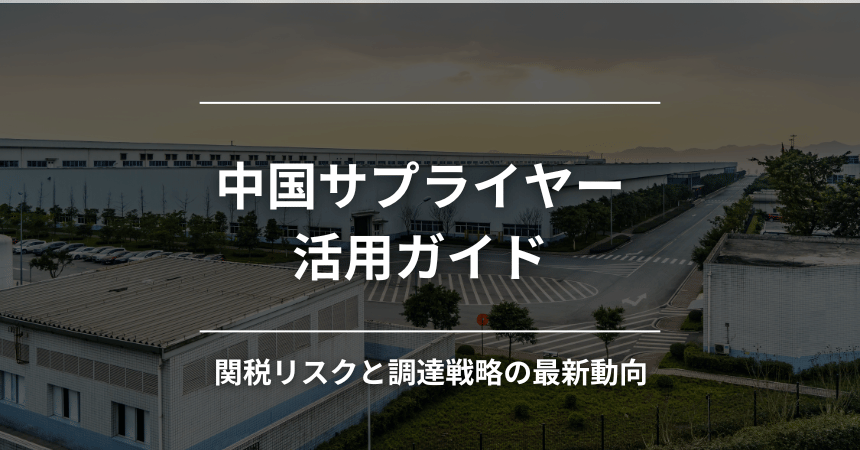加速する「中国撤退」-日本企業の中国撤退方法及び注意点を解説

2023年の世界の流れとして、「中国撤退」「中国離れ」と呼ばれる動きが、いわゆる「米中経済のデカップリング(分離)」を背景に、西側先進国にて加速しています。
米中デカップリングの引き金となった米中貿易戦争、さらに新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、アップルやホンハイ(鴻海)、任天堂といった名だたる企業が中国からタイ、インドネシア、ベトナムへと生産移管を進めています。
本稿では、世界で加速している「中国撤退」の背景および、試練にある「日本企業の中国撤退方法とその注意点」について解説します。
加えて、2022年10月に米バイデン政権が対中政策として発表した「半導体製造装置の輸出禁止強化」について、その対中輸出規制を受けて、日本企業を含む各国企業が中国事業に対して苦渋の選択を強いられつつある現状、さらには、喫緊の状況下にあって中国政府が正式に企業休眠(休業)化法令を交付した背景についても、詳しく解説します。
それらを踏まえて「中国から事業を撤退する際の注意点」をより専門的な論点でわかりやすく解説します。
▼ 加速する「中国撤退」-日本企業の中国撤退方法及び注意点を解説
1. 世界で加速する「中国撤退」と「半導体製造装置の輸出禁止強化」の関連性
ウクライナ戦争以降、中国で半導体が無くなるため、外資系製造企業は撤退を検討せざるを得ない?
トランプ政権が中国からアメリカへ輸出される鉄鋼製品に関税をかけたことから端を発した「米中貿易戦争」により、中国とアメリカの経済的対立は深刻化し、いわゆる「米中経済のデカップリング(分離)」(※)が懸念されるようになりました。
さらに国際社会において、アメリカを筆頭に世界各国による中国に対しての「中国デカップリング」の逆風が吹き荒れています。アメリカが中国製スマホアプリであるWeChatやTikTokを禁止したことが各メディアで大きく報道されたのも記憶に新しいところでしょう。
これらの重要な背景として、2022年10月8日(米国時間10月7日)にバイデン政権が発表した「半導体輸出禁止通達」があります。これには世界の半導体市場において、アメリカの半導体製造装置を使用して生産された特定の半導体チップを中国が入手できないようにする措置が含まれています。
これは日本企業を含む世界各国の企業取引にもっとも大きな影響を与える規制強化であると言っても過言ではありません。なかば強制的に、アメリカの半導体技術を活用する中国の半導体関連企業との取引を中止せざるを得ない可能性が高まるからです。
※デカップリング:
デカップリングとは英語で「分離」を意味し、転じて「二国間の経済や市場が連動していない状態」を指す。米中貿易戦争以降、米中間の経済関係が希薄化してしまった意味で使われるケースが多かった。
さらに現状では、欧州諸国は「デリスキング(※リスク低減の意味。サプライチェーンの偏向を是正する動き以外に、様々な意味合いで使われている)への方向性を打ち出している
2. 中国で最新の半導体を製造できなくなるため、外資企業は撤退を考えざるを得ない?
「中国デカップリング」の風が吹く中でも「在庫半導体が使えるまで」は大丈夫か?
前項で述べた、アメリカの中国に対する規制強化には、自国の覇権固持と台湾有事への米国会の意向が滲み出ていると言えます。
そんなアメリカの中国に対する一連の輸出規制強化において、日本企業を含む外資系企業が、もっとも留意すべきなのが「半導体製造関連エンドユース規制及びスーパーコンピュータ関連エンドユース規制の新設(米国時間10月7日、10月21日施行)」です。
上記の規制強化における重要な4つのポイントは以下の通り。
- 一定の用途向けはEAR99(リスト規制非該当品目)も対象
- 日本、米国等のホワイト国の企業の中国子会社も規制対象
- 日本国内企業向けや中国国外の国向けであっても、許可対象となる
- 規制対象エンドユースには純粋に民生エンドユースの場合も対象に含まれる
※出典
「米国による対中輸出規制の著しい強化について(改訂2版)」CISTEC 事務局
これらの政策が機能すれば、中国の半導体産業は石器時代に戻らざるを得ないことになります。半導体業界で重要とされるのは、技術、人材、運営、市場の4つですが、中国の強みは基本的には市場でした。半導体製造装置がないと、半導体製品は作れません。
半導体チップが無くなってしまえば、市場を強みとする中国の人工知能、ビッグデータ、自動運転、スーパーコンピュータなどの各種先端企業は運営ができなくなり、10年前に戻ることになります。
先述の中国に対する輸出規制強化においては、14nm(ナノメートル)以下の半導体製造装置、技術の中国への輸入禁止、米国技術を用いた半導体の一部輸入禁止、製造装置の輸入禁止の拡大も発表されているため、中国の半導体産業は今後ますます衰退の方向に向かうことが予想されます。
日本企業もアメリカの対中輸出規制には従わなければならない
さらに、仮にこの米国規制に従わなければ、たとえ日本企業であっても金融制裁を受けることとなり取引停止となります。
とりわけ、米国の同盟国である日系企業は、世界の半導体製造業界でそれなりの地位を占めながら復活しつつあるものの、一連の米中対立の中での「対中半導体輸出禁止規制」に対しての追随を迫られています。当然のことながらそれに対応せざるを得ないのが現状なのです。(中国市場での半導体装置売上高は、2022年の220億ドル〈約3.3兆円〉)
事実、日本政府は2023年3月31日付けにて、先端の半導体製造装置23品目について、回路幅が14nm以下を対象とした輸出禁止強化の旨を発表しています。
3. 喫緊の状況下にあって中国政府が正式に「企業休眠(休業)化法令」を交付
本来、中国に「休眠(休業)手続き」は存在していなかった
続いては、前項にて述べた中国に対する一連の輸出規制強化と同様に、2022年3月、中国での企業休眠(休業)における大きな変化があったので、その旨を解説します。
これまで中国には企業休眠の規定が明確化されていませんでした。しかし、2022年3月1日に施行された「新市場主体登記管理条例及び実施細則」にて、休眠制度が明確化され、企業は自主的な選択として3年を上限に休眠会社としての登記が認められるようになりました。
従来は6ヵ月間超の期間、連続して企業活動を停止した場合、市場監督管理局は、会社の営業許可証を取り消すことができると規定されていました。よって6ヵ月超の休業は、法的には、会社の解散に直結していたのです。
しかし先述の「新市場主体登記管理条例及び実施細則」によって、3年を上限に休眠会社としての登記が認められるようになったのです。
「休眠申請が認められる要件」と「休眠申請の流れ」について
休眠会社の申請が認められる要件としては、「自然災害、事故災害、新型コロナ感染症等、社会安全事件に起因して生産経営が困難になった企業」に限定されますが、それらに加え「その他」の項目を選択することができます。(条例30条1項、実施細則40条)
「その他」については「各省、自治区、直轄市人民政府が定める休業届出の状況」を記載することとされていますので、地方政府による方針が明確になっていない地域では管轄当局の判断に一任されます。
続いて「休眠申請の流れ」は以下のようになります。
■休眠申請の流れ
- 所在地の市場監督管理局で事前確認
- 従業員の解雇もしくは雇用休止に関する協議、オフィス賃貸契約の解約、法律文書送付住所と休眠期間中の連絡者の確保 《労務問題の解決が鍵》
- 休眠申請書類の作成
- 所在地の市場監督管理局へ休眠申請
- 毎月・毎四半期の税務申告及び毎年の情報公示
中国法人の場合、6ヵ月間超から1年以上放置されていると登記が抹消されるのですが、長期間放置されていた現地法人では、税務登記が正常に抹消されていない「吊销」と呼ばれる行政処罰を受けている状態が多いです。
これを解除するため実質休眠状態にあった全期間の申告をやり直し、未納付となっている税金・延滞税等を納付しなければなりません。つまり、未完了の税務事項や税務登記抹消が完了して会社の登記抹消が可能となります。
4. 中国から事業を撤退する際の注意点とは?
世界中の企業が中国からの撤退を意向している流れが止まらない中で、日本企業が中国撤退する際に注意しておきたい点は何でしょうか。
具体的な中国撤退の手続きや順序はどうなっているのか?
では中国から事業を撤退する方法論や注意点はどうでしょうか?
中国事業からの撤退数は、経産省の統計などから見ても、他のアセアン諸国などと比較して突出しており、撤退時にもさまざまな局面で政府が介入してくることが要因ともなっています。
さらに、有限責任会社であっても無限責任として責任が親会社へも及び、同一法人格とみなされる不合理な仕組みが困難さの理由です。実務上の撤退方法の選択肢には、以下の方法があげられます。
1 持分譲渡
2 普通清算
3 破産清算
4 休眠化 (規定法令はなし)
■撤退スキームの選択
中国撤退を進める際、重要なのは ①企業としての納品責任つまり作り溜めであり、②従業員のリストラ、③債権債務および資産(土地・建物は除く)の処分となります。
基本的に法人(持分)として売却できるのかどうか、売却できれば持分譲渡のスキームを、売却できなければ土地・建物・設備の売却を行い、その後は解散清算を行うというのが、撤退スキームの骨子となります。
つまり、Step1として、事業を停止した後に、自社で人員・債権・債務および土地と建物以外の資産を処分する。その後、Step2として2つのパターンがあります。
A:資産譲渡+清算を進めるか B:買手企業を見つけ持分譲渡を進めるか の選択という形になります。

■持分譲渡の注意点
持分譲渡は、基本的には会社自体は存続させ、解散・清算より政府認可を得られやすいですが、従業員のリストラに関しては現状法人で過去勤務期間の「経済補償金(退職金)」を支払うといった対応を取ります。売却後の債務をなるべく少なくし、リスクを回避するのがその目的と言えます。
持分譲渡手続きは会社法上、詳細に明記はされていませんが、通常は以下のようになります。
① 譲渡先探しと検討
② 当事者間での交渉、譲渡価格の確定、条件の合意(意向書)
③ 持分譲渡契約締結
④ 株主会または董事会決議
⑤ 審査認可機関への認可申請
⑥ 外商投資企業認可証書(企業批准証書)の変更申請
⑦ 工商行政管理局への変更登記申請
⑧ 譲渡代金の送金
⑨ 各種登記変更
なお、近年の経済状況からして買手が日系企業や台湾・香港企業への持分譲渡は稀有となっているため、中国(内資)企業に売却した際には「外資が内資企業になってしまう」ための手続き、つまり清算手続きと同様の手続きを追加で踏まされることになります。また中国企業への売却のための専門家FA業務も可能になってきております。
■普通清算の注意点
どうしても売却できないと判断した場合、解散清算手続きに突入します。持分譲渡は譲渡対価として相当の金額がキャッシュとして買手企業が株主である日本本社に入金します。それに比べて資産の換価処分で一部の入金しかない解散清算は親会社側が負担する清算コストは出る一方であり、清算という前提が同じ資産の換価にも雲泥の差を生じさせます。
また手続き所要期間自体も、6カ月ぐらいで終わる持分譲渡に比べ、普通清算は最低でも1年超から2年近く掛かり、土地使用権の処分(ワーストケースは政府買取りもあり)も含め、とにかく全てを売却しないと終わりません。
リストラ(解散解雇)の手続き以外に清算手続きを大きく総括的に捉えれば、以下の6つのステップを踏むことになります。
(1) 現地法人の解散認可を申請し、原審査機関へ届け出て許可を受ける。
(2) 清算組を設立して届け出る。
(3) 債権者への通知と新聞公告により現地法人の債権・債務を確定する。
(4) 債権・債務の処理に具体的な処理と清算財産の評価、処理を行う。(かなりの時間と手間が掛かります)
(5) 清算報告書の認可を受け、原審査機関全てから抹消通知をもらう。
(6) 残余財産を出資者に分配・送金する。
■破産清算の注意点
近年持分譲渡や普通清算に比べると、依然としてその数は非常に限定的ですが、破産原因は期限到来済の債務支払いができず、かつ資産が全債務を清算するのに不足すること、または明らかに債務を清算する能力を欠くこととされております。これら破産原因の意義は、日本の破産法上で債務超過や支払不能が破産原因とされているのとほぼ同じです。
その申立てが受理されても、最終の破産清算配当に行き着くまで相当の時間と手間が掛かかる場合が多いと言えます。
新型コロナウイルス感染症を原因として、工場が稼働できず販売経路がストップしたような場合では、その間の経費等で現地法人の債務が大きく膨らんでしまい、生産や販売のストップが一次的なものではなく、再開して売上を創出する目途が立たないといった事情があれば、破産を説明する材料となるものと思います。
■総括的な注意点
中国は米国と同じく言わば連邦制の国であり、地域・所轄によって独自の規定があるため、着手する前に細かいスケジュールや手続きの順序、提出すべき資料明細などは、必ず企業の存在する現地の所轄当局政府に十分に事前確認しておく必要があります。さらに専門家との三位一体のチームアップも必須といえます。
5. 中国からの事業の撤退・現地拠点の閉鎖は難しい?
中国進出よりも中国撤退がなぜ難しいのか?それは現地政府が有形無形に関与するからか?
中国では、進出よりも撤退がはるかに難しいと言われています。というのは、中国では事業を清算することが政府の税収等逸失利益に直結するが故に、清算を進める際には現地政府からの事前承認が必要であるからです。
清算において最も難しいのが、清算に着手する前の事業縮小、つまりリストラとなります。通常大きなリストラの場合、現地政府への承認が必要であり、労働局が主導で工会(労働組合)や公安(警察)を含め各政府部門の共同会議が行われることも多く、総経理同席で事情説明をして政府の意見と協力を求めることになります。
人の問題を乗り越えずして完全な撤退は望めず、最優先は人の処理の対応であると言っても決して過言ではありません。但し会社都合であるため、それにはお金が必要となります。
中国撤退上一番困難な作業であるリストラの方法に関して、以下の4つの方法があげられます。
① 整理解雇(いわゆる経済性リストラ。一定人数以上の解除)≪労働契約法第41条≫;
要件としては、「削減する人員が20人以上であるとき、または20人に満たないが企業従業員総数の10%以上」であり、生産経営に重大な困難が生じた場合等に限られます。法的解雇と言えます。
手続きとしては、(ⅰ)30日前までに工会または全従業員に対して状況説明・意見聴取し、(ⅱ)行政部門への報告を行う必要があります。しかしながら、労災、疾病、妊娠・出産期の女性従業員等の一部の従業員を解除することはできません。
② 予告解雇(客観的状況の重大変化による個別解除で1人からでも適用可)≪労働契約法第40条第3項≫;
要件としては、①労働契約締結に直結する客観的状況に重大変化が生じたことにより労働契約を履行することができなくなったこと、②労使協議を経ても労働契約の内容変更に合意できない場合となります。
なおこの場合は30日前の通知、もしくは1ヶ月分の賃金の支払いが必要とされています。しかし条文上の要件が曖昧であるため、労働契約や就業規則で具体的な定めをしておくことが望ましい。
③ 解散解雇(会社が早期解散を決定した場合)≪労働契約法第44条第5項≫;
会社が早期解散を決定したことが必要になります。この決定は株主会(または董事会)の決議を指します。なお欧米企業のように一方的に即時に労働契約を終了させることは日系企業では少ないです。
④ 合意解除(個別の合意解除)≪労働契約法第36条≫;
後々のリスクを避けるという意味では、最も使用される方法といえます。
なおリストラ時の「経済補償金」とは、労働契約の終了時点において会社側が従業員に対して支払う補償費用(退職金見合い)をいい、労働契約法では以下のように定めています。《労働契約法第47条第2項》
(1)従業員の当該会社における勤務年数1年ごとにつき、1カ月相当の賃金を支払う。6か月以上、1年未満の場合には1カ月で計算し、6カ月未満の場合には0.5カ月分の給与の経済補償を行う。
(2)従業員の月賃金が、会社の所在する直轄市、区を設置するレベルの人民政府が公表する当該地区における前年度の従業員月平均賃金の3倍を超える場合にはこれを上限とし、当該労働者に支払う勤務年数の上限は最長で12年とする。3倍以下の場合には、前年度の従業員月平均賃金を基数とし、勤務年数の上限はない。
さらに会社側は、リストラ実施に先立ち事前に「工会(労働組合)または従業員代表」にリストラ案を提案し、補償条件に関して協議交渉の後、従業員(労働者)からの意見を反映したリストラ案(修正版)を作成し、労働局に届けることになります。実際問題、リストラには3~6か月は内部検討を行う日系企業が多く、会社によっては1年を掛けて事前根回しまで行うケースもあります。
6. 直接投資先からの撤退における課題とは?
撤退を検討しているまたは経験した日系企業の問題点
今回は、世界で加速している「中国撤退」の背景について、実際に検討・実行している日系企業に対して、経産省による「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」について解説し、さらには「撤退方法やリストラの具体的方法」に関しても解説しました。
中小企業庁等の調査によれば、撤退を検討している日系企業を見ると実に6割以上が中国であり、過去に撤退を経験した日系企業はその4割以上が中国となっております。
具体的な撤退の理由は、①環境の変化等による販売不振、②海外展開を主導する人材の力不足、③現地法令・商慣習の問題、④人件費の高騰による採算悪化、⑤従業員確保・育成・管理の困難性、の順序となっております。
さらに、より具体的障害・課題の内容としては、①投資資金の回収、②現地でのリストラの円満進捗、③現地法令への遵守、④取引先への納品責任・合弁先との調整、⑤現地政府への説明・調整、の順序となっております。
最後に重要な点は、4割以上の日系企業が直接投資先において撤退を経験していても、他の拠点において投資を継続しており、ひるむことなく直接投資を再開するなどして現在も直接投資に取り組んでいる点であります。
(参照文献) ・「米国による対中輸出規制の著しい強化について(改訂2版)」CISTEC 事務局
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
オススメの海外進出サポート企業
-
株式会社ダズ・インターナショナル
東南アジア・東アジア・欧米進出の伴走サポートが強み
私たちは東南アジア・東アジア・欧米進出の伴走サポートを強みとしております。
対応する主要各国にメンバーを配置し、海外進出後も支援できる体制を整えています。
事業開始から20年弱、850社を超える成功も失敗も含めた実績・ノウハウから積極的に支援します。
昨今の国際情勢を見てみると良くも悪くも変動性が高く、かつウェブ・SNS等の膨大な情報が仇となり、
リアルタイムかつ最適な情報を獲得することが難しい時代です。
私たちはこの状況に対応すべく、現地のリアルを理解し、支援できる体制づくりにこの数年力を入れています。
特に強化しているエリアは現在日本企業の進出が増加傾向にあるASEAN各国です。
2025年、カンボジア・プノンペンにも新しい拠点を追加しております。
どの国が最適か?から始まる、海外進出のゼロ→イチを伴走する支援をさせていただきます。
------------------------------------
■サポート対象国(グループ別)
海外進出支援や活用・生活を支援する対象とする国は以下の通りです。
※サポート内容により、対応の可否や得意・不得意な分野はあります。
↳欧米(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)
↳アジア①(タイ・カンボジア・ベトナム・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ラオス)
↳アジア②(日本・香港・シンガポール・台湾・韓国)
↳アジア③(ドバイ・サウジアラビア・インドバングラデシュ・モンゴル・ミャンマー)
------------------------------------
■海外進出(前)支援
日本企業の海外ビジネスのゼロイチを共に考え、目標達成のために共に動くチーム
対象法人:これから海外進出を開始する企業 / 海外事業担当者不在、 もしくは海外事業担当者が不足している企業
契約形態:①伴走支援(月額 10万円〜)②スポット支援(施策により変動)
『ポイント』
✔︎ゼロ地点(「海外で何かやりたい」のアイデア段階)から伴走サポート
✔︎BtoB・BtoC・店舗開業など幅広い進出支援に対応
✔︎現地で対応する駐在スタッフを各国に配置
✔︎現地で専門分野に特化したパートナー企業・個人と提携
『対応施策』
⚫︎海外進出の準備・設計・手続き/申請サポート
↳各種市場調査・事業計画設計(稟議書策定) /会社設立/FDA等申請等
⚫︎BtoC販売促進サポート
↳マーケティング企画設計/分析/SNS運用/ECモール出品〜運用
↳プロモーション(広告運用/インフルエンサー施策含む)/各種制作
⚫︎BtoB販路開拓サポート
↳現地パートナー起業候補の探索〜交渉〜契約/展示会サポート
↳セールスマーケティングキット制作
⚫︎飲食店開業サポート(ほか店舗開業サポート含む)
↳エリアマーケティング〜テナント居抜き探索
↳現地人材候補の探索〜交渉〜契約/現地店舗運営代行
------------------------------------
■海外進出(後)支援
現地日系企業の現地での集客課題を共に考え、目標達成のために共に動くチーム
対象法人:すでに海外へ進出済みの企業 / マーケティング関連業務の担当者不在、もしくは不足している企業
契約形態:①伴走支援(月額 500ドル〜)②スポット支援(施策により変動)
『ポイント』
✔︎丸投げ(担当者もいない・知識もない)ウェルカムの代行サポート
✔︎BtoB・BtoC・店舗運営など幅広い集客支援に対応
✔︎現地で対応する駐在スタッフを各国に配置
✔︎現地で専門分野に特化したパートナー企業・個人と提携
『対応施策』
⚫︎マーケティング関連施策サポート
↳各種マーケティングリサーチ
↳デジタルマーケティング全般の企画設計/分析/PDCA改善
⚫︎セールス支援サポート
↳インサイドセールス全般(営業代行/メルマガ配信)
⚫︎各種プロモーションサポート
↳MEO/SEO/リスティング広告/インフルエンサーマーケティング
↳EC運用/SNS運用
⚫︎各種制作サポート
↳サイト/LP/ECサイト/オウンドメディア/コンテンツ(記事・動画)
------------------------------------ -
株式会社東京コンサルティングファーム
【26ヵ国39拠点】各国日本人駐在員が現地にてサポートいたします。
弊社は、会計事務所を母体とした26ヵ国39拠点に展開するグローバルコンサルティングファームです。
2007年に日本の会計事務所として初めてインドに進出し、翌年ASEAN一帯、中南米等にも進出しました。歴が長く、実績・ノウハウも豊富にございます。
海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など国際ビジネスをトータルにサポートしています。
当社のサービスは、“ワンストップ”での サービスを提供できる環境を各国で整えており、特に会計・税務・法務・労務・人事の専門家を各国で有し、お客様のお困りごとに寄り添ったサービスを提供いたします。
<主要サービス>
・海外進出支援
進出相談から登記等の各種代行、進出後の継続サポートも行っています。月額8万円~の進出支援(GEO)もご用意しています。また、撤退時のサポートも行っています。
・クロスボーダーM&A(海外M&A)
海外企業の買収・売却による進出・撤退を支援しています。
・国際税務、監査、労務等
各国の税務・会計、監査や労務まで進出時に必要な業務を幅広く行っています。
・現地企業マッチングサポート
海外販路拡大、提携先のリストアップ、代理店のリストアップ、合弁パートナー探し等を行うことができます。TCGは現地に拠点・駐在員がいるため現地企業とのコネクションがあり、スピーディーに提携先のリストアップなどを行うことができます。 -
グローハイ株式会社
日本企業の世界での売上達成の実現に特化したサービスを提供します
日本に留まらず更なる成長を目標にグローバルに挑戦し続ける日本企業にとって信頼のおける長期的なパートナーであり続けることが私たちの企業使命だと考えております。日本企業の幹部や海外展開のプロジェクトリーダーと共にアメリカに本社を構える私たちの多様な専門性、経験、文化的背景を持つ人材、過去にアメリカや中国やヨーロッパで培ってきたビジネスプロセス、現地ネットワークを最大限に活用し各クライアント特有のビジネス目標を達成させます。
グローハイは戦略コンサルティング、プロジェクトマネジメント、オペレーションサポートと幅広い分野で海外で成功する為の下記のようなサポートを実施しております。
・アメリカ、ヨーロッパでの売上達成
・アメリカ、ヨーロッパでの販路拡大
・アメリカ、ヨーロッパでのECサイト構築とデジタルマーケティングサポート
・効率的かつ低リスクでのアメリカ進出、ヨーロッパ進出
・戦略的パートナーマネジメント
・アメリカでのM&A
・アメリカでの会計、人事、法務の業務委託
グローハイはこれまでに中小企業から大企業まで様々な規模、業界の数多くの日本企業のアメリカ進出、中国進出、ヨーロッパ進出を成功に導いてきました。 -
プルーヴ株式会社
貴社の海外事業進出・展開をサポートさせていただきます
プルーヴは世界市場進出における事業戦略の策定と実行のサポートを行っている企業です。
「グローバルを身近に」をミッションとし、「現地事情」に精通したコンサルタントと「現地パートナー」との密な連携による「現地のリアルな情報」を基にクライアント企業様の世界市場への挑戦を成功へと導きます。 -
Japan Management Systems (Thailand) Co., Ltd. (日本経営システム株式会社タイ現地法人)
海外事業に対して全方位でご支援致します
1970年創業の日本経営システム株式会社のタイ現地法人です。
タイ・ASEANを中心に、幅広い領域での経営コンサルティングを提供しております。
お客様と共に考え、共に解決策を見出す、協同作業が一つの特徴です。
また、特定分野のみに特化しているわけではなく、企業のあらゆる課題に対する解決のご支援をしております。
ビジネスマッチング、市場調査、戦略策定、ガバナンス強化、人事制度策定、M&AやPMI、撤退支援など、お客様のお悩み、課題に全方位で対応させていただきます。