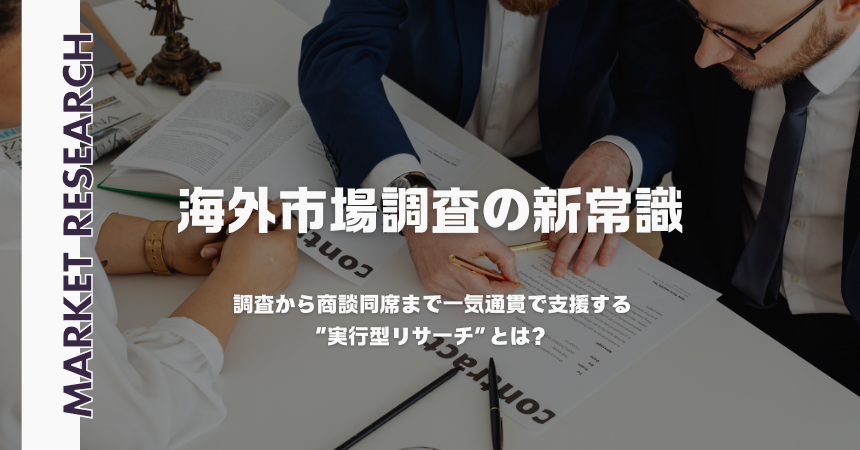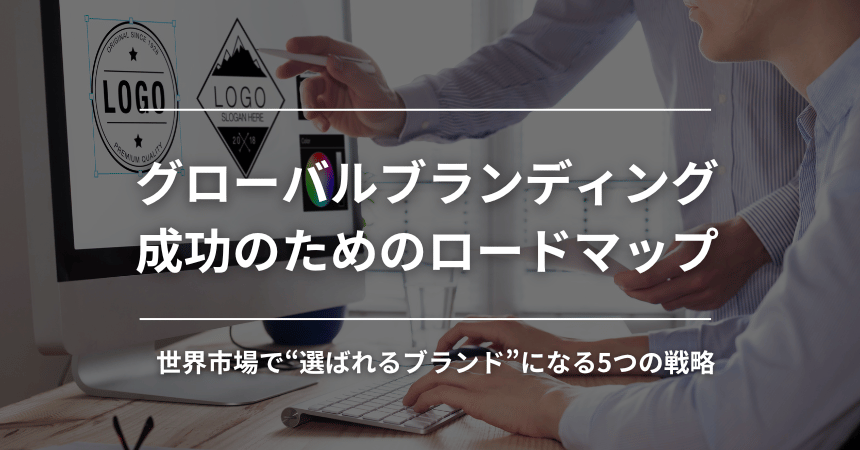輸出通関手続きの流れとは?通関書類・輸出申告書の書き方も解説

輸出通関手続きの流れ、重要な書類であるインボイスやパッキングリストの作成方法、さらに輸出業務をサポートするフォワーダーや通関士の役割についてわかりやすく解説します
海外事業においても輸出ビジネスは比較的イメージがしやすく、実際に人気があります。しかし輸出をする際には、税関による輸出通関が必要なことから、複雑で難しい印象を持つ方も多いかもしれません。
海外市場への進出は、多くの企業にとって魅力的ですが、輸出通関のプロセスは複雑に感じられることがあります。しかし、適切な知識と手順を踏めば、これらのプロセスは決して難しくはありません。
Photo by Greg Goedbel on Flickr
輸出通関手続きの流れとは?通関書類・輸出申告書の書き方も解説
- 1. 輸出入における通関手続きとは?
- 2. 輸出通関の2つの方法とは?
- 3. 輸出通関に必要な輸出書類
- 4. 輸出通関手続きの流れ
- 5. 輸出者が知っておきべき「保税地域」とは?
- 6. 輸出者が知っておくべき「特定輸出者(AEO輸出者)制度」とは?
- 7. 輸出者の輸出業務をサポートしてくれる「通関士」と「フォワーダー」?
- 8. 輸出通関に関するタスクを専門家にアウトソーシングするという選択
アナタの海外ビジネスを成功させるために
1. 輸出入における通関手続きとは?
「海外に自社製品を輸出したい」「海外から原材料を輸入して自社製品を製造したい」など「モノ」を輸出入する際には、通関手続きが必ず必要になります。
まず最初に「通関手続きとは何か?」という基本的なことについて改めて解説します。
輸出入の通関に必要不可欠な「通関手続き」
通関手続きとは、「貨物の輸出入をしようとする者が法定の手続きを経て税関長の許可を受けること。また、その貨物が税関を通過すること(デジタル大辞泉)」と定義づけられています。
例外はありますが、一般的に税関を通さずに海外からモノを受け取ったり、海外へ送ったりする場合は、密輸になってしまいます。改めて〝輸出通関手続〟について、東京税関のHPより「輸出通関手続の概要」の項目を以下に抜粋しますので、ご確認ください。
貨物を輸出しようとするときは、税関へ輸出申告を行い、貨物につき必要な検査を経てその許可を受けなければなりません。
輸出の申告は、輸出しようとする貨物を保税地域に搬入する前であっても行うことはできますが、輸出の許可は、原則として輸出しようとする貨物を保税地域に搬入した後に行われます。
保税地域とは、輸出しようとする貨物または外国から到着した貨物を置く場所として、財務大臣により指定、または税関長により許可された場所です。
輸出の申告は、貨物の輸出者が、輸出の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域の所在地を管轄する税関に対して行いますが、貨物の輸出者から委任を受けて、通関業者が代理申告することもできます。
関税法以外の法令で許可、承認等の輸出規制が行われている貨物を輸出する際には、税関への申告にあたり、当該許可・承認書等を提出する必要があります。
つまり、輸出入をする際には、絶対に税関を通過し許可を受ける必要があります。これは、輸出入されるモノが、危険なもの(銃や薬物等)ではなく、誰が・どこから輸出入を行ったのかを明確にさせるための検査であると言えます。
参考:
「輸出通関手続の概要」東京税関
2. 輸出通関の2つの方法とは?
このセクションからは、本テキストのメインテーマである「輸出通関の基礎知識」について解説していきます。輸出通関業務の中でも重要な、輸出通関を依頼する際の必要書類について簡潔に解説します。
まずは通関手続きには2つの方法があることから解説します。
通関手続きには「自社通関」と「業者に依頼する通関」の2つの方法がある
そもそも通関においては、自分で行う「自社通関」と「業者に依頼する通関」の2つの方法があります。
自社通関とは、自社の商品の通関を輸出者自ら行うことを指しますが、一般的には、税関への輸出入申告は、財務大臣の許可を受けた「通関」を業として営む通関業者に依頼するケースが多いです。
2つの通関手続き方法で共通して必要な書類は「インボイス」と「パッキングリスト」
そして、輸出通関で必要になる書類は、「自社通関」と「業者に依頼する通関」では多少異なります。まず、自分で通関申告をする場合は、「輸出通告書(自分で輸出申告をする際に必要な書類)」「インボイス(仕入書)」「パッキングリスト(包装明細書)」などが必要になります。
そして、業者へ通関申告を依頼する場合は、「インボイス(仕入書)」「パッキングリスト(包装明細書)」「船積依頼書(シッピングインストラクション)」「委任状」などが必要になります。
基本的には、後述するフォワーダーなどの通関業者へ通関業務を依頼する場合は、「インボイス(仕入書)」と「パッキングリスト(包装明細書)」は輸出者が用意し、「船積依頼書(シッピングインストラクション)」「委任状」については、通関業者が用意するのが一般的です。
いずれにせよ「自社通関」と「業者に依頼する通関」の2つの方法において共通する必要な書類は、「インボイス(仕入書)」と「パッキングリスト(包装明細書)」になります。
次項からは、「輸出通関を業者に依頼する際に必要な輸出書類」について解説していきます。
3. 輸出通関に必要な輸出書類
ここからは、輸出通関に必要な書類について解説します。
前項にて解説したように、自分で行う「自社通関」と「業者に依頼する通関」では、必要な書類は異なりますが、基本的に輸出通関で必要な書類は以下の5つになります。
① 輸出申告書
② インボイス(仕入書)
③ パッキングリスト(包装明細書)
④ 船積依頼書(シッピングインストラクション)
⑤ 委任状
以下より順番に解説します。
① 輸出申告書
自社での輸出手続きには、「輸出申告書(E/D)」が必要不可欠です。
輸出申告書とは、輸出される商品に関する重要な情報を税関に正式に申告するための公式文書です。輸出申告書には、船積み依頼書、インボイス、商品価格や数量などの基本情報が書かれたバッキングリストの情報を盛り込む必要があります。
具体的には、商品の詳細な説明や数量、価値などの情報が含まれており、輸出国と輸入国、送り主と受取人の情報も記載されている必要があります。
最近ではNACCSと呼ばれる電子システムの手続きが可能になっています。
② インボイス(仕入書)
「インボイス(仕入書)」とは、何をいくらで販売するかの取引を示す書類です。
具体的には、発送元・発送先情報といった国際配送に必要な情報に加えて、商品・数量・金額・取引条件・出荷地・着地といった項目が記載されている必要があります。
つまりインボイス(仕入書)に記載されるべき情報は、誰からどこに向けてどんな荷物が発送されていくのかが分かる必要があります。
また、このインボイス(仕入書)を元にして、輸入国側で輸出国側へ支払いを行い、関税などの税金を納付することで、輸入者が荷物を受け取ることができます。
以上を踏まえて、税関に提出するインボイス(仕入書)は、以下の要件を満たす必要があります。
・貨物の品名、種類、数量、価格、代金支払方法、荷送人および荷受人の住所、居所、氏名、名称等が記載されていること
③ パッキングリスト(包装明細書)
「パッキングリスト(包装明細書)」とは、商品をどのように積み込んでいるのかを示す書類です。インボイス(仕入書)を補完するもので、輸出する貨物の個数、包装後の重量・容積などが記載されている必要があります。
また、インボイス(仕入書)とパッキングリスト(包装明細書)の双方を、ひとつの書類で兼用するケースもあります。
④ 船積依頼書(シッピングインストラクション)
「船積依頼書(シッピングインストラクション)」とは、フォワーダーなどの通関業者を経由して、船会社および航空会社(航空貨物代理店)がそれぞれ発行する「船荷証券(Bill of Lading: B/L ※ビーエル)」「航空運送状(Air Waybill: AWB ※エーダブリュービー)」を作成するための情報としての書類です。
輸出者の依頼を受けたフォワーダーなどの通関業者が作成するケースと、輸出者が作成するケースの2パターンがありますが、どちらが作成するかは、輸出者と通関業者の取り決めで決まることが多いです。
⑤ 委任状
「委任状」とは、通関業者と初めて取引を行うときに用意する書類です。通関業者により書式が異なります。
通関業者は、通関業務に際して帳簿類を設け、それらを一定期間保存することが義務付けられています。保管義務のある書類のひとつに「依頼者から依頼を受けたことを証する書類」があります(通関業法第22条第1項、通関業法施行令第8条第2項)。
ちなみに委任状に関しては、フォワーダーなどの通関業者が用意し、輸出者がそれにサインをするのが一般的です。
参照:
「通関業者に輸出通関を依頼する際の必要書類:日本」JETRO
4. 輸出通関手続きの流れ
ここからは輸出通関手続きの流れについて解説します。
貨物が出荷した後、実際に輸出が可能になるまでには、おもに以下のプロセスを辿ります。
① 出荷
② 他法令手続き
③ 輸出申告
④ 審査
⑤ 検査
⑥ 輸出許可
⑦ 船積み・搭載
(税関HPより)
以下より、輸出通関手続きの流れについてプロセス順に見てきましょう。
① 出荷
出荷プロセスでは、輸出される商品が梱包され、輸送のために出発地点から移動する準備が整えられます。この段階で、商品は適切に梱包され、輸送中の損傷や紛失を防ぐための措置が講じられる必要があります。
また、適切な物流業者の選定、輸送スケジュールの調整、および必要な書類(船積み依頼書、インボイスなど)の準備も含まれます。
② 他法令手続き
他法令手続きは、特定の商品に関連する追加の法規制や基準を満たすためのプロセスです。 例えば、危険物質、特定の技術製品、農産物など特定のカテゴリーの商品は、追加の許可や認証を必要とする場合があります。また、輸出対象国の法律や国際的な取り決め(例えばワシントン条約〈CITES〉などの環境保護関連の国際条約)に従うことが求められることもあります。
③ 輸出申告
輸出申告では、輸出される商品の詳細な情報を輸出申告者として税関に提出します。
この申告書には、商品の種類、数量、価値、輸出先国、生産国、送り主と受取人の情報などが記載されます。この申告は、税関による輸出許可の基礎となり、関税計算や輸出統計の作成にも使用されます。
④ 審査
審査プロセスでは、税関当局が提出された輸出申告書や関連文書を詳細に検討します。
この段階では、商品が適用される輸出規制や法律に遵守しているかが確認され、必要に応じて追加情報や訂正が求められることもあります。
⑤ 検査
検査段階では、税関職員が実際に貨物を物理的に検査することがあります。この検査は、申告内容と実際の貨物が一致しているかを確認するために行われ、不正や誤りを防ぐための重要な手段です。
高リスクと見なされる貨物やランダムに選ばれた貨物が検査の対象となることが一般的です。
⑥ 輸出許可
輸出許可は、税関が申告内容と検査結果に基づいて貨物の輸出を正式に承認するプロセスです。この許可が下りた時点で、貨物は法的に輸出される資格を得ます。
⑦ 船積み・搭載
最終段階の船積み・搭載では、輸出許可を得た貨物が船舶や航空機、トラックなどの輸送手段に積み込まれ、実際に輸出先へと輸送されます。この段階では、物流会社が貨物の安全な輸送と、目的地へのタイムリーな到着を確保するための調整を行います。
5. 輸出者が知っておきべき「保税地域」とは?
ここでは、前項で解説した「輸出通関手続きの流れ」の補足として、商品の輸出の際に認識しておくべき、保税地域について簡潔に解説します。
貨物は出荷後に保税地域へ移動される
大前提として、商品を輸出する場合、保税地域で輸出許可を受けなくてはなりません。
税関によると、保税地域とは、「輸出入貨物を法の規制下に置くことにより、秩序ある貿易を維持し、関税などの徴収の確保を図るとともに、貿易の振興及び文化の交流などに役立てる」ための場所であると述べています。つまり、輸出入貨物の審査を行うための場所だと言えるでしょう。
保税地域には5種類あり(指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域)、その種類によって機能や蔵置期間が異なります。そのうちのひとつにコンテナヤードなどに代表される「指定保税地域」がありますが、ここは、外国貨物(輸出許可がされた貨物、輸入手続きがまだ終わっていない貨物等)を積み卸したり、運搬したりするための場所です。その為、その貨物が置ける期間も1ヵ月と限られています。
その他、造船所や製鉄所に多い「保税工場」では、非関税のまま外国貨物を加工や製造ができ、外国貨物が置ける期間も2年と長くなっています。それ以外に、「保税蔵置場」「保税展示場」「総合保税地域」もありますが、一般的な輸出入の場合には、「指定保税地域」を通過する必要があると言えます。
6. 輸出者が知っておくべき「特定輸出者(AEO輸出者)制度」とは?
さらに「輸出通関手続きの流れ」の補足として、一連の通関手続きを簡略化できる「特定輸出者(AEO輸出者)制度」についても、簡潔に解説します。
通関手続きが簡便になる「特定輸出者(AEO輸出者)制度」
「特定輸出者(AEO輸出者)制度」とは、6つあるAEO(=Authorized Economic Operator)制度のひとつです。AEO制度とは、2001年の同時多発テロを契機に、「国際物流のセキュリティ確保」と「物流円滑化の推進」の両立を目的に創設された制度で、日本でも2006年から導入されています。
「貨物のセキュリティ管理が整っている」および「コンプライアンス(法令遵守)体制が整っている」事業者が、税関によって「特定輸出者(AEO輸出者)」に認定されることで、輸出する貨物を保税地域ではなく任意の場所で輸出許可を得ることができるなど、輸出に関する手続きやコストを削減できます。
「特定輸出者(AEO輸出者) 制度」を活用するには、関税法第67条に定められた用件をクリアし、特定輸出者承認申請書やその他書類を提出し、税関長の承認を得る必要があります。
参照:「AEO(Authorized Economic Operator)制度」税関
7. 輸出者の輸出業務をサポートしてくれる「通関士」と「フォワーダー」
ここまで輸出通関について見てきましたが、実際の輸出業務では、より複雑な手続きが必要なケースもあります。その為、貿易会社や商社等、海外との輸出入業務が日常業務となっている企業では、「通関士」や「フォワーダー(運送貨物取扱業者)」といった通関業者に輸出の通関手続きを依頼することもあります。
この項ではそんな「通関士」と「フォワーダー」について簡潔に解説します。
通関士という通関のプロ
輸出入に関わる通関業務の専門家、それが「通関士」です。通関士は、国家資格の一つで、取得が難しい資格の一つとして数えられます。通関士の業務は、貨物の輸出入に関わる申告書類の審査と申告が主な業務となっています。
後述するフォワーダー業者の中にも通関士がいるため、代理で輸出通関手続きを依頼することが可能です。現在、通関士は不足気味であると言われています。今後、日本企業の海外進出が増えることを考えると、通関士の需要は高いと言えます。
フォワーダーは国際物流の専門家
フォワーダーとは、一言で言いかえれば「国際物流のプロ」です。いわばオールマイティな通関士というイメージが近いかもしれません。
複雑な手続きや国ごとによって異なる輸出入方法や関税、法規制を熟知しており、現地の販売会社と依頼主をつなぐ、国際物流の専門業者です。
フォワーダーの種類と仕事内容とは?
フォワーダーにも種類があり、それによって仕事内容が異なります。大きく分けると、
・非船舶運航業者
・ブローカー等
・特定サービスを提供する運送業者
非船舶運航業者は、自身で船舶を所有せずに、荷送人として船の手配を行います。ブローカーは、自身名義で運送契約の取次ぎを行いますが、契約の当事者として運送人の責任を負いません。特定サービスを提供する運送業者は、さらに3つに分けることができます。
・混載業者
・国際複合一貫運送業者
・インテグレーター
混載業者は、個々の貨物を小口貨物としてまとめ、一括大口貨物として仕向地に運ぶ業者です。国際複合一貫運送業者は、海上輸送+陸上輸送のように、異なる輸送手段を組み合わせて、貨物の引受から引渡しまで一貫して運送を行います。インテグレーターは、自社で飛行機を有し、航空輸送+陸上輸送によってドアツードアで貨物を届けます。
(JETROより)
以上を踏まえると、仕向地や貨物の形態・大きさ等によって依頼すべきフォワーダー業者が異なってくることがわかります。
多様な輸送手段を持つフォワーダー
フォワーダーには、通関の知識だけでなく、ある国の法規制や関税の知識を熟知している、あるいは多様な輸送手段を持っている業者が数多くいます。その為、最適な輸送手段の選択やトラブル回避のリスクヘッジが期待できます。
多様な輸送手段を持つフォワーダーの存在は、国際物流における効率的なサプライチェーンの確立やコストダウンにもつながります。
8. 輸出通関に関するタスクを専門家にアウトソーシングするという選択
この記事を読んでいただいたならば、輸出通関プロセスが複雑な作業であることがお分かりいただけるかと思います。自社のリソースだけでこれらを完全にカバーすることは、大きな時間と労力を必要とします。
輸出通関手続き成功の秘訣は輸出業務サポート企業の活用にあり
輸出通関業務は、その複雑さを鑑みると、経験豊富な専門家に依頼することが非常に効果的です。
輸出通関プロセスは、単に商品を国境を越えて移動させること以上の意味を持ちます。これには、国際貿易法の遵守、関税・税制の理解、精確な文書の作成、商品分類、さらには各国の規制への適応など、多くの専門的知識が必要です。
自社の強みと専門性を活かしつつ、未知の市場でのリスクを最小限に抑えるためにも、専門家のサポートを受けることは、特に輸出通関を行う際には有効です。これにより、効率的かつ効果的に通関手続きを進め、輸出ビジネスの円滑な進行と成功を促進することが期待できます。
「Digima〜出島〜」に寄せられた輸出通関業務に関する相談事例
そこで、ひとつの選択肢として浮かび上がってくるのが、「自社の輸出通関業務に必要なタスクを専門家にアウトソーシングする」ということです。
例えば、「Digima〜出島〜」には以下のような輸出通関業務に関する相談が寄せられています。
新たな事業展開の一環でアジアから使い捨て食品容器を輸入することを検討しています。この輸入プロセスに関わる業務をサポートしてくれる企業を探しており、特にインボイスの作成、通関手続き、保険関連のサポートが必要です。
初期段階ではテスト販売を行う予定です。それに伴い、適切なコンテナの積載量についてもアドバイスをいただけたらと思っております。
(業種:卸売・小売業・飲食業 / 進出国:アジア)
もちろん、その全てをアウトソーシングする必要はありません。これまでに培ってきた自社の強みは活かしつつ、知見が乏しい分野においては、その道のプロの専門家のサポートを受けるという選択も充分に効果的なのです。
もし貴社が初めて輸出通関業務に挑戦する段階であるならば、なおのこと専門の進出サポート企業の支援を検討することをオススメいたします。
9. 優良な輸出入・貿易・通関業者をご紹介
御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
今回は「輸出通関の基礎知識」と銘打って、輸出通関手続きの流れや、輸出通関申告の際に必要な書類であるインボイス(仕入書)やパッキングリスト(包装明細書)などの解説を中心に、商品の輸出入を行う企業に代わり通関業務などを行うフォワーダーや通関士の役割などを解説しました。
「Digima〜出島〜」には厳正な審査を通過した優良な輸出入・貿易・通関業者が多数登録しています。もちろん、複数の企業の比較検討も可能です。
「自社製品を海外に輸出したい」「通関手続きが難しくてよくわからない」…といった、海外への輸出のご質問・ご相談を承っています。
ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、御社にピッタリの輸出入・貿易・通関業者をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。
(参照文献)
・コトバンク(デジタル大辞泉)「通関」
・税関「保税地域の概要」
・税関「貨物到着から貨物引取までの流れ 通関の流れ(図)(カスタムスアンサー)」
・税関「特定輸出者制度を利用する際の手続き及び承認の要件について(カスタムスアンサー)」
・税関「税関で確認する輸出関係他法令の概要(カスタムスアンサー)」
・通関士Potal「通関士の仕事」
・通関士Potal「通関士の需要」
・JETRO「物流業者の種類と概要:日本」
・貿易キャラナビ(2017月1月23日) Tlady「「輸出通関手続き」はどのように行われているの!?」
・貿易キャラナビ(2015月7月6日) Tlady「国際物流のコーディネーター「フォワーダー(Forwarder)」」
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
もっと企業を見る

海外進出・海外ビジネスで
課題を抱えていませんか?
Digima~出島~では海外ビジネス進出サポート企業の無料紹介・
視察アレンジ等の進出支援サービスの提供・
海外ビジネス情報の提供により御社の海外進出を徹底サポート致します。
0120-979-938
海外からのお電話:+81-3-6451-2718
電話相談窓口:平日10:00-18:00
海外進出相談数
22,000件
突破