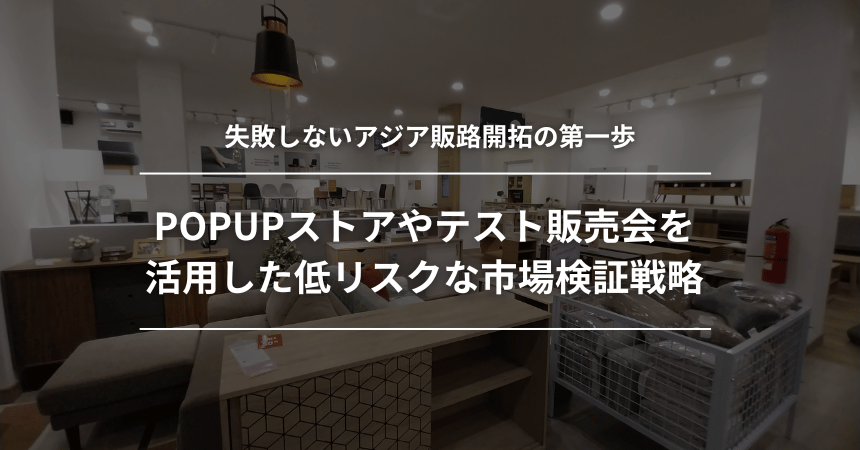【徹底解説】「小さな会社」がするべき海外事業の準備〜「海外進出」は夢じゃない!

「海外進出」と聞くと、多額の資金や優秀な人材が必要な、大手企業だけの戦略だと思っていませんか。国内市場の縮小傾向やインターネットの急速な普及により、独自の技術や魅力的な商品を持つ日本の小さな会社(スモールビジネス)にとっても、海外市場は大きなチャンスの宝庫となりつつあります。
とはいえ、情熱だけでグローバルマーケットに飛び込んでも、文化や商習慣の壁に阻まれ、手痛い失敗を喫しかねません。成功の鍵は、自社の身の丈に合った「入念な準備」にあります。
この記事では、海外進出を本気で考える小規模事業者の皆様に向けて、まず何から始め、どのようなステップを踏むべきかを具体的に解説します。
(※なお、本記事でいう「小さな会社(スモールビジネス」とは、中小企業庁の「小規模事業者」の定義に基づき、おおむね常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の事業者を想定して説明します。)
▼ 【徹底解説】「小さな会社」がするべき海外事業の準備〜「海外進出」は夢じゃない!
1. 海外で売りたければ「日本で売れている」ことが大事
海外進出を考えるとき、「海外でウケそうなものは何か?」と新しい商品を開発したり、奇抜なアイデアを求めたりしがちです。しかし、その前に立ち止まって、自社の現状を見つめ直してください。
あなたの主力商品は、今、日本国内でしっかりと売れていますか?
海外のバイヤーは必ずこの質問をしてきます。彼らは私たちが想像する以上にシビアです。彼らが日本の商品を買い付ける際、最も重視するポイントの一つが「日本国内での実績」です。
「日本で長年愛されている定番商品」
「特定の分野や地域で高いシェアを誇る」
「国内のメディアで何度も取り上げられている」
など、日本国内でのわかりやすい実績は、その商品の品質や魅力を客観的に証明する何よりの「お墨付き」となります。バイヤーは、その実績を見て「この商品なら、自国でも売れるかもしれない」と初めて興味を持つのです。逆の観点から言えば、商品の本国である日本で評価されていないものが、文化も言語も異なる海外市場で受け入れられるだろうと考えるわけがありません。
もちろん、最初から海外のニッチな市場に特化するという戦略もありますが、多くの小さな会社にとっては、まず足元である日本市場でしっかりと結果を出すことが、海外展開への一番の近道であり、最も堅実な準備となります。
2. ヒト・モノ・カネ:自社の「強み」と「課題」を徹底分析
国内である程度の実績が確認できたら、次に自社の経営資源、すなわち「ヒト・モノ・カネ」の観点から、海外展開に耐えうる体力があるかを冷静に分析します。これは、自社の「強み」と「課題」を洗い出す作業です。
(1) ヒト:海外展開を担う人材はそろっていますか。
海外ビジネスには、国内とは異なる専門知識が不可欠です。例えば下記のような能力が、海外ビジネスには必要となってきます。
語学力: 最低限、英語でのコミュニケーション(メール、商談)は可能ですか。
貿易実務: 輸出入の手続き、関税、インコタームズ(貿易条件)など、専門的な知識はどれぐらい理解されていますか。
現地理解: 進出先の商習慣、法律、文化を理解し、交渉できる能力は十分ですか。
社長自身がすべてを担うのは現実的ではありません。もし社内に適任者がいない場合、どうしますか? 新たに採用するのか、既存の従業員を育成するのか、あるいは外部の専門家(コンサルタント、フォワーダー、海外進出支援企業)や商社に委託するのか。人材の観点から、具体的な計画が必要です。
(2) モノ:その商品・サービスは海外で通用しますか?
日本で売れている商品が、そのまま海外で売れるとは限りません。下記の観点から、自社の商品・サービスが海外市場に適しているかを確認してみてください。
ニーズと適合性: その商品やサービスは現地のニーズに合っていますか? 気候、体格、生活習慣の違い(例:家電の電圧、食品の味付け)を考慮していますか。
ローカライズ: 現地の嗜好に合わせて、パッケージデザイン、容量、名称などを変更する「ローカライズ(現地最適化)」はできそうですか。
法規制と認証: 最も重要とも言えるのが規制です。食品の成分規制、化粧品の認可、電化製品の安全規格(CEマーク、UL認証など)をクリアできそうですか? これを怠ると、輸出自体ができません。
知的財産: 自社の商標や特許は、進出先(あるいは進出可能性のある国)で保護されていますか? ブランド価値のある商品であれば、模倣品対策は必須です。
(3) カネ:海外展開にかかる資金は十分にあるか?
海外進出は、国内ビジネスよりも格段にコストがかかります。例えば
初期投資: 市場調査費、現地視察費、展示会への出展費、外国語のWebサイトやパンフレットの作成費、翻訳費など。
運転資金: 輸送費、関税、広告宣伝費、保険料、代金回収までのキャッシュフロー(数ヶ月かかることも)など。
予備費: 為替変動リスクや、予期せぬトラブルに対応するための資金も必要です。
これらの費用を試算し、十分な自己資金を確保し、どれぐらいの期間で回収ができるか、あるいは後述する融資や補助金で調達できるかを具体的に計画することが重要です。
3. 海外へモノを売る方法は一つではない
「海外展開」と聞くと、すぐに「現地に支店を出す」、「現地のバイヤーへ、コンテナで大量に直接輸出する」といったことをイメージしがちです。しかし、それらは小さな会社にとっては、極めてハイリスクな方法であり、最初に取るべき戦略ではありません。
もっとリスクを抑え、スモールスタートできる「海外への売り方」がいくつもあります。
(1) 越境EC(Eコマース)
自社のECサイトを多言語化・多通貨対応にするか、あるいは海外の巨大ECモール(Amazon、eBay、Shopee、Lazada、Tmallなど)に出店する方法です。
メリット: 比較的低コストで世界中の消費者に直接商品を販売できます。どの国・地域で自社商品が受け入れられるかを見極める「テストマーケティング」の場としても最適です。
課題: 決済、配送、言語(カスタマーサポート)には思ったよりも手間がかかります。この壁をどうクリアするかを考える必要があります。
(2) 訪日外国人観光客(インバウンド)への販売
これは、「日本にいながら海外に売る」という考え方です。小さな会社にとっては海外に行って販路開拓する手間や規制対応の必要性が無くなるため、手軽に海外市場を取り込む有力な手段となります。
メリット: 店舗での免税対応、多言語メニューやPOPの整備、SNSでのインバウンド向け情報発信などを通じて、訪日客に直接商品をアピールできます。
波及効果:購入した訪日客が帰国後、自国でその商品の魅力を口コミで広めてくれたり、越境ECのリピーターになってくれたりする可能性があります。
課題:リピーターが付きづらいため、一部の定番商品を除き、継続的な販促活動が必要になることが多いです。
(3) 国内の「アメリカ」市場、米軍基地への販売
少し特殊な方法ですが、日本国内にある米軍基地内のPXやカミサリーのような商業施設、関連施設への納入も、一種の海外進出と言えます。いわば国内にある「アメリカ」市場が米軍基地関連の需要です。
メリット: 取引は国内で完結しますが、求められる品質基準や商習慣は米国(海外)のものです。国内取引の延長線上で、海外のニーズやスタンダードを経験する貴重なシミュレーションの場となります。
デメリット:米軍関係者との接触が必要で、販売の糸口を探すことは容易ではありません。また、US HACCP等、米国の高い基準や規制を満たす必要もあります。
4. 資金と知恵を確保!公的支援をフル活用しよう
リソースの限られる小さな会社にとって、国や自治体、関係機関が用意している公的な支援制度は、海外進出の強力な武器となります。特に身近なあなたの地元の商工会議所・商工会は、これらの支援の入り口として最適です。
特に資金調達では、商工会議所・商工会の支援は大変強い海外ビジネスのための武器になります。具体的な活用できる支援を例示しましょう。
(1) 小規模事業者持続化補助金
販路開拓や生産性向上に取り組む小規模事業者を支援する、非常に人気が高く使い勝手の良い補助金です。
活用例: 海外向けのECサイト構築費、外国語のパンフレット・チラシの作成費、海外展示会への出展費用、専門家経費など、海外展開に関わる費用の多くが対象となります。(※申請枠や公募要領により対象経費とその範囲が異なりますので、必ず最新情報を確認してください)
(2) マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
商工会議所・商工会の経営指導を受けている小規模事業者が利用できる、日本政策金融公庫の融資制度です。
特徴: マル経融資は、無担保・無保証人・低金利で資金を借りられるのが最大の魅力です。融資上限2,000万円、返済期間最長10年(据置2年)と、海外展開に必要な初期投資や、当面の運転資金として活用できます。
小規模事業者持続化補助金と、マル経融資はどちらも地元の商工会議所・商工会の支援を受けることが応募や利用の条件となることから、小さな会社にとって非常に相性の良い支援策です。
(3) 専門家派遣制度の活用
商工会議所・商工会や、JETRO(日本貿易振興機構)、中小機構(中小企業基盤整備機構) などでは、海外ビジネスに関する専門家を派遣してくれる制度を設けています。
貿易実務、海外法務、現地マーケティングなど、小さな会社に不足しがちなノウハウや知見を、専門家から直接、安価(または無料)で学ぶことができます。一人で悩まず、プロの知恵を借りてしまうのが、海外ビジネスを成功させる近道です。
5. まとめ:「あわてず」「あせらず」「あきらめず」で着実な一歩を
小規模事業者の海外進出は、決して簡単な道のりではありません。しかし、入念な準備と、自社の身の丈に合った戦略があれば、国内市場だけでは得られない大きな成長とチャンスを掴むことができます。今回の記事のポイントをまとめます。
・まずは「日本で売る」こと。国内での実績が、海外での信頼の証となる。
・「ヒト・モノ・カネ」で自社を徹底分析し、強みと課題を明確にする。
・「越境EC」や「インバウンド」など、海外直接輸出以外のスモールスタートも検討する。
・「補助金」「融資」「専門家」など、使える公的支援はすべて活用する。
海外進出は、一発逆転のホームランを狙うものではなく、地道なヒットを積み重ねるようなものです。小さな会社に限らず、海外ビジネスの成功には時間がかかります。
松下幸之助の言葉とされる「あわてず」「あせらず」「あきらめず」この3つの「あ」の精神で、夢の海外進出に向けて、着実な一歩を踏み出しましょう。
小さな会社の海外進出ならサウスポイントへご相談ください
当社サウスポイントでは、国家資格である中小企業経営のエキスパート「中小企業診断士」を複数名配置し、小さな会社の海外進出支援経験豊富な当社代表を中心に、皆様のご相談をお引き受けしています。
知りたいことを15分で回答する海外ビジネススポット相談や、最短1日での海外事業戦略策定など小さな会社が手軽に安価に使えるメニューをご用意しております。進出可能性の確認・海外とインバウンドへの販路開拓・資金繰り・補助金・公的支援の活用方法など、海外ビジネスで気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談