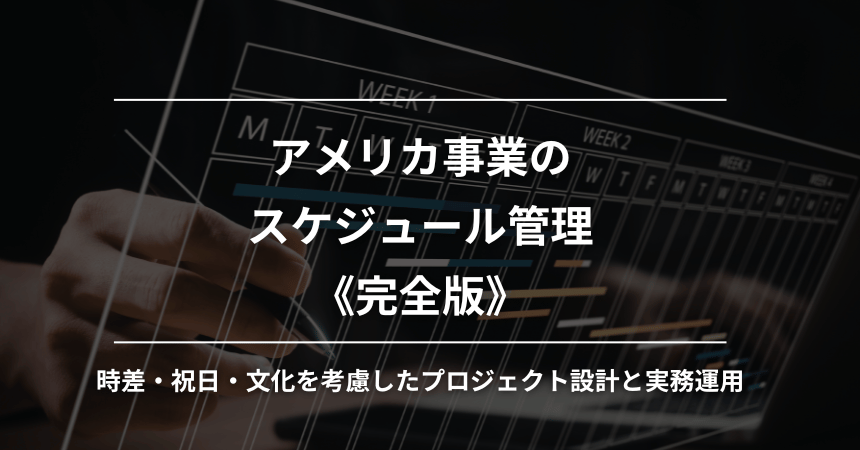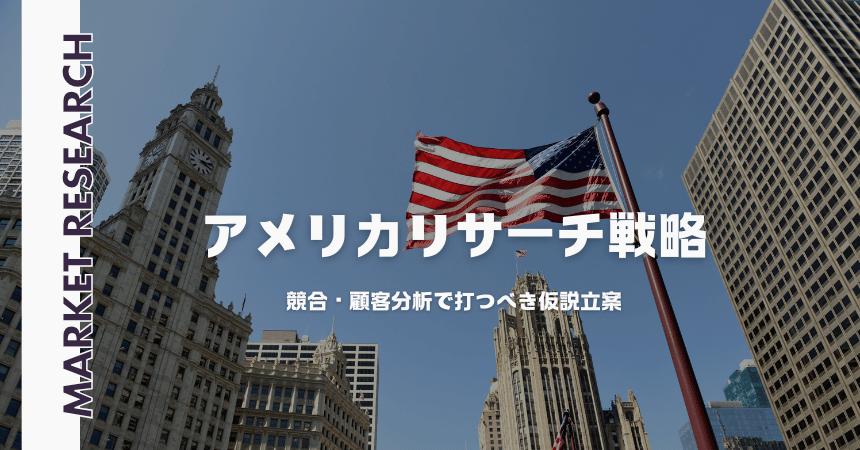UL認証とは? | 取得方法から合格のポイントまで徹底解説!

UL認証は、製品の安全性を保証するための重要な認証制度であり、特にアメリカ市場への参入を目指す企業にとって避けては通れない規格の一つです。電気・電子機器、産業機械、化学製品など幅広い分野で求められ、UL認証を取得することで製品の信頼性が高まり、販売促進にもつながります。
本記事では、そんなUL認証の概要や取得方法、審査のポイントについて詳しく解説します。UL認証の基準を理解し、スムーズに取得できるよう準備を整えましょう。
▼ UL認証とは? | 取得方法から合格のポイントまで徹底解説!
UL認証とは?

UL認証の背景と目的
UL(Underwriters Laboratories)は、1894年に設立された非営利の安全試験・認証機関であり、主に北米市場向けの製品安全基準を策定・審査しています。UL認証は、製品の電気的安全性、耐久性、発火防止性能などを評価し、基準を満たした製品に対して認証マークを付与する制度です。
UL認証の目的は、製品の安全性を向上させ、消費者や企業が安心して使用できる環境を整えることです。特に、電気・電子機器の分野では、UL認証の有無が市場競争力を大きく左右する要因となることも少なくありません。
UL認証の概要
UL認証は、大きく「製品安全試験」「工場審査」「定期監査」の3つのステップから構成されます。企業は、ULの定める規格に準拠した設計・製造を行い、試験に合格することで認証を取得できます。取得後も、ULによる定期的な工場審査が行われ、継続的な品質管理が求められます。
UL認証にはいくつかの種類があり、代表的なものとして以下のようなものがあります。
- UL Listed(リステッド認証):市場向けの最終製品に付与される認証
- UL Recognized(レコグナイズド認証):部品や構成要素に適用される認証
- UL Classification(クラス分類認証):特定の用途や性能基準に基づいた認証
他の認証との違い
UL認証は、CEマーク(欧州向け)、FCC認証(通信機器向け)などの他の規格とは異なり、特に北米市場向けの安全基準に重点を置いている点が特徴です。アメリカでは、多くの州や自治体がUL認証を取得した製品の使用を義務付けており、取得していない製品は市場での流通が困難になる場合があります。
また、ULは第三者認証機関として独立性を保ち、厳格な基準を適用することで高い信頼性を確保しています。メーカーが自己宣言できるCEマークとは異なり、UL認証の取得には第三者機関の試験をクリアする必要があるため、より厳密な安全性保証が求められます。
UL認証の取得が必要な業界への影響
UL認証は、特に以下の業界で強く求められています。
- 電気・電子機器(家電製品、照明器具、IT機器など)
- 産業用機械(ロボット、自動化機器、制御盤など)
- 電池・蓄電システム(リチウムイオン電池、UPSなど)
- 化学製品(防火材料、プラスチック、塗料など)
これらの分野では、安全基準を満たしていない製品の市場流通が規制される場合が多く、UL認証を取得することが市場参入の必須条件となっています。
UL認証の主な要件

製品試験と評価
UL認証を取得するためには、ULの定める安全基準を満たすことが求められます。この安全基準は、製品の種類ごとに細かく設定されており、特に電気・電子機器や産業機械などでは、厳格な試験が必要となります。試験内容は主に以下のようなものがあります。
1. 電気的安全性試験
電気機器に対するUL認証の重要な試験のひとつが 電気的安全性試験 です。この試験では、製品が過電流や短絡、異常な電圧変動に対してどのような耐性を持っているかを確認します。具体的には以下の試験が実施されます。
- 過電流試験:定格以上の電流が流れた場合、製品が適切に遮断されるかどうかを確認する。
- 耐電圧試験:製品が一定の高電圧に耐えられるかを検証する。
- 漏電試験:製品の絶縁が適切であり、使用時に電流が外部に漏れないかを測定する。
このような試験を通じて、製品が消費者の安全を確保できる設計になっているかが評価されます。特に、電源を使用する製品では、電気的なトラブルによる火災や感電事故のリスクがあるため、UL認証の基準は非常に厳しく設定されています。
2. 耐久性試験
製品が長期間にわたって安全に使用できるかどうかを評価する 耐久性試験 もUL認証の取得に不可欠です。試験の内容は、製品の種類や用途によって異なりますが、一般的には以下のような項目が含まれます。
- 温度サイクル試験:高温・低温の環境を交互に設定し、製品が温度変化に耐えられるかを検証する。
- 振動試験:輸送や使用中に発生する振動に対する耐久性を確認する。
- 機械的ストレス試験:繰り返しの使用や圧力が加わった場合に製品が変形しないかを評価する。
特に、業務用の電気機器や建材などでは、長期にわたる使用が想定されるため、耐久性試験の基準は厳格です。製品が過酷な環境下でも適切に動作し、劣化による事故を防ぐことが求められます。
3. 発火・燃焼試験
UL認証の中でも特に重要なのが、発火や燃焼に関する試験 です。電気製品やプラスチック素材が発火源となる事故を防ぐため、以下のような試験が実施されます。
- 燃焼速度試験:製品の素材が燃えやすいかどうかを評価する。
- 発火試験:高温や異常電流が流れた際に、製品が発火するかどうかを確認する。
- 自己消火試験:製品が万が一燃えた場合に、火が自然に消えるかどうかを検証する。
特に、プラスチックやゴム製の部品を使用する場合、自己消火性を持つ難燃性材料を採用することで、試験をクリアしやすくなります。
4. 環境試験
UL認証では、製品が特定の環境条件下で安全に動作するかどうかも検査されます。特に以下のような試験が行われます。
- 湿度耐性試験:高湿度の環境でも絶縁が保たれるかを確認する。
- UV耐性試験:屋外で使用される製品が紫外線による劣化に耐えられるかを評価する。
- 塩水噴霧試験:海岸地域や高塩分環境下でも金属部分が腐食しないかを検証する。
こうした試験を通じて、製品が特定の使用環境に適合していることを証明しなければなりません。
工場審査(FUS:Follow-Up Service)
UL認証の取得後、製品の品質を維持するために 工場審査(Follow-Up Service:FUS) が実施されます。この審査は、認証を取得した製品が 一貫してUL基準を満たしているか を確認するために行われ、年に1回~2回程度、ULの審査員が製造現場を訪問して監査を行います。
工場審査では、まず製造プロセスが認証取得時と同様に運用されているかどうかが確認されます。具体的には、生産ラインに変更が加えられていないか、品質管理が適切に行われているかが厳しく評価されます。次に、使用されている材料や部品についても、認証取得時の仕様と一致しているかがチェックされます。仕入れ先の変更があった場合には、変更後の部品や材料がULの基準に適合しているかどうかが特に注意深く確認されます。さらに、製造された製品からランダムに抜き取られたサンプルに対して試験が実施され、基準に適合しない場合には速やかに修正措置が求められます。
もし、これらの工場審査のいずれかで不合格となった場合、UL認証が取り消される可能性や、既に市場に出回っている製品の回収が求められるリスクがあるため、企業にとっては日々の品質管理体制の強化と、定期的な内部監査の実施が極めて重要となります。
UL認証の取得プロセス

1. ULへの申請(事前準備と提出)
UL認証を取得するための第一歩は、ULへの申請手続きを行うことです。申請はULの公式ウェブサイトを通じて行うことができますが、事前にしっかりとした準備を整えておくことが重要です。申請の際には、以下の情報を提出する必要があります。
- 申請に必要な情報
- 製品の名称および型番
- 製造元の企業情報
- 製造国および工場の所在地
- 使用する材料や部品の詳細
- 製品の設計図や回路図(電子機器の場合)
- 使用環境(屋内・屋外・高温環境など)
ULは、申請された製品がどの規格に適合するかを判定し、必要な試験項目を決定します。製品が複数のカテゴリに該当する場合、異なる規格が適用されることがあり、試験内容や審査の手順が変わることがあります。そのため、UL認証を取得した経験がない場合は、ULの担当者や認証コンサルタントと相談しながら進めることが推奨されます。
また、UL認証の取得には ULと契約を締結する必要があり、試験費用や審査費用の見積もりが提示されます。この段階で費用感を把握し、予算内で対応可能かどうかを確認しておきましょう。
UL認証の取得にかかる費用は、製品の種類や試験項目の数、工場審査の複雑性、さらには製造工程の規模など、さまざまな要因によって大きく左右されるため、決まった金額はありません。一般的には、UL認証の費用は数十万円から数百万円に及ぶケースが多く、特に高度な試験や複雑な審査が必要な製品の場合は、さらに高額になる可能性もあります。
2. 書類審査(設計レビュー)
ULへの申請が完了すると、次のステップとして 書類審査 が行われます。書類審査では、提出した設計図や製品仕様書をもとに、ULの技術担当者が規格に適合しているかどうかをチェックします。
主な審査内容は下記のとおりです。
- 製品設計がUL規格に適合しているか
- 使用する材料がUL規格で認められているか
- 回路設計や配線が安全基準を満たしているか
- 発熱や漏電のリスクがないか
この段階で問題が発覚すると、ULから設計変更の指示が出されることがあります。たとえば、使用している材料が耐燃性の基準を満たしていない場合、認証済みの材料に変更しなければならないことがあります。また、回路設計に問題がある場合は、過電流防止機能の追加や、配線の見直しが必要になることもあります。
書類審査にかかる期間は2~4週間程度 ですが、修正が必要な場合はさらに時間がかかることがあります。スムーズに進めるためには、ULの認証基準を事前に確認し、申請前に設計の見直しを行うこと が重要です。
3. 試験・評価(UL試験所での実施)
書類審査をクリアすると、次に ULの試験機関での製品試験 が行われます。この試験は、製品がULの安全基準を満たしているかを確認するもので、先程の項目で挙げたようなさまざまな試験が実施されます。
製品の種類によって試験内容が異なるため、試験の詳細は事前にULと調整する必要があります。試験にかかる期間は4週間~8週間程度 ですが、試験に不合格になった場合は再試験が必要となり、さらに時間がかかることがあります。
試験で不合格となった場合、問題点を改善したうえで再試験を受ける必要があります。このとき、試験費用が追加で発生することもあるため、最初の試験で合格できるように、事前に自社での試験や評価をしっかりと行っておくことが推奨されます。
4. 工場審査(FUS: Follow-Up Service)
UL試験に合格した後、認証を取得する前に 工場審査(FUS) が行われます。これは、UL認証取得後も製品の品質が維持されることを確認するためのプロセスです。
工場審査には 1~2日程度 かかりますが、問題が発生すると再審査が必要となり、認証取得が遅れることになります。そのため、UL審査の基準に沿った品質管理体制を整えておくことが重要です。
5. 認証取得とULマークの付与
工場審査が完了すると、正式にUL認証が発行され、製品にULマークを付与することが許可されます。ULマークは、製品の安全性を示す重要な証明となり、米国市場での信頼性向上に大きく貢献します。
ただし、UL認証は 取得後も定期的な更新と監査が必要 です。ULは、認証を維持するために年1~2回の工場監査を実施し、製品の品質が継続的に基準を満たしているかを確認します。万が一、不適合が見つかった場合、認証の取り消しや製品の市場回収を求められることもあるため、品質管理の徹底が求められます。
UL認証取得を成功させるためのポイント

設計段階からUL規格を考慮する
UL認証の取得を円滑に進めるためには、製品の設計段階からULの安全基準や評価項目を十分に理解し、反映させることが極めて重要です。設計初期の段階で、UL規格に適合した材料や部品、回路設計、さらには構造設計などの各要素を選定することで、後の試験段階での不合格や再試験のリスクを大幅に低減することが可能となります。
たとえば、耐火性や耐熱性、過電流保護といった製品の基本安全性を確保するため、認証実績のある素材を採用するなど、初期段階での徹底した対策が求められます。また、設計変更が生じた場合には、迅速にUL規格の再確認を行い、必要な修正措置を講じる体制を整えることが、認証取得の成功に大きく寄与するでしょう。
こうした取り組みは、後工程での試験不合格を防ぐとともに、製品全体の信頼性向上にもつながり、企業にとっては市場での競争力を高める重要な要素となります。
事前に社内試験を実施する
UL認証試験に臨む前に、社内で実施可能な試験や評価を行うことは、認証取得の成功に直結する非常に有効な対策です。自社内で製品の耐久性、電気的安全性、耐火性、さらには機械的強度など、UL認証で求められる各項目に対して十分な検証を行うことで、実際のUL試験時に予期せぬ問題が発生するリスクを大幅に低減することが可能となります。
事前に実施した試験結果をもとに、設計や製造工程における不具合や改善点を早期に把握し、必要な対策を講じることは、再試験や追加費用の発生を防ぐだけでなく、製品全体の品質向上にも寄与します。また、内部試験の結果を詳細に記録しておくことで、ULへの説明資料として活用できるため、認証プロセス全体がスムーズに進むとともに、企業の品質管理体制の信頼性を高めることができます。
スケジュールの余裕を持った計画を立てる
UL認証の取得プロセスは、製品の設計から試験、工場審査に至るまで多岐にわたるため、通常は数ヶ月から1年以上の期間を要する場合があります。そのため、製品の市場投入や新製品発表といった企業のビジネス戦略に支障が出ないよう、UL認証取得のためのスケジュールを十分に余裕を持って計画することが不可欠です。
各工程に必要な期間を正確に見積もり、万が一の再試験や修正対応のための時間も加味したスケジュール管理を行うことで、認証プロセスにおける予期せぬ遅延やコスト増加を未然に防ぐことができます。特に、試験や工場審査の段階では、認証機関との連絡調整や必要書類の提出が求められるため、余裕をもった計画が製品の品質保持と市場投入のタイミングに大きく影響します。
品質管理体制の整備を徹底する
UL認証を取得した後も、その認証を維持し続けるためには、日々の品質管理体制の整備が極めて重要となります。製品の設計や製造工程において、常に認証取得時と同じ基準を遵守することが求められ、万一の不具合発生に迅速に対応できるよう、内部監査や生産記録の厳密な管理が不可欠です。
製造ライン全体で品質チェックを徹底し、製造工程での変更や材料の使用状況がUL認証基準に照らして問題ないかどうかを常に監視することが、認証の取り消しリスクを低減し、企業の信頼性向上に繋がります。さらに、部品や材料に変更が生じた場合には、即座にUL基準に再評価を行い、必要な対策を講じる体制を整えることで、認証維持のためのリスクマネジメントを実現することが可能です。こうした継続的な品質管理の徹底は、単にUL認証の維持だけでなく、企業全体の品質向上や顧客満足度の向上にも直結するため、長期的な視点での管理体制の強化が求められます。
認証取得の専門家やコンサルタントの支援を活用する
UL認証のプロセスは非常に複雑であり、初めて認証取得に挑戦する企業やリソースの限られた事業者にとっては、内部のみで対応することが難しい場合があります。そのため、UL認証に精通した専門家やコンサルタントの支援を積極的に活用することが有効な手段となります。彼らは最新のUL基準や試験手法、申請プロセスに関する豊富な知識と経験を有しており、書類作成から試験対策、工場審査の準備に至るまで、各工程で具体的かつ的確なアドバイスを提供してくれます。
専門家のサポートを受けることで、設計段階からの対応策が明確になり、社内試験や内部監査の実施も効率的に進めることができ、認証取得までの期間短縮やコスト削減も実現できます。加えて、最新の市場動向やULの更新情報を迅速にキャッチアップするためにも、外部の専門家の知見は貴重であり、グローバル市場での競争力向上にも大きく貢献します。UL認証取得にあたって、信頼できるパートナーとの連携を強化し、効率的かつ確実な認証取得プロセスを実現することをおすすめします。
UL認証に関する最新情報
技術革新の影響
UL認証の基準や試験方法は、近年の技術革新に合わせて変化しています。かつては電気的安全性や耐久性が主な評価項目でしたが、IoT機器やスマートデバイスの普及により、情報セキュリティやデータ保護の評価も重視されるようになりました。
これに伴い、企業は製品開発の段階から安全性だけでなく、サイバー攻撃に対する防御策や、ソフトウェアのアップデートが可能な設計を取り入れる必要があります。最新技術を活用する製品ほど、認証プロセスにおいて高度な技術的検証が求められ、UL側も迅速に新たな評価基準を整えている状況です。
環境への配慮と持続可能性
環境への配慮は、UL認証においても重要なテーマになっています。世界的な環境規制や持続可能な開発目標に対応するため、ULは製品の環境負荷や省エネルギー性能に関する評価項目を強化しています。
具体的には、使用材料の有害物質削減、リサイクル性の向上、さらには製品全体のエネルギー消費量の低減などがチェック対象となっています。企業は、製品設計の初期段階から環境にやさしい素材の選定や省エネ設計を取り入れることで、UL認証取得とともに環境負荷の低減にも寄与できるようになっています。
デジタル化の進展
UL認証の取得プロセスは、デジタル化の進展によって大きく効率化されています。ULはオンラインシステムや各種デジタルツールを導入し、申請書類の提出から審査、試験結果のフィードバックまでの一連の流れを簡素化しました。従来は紙ベースで行われていた手続きが自動化され、企業はより迅速に必要な情報を管理できるようになっています。これにより、UL認証にかかる期間や労力が削減され、企業にとってはコスト面でもメリットがあると言えるでしょう。
国際的認知度の向上
UL認証は、もともと北米市場向けの安全規格として知られていましたが、現在ではグローバルな市場でも高い評価を得ています。多くの国や地域でUL認証を取得した製品は、製品の信頼性や安全性の証として認識され、輸出入において重要な判断基準となっています。
さらに、国際的な基準との整合性や相互承認の動きが進んでいるため、UL認証を取得することで世界各国での市場参入が容易になり、企業の競争力向上にもつながっています。
まとめ
UL認証は、製品の安全性と品質を保証し、特にアメリカ市場をはじめとする国際市場での信頼性を確保するために不可欠な認証制度です。本記事では、UL認証の概要から取得プロセス、工場審査のポイント、そして成功のための対策について詳しく解説しました。
認証取得をスムーズに進めるためには、設計段階からUL基準を考慮し、社内試験を実施することが重要 です。さらに、品質管理体制の整備と、計画的なスケジュール管理によって、試験の不合格や認証取得の遅れを防ぐことができます。UL認証の維持には、定期的な工場審査をクリアする必要があり、品質管理の徹底が欠かせません。
また、技術革新や環境規制の強化、デジタル化の進展に伴い、UL認証の基準も変化し続けています。企業は最新情報を常にチェックし、柔軟に対応することが求められます。特に、UL認証に関する専門知識を持つコンサルタントと連携することで、より効率的に認証を取得・維持することが可能です。
その点、「Digima~出島~」には、優良なアメリカ展開の専門家が多数登録されています。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
UL認証の取得は単なる規制対応ではなく、企業のブランド価値を高め、市場での競争力を強化する重要な要素です。確実な認証取得と品質管理を行うことで、国内外の市場での信頼を築き、長期的な事業成長につなげていきましょう。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
オススメの海外進出サポート企業
-
YCP
グローバル22拠点✕800名体制で、現地に根付いたメンバーによる伴走型ハンズオン支援
<概要>
・アジアを中心とする世界21拠点、コンサルタント800名体制を有する、日系独立系では最大級のコンサルティングファーム(東証上場)
<サービス特長>
・現地に根付いたローカルメンバーと日本人メンバーが協働した伴走型ハンズオン支援、顧客ニーズに応じた柔軟な現地対応が可能
・マッキンゼー/ボストンコンサルティンググループ/ゴールドマンサックス/P&G/Google出身者が、グローバルノウハウを提供
・コンサルティング事業と併行して、当社グループで展開する自社事業群(パーソナルケア/飲食業/ヘルスケア/卸売/教育など)の海外展開実績に基づく、実践的なアドバイスを提供
<支援スコープ>
・調査/戦略から、現地パートナー発掘、現地拠点/オペレーション構築、M&A、海外営業/顧客獲得、現地事業マネジメントまで、一気通貫で支援
・グローバル企業から中堅/中小/スタートアップ企業まで、企業規模を問わずに多様な海外進出ニーズに応じたソリューションを提供
・B2B領域(商社/卸売/製造/自動車/物流/化学/建設/テクノロジー)、B2C領域(小売/パーソナルケア/ヘルスケア/食品/店舗サービス/エンターテイメントなど)で、3,000件以上の豊富なプロジェクト実績を有する
<主要サービスメニュー>
① 初期投資を抑えつつ、海外取引拡大を通した円安メリットの最大化を目的とする、デジタルマーケティングを活用した海外潜在顧客発掘、および、海外販路開拓支援
② 現地市場で不足する機能を補完し、海外事業の立ち上げ&立て直しを伴走型で支援するプロフェッショナル人材派遣
③ アジア圏での「デジタル」ビジネス事業機会の抽出&評価、戦略構築から事業立ち上げまでの海外事業デジタルトランスフォーメーションに係るトータルサポート
④ 市場環境変動に即した手触り感あるインサイトを抽出する海外市場調査&参入戦略構築
⑤ アジア特有の中小案件M&A案件発掘から交渉/実行/PMIまでをカバーする海外M&A一気通貫支援
⑥ 既存サプライチェーン体制の分析/評価/最適化、および、直接材&間接材の調達コスト削減 -
株式会社ダズ・インターナショナル
東南アジア・東アジア・欧米進出の伴走&現地メンバーでの支援が強み
私たちは企業の海外挑戦を設計→実行→着地まで伴走支援いたします。
これまでの企業支援数は1,500以上です。
私たちは『どの国が最適か?』から始まる海外進出のゼロ→イチから、
海外進出後のマーケティング課題も現地にて一貫支援いたします。
※支援主要各国現地にメンバーを配置し、海外進出後も支援できる体制
------------------------------------
■サポート対象国(グループ別)
↳アジア①(タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・インドネシア・フィリピン・ラオス)
↳アジア②(日本・香港・シンガポール・台湾・韓国)
↳アジア③(ドバイ・サウジアラビア・インドバングラデシュ・モンゴル・ミャンマー)
↳欧米(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)
※サポート内容により、対応の可否や得意・不得意な分野はあります。
------------------------------------
■対応施策ラインナップ
①"市場把握"サポート
目的は"海外現地を理解し、事業の成功可能性を上げる"こと。
(以下、含まれる施策)
↳市場概況・規制調査
↳競合調査
↳企業信用調査
↳現地視察企画・アテンド
②"集客活動"サポート
目的は"海外現地で売れるためのマーケティング活動を確立"すること。
↳多言語サイト制作
↳EC運用
↳SNS運用
↳広告運用(Google/Metaなど)
↳インフルエンサー施策
↳画像・動画コンテンツ制作
③"販路構築"サポート
目的は"海外現地で最適な海外パートナーとの取引を創出"すること。
↳商談向け資料制作
↳企業リストアップ
↳アポイント取得
↳商談創出・交渉サポート
↳契約サポート
④"体制構築"サポート
目的は"海外現地で活動するために必要な土台"をつくること。
↳会社設立(登記・銀行口座)
↳ビザ申請サポート
↳不動産探索(オフィス・倉庫・店舗・住居)
↳店舗開業パッケージ(許認可・内装・採用・集客)
↳人材採用支援(現地スタッフ採用支援)
------------------------------------ -
合同会社サウスポイント
世界と日本をつなぐ架け橋「沖縄」から海外展開を支援しています
2017年7月日本・沖縄と海外の万国津梁の架け橋を目指して、企業の海外展開支援を目的として沖縄・那覇で設立。アジア・欧州を中心に沖縄県内・沖縄県外企業の海外進出・国際展開のサポートを実施しています。2022年7月には観光産業の伸びの著しい石垣市に八重山事務所を開設しております。
沖縄をハブに、台湾・中国・香港・ベトナム・タイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・オーストラリア・ニュージーランド・イギリス・ドイツ・ブラジル各国にパートナーエージェントを配置し、アメリカ合衆国・インドは提携先を設けていますので、現地でも情報収集、視察等も直接支援可能、幅広く皆様の海外展開とインバウンド事業をサポートしております。 -
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。
実績:
東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)
東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)
南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)
北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)
中東(トルコ、サウジアラビア等)
ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)
アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等) -
株式会社コンパスポイント
Amazonを使った日本企業の海外進出をサポートします。
弊社コンパスポイントでは、越境EC、各国Amazon特有のノウハウに加え、
貿易に関する知識と数多くの企業様への支援実績に基づいて
Amazonを中心とした国内外EC全般のサポートとコンサルティングを提供させて頂いております。
また、中小機構開のEC・IT活用支援パートナー、及び販路開拓支援アドバイザー、
JICAマッチング相談窓口コンサルタント、
複数の銀行の専門家として企業様のご支援をさせて頂いており、
また、中小機構、銀行、地方自治体、出島 等が主催する各種セミナーでの登壇も行っております。
日本Amazonはもちろん、北米、欧州、インド、オーストラリア、サウジ、UAE、
トルコ、シンガポールAmazonなどへの進出サポートを行っており、
中小企業から大手まで、またAmazonに出品可能なあらゆる商品に対応致します。
企業様が海外Amazonへ進出される際にハードルとなる、
Amazon販売アカウントの開設、翻訳、商品画像・動画撮影、商品登録、国際配送、
多言語カスタマーサポート、国際送金サポート、PL保険、Amazon内広告を含む集客、
テクニカルサポート、アカウント運用代行、著作権・FDA・税務対応・GDPR対応サポート、
市場調査、コンサルティング、SNSマーケティング、メディアバイイング、現地スタッフの手配
等について、弊社パートナーと共に対応させて頂きます。
また、国内Amazonの場合、並行して楽天、ヤフー、自社サイト、SNS、メディアサイト、広告なども含めたデジタルマーケティングのトータルサポートも実施しております。