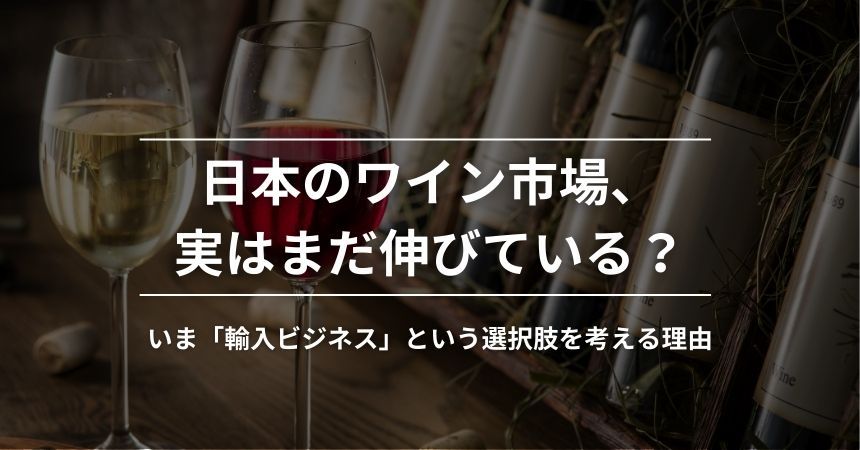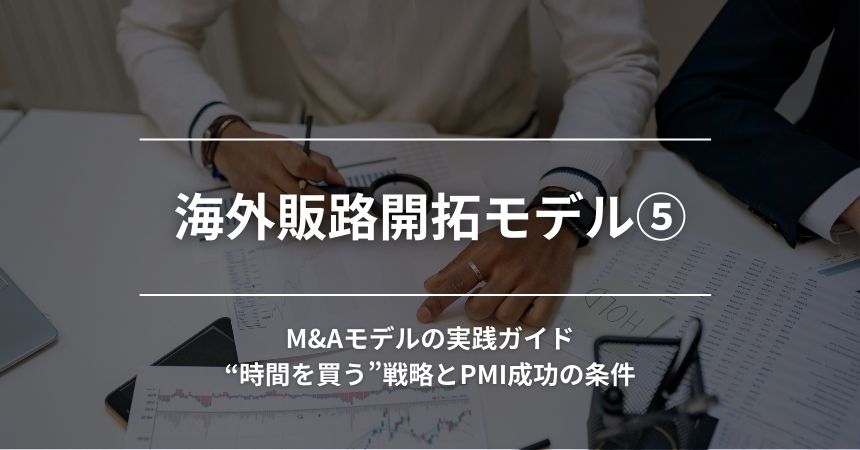ISOの基礎知識 | ISO(国際標準化機構)認証の種類と取得方法をくわしく解説

ISOとはスイスに本拠地を置く非政府組織である国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称です。「ISO」という言葉がISO規格やISOマネジメントシステムのことを指すこともあります。
ISOの基礎知識として、ISOの基本情報に加え、海外ビジネスで「ISO認証」取得をする必要性や、ISO認証取得のメリット&デメリットについて解説します。海外市場における自社の商品の信頼と価値を高めるためにも、ISO認証の種類とISO認証の取得方法についてしっかり確認しておきましょう。
▼ISOの基礎知識 | ISO(国際標準化機構)認証の種類と取得方法をくわしく解説
- 1. ISOの基本情報
- 2. 海外ビジネスで「ISO認証」取得をする必要性とは?
- 3. ISO認証のメリット
- 4. ISO認証のデメリット
- 5. ISOマネジメントシステムの種類
- 6. ISO認証の取得方法をステップ別に解説
▼アナタの海外ビジネスを成功させるために
1. ISOの基本情報
ISOとは
ISOとは冒頭でもお伝えしたとおり、本来はスイスに本拠地を置く非政府組織である国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称ですが、ISOが策定した国際規格やその認証のことを「ISO」と呼ぶこともあります。
「ISOを取得」という表現はかなり一般的になっていますが、本来は「ISO規格の認証を取得する」「ISO認証を取得する」という表現が正しいです。
国際標準化機構とは?
国際標準化機構は、1947年2月23日に設立されたスイス民法による非営利法人です。スイスのジュネーヴに本部があり、国家間に共通な標準規格を策定・提供し、世界貿易を促進している独立組織で、国際規格の世界的相互扶助を目的としています。
ISOへの加盟は1ヵ国1機関と定められています。世界で160ヵ国以上の国・地域が加盟しており、日本からはJISC(日本工業標準調査会)が加盟しています。
約2万ある規格は、工業製品・技術・食品安全・農業・医療など、電気関係を除くあらゆる分野を網羅しています。ISOの公用語は英語・フランス語・ロシア語です。
ISOの語源は、ギリシャ語の「isos=相等しい」から来ているのだとか。
ISOは世界標準の規格を策定している
ISOは技術報告書、技術仕様書、公開仕様書、技術正誤表、ガイドなども発行していますが、主な刊行物は国際規格です。
国際規格はとても重要なもの。例えば長さや重さの単位が同じなのに国ごとに実際の数値が異なっていたり、安全の基準が国によってバラバラだったりすると、他国との間で製品をやり取りするのはとても困難です。世界で同じ基準を持つことができれば、国際交流がぐっとスムーズになります。
ISOが国際的に共通の基準を設けることは、世界中の製品の安全性や質を高めることや、世界貿易を発展させることに役立っています。
ISOで定められた国際規格は、「ISO [IS] nnnnn[-p]:[yyyy] - 題名」の形式で指定されます。「nnnnn」は規格の番号で、規格が複数に分かれる場合、個別の部を指定する場合に使用するのが「p」です。(「-p」をつけない場合は全ての部を指します)
発行年もしくは改訂年が「yyyy」の部分に表示され、他の標準化団体と合同で制定した規格である場合は、「ISO」の部分が「ISO/IEC」 などと記載されます。
2. 海外ビジネスで「ISO認証」取得をする必要性とは?
ISOの規格は世界標準の規格ですから、認証を取得するのは国際的なお墨付きをもらえるのと同じこと。つまり、海外でビジネスをする際に企業の安心感や信頼感をアピールしやすくなります。
海外におけるISO認証の現状
例えばISO9001は品質マネジメントシステムの規格ですが、ISOによると2018年時点では、日本においては34,335件、ISO9001の認証が発行されています。これは何と、世界第4位の認証取得数です。ちなみに、1位は中国、2位はイタリア、3位はドイツ。1位の中国の取得数は295,703と、他の国と桁が違う取得数となっています。
環境マネジメントシステムの規格であるISO14001の認証取得数を見ると、1位が中国の136,715件、2位が日本の19,131件となっており、以下はイタリア、スペイン、イギリス、ドイツ、インド、フランス……と続きます。
いずれも中国の認証取得数が非常に高く、これは他国に比べて人口や企業の数が多いことも理由に挙げられるでしょうが、規格に対する中国企業の意識の高さが伺えます。また、環境に関する規格の認証取得数はヨーロッパ諸国が上位となっており、環境に対するヨーロッパの意識が垣間見えるランキングとなっています。
ISOの規格認証を取得しているのはアジア諸国が多く、欧米では認証を取得せずにISOに適合していることを自ら宣言する「自己適合宣言」を行っている企業も少なくないようです。
海外進出の際に重要視されるISO9001とは?
前項でも少し触れましたが、海外進出で重要視される品質マネジメントシステムの規格「ISO9001」についておさえておきましょう。
ISO9001とは品質の標準化に関する規格。わかりやすく言うと『よりよい製品やサービスを提供するための仕組みを評価するガイドライン』のことです。
製品やサービスの品質マネジメントシステムに関する規格であるISO9001が取得されていれば、マニュアルが作られ、記録が残されているので、誰が作っても同じ製品が出来ます。つまり、高い品質を保つことができるのです。
ISO9001は「製品やサービスの品質を継続的に改善し、顧客の要求に応えることで顧客満足を目指す」ことを目的に作られた規格です。
さて、そのISO9001ですが、2015年9月に各条項がより細かく、詳細に記述されるようになりました。なぜでしょうか?国際的なお墨付きであるISOは、取得だけを目的にする企業も多く、マーケティング目的で取得はしたものの、実際は中身のないISO9001が量産されてしまうという事態が起こったからです。
3. ISO認証のメリット
ここからはISO認証のメリットとデメリットについて、それぞれ見ていきましょう。まずはメリットから。
ISOのメリット
ISO認証を取得するメリットは、国際的なお墨付きを得られることだけではありません。ISOの取得にあたってルールの設定や、それをチェックし、さらによいものに改善していく仕組みが作られるというメリットもあります。
ISOのメリットはおもに下記の3つ。
・ルールとその改善の仕組みが作られる
・組織を管理する手順や役割が明確になる
・第三者に審査してもらっているお墨付きが得られる
メリット1: ルールとその改善の仕組みが作られる
ISOを構築した当初は、システムを構築することだけに必死になってしまい、なかなか効果を実感できないという声も多く聞かれますが、ISOは取得して終わりではなく「継続すること」がもっとも大切。継続することで効果が出る仕組みづくりですから、長期的な経営計画に基づいたマネジメントシステムを構築し、内部監査または第三者による審査を行うことで、継続的に改善を行うことができる企業風土を作っていきましょう。
ISOでは、組織としてのルールを作り、そのルールがしっかりと守られるよう、誰もが同じ手順で作業できるような「作業の標準化」を行います。
「作業の標準化」によって全員が同じ手順で効率よく作業できれば、時間や作業工程でそれまで生じていた無駄がなくなります。また、決められた手順と相違がないか、作業内容を確認する習慣ができるようにもなります。手順が決まっており、しっかりとしたマニュアルがあれば、入ったばかりの新入社員でも、ベテランと同様の作業を行うことができますし、これは教育を行う仕組みとして社内に構築することができます。
また、作ったルールをその通りに動かすだけではなく、不都合があれば見直したり、さらによくするためのルールはないかを継続的に確認したりすることで、業務事態の質や労働環境もさらによいものになっていきます。
メリット2: 組織を管理する手順や役割が明確になる
ISOは個人ではなく組織全体を管理するための仕組みづくり。手順を明確にし、マニュアルを作成することで、業務の手順だけでなく、個々の役割や責任、権限も明確になります。
「どこで」「誰が」「何をしているのか」が明確になれば、無駄がはっきりしますし、誰が何をしているか、何をすべきかがはっきりしていれば、社内コミュニケーションもスムーズになります。何が無駄かわかるので、文書などの管理も楽になります。
システムに沿って業務を行うことができるようになれば、トラブルが生じてもシステムとして解決しやすくなるため、ミスやクレームを人のせいにするのではなく、システムとして解決する手段を見つけようとするようになります。
メリット3: 第三者に審査してもらっているお墨付きが得られる
ISOの大きな特徴が「第三者による審査であること」です。企業にとって第三者であるISOの審査員に対して自社のルールを公開。そのルールをしっかりと遵守していることを示した結果が「認証」です。 この「認証」は「信頼の証」とも言えるでしょう。
大手企業は自社内で独自の管理システムを構築できますが、中小企業はなかなかそれが難しいため、取得によって企業の信頼を示すことができるISOは、中小企業にとっても強い味方です。
4. ISO認証のデメリット
続いては、ISO認証のデメリットについてです。
ISOのデメリット
マニュアルやルール策定など、とにかく記録することが多く、文書が増えるのはISOのデメリットと言えるでしょう。その他にも、下記のようなデメリットが考えられます。
・文書が増える
・これまでの仕組みとかけ離れ、混乱を生む可能性がある
・すぐに効果を感じにくい
デメリット1: 文書が増える
マニュアルやルールなど、作る文書が多く、また記録も取る必要があるため、とにかく文書が増える、という思いを現場に抱かせやすくなるのがISOのデメリットの一つ。でも、煩わしいと感じるのは、それまでに文書化の習慣がなかったからとも考えられます。
ISOのために作る文書や記録は、業務のために必要な文書ですから、既存のマニュアルなどを利用して、できるだけ現場の負担を減らしながら、できることから始めていきましょう。
デメリット2: これまでの仕組みとかけ離れ、混乱を生む可能性がある
これまで個人の能力や機転に依存した業務体制で動いていた場合、急にルールでがんじがらめになって社員がやりづらさを感じる、ということもあるでしょう。「業務の標準化」を行う目的は、誰がやっても同じ仕事を変わらない品質で行うことができるようにするため。それは組織のためであり、ひいては個人のためでもあります。
とはいえ、現在うまくいっているのであれば、変える必要性を感じないと思ってしまうのも当然のことです。ISOで高い目標を設定しすぎるのも社員のやる気を失わせる原因となってしまうので、理念に沿った現実的かつ具体的な目標を立て、組織全体のマニュアルとして「できる人」の手腕や方法を全員が共有し、発揮できるような仕組みを作っていきましょう。
デメリット3: すぐに効果を感じにくい
ルールとマニュアルを作っただけで今日から効果が出る、というケースは残念ながらほとんどないでしょう。大切なのは継続し、改善し続けること。認証を取得だけして満足してしまわないようにしましょう。
5. ISOマネジメントシステムの種類
ISOマネジメントシステムの種類にはいくつかの規格がある
ISOマネジメントシステム規格にはいくつかの種類があり、「9001」「14001」などの番号が振られています。ISOの種類は基本的には業種ではなく、目的で分類されていますが、特定の業種や製品に適用される「セクター規格」というものがあります。例えばISO9001のセクター規格としては、下記のようなものがあります。
・IATF16949(自動車)
・ISO13485(医療機器)
・JISQ9100(航空宇宙)
おもなISO及びマネジメントシステムの種類と目的
ISOにはさまざまな種類がありますが、おもなものを下記に記載します。
ISO 9001 (品質マネジメントシステム)
顧客に品質のよい製品やサービスを提供すること、すなわち『顧客満足』の向上。
ISO 14001 (環境マネジメントシステム)
会社を取り巻く地域の方々(利害関係者)のために環境に与える悪影響をなくすこと、すなわち『環境保全』。
ISO17025 (試験・校正機関)
試験所や校正機関が、正しい結果を生み出せるかどうかを認定。
ISO20000 (ITサービス)
ITサービスの内容やリスクを明確にする。また、効率性や改善の機会を作ること。
ISO 22000/FSSC 22000 (食品安全マネジメントシステム)
消費者にとって安全な食品を届けること。
ISO 22301(事業継続マネジメントシステム)
災害などが起こっても、事業が継続できるようにすること。
ISO 27001 (情報セキュリティマネジメントシステム)
情報の漏洩を防ぐこと。
ISO 39001(道路交通安全マネジメントシステム)
交通事故による死亡事故・重傷事故の発生を撲滅させること。
ISO 45001 (労働安全マネジメントシステム)
従業員が安全な労働環境の下で働けるようにすること。
ISO50001 (エネルギー)
エネルギー使用を効率化し、使用量を削減すること。
6. ISO認証の取得方法をステップ別に解説
ではいよいよISO認証の取得方法について解説します。各段階におけるステップ別に見ていきましょう。
■準備〜キックオフのステップ
●取得範囲を決定
取得範囲の定め方により、ISO構築の期間、マニュアルの内容などが異なるので、ISOをどこまで適用させるかを最初に明確にしておきましょう。これが明確になっていないと、構築を始めてから取得範囲を変更するということにもなりかねません。
●取得するISOを決定
目的と、そのために必要な規格を定めることで、取得するISOが明確になります。もちろん一つだけとは限りません。必要に応じて複数のISOを運用することもあります。
●ISO構築〜取得における担当者を決める
責任者を置き、プロジェクトメンバーを選出します。ISOの運用は会社全体で行うことですが、ISOシステムを構築し、マニュアルを作る作業を事務局が中心となって進めていきます。
●キックオフ
経営者がすべての従業員に対し「ISOを取得する」ことを宣言します。ISOは会社全体で取り組む大きなプロジェクトです。取得には長い期間がかかります。取得して終わりではなく、その後も「ISO認証を持つ企業」として維持・継続が必要ですから、このキックオフ宣言は、経営者と共に、すべての従業員に「ISOを取得する」意識を持たせるための大切な儀式だと言えます。
■構築のステップ
●ISOに関する知識を深める
社内で勉強会、研修等を開催し、ISO規格について知識を深めましょう。
●マネジメントシステムの構築
まずは現在の業務を見直します。社内にもともとある規定や、文書のテンプレート、フォームなどがあればそちらも確認し、管理方法も把握しておきます。
現状の業務手順についてヒアリングを行い、業務の流れを整理する必要があるでしょう。ISOの規格に沿ってそれをどのように改善すればよいかを考え、マニュアルを文書で作成しましょう。作成した文書をもとに仕事を行い、実務・システム両方を改善しながら書類の内容を見直します。
●マニュアルにもとづいて業務を行い、見直して改善
マニュアルができたらしばらくの間それを「試運転」してみましょう。マニュアルどおりにやってみると、意外とうまくいかないことが出てくるものです。「現場にそぐわない手順だった」「必要な事項が記載されていなかった」「このルールは必要なかった……」そんな意見が出てきたら、どんどんマニュアルを更新していきましょう。改善を重ねながら、より効率的で効果的な運用へとブラッシュアップしていきます。
また、マニュアルで規定した内容を遵守できるような社員教育も必要です。
●内部監査を実施する
内部監査員による内部監査を実施します。運用がマニュアルどおりかどうか、改善の効果が出ているかをしっかり監査しましょう。
●検証や改善を行う
データ分析やマネジメントレビューを行い、運用状況の検証や、効率的かつ効果的な改善を行います。また、マネジメントシステムを更新した際には効果を確認し、効果がある場合は文書を改定し、社内に定着させましょう。
■審査〜認証のステップ
さあ、いよいよ審査です。審査から認証までは、下記のような流れとなります。
第1段階審査
⇩
第2段階審査
⇩
認定証の発行
もちろん、認証されて終わりではありません。認定証発行後は毎年数回、社内において内部監査およびマネジメントレビューを行います。年1回の維持審査と3年おきの更新審査の2種類の審査があります。
それぞれの審査について詳しく見ていきましょう。
■第1段階審査(本審査)→ISO取得
第1段階審査は主に文書での審査ですが、訪問もあります。細かい部分を第2段階審査で見るために、審査する側が概況をつかむための審査です。
この審査では、対象の企業・組織がISO認証取得に向けて審査を受ける状況に達しているかどうかを全体的に判断されます。ここを通過できれば、本審査の第2段階審査に進むことができます。
書類やシステム自体の見直しを図る審査は数回行われ、6カ月~1年ほどかかります。
■第2段階審査
第1段階で問題があった場合、改善が済んだら本審査を行い、基準を満たしていれば登録申請を行います。申請が下りれば、晴れて「ISO取得認証」を名乗ることができます。
ちなみに、審査をする第三者機関と登録書を発行する組織は別の組織です。審査をする機関は「認証機関」、登録書を発行する機関は「認定機関」と呼ばれます。
第2段階審査は、ISOの要求にそった「運用」が出来ているかどうか、現場を中心に実地で確認される審査です。
オフィスや工場、店舗などに審査員が入り、ISOの要求事項すべてにおける運用の適切性、有効性を評価します。
この段階で不適合指摘が出た場合は、修正・原因究明・再発防止策を実施することになりますが、基準を満たしていると判断してもらえれば、登録申請を行います。申請がおりたらいよいよ、念願の「ISO取得認証」です。
■取得後
認証登録の有効期間は3年。ISO規格を維持するためには定期的な審査が必要です。認証登録後は、半年または1年ごとにISOを維持するための審査を受けなければいけません。この維持審査を「サーベイランス審査」と呼びます。また、3年ごとに受ける必要のある、システム改善などを含めた更新審査は「再認証審査」と呼ばれます。
7. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
今回は「ISOの基礎知識」として、ISOの基本情報に加え、海外ビジネスで「ISO認証」取得をする必要性や、ISO認証取得のメリット&デメリットについてについて解説しました。
取得が目的になりがちなISOですが、それぞれに明確な目的があり、目的のためにルールや仕組みを設けることで、業務の標準化を行い、業務を改善することができます。その結果、海外でも通用する評価を得ることができるのです。
国際的なお墨付きを得るためには、国際的な基準や評価について理解を深める必要がありますし、ISO認証を得るまでに作成する文書の量や、準備だけでも数ヶ月かかることを考えると、社内に知識を持った社員がいない場合はかなり大変な業務となります。まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
「Digima〜出島〜」には、厳選な審査を通過した、様々な支援を行う優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。
「海外へ進出したいが何から始めていいのかわからない」「自社商品・サービスが海外現地でニーズがあるかどうか調査したい」「海外進出の戦略立案から拠点設立、販路開拓までサポートしてほしい」「海外ビジネスの事業計画を一緒に立てて欲しい」…といった海外ビジネスにおける様々なご質問・ご相談を承っています。
ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、御社にピッタリの海外進出サポートサポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
もっと企業を見る

海外進出・海外ビジネスで
課題を抱えていませんか?
Digima~出島~では海外ビジネス進出サポート企業の無料紹介・
視察アレンジ等の進出支援サービスの提供・
海外ビジネス情報の提供により御社の海外進出を徹底サポート致します。
0120-979-938
海外からのお電話:+81-3-6451-2718
電話相談窓口:平日10:00-18:00
海外進出相談数
22,000件
突破