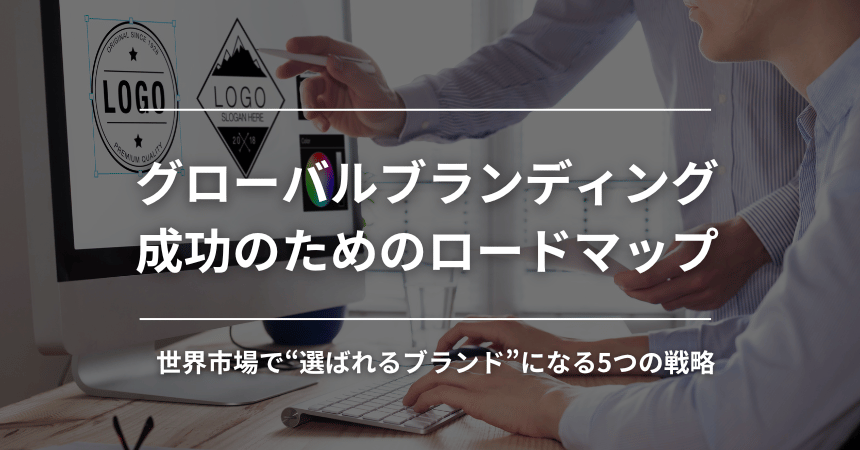食品輸出の基礎知識-日本の食品輸出国・品目別ランキングも併せて解説

「食品輸出の基礎知識」として、食品輸出の手続きの流れ、食品輸出に関する規制、輸出の種類や輸出免税といった、食品の輸出に関して事前に知っておくべきことをわかりやすく解説します。
また、2022年の日本における食品・農林水産物の輸出額総額は過去最高の1兆4,148億円となりました。上記解説にあわせて、農林水産省が発表している「2022年度の食品・農林水産物の輸出額&品目別内訳の国・地域別ランキング」もご紹介します。
ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」。農林水産省と外務省の調査によると、海外の日本食レストラン数は、2019年の時点で約15.6万店。2017年の約11.8万店から3割増でした。また、2021年の海外における日本食レストランは、2019年の約15.6万店から微増の約15.9万店。いずれにせよ日本食や日本の食材は海外でも大人気と言えるでしょう。
2020年6月には、日本政府は新型コロナウイルスが世界に及ぼす影響を踏まえ、家庭向け食品の輸出を強化する方針を示しました。今後、インターネットを活用した販促を重視し、オンライン商談会や越境ECなどを活用できる環境整備を進めていく方針です。
さらに日本政府は農林水産物・食品の輸出額を2030年までに5兆円にする目標を掲げており、日本からの食品の輸出は今後も成長が見込める分野であることは間違いありません。
Photo by Liz Caldwell on Unsplash
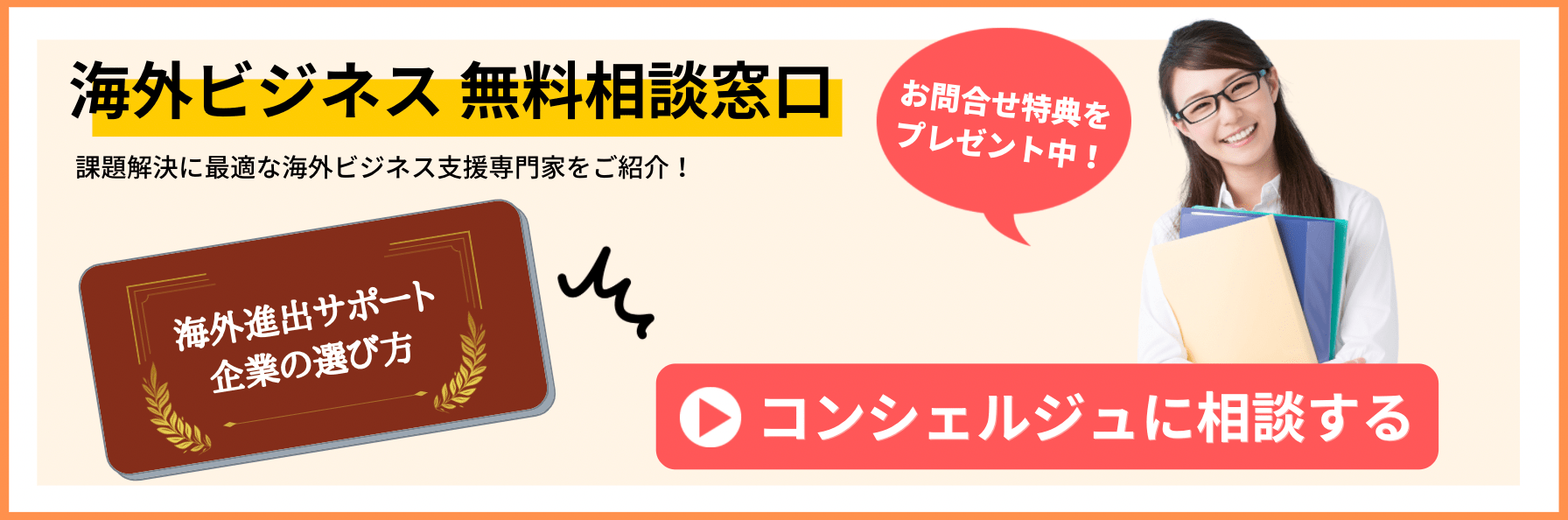
▼食品輸出の基礎知識-日本の食品輸出国・品目別ランキングも併せて解説
- 1. 食品輸出の手続きの流れ
- 2. 食品輸出・農林水産物の輸出に関する規制について
- 3. 輸出の定義と輸出免税について
- 4. 海外へ輸出する際の「モノの流れ」と「輸出(貿易)の種類」
- 5. 食品の輸出に関して事前に知っておくべきこと
- 6. 食品・農林水産物の輸出額&品目別内訳|国・地域別ランキング
- 7. 日本企業の輸出入・貿易・通関に関するトレンド【2022年度】
▼アナタの海外ビジネスを成功させるために
1. 食品輸出の手続きの流れ
食品輸出手続きの大まかな流れ
さっそく食品輸出の手続きの流れについて見ていきましょう。
大まかな流れとして、食品を輸出する際の手続きは、おもに下記のような順番で進めていきます。
① 輸出国を決定するための調査
↓
② 輸出計画の策定
↓
③ 輸出に取り組むための体制の整備
↓
④ 事業パートナーの選定
↓
⑤ 輸出国での販売継続方法の検討
以上を踏まえて、それぞれの手続の内容を確認していきましょう。
① 輸出国を決定するための調査
食品の輸出を考えるのであれば、輸出する国の選定や販路を開拓していく方法だけでなく、どんな商品がどれくらいの価格帯で売れるのかもしっかり調査しておく必要があります。まずは農林水産省、JETRO、中小機構等のホームページの情報を調べてみましょう。
展示会やイベントなどへの参加も有効な情報源となりますが、新型コロナウイルスの感染状況によっては展示会やイベントの開催自体が難しいケースもありますので、オンラインで開催されているものがないか、探してみるのもオススメです。
イベントや展示会などに参加する際には、現地の情報をできるだけ得るようにすると良いでしょう。小売の状況や飲食店の状況、消費者の好みなどを知ることができれば、輸出の際の商品選定や価格設定、販促を考えるのに役立ちます。
相手国・地域の特徴を調査することができたら、輸出条件を調査します。動植物検疫、衛生証明、関税などの輸出条件について調べましょう。
② 輸出計画の策定
輸出する食品の輸出プランを策定します。適合性の検討、輸出先の国やターゲットとなる顧客層を決定し、事業パートナーが必要かどうかも検討します。
商品の強みを明確にし、輸出時期、検疫手続き、輸送方法、価格・数量など、具体的な計画を立てます。また、知的財産権の管理も大切です。海外で販売を計画する際には、他社から商標出願されていないかあらかじめ確認し、輸出先に対して商標等を出願、登録しておきましょう。
③ 輸出に取り組むための体制の整備
社内での貿易実務の担当を決め、輸出計画に対応できるような生産体制を整えましょう。輸出を継続して行うなら、原材料や生産設備を確保し、安定した生産体制は必須です。
④ 事業パートナーの選定
生産者が輸出にかかわるすべての業務を行うのはなかなか大変です。国内の輸出業者や、輸出先の輸入業者・卸売業者などを事業パートナーとして活用するとさまざまな取引がスムーズに進みます。
⑤ 輸出国での販売継続方法の検討
安定した販路として輸出を継続していくためには、信頼できる事業パートナーとより良い関係を構築することが必要です。本格的に輸出を始める前に、試験輸出も必ず行うようにしましょう。
…大前提として、輸出の手順・管理などは、定期的に見直し・改善を行うべきです。法令などが変わる場合もありますので、輸出に関する情報も定期的にチェックすることが大切です。
2. 食品輸出に関する規制について
輸出先国によって必要な書類や手続きは異なる
日本企業が海外への食品輸出を検討している場合、多くの手続きや証明書が必要となります。以下に、一般的に考慮すべき手続きや証明書に関する情報を示しますが、輸出先国によって必要な書類や手続きは異なることもありますので、該当する国や地域の公式情報をご参照ください。
■食品の輸出に関する手続き・証明書の一般的な概要
・輸出通関手続き:
商品の出荷時に税関に提出する書類が必要となります。これには、輸出貨物の内容や数量、価格等の情報が詳細に記載される「輸出貨物の通関申告書」が含まれます
・衛生証明書:
多くの国では、食品の輸入時に衛生状態を証明する書類が必要です。日本の場合、都道府県の指定検査機関で取得することができます。
・原産地証明書:
一部の国では、関税優遇や規制対応のために、商品の原産地を示す証明書が必要となる場合があります。
・品質証明書:
品質や成分を証明するための書類。一部の国では必要とされます。
・成分表示 / ラベリング:
輸入国の規制に従って、食品の成分、栄養成分、アレルギー情報等の表示が必要です。
以下は、農林水産省による、農林水産物・食品輸出の際に要求される可能性のある手続きや証明書等をまとめた表になります。

※出典:
「日本国内の輸出に係る制度 / 農林水産物・食品輸出の際に輸出国政府当局が要求する可能性のある証明書等について」農林水産省
3. 輸出の定義と輸出免税について
続いては、改めて「輸出の定義」と「輸出免税」についても理解しておきましょう。
国内で消費されるものに対しては消費税が課されることはご存じだと思います。それに対して、外国で消費されるものには課税しないという考えがあります。つまり輸出に対しては消費税が免除されるのです。以下よりそれぞれについて見ていきましょう。
■輸出の定義について
一般的に「輸出」とは、国内から外国へ商品を売り外貨を得る取引のことを言いますが、関税法における輸出の定義は、関税法2条によると「内国貨物を外国に向けて送り出すこと」とされています。
内国貨物とは、「現在、日本国内に存在するもの」のこと。日本国内に存在している時点で内国貨物なので、海外から送られてきて輸入許可を得たものも内国貨物に含まれます。
それ以外は全て外国貨物となります。
■輸出免税について
先述したように、輸出は輸入とは異なり、関税がかかりません。輸出取引は消費税が免除となるため、輸出のための仕入商品や、輸出業務、事業にかかった諸経費への国内消費税を、所轄の税務署長に申請することで還付を受けることができます。
4. 海外へ輸出する際の「モノの流れ」と「輸出(貿易)の種類」
続いては、輸出の際の「モノの流れ」と「輸出(貿易)の種類」について解説します。
■輸出時のモノの流れ
輸出時の流れは、図で示すと以下のようになります。
の流れ.png)
基本的に貿易には3つの流れがあるとされており、ひとつめが「お金」、ふたつめが「モノ」、みっつめが「書類」(貿易に必要な手続きの書類や船積み書類など)となっています。
いずれにせよ、貿易においては、商品の紹介から受け渡しまでの間で、たくさんの人たちがそれらの流れに関わります。
輸出(貿易)の種類 | 直接貿易と間接貿易について
続いて輸出(貿易)の種類ですが、輸出の形態には2種類あり、直接貿易、間接貿易と呼ばれるものがあります。それぞれの違いを見ておきましょう。
■直接貿易
輸出にかかわる業務をすべて自社で行うのが直接貿易です。
海外買主との交渉や売買契約から、通関手続き、運送、決済に至るまで、自社で行うことで仲介にかかる手数料が一切かかりません。その分利益が増えますし、コスト削減にもつながります。ただし、資金負担や為替に関するリスクもすべて、自社で負うことになります。
■間接貿易
手続きを代行してもらうのが間接貿易です。
国内の代理店や商社に代行してもらうため、国内の取引で輸出手続きが成立します。代行には仲介手数料などが発生しますが、専門家にお願いできるので、プロの持つさまざまな情報やネットワークを利用することができます。
5. 食品の輸出に関して事前に知っておくべきこと
食品の輸出は事前に確認する項目が多く規制も厳しい
このセクションでは「食品の輸出に関して事前に知っておくべきこと」について解説します。
そもそも食品の輸出は、ほかの製品などと比較して、事前に確認する項目が多く、規制も厳しいです。なぜなら、食品は国民の健康に関わる大切なもの。世界のどの国においても、食品以外の商品と比べて通関手続きは厳しいものとなっています。先進国と呼ばれる国では特に食品の安全に対する規制が厳しい傾向にあり、輸出先である国の規制要件を満たさないと取引はできません。
輸出の際は通関手続き等に必要な書類をしっかり確認し、用意しなければなりません。食品に関する国際的な基準には、CODEX、HACCP、FDAなどがあります。以下、順を追って簡潔に説明していきます。
※参照:
『コーデックス規格の特徴』厚生労働省
CODEX(コーデックス)
FAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)によって合同で設立された食品規格委員会(コーデックス委員会)が策定している、世界的な食品規格のことです。
コーデックス委員会で作られる食品の国際規格・基準には、大きく分けて2タイプあります。
ひとつは農畜産物の生産段階から消費者の食卓に並ぶまで、全ての段階で守られるべき安全に関する基準。もうひとつは、食品の品質に関する規格。この品質規格は、国同士で公正な貿易を促進するために必要と考えられています。
例えば、ある特定の食品に含まれるべき成分とその量などが当てはまります。また、製造方法、その内容を表示に関する指針、検査方法、これらの食品貿易に必要な輸出証明の方法・手続きなども策定されています。
つまり、各国の政府は、自国のp食品規格を策定する際にコーデックスを意識する必要があるのです。ですから生産者としても(そして消費者としても)、食品を輸出する際は、生産者としてコーデックスについて大まかな知見を持っておく必要があると言えるでしょう。
HACCP(ハサップ)
元々はアメリカのNASAにおいて宇宙食の安全性を確保するために考案された、食品の安全性を確保するための衛生管理の手法。こちらもCODEXと同じく、コーデックス委員会から発表されています。
日本でも、2018年6月に可決した改正食品衛生法によって、食品を扱う全事業者に対し、HACCPによる衛生管理の義務化が2020年6月より行われることとなりました。2020年の法律施行から1年間は猶予期間となっており、HACCPの完全制度化が開始するのは2021年6月からとなっています。
すでにヨーロッパやアメリカでは90年代からHACCP義務化の動きがあり、ヨーロッパも2006年から完全義務化を実施しています。
日本からそのような諸外国へ食品を輸出する際は、このHACCPの認証を取得することで、海外の企業に対して「国際基準の衛生管理」を行っていることをアピールすることができます。
FDA(エフディーエー)
FDAとは、元々はアメリカのNASAにおいて宇宙食の安全性を確保するために考案された、食品の安全性を確保するための衛生管理の手法。こちらもCODEXと同じく、コーデックス委員会から発表されています。
FDAは1906年に設立された、日本でいう厚生労働省に似た役割を持つ公的機関であり、食品、医薬品や医療機器、化粧品などの販売・流通において、許可や違反品の取り締まりといった行政を専門的に行っています。
仮にFDAの認証が必要な食品を、FDA認証を取得せずにアメリカへ輸出してしまうと、最悪の場合、懲役を伴う刑罰が課せられることもあります。そうならないためにも、アメリカへの食品輸出を考えている場合は、FDAについて知っておくことが重要なのです。
その他
EUや米国が受け入れを原則禁止している食品として、陸上動物の肉類やその加工品が挙げられます。これは中国や東南アジア諸国も同様です。
輸出畜産物の検査は、輸入検査対象(指定検疫物)のうち、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に規定される野生動物由来製品の他、相手国(輸出先の国)が家畜の伝染性疾病を拡散するおそれの有無についての輸出国政府の証明書を要求しているものに対して実施されます。
相手国が日本の畜産物等の輸入を停止している場合には、輸出検疫証明書の交付はできません。
検査の対象となるものは、相手国が輸入にあたって輸出国に対し、家畜の伝染性疾病を拡散するおそれのない旨の証明を要求しているもの、輸出に当たり農林水産大臣が国際検疫上必要と認めて指定するものが対象となります。
『輸出畜産物の検査手続』動物検疫所
6. 食品・農林水産物の輸出額&品目別内訳 | 国・地域別ランキング
2022年の日本における食品・農林水産物の輸出額総額は過去最高の1兆4,148億円
続いては、農林水産省による『2022年の農林水産物・食品の輸出実績』から、食品・農林水産物の輸出額を品目や国・地域別に見ていきましょう。

2022年の日本における食品・農林水産物の輸出額総額は、過去最高の1兆4,148億円でした。前年比14.3%で増加しており、額では1,766億円の増加となりました。
■農産物、林産物、水産物及び少額貨物の実績額
・農産物:8,870億円(対前年比+10.3%)
・林産物: 638億円(対前年比+11.9%)
・水産物:3,873億円(対前年比+28.5%)
・少額貨物:767億円(対前年比+1.5%)
以降より、それらの内訳を、国・地域別および品目別に見ていきましょう。
食品・農林水産物の国・地域別ランキング
 ・1位:中国 2,783億円(+25.2%)
・1位:中国 2,783億円(+25.2%)
・2位:香港 2,086億円(-4.8%)
・3位:アメリカ 1,939億円(+15.2%)
・4位:台湾 1,489億円(+19.6%)
・5位:ベトナム 724億円(+23.8%)
・6位:大韓民国 667億円(+26.6%)
・7位:シンガポール 562億円(+37.3%)
・8位:タイ 506億円(+14.9%)
・9位:フィリピン 314億円(+51.6%)
・10位:オーストラリア 292億円(+27.1%)
・ - :EU 680億円(+8.2%)
※( )内の数値は対前年比増減率
国別で見ると中国がもっとも多く1位、香港が2位、3位がアメリカとなっています。前年比で見ると、1位の中国が25.2%増加、2位のアメリカが15.2%増加しているのに対して、3位の香港がトップ10ヵ国の中で唯一4.8%減少しています。
全体としては、アメリカ以外はトップ10の全てがアジア・オセアニア地域となっており、EUは680億円となっています。
食品・農林水産物の品目別ランキング

■大分類ランキング
1位:農産物:8,870億円(対前年比+10.3%)
2位:水産物:3,873億円(対前年比+28.5%)
3位:林産物: 638億円(対前年比+11.9%)
上記をさらに分別すると、下記のようなランキングとなっています。
■品目別ランキング
1位:農産物(畜産物):126,827百万円(対前年同期比 +11.3%)
2位:農産物(その他農産物):123,612百万円(対前年同期比 +4.9%)
3位:農産物(加工食品):505,167百万円(対前年同期比 +9.9%)
4位:水産物(水産物<調整品除く>):300,448百万円(対前年同期比 +28.7%)
5位:水産物(水産調整品):86,878百万円(対前年同期比 +27.8%)
6位:農産物(野菜・果物等):68,702百万円(対前年同期比 +20.6%)
7位:林産物(林産物):63,761百万円(対前年同期比 +11.9%)
8位:農産物(穀物等):62,696百万円(対前年同期比 +12.2%)
※出典:
『2022年の農林水産物・食品の輸出実績」について』 農林水産省
7. 日本企業の輸出入・貿易・通関に関するトレンド【2022年度】
日本企業の「輸出入・貿易・通関」はコロナ禍に加速
最後に本稿のメインテーマ「食品輸出の手続き・規制」の補足情報として、「日本企業の輸出入・貿易・通関に関するトレンド」をご紹介します。
毎年、海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima~出島~」では1年間の進出相談と海外進出企業ならびに、海外進出支援企業を対象に実施したアンケートをもとに「海外進出白書」を作成しています。

上記が「Digima~出島~」寄せられた海外進出相談全体の「業種別割合」「相談内訳」となります。
右のグラフの相談内容別の割合を見てみると、海外進出の主な目的はマーケット開拓となっており、「販路拡大(営業代行・販売代理店探し)」に関する相談が最も多く寄せられていますが、僅差の2番手で「輸出入・貿易・通関」がランクインしています。1位2位ともにマーケット開拓に関連が深い相談となっています。
コロナ禍後「輸出入・貿易・通関」は海外への販路開拓の動きが加速するとともにニーズを高めており、2020年度:8%→2021年度:12%→2022年度:14%と、「販路拡大(営業代行・販売代理店探し)」に迫っています。
上記の内容をさらに深掘りした日本企業の海外進出動向を「海外進出白書」にて解説しています。
『海外進出白書(2022-2023年版)』には、日本企業の海外進出動向の情報以外にも、「海外進出企業の実態アンケート調査」「海外ビジネスの専門家の意識調査」など、全117Pに渡って、日本企業の海外進出に関する最新情報が掲載されています。
下記のバナーより「海外進出白書(※PDFデータ(A4サイズ)/全117Pの大ボリューム!)」無料ダウンロードが可能です。

8. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
食品の輸出は、規制緩和や決済の簡素化などで手続きが以前より簡単になったこと、昨今のインターネットの普及により、海外の情報も得やすくなったことなどから、最近は間接貿易よりも直接貿易を選ぶ企業も増えてきました。
とは言え、間接貿易もまだまだ利用されています。専門家が持っている最新の情報やネットワークを利用できるのが間接貿易のメリット。直接貿易にするか、間接貿易にするか、事業パートナーの選定など、考えることはたくさんあります。まずは信頼できる専門家に相談してみることもおすすめします。
「Digima〜出島〜」には、厳正な審査を通過した、様々な支援を行う優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。当然、複数の企業の比較検討も可能です。
「海外へ自社の加工食品を輸出したい」「進出先の現地物流に必要な費用が知りたい」「海外へ農産物を輸出したい」…といった多岐に渡る海外進出におけるご質問・ご相談を承っています。
ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、御社にピッタリの輸出入・貿易・通関サポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
もっと企業を見る