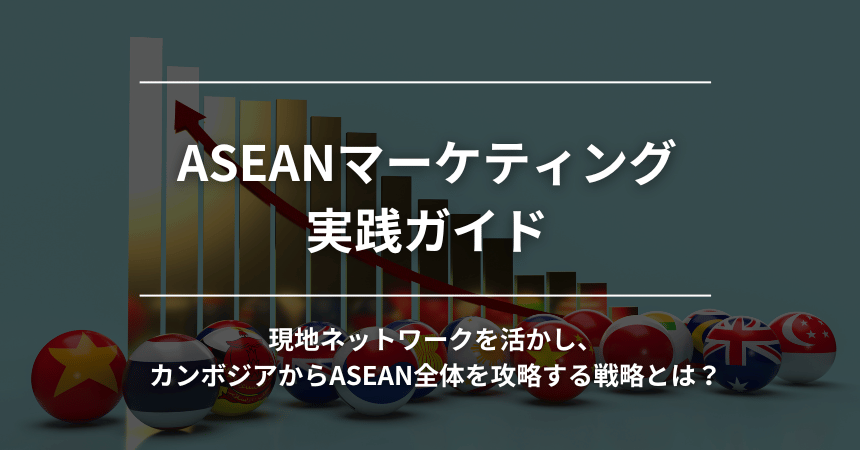外国人を採用するには? 企業が知っておくべき基礎知識と実務対応

近年、日本の企業にとって外国人材の採用はますます重要なテーマとなっています。特に中小企業やサービス業、製造業では、日本人労働者の確保が難しくなっており、外国人採用は選択肢の一つから「必要不可欠な手段」へと変わりつつあります。
総務省のデータにおいても、日本の労働人口は減少傾向にあり、特に若年層の働き手が不足しています。一方で、政府は外国人労働者の受け入れ制度を拡充し、特定技能制度の導入や高度人材の受け入れを積極的に推進しています。こうした背景から、多くの企業が外国人材を採用し始めており、実際にその効果を実感している事例も増えてきました。
外国人を採用することで、単に人手不足を補うだけでなく、新しい視点や発想を取り入れることができます。例えば、海外市場への展開を視野に入れている企業にとっては、外国人社員が持つネットワークや語学力が強みとなるでしょう。また、社内の多様性が高まることで、新しいアイデアやイノベーションの創出にもつながる可能性があります。
しかし、外国人材の採用には、在留資格や法的手続き、定着支援など、企業側が理解しておくべきポイントが多く存在します。本記事では、外国人採用に必要な基礎知識と実務対応について詳しく解説し、企業がスムーズに採用プロセスを進めるための情報を提供します。
▼ 外国人を採用するには? 企業が知っておくべき基礎知識と実務対応
外国人採用の主な方法と雇用形態
外国人を採用する際には、どのような雇用形態が適しているのかを明確にすることが重要です。企業のニーズや採用目的に応じて、最適な形態を選ぶ必要があります。雇用形態には、正社員・アルバイト・技能実習生・特定技能・派遣労働者など さまざまな選択肢があり、それぞれの制度や条件を理解することが、スムーズな採用のカギとなります。
1. 正社員としての採用(技術・人文知識・国際業務など)
企業が外国人材を正社員 として採用する場合、主に「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」などの在留資格を持つ外国人が対象となります。これは、主にホワイトカラー職(エンジニア、通訳、貿易業務、マーケティングなど)で活躍する外国人向けの資格であり、日本の専門職市場での需要が高まっています。
この形態のメリットは、安定した労働力の確保と企業への貢献度が高いこと です。特に、外国語スキルや異文化理解を活かした業務(海外営業、貿易実務、多言語カスタマーサポートなど)では、外国人社員が大きな力を発揮することが期待されます。
一方で、在留資格の取得・更新の管理や、日本語能力の差によるコミュニケーションの課題など、企業側のサポートが求められる場面もあります。そのため、企業が外国人社員の成長を支援する仕組みを整えることが、長期的な定着につながるポイント となります。
2. アルバイト・パートとしての採用(留学生・家族滞在など)
飲食店、コンビニ、ホテル、工場などの業種では、外国人アルバイト の活用が進んでいます。特に、留学生や家族滞在の在留資格を持つ外国人は、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内(長期休暇中は週40時間) の範囲でアルバイトが可能です。
この形態のメリットは、短期間で採用できることや、人手不足を補う即戦力になりやすいこと です。特に、都市部の飲食業や接客業では、英語や中国語などの外国語対応ができる外国人アルバイトが重宝されています。
しかし、留学生の場合、卒業後は正社員雇用を希望するケースが多いため、長期雇用には適していません。また、労働時間の制約や在留資格の更新手続きが必要になるため、企業側は適切な管理が求められます。
3. 技能実習生の受け入れ(建設・製造・農業など)
技能実習生制度は、発展途上国の人材が日本の技術を学び、母国へ持ち帰ることを目的とした制度 です。農業、漁業、建設業、食品製造業、繊維業など、日本の労働力不足が深刻な分野で多く採用されています。
技能実習生の受け入れには、監理団体を通じた制度利用が必要 であり、企業単独での受け入れはできません。最長5年間の滞在 が可能ですが、制度の本来の目的は「技術移転」であるため、実習期間が終了すると帰国しなければなりません。
メリットとしては、一定期間の安定した労働力の確保 が可能である点が挙げられますが、一方で、日本語の習得や生活支援が必要なため、企業側のサポート体制が求められます。また、不適切な労働環境を提供すると、問題が発生するリスクがあるため、適切な管理と法令遵守が不可欠です。
4. 特定技能の活用(即戦力となる外国人採用)
特定技能制度 は、日本国内の人手不足を解消するために導入された制度であり、14の産業分野(外食、宿泊、介護、建設、製造業など) で即戦力となる外国人を雇用することが可能です。
特定技能1号の外国人は、最長5年間の就労が可能 であり、試験に合格することで日本での就労が認められます。また、特定技能2号に進めば、在留資格の更新や永住申請も可能 になるため、企業にとって長期的な人材確保の手段となります。
技能実習生制度と異なり、特定技能は「労働力確保」を目的としているため、帰国義務がなく、即戦力として活躍できることが大きなメリット です。しかし、特定技能の取得には業種ごとの試験合格が必要 であり、企業側は適切なサポートを提供する必要があります。
5. 派遣・業務委託による外国人の活用
企業が直接雇用するのではなく、人材派遣会社や業務委託を通じて外国人材を活用する方法 もあります。特に、製造業やIT業界では、外国人エンジニアや専門職を派遣社員として採用するケースが増えています。
この形態のメリットは、企業側の手続き負担が少なく、必要なスキルを持つ人材を迅速に確保できる点 です。特に、在留資格の管理や労務管理の一部を派遣会社が担うため、初めて外国人採用を行う企業にとってはリスクが少なくなります。
一方で、長期雇用を前提とした人材育成には適していないため、将来的な正社員登用の可能性を視野に入れた戦略的な採用計画が必要 となります。
在留資格とは? 採用時に必要な基礎知識
在留資格とは何か? 外国人が働くための前提条件
日本で外国人を採用する際にまず押さえておくべきなのが「在留資格」です。在留資格とは、外国人が日本に滞在し、活動する内容を法的に認めるもので、これがなければ就労は認められません。つまり、在留資格の内容によって、どのような職種で働くことができるかが厳格に決まっているのです。企業が外国人を採用する際には、その業務内容が在留資格の範囲に合致しているかを確認しなければなりません。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人は、エンジニアや通訳、営業、マーケティングなどのいわゆるホワイトカラー職での就労が認められています。一方で、清掃や単純作業と見なされる業務は、この在留資格では原則として就労不可です。このように、在留資格に合致しない業務を命じると、企業側も違法行為とされ、処罰の対象になる恐れがあるため、特に注意が必要です。
主な就労可能な在留資格と特徴
外国人の就労に関係する主な在留資格には以下のようなものがあります。
技術・人文知識・国際業務
- 外国の大学を卒業し、日本の企業でエンジニア、通訳、貿易業務、マーケティングなどの業務に従事するケースに該当します。文理問わず幅広い業種で活用されており、国内在住の留学生の多くがこの資格に移行して就職します。
高度専門職
- より高い専門性が求められる業務に従事する外国人向けの資格で、在留期間の優遇や配偶者の就労許可、永住申請の簡素化など、多くの優遇措置があります。
特定技能(1号・2号)
- 人手不足が深刻な14分野(介護、外食、建設、農業など)で働くことができる比較的新しい制度です。1号では最長5年まで滞在可能ですが、2号へ移行できれば家族の帯同や長期在留も可能になります。
技能実習
- 発展途上国の人材に対して日本の技術を移転することを目的とした制度。建設や製造など、実習が制度の本旨であるため、就労との位置づけはやや異なります。
留学・家族滞在(資格外活動)
- 留学生や家族滞在中の外国人がアルバイトとして働くには、「資格外活動許可」を得る必要があります。就労時間は原則として週28時間までと定められています。
採用にあたっての在留資格の確認・変更・管理
企業が外国人を採用する場合には、在留カードやパスポートを確認し、現在の在留資格が就労を許可しているかを必ずチェックする必要があります。特に、在留期間や就労可能な活動内容を把握し、実際に従事させる業務との整合性を取ることが重要です。
また、内定を出した後、外国人が現在の在留資格で就労できない場合には「在留資格の変更申請」が必要になります。たとえば、大学卒業予定の留学生を正社員として採用する際には、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請を行います。この手続きは本人が行うものですが、企業側で必要な書類(雇用契約書、会社案内など)を用意してサポートすることが求められます。
さらに、在留資格には「期限」があるため、定期的に在留カードの有効期限を確認し、更新の時期が近づいた場合は従業員に声をかけ、必要な対応を促す体制も重要です。更新を怠ると不法就労となり、企業にも罰則が課されるリスクがあります。
採用時に企業が行うべき手続きと注意点
採用時に必要な手続きの全体像
外国人を採用する際には、通常の日本人採用とは異なる法的手続きが発生します。最も重要なのは、在留資格の確認と就労内容との整合性です。採用時に企業がまず行うべきは、本人が保有している在留資格が採用予定の職務内容に適合しているかを確認することです。在留カードには、在留資格の種類や在留期間が記載されており、それを基に判断します。
また、在留資格が適合していても、滞在期限が迫っている場合には更新の手続きが必要です。更新は本人が申請するものですが、企業は必要書類(雇用契約書、会社概要、職務内容説明書など)の作成協力を求められます。採用前後でビザ(在留資格)の変更が必要となる場合もあり、手続きに要する期間(通常1~2カ月)を考慮して採用スケジュールを組む必要があります。
雇用契約と労働条件通知書の整備
外国人に限らず、労働者を雇用する際には、労働基準法に基づいて労働条件を明示しなければなりません。特に外国人労働者に対しては、日本語が母語でないことを踏まえ、契約内容をできるだけ平易な言葉で説明し、理解を得た上で締結する ことが重要です。必要に応じて英語版の契約書を併記したり、通訳者を通じて説明を行うことも効果的です。
また、企業は労働条件通知書を交付し、就業時間、給与、休日、業務内容などを明確に記載する必要があります。日本では当たり前とされる労働慣行が外国人にとっては不明瞭なこともあるため、事前に丁寧な説明を行い、入社後のミスマッチを防ぐ工夫が求められます。
入国管理局およびハローワークへの届出義務
企業が外国人を採用した場合、「外国人雇用状況の届出」 をハローワークへ提出する義務があります。この届出は、在留資格を保有するすべての外国人労働者に対して義務付けられており、採用時と離職時に届け出る必要があります。届出を怠った場合、企業には罰則が課される可能性があるため、確実な対応が必要です。
また、在留資格の変更や更新を行う場合は、本人が入国管理局に申請を行いますが、企業も協力書類の提出を求められます。たとえば、「雇用理由書」「会社案内」「職務内容説明書」などが一般的です。書類の不備や不明瞭な職務内容は審査の遅れや不許可の原因となるため、注意が必要です。
違法就労を防ぐためのポイント
外国人の就労において、企業が特に留意しなければならないのが「違法就労の未然防止」です。在留資格の範囲外での就労、在留期間満了後の就労継続、あるいは不法滞在者の雇用は、雇用主である企業にも重大な責任が問われます。雇用主は違法就労助長罪に問われる可能性があり、罰金刑や企業の社会的信用の失墜といった大きなリスクを背負うことになります。
このリスクを避けるためにも、企業側は定期的に従業員の在留カードの有効期限や在留資格の内容を確認し、更新が近い場合には早めに本人に対応を促す体制を整えておくことが重要です。また、在留カードの偽造も問題になっているため、出入国在留管理庁のウェブサイトを活用した「在留カード等番号失効情報照会」 で真正性の確認を行うことも有効です。
外国人採用のメリットとリスク
外国人採用のメリットとは? 企業にもたらすプラスの要素
外国人材の採用は、人手不足の解消という側面だけではなく、企業の成長や競争力向上にも大きく寄与する可能性があります。たとえば、グローバル展開を目指す企業にとっては、外国人材の語学力や異文化理解、母国とのネットワークなどが新たな市場開拓の原動力となります。現地の消費者感覚を持った人材を商品開発やマーケティングに活かすことで、これまでにない視点からの提案や改善が期待できるでしょう。
また、社内の多様性が高まることで、組織内に刺激が生まれ、既存の社員にも良い影響を与えることがあります。異なる文化や価値観を持つ人材と共に働く経験は、チームの柔軟性や課題解決力を高め、ひいては組織のイノベーションを促進する要因ともなり得ます。
加えて、外国人材は日本での就業に対する意欲が高いことが多く、与えられた役割に対して真摯に取り組む傾向があります。責任感を持って仕事に取り組む姿勢は、長期的な定着にもつながりやすい傾向があります。特に、キャリア志向が強い高度外国人材にとっては、企業が成長機会や働きやすい環境を提供できれば、ロイヤリティの高い社員となる可能性も高いです。
採用リスクと事前に押さえておくべき課題
一方で、外国人採用にはいくつかのリスクや課題も伴います。最も多く聞かれるのが、言語や文化の違いによるコミュニケーションの難しさです。日本語能力が十分でない場合、指示が正確に伝わらず業務効率に影響を及ぼしたり、同僚との意思疎通に支障が出ることもあります。また、間接的な表現や曖昧さを重んじる日本の職場文化が、外国人には理解しにくいという点も指摘されています。
さらに、在留資格の期限管理やビザ更新のサポートといった、企業として対応しなければならない行政手続きもあります。これらは通常の日本人採用にはない業務であるため、担当者が制度に不慣れな場合、見落としやミスが発生するリスクがあります。とくに、在留資格の範囲外での業務従事が認められた場合、企業にも法的な責任が生じるため、慎重な運用が求められます。
また、外国人材の中には「母国での就職を目指すまでの一時的な滞在」と考える人もおり、短期での離職につながることもあるため、定着支援の仕組みを整えておくことが望まれます。言語研修、生活支援、社内コミュニケーションの強化など、受け入れ後のケアは採用成功のカギとなる要素です。
メリットを活かし、リスクをコントロールするために
外国人採用を成功させるには、単に人を採るだけでなく、採用後の環境づくりや支援体制の整備が不可欠です。言語研修や生活ガイダンス、日本企業のマナーや文化に関する研修などを行うことで、入社後の定着率や業務遂行能力を高めることができます。さらに、先輩社員によるメンター制度の導入や、定期的な面談を通じて不安や悩みを吸い上げる取り組みも有効です。
企業としては、リスクをゼロにすることはできなくとも、事前に課題を予測し、仕組みでフォローすることで、外国人採用を確実に事業の成長へとつなげていくことができます。次の章では、こうした受け入れ体制の具体的な整備方法や定着支援策について、さらに詳しく見ていきます。
定着率を高める受け入れ体制と支援の工夫
定着のカギは「職場外」まで見据えたサポート体制
外国人を採用する際、採用活動そのものよりも、その後の「定着支援」のほうが重要だと感じる企業は少なくありません。せっかく採用しても、数カ月で離職してしまっては意味がなく、継続的に活躍してもらうためには、入社後の生活・業務・人間関係の不安を取り除く体制が不可欠です。
特に初めて来日する外国人にとって、日本での生活は戸惑いの連続です。住居探し、役所での手続き、銀行口座や携帯電話の契約など、生活の基盤を整える段階でつまずくことも少なくありません。企業がこうした手続きを丁寧にサポートすることで、安心して業務に集中できる環境が整い、早期離職のリスクも大きく低減されます。
また、日本特有のビジネスマナーや上下関係への理解を深めるために、オリエンテーションや社内ルールの説明会を実施することも有効です。仕事の内容だけでなく、組織文化やコミュニケーションの“前提”をしっかり共有することで、本人の戸惑いを減らすことができます。
言語の壁を超える仕組みづくり
外国人材との日常的なコミュニケーションにおいて、日本語能力の差は大きな課題の一つです。業務上の指示やマニュアルが十分に伝わらないと、誤解やストレスを生み、本人の成長を妨げてしまうことがあります。
この問題に対しては、社内で日本語教育の機会を提供することが効果的です。外部の日本語学校との提携や、eラーニングツールの導入により、働きながら言語能力を高められる環境を用意する企業も増えています。とくに「読む・書く」よりも「話す・聞く」に重点を置いた実用的なトレーニングが、職場での即戦力につながりやすい傾向にあります。
また、現場の日本人社員にも外国人との接し方についての理解を促すことが大切です。簡潔な日本語を心がける、曖昧な表現を避ける、確認を怠らないなど、外国人に伝わりやすいコミュニケーションを取る意識づけが、相互理解を深めます。
メンター制度や相談窓口で孤立を防ぐ
職場での定着を妨げる要因の一つに、外国人社員が孤立感を抱きやすい環境が挙げられます。特に同じ国出身の同僚がいない場合、業務の悩みはもちろん、文化的な違いからくる不安を打ち明ける相手がいない状況が続くと、精神的なストレスに発展することもあります。
このような課題を解消するために有効なのが、メンター制度の導入です。入社後一定期間、日本人の先輩社員が業務・生活両面のサポートを行うことで、本人の不安を早期に取り除き、信頼関係を築くことができます。また、制度化された「相談窓口」を設けて、言語・文化・就労面の相談ができる環境を整備することも重要です。
小さな悩みでも気軽に相談できる仕組みがあるだけで、外国人社員の心理的負担は大きく軽減されます。「一緒に働いている」という安心感が、定着率を大きく左右する要素となるのです。
成功する外国人採用のポイントと事例紹介
外国人採用で成果を上げた企業の事例
実際に外国人材を採用し、戦力として活躍してもらっている企業の事例を見ると、いくつかの共通点が見えてきます。たとえば、ある製造業の中堅企業では、ベトナム人技能実習生の受け入れをきっかけに、特定技能や技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人を段階的に採用してきました。社内には当初、言語や文化の違いに戸惑いがあったものの、外国人社員に対する指導体制やマニュアルの整備、通訳者の配置などを通じて、3年後には現場の中心戦力として高く評価されるようになりました。
また、別のIT企業では、日本国内の外国人留学生を積極的にインターンシップに受け入れ、卒業後に正社員として採用する流れを作っています。日本語研修やキャリア相談を定期的に行い、本人の適性に合わせた配属を行うことで、3年間の定着率は90%以上という高水準を維持しています。この企業では「文化や言語の違いは障害ではなく、むしろ新しいビジネスチャンスを開く鍵」と捉えており、外国人社員の視点を活かした商品開発にも取り組んでいます。
採用成功のポイントは「準備・理解・継続」の3要素
こうした成功事例からは、外国人採用において重要な要素が浮かび上がります。ひとつ目は「準備」。採用前に、就労可能な在留資格の理解、必要な手続きの把握、業務内容との適合性の確認など、事前準備ができている企業ほど、採用がスムーズに進みます。また、外国人が働く環境を整えることも含まれます。例えば、外国語対応可能なマニュアルの用意や、生活支援制度の設計は、入社後の定着を左右する要素となります。
ふたつ目は「理解」。異文化を受け入れる姿勢と、日本人社員側の意識改革が求められます。文化的背景や価値観の違いを理解しようとする姿勢が職場に根づいていれば、外国人社員も安心して能力を発揮できます。コミュニケーション上のすれ違いを減らし、チームの一体感を高めるためには、受け入れ側の理解が不可欠です。
そして三つ目は「継続」。採用した後に、定期的な面談やキャリア相談を行い、成長支援を継続することで、外国人社員のエンゲージメントが高まり、長期的な活躍につながります。単に働いてもらうのではなく、「どうすれば成長できるか」「どのように貢献できるか」をともに考える姿勢が、外国人材との信頼関係を築く上で極めて重要です。
外部リソースの活用も成功への近道に
すべてを自社だけで完結させようとすると、制度の理解不足や対応ミスが起こりやすくなります。特に初めて外国人採用に取り組む企業では、行政書士や外国人雇用専門の人材会社、通訳支援サービスなど外部の専門機関との連携が有効です。とくに在留資格の取得や変更、生活支援に関しては、外部の専門性を活かすことで、制度上の不備やトラブルを防ぐことができます。
また、留学生との接点を作るために、大学や専門学校、自治体が主催する「外国人材合同説明会」への参加もおすすめです。外国人材との接点を持ち、早期にマッチングを図ることで、スムーズな採用へとつながります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 外国人を採用するには、どのような在留資格が必要ですか?
A. 採用する業務内容によって必要な在留資格は異なります。オフィスワークなどのホワイトカラー職には「技術・人文知識・国際業務」、介護や外食などには「特定技能」、現場系の実習目的であれば「技能実習」が該当します。必ず職務内容に合った在留資格であるかを確認してください。
Q2. 日本語が話せない外国人でも採用できますか?
A. 業務内容によります。接客や社内連携が多い仕事ではある程度の日本語力が必要です。一方で、ITエンジニアや研究職など、専門性が高く言語の制約が少ない職種では、日本語力が十分でなくても採用されるケースがあります。
Q3. ビザ申請は企業が行うのですか?
A. ビザ(在留資格)の申請は本人が行いますが、企業は必要書類(雇用契約書、会社概要、職務内容の説明など)を準備し、サポートする必要があります。初めての場合は、行政書士などの専門家に相談すると安心です。
Q4. 採用コストはどれくらいかかりますか?
A. 国内在住の外国人を直接採用する場合、日本人採用と大きな差はありません。ただし、海外からの採用や技能実習生、特定技能制度などを利用する場合は、送り出し機関や監理団体への費用が発生し、数十万円〜100万円程度かかることもあります。
Q5. 外国人が途中で辞めてしまうリスクが心配です。どうすれば防げますか?
A. 文化や言葉の違いによる孤立、不安、期待とのギャップが主な離職原因です。採用後の生活支援、日本語教育、定期面談、メンター制度など、フォロー体制を整えることで、定着率は大きく改善します。
Q6. 違法就労を防ぐにはどうすればいいですか?
A. 在留カードを必ず確認し、業務内容と在留資格が一致しているかを見極めてください。また、在留期限の管理も重要です。出入国在留管理庁のウェブサイトで在留カードの真偽も確認できます。
まとめ|外国人採用の第一歩は正しい理解から
外国人採用は、日本の深刻な人手不足を補う手段として注目されるだけでなく、企業に新しい価値や多様な視点をもたらす可能性を秘めた取り組みです。しかし、制度の理解不足や受け入れ体制の不備があると、せっかく採用した人材が早期に離職したり、企業側が法的トラブルに巻き込まれるリスクもあります。
採用にあたっては、在留資格の適切な選定と申請、労働条件の明示、法令に基づく各種届出が基本です。加えて、言語や文化の違いを乗り越えるためのコミュニケーション支援や、生活面でのフォロー体制も定着率を高める重要な要素となります。
成功している企業は、採用前の制度理解から採用後の育成・相談体制までを丁寧に整えており、外国人材を「即戦力」ではなく「将来の中核人材」として育てる意識を持っています。外国人採用を進めるには、制度と人への理解を両立し、長期的な視点で取り組むことが何より大切です。
なお、「Digima~出島~」の運営する外国人採用プラットフォーム「開国エンジン~縁人~」では、グローバル人材採用に関する無料相談窓口を設けています。この記事で紹介したような課題について、プロフェッショナルに相談されたい方は、ぜひご活用ください。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談