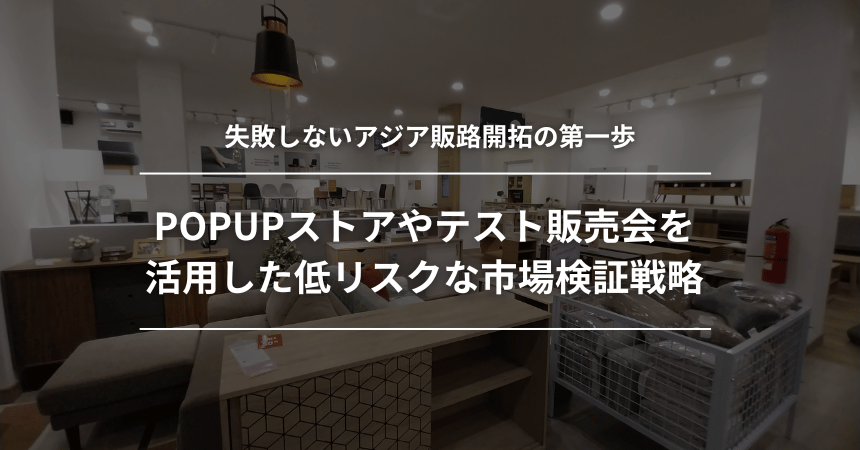日本企業は「外国人材“総活用”」の時代へ|全業種対応!グローバル人材活用の最前線と成功のヒント

近年、日本企業にとって外国人材の活用がますます重要なテーマとなっています。少子高齢化による人材不足に加え、海外市場への進出やグローバル化の流れが加速する中で、従来の日本人中心の人材戦略だけでは立ち行かなくなっているのが現実です。かつては限られた業種でしか見られなかった外国人材の採用も、今や製造業、サービス業、IT、建設など、あらゆる業種に広がりを見せています。
こうした状況の中、今後求められるのは「外国人材を採用するかどうか」ではなく、「どのように活かすか」を企業ごとに具体的に設計することです。外国人材は、単なる“人的リソース”ではなく、企業の海外展開や事業革新を支える“未来の中核人材”として位置付けられつつあります。私たちは今まさに、「外国人材“総活用”時代」の入り口に立っていると言えるでしょう。そこで「Digima~出島~」では、5月を通して『日本企業は外国人"総活用"時代へ「グローバル人材特集」』と題して、特集を展開していきます。
本記事では、グローバル人材の定義から採用・育成・活用の実務的なポイントを整理し、特に海外展開の現場での業種別活用シーンに焦点を当てて解説します。人材戦略と海外戦略の統合を目指す企業の皆さまに向けて、実践的なヒントと考え方をお届けします。是非、参考にしてください。
▼ 日本企業は「外国人材“総活用”」の時代へ|全業種対応!グローバル人材活用の最前線と成功のヒント
いま求められる「グローバル人材」とは何か?
外国人材とグローバル人材の定義と違いを明確にする
外国人材とグローバル人材は、しばしば同じ文脈で語られることがありますが、その意味合いには明確な違いがあります。外国人材とは、その名のとおり国籍が外国にある、または外国にルーツを持つ人材を指します。一方でグローバル人材とは、単に国籍や出身地にかかわらず、異文化に対応し、国境を越えてビジネスを展開できる知識・スキル・価値観を持つ人材のことを意味します。つまり、日本人であっても、海外市場に適応できる視野を持ち、英語などの語学力を備え、多様な文化や価値観を受け入れながら成果を上げられる人材は“グローバル人材”に該当するのです。
しかし、現実的には「外国人材=グローバル人材」として扱われる場面も多く、特に日本企業では外国人を採用することでグローバル対応を進めようとする傾向があります。そこで重要なのは、単に外国人を採用するのではなく、“その人がどのような越境能力を持ち、どのような役割を担えるのか”という視点を持つことです。採用や配置、育成の全てのプロセスにおいて、この観点が抜け落ちると、せっかくの人材を“戦力化”できない結果になりかねません。まずはこの違いを理解したうえで、自社にとって必要な人材像を定義することが、外国人材“総活用”の第一歩となります。
日本政府の高度外国人材政策と企業が使うべき制度群
外国人材の活用を国家戦略として位置づけている日本政府は、ここ数年、外国人の受け入れ促進に向けた制度整備を進めています。特に注目されているのが「高度外国人材制度」です。これは、学歴・職歴・年収などのポイントによって在留資格を柔軟に認めるもので、制度上の優遇措置(在留期間の延長や家族の帯同など)を通じて、日本で長期的に活躍する人材を引き込もうとするものです。
さらに2023年には「J-Skip(特定高度人材制度)」や「J-Find(留学生の就労移行支援)」といった新たな仕組みも導入され、より幅広い人材が日本企業で働ける環境が整いつつあります。こうした制度は、特に採用初期の手続きやビザ発給、在留管理において企業側の負担を大きく軽減します。とはいえ、制度があるからといって自動的に人材が集まるわけではなく、それを活かすには企業側の理解と準備が不可欠です。
外国人材の採用を検討している企業にとっては、これらの制度をしっかりと把握し、どのような人材をどの制度で受け入れるのかを設計することが大切です。政府支援を「活用できるか否か」が、その後の採用成功と定着の大きな分かれ目となるでしょう。
外国人材“総活用”が進む背景と、企業の人材戦略の転換点
外国人材の“総活用”が求められる時代的背景には、いくつかの重要な要因があります。まず、国内市場の縮小と人手不足という構造的な課題です。特に地方や中小企業では、日本人だけで組織を維持・拡大することが難しくなっており、あらゆる業種で人材の確保が喫緊の課題となっています。
一方で、日本企業の海外展開は年々加速しており、新たな市場での事業立ち上げや、現地顧客との関係構築を担える“現場に強い人材”が求められています。その中で、言語力だけでなく、異文化理解や現地ネットワークを持つ外国人材の価値が見直されているのです。もはや外国人材は、技能職や一部の専門職に限った話ではなく、営業・開発・企画など、企業の中核領域で活躍する存在として期待されています。
企業にとっての課題は、「採用するかどうか」ではなく、「どう活かすか」に変わってきています。つまり、外国人材は一時的な“穴埋め”ではなく、企業の未来を共に創る“戦略的人材”であるという認識を持たなければなりません。このような視座の転換が、これからの人材戦略に求められているのです。
外国人材を“採用”し、“戦力化”するまでの実務ポイント
採用ルート別の違い(国内留学生/海外大学/現地採用)
外国人材を採用する際には、「どこで」「どのように」人材を見つけるかが成功の第一歩になります。大きく分けて、国内留学生の採用、海外大学・教育機関からの採用、現地法人での直接採用の3つのルートがあります。国内の大学や専門学校に通う留学生は、日本語能力が比較的高く、就労ビザの取得も円滑なケースが多いため、採用後の定着率も安定しやすい傾向があります。一方で、海外大学を卒業した外国人を日本国内で雇用する場合は、内定から入国までの手続きや、文化・生活習慣のギャップに配慮したサポートが求められます。
さらに、海外拠点を持つ企業では、現地採用によって母国の市場に精通した人材を確保するケースも増えています。現地人材は、顧客対応や商習慣の理解などにおいて非常に有効であり、海外展開を視野に入れた人材戦略として有力です。採用ルートごとに必要な支援や法的な手続き、コスト構造が異なるため、企業の目的と照らし合わせた採用設計が求められます。画一的に考えるのではなく、ターゲット業務や組織体制に応じて最適な採用ルートを見極めることが、外国人材活用の出発点となります。
定着のために必要な職場整備と制度対応
外国人材を採用しても、十分に活躍してもらうためには「定着支援」が欠かせません。特に初めて外国人材を受け入れる企業にとっては、言語や文化の違いが予想以上に業務やコミュニケーションに影響を与えることがあります。そのため、職場内のコミュニケーション環境や、業務上のルール、キャリア形成の方針などを明確に伝える仕組みづくりが重要です。
また、在留資格の管理やビザ更新のサポートなど、法的・制度的な面でも企業側に一定の知識と体制が求められます。外国人材の多くは、不安定な雇用や将来の見通しの立てにくさを感じており、それが離職の要因にもなっています。だからこそ、単なる就業機会の提供ではなく、「この会社で長く働き続けられる」という安心感を与えることが、定着と戦力化への近道になります。
社内には、外国人材受け入れにあたっての担当者やメンターを置くといった配慮も有効です。特別扱いする必要はありませんが、必要な支援を明確に用意することで、外国人社員も自らの役割に集中しやすくなります。採用と同時に「受け入れ体制の整備」まで視野に入れることが、外国人材を真に活かすための鍵となります。
外国人材の“専門性”を活かす育成とキャリア設計
外国人材を採用する際、企業が見落としがちなのが「専門性の活用」と「キャリア設計」の視点です。日本では従来、総合職的な育成文化が根強く、配属や業務範囲が柔軟に決まることが多いですが、外国人材に対しても同じような前提で運用すると、早期のミスマッチや離職を招く恐れがあります。むしろ、外国人材の中には「自分の専門性を発揮したい」「特定分野で成長したい」という意識が強くあることが少なくありません。
そのため、採用の段階で職種や職務内容を明確にし、入社後には期待される役割と将来的なキャリアパスを丁寧に提示することが求められます。また、研修制度や評価制度も、多様なバックグラウンドに対応した設計が必要です。例えば、日本語能力を補う語学支援や、異文化コミュニケーションに関する研修を通じて、職場での活躍を後押しすることができます。
さらに、将来的にリーダーやマネジメント層としての活躍を期待するならば、段階的な育成プランの策定も重要になります。外国人材を「一時的な労働力」ではなく、「未来の組織を担う人材」として位置付ける姿勢こそが、真の“総活用”の第一歩となるでしょう。
海外進出・海外展開を支える“外国人材活用”の有用性とは?
海外拠点立ち上げや現地法人運営を支えるキーパーソンに
海外に新たな拠点を構える際、また現地法人を運営する場面では、その国の言語や商習慣、制度に精通した人材の存在が極めて重要です。こうした場面で、日本企業が注目すべきなのが外国人材の活用です。特に母国がターゲット市場である外国人であれば、現地のビジネス文化を理解し、行政手続きや採用活動、現地スタッフとの関係構築などを円滑に進める橋渡し役として機能します。
さらに、日本の経営方針や品質基準を現地に伝える際にも、外国人材が間に立つことで誤解や摩擦を防ぎ、円滑な立ち上げと運営が実現できます。実際に、現地出身の外国人材を中核に据えることで、進出後の早期黒字化やトラブルの回避に成功した企業も少なくありません。海外拠点の成功は、優れた事業計画だけでなく、現地と本社をつなぐ“実行者”がいるかどうかにかかっているのです。外国人材をキーパーソンとして登用することは、グローバル経営を担う第一歩といえるでしょう。
海外顧客・パートナーとの関係構築における信頼形成の中核
海外市場での成功には、顧客や現地パートナーとの信頼関係の構築が不可欠です。特に文化や価値観が異なる海外では、言語能力だけでなく、その国特有のビジネスマナーや交渉スタイルを理解している人材の存在が、事業の成否を大きく左右します。外国人材は、こうした場面で“企業の顔”として機能し、言葉の壁や文化的なギャップを乗り越える存在として高い効果を発揮します。
たとえば、輸出営業の現場においては、商談時に現地の言葉で会話を進められるだけで、相手との距離が一気に縮まることがあります。また、現地の企業文化を理解した対応ができることで、パートナーからの信頼も厚くなります。こうした積み重ねが、長期的な取引や提携へとつながり、競合との差別化にもなり得るのです。
外国人材は単なる翻訳者ではありません。企業の価値を“現地の文脈で”伝えることができる、極めて戦略的な存在です。グローバル市場でのプレゼンスを高めていくうえで、彼らの持つネットワークや異文化対応力をどう活かすかが、大きなカギとなるでしょう。
「本社⇔海外」をつなぐハイブリッド型人材の台頭
近年、日本本社と海外拠点をつなぐ“ハイブリッド型人材”の存在が、グローバル企業の中で注目されています。これは、外国籍でありながら日本の文化やビジネス習慣にも精通し、かつ現地の視点も持ち合わせた人材のことを指します。彼らは、単なるブリッジではなく、“両方の現場を動かせる”実行力を備えた貴重な存在です。
たとえば、海外工場で発生した課題を日本の本社に適切に伝えたり、現地の従業員の声を経営層に反映させたりと、経営判断をサポートするポジションで活躍するケースが増えています。また、グローバルプロジェクトの推進や、複数拠点間の調整役としても力を発揮します。
このようなハイブリッド人材は、単に言葉が話せるというだけでなく、両国の価値観を理解し、組織間の“文化の翻訳者”として機能するのが特徴です。企業がグローバルに成長していくうえで、こうした人材を意図的に育成・登用することは、国際競争力を支える強力な戦略となるでしょう。外国人材を“海外専任”とするのではなく、“社内の越境者”として活かす発想が、これからの人材活用には求められています。
業種別・外国人材“総活用”の最前線|海外展開の現場でこう使う!
製造業|現地生産・技術移転・品質管理を担うブリッジ人材
製造業における外国人材の活用は、従来の「技能実習」の枠を超え、より中核的な役割へとシフトしています。特に海外工場を展開する企業においては、現地の技術者や管理者と日本の本社をつなぐ“ブリッジ人材”としての外国人材の存在が欠かせません。彼らは、言語能力だけでなく、日本式の製造管理や品質基準を理解しており、それを現地の生産現場に的確に伝える役割を担っています。
また、技術移転の場面においても、日本人社員が一から現地に赴いて対応するのではなく、既に社内文化を理解している外国人社員が中継役となることで、指導の効率性が飛躍的に高まります。たとえば、ベトナムやタイなどでの現地生産において、日本語を話せる現地出身エンジニアが日本本社と密に連携し、生産工程の改善提案や現場管理を担っている例も増えています。
製造業のグローバル化が進む中で、こうした外国人材は単なる労働力ではなく、「製造ノウハウの伝道者」として、海外拠点の安定運営と品質確保に貢献する存在となっています。
小売・飲食・観光|現地顧客対応からマーケット浸透の先導役に
小売・飲食・観光業においては、外国人材の活用がより“顧客接点”に近いところで進んでいます。とりわけ、インバウンド需要の回復や、越境ECによる海外展開の加速に伴い、多言語対応や異文化への理解を備えた外国人スタッフが、現場での価値を高めています。
たとえば、訪日外国人観光客への接客においては、単に言語を話せること以上に、文化的な違いを理解した柔軟な対応が求められます。外国人スタッフがその架け橋となることで、サービスの満足度が格段に向上し、SNSを通じた好意的な拡散などの副次的効果も期待できます。
さらに、海外市場への商品展開においても、現地出身の外国人材が「その国で何が売れるか」「どう伝えるべきか」といった視点でアドバイスを行い、マーケティング戦略の立案や商品パッケージの改善に貢献しているケースがあります。日本の小売や飲食サービスの“価値”を現地の感覚で翻訳できる存在として、外国人材は非常に大きな役割を担っています。
IT・スタートアップ|海外開発拠点と本社をつなぐグローバルチーム構築
IT・スタートアップ業界では、すでに外国人材の登用が日常化しており、技術開発だけでなく、チームビルディングやグローバル展開の中心を担う人材も増えています。特に、エンジニア不足が深刻な日本国内においては、海外の優秀な開発者を採用し、オンラインで連携するモデルが急速に浸透しています。
その中で注目されているのが、現地開発拠点と日本の本社をつなぐ“プロジェクトコーディネーター”としての外国人材の存在です。彼らは技術とマネジメントの両方に通じており、異文化チーム間の意思疎通を円滑にし、品質や納期のブレを最小限に抑える役割を果たします。
また、グローバルサービスの開発においては、ユーザー体験やUI設計における“文化的感性”も重要な要素です。このような場面でも、外国人メンバーの意見や視点が大いに活きています。スタートアップにおいては、スピードと柔軟性が求められるため、多様な人材の混成チームでの試行錯誤こそが競争力につながります。外国人材は、単なる技術者ではなく、グローバル戦略の実行者として不可欠な存在です。
建設・インフラ・物流|海外プロジェクト現場の即戦力+中長期幹部候補
建設業やインフラ・物流業界でも、外国人材の存在感が年々高まっています。特に、東南アジアや中東、アフリカなどで進められる大規模インフラプロジェクトでは、現地の法制度や商慣習に対応しつつ、技術品質を維持できる“現場対応力のある人材”が求められています。
そのような現場で、日本語と現地語の両方を使いこなし、技術的な知見も備えた外国人材が活躍することで、施工管理や調整業務がスムーズに進みます。たとえば、現地パートナー企業や労働者との意思疎通、資材調達の交渉、行政との折衝など、あらゆる業務の中核に外国人材が関与しているケースがあります。
また、物流業界においても、海外拠点との連携や越境物流の管理において、外国人スタッフがオペレーションの要となっている事例が増えています。さらに、長期的にはマネジメント層への登用を前提としたキャリアパス設計を行う企業も出てきており、「現場即戦力」から「経営参画」へと役割の幅が広がっています。人材の“ローカル化”を目指すうえでも、外国人材は欠かせない戦力と言えるでしょう。
外国人材“総活用”を企業の“武器”にする制度・支援・戦略設計
活用できる公的支援・制度の整理(経産省・出入国在留管理庁・自治体)
外国人材の活用にあたっては、各省庁や自治体が提供する支援制度や優遇策を積極的に活用することが重要です。中でも、経済産業省や出入国在留管理庁(旧入管)が整備している「高度外国人材ポイント制度」は、一定の学歴・職歴・年収などの条件を満たした外国人に対して、在留資格の優遇や永住申請の緩和といった措置を提供するもので、グローバル人材の長期活用に向けた制度として注目されています。
また、2023年に導入された「J-Skip(特定高度人材制度)」や「J-Find(留学生向け就労支援)」は、より柔軟かつ迅速な在留資格の取得を可能にする仕組みであり、企業にとっては人材確保のスピードアップに直結します。さらに、地方自治体による外国人材の就職マッチングイベントや、生活支援体制の整備も進んでおり、特に地方企業にとっては強い味方となります。
これらの制度は“知っているかどうか”で企業の対応力に大きな差が出るため、人事担当者や経営者が継続的に最新情報を把握し、自社にとって最も効果的な支援を選択していくことが求められます。
民間サービス・マッチングの活用と注意点
外国人材の採用・活用においては、民間の専門サービスを上手に活用することで、採用効率や定着率を高めることが可能です。特に、グローバル人材に特化した人材紹介会社や求人プラットフォーム、あるいは外国人留学生に対応した大学連携プログラムなどは、企業が自力で採用活動を展開するよりもはるかにスムーズな人材獲得を実現します。
また、近年では「採用後の定着支援」を提供するコンサルティング会社や、外国人社員向けの研修・日本語教育を提供する事業者も増えており、組織の多文化共生力を高めるパートナーとして重要な役割を担っています。
ただし、民間サービスの選定においては、単なるコスト比較にとどまらず、自社の業種や採用目的に合った専門性を持つ事業者を選ぶことが重要です。また、契約条件やアフターサポートの内容も必ず確認し、短期的な採用成功にとどまらず、中長期での活躍を視野に入れた連携ができるかどうかを見極める必要があります。
海外展開×人材活用の統合戦略を描く方法
外国人材の活用は、もはや単なる採用手段ではありません。企業が海外展開を成功させるためには、人材戦略と事業戦略を統合的に設計し、両者が一体となって動く体制を構築することが不可欠です。つまり、「どの国でどの事業を行うか」と同時に、「どのような人材をどのポジションで活用するか」を計画段階からセットで考えるべきなのです。
この視点に立てば、現地の市場調査や販路開拓に先立って、その地域の文化や商習慣を理解する外国人材の確保が必要になります。また、海外プロジェクトを本社から遠隔で管理するだけでなく、現地に“信頼できる人”を配置することで、スピードと柔軟性を両立させた意思決定が可能になります。
特に中小企業や地方企業にとっては、リソースに限りがある中で「人材による海外展開の加速」は大きな武器になります。外国人材を“外部人材”としてではなく、“未来の事業推進者”として捉えること。これが、真の意味での「総活用」に向けた、最も戦略的な第一歩と言えるでしょう。
まとめ|外国人材は“海外事業の未来”そのものである
これまで、日本企業における外国人材の活用は、一部業種に限られたものでした。しかし今、私たちはその段階を越え、あらゆる業種・企業規模において、外国人材の“総活用”が求められる新しい時代に突入しつつあります。少子高齢化による人材不足という国内の構造的課題に加え、海外市場の成長と企業のグローバル化が同時に進む中で、外国人材は単なる“人的補充”ではなく、事業を前に進める「未来への投資」としての意味合いを持ち始めています。
本記事では、グローバル人材の定義から採用・育成・定着の実務、さらには海外展開の現場での業種別活用シーンまで、多角的に解説してきました。重要なのは、採用の有無ではなく、戦略に基づいた「どう活かすか」という設計のあり方です。外国人材は、外からやってくる“協力者”ではなく、これからの企業の中核を担う“当事者”として迎え入れるべき存在です。
外国人材を通じて、企業は文化を広げ、視野を広げ、事業を広げていくことができます。この“総活用”時代をどう捉えるかが、自社の成長戦略そのものを左右すると言っても過言ではありません。今こそ、自社の未来を見据えた人材活用のあり方を、根本から見直すタイミングではないでしょうか。
なお、海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima~出島~」の運営する「開国エンジン~縁人~」のようなグローバル人材マッチング支援サービスを活用することで、自社に最適な人材やエージェントと出会うことが可能です。是非、お気軽にご相談ください。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談