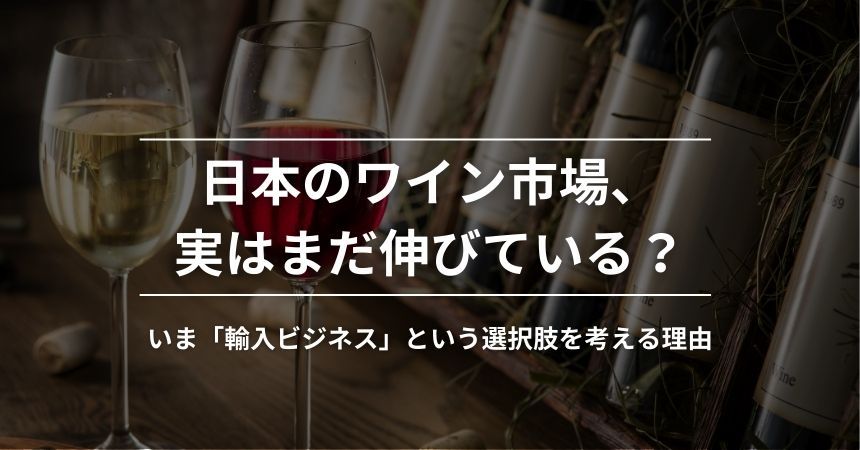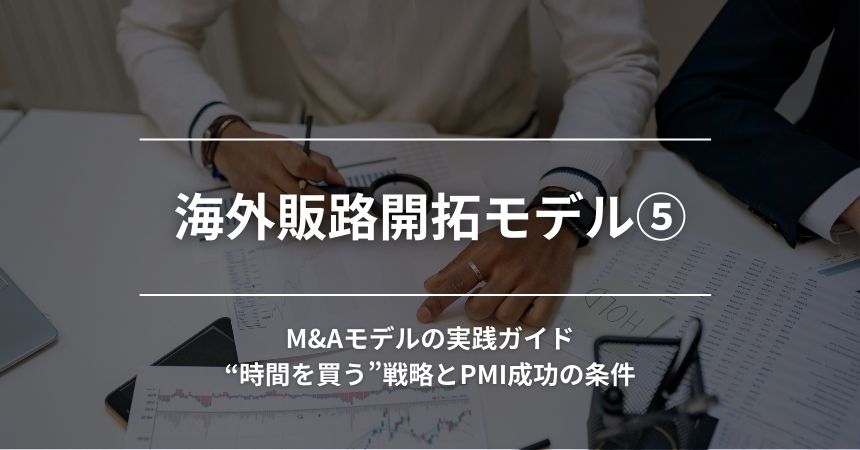IOSSとは?EU越境ECの新VAT制度をわかりやすく解説|仕組み・登録方法・メリットと注意点まで

EU域内に向けた越境ECを展開する日本企業にとって、2021年7月に導入されたIOSS(Import One-Stop Shop)制度は、避けて通れない税務対応の一つとなりました。これまで、150ユーロ以下の商品についてはVAT(付加価値税)の免税措置があったため、購入者側・販売者側の双方にとって比較的簡易な手続きが可能でした。しかし、新制度の施行により、免税が廃止され、すべての低額輸入品にVATが課される仕組みに改められました。
このような制度変更は、消費者保護やEU加盟国間の税収の公平性を目的としたものですが、EC事業者にとっては、VATの徴収・申告を含めた対応の複雑化という新たな課題を生んでいます。一方で、IOSS制度を正しく理解し、適切に導入することで、通関時のトラブルを回避し、顧客の満足度を高めることも可能です。
本記事では、IOSSの制度概要から導入のメリット、登録方法、未対応時のリスク、さらには日本企業が対応を進める際の実務的ポイントまでを体系的に解説します。EU向けEC販売を行う事業者の皆さまが、制度変更に柔軟に対応し、よりスムーズなビジネス展開を実現するための一助となれば幸いです。
▼ IOSSとは?EU越境ECの新VAT制度をわかりやすく解説|仕組み・登録方法・メリットと注意点まで
IOSSとは?制度の背景と概要
IOSSとは?EUが導入したVAT新制度の概要
IOSS(Import One-Stop Shop)は、EU(欧州連合)が2021年7月に導入した新しいVAT(付加価値税)制度です。従来、EU域外からEU内の消費者に対して150ユーロ以下の商品を販売する際には、VATが免除されていました。しかしこの制度は、域内の事業者と域外の事業者の間に税制上の不公平を生じさせており、不正や脱税の温床になるとの懸念も指摘されていました。
IOSSはこうした問題を解消するため、150ユーロ以下の商品にもVATを課し、販売者が商品販売時にVATを徴収し、EUに一括で申告・納税できる仕組みを提供するものです。従来は配送業者や買い手が通関時に支払っていたVATを、販売者が前もって価格に上乗せし、EU税務当局に報告する形式に変えることで、課税の透明性と事務処理の効率性が向上しました。特に、eコマースを通じてEUに商品を販売する事業者にとって、IOSSは実務上不可欠な制度となりつつあります。
なぜ導入されたのか?旧制度との違いと制度改革の背景
IOSS導入の背景には、欧州各国で問題視されていた「VATの未回収」や「課税の抜け道」がありました。旧制度では、150ユーロ以下の商品はVATの免税対象とされていたため、実際にはEU域外からの商品購入の多くが無税で消費者に届いていました。その結果、EU域内の小売業者がVATを納税しているのに対し、域外の事業者は免除されているという構造的な不公平が生じ、価格競争力の面でも不均衡が拡大していたのです。
この状況を是正するため、EUは電子商取引に関わるVAT制度の抜本的な改革を行い、免税措置の廃止とIOSS制度の導入を決定しました。これにより、越境ECにおいても域内事業者と同等の課税が行われることとなり、税収の安定化、公平性の確保、そして通関手続きの簡略化という三つの目的を達成する制度として整備されました。グローバル化が進む中で、税制度のデジタル対応が急務であるという欧州の姿勢が、この改革に色濃く反映されています。
IOSSが対象とする取引とは?150ユーロ以下・B2Cがカギ
IOSSの対象となるのは、EU域外からEU域内の消費者(B2C)に対して行われる150ユーロ以下の商品の販売です。ここで重要なのは、取引が「事業者対個人(B2C)」であり、かつ商品価格が150ユーロ以下であることが要件となっている点です。法人取引(B2B)や、150ユーロを超える商品についてはIOSSの対象外となり、別途通常の通関・VAT手続きが必要となります。
また、販売者がEU域内に法人拠点を持たない場合は、EU内の税務代理人(VAT Intermediary)を通じてIOSSに登録する必要があります。IOSSに登録すると、EU加盟国ごとにVATを個別に申告する必要がなくなり、IOSSポータルを通じて一括でVAT申告・納付ができるようになります。こうした制度の導入により、EC事業者にとっては煩雑な手続きを簡素化しつつ、消費者にとっても「関税や追加費用の心配がない」透明な購入体験が実現されるのです。
IOSSを利用するメリットと導入の意義
IOSSを導入することで何が変わるのか?通関手続きの簡素化
IOSSを導入する最大のメリットのひとつは、通関手続きの簡素化です。従来、EU域外からの商品がEU内に届く際には、VATの支払いが通関時に必要となり、配送業者が消費者から税金を立て替えたり、到着時に徴収したりすることが一般的でした。これにより、配送遅延や追加請求による顧客の不満が生じやすく、EC事業者にとっても苦情対応や返品リスクを抱える要因となっていました。
IOSSに登録すると、事業者は販売時点でVATを徴収し、商品発送時には「IOSS番号」をインボイス等に記載することで、通関手続きをスムーズに行えるようになります。配送業者はその情報をもとに通関処理を行い、VATの再請求や立替は不要となります。こうした仕組みによって、購入から配送までのリードタイムが短縮され、配送トラブルの発生リスクも大きく減少します。とくに、消費者にとっての「関税・税金で商品が届かないかもしれない」という不安を解消できる点は、リピート購入にもつながる大きな利点です。
VATを販売時点で徴収できる安心感と顧客満足度の向上
IOSSでは、商品価格にVATを上乗せし、販売時点であらかじめ徴収する仕組みが採用されています。これにより、消費者は購入時点で総額を正確に把握でき、後から思わぬ追加請求を受けることがなくなります。こうした価格の明確性と予見性は、ECにおけるユーザーエクスペリエンスを向上させる大きな要素であり、特にEU域内の顧客は税制に敏感であるため、透明な価格表示は信頼の獲得につながります。
また、配送時にVATを支払う必要がないため、商品受け取り時の手間や心理的負担も軽減されます。これまで、通関時にVATが請求され、場合によっては「関税+手数料」まで課されるケースもありました。IOSSを導入することで、こうした摩擦を事前に解消でき、配送から受け取りまでの一連の体験が円滑になるのです。
結果として、消費者の満足度が向上し、クレームや返品の減少、さらにはブランドイメージの向上にもつながります。特に初回購入者にとっては、安心して取引を完了できるということ自体が再購入の意欲を高める重要な要因となるため、EC事業者にとっては戦略的にも大きな意味を持つ対応といえるでしょう。
事業者側にとっての利便性とコストメリットとは?
IOSSの導入は、消費者の利便性向上だけでなく、事業者側にとっても複数の実務的メリットがあります。特筆すべきは、EU各国ごとのVAT登録が不要になる点です。従来であれば、EU加盟国に対してそれぞれ個別にVAT登録を行い、国ごとに税務申告をしなければならず、税務管理コストや人的リソースの負担が非常に大きいものでした。
IOSSでは、EU内のいずれか1か国に登録すれば、すべてのEU加盟国に向けた販売についてその登録国を通じてVATを一括申告・納付することができます。たとえば、フランスでIOSS登録を行えば、ドイツやスペイン、イタリア向けの販売もすべてフランスを通じて処理可能となるわけです。これにより、税務処理が大幅に効率化され、特に中小規模の越境EC事業者にとっては、管理負担とコストの削減が期待できます。
さらに、VAT徴収が自社の販売フローに組み込まれることで、税金に関する消費者とのトラブルや説明責任が減少し、CS部門の対応工数も抑えられます。IOSSは単なる税務制度ではなく、EC業務全体の合理化にもつながる制度といえるでしょう。
IOSSの登録方法と手続きの流れ
IOSS番号の取得方法:EU内代理人(VAT Intermediary)の役割
IOSS制度を利用するためには、まずEU加盟国のいずれかを通じてIOSS番号を取得する必要があります。EU域内に拠点を持たない日本企業などの非居住者が登録を行う場合は、EU内に所在する「税務代理人(VAT Intermediary)」を通じて申請を行うことが義務付けられています。これは、非居住者がEU内の税務当局と直接やり取りを行うのではなく、代理人を介して登録・申告・納税を行うという制度設計です。
税務代理人は、IOSSの登録申請だけでなく、月次で行われるVAT申告や納税、帳簿の保存義務の履行支援など、実務全体をサポートしてくれる存在です。登録国としては、事業の主たる販売先国、あるいは代理人の本拠地がある国を選ぶのが一般的です。なお、代理人によっては登録申請だけでなく、IOSS番号の維持・管理までを包括的にサポートするプランを提供しており、EC事業者にとっては負担を軽減する重要なパートナーとなります。
必要な書類・情報と申請ステップの整理
IOSS登録の際には、申請に必要な基本情報や書類を整備しておくことが求められます。具体的には、事業者の会社情報(商号、所在地、納税者番号など)やECサイトの運営形態、商品カテゴリー、販売国リスト、年間の取引予定額などが代表的な提出項目です。これらは、EU税務当局が申請内容の妥当性を確認するために必要となる情報であり、不備があると申請が受理されないこともあるため、正確性が求められます。
申請は、選定したEU加盟国の税務ポータル(たとえばフランス税務当局であれば「Impots.gouv.fr」)を通じてオンラインで行うのが一般的です。代理人を通じての申請であれば、必要書類の確認や入力も代行してもらえるため、言語の壁や制度理解に不安のある事業者でも比較的スムーズに登録手続きを進めることが可能です。申請後、通常は2週間〜1か月程度でIOSS番号が付与され、その番号を用いた販売が正式にスタートできるようになります。
IOSS登録後の運用管理:月次申告・記録保存の義務
IOSSへの登録が完了した後は、月単位でのVAT申告と納付、取引記録の管理といった運用業務が継続的に発生します。具体的には、EU加盟国ごとに発生した売上金額とVAT額をまとめ、登録国の税務当局に対して月次で電子申告を行い、申告分のVATをまとめて納付する流れとなります。売上がない月も申告義務がある点に注意が必要です。
また、IOSSでは取引データを10年間保管する義務が課されています。これには、取引日時、対象国、金額、VAT率、徴収VAT額などの詳細情報が含まれます。データは税務調査の際に提出を求められる可能性があるため、社内での記録体制やシステム面の整備も重要となります。販売管理ソフトや会計システムとの連携を図り、日常的に正確な取引データを蓄積・管理しておくことが、IOSS制度を安全に運用するための基盤となります。
IOSSの登録はスタート地点にすぎず、その後の継続的な対応こそが制度の信頼性と顧客満足度を高める鍵となります。特に月次の申告業務はルーティン化が必要なため、専門家やシステムベンダーとの連携を前提に、運用体制を早期に整備することが求められます。
IOSSを使わない場合の通関とVAT徴収の流れ
IOSS未使用時の課税処理:配送業者による代行徴収とは
IOSSを利用しない場合でも、EUに商品を発送する際には、150ユーロ以下であってもVATが課税されることに変わりはありません。この場合、通常はEU側での通関時に配送業者がVATを立て替え、消費者から商品受け取り時に徴収する「配送時課税モデル」が適用されます。たとえば、DHLやFedEx、国際郵便などが代理でVATを支払い、後から手数料を加えて消費者に請求する仕組みです。
この方法は、事業者側の手間は少ないものの、消費者が商品を受け取る際に予期せぬ追加費用を求められる可能性があるため、購入体験としては好ましいものではありません。特に、商品代金と送料だけで決済を終えたつもりの顧客にとっては、配達時のVAT請求が驚きや不信感につながることが多く、クレームや返品のリスクも高まります。また、配送業者によっては立替手数料や通関手数料が上乗せされるため、最終的なコストが高くなる傾向もあります。
関税・VATの二重支払いリスクと配送遅延の可能性
IOSSを利用しない販売では、課税処理が配送段階に委ねられるため、VATの処理が不透明になりやすく、場合によっては二重課税や過剰請求といったトラブルが発生する可能性もあります。たとえば、販売時に誤ってVATを含めて請求したにもかかわらず、配送時に再度VATが徴収されるというケースは、EC事業者の信頼を損ねる結果になりかねません。
また、VAT支払いを巡って消費者が配達を拒否したり、関税・手数料に関するトラブルが解決されないまま商品が差し戻されるといった事態も少なくありません。これにより、配送遅延や返送コストの発生、在庫管理の混乱など、販売者にとっても大きな業務負荷がかかることになります。IOSSを活用すればこうした不確実性を排除し、税務処理を販売時点で完了させることで、物流の安定性を高める効果が期待できます。
EU域内消費者から見たIOSS未対応ECサイトの印象と影響
現代の消費者は、購入から受け取りまでのプロセスに「シンプルさ」と「予測可能性」を求めています。その観点から見ると、IOSSに未対応のECサイトは、EU域内の消費者にとって必ずしも安心できる存在とはいえません。とくにVATや通関手続きに不慣れな一般消費者にとっては、注文後に追加費用が発生すること自体が大きな不満要因となり、購入を見送る原因にもなり得ます。
また、EU圏ではIOSS制度の普及とともに、消費者の税制度に対する理解も進んでおり、「IOSS番号付き=信頼できる販売者」という印象が定着しつつあります。反対に、IOSS番号を明示していないサイトや、VATに関する説明が不十分なサイトは、価格の透明性に欠けると受け取られやすく、競合サイトとの比較において不利になるリスクがあります。リピーター獲得や長期的なブランド育成を目指すEC事業者にとって、IOSS対応は単なる制度対応ではなく、「顧客との信頼関係を築く手段」として捉えるべき要素といえるでしょう。
日本企業がIOSS対応するための実務ポイント
IOSSの対象事業者かどうかを判断する基準とは?
IOSS制度への対応を検討する際、まず自社が「IOSSの対象事業者であるかどうか」を明確に把握する必要があります。IOSSの対象となるのは、EU域外からEU内の個人消費者に向けて、150ユーロ以下の物品をB2C(企業対個人)で販売している事業者です。この条件に該当する場合、IOSSの利用が可能となり、税務手続きや通関を簡素化できる可能性があります。
一方、法人向けのB2B取引や150ユーロを超える高額商品の販売、あるいはEU内での在庫保有を通じた販売などはIOSSの適用外となります。また、AmazonやeBayなどのマーケットプレイス経由で販売する場合は、プラットフォームがIOSS登録を行い、VATの徴収・納付を代行するケースもあるため、自社での登録が不要な場合もあります。自社の販売形態・チャネル・価格帯を正確に整理したうえで、IOSS対応の必要性と範囲を見極めることが第一歩となります。
対応すべき販売チャネル・物流業者・決済フローの整理
IOSS対応を進めるには、自社の販売チャネルと物流体制、決済手段の全体像を把握し、制度運用と整合性のある形に再構築する必要があります。たとえば、自社ECサイトを通じてEUの複数国に商品を販売している場合、各国のVAT率を販売価格に反映させるロジックを導入することが求められます。これには、カートシステムや決済ゲートウェイの設定見直しが不可欠です。
また、物流面でも、インボイスへのIOSS番号の記載、発送業者との情報共有体制、通関処理時の書類様式などを確認する必要があります。配送業者によっては、IOSSを前提とした優遇通関の枠組みを提供している場合もあるため、事前に活用可能なスキームを確認するとよいでしょう。さらに、売上記録とVAT申告を正確に紐づけるため、販売管理システムや会計ソフトとの連携を意識した運用設計も重要な検討ポイントとなります。
IOSS運用のために必要な社内体制と外部パートナーの活用
IOSS制度は登録すれば終わりではなく、月次のVAT申告・納付や取引データの記録管理といった継続的な運用が求められます。そのため、社内での運用フローを明確にし、担当部門の役割分担を定めておくことが必要です。とくに、経理・税務部門と受注・出荷部門の連携が重要であり、申告用の売上データやVAT額が正確に集計される体制を構築しておくことが、トラブル防止につながります。
また、EU域外の事業者である日本企業がIOSSを運用する際には、現地の税務代理人(VAT Intermediary)との協業が必須となります。この代理人は、IOSSの登録申請から月次申告、納税サポート、税務調査対応までを広く支援する存在であり、信頼性と対応力のあるパートナーを選ぶことが極めて重要です。英語または現地言語でのやり取りに不安がある場合は、日本語対応のある専門家やコンサルティング会社を活用するのも有効です。外部パートナーと連携しながら、自社の販売体制に合ったIOSS運用モデルを確立していくことが、EUビジネスの安定化と拡大のカギを握ります。
まとめ:EU越境ECにおけるIOSS対応は“信頼”への投資
IOSS(Import One-Stop Shop)は、EUが導入した新たなVAT制度として、越境ECにおける課税と通関のルールを大きく変えました。150ユーロ以下の商品をEU域内の個人消費者に販売する場合、IOSSに対応していなければ、通関時のVAT徴収による配送遅延や追加費用、そして消費者の不満といったリスクを抱えることになります。反対に、IOSSに適切に対応することで、販売時点でのVAT処理が可能となり、通関はスムーズになり、価格の透明性も確保されます。
制度の理解と対応には一定の準備とコストが必要ですが、それ以上に得られるメリットは大きく、なによりEU圏の消費者からの信頼を築くうえでの土台となります。IOSS対応は、単なる税務対策ではなく、EU市場における事業の継続性と拡張性を高める“戦略的なインフラ整備”とも言えるでしょう。
特に日本企業にとっては、制度の複雑さや言語の違いが障壁となる場面もあるかもしれませんが、外部専門家との連携やツール活用によって十分に対応は可能です。これからEU市場への進出や販路拡大を検討している事業者にとって、IOSSは避けて通れないテーマであり、今こそ制度理解と実務対応を進めるタイミングです。信頼される越境EC事業者として、持続可能なビジネス基盤を築く第一歩として、IOSS対応を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
なお、「Digima~出島~」には、優良な越境ECビジネスの専門家が多数登録されています。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
本記事が、越境EC事業を検討される日本企業の皆様にとって、実務の一助となれば幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談