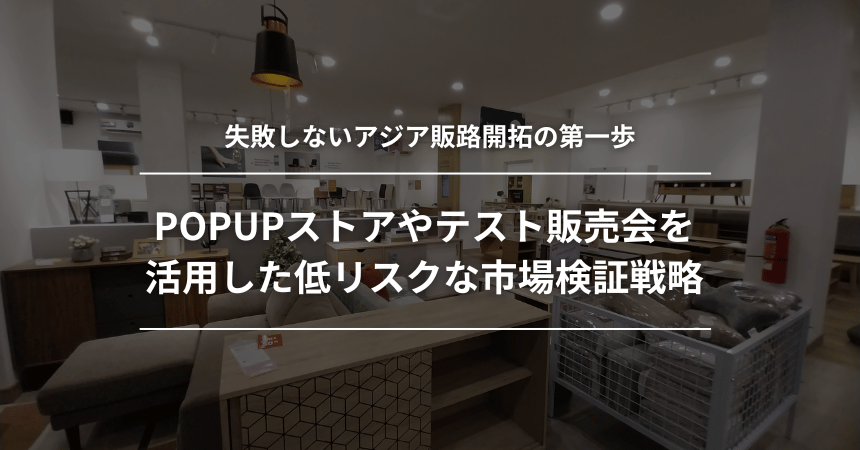DEIとは?海外展開する日本企業に求められる外国人材活用と組織づくりの新常識

グローバル市場への展開を進める日本企業が増えるなかで、現地のニーズに対応するための柔軟な組織づくりがますます重要になっています。中でも近年注目を集めているのが、DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)という考え方です。これは、企業が多様な人材を受け入れるだけでなく、その違いを前提としながら活躍できる環境を整備することを意味します。
とりわけ、外国人材の採用・活用を進める企業にとって、DEIの視点は不可欠です。単に国籍や言語の違いを超えて雇用するだけでは、職場でのすれ違いや定着率の低下といった課題を防ぐことはできません。文化・価値観・思考スタイルの多様性を組織の強みに変えるためには、「公平性のある評価制度」「異なる声を歓迎する職場文化」「制度的な包摂」の3つをバランスよく整える必要があります。
本記事では、DEIそれぞれの意味や考え方を解説したうえで、海外展開を進める日本企業がなぜDEIを“戦略的な視点”で捉える必要があるのかを、外国人材活用の文脈から具体的に読み解いていきます。採用から定着、さらには現地との連携・多様な市場への対応に至るまで、DEIを軸に据えた組織変革のあり方を実務的にご紹介いたします。
▼ DEIとは?海外展開する日本企業に求められる外国人材活用と組織づくりの新常識
DEIとは?ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンの基本理解
D・E・Iそれぞれの意味と違い
DEIは「Diversity(多様性)」「Equity(公平性)」「Inclusion(包摂性)」の頭文字をとった概念であり、単なる人材の多様化ではなく、それを組織の力として活かすための仕組みと文化のあり方を指します。
まずDiversity(多様性)は、国籍や性別、年齢、宗教、言語、文化的背景など、あらゆる違いを持つ人々を受け入れることを意味します。これは採用の段階だけでなく、働き方や価値観の違いも含めて捉えるべき概念です。
次にEquity(公平性)は、全ての人が平等に扱われることではなく、「異なる条件にある人に対して、適切な配慮や支援を通じて公正な機会を提供すること」を指します。つまり、均一なルールを押しつけるのではなく、個別の背景に配慮した設計が求められます。
最後にInclusion(包摂性)は、多様な人々が単に「存在している」状態ではなく、それぞれが意見を言いやすく、尊重され、活躍できる環境を築くことです。DEIの“要”とも言える要素であり、真に多様な組織が機能するための土台になります。
なぜいま企業にDEIが求められているのか?
DEIが注目されるようになった背景には、グローバル化の進展とともに、労働力の多様化、価値観の多元化が急速に進んでいるという時代の要請があります。加えて、企業の持続的成長においては「同質性」ではなく「多様性」がむしろ競争優位の源泉となる、という認識が世界的に広がってきたことも一因です。
さらに、ESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGsの浸透により、DEIは単なる人事施策ではなく、企業の社会的責任の中核をなす戦略的課題と位置づけられるようになりました。特に外国人材や女性、シニア層など、従来の日本企業では少数派であった人材の登用が不可欠となる中で、個人の背景に応じた働き方やキャリア形成を支援する必要性が高まっています。
また、多様な市場や国で事業展開する企業にとって、DEIは外向きの戦略だけでなく、内向きの体制整備としても重要です。採用だけでなく、定着・活躍・評価に至るまでをDEIの視点で再設計することが、グローバル市場での信頼確保と持続可能な経営に直結します。
CSRではなく「経営戦略」としてのDEI
従来、日本企業における「多様性」への取り組みは、CSR(企業の社会的責任)や労務管理の延長線上で語られることが多くありました。しかし今日では、DEIは“倫理”ではなく“経営戦略”として実装されるべき課題と認識されつつあります。
たとえば、多様な人材による視点の違いは、イノベーションの源泉になります。異なる考え方を尊重し、自由に意見を出し合える環境が整えば、組織全体の課題解決力や市場適応力が高まるからです。また、グローバル展開においては、DEIの浸透度そのものが現地ステークホルダーとの信頼関係に影響を与えるケースも少なくありません。
つまり、DEIに本気で取り組むことは、「採用の幅を広げる」だけでなく、「組織そのものの競争力を底上げする」経営的な決断です。そして、その中心には、異文化・異価値観を受け入れ、尊重し、活かすという姿勢が求められます。これは、海外展開を志向する日本企業にとって不可欠な組織変革の第一歩となるでしょう。
外国人材活用とDEIの関係|組織に求められる変化
多様性の“受け入れ”と“活かす”は別物
外国人材を採用しただけで「多様性を推進している」と考えてしまう企業は少なくありません。しかし、単に国籍や言語の異なる人材が社内に存在しているという状態は、多様性を「受け入れている」ことに過ぎず、「活かしている」とは限りません。真のDEIとは、個々の違いを尊重し、それぞれが能力を発揮できる環境を組織として整備することにあります。
たとえば、外国人社員が会議で意見を求められても、「空気を読む」文化に戸惑い、意見を出しづらいと感じるケースがあります。また、評価制度や昇進の基準が不透明で、自分に期待されている役割が見えにくいといった不安も生じがちです。こうした状況下では、せっかく優秀な人材を採用しても、その能力が十分に発揮されず、早期離職につながるリスクも高まります。
したがって、外国人材を“活かす”には、制度やコミュニケーションのあり方、職場文化そのものを見直す必要があります。違いを単に「受け入れる」段階から、「組織の力に変える」段階へと踏み込むことが、DEIの真価であり、日本企業の次なる成長を支える鍵でもあります。
「公平性」を考慮した制度・評価・教育設計
Equity(公平性)は、DEIの3要素の中でも、最も制度設計と密接に関わる概念です。特に外国人材を活用するうえでは、「平等に扱うこと」と「公平に評価すること」は似て非なるものです。すべての社員に同じ機会やルールを提供することは一見“平等”に見えますが、背景や事情が異なる外国人材にとっては、実質的に不利な状況を生むこともあります。
たとえば、日本語を第二言語として使う社員にとって、日本語での報告資料作成や会議での発言が人事評価に強く影響する場合、それは「平等」なルールであっても「公平」ではありません。また、宗教や文化によって就業時間や休日の取り扱いに制約がある場合、それを踏まえた柔軟な勤務制度や休暇制度の設計が求められます。
さらに、外国人社員が自社のカルチャーや業務に適応するまでには時間がかかるため、段階的な教育支援やキャリア設計の伴走体制も重要です。制度として公平性を担保するには、「誰にでも同じことを求める」のではなく、「違いに応じた適切な機会や支援を提供する」という視点が必要です。それがEquityの本質であり、組織の信頼性にも直結します。
“異なる声”を排除しない職場づくりとは?
Inclusion(包摂性)は、採用された多様な人材が実際に職場の一員として認識され、安心して意見を述べ、貢献できる状態を指します。この“心理的安全性”の担保こそが、多様なメンバーの力を引き出すための前提条件です。
しかし現実には、外国人社員の意見が組織の意思決定に反映されにくかったり、ミーティングで発言してもスルーされたりと、無意識のうちに「異なる声」が排除されるケースが少なくありません。こうした状態が続けば、社員は次第に意見を控えるようになり、組織は多様性の力を失っていきます。
そのためにはまず、上司や同僚が「意見の背景を理解しようとする姿勢」を持ち、文化や語学の壁を乗り越える努力を日常のなかに組み込む必要があります。さらに、社内で“少数派”の立場にある人々が安心して声を上げられるよう、双方向のフィードバック制度、相談窓口の設置、多言語対応の社内ツールなどの整備も求められます。
Inclusionは「制度」だけで成り立つものではありません。日々の言葉遣いや態度、関係性の中で培われていくものです。だからこそ、外国人材の活用に本気で取り組む企業には、この「包摂する文化づくり」への地道な努力が求められるのです。
海外展開企業にこそDEIが不可欠な理由
現地スタッフ・パートナーとの共創にDEIが影響する
海外に事業を展開する企業にとって、現地のスタッフや取引先、パートナー企業との関係構築は、単なる「人的なつながり」を超えて、事業の安定と成長を支える基盤となります。こうした関係を築く際に、DEIの姿勢があるかどうかは、相手からの信頼形成に大きな差を生みます。
たとえば、現地採用のスタッフに対して本社の価値観を一方的に押し付けたり、意思決定の場に現地の意見が反映されなかったりすれば、「自分たちは軽視されている」という感情を生み、離職や士気低下につながります。反対に、文化的背景や職務習慣の違いを尊重し、相互の価値観を踏まえたコミュニケーションを心がけることで、“共に働くパートナー”としての信頼関係が構築されていきます。
また、現地の多様性や社会的価値観を理解する姿勢そのものが、企業の“社会的信用”に直結します。取引先や顧客がグローバル企業を選ぶ際、「DEIへの取り組みがあるか」を重要な評価軸とするケースも増えており、日本企業としてもその視点を持つ必要があります。
本社-現地間の“カルチャーギャップ”を埋める鍵
海外拠点との連携において、日本本社と現地法人の間で起こる“カルチャーギャップ”は、海外展開企業にとって長年の課題です。価値観の違い、報連相のスタイル、意思決定の速度、リーダーシップのあり方など、細部に至るまで認識のズレが積み重なると、やがては事業の足並みの乱れやトラブルの温床になります。
ここで重要となるのが、DEIの視点です。つまり、「違いがあることを前提とする」マインドセットを本社が持てているかどうか。画一的な日本式のルールや文化を押し通すのではなく、多様な価値観を前提に組織を設計・運用する姿勢が求められます。
たとえば、現地幹部を意思決定のプロセスに参加させる、言語や文化の違いに配慮したマネジメントマニュアルを整備する、本社研修を多言語・多文化に対応させるといった取り組みは、本社-現地の“心理的な距離”を縮める実践的なDEI施策と言えるでしょう。カルチャーのギャップを埋めるには、制度と対話の両面でのアプローチが不可欠です。
多様な市場に対応するための“内なる多様性”
グローバル市場での成功には、その地域に根ざした価値観やニーズを理解し、商品・サービスに反映させる力が不可欠です。そしてそのためにこそ、企業の内側に多様性を取り込む必要があります。つまり、さまざまな国・文化・視点を持った人材を社内に迎え、意思決定や商品開発のプロセスに関与させることで、多様な市場のニーズを“肌感覚”で捉える力が育まれるのです。
海外展開を進める企業が日本本社中心の思考から脱却できない場合、現地の文化に根ざした提案ができず、せっかくのチャンスを逃すこともあります。一方、外国人材や現地社員の声が企画段階から反映されている企業は、より的確に市場に響く製品やサービスを生み出すことが可能です。
これはDEIの観点から見ると、「外に対応するために、内側を変える」アプローチとも言えます。内なる多様性が高まることで、組織はより柔軟に、そして競争力のある存在へと進化します。海外展開企業にこそ、DEIは“対外戦略の土台”として実装されるべき考え方なのです。
DEI推進に向けた企業内実践と課題整理
トップの意思と現場の自走力をどう両立させるか
DEIの取り組みを社内で定着させるには、経営トップによる強いメッセージと、現場の“自走力”の両方が欠かせません。どちらか一方だけでは、表面的なスローガンに留まったり、現場での理解が進まず形骸化したりする危険性があります。特に外国人材を含む多様な人材の活躍を目指す企業にとって、理念と実務のギャップを埋める運用設計が問われます。
まず、トップのコミットメントは、DEIを「一時的な取り組み」ではなく、「中長期の経営戦略」として位置づけるために不可欠です。経営陣がDEIの重要性を明言し、全社方針として明文化することで、現場に対する“後押し”が生まれます。
一方で、現場が主体的にDEIを理解し、業務に落とし込むには、社員一人ひとりの納得感と実感が必要です。たとえば、多様性に関する社内ワークショップや、外国人社員との交流機会を設けることで、自分ごととしてDEIに向き合う土壌を育てることが重要です。経営からのメッセージと、現場の経験値が結びつくことで、DEIは“根づく取り組み”へと進化していきます。
言語・宗教・習慣の違いを前提とした社内制度整備
外国人材を受け入れる際、制度や就業規則が日本人中心に設計されているままでは、文化や生活習慣の違いによる不公平感や摩擦を生み出す原因になります。DEIを推進するうえでは、制度そのものを“同一基準”ではなく“多様な背景に対応する前提”で見直す必要があります。
たとえば、宗教的な理由によって食事や礼拝時間に配慮が必要な社員には、休憩時間の柔軟化や礼拝スペースの確保といった措置が求められます。また、日本語を母語としない社員には、社内通知・マニュアル・研修資料の多言語化、やさしい日本語の活用といった情報保障も不可欠です。
さらに、外国人社員にとって評価制度やキャリアパスが不透明である場合、「公平に扱われていない」と感じる要因になります。明文化された評価基準とフィードバック機会の整備、成長支援の仕組みづくりが、定着と活躍を支える制度の柱になります。
DEIの観点から制度を見直すことは、外国人材の活躍を支えるだけでなく、日本人社員にとっても働きやすく、公正な職場環境の整備につながります。これは全社的な“組織アップデート”でもあるのです。
アンコンシャスバイアスへの継続的な働きかけ
DEI推進の最大の障壁のひとつが、「無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)」です。これは、本人に悪意がなくても、無意識のうちに特定の人々に対して偏った見方をしてしまう認知の癖を指します。たとえば、「外国人はすぐ辞める」「日本語が流暢でなければリーダーにはなれない」といった思い込みが、知らず知らずのうちに組織の判断や評価に影響を及ぼしていることがあります。
アンコンシャスバイアスは、自覚しづらく、排除しきれないものです。だからこそ、継続的に“気づき”を得る場を設けることが効果的です。たとえば、社内で定期的に行うバイアス研修、ケーススタディを用いたディスカッション、現場での体験共有などが、社員一人ひとりの意識変容を促します。
また、組織全体としてバイアスを排除する取り組みとして、人事評価の多面化や面接のチェックリスト化など、「恣意性の入り込まない設計」も重要です。DEIは単なるスローガンではなく、こうした意識と制度の両輪で構築される“文化のインフラ”です。多様性を真に力に変えるためには、個人と組織の両面からの地道な努力が欠かせません。
日本企業がDEIを“外国人材活用”の力に変えるために
採用だけでなく“定着・活躍”を支えるDEI視点
外国人材の採用を進める日本企業が直面しやすいのが、「採用できても長く働いてもらえない」という課題です。その背景には、文化や制度への適応の難しさ、キャリアの見通しの不透明さ、評価の不公平感など、職場環境に起因する要素が少なくありません。ここにこそ、DEIの視点が真価を発揮する場面があります。
採用の時点で多様な人材を迎え入れることはスタートに過ぎません。むしろ重要なのは、その後の定着支援、能力発揮の機会提供、成長の伴走といった、長期的な活用フェーズです。たとえば、オンボーディングプログラムに多言語対応や文化教育を組み込む、上司による定期的な1on1を通じてキャリアの方向性を確認するなど、“働き続けられる環境”の構築がDEIの実践そのものと言えます。
また、採用後の声に耳を傾け、制度や仕組みをアップデートしていく柔軟性が、組織全体の成長につながります。外国人材の“定着”をゴールとせず、“活躍”を共に設計するという視点が、これからの企業には求められます。
「文化を越えて共に働く」組織設計のヒント
外国人材と共に働くうえで、最も大切なのは、「文化の違いを問題視するのではなく、前提とする」ことです。日本の組織文化が良い・悪いではなく、どのようにその文化を“翻訳”し、“共有”していくかが鍵となります。
たとえば、報連相やホウレンソウ文化が強い組織では、その背景にある「事前報告を重視する理由」を丁寧に説明することが重要です。同様に、定時退社やチーム重視の働き方に戸惑う外国人に対しても、「なぜそれが大切にされているのか」を言語化し、伝えていく姿勢が信頼を生みます。
このような“文化の翻訳”を可能にするには、組織として多文化に対応するマネジメントスキルを磨く必要があります。具体的には、異文化トレーニングの導入、社内における通訳・バイリンガル人材の活用、または文化の違いを前向きに捉えるワークショップの実施などが挙げられます。
文化を越えて共に働くとは、「違いを恐れない組織」になることでもあります。それは外国人材に限らず、多様な個性を受け入れ、高め合う組織へと進化する過程そのものです。
DEIをベースにした外国人材マネジメントの未来像
これからの日本企業にとって、DEIは「外国人材のため」だけの施策ではなく、企業全体のマネジメント刷新の起点となる可能性を秘めています。少子高齢化が進む中、外国人材の登用は不可逆的な流れであり、それに対応するための組織文化の変革は、もはや一部の先進企業だけのテーマではありません。
DEIの視点を組織に取り入れることで、外国人材の採用・定着・活躍のサイクルが自然と生まれ、結果として国内外の多様な市場に対応できる強い組織が育まれます。また、外国人材が活躍する姿は、他の社員への刺激にもなり、社内の活性化や人材育成の土壌にもなります。
今後は、「DEIを掲げる」こと自体がゴールではなく、「DEIのある組織設計を通じて、全員が力を発揮できる場をどうつくるか」が問われていくでしょう。外国人材のマネジメントをDEIの視点から見直すことは、変化の時代を生き抜く日本企業にとって最も実践的な組織づくりの鍵であり、その先にあるのは国境を越えた真の共創の未来です。
まとめ:DEIで外国人材を「活かす」企業へ
DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)は、単に“多様な人材を受け入れる”という枠を超えて、組織として多様性を戦略的に活かし、全員が力を発揮できる環境をつくるための基盤です。特に、海外展開を進める日本企業や、外国人材の採用を進める企業にとって、DEIの視点はもはや“あった方がよい”ものではなく、“不可欠な前提”となりつつあります。
外国人材を採用しても、その人たちが文化や言語の壁に孤立したままでは、定着や活躍は望めません。逆に、制度や職場環境をDEIの観点で見直し、違いを強みに変える仕組みを構築すれば、外国人材は企業の成長をけん引する存在となります。そしてそのプロセスは、日本人社員にとってもより働きやすく、多様な視点が尊重される職場の実現につながっていきます。
DEIを“理念”で終わらせるのではなく、“実務”と“文化”に落とし込む。それが、日本企業がこれからの時代を生き抜き、グローバルで選ばれる組織へと変革するための鍵です。外国人材の受け入れをきっかけに、自社の在り方そのものを見直す――そんな前向きな変化が、これからの組織の競争力となることでしょう。
なお、海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima~出島~」の運営する「開国エンジン~縁人~」のようなグローバル人材マッチング支援サービスを活用することで、自社に最適な人材やエージェントと出会うことが可能です。是非、お気軽にご相談ください。
本記事を参考に、自社に最適な外国人材の採用戦略を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談