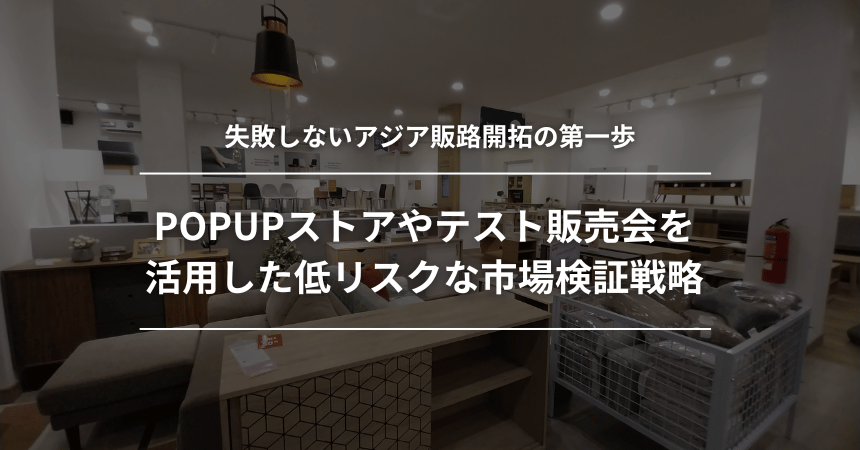英語圏で共感されるブランドとは?トランスクリエーションの実践戦略と導入ステップ

日本発のブランド(製品やサービス)が、英語圏市場に挑戦する機会はますます増えています。しかし、その多くが直面するのが「きちんと翻訳したはずなのに、なぜか伝わらない」「広告表現が現地では響かない」といった“文化の壁”です。言語を翻訳するだけでは、ブランドの魅力が本来の力を発揮できない──そんな課題を乗り越える手法として、近年注目されているのが「トランスクリエーション(Transcreation)」です。
単なる翻訳やローカライズとは異なり、トランスクリエーションは文化歴史的背景や価値観の違いをふまえた“共感される表現”を再構築するアプローチです。本記事では、英語圏に向けたブランド展開においてトランスクリエーションがなぜ重要なのか、どのように進めていけばよいのかを、実務目線でわかりやすく解説します。英語圏市場への本格展開を視野に入れている企業のご担当者さまにとって、ブランドが“真に共感される”ための戦略設計のヒントとなれば幸いです。
▼ 英語圏で共感されるブランドとは?トランスクリエーションの実践戦略と導入ステップ
1. 「翻訳では届かない」時代のブランド課題
単なる翻訳では、ブランドの価値が正しく伝わらない
日本企業が英語圏市場に進出する際、まず取り組むのが言語の翻訳です。しかし、「言葉を英語にしただけ」では、現地のユーザーにメッセージが届かないケースが多くあります。たとえば、日本語ではポジティブな意味を持つ「こだわり」という表現も、直訳された英語 “obsession” はやや重く、ネガティブに捉えられることがあります。こうした“ずれ”は、単語レベルの違いだけでなく、背後にある文化的背景や価値観の差に起因しています。
文化の違いが、共感のハードルを高める
翻訳上の課題は単語だけではなく、トーンや口調などの表現スタイルにも及びます。日本の広告表現では、控えめで遠回しな言い方がよく使われますが、英語圏ではストレートで自信に満ちたメッセージの方が効果的とされます。このギャップを放置したまま現地展開を行うと、ブランドメッセージが曖昧になり、競合他社に埋もれてしまうリスクがあります。つまり、文化的な期待値や表現のニュアンスまでを加味しない限り、真に“伝わる”ブランド発信は実現できないのです。
“言葉の再構築”としてのトランスクリエーションの重要性
このような課題を解決するためのアプローチとして注目されているのが「トランスクリエーション」です。トランスクリエーションとは、単なる翻訳ではなく、原文の持つ意図や価値を維持しながら、文化的背景に合った形でメッセージを再構築する手法です。言い換えれば、ブランドの「本質=魂」を損なうことなく、異なる文化圏においても自然に、そして強く共感される形へと“表現し直す”プロセスともいえます。次章では、このトランスクリエーションという概念の詳細と、翻訳・ローカライズとの違いについて詳しくご紹介していきます。
参考:なぜ文化的適応が重要か
2. トランスクリエーションとは?翻訳・ローカライズとの違い
翻訳との違いは「情報の正確さ」から「感情の共感」へ
一般的な翻訳は、元の文章に含まれる言葉や情報を、できる限り正確に他言語へ置き換える作業です。たとえば、製品マニュアルや契約書のように、意味の正確性が重要な文書では翻訳が不可欠です。しかし、ブランドメッセージや広告表現では、単に意味が正しければよいわけではありません。重要なのは、受け手の心にどう届くかという感情面でのインパクトです。この点で、翻訳は「通じる」ことを目的とし、トランスクリエーションは「心に伝わり、響く」ことを目的とする、と表現することができます。
ローカライズとの違いは「言葉」か「設計」か
ローカライズとは、ある程度文化に配慮した言葉や仕様の調整を含むプロセスで、ソフトウェアやWebサービスなどで多用されます。たとえば、通貨表記の変更や、祝日、単位系などを現地仕様に合わせることが主な目的です。対してトランスクリエーションは、文脈・感情・表現スタイルの再設計に重きを置きます。たとえば、商品名やキャッチコピー、スローガンを、現地の文化や価値観に響く言葉へ再構築する必要がある場面では、ローカライズでは対応しきれない領域になります。
トランスクリエーションは「創造的翻訳」である
トランスクリエーションは「翻訳」と「クリエイティブ」を組み合わせた、戦略的な再表現プロセスです。元の言葉に込められた意図やブランドの核を理解したうえで、単に置き換えるのではなく、その国の文化や言語感覚に合わせて最適な言い回しやトーン、表現手法を選びます。そのため、コピーライターやマーケター、文化理解の深いローカルスタッフなど、多様なスキルを持つチームによる協働が求められます。こうしたプロセスを通じて、トランスクリエーションは現地の言葉や文化を踏まえた“伝える力”を持つ表現へと昇華させるのです。
3. 英語圏で響くブランド構築のポイント
共感を得るには、まず“現地視点”で価値を再定義する
英語圏でブランドが受け入れられるためには、単に自社の魅力をアピールするだけでなく、その価値を英語ネイティブの視点で“語り直す”ことが求められます。日本で評価されている強みが、そのまま英語圏で刺さるとは限りません。たとえば、日本では当たり前と考えられている製造プロセスなどにおける細かい工程管理が、米国では尊敬の対象になる場合もあります。また、日本企業がよく訴求する「品質」や「職人技」といったキーワードも、英語圏では「エクセレンスの追求」「クラフトマンシップ」といった表現に置き換えないと、その価値が十分に伝わらないことがあります。ブランドストーリーの設計段階から、ターゲットの文化的価値観を踏まえた“語り方の最適化”が必要なのです。
「伝統」や「繊細さ」よりも「意図」と「インパクト」を重視
英語圏では、特に北米市場を中心に、ブランドの“明確な意図”と“消費者とのつながり”が重視されます。「なぜこのブランドが存在するのか」「この商品を通じて何を実現しようとしているのか」といったブランドの“Why”に共感を得ることで、初めて選ばれる候補となります。日本と同様にレビュー(口コミ)もチェックはしますが、最終的には、自分自身の判断と体験をとても重視します。また、表現においても曖昧さや慎み深さは敬遠され、簡潔でストレート、かつポジティブな語り口が好まれます。日本的な美意識を維持しつつも、伝え方は現地仕様に適応させる必要があります。
コピーだけでなく、ビジュアルや体験設計も“翻訳”する
見落とされがちですが、英語圏の消費者との信頼関係を構築するために最も重要なことは、貴社のブランドのストーリーやビジョンに基づくブランドナラティブのガイドラインをきちんと作成することです。
共感されるブランド構築は、言葉だけに留まりません。ウェブサイトの構造や情報フロー、色づかいやフォント、人物モデルの選択といったビジュアル表現も、文化圏によって好まれる傾向が異なります。欧米では読みやすさ・アクセシビリティへの配慮が重要視され、ユーザーインターフェースもシンプルかつ直感的であることが求められます。また、店頭におけるPOPやSNSなどを含め、ブランドに触れる体験全体が統一されているかどうかも評価の対象になります。トランスクリエーションは、ブランド体験全体の設計にまで踏み込むことが必要なのです。上記のガイドラインはそのような全体設計のための青写真となるものです。
4. トランスクリエーション導入のステップと体制づくり
ブランドの「核」を再定義することから始める
トランスクリエーションを導入する際、まず必要なのは、自社ブランドの核となる価値を明確にすることです。これは単にキャッチコピーやプロダクトの特徴を言語化するだけではなく、「私たちはなぜこの事業をしているのか」「どんな課題を誰に対して解決したいのか」といった、パーパス(存在意義)やストーリーの再定義に踏み込む作業です。英語圏で共感されるブランドへと変換するには、この価値の“翻訳可能性”を意識しながら、伝えたいエッセンスを精緻に言語化したブランドナラティブが必要となります。
社内と外部の連携体制を構築する
次に重要なのが、トランスクリエーションを実行する体制の整備です。日本企業内に英語のネイティブ感覚を持つライターや編集者が常駐していることは稀です。そのため、英語圏とのネットワークが豊富なトランスクリエーションパートナーやグローバルコピーライターとの協働が現実的な選択となります。このとき、社内チームはブランド理解と意思決定を担い、外部チームは表現の具体化と文化適応を担当するという役割分担が効果的です。社内での言語表現に対する共通認識を持つことも、成果物のクオリティを高めるうえで欠かせません。
適切なスケジュール設計とフィードバックの仕組み
トランスクリエーションは単なる翻訳作業と比べ、検討と調整に時間を要します。プロジェクト開始時には、英語圏独自のリサーチ→コピー案の草稿→仮テスト→フィードバック反映といったプロセスを踏む必要があるため、通常よりもスケジュールにゆとりを持たせることが大切です。また、文化的な観点でのニュアンスの違いを修正するためにも、現地在住のネイティブチェックを入れるなど、多層的なレビュー体制の構築が求められます。完成したコピーだけでなく、サイト全体や広告文脈にどうフィットするかまで検証する姿勢が、成功のカギとなります。
5. 成功事例に学ぶ“伝わる表現”とその背景
成功のカギは「翻訳」ではなく「再解釈」
トランスクリエーションが効果を発揮した実例として注目されるのは、日本独自の価値や文化を持つ商品が、英語圏向けに再構成されたブランドコミュニケーションを通じて成功を収めたケースです。たとえば、ある日本の伝統工芸ブランドでは、“匠の技”や“手仕事の美”といったコンセプトをそのまま訳すのではなく、「timeless craftsmanship」「The beauty of handcraft」といった表現に変えることで、英語圏でも共感されるストーリーとして伝えることに成功しました。そして、このストーリーを視覚的に表現する、最適なビジュアルデザインも重要となります。例えば、ウェブサイトではトップ画面において、短いコピーと目を引くビジュアルデザインで、初めて見る人たちを瞬時に惹きつける工夫が必要です。こうした再解釈は、トランスクリエーションならではの視点です。
文化への配慮がブランド信頼を生む
また、多様性に富む英語圏での広告展開においては、宗教的・歴史的、そして社会的な文脈への配慮も成功を左右するポイントになります。たとえば、ある日本の食品メーカーが北米市場でキャッチコピーを展開する際、直接的な健康志向を訴求しすぎた結果、現地では「過剰な医療広告」と誤解されるリスクがありました。このような場面でトランスクリエーションのプロセスが入ることで、「日常に自然な健康を届ける」という表現に変えられ、信頼を損なわずにメッセージを伝えることができたのです。これは、文化的コンテクストをふまえた表現設計の意義を示しています。
意義・目的の“再構築”が、選ばれるブランドをつくる
最終的に、トランスクリエーションとは、企業の狙いや情熱を「翻訳」するのではなく、「再翻訳=再構築」するプロセスです。成功した企業は、表層的な言い換えではなく、ブランドの核心を言語・文化・表現の枠を超えて再解釈する力を持っていました。その背景には、ターゲット市場の価値観を深く理解し、尊重する姿勢があります。トランスクリエーションは、単なる表現手法ではなく、文化をまたいで信頼と共感を築くためのコミュニケーション戦略なのです。
6. まとめ:海外展開における「コミュニケーション」の再設計の重要性
英語圏をはじめとする海外市場への展開において、単なる言語の置き換えだけでは、ブランドが本来持つ魅力や信頼感を的確に伝えることはできません。市場が成熟し、消費者の価値観が日本よりもはるかに多様化した市場で、企業が選ばれる存在になるためには、現地の文化的背景を理解し、共感を呼ぶ表現に昇華させる視点が求められます。
トランスクリエーションは、そのようなニーズに応える“コミュニケーションの再設計”の戦略です。翻訳でもローカライズでもないこの手法は、言葉の意味だけでなく、感情・文脈・文化を読み解きながら表現を再構築するプロセスであり、単なる作業ではなくクリエイティブな意思決定を伴う取り組みです。
これまで見てきた通り、成功するブランドは、トランスクリエーションを通じて「誰に」「何を」「どう伝えるか」を言語と文化の両面から設計しています。社内の認識統一や外部専門家との連携、十分な検証プロセスを通じて、“伝わる”コミュニケーションが形づくられているのです。
グローバル市場での存在感を確かなものにしたい企業にとって、トランスクリエーションはもはや選択肢ではなく、必須の戦略的投資といえるでしょう。文化と言語を越えて、共感されるブランドを構築する――その第一歩として、本記事の内容が参考になれば幸いです。
なお、弊社では、食品、業務用精密機器、次世代クリーナー、XRテクノロジー製品など、伝統的な商品から最新技術製品まで多岐にわたる実績がございます。英語圏での実績を多く持ち、現在は日本に住む米国人ディレクター陣が直接貴社をサポートいたします。是非、お気軽にご相談ください。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談