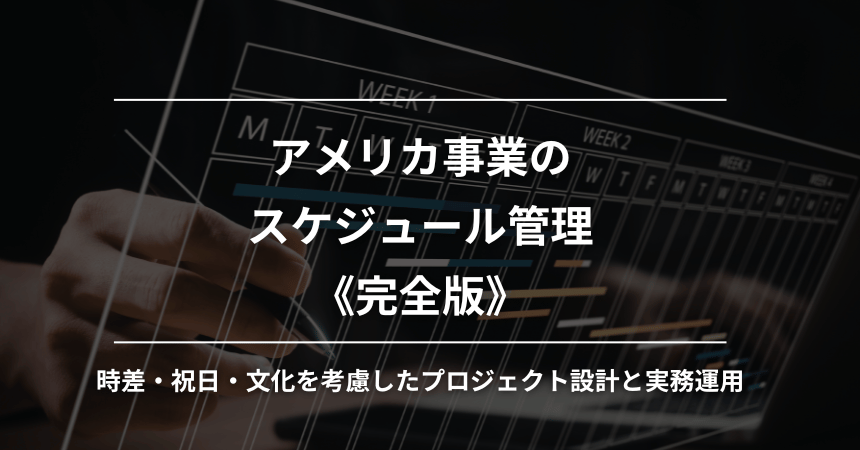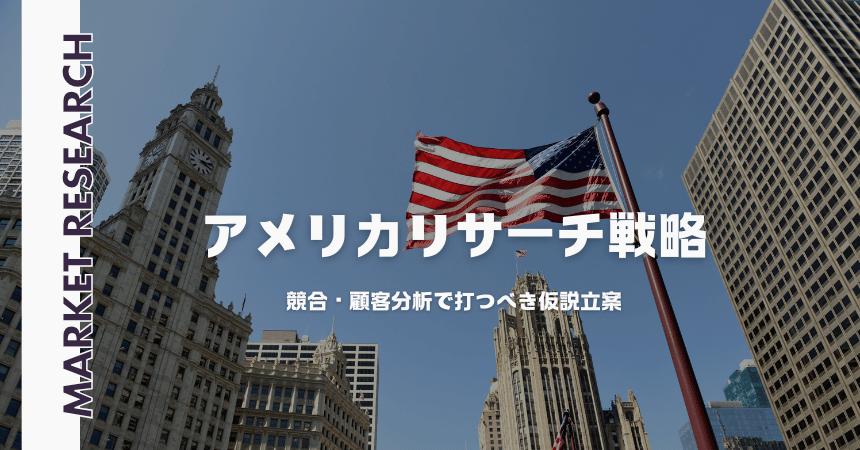“Made in USA” 表示の要件と実務戦略 — 製造業が知るべき米国ビザ比較(L-1 / E2 / B-1)

近年、「Made in USA」の取得を目指してアメリカ国内に製造拠点を設ける日本企業が増えています。その背景には、政権を超えて継続されているアメリカの国内製造業回帰政策や、補助金・税制優遇を受けられる法制度の整備があり、現地生産・雇用創出を行う企業への期待が高まっている現状があります。「Made in USA」のラベルは、単なる製品表示ではなく、企業の信頼性や米国社会との一体性を象徴する“戦略的資産”として位置づけられているのです。
一方で、現地での生産体制を構築するためには、製造工程の実態を整えるだけでなく、日本からの技術者・管理者の派遣を通じて「日本流ものづくり」を根づかせることが不可欠です。その際に重要となるのが、目的に応じた適切なビザの選定と、人材配置の戦略的な設計です。
本記事では、アメリカ製造拠点の構築に必要な制度理解、就労ビザの活用方法、そして実際の成功事例までを詳しく解説します。米国市場での競争力を高めたい製造業の皆様にとって、必読の内容です。是非、参考にしてください。
▼ “Made in USA” 表示の要件と実務戦略 — 製造業が知るべき米国ビザ比較(L-1 / E2 / B-1)
なぜ今「Made in USA」取得が注目されているのか?
トランプ前政権・バイデン政権の共通路線としての「米国内製造業回帰」政策
米国ではここ10年以上にわたり、「製造業を再びアメリカに」という政策が、政権の枠を超えて重要課題とされてきました。特にトランプ前政権では「アメリカ第一主義」のもと、企業に対して生産拠点を米国内に戻すことを強く促す政策を展開。一方、バイデン政権下でもその流れは大きく変わることなく継続され、むしろグリーンエネルギーや半導体といった戦略的産業に対して積極的な補助金制度が導入されました。そして現在、トランプ氏の再登板により、この「国内製造回帰」路線はさらに加速する見込みです。
両政権に共通するのは、単なる貿易保護主義ではなく、「雇用の創出」と「サプライチェーンの安定」を目的とした構造的な政策である点です。この方針のもと、製造業の米国内投資には広範な支援とインセンティブが設けられ、外国企業にとっても新たな機会が生まれています。
IRA法・CHIPS法などによる補助金・優遇措置と日本企業のチャンス
近年制定されたIRA(インフレ抑制法)やCHIPS法(半導体支援法)は、アメリカ国内における製造業の競争力を高める目的で策定された法律です。これらの法制度では、国内に生産拠点を設ける企業に対し、税制優遇、補助金、インフラ支援といった多様な恩恵が用意されています。特に電気自動車、再生可能エネルギー、半導体などの分野では、その支援額は数十億ドル規模に達しています。
こうした制度は、米国企業だけでなく、米国内に製造拠点を持つ外国企業にも適用されることから、日本の製造業にとっても大きなチャンスとなっています。たとえば、日本の部品メーカーがアメリカに工場を設立すれば、現地完成品メーカーとのサプライチェーン連携だけでなく、各種の優遇措置を受けられる可能性が生まれます。
その背景にある、現地生産+雇用創出=“好まれる企業像”
アメリカ政府や社会が求めているのは、単にモノを売るだけの外国企業ではなく、「アメリカに投資し、雇用を生み、税金を納めるパートナー」としての企業像です。現地生産による製品の提供、現地人材の積極的な雇用、地域コミュニティへの貢献といった活動は、企業イメージや政策面での評価にも直結します。
「Made in USA」の取得は、そうした“好ましい企業像”を体現する重要なシグナルとなります。それは単なるラベルではなく、「自社がアメリカ社会の一員として責任を果たしている」という証明に他なりません。今後、政治的・経済的な支援を受けるためにも、現地での製造・雇用体制を整えることは、競争力強化の要として注目されるでしょう。
「Made in USA」認定の要件とは?製造業に求められる実態
FTC(連邦取引委員会)によるMade in USAの定義
「Made in USA」の表記は単なるマーケティングラベルではなく、連邦取引委員会(FTC:Federal Trade Commission)が明確なガイドラインを設けて監督している、非常に厳格な認定表示です。FTCによると、製品が「Made in USA」と表示されるためには、「全てまたはほとんどすべての工程がアメリカ国内で行われていること」が要件とされています。この“ほとんどすべて”には、製品の原材料、主要な部品、組立て、最終工程などが含まれ、単なる最終仕上げのみでは認定されません。
この規定は誤認表示の防止を目的としており、実際に違反した企業には罰則や是正措置が課されることもあります。そのため、日本企業が「Made in USA」を取得・表示したいと考える場合、ガイドラインに基づいた事前確認と、表示の根拠となる製造実態の整備が重要です。
実際に取得するために求められる“生産工程”の割合
FTCのガイドラインでは定量的な「○%以上」といった明確な数値は示されていませんが、実務上はコストベースで製造工程の75%以上がアメリカ国内で完結していることが一つの目安とされています。これは、単に最終組み立てだけをアメリカで行い、主要部品を他国から輸入しているような場合には「Made in USA」と表示するには不十分であるということを意味します。
例えば、電子部品や自動車部品の製造であれば、基幹部品の加工や組立だけでなく、開発や設計、品質検査までを一貫してアメリカ国内で行っていることが求められます。製造業にとってはこの要件を満たすために、部品調達の見直しや工程の再編が必要となるケースも多く、実態に即した慎重な体制整備が不可欠です。
単なる輸出拠点では不可、本格的な製造拠点の必要性
日本企業の中には、アメリカ市場向けの製品を日本やアジアで製造し、米国に輸出するモデルを維持しつつ、「Made in USA」の表示を検討する企業もあります。しかし、前述のFTCガイドラインを踏まえると、これは現実的ではありません。つまり、「Made in USA」の表示は、単なる輸出拠点としてではなく、アメリカ国内で本格的な生産活動を行うことが前提とされるのです。
このため、部品の現地調達体制や、最終組立・品質検査・出荷体制の構築など、現地製造拠点としての自立性と完結性が強く問われることになります。単なる営業拠点では不十分であり、生産拠点としての人的・技術的リソースの整備が不可欠です。ここに、日本人技術者の派遣や、現地スタッフとの連携を見据えたビザ戦略の重要性が絡んでくるのです。
アメリカ国内に製造拠点を持つメリットと日本企業の最新動向
関税・政治リスクの回避とサプライチェーンの安定化
アメリカ国内に製造拠点を設ける最大のメリットのひとつが、国際的な関税政策や貿易摩擦といった政治的リスクからの回避です。近年の米中貿易摩擦では、中国からアメリカへの輸出に対して高い関税が課され、多くの企業がサプライチェーンの見直しを迫られました。こうした動きは今後も継続、あるいは再燃する可能性が高く、アメリカ国内での生産体制の整備は、有事に備えた“安定供給の保険”とも言えるでしょう。
さらに、現地調達・現地生産を通じて、物流リードタイムの短縮、在庫最適化、顧客対応のスピード向上が図れる点も見逃せません。とくに半導体、自動車、医療機器など、需要変動や規制対応がシビアな業界では、この即応性が競争力の決定要因となります。
地元雇用の創出による政治的評価とブランディング
アメリカで製造拠点を設け、現地従業員を雇用することは、企業としての社会的評価にも大きく貢献します。連邦・州レベルの政府関係者は、雇用創出に前向きな企業に対して、各種の支援制度やインセンティブを優先的に提供する傾向にあります。また、地域経済への貢献が可視化されれば、自治体や地元メディアからの評価も高まり、企業イメージの向上につながります。
さらに、サステナビリティや地域社会との共生といった観点からも、「アメリカでつくる」ことはブランディングの武器になります。とくに“アメリカ製”に対する消費者の信頼感が根強い業界では、「Made in USA」表記がマーケティング上の優位性を生み出すことも珍しくありません。
実際に進出を進める日本の製造業の最新動向
こうした環境の中で、すでに多くの日本企業がアメリカでの製造体制強化に動き出しています。たとえば、自動車部品メーカーの大手は、ケンタッキー州やアラバマ州に新工場を設立し、EV関連部品の現地生産を拡大しています。また、半導体装置や電子部品の分野でも、アリゾナ州やテキサス州への進出が相次いでいます。機械、素材、医療機器などの分野でも、米国子会社による現地生産体制を本格化するケースが増加中です。
これらの企業は、単に生産設備を設置するだけでなく、開発・品質保証・調達といった機能を含めた“総合拠点”として現地法人を位置づけ、持続的な競争優位の基盤を築こうとしています。その過程で不可欠となるのが、日本からの人材派遣によるノウハウ移植と、長期的な体制づくり。そのための「ビザ戦略」が、まさに次章のテーマとなります。
ビザ戦略がカギ!Made in USAに向けた就労ビザ活用の考え方
なぜ「人材の送り込み」が必要なのか(技術指導・立上げ・品質維持)
アメリカに製造拠点を設ける際、多くの日本企業が直面するのが「どうやって現地に日本の品質基準とものづくりの文化を根づかせるか」という課題です。工場設備を導入し、現地スタッフを雇用しただけでは、すぐに日本と同等の生産性や品質管理体制が確立できるとは限りません。立ち上げ初期には、製造ノウハウを持つ日本人技術者の現地派遣が欠かせず、工程設計や品質管理、設備調整、現地スタッフへの教育など、実務面での“日本流の移植”が必要とされます。
また、量産体制が整った後でも、定期的に本社から技術や経営層を派遣し、現地との連携を強化することが、品質の維持や経営の一体性を保つ上で不可欠となります。こうした「現場に人を送る」戦略を可能にするのが、適切な就労ビザの活用なのです。
現地採用だけでは補えない“日本流ものづくり”の移植
アメリカ人技術者の中にも優秀な人材は多く存在しますが、こと“日本流のものづくり”においては、工程管理、5S、現場改善といった暗黙知が大きな役割を果たします。これらはマニュアルだけでは伝えきれない領域であり、現地採用だけに頼って再現するのは困難です。特に「品質ゼロディフェクト」や「カイゼン文化」といった企業の競争力の根幹に関わる考え方は、現場での実践を通じて体得していく必要があります。
したがって、本社からの技術者や現場責任者の派遣は、単なる管理業務ではなく、「文化の伝承者」としての役割を担うものとなります。このような文脈においても、ビザ取得は単なる事務手続きではなく、経営戦略の中核的な要素と位置づけるべきです。
現場運営・生産管理・品質保証で求められる日本人技術者の存在
製造拠点の運営において、最も重要なのは「誰が現場を仕切るか」という人材の配置です。生産ラインの運転開始から安定稼働までには、きめ細かい調整が必要であり、日々の改善活動や不具合対応を的確にこなすためには、経験と判断力が求められます。特に、高い品質基準を求められる分野では、品質保証担当者の役割が極めて大きく、製品クレームの防止や、顧客監査への対応も含めて、日本的な“現場力”が問われます。
こうした現場運営を現地任せにせず、日本人スタッフが中核を担うことで、製品の安定供給とブランド価値の維持が可能となります。その前提として、戦略的なビザ取得と、人材の中長期的な派遣計画が必要となるのです。次章では、こうした戦略を支える具体的なビザの種類と活用法について詳しく解説します。
製造業に適したアメリカのビザとは?主要ビザの比較と活用例
L-1(社内転勤ビザ):技術・管理職を本社から駐在員として派遣
製造業が多く活用している就労ビザの一つが「L-1ビザ」です。これは、日系企業のアメリカ法人が本社や海外拠点からマネジメント職や専門職の社員を一定期間アメリカに赴任させるためのビザで、現地法人と日本本社の関係性が明確であれば比較的取得しやすい点が特徴です。
製造業では、工場立ち上げや工程管理、生産技術、品質保証などのポジションでL-1ビザが広く活用されています。申請には、日本法人と米国法人が「親子関係または姉妹会社」である必要があり、対象者は「直近3年のうち1年以上、日本本社で継続して勤務していること」が条件となります。
E-1・E-2(貿易・投資家ビザ):現地法人設立と連動したビザ戦略
E-1(貿易ビザ)およびE-2(投資家ビザ)は、日米間で締結されている通商条約をもとに発給される非移民ビザで、日本人が所有・運営するアメリカ企業での就労を可能にします。特にE-2ビザは、製造業が米国に現地法人を設立する際に、初期メンバーや技術者、経営管理者を送り込むための手段として活用されることが多いです。
このビザの利点は、比較的柔軟な運用が可能である点にあります。一方、ビザの維持には現地法人の「実体ある運営」と「日常的な事業活動」が必要であり、名ばかりのペーパーカンパニーでは許可が下りません。したがって、工場運営や雇用創出の実態と連動させた戦略的な設計が求められます。
B-1 Industrial Worker:据付・保守要員の短期派遣
「B-1 Industrial Worker」は、米国に納入した設備や機械の設置、調整、メンテナンスなどを行うために、日本本社の技術者を短期間派遣する際に使われるビザです。原則として米国内で報酬を受け取らず、かつ米国法人との直接的な雇用関係が発生しない業務に限られますが、据付工事やトラブル対応など、製造業における技術支援に適したビザです。
近年、入国審査が厳格化していることもあり、申請書類や活動内容の説明が不十分だと入国拒否のリスクもあります。そのため、派遣の目的、期間、作業内容について明確に説明できる書類の準備が不可欠です。あくまでも「短期の補助的業務」であることが前提となるため、恒常的な工場運営には不向きですが、初期導入や定期点検などには有効な選択肢となります。
B-1 in lieu of H-1B:高度専門職の短期派遣
「B-1 in lieu of H-1B」は、通常は米国で就労ビザが必要となる専門的な業務(たとえば設計支援や研究開発、プロセス改善)を、日本企業の社員が一時的に行う際に適用されるビザです。製造業における高スキル人材の短期派遣に活用されています。
原則として米国内で報酬を受け取らず、かつ米国法人との直接的な雇用関係が発生しない業務に限られますが、短期的な技術サポートや、パイロットラインでの試験稼働、顧客対応など、場面に応じた活用が進んでいます。
ビザ取得と人材派遣の成功事例|どのように進めるべきか
人事・法務・現地法人の連携と、外部専門家の活用がカギ
アメリカでのビザ取得・人材派遣プロセスは、日本国内の制度とは異なり、移民法や現地労務規制に関する理解が不可欠です。そのため、本社人事部門・法務部門・現地法人の実務担当者が一体となり、ビザ戦略を策定・運用していくことが求められます。さらに、移民法に精通した現地の専門家(弁護士や行政書士)と早期から連携を取り、要件の整理や申請手続き、監査対応まで万全を期すことが不可欠です。
実際、成功企業ほどこの「三位一体」の体制づくりに力を入れており、拠点立ち上げにかかる時間や手続きのトラブルを最小限に抑えています。逆に、各部門が独自に動いた結果、申請書類の齟齬や手続きの遅延、想定外の不許可事例に直面したケースも見られます。人材の派遣=経営インフラの構築と捉え、綿密な準備が不可欠です。
成功企業に共通する“現場主導の戦略的人材配置”
最終的な成功のカギを握るのは、「誰をいつ、どの役割で現場に投入するか」という人材配置の設計力です。とくに製造業では、品質や安全を維持しながら稼働を軌道に乗せるまでに相応の時間がかかります。そのため、短期の出張者ではなく、現地で腰を据えて働く中核人材の存在が欠かせません。立ち上げフェーズでは、単に語学力やマネジメントスキルがあるだけでなく、現地の文化・作業者とのコミュニケーションに柔軟に対応できる人材が求められます。
また、現場からのフィードバックを経営陣がすばやく吸い上げ、ビザ更新や人員追加の判断を柔軟に行える体制が理想です。「誰を、いつ、どこに、どのビザで派遣するか」を現場主導で戦略的に組み立てることで、拠点の競争力は大きく左右されます。
まとめ
「Made in USA」取得は、アメリカ市場での信頼獲得や政府補助制度の活用、関税回避といったさまざまな戦略的メリットをもたらす、製造業にとって重要な選択肢です。とくに、第2次トランプ政権下で国内製造業回帰がさらに進む中、現地生産体制の整備と、それにともなう雇用創出が、企業の評価に直結する時代となっています。
しかしながら、「Made in USA」取得には、FTCの厳格な基準を満たす製造実態が求められ、単なる輸出拠点では不十分です。工場の立ち上げや品質基準の確立には、日本本社からの人材派遣が不可欠であり、その実現には適切なビザ戦略が伴います。L-1、E-2、B-1など、目的や期間に応じてビザを選定し、現場主導での人材配置を進めることが、成功の鍵を握ります。
本記事で紹介した事例のように、法務・人事・現地法人が連携し、外部専門家と共に中長期的な視点で体制を構築することが、アメリカでの製造拠点を確実に根付かせ、企業価値を高める第一歩です。対米進出を検討する製造業の皆さまにとって、今回の情報が具体的な戦略立案の一助となれば幸いです。
なお、グリーンフィールドではアメリカビザの申請を専門に取り扱っており、アメリカ進出のためのビザ戦略のコンサルティングから、大使館・領事館のビザ申請までサポートしております。是非、お気軽にご相談ください。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
オススメの海外進出サポート企業
-
YCP
グローバル22拠点✕800名体制で、現地に根付いたメンバーによる伴走型ハンズオン支援
<概要>
・アジアを中心とする世界21拠点、コンサルタント800名体制を有する、日系独立系では最大級のコンサルティングファーム(東証上場)
<サービス特長>
・現地に根付いたローカルメンバーと日本人メンバーが協働した伴走型ハンズオン支援、顧客ニーズに応じた柔軟な現地対応が可能
・マッキンゼー/ボストンコンサルティンググループ/ゴールドマンサックス/P&G/Google出身者が、グローバルノウハウを提供
・コンサルティング事業と併行して、当社グループで展開する自社事業群(パーソナルケア/飲食業/ヘルスケア/卸売/教育など)の海外展開実績に基づく、実践的なアドバイスを提供
<支援スコープ>
・調査/戦略から、現地パートナー発掘、現地拠点/オペレーション構築、M&A、海外営業/顧客獲得、現地事業マネジメントまで、一気通貫で支援
・グローバル企業から中堅/中小/スタートアップ企業まで、企業規模を問わずに多様な海外進出ニーズに応じたソリューションを提供
・B2B領域(商社/卸売/製造/自動車/物流/化学/建設/テクノロジー)、B2C領域(小売/パーソナルケア/ヘルスケア/食品/店舗サービス/エンターテイメントなど)で、3,000件以上の豊富なプロジェクト実績を有する
<主要サービスメニュー>
① 初期投資を抑えつつ、海外取引拡大を通した円安メリットの最大化を目的とする、デジタルマーケティングを活用した海外潜在顧客発掘、および、海外販路開拓支援
② 現地市場で不足する機能を補完し、海外事業の立ち上げ&立て直しを伴走型で支援するプロフェッショナル人材派遣
③ アジア圏での「デジタル」ビジネス事業機会の抽出&評価、戦略構築から事業立ち上げまでの海外事業デジタルトランスフォーメーションに係るトータルサポート
④ 市場環境変動に即した手触り感あるインサイトを抽出する海外市場調査&参入戦略構築
⑤ アジア特有の中小案件M&A案件発掘から交渉/実行/PMIまでをカバーする海外M&A一気通貫支援
⑥ 既存サプライチェーン体制の分析/評価/最適化、および、直接材&間接材の調達コスト削減 -
株式会社ダズ・インターナショナル
東南アジア・東アジア・欧米進出の伴走&現地メンバーでの支援が強み
私たちは企業の海外挑戦を設計→実行→着地まで伴走支援いたします。
これまでの企業支援数は1,500以上です。
私たちは『どの国が最適か?』から始まる海外進出のゼロ→イチから、
海外進出後のマーケティング課題も現地にて一貫支援いたします。
※支援主要各国現地にメンバーを配置し、海外進出後も支援できる体制
------------------------------------
■サポート対象国(グループ別)
↳アジア①(タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・インドネシア・フィリピン・ラオス)
↳アジア②(日本・香港・シンガポール・台湾・韓国)
↳アジア③(ドバイ・サウジアラビア・インドバングラデシュ・モンゴル・ミャンマー)
↳欧米(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)
※サポート内容により、対応の可否や得意・不得意な分野はあります。
------------------------------------
■対応施策ラインナップ
①"市場把握"サポート
目的は"海外現地を理解し、事業の成功可能性を上げる"こと。
(以下、含まれる施策)
↳市場概況・規制調査
↳競合調査
↳企業信用調査
↳現地視察企画・アテンド
②"集客活動"サポート
目的は"海外現地で売れるためのマーケティング活動を確立"すること。
↳多言語サイト制作
↳EC運用
↳SNS運用
↳広告運用(Google/Metaなど)
↳インフルエンサー施策
↳画像・動画コンテンツ制作
③"販路構築"サポート
目的は"海外現地で最適な海外パートナーとの取引を創出"すること。
↳商談向け資料制作
↳企業リストアップ
↳アポイント取得
↳商談創出・交渉サポート
↳契約サポート
④"体制構築"サポート
目的は"海外現地で活動するために必要な土台"をつくること。
↳会社設立(登記・銀行口座)
↳ビザ申請サポート
↳不動産探索(オフィス・倉庫・店舗・住居)
↳店舗開業パッケージ(許認可・内装・採用・集客)
↳人材採用支援(現地スタッフ採用支援)
------------------------------------ -
GoGlobal株式会社
企業のグローバル戦略を一気に加速!最短2週間で海外進出・雇用を実現
GoGlobalは
「すべての海外進出」を
サポートします
ビジネスチャレンジには、悩みがつきもの。
海外進出を検討する方々からは、「どうやって人材を確保するのか」「どういった進出形態があり得るのか」「進出する上で気をつけなければならない点は何か」「どこから手をつければいいのかわからない」といったお悩みをよくお聞きします。
GoGlobalではこうした疑問点・課題を解決し、現地に会社を作る前段階からあらゆるケースに対応します。コストと時間を最小限に抑え、スピーディーかつ円滑な海外進出をサポートいたします。海外進出のDAY1から、成長・成熟フェーズまで一貫してGoGlobalにお任せください。 -
グローハイ株式会社
日本企業の世界での売上達成の実現に特化したサービスを提供します
日本に留まらず更なる成長を目標にグローバルに挑戦し続ける日本企業にとって信頼のおける長期的なパートナーであり続けることが私たちの企業使命だと考えております。日本企業の幹部や海外展開のプロジェクトリーダーと共にアメリカに本社を構える私たちの多様な専門性、経験、文化的背景を持つ人材、過去にアメリカや中国やヨーロッパで培ってきたビジネスプロセス、現地ネットワークを最大限に活用し各クライアント特有のビジネス目標を達成させます。
グローハイは戦略コンサルティング、プロジェクトマネジメント、オペレーションサポートと幅広い分野で海外で成功する為の下記のようなサポートを実施しております。
・アメリカ、ヨーロッパでの売上達成
・アメリカ、ヨーロッパでの販路拡大
・アメリカ、ヨーロッパでのECサイト構築とデジタルマーケティングサポート
・効率的かつ低リスクでのアメリカ進出、ヨーロッパ進出
・戦略的パートナーマネジメント
・アメリカでのM&A
・アメリカでの会計、人事、法務の業務委託
グローハイはこれまでに中小企業から大企業まで様々な規模、業界の数多くの日本企業のアメリカ進出、中国進出、ヨーロッパ進出を成功に導いてきました。 -
Link Compliance Group
グローバル展開をもっと簡単に!最速・最安で海外進出・雇用をサポート
リンクコンプライアンスは、香港、マレーシア、シンガポール、米国、中国を中心に、PEO/EOR(雇用代行)、人事労務アウトソーシング、人材紹介、RPO(採用代行)を提供するHRソリューション企業です。2013年の設立以来、「より速く、より手頃な価格で、より効果的なサービス」をモットーに、企業の人材管理をサポートしています。
【主なサービス】
1. PEO/EOR(雇用代行)
・海外での雇用・人事労務・福利厚生を一括代行し、迅速かつ低コストで対応。
2. 人事労務アウトソーシング
・給与計算、福利厚生、人事コンプライアンス、リスク管理など。
3. 人材紹介
・現地に精通したコンサルタントが迅速に人材をマッチング。
4. RPO(採用代行)
・採用計画から運用管理まで一貫サポート。フレキシブルな契約と競争力のある料金が強み
(例:急成長中のIT企業がエンジニアを大量採用するため、RPOを導入。)
【その他提供可能なサービス】
5. 海外企業の日本進出支援(EOR)
・海外企業が日本での事業展開をスムーズに進めるため、法人設立なしで従業員を雇用。
・日本市場進出を低コストかつ迅速に実現します。
6. 日本国内の外国人雇用・ビザ申請サポート
・日本国内で外国人を雇用する企業向けに、ビザ(在留資格)申請・更新のサポートを提供。
まずはお気軽にお問い合わせください。