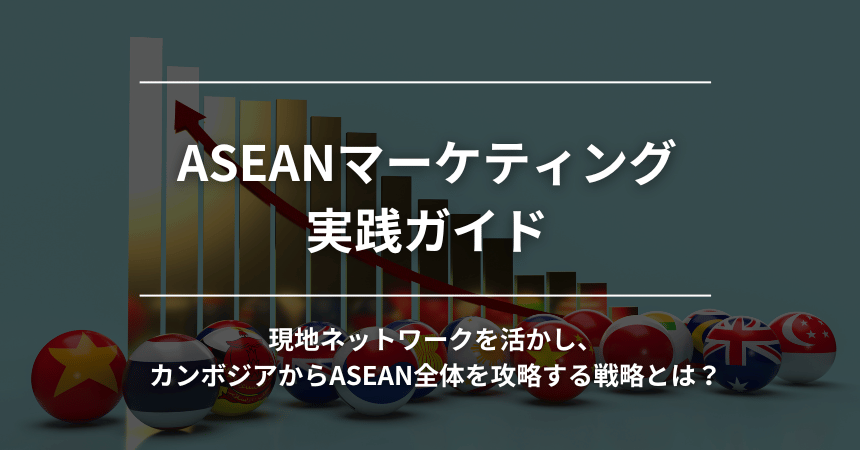海外進出のメリット&デメリット〜日本企業が海外進出する2つの理由と目的とは?〜

日本企業が海外進出をするメリットとデメリットをメインテーマに、「日本企業が海外進出をする大きな2つの理由」「海外ビジネスの流れと海外事業計画の進め方(フロー)」についてわかりやすく解説します。
極論すれば、日本企業が海外進出する理由と目的は、「国外に市場を求める」か「国外に生産拠点を求めるか」のいずれか2つでしかありません。
ご存じの通り日本の市場は縮小しています。その要因としては少子高齢化による生産年齢人口の低下、最低賃金の上昇率の低下からくる消費購買力の低下などがあります。
それに対して、世界の市場は拡大しています。その要因としては、全てが日本と逆で、人口増にともなう生産年齢人口の増加、最低賃金の上昇率の高さからくる消費購買力の増加などがあります。
このような状況の中で、多くの日本企業が海外に活路を見い出すことはーー特にここ20年ほど人口が増え続け、生産力および消費購買力の上昇および経済発展が期待されているアジア諸国へ進出することはーー自明の理と言えるでしょう。
国内市場ではなくグローバルマーケットへの販路拡大を目指し、自社の商品およびサービスを海外展開していくことは、今後多くの日本企業にとって、大きなメリットとなるはずです。
Photo by Ben White on Unsplash
▼海外進出のメリット&デメリット〜日本企業が海外進出する2つの理由と目的とは?〜
▼アナタの海外ビジネスを成功させるために
1. なぜ海外進出をするのか? 日本企業が海外ビジネスをする2つの理由とは?
日本企業が海外進出をする大きな理由は2つ
海外進出のメリット・デメリットについて考察する前に、なぜ日本企業が海外進出をするのか? その2つの大きな理由について解説します。
結論から言うと、日本企業が海外進出する理由としては以下の2つになります。
① 自社の商品・サービスの販路開拓・拡大のための市場を獲るために進出する
② 自社の商品・サービスの生産拠点を海外に移転するために進出する
以下より簡潔に見ていきましょう。
自社の商品・サービスの販路開拓・拡大のための市場を獲るために進出する
ご存じの通り、少子高齢化によって、日本の市場は年々シュリンク(縮小)しています。それとは対照的に、海外の、特に東南アジア諸国などの新興国は、人口も増加傾向にあり、最低賃金のベースアップも年々ベースアップしているため、消費者たちの消費購買能力も上昇しています。
したがって、国内市場が頭打ちになりつつある日本の企業が、自社の商品・サービスの販路拡大を画策するならば、国内市場ではなく海外市場に活路を求めるのはごく自然な成り行きと言えます。
自社の商品・サービスの生産拠点を海外に移転するために進出する
一昔前「チャイナプラスワン」というワードが話題となりました。これまでの中国に集中していた自社の製造拠点を、集中投資のリスクを避けるため、中国以外に拠点を移転して投資をするという経営戦略を指します。
中国が「世界の工場」と言われていた時期は、安い人件費と生産コストをインセンティブに、多くの日本企業が中国現地に生産工場を置いていました。しかし近年、中国は驚異的な経済成長を遂げ、人件費も上昇し、「海外の生産拠点」としてのメリットは次第に薄くなりつつあります。
その代わりに脚光を浴びたのが、相対的に人件費や生産コストが低いとされるベトナムやタイ、カンボジアやミャンマーといった東南アジアの新興国です。日本企業以外もたくさんの外資企業がこれらの国々に生産拠点を置きつつあります。
海外進出する理由をしっかりと認識することがファーストステップ
極論すれば、海外進出の目的とは、「国外に市場を求める」か「国外に生産拠点を求めるか」のいずれか2つでしかありません。
ちなみにかつて「世界の工場」と呼ばれていた中国は、いまや「世界の市場」と呼ばれるまでに、グローバルマーケットとしての価値を高めつつあります。かつて話題となった〝爆買い〟や、いまだ衰えを知らぬ〝中国への越境ECブーム〟も、その延長線上にあります。
いずれにせよ、あなたの海外進出が、「市場を求めて」なのか、「生産拠点を求めて」なのか、あるいはその両方なのかを認識することがファーストステップです。
それをしっかりと認識すれば、おのずと自社の海外進出の目的が明確化されていきます。
2. 海外進出のメリット
日本企業が海外進出をする2つの大きな理由を理解したら、ここからは海外進出のメリット・デメリットについて見ていきましょう。まずは5つのメリットからです。
メリット1: より大きな市場規模での販路開拓
2019年6月に国連が公表した「世界人口予測」によると、世界の人口は2019年の77憶人から、2030年に85憶人(10%増)、2050年には97憶人(26%増)、2100年には109憶人(42%増)に推移していくと予測されています。
2020年6月に総務省が発表した日本の総人口は1億2,593万人(概算値)となっていますが、すでに9年連続で減少しており、2060年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は40%近い水準になると推計されています。
近年、アジアの各都市では、法定賃金の引き上げが続いており、タイやベトナムやインドネシアやカンボジアといったアジア諸国においても、最低賃金のベースアップが毎年実施されています。
対する日本の最低賃金は、それらのアジア諸国と比較して依然として高いものの、それらの国々との最低賃金ベースの格差は年々縮まりつつあります。
今更言うまでもなく、日本の市場は縮小しているのです。
その要因としては少子高齢化による生産年齢人口の低下、最低賃金の上昇率の低下からくる消費購買力の低下などがあります。
それに対して、世界の市場は拡大しています。
その要因としては、全てが日本と逆で、人口増にともなう生産年齢人口の増加、最低賃金の上昇率の高さからくる消費購買力の増加などがあります。
今後、日本の労働市場において積極的にAI(人工知能)やBI(ベーシックインカム)を相次いで導入したり、より多くの優秀な外国人人材を受け入れたとしても、国内市場における消費力の落ち込みも生産人口の低下も避けることは難しいというが現実的な見方です。
このような状況の中で、多くの日本企業が海外に活路を見い出すことはーー特にここ20年ほど人口が増え続け、生産力および消費購買力の上昇および経済発展が期待されているアジア諸国へ進出することはーー自明の理と言えるでしょう。
国内市場ではなくグローバルマーケットへの販路拡大を目指し、自社の商品およびサービスを海外展開していくことは、今後多くの日本企業にとって、大きなメリットとなるはずです。
メリット2: 人件費・原材料費などのコストの削減
ふたつの目のメリットは、日本と比較した際の、海外(アジア諸国)の人件費および原材料費などの生産コストの安さです。
先述したように、アジア各国の最低賃金は軒並み上昇を続けています。確かにOECD(経済協力開発機構)加盟国である先進国で比較した場合、日本の最低賃金は決して上位ではありません。
しかし、発展途上にある中国を含めたアジア各国と比較した場合は、依然日本の最低賃金はトップでもあるのです。
単純に、これらの発展途上国に進出した場合、日本国内より人件費を低く抑えることが可能です。また、原材料となる一時産品(鉱物資源・農産物など)も、日本国内よりも海外現地のほうが安く調達できます。
昨今の海外進出における「人件費と原材料費の上昇が要因となった事例」として「中国の生産移管」があります。
かつては、その豊富な労働力と安価な人件費から〝世界の工場〟としてたくさんの外資企業が進出していた中国ですが、その著しい経済発展(および米中貿易戦争&新型コロナ感染拡大)により、多くの企業が東南アジア諸国に生産拠点を移動させつつあるのが現状のトレンドです。
よりシンプルに言えば、中国の人件費と生産コスト(原材料費含む)が上昇したため、多くの外国企業が、人件費と生産コストがより低い国々へと拠点および市場を移転させたのです。
もちろん先述したように中国の人件費および生産コストは、日本のそれと比較した場合、まだまだ低い水準ですし、依然多くの外国企業が中国に生産拠点と販売市場を持っています。
重要なポイントは、単純に、日本よりも人件費と生産コストが低い国に進出した方が、より多くの利益を得ることができるということです。
もちろん、ただコストが安いからと言って、それだけで海外進出を決めるのは早計です。しかしそれが大きなメリットであることは言うまでもありません。
メリット3: 税率の低さによるコストの削減
近年、世界各国の法人税率は引き下げ傾向にあります。2024年時点での主要国の法人税率を比較すると、日本は約29.7%であり、OECD加盟国の平均である23.7%を上回っています。
一方、アジア諸国では以下のような税率となっています。
中国:25%
韓国:26.5%
タイ:20%
台湾:20%
シンガポール:17%
香港:16.5%(課税所得200万香港ドルまでの税率は8.25%)
フィリピン:25%
これらの国々は、外資誘致のための優遇制度を積極的に導入しています。
例えば、タイ政府は特定の条件を満たす外資系企業に対し、法人税の免除や減免を行っています。 また、中国では「外商投資を奨励する産業目録」に基づき、特定の産業への投資に対して税制上の優遇措置が提供されています。
このように、アジア各国は自国の経済発展のために、外資のための様々な税優遇制度を実施しているのです。つまり、海外進出をして、現地に拠点を持つことで、節税もできるというメリットがあるのです。
メリット4: 新規プロジェクト・商品開発につながるシナジー効果
誤解を恐れずに言えば、海外進出を自社のみの単体で行うことは非常にまれなケースです。後述しますが、自社の商品・サービスを海外展開するには、現地のビジネス事情に詳しいパートナーもしくは現地企業との何らかの提携(アライアンス)を結ぶことがベターであるからです。
大きな理由としてはふたつあり、ひとつは単純に現地の事情に詳しいパートナーがいないとビジネスを成功させるのが難しいこと。もうひとつは、海外現地のパートナーおよび現地企業と提携することで、いわゆる〝シナジー効果〟を得ることができるからです。
シナジー効果とは、ある2つの要素を組み合わせることによる相乗効果を指します。それは大きく分けて「事業シナジー」と「財務シナジー」とに分けられます。
事業シナジーには、「売り上げの増加」「ノウハウの統合」「コスト削減」「スケールメリット」「人材の活用」などがあり、財務シナジーには「余剰資金の活用」と「節税」などがあります。
「節税」や「売り上げの増加」「コスト削減」などは既にメリットとして解説しましたが、文化やトレンドが日本とは全く異なる海外での事業活動を通して、現地パートナーと「ノウハウを統合」させることで、新たな新規プロジェクトやプロダクト開発が生まれる可能性は大いにあります。
これもまた後述しますが「人材の活用」においても、日本とは異なる現地人材をマネージメントすることで、否応なく自社のノウハウや経験値がアップしていくことは言うまでもないでしょう。
これら海外ビジネスを通したあらゆるシナジーはすべてメリットと言っても過言ではありません。
メリット5: 企業価値・ブランドイメージの向上
誤解を恐れずに言えば、海外に拠点を持つことで、自社および商品・サービスのブランドイメージは向上するはずです。グローバリズムが浸透している世界において、海外でのマーケットを開拓しているという事実は、自社商品およびサービスが持つ、独自性・差別ポイント・強み・価値といった部分でプラスに働きます。
また海外進出をすることで得た経験や知識は、必ずや自社および事業に変化をもたらします。相対的にその多くが内向きな日本企業において、日本を飛び出して海外でチャレンジすることが、自ずと自社の企業価値を高めていくことは想像に難くないですし、それが大きなメリットとなる得ることも充分にご理解いただけると思います。
3. 海外進出のデメリット
5つのメリットに続いては4つのデメリットを見ていきましょう。
デメリット1: 人材管理のコスト
日本の労働市場と比較した場合、多くの国々において人材は流動的です。いわゆる終身雇用や年功序列という雇用形態および考え方を採用している国は少なく、ひとつの会社に長く勤め続けるという価値観も薄く、人材の定着率も決して高くはありません。
給与などの待遇面で満足しなかったり、他に条件のよい職場があれば、積極的に転職するのが多くの国では一般的と言ってよいでしょう。
後述しますが、そもそも言語や文化の異なる外国人スタッフをマネージメントすることは様々な面でコストがかかりますし、日本人スタッフを海外現地に駐在させるとしても、それぞれの人材の労働環境はもちろん、生活面や精神面でのケアを充分に心がけなければなりません。
いずれにせよ、人材にまつわる雇用形態の制度構築などを含めた労務管理は、日本以上に注意して実施していく必要があります。
デメリット2: 人件費の上昇
前項のメリット部分にて解説した、海外進出における「人件費」についてですが、これはメリットであると同時にデメリットともとらえられます。
先述したように、アジア各国の最低賃金は軒並み上昇を続けています。今後、新興国の安価な労働力のみを目的とした海外進出は減少していくでしょう。
それこそ製造業やIT業のように、海外で製品やソフトウェアを「安く」製造することによって利益を増やすことは今後困難になっていきますが、小売業やサービス業、飲食業などといった、現地の市場を対象とした海外ビジネスにおいては、「最低賃金」の上昇は必ずしもマイナスではありません。
むしろ見方を変えればメリットととらえることも可能です。なぜなら現地従業員の所得が増えるということは、現地の消費購買力が強化され、将来的に、小売業やサービス業、飲食業といった業種の顧客単価の増加に繋がっていくからです。
デメリット3: 法規制やカントリーリスクによる為替変動
海外現地の法制度や規制、現地の政治状況や治安などのカントリーリスク、それらにともなう経済情勢も、大きなデメリットとなり得ます。
カントリーリスクとは、その国の政治や経済の変化によって、証券市場や為替市場に混乱が生じることで、そこに投資した資産の価値が変動するリスクを指します。極端な話ですが、それこそデフォルト(債務不履行)が発生して国全体の経済が破綻してしまうことも世界では珍しくないのです。
また、その国の法制度や規制の内容次第で、事業を展開したい商品やサービスによっては、通常以上に参入障壁が高くなったり、場合によっては事業展開できないケースもあり得ます。特に製造業以外は、業種業態によって、外資比率が決められていたり、現地従業員の外国人比率にも規制があったりするので、事前の充分な情報収集が必要です。
デメリット4: 言語や文化、商習慣の違い
言語の違いはもちろんのこと、その国独自の文化(宗教なども含む)や商習慣についての理解がないと思わぬトラブルが発生します。
海外ビジネスにおいては、英語でのコミュニケーションが基本となるケースがほとんどですが、もちろん現地の言葉が話せることにこしたことはありません。
また文化や風俗の違いについても、その国の伝統や宗教やジェンダーの価値観などを理解しなければ、本当の意味での信頼関係を築くことは難しいでしょう。完全に理解するのは難しくても、積極的に理解を深めようと努力している姿勢を見せることは重要です。
また、商談やミーティングの際に必要となるのは、その国ならではの商習慣についての知識です。日本では常識とされることも海外では非常識であるケースも多々あります。言語や文化同様に、その国独自の商習慣についても事前に学習して、常日頃から意識することを心がけましょう。
4. 海外進出の流れと事業計画の進め方
海外進出のメリット・デメリットを理解したら、最後は簡潔に「海外進出の流れと事業計画の進め方」について見ていきましょう。
下記のフローは一般的な例であり、あなたの海外ビジネスの業種業態、海外事業で取り扱う商品およびサービスによって異なりますが、基本的な流れは下記に準じるととらえていただいて結構です。
① 海外進出の目的を明確にする
先述したように、極論すれば、海外進出の目的とは、「国外に市場を求める」か「国外に生産拠点を求めるか」のいずれか2つでしかありません。
それらを充分に認識した上で、「なぜ海外進出をするのか?」「海外進出の最終的な目的とは何か?」を明確化しましょう。
② 情報収集をする
「どこの国にビジネスチャンスがあるのか?」「自社の商品・サービスで海外展開する際に進出すべき国は?」「◯◯国に進出したいが、どうやって進めればいいのか?」――。海外ビジネスを検討しはじめた日系企業は、最初にこうした疑問にぶつかるでしょう。そのため、まず行うべきことは「情報収集」です。
③ 市場調査を実施
海外展開したい商品・サービスが、すでに国内で認知されていても、それが海外でも成功するとは限りません。そもそも自国での方法論が通用しないケースの方が多いはずです。
自らの海外事業を成功させるには、進出国の法規制や規格にフィットした商品・サービスであることに加えて、その国のユーザーのニーズ・生活習慣・趣味趣向などにもマッチしたマーケティングおよびビジネス展開をしなければなりません。
2020年代を迎えて世界中であらゆる物事が絶えず変わり続けています。そんな時代の海外ビジネスにおいて「海外市場調査」は必要不可欠なタスクです。
④ 海外視察を実施
海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima〜出島〜」にて実施した「海外展開をスタートさせた企業が、まず何をしたか?」という調査において、70%以上の企業が「現地視察」と回答しています。
また「海外視察は何回実施したか?」という質問には40%以上の企業が「7回以上」と回答しています。進出先を検討している段階でも決まったあとでも、現地を訪れるということが重要視されていることがわかります。
そんな「海外現地視察」ですが、通常の海外出張と比較すると、その訪問先は多岐に渡ります。
それこそ、同業他社から、現地市場や店舗、さらには公的機関(JETROや現地政府高官など)や教育機関、あるいは不動産やレンタルオフィス、さらには現地の知人や、進出予定先のコンサルや会計士といった現地パートナーなど、枚挙に暇がありません。 …とは言うものの、いざこれらの訪問先のアポイントを取得し、それぞれの担当者に会いに行くことは、決して簡単なことではありません。
なかなか難しそうな「海外現地視察」ですが、その高そうなハードルを一気に下げる方法があります。それが、訪問予定先のコンサルや会計士といった「現地パートナー」を有効に活用することです。
⑤ 海外展示会への出展
海外での展示会や見本市への出展は、限られた時間やコストの中で海外進出をするために、大変有効な方法です。進出したい国が決まったら、市場調査を兼ねて、現地の展示会に出展してみるのもひとつの手です。
現地のマーケットの肌感を感じながら市場調査ができるので、有益な海外進出のヒントが得られるはずです。いきなり現地に進出する際のリスクやコストをおさえつつ、現地の最新情報が得られるのが展示会・見本市の大きなメリットです。
⑥ 海外進出に必要な「予算計画の策定」
「予算」とは、「事業の将来を踏まえた経営ビジョンをもとに、具体的な目標を数字として表現したもの」になります。
海外ビジネスに限らず、すべてのビジネスは「具体的な数値目標=予算」が存在するからこそドライブしていきます。もちろん、「この海外ビジネスを成功させるぞ!」といった情熱やモチベーションは必要不可欠です。
しかし、それらはいわば燃料のようなもので、「予算」という目的地がなければ、どこにも辿り着くことはできません。
予算を立てるメリットは、それこそ様々なものが存在しますが、あえてひとつに絞るなら、「やるべきことが明確になる」、これに尽きます。
自らが志した海外事業での目標を達成するために「何を・どのように・どれくらい」実行すればいいのかがクリアになると同時に、仮に達成できなかった場合は、それらを改善するための検証も可能になります。
いわば「予算を立てる」とは、その利益を達成するために、売上をいくらにするのか、さらには経費をいくらにするのか…といったことを決定する作業です。
それにはまず、中長期的な達成目標を策定した上で、それらを〝いつまでに〟〝どのように〟〝どのくらい〟達成するのかといったプランを立てます。
それこそが「予算計画」なのです。
⑦ 資金調達(助成金・補助金の申請をする)
海外ビジネスには、やはり先行投資が必要です。いかに情熱があり、また素晴らしいコンテンツを持っていたとしても、先立つお金がなければ何もできません。
そもそも「海外展開資金の作り方」にはどのような方法があるでしょうか? 代表的なものを以下に挙げてみましょう。
・銀行からの融資
・助成金・補助金の活用
・現地企業とのジョイントベンチャー
・ベンチャーキャピタルからの出資
・リースバック
・親子ローン
・株式上場
それぞれ特徴があり、当然、実施できる企業とできない企業があることでしょう。
そもそも、海外進出の資金調達に苦労する中小企業にとっては、返済不要の「補助金」「助成金」の活用こそが、海外進出成功のカギとなると言っても過言ではありません。
下記の記事コンテンツにて、「海外進出」で活用できる「補助金」「助成金」と題して、海外での起業や会社(法人)設立のための資金調達を支援する補助金・助成金について詳しく解説しているので、ぜひ貴社の海外進出の資金調達にお役立てください。
潤沢な資金調達は「海外ビジネス」を円滑に進めるための第一歩でもあります。よりスピード感のある展開を目指すためにも、正しい知識を持ち、ベストな方法を選択することから、勝負は始まっています。
⑨ 海外現地への会社設立(法人登記)
海外に進出する際には、現地法人(子会社)・支店・駐在員事務所など、様々な形態があります。
いずれのケースでも、現地進出を検討する際には、現地での手続きや法人登記などは必要不可欠です。しかしながら現在、法人登記について国際的な基準は設けられておらず、進出を検討している国や地域の制度に則って手続きを行わなくてはなりません。
もともと法人登記は複雑であることに加えて、さらに使用言語も異なるとなると、個人で手続きを進めるのは、非常に困難を伴います。
海外での会社設立は、その道のプロフェッショナルである登記代行会社に依頼することが一般的と言えるでしょう。海外進出を検討する際には、まずは海外現地の登記代行会社に問い合わせてみることが進出への近道となるケースもあります。
いずれにせよ、海外で会社設立(法人設立)するための最低限の知識を持っておくことは必要不可欠であることは言うまでもありません。
5. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
貴社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
今回は「海外進出のメリット・デメリット」をメインテーマに、「日本企業が海外進出をする大きな2つの理由」「海外進出の流れと事業計画の進め方(フロー)」について解説しました。
「Digima〜出島〜」には、厳正な審査を通過した、様々な支援を行う優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。
「海外へ進出したいが何から始めていいのかわからない」「自社商品・サービスが海外現地でニーズがあるかどうか調査したい」「海外進出の戦略立案から拠点設立、販路開拓までサポートしてほしい」「海外ビジネスの事業計画を一緒に立てて欲しい」…といった海外ビジネスにおける様々なご質問・ご相談を承っています。
ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、貴社にピッタリの海外進出サポートサポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。
(参考文献)
・「諸外国における法⼈実効税率の⽐較」財務省
・「法人税率-国のリスト」TRADING ECONOMICS
・「法人税の実効税率比較(2024年版)日本VS主要国」johoseiri.net
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
もっと企業を見る