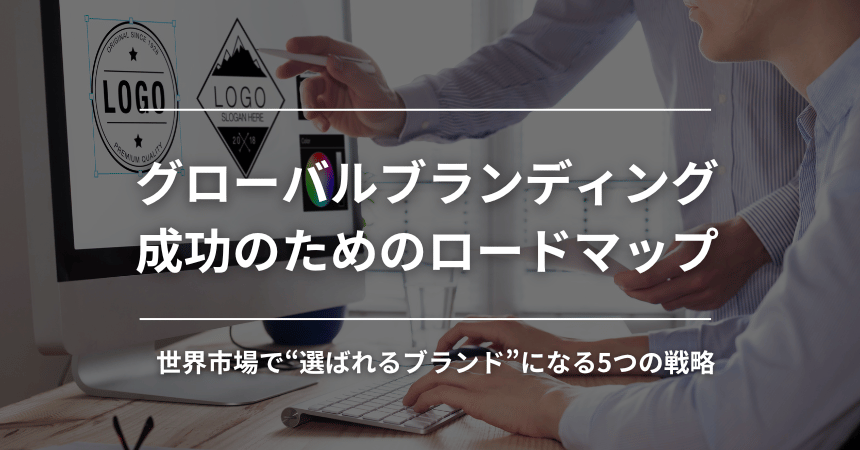【2025年版】グローバル人事の現在地と未来|アジアから広がる変化と組織の成長

企業のグローバル化が加速する中、人事部門の役割はかつてないほど多様化し、戦略的重要性を増しています。従来の「従業員を支える管理部門」から、「経営と並走し組織成果を生み出すパートナー」へと進化を遂げているのが、現代のグローバル人事の姿です。特にアジアでは、人口動態の変化やデジタル化、雇用観の多様化が急速に進んでおり、そこから生まれる新たな課題と可能性は、日本の人事にとっても見逃せないテーマです。
本記事では、「アジアのHR最前線」をキーワードに、変容するHRの役割、アジア人リーダーの台頭、柔軟な働き方の普及、AIとデータによる人事の再定義などを取り上げます。制度や仕組みの議論にとどまらず、人と組織の可能性をどのように広げていけるかという視点から、ヒントを探っていきます。
▼ 【2025年版】グローバル人事の現在地と未来|アジアから広がる変化と組織の成長
1.変化するグローバルHRの役割と期待値
「人を支える」から「戦略を動かす」へ
従来、人事部門は「従業員を支える裏方」としての位置づけが主流でした。しかし、特にアジアの成長国ではこの役割に大きな変化が起きつつあります。たとえばフィリピンでは、BPOや外資系企業の進出を背景に、人事が単なる管理機能にとどまらず、経営陣とともにビジネス成果にコミットする「組織づくりのファシリテーター」へと進化しています。戦略人事、組織開発、リーダーシップ育成といった領域での関与が求められ、経営と現場をつなぐ存在としての役割が広がっています。
ビジネス成果と直結する人事へ
グローバルなビジネス環境において、人事の評価の軸も変わりつつあります。これまでは採用人数や研修時間など「活動量」に基づく評価が主流でしたが、今では「ビジネス成果にどう貢献したか」が問われるようになりました。たとえば、離職率の低下やスキルギャップの解消といった成果指標がKPIとして用いられるようになり、従業員満足度やエンゲージメントの向上も経営課題として重視される傾向にあります。人事が自らの機能価値を示すには、単なる業務遂行だけでなく、「人と組織にどのような変化をもたらしたか」という視点が不可欠になっています。こうした変化は、日本企業にとっても無視できないものであり、日々のオペレーションに追われる現場の実情を踏まえつつ、戦略的に組織を設計し直す視点が求められています。
アジア全体に広がる“戦略人事”の潮流
こうした動きはフィリピンに限らず、タイ、マレーシア、インドネシアなどでも見られます。従業員の価値観やキャリア志向が多様化する中、画一的な制度や仕組み、マネジメントだけでは対応できない時代に入りました。そこで期待されるのは、変化を支え、制度と文化の両面から環境を整える人事の役割です。たとえば、Z世代の台頭によって「柔軟な働き方」や「個人の成長機会」を重視する傾向が強まる中、それに応える制度設計や評価体系の見直しが人事主導で進められる場面も増えています。こうした動きは単なるトレンドではなく、組織の未来を左右する構造変化であり、持続的な成長につながる取り組みとなっています。
2.アジア発リーダーシップの時代へ
地域本部に広がるアジア人リーダー
近年、多国籍企業では、経営層にアジア出身のリーダーが増えています。特に2016年以降、ASEAN諸国やインドを拠点とする地域本部において、CEOやCOO、CHROなどの経営層にアジア出身の人材が起用されるケースが増え、西洋主導だった従来の組織構造に変化が見られるようになりました。この背景には、急速に成長するアジア市場の現場感覚に精通した人材が、より的確でスピーディな意思決定を行えるという実利的な理由があります。また、各国に根差した文化的文脈を理解し、ローカルとグローバルの橋渡しを担えるリーダーへの需要が高まっていることも一因です。
アジアのリーダーが変えるマネジメント像
アジア出身のリーダーが増えることで、マネジメントスタイルそのものにも変化が起きています。従来の欧米型のトップダウン的なリーダーシップから、現場の状況を踏まえたボトムアップ志向や、共感・調和を重んじるスタイルが広まりつつあります。たとえばインドネシアやタイでは、チームメンバーの自律性を尊重しながらも、文化的背景に配慮した柔軟な意思決定が求められることが多く、それに適応できるリーダーが成果を上げています。これは「欧米型かアジア型か」という対立ではなく、双方の強みを融合させた新しいリーダー像と言えます。
日系企業に求められる視点
こうした流れの中で、アジアでビジネスを展開する日系企業にも、現地発のリーダー育成やHR戦略の再構築が求められています。日本的な合意形成やチームワークといった日本的な価値観は引き続き評価されているものの、若手人材の早期登用、成果重視など、現地の期待とはズレが生じやすい部分もあります。問われているのは、現地の人材の強みを引き出し、日本的な価値観とどのように掛け合わせていくかという視点です。
3.働き方の未来とHRの再設計
柔軟な働き方が“標準”になる時代へ
アジア各国では、Z世代やY世代の価値観の変化により、柔軟な働き方へのニーズが急速に高まっています。リモートワークの浸透に加え、ギグワークやプロジェクト単位の働き方が広がり、従来の「正社員中心」「定時勤務・オフィス常駐」といったモデルでは、多様な人材の期待に応えることが難しくなっているのが現実です。企業にとっては、フレキシブルな勤務制度の導入だけでなく、評価制度やマネジメントのあり方も再構築する必要があります。柔軟性を仕組みに落とし込むと同時に、社員が声を上げやすい文化をつくることが求められています。
雇用制度の再構築が急務
柔軟な働き方が広がる一方で、雇用制度がその変化に追いついていない国も多く見られます。たとえばフィリピンでは、正社員を前提とした労働法が依然として強く、業務委託やパートタイムといった柔軟な雇用形態に対応した法整備が遅れています。こうした制度のギャップは、企業側にとってもコンプライアンス上のリスクや、制度運用の複雑さを生む要因となります。また、働き方の自由度が求められる一方で、労働者の安全網をどう担保するかという新たな課題も浮上しています。人事には、「現行制度をどう守るか」だけでなく、「制度をどう進化させるか」という視点が求められています。
“起業家的マインドセット”とチームワーク文化の融合
変化の時代において、企業が継続的に成長していくためには、社員一人ひとりが自ら考え、動く「起業家的マインドセット」を持つことが重要です。アジアの成長企業では、このような精神を育むための人材開発プログラムや制度づくりが進んでいます。一方で、日本企業が長年培ってきた「チームワーク」の文化も、組織としての持続性を支える大きな強みです。今求められているのは、これら二つの価値観を融合させ、個人の自律性と組織の安定性を両立させる人材戦略です。HRはその接点となる役割を担い、評価制度や育成施策を通じて両者を結びつけていく必要があります。個と組織が共に進化する環境づくりこそ、これからのHRにとって最も重要なミッションの一つです。
4. AIとデータが導くピープルアナリティクスの時代
AI導入で変わる人事業務の在り方
AIの活用は、これまで直感や経験に依存していた人事領域に新たな視点と精度をもたらしています。たとえば採用では、履歴書やエントリー情報をもとに候補者の適合度を分析し、面接前のスクリーニングを効率化する事例が増えています。また、社員のスキル習得状況やキャリア傾向を可視化し、配置や育成に活かす動きも進んでいます。アジア諸国でも営業やカスタマーサービスの分野を中心にAIの導入が進んでおり、人事部門においてもその波は加速しています。重要なのは、AIを「人を置き換えるもの」ではなく「意思決定を支えるパートナー」として捉えることです。定型業務をAIに任せることで、人事はより戦略的な領域にリソースを集中できるようになります。
「職が奪われる」ではなく「進化する」HR
AIの普及によって、しばしば「人の仕事が奪われるのではないか」という懸念が語られます。しかし、実際には多くのHR専門家が指摘するように、AIによって人事部門の役割が「代替」されるのではなく「進化」するという視点が重要です。AIは大量データの分析や予測に優れていますが、共感や信頼構築は人間にしかできない領域です。特に多様な文化・価値観が交錯するグローバル組織では、微妙なニュアンスや信頼構築を担う“人の感性”が不可欠です。アジアにおけるHRの現場では、こうした「テクノロジーと人の融合」に前向きな姿勢が多く見られ、変化への柔軟な適応力が文化的な強みとして発揮されています。
ピープルアナリティクスの可能性
ピープルアナリティクスとは、社員の行動や実績、属性データを分析し、人材に関する意思決定をデータドリブンで行う手法です。これにより、採用、育成、配置、離職防止といった多岐にわたる人事施策が、より論理的かつ客観的に設計できるようになります。たとえば従来は「研修時間」や「面談回数」といった“活動量”に注目されていましたが、今では「スキルギャップの解消度」や「業務成果への貢献度」といった“成果ベースのKPI”へと移行しつつあります。ただし、質の高い分析には信頼できるデータ基盤が不可欠であり、データの収集方法や管理体制そのものを見直す必要があります。人事におけるデジタル変革は、単なるツール導入ではなく、組織文化そのものを再定義するプロセスとも言えるでしょう。
5.多様化する人材ニーズとマネジメントの再構築
ニューカラー人材とシルバーワーカーが変える組織構造
人材の定義が大きく変わりつつある今、企業は従来型のキャリアパスや役職制度の見直しを迫られています。とりわけ「ニューカラー人材」と呼ばれる、高度なITスキルやデータリテラシーを持つ専門職人材は、もはや管理職以上の待遇や裁量を必要とする存在です。一方、定年後も知見や経験を活かして働く「シルバーワーカー」の活躍も注目されており、世代間の共存と協働が組織の生産性に直結する時代が到来しています。こうした多様な人材を活かすには、従来の階層的な組織構造から脱却し、職種・スキル・貢献に基づいた柔軟な人材マネジメント体制への転換が必要です。世代や背景の違いを「多様化」とだけ捉えるのではなく、互いに学び合うことで組織の力に変える視点が求められます。
離職率の高さにどう対応するか
アジア諸国では、特にBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)業界を中心に、離職率の高さが慢性的な課題となっています。たとえばフィリピンでは、BPO業界の年間離職率が45%に達するケースもあり、組織運営や人材育成の継続性に大きな影響を与えています。この背景には、キャリアアップの機会不足、成長実感の欠如、マネジメントとの価値観のズレなどが挙げられます。人事部門はこうした課題に対し、定着率向上を目的としたキャリアパスの可視化や、1on1ミーティングによる対話機会の強化など、エンゲージメント向上施策を導入する必要があります。離職を防ぐには報酬だけでなく、「この会社で成長できる」という納得感のある環境をいかに提供できるかが問われています。
グローバルに活躍できるリーダーを育てるには
人材が多様化する今、グローバルに活躍できるリーダーの要件も変化しています。単に語学力や専門性に優れているだけでなく、異文化理解力、心理的安全性の醸成力、チームビルディングの柔軟性など、幅広い資質が求められるようになりました。日本企業においては、リーダー育成と評価の基準が旧来的な枠組みにとどまりがちですが、今後はスキルベースでの人材評価、透明性の高いフィードバック文化、オープンな対話を促す仕組みが不可欠です。また、海外赴任だけでなく、現地人材のリーダー化を視野に入れた育成プログラムや、逆境で学ぶレジリエンス型研修など、多様なアプローチが求められています。グローバルリーダーとは“どこで生まれ育ったか”ではなく、“どこで誰と成果を出せるか”に重きが置かれる時代なのです。
7.まとめ|「共に育ち、未来をつくる」人事へ
グローバルビジネスの主戦場がアジアへとシフトする中で、人事部門の役割もまた大きく変化しています。単なる採用や労務管理の担い手ではなく、人と組織の成長を支える戦略的な存在へと進化しています。特にアジアでは、ローカルの現場感覚を持ち、文化的背景に配慮しながら変化に適応できるリーダーが台頭し、その中心に戦略的な人事の存在が見え始めています。
また、柔軟な働き方の拡大やAIの導入、価値観の多様化といった新たな潮流は、従来の人事制度や組織マネジメントのあり方に根本的な見直しを迫っています。これからのグローバル人事には、テクノロジーと人間性、データと共感、効率と共創を統合する複眼的な視点が欠かせません。
日本企業にとっても、アジアという舞台はもはや「進出先」ではなく「共に成長するパートナー」として捉えるべき存在です。人材戦略の再定義を通じて、組織全体を変革しうる人事部門の可能性に目を向けることで、グローバルな成長軌道に乗るための道筋がより鮮明になるはずです。今、まさに「東から世界を動かす」人事の時代が始まっています。
なお、People Treesは、一社ごとの経営戦略や人・組織の状況にあわせ、ハンドメイドで人事のあらゆる領域のご支援をさせていただいております。現場の実務に伴う苦労やリアルな課題に寄り添いながら、広い視野で未来を見据えるパートナーとして、共に考えていきます。企業のグローバル進出や海外拠点のマネジメント等において「何から始めたらいいかわからない」「どのように進めていけばわからない」等ございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談