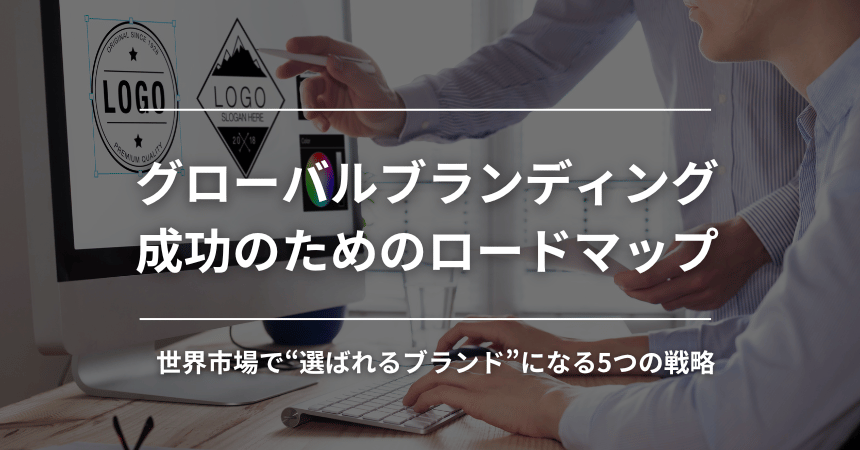FTA(自由貿易協定)の基礎知識 | 世界と日本のFTA件数・EPAとの違い・メリット&デメリット…ほか

FTA(= Free Trade Agreement)とは、日本語で「自由貿易協定」と呼ばれるもので、2ヵ国以上の特定の国・地域の間で、貿易自由化のために締結する協定のことを指します。
FTAのメリットは「関税の軽減・免除」にあります。FTAを相手国と締結することで、協定の内容および交渉によって、段階的な関税の軽減・免除ができるようになり、お互いのメリットを追求した貿易ができる可能性が高まるのです。
本文にて解説しますが、世界各国・地域では486のFTAが確認されています。そして日本も、2001年1月のシンガポールとのFTAを契機として、22のFTA・EPA案件を持っています(※2019年12月現在)
今後各国間のFTA締結が増加していくことで、日本企業が海外に進出するための環境も整備されていき、締結国同士の経済も活性化されることでしょう。
FTAの基礎知識として、そもそもFTAとは何か? FTAとEPAの違い、FTAのメリット&デメリット、世界経済でFTAが増加している背景と理由、世界と日本におけるFTAの件数、FTAが誕生した歴史的背景…などについて解説します。
▼FTA(自由貿易協定)の基礎知識 | 世界と日本のFTA件数・EPAとの違い・メリット&デメリット…ほか
- 1. FTAとは
- 2. FTAとEPAの違いについて
- 3. FTAのメリット&デメリット
- 4. 世界経済でFTAが増加している背景と理由
- 5. 世界と日本におけるFTAの件数とは?
- 6. FTAが誕生した歴史的背景を知る
▼アナタの海外ビジネスを成功させるために
1. FTAとは
FTA(= Free Trade Agreement)とは「自由貿易協定」のこと
まずは簡潔にFTAとは何かについて解説します。
FTA(= Free Trade Agreement)とは、日本語で「自由貿易協定」と呼ばれるもので、2ヵ国以上の特定の国・地域の間で、貿易自由化のために締結する協定のことを指します。
具体的には、物品の関税やサービス貿易の障壁などを削減・撤廃することを目的としており、FTAを締結した国・地域は、お互いの輸入品に対して課せられている関税や、関税以外で輸出入を制限している処置(※ 非関税障壁 など)を撤廃することなどを約束します。
※非関税障壁:
関税以外の方法で自由貿易の妨げとなる手段や制度。輸入数量制限・輸入課徴金・差別的貿易金融制度などがある
FTA(自由貿易協定)の目的
続いてはFTAの目的について見ていきましょう。
FTA(自由貿易協定)を締結することによって、締結国・地域の間で自由貿易が可能になり、お互いの貿易や投資が拡大されます。つまりFTAを締結する国々が増えれば増えるほど、世界経済は活性化されていくのです。
つまり、FTAの目的とは、国・地域間の貿易の自由化を促進し、関税などの自由貿易に関する障壁をなくし、国・地域同士の市場を統合し、世界の経済を成長させることにあります。
FTAの現状
2020年現在、世界におけるFTAの現状としては、EU(= European Union / 欧州連合)やNAFTA(= North American Free Trade Agreement / 北米自由協定)といった複数国からなる代表的な協定をはじめ、そのほかの二国間の協定も含めると、約200以上のFTAが締結されています。
後述しますが、世界各国・地域では486のFTAが確認されています(構想・交渉中、署名などを含む)。そして日本も、2001年1月のシンガポールとのFTAを契機として、22のFTA・EPA(※)案件を持っています(※2019年12月現在)。
※EPA:
経済連携協定(Economic Partnership Agreement)を正式名称とする、特定の国や地域間の貿易や投資を促進するための条約
2. FTAとEPAの違いとは?
EPAはFTAより幅広い分野での共通ルールを定めた協定
このセクションでは、FTAと引き合いに出されるEPAとのそれぞれの違いについて見ていきましょう。
そもそもEAPとは何かと言いますと、経済連携協定(Economic Partnership Agreement)を正式名称とする、特定の国や地域間の貿易や投資を促進するための条約です。
結論から言えば、FTAとはEPAに含まれるもので、FTAが「関税の撤廃・削減を定める」のに対して、EPAは「関税だけでなく知的財産の保護や投資ルール、さらには人的交流の拡大なども網羅」したものになります。
つまり…
■FTA:
特定の国・地域間での関税やサービス貿易の障壁などを削減・撤廃するルールを定めた協定
■EPA:
投資規制の撤廃、知的財産制度の保護、人的交流など、FTAと比較してより幅広い分野での共通ルールを定めた協定
…ということになります。
FTA・EPAともに世界経済を発展させるという目的は同じ
ここまでFTAとEPAの違いについて述べましたが、FTAとEPAが明確かつ厳密に区別されているとは言えないのが各メディアでの現状です。ケースによっては、FATとEPAを同じものとして扱っているコンテンツも見られます。
ただ、FTAもEPAのいずれもが、世界の国・地域間での自由貿易を活性化し、世界経済を発展させていくという目的を掲げていることは共通しています。
3. FTAのメリット&デメリット
このセクションではFTAの持つメリットとデメリットについて見ていきましょう。
FTAのメリット
FTAのメリットは「関税の軽減・免除」にあります。
そもそも関税率は、各国で独自に決めることができますが、WTO(世界貿易機関)に加盟している場合、WTO協定税率にあわせて、決められた関税率で貿易をしなければならず、国ごとに税率を変更することが原則できません。
しかし、FTAを相手国と締結することで、協定の内容および交渉によって、段階的な関税の軽減・免除ができるようになり、お互いのメリットを追求した貿易ができる可能性が高まるのです。
そもそも多くの国々同士がFTAを締結することで、国際貿易における投資および自由化が促進されます。
その結果、必然的に、日本企業が海外に進出するための環境も整備されていき、締結国同士の経済も活性化されるのです。
FTAのデメリット
そもそもFTAは締結した国々それぞれの貿易上のメリットを最大化させるのが目的ではあるのですが、仮にすべての品目の関税を撤廃してしまうと、貿易上の大きなバイアスが発生してしまうかもしれません。
また、これまで関税によって守ってきた自国の特定産業の担い手がいなくなってしまったり、基幹産業として成長させたい産業の育成が滞ってしまう可能性も高まります。
つまり、FTAの協定内容によっては、従来は守られていた産業が衰退してしまったり、自国の特定産業が育たなくなってしまうデメリットもあるので注意が必要です。
4. 世界経済でFTAが増加している背景と理由
多国間貿易の合意形成に時間がかかるWTOからフレキシブルに自由化を推進できるFTAへ
先述したように、2020年現在、世界におけるFTAは、複数国からなる代表的な協定をはじめ、そのほかの二国間の協定も含めると、約200以上が締結されています。
今日のようにFTAが増加し続けてきた理由としては、1994年に発足したWTO(= World Trade Organization / 世界貿易機関)体制の下で推進されてきた、従来の多国間貿易自由化交渉がスムーズに進まなくなってしまったという状況があります。
現在、WTO加盟国・地域は164。WTOには、加盟国が自由にモノ・サービスなどの貿易ができるようにするためのルールを決定したり、分野ごとに交渉や協議を実施する場が設けられていますが、普通に考えて、164の加盟国・地域すべての利害を調整した共通ルール・制度を作ることは、時間もかかり、現実的に難しいことは想像に難くないと思います。
そのように多国間貿易における合意形成に時間がかかってしまうWTO交渉に依存せずに、お互いの経済的な利害が一致する国や地域同士で、可能な範囲で自由化を推進していこう…という世界的な動きが、今日のFTAの増加をうながしていることは言うまでもありません。
5. 世界と日本におけるFTAの件数とは?
世界におけるFTAの件数
世界におけるFTAの現状に続いては、世界および日本が締結しているFTAについて見ていきましょう。
まずは世界のFTAについてですが、下記はJETRO(日本貿易機構 / Japan External Trade Organization)による、世界におけるFTAの状況です。
FTAの進展度合いに応じて4つの段階に分類されています。
①【発効済、暫定適用】320 件
②【署名済、交渉妥結】・・・政府間交渉は終了しているが批准が済んでいないもの、および協定文の確定作業段階にあるもの(49 件)
③【交渉中、交渉開始合意】・・・交渉が行われているもの、交渉開始に合意したもの、交渉中断となったもの(93 件)
④【構想・検討段階、政府間予備協議など】・・・交渉開始検討中のもの、共同研究・構想段階のもの(24 件)
発行済・暫定適用、署名済・交渉妥結、交渉中・交渉開始合意、構想・検討段階、政府間予備協議など…といった4つの段階を含めると486件のFTAが確認されています。(※2019年12月時点)
※参照サイト:
『世界と日本のFTA一覧』 JETRO
日本におけるFTA・EPAの件数
世界に続いては、日本のFTA・EPAの件数について見ていきましょう。
結論から言うと、2019年12月の時点で、日本が関わっているFTAおよびEPAの件数は22件となっています。その内訳は以下のとおりです。
①【発行済・署名済】18件
シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN全体、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、TPP12(署名済)、TPP11、日EU・EPA
②【交渉中】4件
RCEP(アールセップ / 東アジア地域包括的経済連携)、トルコ、コロンビア、日中韓
③【その他(交渉中断中)】3件
GCC(湾岸協力理事会)、韓国、カナダ
※参照サイト:
『日本のEPA・FTAの現状』外務省
そもそも日本の通商交渉はWTO体制下の多国間主義に重きを置いていたことで、FTAに対する取り組みは、欧米諸国と比較すると遅れていました。
しかしグローバル経済が拡大していくなかで、日本がFTAを締結していないことで、海外ビジネスにおいて日本企業が不利益をこうむるケースも発生していました。そのような状況から、日本政府もFTAを推進する意識を従来よりも強く持ちつつあると言えるでしょう。
6. FTAが誕生した歴史的背景を知る
GATT→WTO→FTAの歴史的関係とは?
最後のセクションでは、FTAが誕生した歴史的背景について解説します。
結論から言えば、FTA誕生の背景を知ることは、そのまま多国間貿易の歴史を知ることにつながります。
そもそもFTAは、WTO体制下における多国間貿易が行き詰まったことから発展を遂げたことは、前項までで述べました。
そのWTOも、以前より存在していたGATT(= General Agreement on Tariffs and Trade / 関税及び貿易に関する一般協定)が発展する形で設立されたのです。
GATTとは、1947年に調印された、関税障壁を撤廃するための国際的な協定です。そしてWTOは、ウルグアイ・ラウンドと呼ばれる、世界貿易上の障壁をなくし、貿易の自由化や多角的貿易を促進するために行われた多国間通商交渉を経て、1995年にGATTを発展させる形で成立しています。
これらの多国間貿易に関連する3つの協定・機関を設立順に並べてみると…
・GATT(= General Agreement on Tariffs and Trade / 関税及び貿易に関する一般協定):1947年に調印、1948年に発足
⇓
・WTO(= World Trade Organization / 世界貿易機関):1995年に設立
⇓
・FTA(= Free Trade Agreement / 自由貿易協定):1990年代以降より締結する国・地域が急増
となります。
「ブロック経済」と「保護主義」によって「高関税化」が促進…やがて第二次大戦が勃発
GATT、WTO、FTAの成立順番がわかったところで、これらの協定・機関が、世界の歴史においてどのような関連性をもっていたのかを見ていきましょう。
もとをたどれば、現在の多国間貿易の仕組みが作られた要因には、1929年の世界恐慌にあります。
1929年に発生した世界恐慌によって、世界はその負の連鎖を断ち切るために「高関税」という処置をとりました。具体的には、資源を持つ国々が自国と植民地との経済関係を強化する一方で、それ以外の国には高い関税をかけました。
これがいわゆる「ブロック経済」です。
そして世界恐慌の発端となったアメリカは、自国への輸入にかかる関税を高めるという「保護主義」政策をとります。
資源を持つ国々が実施した「ブロック経済」と「保護主義」が世界中に浸透した結果、資源を持たない国々は植民地を獲得するため、周辺国の侵略を開始します。
それが1939年に起こった第二次世界大戦の大きな要因のひとつです。
つまり第二次世界大戦は「高関税」が引き起こしたとも言えるのです。
やがて第二次大戦も終盤になった頃、イギリスとアメリカの間で、戦後の貿易体制に関する協議が行われ、1947年にGATTが誕生します。先述したように、GATTとは、関税障壁を撤廃するための国際的な協定であり、簡単に言えば、「世界共通の関税に関するルール」です。
第二次大戦後、GATT(世界共通の関税に関するルール)は世界中に拡大していき、やがて、GATTを発展解消させる形で1995年にWTO(世界貿易機関)が設立されます。さらにWTO体制下における多国間貿易が行き詰まったことから、1990年代には、本テキストのテーマである「FTA」のニーズが高まり、今日の隆盛へと至ったのです。
7. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
今回は「FTA(自由貿易協定)の基礎知識」として、そもそもFTAとは何か? FTAとEPAの違い、FTAのメリット&デメリット、世界経済でFTAが増加している背景と理由、世界と日本におけるFTAの件数、FTAが誕生した歴史的背景…などについて解説しました。
「Digima〜出島〜」には、厳正な審査を通過した、様々な支援を行う優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。
「自社商品の輸出入時の関税が削減されるケースについて知りたい」「自社商品を輸出したい」「海外から商材を輸入したい」「通関や輸出入許可の申請をサポートしてほしい」「海外へ進出したいが何から始めていいのかわからない」…といった海外ビジネスにおける様々なご質問・ご相談を承っています。
ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、御社にピッタリの海外進出サポートサポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
もっと企業を見る