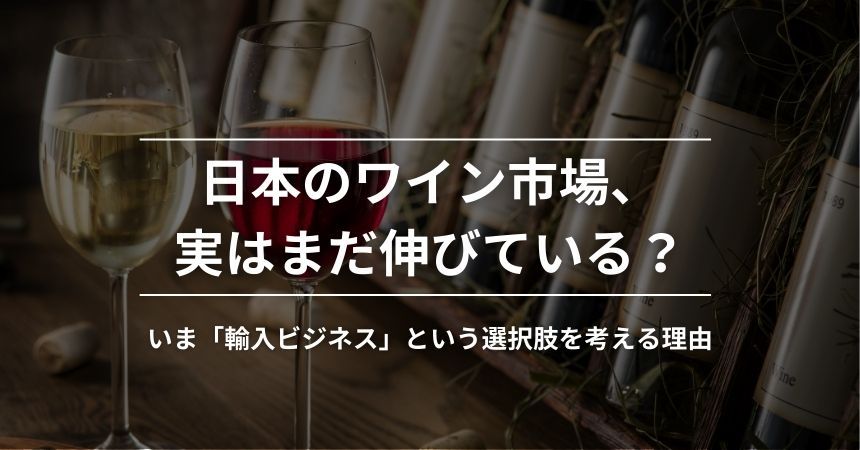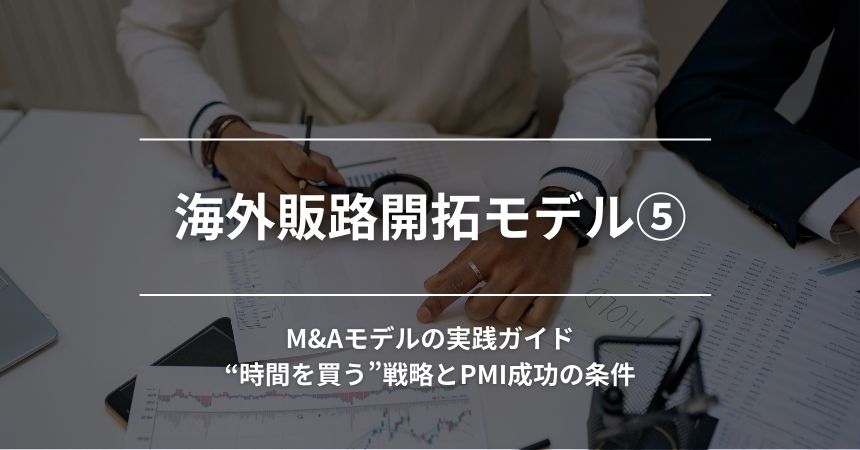PSEとは?認証取得の流れ / PSE表示に必要な2つの検査とは?

「PSE」とは、電気用品の安全確保について定められている法律である「電気用品安全法」を指します。
「電気用品安全法」とは、電化製品の事故を防ぐために電気用品の安全確保について定められている日本の法律です。
そして、PSEとは、Product Safety Electrical Appliance and Materialsの略で、その「電気用品安全法」の基準に適合していることを示す表示がPSEマークです。
先述したように「電気用品安全法」とは日本の法律であり、PSEマークも日本の安全基準に適合したことを示す表示ですが、仮に海外から電化製品を輸入した場合でも、日本で販売する際は「PSEマークの表示」が必要となります。
また本文内で詳しく解説しますが、PSEマークとは「認証」されたり「取得」するものではなく、事業者自身が表示するマークになります。
では、この「PSEマークの表示(認証・取得)」は、どのような手続きを踏めば可能となるのでしょうか?
本テキストでは、電気用品安全法やPSEマークの基礎知識として、「対象となる電化製品」や「PSEマークの表示(認証・取得)」までの流れ、また電気用品の輸入業者が注意すべき「PSE適合検査」「PSE自主検査」についてもわかりやすく解説します。
▼PSEとは?認証取得の流れ / PSE表示に必要な2つの検査とは?
- 1. PSE(電気用品安全法)とは?
- 2. PSEマークとは?
- 3. 海外から電気用品の輸入する際に注意すべき「PSE対応」とは?
- 4. 「PSE適合検査」「PSE自主検査」とは?
- 5. PSEマーク表示までの流れ
▼アナタの海外ビジネスを成功させるために
1. PSE(電気用品安全法)とは?

PSEとは、Product Safety Electrical Appliance and Materialsの略で、「電気用品安全法」のことです。以下よりPSEの概要について見ていきましょう。
PSE(電気用品安全法)の概要
照明やエアコンなど、私たちの生活になくてはならない電気用品。これらの品質に問題があると、火事や感電などの事故のリスクが高まります。そのような事故を防ぐために電気用品の安全確保について定められている日本の法律が「電気用品安全法」なのです。電気用品安全法の第一条にはこのように書かれています。
この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
もともと、日本において電気用品の安全確保について定めていた法律には「電気用品取締法」がありましたが、手続きが非常に煩雑で、事業者からは改善を求める声が多く上がっていたそうです。また、輸入の際の障壁になるとも問題視されており、「電気用品取締法」を抜本的に改正した「電気用品安全法」が2001年に施行されることになりました。
関連する法令は「電気用品安全法施行令」「電気用品安全法施行規則」「電気用品の技術上の基準を定める省令」の3つで、それぞれの法令において電気用品の定義や、手続きに関する規則、技術的な基準が定められています。
PSEの対象となる電気製品とは?
電気安全法において指定されている「電気用品」は457品目。中でも特に安全上規制が必要なものとして116品目の「特定電気用品」が指定されています。
電気安全法における「電気用品」とは、電気安全法第二条に記載されている、下記の3つのいずれかに該当するものを言います。
1. 一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であり、政令で定めるもの
2. 携帯発電機であり、政令で定めるもの 3. 蓄電池であり、政令で定めるもの「電気用品」であり、「特定電気用品」以外の電気用品
1の一般用電気工作物は、一般家庭などで使われる、電力会社が供給する交流 100 ボルト、200 ボルトの商用電源に接続される電気工作物のことです。特定電気用品とは、危険が生じるおそれの高い電気用品のこと。
パソコン本体は電気用品ではありませんが、パソコンのACアダプターは電気用品となります。
2. PSEマークとは?

PSEマークとは、電気用品安全法の基準に適合した電化製品に掲示される印です。電気用品安全法の施行により、メーカーや輸入業者は「PSEマーク」をつけて販売することを義務付けられたため、PSEマークのない製品は製造・輸入・販売をすることができなくなりました。
2018年の法改正により、それまでは対象外だったモバイルバッテリーが2019年2月1日以降、規制対象商品に追加されることになりました。
以下よりPSEマークについて詳しく見ていきましょう。
PSEマークには2種類ある
PSEマークには「ひし形」のものと「丸型」のものがあります。一般的な屋内コンセントから、AC100Vを供給されて使用する機器は、この2種類のPSEマークいずれかが貼られていなければ販売はできません。
3. 海外から電気用品の輸入する際に注意すべき「PSE対応」とは?

海外から電化製品を輸入して日本で販売する際は「PSE」の確認が必要
このセクションでは、海外ビジネスに従事しているビジネスパーソンにとって重要な、海外から電気用品を輸入する際に注意すべき「PSEの対応法」について解説します。
そもそも電気用品は許可製品ではありません。日本の法律に適合していない電気用品であっても輸入が可能なのです。
したがって、日本の法律に適合していないにも関わらず、事前に何も調べずにそのまま販売すると違法になってしまいます。
つまり、電気用品を輸入する際には必ず、PSEに適合している製品かどうかを調べる必要があるのです。
日本の法律に合わない電化用品はいくら安くても輸入NG
事前によく調べずに発火の恐れがある危険な製品を販売するというのはモラルに欠ける行いですし、違法な製品を販売すると、当然ですが法によって罰せられます。
日本の法律に適合していない電気用品を輸入した場合、電気用品安全法第57条6号により、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または両方を科されます。法人に対しては電気用品安全法第59条により、1億円以下の罰金(59条)が科せられます。
どんなに安くて素敵な製品であっても、日本の法律に合わない電気用品を輸入してはいけないのです。
電気用品輸入事業者に課せられた5つの義務について
このセクションでは、電気用品輸入業者に課せられた5つの業務について解説していきます。
電気用品安全法に基づき、電気用品輸入事業者に対しては下記の5つの義務が課せられています。
① 届出の義務
② 技術基準の適合義務
③ 自主検査の実施及び検査記録の保存義務、
④(特定電気用品の場合)適合性検査証明書の保存義務
⑤ 表示の義務
以下より、順を追ってみていきましょう。
① 届出の義務
■電気用品輸入事業届出書
電気用品輸入事業者は、輸入事業の開始の日から30日以内に電気用品輸入事業届出書を届け出る義務があります。
届出を行っている電気用品の区分で異なる電気用品を新たに輸入する際は、様式第6の「事業届出事項変更届出書」を提出する必要があります。
異なる電気用品の区分となる電気用品を新たに輸入するケースの場合は、様式第1の「電気用品製造(輸入)事業届出書」による届出が必要です。
■事業届出事項変更届出書
電気用品輸入事業者は、下記の3つの事項に変更があった場合は遅滞なく届け出る義務がありますが、法人の代表者名の変更のみの場合はこの限りではありません。
(1) 輸入事業者の氏名又は名称及び住所
(2) 輸入する電気用品の型式の区分
(3) 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
■電気用品輸入事業廃止届出書
電気用品輸入事業者が事業を廃止する場合にも届け出なければなりません。将来にわたって輸入事業の見込みのない場合は、電気用品製造(輸入)事業廃止届出書の届出が必要です。
② 技術基準の適合義務
■基準について
電気用品を輸入する場合は、経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうか、必ず確認しなければなりません。
すべての電気用品に対応する技術基準は、「性能規定」という規定が技術基準省令において定められており、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈については「技術基準省令解釈」が示されています。
■届出が不要なケース
以下の場合には技術基準適合確認は不要となりますが、試験的製造輸入以外は事業届出が必要です。
※次のような特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき
・ツーリスト・モデル
・リチウムイオン畜電池
・アンティーク照明
・「ビンテージもの」の電気楽器
・試験的に製造し、又は輸入するとき
・届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入
■他国の基準適合マークがついている場合
他国の基準適合マークとして、例えばULマークやCEマークといった認証マークがついている製品についてはどうなのでしょうか?
他国で基準に適合していたとしても、日本の基準に適合しているとは限りませんから、必ず電気用品安全法に基づいて技術基準適合確認などを行う必要があります。
※ULとはアメリカの認証企業。ULにおいて評価試験に合格するとUL認証マークの使用が認められます
※CEマークはEU加盟国の基準を満たすものにつけられる基準適合マークです
③ 自主検査の実施及び検査記録の保存義務、
届出輸入事業者は技術基準の適合義務を行った上で、経済産業省令で定める検査を輸入する電気用品に対して実施する必要があります。
輸入事業者自らが自主検査を実施。
↓
海外製造事業者に対しても、検査の方式に従った自主検査を実施してもらう。
↓
検査記録を入手、保管。
検査記録は検査を行った日から3年間保存しなければいけないので、そこも注意が必要です。
④(特定電気用品の場合)適合性検査証明書の保存義務
特定電気用品は本来、経済産業大臣の登録を受けた者の検査を受け、その適合性を確認した証明書を保存する必要があるのですが、輸入事業者の場合は、海外の製造事業者から適合性検査証明書の副本を入手・保管すれば、適合性検査証明書の交付を受け、それを保管していることと同等と見なされます。
検査証明書はコピーでは証明書として認められませんので、必ず副本として証明された原本を用意しましょう。
⑤ 表示の義務
基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、届出事業者はPSEマークなど、国が定めた表示を付けることができます。
電気安全法に基づいて、届出事業者が表示する事項は、下記の4つの項目になります。
1.記号
2.届出事業者名
3.登録検査機関名称(特定電気用品の場合)
4.定格電圧、定格電流等の諸元
原則、1.~3.は、原則、近接して表示しなければなりません。
また、届出事業者以外は電気用品にこれらの表示を行うことはできず、届出事業者であったとしても、所要の義務を履行せず電気安全法の表示を行うことは禁止されています。
製造・輸入事業者が販売する場合にも定められた方式の表示を付した上で販売しなければなりませんし、製造や輸入事業を行わない者が販売する場合は、法に基づいた表示を確認した上で販売しなければならないことにも注意しましょう。
以下より、4つの項目について解説していきます。
■1. 記号
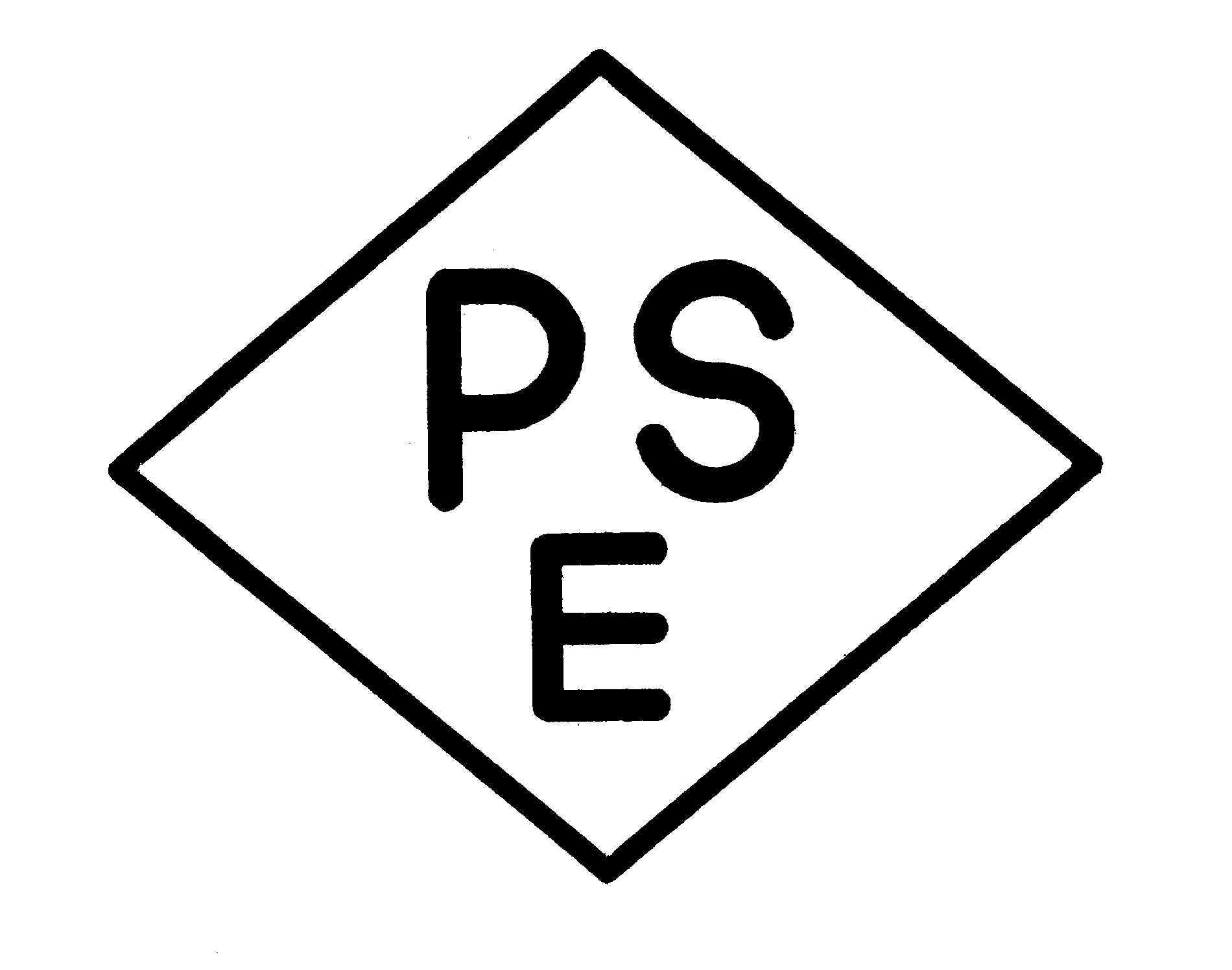
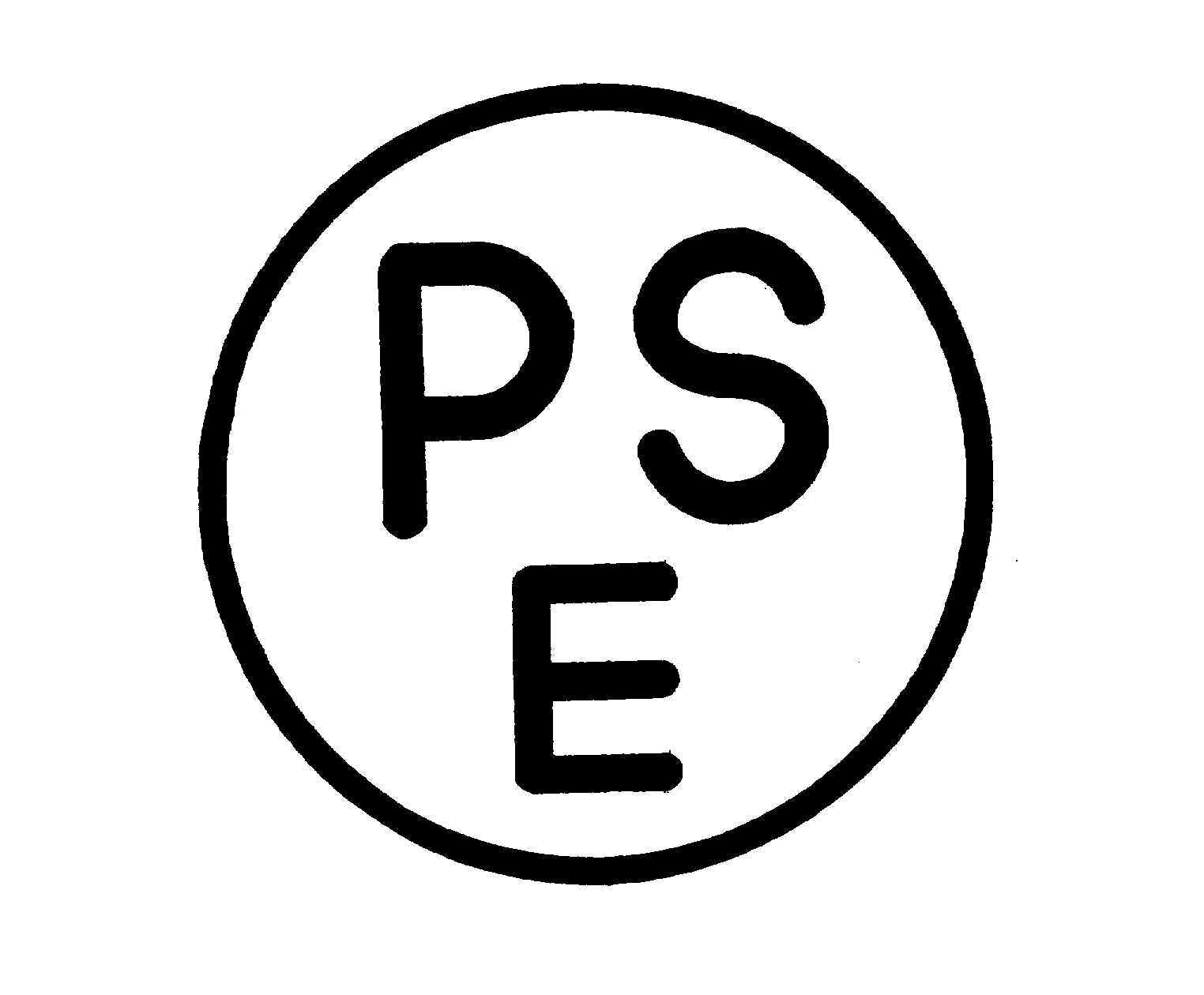
ここでの「記号」とはPSEマークのこと。表示にあたって、全体の大きさや枠の太さ、フォント形式、サイズ、色は自由ですが、文字の位置関係や枠の形を変更するなどした場合、記号として識別できないと判断される場合があるので気をつけましょう。
また、表示シールなどは国から供給されるものではないので、事業者が銘板等にデザインして表示します。
■2. 届出事業者名
原則、表示するのは事業者の正式名称(個人事業者の場合は氏名)ですが、承認を受けた略称や、届出を行った登録商標なら正式名称でなくても表示することができます。また、略称と言っても「株式会社」を「(株)」に、「財団法人」を「(財)」に略すといったケースには承認は不要です。
■3. 登録検査機関名称(特定電気用品の場合)
原則、表示するのは登録検査機関の正式名称ですが、登録検査機関が承認を受けている略称や、届出を行った登録商標の場合は、正式名称でなくても表示が可能です。
■4. 定格電圧、定格電流等の諸元
表示すべき事項及び表示の方法は、電気用品によって異なります。
以下、経済産業省のHPにて掲載されている『電気用品安全法 / 電気用品安全法令・解釈・規定等』を参照すると…例えばヒューズについては、別表第3の附表第5に記載があります。またリチウムイオン蓄電池については、別表第9の附表第2に記載されています。
詳しくは下記にリンクした経済産業省の『電気用品安全法 / 電気用品安全法令・解釈・規定等』の「通達 / 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の各別表を確認してください。
※参照:
『電気用品安全法 / 電気用品安全法令・解釈・規定等』経済産業省
4. 「PSE適合検査」「PSE自主検査」とは?

PSEとは取得するものではなく届け出るもの
このセクションでは「PSE適合検査」と「PSE自主検査」の2つの検査について解説します。
大前提として、そもそもPSEは取得するものではありません。PSEは届出制です。したがって自主検査が基本であり、輸入を検討している電気用品があるなら、その商品がPSEの対象かどうかを判断するのは事業者になります。
つまり、なんらかの許可を得るのではなく、事業者自身の責任において判断し、届出を行わなければいけません。
そこで必要となるのが「PSE適合検査」「PSE自主検査」となります。
「適合性検査」と「自主検査」が必要な理由とは?
電気用品の製造または輸入事業を行うためには、国への事業届出、技術基準適合確認、自主検査を行う必要があります。
ここからは、「適合性検査」と「自主検査」について改めて確認しておきましょう。
■PSE適合性検査とは
適合性検査は、実物を検査する「技術基準への適合性の確認」と、現場検査である「製造工場などの検査設備の確認」の2つからなる検査です。
登録検査機関において検査を行い、証明書の交付を受け、それを保存します。
■PSE自主検査とは?
PSE届出を行った製品は、全数自主検査を行う必要があります。輸入業者の場合はメーカーに出荷品全てに対して検査を行ってもらい、その検査結果を取り寄せ、保存します。
電気用品によって検査項目は異なりますが、「外観検査」「絶縁耐力検査」「通電検査」は必須です。
5. PSEマーク表示までの流れ

国への事業届出、技術基準適合確認、適合性&自主検査などを行う必要がある
PSEの概要や検査内容について理解したところで、最後のセクションにて「PSEマークが表示されるまでの流れ」を改めて確認しておきましょう。
① 事業届出
事業開始から30日以内に事業届出を行います。
② 基準適合確認
取り扱う電気用品が、国が定める技術基準に適合しているかを確認します。
③ 適合性検査(特定電気用品の場合)
特定電気用品は登録検査機関で適合性検査を受けます。
④ 自主検査
自主検査は、すべての電気用品について行います。
⑤ PSEマークを表示する。
検査をクリアすればPSEマークを表示することができます。その他、事業者名や定格電流など、国が定めた内容もあわせて表示します。
6. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
今回は「知的財産権の基礎知識」として、知的財産権の種類やその対象と出願方法、また海外進出の際に大きなリスクとなり得る「海外ビジネスにおける知的財産権の侵害事例」などについて解説しました。
私たちの生活になくてはならないものとなっている電気用品は、とても便利な反面、火災などの事故の危険性もある、取り扱いに注意が必要な製品です。そのため、法によって事故を防ぐための方が定められているのです。
PSEマークは、消費者が安心して電気用品を購入できるだけでなく、メーカーや輸入業者の信頼性を高めるためにもとても大切な認証ですが、手続きや検査などはなかなか手間がかかるものです。
もし海外ビジネスにおいて、PSEマークの表示の手続きや検査などにお困りなら、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。輸入にあたってのその他の手続きについても安心して相談することができます。
「Digima〜出島〜」には、厳正な審査を通過した優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。当然、複数の企業の比較検討も可能です。
「海外に自社商品を輸出したい」「海外から商材を輸入したい」「通関や輸出入許可の申請をサポートしてほしい」「海外へ進出したいが何から始めていいのかわからない」…といった海外との輸出入に関する課題はもちろん、多岐に渡る海外進出におけるご質問・ご相談を承っています。
ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談