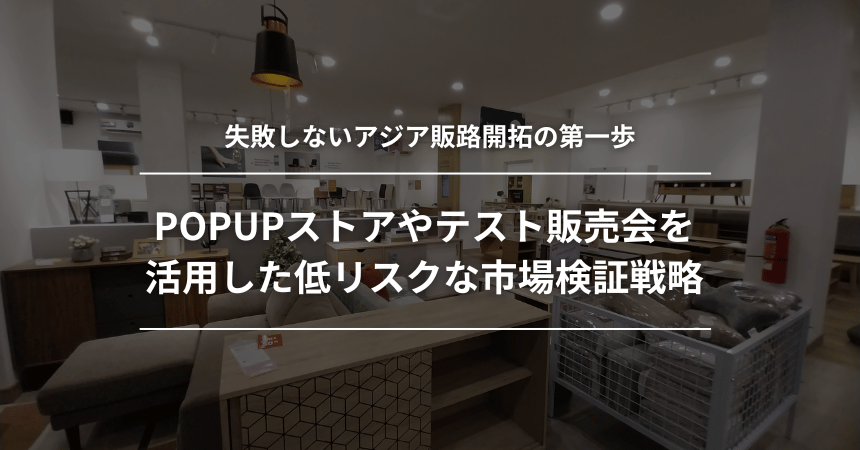外国人採用に必須の「在留資格」完全ガイド|29種類一覧・申請手続き・企業が知るべき実務ポイント

近年、多くの企業がグローバル人材の採用を積極的に進めており、外国人従業員の活躍の場がますます広がっています。その一方で、初めて外国人を採用する企業や、外国人雇用の管理を担当するご担当者の方からは、「在留資格」についての疑問や不安の声も多く聞かれます。実際、在留資格の仕組みや取得手続きは日本人の採用とは大きく異なり、制度への正しい理解がなければ、思わぬリスクやトラブルにつながることも少なくありません。
本記事では、「外国人採用に必須の『在留資格』完全ガイド」と題し、企業の人事・労務担当者や経営層の皆さまに向けて、在留資格の全体像や29種類の分類一覧、主な就労系資格の特徴、取得や更新の実務ポイント、そして外国人雇用におけるリスク管理までを体系的に解説します。専門用語や制度の細かな違いもわかりやすくご説明し、日々の実務にすぐ役立つ情報を網羅しています。
これから外国人採用を検討される企業の方はもちろん、すでに外国人雇用に携わっているご担当者にも、「知っておくべき最新の在留資格事情」として、ぜひご活用ください。制度を正しく理解し、安心して外国人材を迎え入れるための第一歩を、本記事で踏み出しましょう。
▼ 外国人採用に必須の「在留資格」完全ガイド|29種類一覧・申請手続き・企業が知るべき実務ポイント
在留資格とは?全体像と29種類の一覧
在留資格の基本と“ビザ”との違い
外国人材を採用・雇用する際、必ず押さえておきたいのが「在留資格」と「ビザ」の違いです。一般的に「ビザ(査証)」は日本への入国許可を得るために大使館や領事館で発給されるものであり、入国そのものを可能にする“切符”のような存在です。一方、「在留資格」とは、外国人が日本国内でどのような活動(仕事や学業、家族としての滞在など)を行うか、その活動内容ごとに法的に許可された資格のことを指します。日本に入国した後、どのような目的でどの範囲の活動を認められるかは、この在留資格によって厳密に定められています。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労を目的とした資格から、「留学」「家族滞在」など就労が認められていない資格まで多岐にわたります。この違いを理解せずに採用や雇用管理を進めると、企業側が不法就労助長などの法的リスクを負う可能性もあるため、在留資格という制度の基礎をしっかり押さえることが重要です。
在留資格の分類と概要|29種類の目的別一覧
日本の在留資格は、外国人が「どのような目的で日本に滞在するのか」に応じて細かく分類されています。現在、法務省が定める在留資格は全部で29種類存在し、大きく分けて「活動に基づく在留資格」「身分・地位に基づく在留資格」「告示による特定活動」の3つの系統があります。「活動に基づく在留資格」には、就労を目的とした「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「経営・管理」などのほか、教育・芸術・研究など特定の活動を認める資格が含まれます。「身分・地位に基づく在留資格」には、「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」などがあり、これらは原則として活動内容に制限がなく、自由な就労や滞在が可能です。また、「特定活動」は、インターンシップやワーキングホリデーなど個別に告示で定められた活動に対応する柔軟な資格となっています。それぞれの資格には対象となる活動や滞在目的、取得条件が異なるため、採用計画や雇用管理を行う際は、必ず該当する資格を確認することが求められます。
-
就労が可能(活動に基づく在留資格)
- 技術・人文知識・国際業務:通訳・SE・経理など、専門的知識を活かしたホワイトカラー職に就くための一般的な就労資格。
- 特定技能:介護・外食・建設など14業種で、即戦力としての外国人労働者を受け入れる制度。
- 高度専門職:学歴・職歴・年収などを点数化し、高度人材に優遇措置が与えられるポイント制ビザ。
- 経営・管理:外国人が日本で会社を経営・設立したり、役員として活動するための資格。
- 企業内転勤:海外子会社などから日本へ転勤する社員が対象。日本語力の要件は不要。
- 技能:調理師・建設作業員など、特定の熟練技能をもつ外国人の就労を認める資格。
- 介護:日本の介護福祉士資格を有する外国人が、介護業務に従事するための資格。
- 法律・会計業務:外国法事務弁護士、公認会計士など、国家資格に基づく業務を行う場合に必要。
- 医療:医師・看護師など、日本の医療関連資格を取得した者が医療業務に従事する資格。
- 教授:大学や高等教育機関で教育・研究に従事する教員向け資格。
- 教育:小中高校などの教員が教育活動を行う際の資格。教授とは対象機関が異なる。
- 研究:公的機関や企業の研究所などで、調査・研究業務を行うための資格。
- 芸術:作曲家・画家・彫刻家など、芸術活動を主たる目的として滞在するための資格。
- 宗教:外国の宗教団体に派遣された宣教師などが、日本で宗教活動を行うための資格。
- 報道:海外メディアの記者やカメラマンなどが、日本で取材活動を行うための資格。
-
一部就労可能・制限付きの活動に基づく資格
- 留学:主に大学・専門学校などで学ぶ目的の資格。資格外活動許可によりアルバイトが可能。
- 研修:日本の企業等で非就労型の技能・知識を習得するための制度。実務従事は不可。
- 技能実習:発展途上国への技術移転を目的とする制度。実態は就労に近く、制度改革が進行中。
- 文化活動:日本文化の研究や伝統芸術など、報酬を伴わない活動を目的とする資格。
-
身分・地位に基づく在留資格(就労制限なし)
- 永住者:在留期限のない在留資格。就労・活動に制限がなく、幅広い活動が可能。
- 日本人の配偶者等:日本人の配偶者・子などが対象。活動制限がなく、就労も自由。
- 永住者の配偶者等:永住者と結婚した外国人、その子どもなど。活動に制限なし。
- 定住者:日系人や難民認定者など、個別の事情により長期滞在が許可された者。自由な就労が可能。
- 家族滞在:留学生や就労者に帯同する配偶者・子が対象。資格外活動許可での就労は一部可能。
-
告示による特定活動(個別に指定された活動)
- 特定活動:インターン、ワーキングホリデー、EPA介護候補者など、多様な個別活動に対応。内容は告示で定められる。
企業が押さえておくべき“就労可否”の判断基準
企業が外国人を採用する際に最も重要なポイントの一つが、「在留資格によっては就労が認められていない場合がある」という事実です。在留資格には、就労が認められるもの(例:「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」など)、原則として就労ができないもの(例:「留学」「家族滞在」)、活動内容が限定されるもの(例:「研修」「文化活動」)があります。さらに、就労が許可されている資格であっても、従事できる職種や業務内容が細かく定められているため、雇用する側はその範囲をしっかり把握しなければなりません。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」であれば、通訳やシステムエンジニア、経理などの専門業務に限定され、単純労働には従事できません。また、「留学生」の場合は「資格外活動許可」を得ることで週28時間以内のアルバイトが認められていますが、本来の資格内容から逸脱する業務は認められていません。こうした細かな就労範囲の違いを正しく理解し、採用時には在留カードや就労資格証明書などを必ず確認することが、企業側のリスク回避と安定した外国人雇用の第一歩となります。
主な就労系在留資格と活用パターン
技術・人文知識・国際業務/高度専門職の特徴と要件
外国人の就労ビザとして最も一般的に利用されているのが、「技術・人文知識・国際業務」です。この資格は、いわゆるオフィスワークを中心とした専門的業務を対象としており、大学や専門学校などで修得した知識に基づいた業務であることが求められます。たとえば、通訳・翻訳、システムエンジニア、経理、貿易事務、企画・マーケティングなどが該当します。日本企業にとっては、外国人留学生の新卒採用や、専門性をもつ外国人材を雇用する際の主力資格といえるでしょう。一方で、この資格では単純労働は認められておらず、業務内容が資格の範囲を逸脱していると判断されれば不法就労と見なされるおそれがあります。
また、同じく就労系資格で注目されているのが「高度専門職」です。これは高学歴・高収入・職歴などの条件をポイント制で評価し、一定点数以上を満たす外国人材に対し、優遇措置(在留期間の延長、永住申請の緩和など)を提供する制度です。優秀な人材を継続的に確保したい企業にとって、有効に活用できる制度といえるでしょう。
特定技能・技能実習・技能ビザの違いと使い分け
人手不足が深刻な業種を中心に近年利用が進んでいるのが、「特定技能」と「技能実習」、そして「技能」ビザです。まず「特定技能」は2019年に導入された比較的新しい制度で、介護・外食・建設・農業など14の分野で、一定の技術や日本語能力を持つ外国人に対し、即戦力としての就労を認める仕組みです。雇用する企業には受け入れ計画の提出や支援体制の整備義務が課されており、制度に沿った運用が求められます。
一方、「技能実習」はもともと開発途上国への技術移転を目的とした制度ですが、実態としては労働力確保の手段として使われている面も否めません。制度的には「教育」目的とされており、企業には実習計画の遵守が求められます。また、将来的には「特定技能」への移行が想定されており、制度のあり方自体が見直されつつある状況です。
「技能」ビザは、調理師、建築技能者、宝石細工職人など、特定の熟練技能職に就く外国人に与えられるもので、日本特有の職人文化や伝統技術の分野でも活用されています。それぞれの資格には制度上の違いがあり、企業の採用目的や業種に応じた適切な選択が必要です。
その他の就労系資格(経営・管理/企業内転勤など)
就労系の在留資格の中には、特定の職種や立場に応じて設けられているものもあります。代表的なものが「経営・管理」ビザで、これは外国人が日本国内で会社を設立したり、企業の経営や管理に従事したりする場合に必要となる資格です。たとえば、外国資本による起業、外国人経営者の招聘、外国企業の日本支社開設などの場面で多く利用されており、一定額以上の投資や物理的な事業所の確保などが条件となります。
また、「企業内転勤」は、外国にある親会社・子会社・関連会社からの人材を日本に転勤させる場合に使用される資格で、海外グループ企業との連携が密な企業にとって非常に有用です。この資格では、日本語能力の要件はなく、転勤元との雇用関係が継続していることが前提とされます。
そのほか、医師や弁護士など国家資格が必要な専門職向けの「医療」「法律・会計業務」、芸術活動に従事する「芸術」など、業務内容に特化した在留資格も多岐にわたります。採用の対象者がどの資格に該当するかを見極めることが、円滑なビザ取得・雇用管理の第一歩になります。
在留資格の取得・変更・更新の手順と必要書類
新規取得・変更のフロー(呼び寄せ/国内採用)
外国人材を採用する際の在留資格の手続きは、候補者が「海外在住」か「すでに日本に滞在しているか」によって、大きく2つのパターンに分かれます。
まず、海外在住者を日本に呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行うのが一般的です。これは日本の企業(受け入れ機関)が入管に対して申請し、審査の結果「この人は在留資格を得る条件を満たしています」と証明する書類が発行されます。これを本人が現地の日本大使館・領事館に持参してビザ申請を行い、日本に入国する流れになります。
一方、すでに日本国内に滞在している外国人(例:留学生や技能実習生など)を採用する場合は、「在留資格変更許可申請」が必要になります。たとえば、留学生が卒業後に企業に就職する場合、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザに変更することになります。
どちらのケースでも、申請書類の内容に不備があると審査が長引いたり、不許可となることもあるため、企業側の準備体制が非常に重要です。
在留資格更新のスケジュールと企業が留意すべき実務
外国人社員がすでに就労している場合でも、在留資格には「有効期限」が定められており、定期的な更新手続きが必要となります。更新のタイミングは通常、在留期限の3か月前から受け付け可能であり、期限切れぎりぎりの申請は避けるべきです。審査には1か月〜2か月程度かかることもあるため、スケジュール管理は極めて重要です。
企業としては、社員の在留カードの有効期限を日頃から管理し、更新の準備を適切に進める必要があります。在留期限を過ぎてしまった場合、本人は不法滞在の状態となり、企業側も不法就労助長罪に問われるリスクを抱えることになります。また、更新申請中でも審査中であれば合法的に在留を継続できますが、原則として同一業務・同一条件での継続が求められる点にも注意が必要です。
更新の際も、審査対象は過去の勤務状況や企業の継続性などが確認されるため、直近の給与支払状況や雇用契約の継続内容が問われます。単なる“形式的な更新”ではなく、企業として責任ある就労管理を継続しているかが見られているという意識を持つことが重要です。
企業が準備・提出すべき主な書類一覧
在留資格の取得や更新をスムーズに進めるためには、企業側が用意すべき書類を正確に把握し、漏れなく整えることが大切です。主な書類としては、まず「雇用契約書」が挙げられます。これは就労条件を明記するものであり、勤務開始日、勤務地、業務内容、給与などを正確に記載する必要があります。内容が不明確であったり、業務が在留資格の範囲外と判断されると、審査に影響する可能性があります。
次に、「業務内容説明書」や「会社案内資料」も求められるケースが多くあります。これらは、応募者がどのような職務に就くのか、それが在留資格の要件に合致しているかを判断するための資料です。特に「技術・人文知識・国際業務」では、その業務が専門的であることを具体的に示すことが重要です。
また、企業の登記事項証明書や決算書類など、企業の信頼性を示す資料も必要になる場合があります。新設法人や小規模事業者の場合は、より慎重に審査される傾向があるため、丁寧な書類作成と説明資料の補足が求められます。これらの準備を入念に行うことで、申請の通過率や審査期間の短縮にもつながります。
外国人雇用における企業リスクと適切な管理方法
在留カード・就労資格証明の確認と管理
外国人を雇用する企業にとって、在留カードの確認は基本かつ最重要のステップです。在留カードには、氏名や在留資格、在留期間、就労制限の有無などが記載されており、採用時には必ず原本を確認し、コピーを保管しておくことが求められます。ここで注意すべきなのは、在留資格の種類によっては就労が許可されていない、または制限付きである場合があるという点です。企業がこれを見落とし、不適切な業務に就かせた場合には、不法就労助長罪に問われるリスクが発生します。
さらに、在留カードの内容だけでは不十分な場合は、「就労資格証明書」の取得を検討することも有効です。これは、採用予定の業務内容が在留資格に適合しているかどうかを事前に入管に確認するための制度で、本人または企業側から申請が可能です。とくに、業務内容が資格の範囲に該当するか不安がある場合や、在留資格の変更後に業務内容が変わる場合には、取得しておくことで審査の明確化と将来のリスク回避につながります。こうした基本的な確認を怠らず、記録としても残すことが、企業にとっての安全対策となります。
在留期間・資格外活動・各種届出の実務管理
外国人社員の在留期間は、日本人社員のように無期限ではなく、1年・3年・5年などといった期限付きで付与されています。そのため、企業は各従業員の在留期限を的確に管理し、更新漏れを防ぐ体制を整えておく必要があります。最近では、エクセルや人事労務ソフトによるリマインダー機能、もしくは行政書士事務所への外部委託といった方法で、期限管理をシステム化する企業も増えています。
また、「資格外活動」についても留意が必要です。本来の在留資格とは異なる業務や副業を行う場合は、事前に入管から「資格外活動許可」を得る必要があります。たとえば、留学生がコンビニでアルバイトをする、家族滞在者が短時間だけ働くといったケースです。許可を得ないままの就労は不法就労と見なされ、本人だけでなく雇用主も法的責任を問われる可能性があります。
さらに、外国人を雇用・退職させた場合には、14日以内に「雇用状況の届出」をハローワークと入管庁に提出する必要があります。この手続きを怠ると、行政指導や次回申請時の審査に影響する恐れがあるため、採用から退職までの一連の情報管理を社内でルール化しておくことが望まれます。
労務管理・社内コミュニケーションで起こりがちなトラブル例と対策
外国人社員との労務管理においては、日本人社員とは異なる文化や価値観、言語の壁を背景とした誤解やトラブルが生じやすい傾向があります。特に問題となりやすいのが、「雇用契約の理解不足」です。契約書に記載されている内容が十分に伝わっていなかったり、日本語や専門用語の難解さによって誤解が生じるケースがあります。このようなトラブルを防ぐには、契約時にわかりやすい言葉で丁寧に説明することが大切です。必要に応じて、英語や母語の翻訳版を準備するなど、理解を深める工夫が求められます。
また、勤怠や休暇、残業などに関する認識の違いから、職場での不満や離職につながるケースもあります。日本の職場文化に不慣れな外国人材に対しては、入社時に研修を行い、制度や社内ルールを丁寧に説明することがトラブル防止につながります。さらに、定期的な面談や相談窓口の設置など、日常的なコミュニケーションの機会を持つことも重要です。
これらの配慮や体制整備を通じて、外国人社員が安心して働ける環境を構築することは、企業の離職率低下や定着率向上にも直結します。単なる法令遵守にとどまらず、多様性を受け入れる企業文化を育てる姿勢が、持続可能な外国人雇用には欠かせません。
まとめ|制度理解から始める安定した外国人雇用
外国人材の採用は、単なる人手確保にとどまらず、企業にとって新たな成長や国際展開への足がかりともなり得ます。しかし、その出発点となるのが「在留資格」の正しい理解と適切な運用です。在留資格には29の種類があり、就労が可能かどうか、どの業務に従事できるのかといった条件がそれぞれ異なります。採用時だけでなく、在留期間の更新管理や就労範囲の遵守といった実務面にも注意を払うことが、企業と外国人材の双方にとって安心できる雇用関係を築く鍵となります。
本記事では、制度の全体像から具体的な資格の特徴、手続きの流れ、リスク管理までを解説しましたが、実務では個別事情によって対応が異なる場面も多くあります。不明点がある場合には、行政書士や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。また、自治体やJETROなどによる支援制度を活用することで、より円滑な運用が可能になります。
制度を理解し、適切に活用することで、外国人材の採用は“リスク”ではなく“企業の競争力”へと転換できます。グローバル時代にふさわしい組織づくりの一環として、在留資格への理解を深めていくことが求められています。
なお、海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima~出島~」の運営する「開国エンジン~縁人~」のようなグローバル人材マッチング支援サービスを活用することで、自社に最適なエージェントと出会うことが可能です。是非、お気軽にご相談ください。
本記事を参考に、自社に最適な外国人材の採用戦略を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談