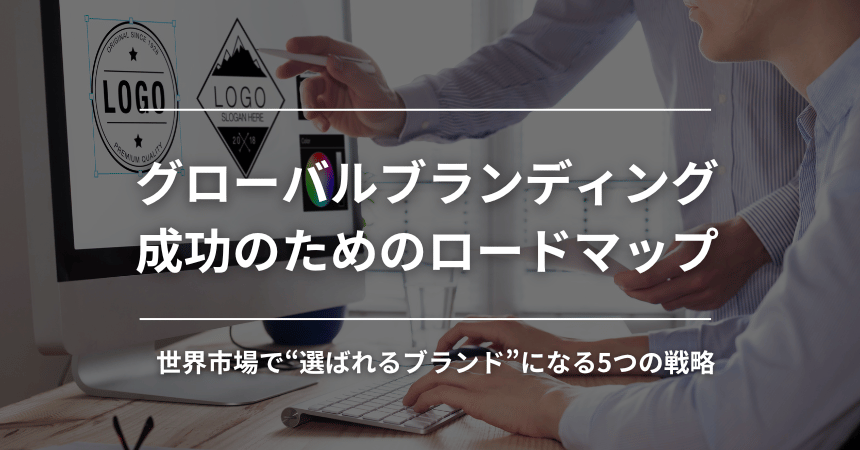AI時代にこそ求められる「グローバル人材」──テクノロジーでは代替できない“人”の価値とは?
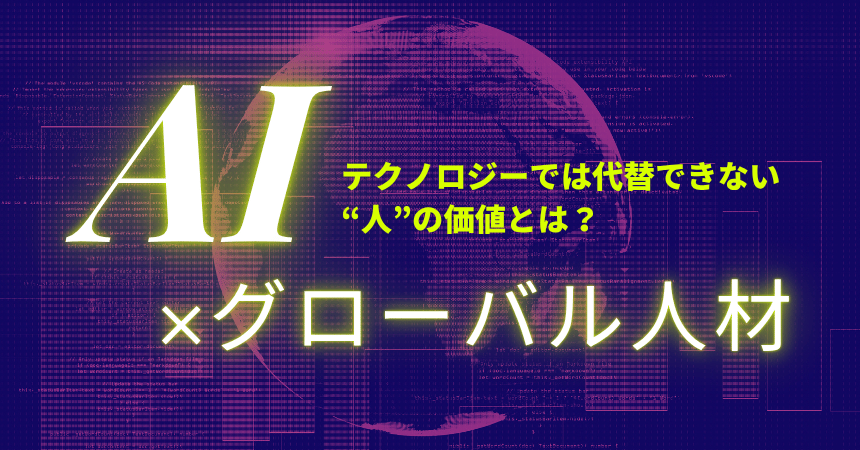
AIや自動化が急速に進展する現代において、ビジネスの競争環境はこれまで以上にグローバル化しています。多くの企業が海外展開や現地化を推進する中で、「人」の果たす役割が再び注目されています。AIが得意とするのはパターン認識や大量データの処理といった定型業務であり、一方で文化の違いを理解し、信頼関係を築きながら現地市場で機動的に動けるのは“人”ならではの力です。特に現地とのネットワーク形成や、柔軟な意思決定、共創的な関係構築においては、グローバル人材の価値が改めて見直されています。
本記事では、「グローバル人材」という言葉が示す意味を、日本人・外国人という国籍の枠を超えた“越境型人材”として広く捉え、AI時代における人の価値と役割、そしてその活用・育成戦略について詳しく解説していきます。テクノロジーが発展するほど、人にしかできないことが際立つ今、グローバル戦略における“ヒトの力”に改めて目を向けることが求められています。是非、参考にしてください。
▼ AI時代にこそ求められる「グローバル人材」──テクノロジーでは代替できない“人”の価値とは?
1. 現地化における「人」の役割とネットワークの力
なぜ“現地化”には「人」の力が欠かせないのか
海外市場への進出を成功させるために避けて通れないのが「現地化」です。製品・サービスのローカライズだけでなく、現地の文化、商習慣、生活リズムに根ざした経営やマーケティングが求められます。ここで中心となるのが「人」の存在です。たとえ最先端のAIを導入しても、現地の消費者心理やビジネスパートナーとの信頼関係構築、あるいは突発的な課題への対応といった“人間的な柔軟さ”までは代替できません。現地の文脈を読み解き、機微に対応できる人材の存在こそが、現地化の実現に不可欠なのです。
AIにはできない、信頼構築と共感のマネジメント
AIが進化した現代においても、人と人との信頼関係がビジネスの成否を分けるケースは多く存在します。特に海外では「まずは信頼ありき」で取引が始まることも多く、日本のように契約書で完結する関係とは異なる文化もあります。このような場面では、現地の文化的背景を理解し、相手の感情や立場に配慮した「共感力」や「対話力」が重要になります。これはAIでは再現できない、“人間らしさ”が求められる領域です。グローバル人材は単なる語学力や知識にとどまらず、こうした人間的スキルを発揮できる存在として、企業の国際展開を下支えしています。
ローカルネットワークが開く新たな市場への扉
現地のパートナーや消費者とのつながりを築くうえで、ネットワーク形成は欠かせません。信頼できる現地の人材を活用することで、ローカル市場の動きや行政対応、販路開拓などにおいてリアルタイムの情報を得ることが可能になります。さらに、その人材を中心としたネットワークが広がることで、これまでアクセスできなかった市場やチャンネルに道が開けることもあります。グローバル人材は、企業と現地社会を結ぶ橋渡し役であり、現地で根を張って長期的に信頼を築く“顔の見える資産”でもあるのです。
2. グローバル人材とは誰か──越境型人材の新定義
国籍や言語だけでは定義できない“グローバル性”
グローバル人材という言葉から、多くの方がまず思い浮かべるのは、語学に堪能で、海外で働いた経験があり、異文化に適応できる外国人材やバイリンガル人材かもしれません。しかし今日のビジネス環境において、グローバル人材の定義はより広く、より本質的なものへと進化しています。単なる語学力や海外経験だけでなく、「異なる価値観を受け入れ、協働できる力」「多文化の中で共通の目的を共有し推進できる力」が問われる時代です。国籍や言語ではなく、どれだけ“越境する意識”を持てるかが、真のグローバル性を測る指標になっています。
外国人材だけでなく、日本人にも求められる越境力
グローバル人材=外国人、というイメージが先行しがちですが、実際には日本人であっても、国内外の文化的ギャップを橋渡しできる視野とスキルを持つ人材は、グローバル人材といえます。たとえば、国内にいながら海外拠点と連携し、現地の文脈に合わせた施策を実行できる人や、外国人スタッフと円滑に協働できる人は、まさに越境型の価値を発揮している存在です。国をまたぐか否かではなく、“異なる文化や価値観の中で自分の役割を果たせるか”という視点こそが、これからのグローバル人材の本質といえるでしょう。
「越境型」人材が組織にもたらすイノベーション
文化や慣習の異なる環境に身を置き、そのギャップを乗り越える経験は、創造性や問題解決力を育てます。越境型人材は、自らの中に複数の価値観を共存させながら、新たな視点で課題に向き合うことができます。こうした人材が組織に加わることで、硬直しがちな意思決定プロセスに風穴を開け、多様な発想や柔軟なアプローチを持ち込むことが可能になります。特にグローバル展開を志向する企業にとっては、現地適応と全体最適のバランスをとるうえで、越境型人材の存在が大きな武器となります。
3. 育てるべき力は何か──グローバル人材育成の要諦
異文化理解力と“他者の前提”を想像する力
グローバル人材に求められる最も重要な能力のひとつが、異文化理解力です。これは単なる文化知識の蓄積ではなく、相手の立場や背景を想像し、その前提に配慮して行動できる“想像力”に近いものです。たとえば、日本では控えめな態度が美徳とされる場面でも、海外では自己主張や迅速な意思表示が求められることがあります。こうした価値観の違いを「どちらが正しいか」ではなく「どのようにすれば双方の意図が伝わるか」という視点で考えられる人材こそ、真に異文化適応力のある人といえます。
言語力以上に必要な「対話力」と「共創力」
もちろん、英語や現地語のスキルは重要ですが、それ以上に問われるのが、対話力と共創力です。言葉を操る力ではなく、言葉を使って相手とどのように関係性を築き、信頼を醸成できるかがグローバルな環境では問われます。特に国や文化を超えたビジネスの現場では、異なる立場の人々と共通の目的を見出し、共に価値をつくる「共創」が求められます。そのためには、相手の意見を引き出し、対話を通じて新たな選択肢を見出す力が不可欠です。このような力は、言語力よりも広い文脈での“関係性構築力”ともいえるでしょう。
“どこでも成果を出す”自律的な思考と行動
多様な価値観やスピード感が交錯する環境で成果を出すには、明確な指示を待つだけでは不十分です。グローバル人材には、自ら課題を発見し、環境に合わせて柔軟に動ける“自律性”が強く求められます。特に海外の現場では、意思決定のスピードや期待される成果の水準が異なるため、「言われたことをやる」のではなく、「何をすべきかを考え、動く」ことが前提となります。このような自律的なマインドと行動力は、長期的にグローバルな場で価値を発揮し続けるうえで欠かせない要素です。
4. なぜ“人”が鍵となるのか──AI時代のグローバル戦略
自動化では代替できない「文脈理解」と「現地感覚」
近年、AIや自動化技術の進展によって、定型業務や分析業務は効率化が進みつつあります。たしかに、翻訳、データ収集、商談前の情報整理といった作業は、AIによって一部代替可能になりました。しかし、現地の人々の感覚や文化的背景を踏まえて意思決定を行う「文脈理解」は、依然として人にしか担えない領域です。たとえば同じプロモーション施策でも、台湾、インドネシア、ドイツでは反応や適切な表現が異なります。こうした微妙な“現地感覚”を察知し、適応していく柔軟性は、人間の深い観察力や感情の機微に根ざした能力であり、AIには代替できません。
グローバルネットワーク構築における“信頼”の重み
海外ビジネスでは、「誰と組むか」が結果を大きく左右します。パートナー企業、現地の営業担当、自治体関係者など、関係性を築く上で決定的に重要なのは“信頼”です。そしてこの信頼は、単なる言語スキルや論理性ではなく、人としての誠実さ、柔軟さ、共感力によって育まれます。国境を越えたネットワークづくりには、「人として信頼できるかどうか」が問われるため、グローバルに通用する人材は単なるスキルホルダーではなく、“関係をつなぐ力”を備えた存在でなければなりません。
テクノロジーと“人”の融合が競争力を生む
AIやデジタルツールはあくまで手段であり、それをどう使い、どこに価値を生み出すかは“人”の判断に委ねられます。たとえば、AIによるデータ分析から得られたインサイトを、現地の顧客心理や市場慣習と結びつけて商品開発に活かすプロセスは、まさに人の創造力と解釈力が発揮される場面です。今後のグローバル戦略では、「テクノロジーを活用できる人」「人を動かすテクノロジー活用」がますます重要になります。つまり、AI時代だからこそ、人の価値が“薄れる”のではなく、“問われる”のです。
5. 企業はどう向き合うべきか──人材戦略の再構築へ
グローバル人材を“育てる”という視点の必要性
多くの企業では「グローバル人材がいない」「採用が難しい」といった課題が語られますが、そもそも“グローバル人材は生まれながらの存在”という先入観が障壁になってはいないでしょうか。語学や異文化理解は、後天的に身につけられるスキルであり、適切な環境と経験によって人は成長します。企業は、海外経験の有無や国籍といった表面的な属性だけでなく、学ぶ意欲や柔軟性といった本質的なポテンシャルに注目し、自社内でグローバル人材を育成する姿勢が求められます。たとえば、国内外の拠点間での短期異動、異文化環境でのチーム運営経験を積ませるといった“育てる設計”が不可欠です。
多様性を受け入れる組織風土の形成
グローバル人材を活用するには、その前提として「多様な人材が安心して働ける組織文化」がなければなりません。異なる文化・言語・価値観を持つ人々が共に働く現場では、誤解や軋轢が生じることもあります。それを乗り越えるには、心理的安全性が確保され、意見の違いを建設的に受け止めるマネジメントが重要です。また、言語面でのフォローや生活面での支援制度も不可欠です。多様性を“管理する”のではなく、“受け入れ、活かす”という視点を持った組織風土があってこそ、グローバル人材は力を発揮できます。
海外拠点との“対等な連携”を目指す体制づくり
本社主導の一方通行では、現地の実情に即した戦略は生まれにくく、グローバル化の本質からも逸れてしまいます。現地法人や外国籍社員を単なる“実行部隊”ではなく、戦略策定や意思決定の段階から関与させることで、より実効性のあるグローバル経営が可能になります。たとえば、現地のマーケット理解や人脈、消費者感覚を持つグローバル人材を経営層や中核メンバーに据えることも有効です。海外拠点との関係を“支店と本社”ではなく、“対等なパートナー”と捉える意識の変革が、企業の持続的なグローバル展開を後押しします。
6. まとめ|グローバル人材が企業の未来をつくる
AIやデジタル技術が加速度的に進化し、世界のビジネス環境が目まぐるしく変化する今、企業にとって“人”の価値がますます問われる時代に突入しています。特にグローバル市場においては、文化の違いを理解し、変化にしなやかに対応しながら、現地に根差した視点で意思決定できる人材の存在が、事業の成否を左右するといっても過言ではありません。
これまで「語学力」や「海外経験」といった表面的な指標で語られがちだったグローバル人材の定義も、今ではより本質的なスキル――すなわち、多様性を受け入れ他者と協働する力、自ら課題を発見し解決へ導く姿勢、変化を楽しみながら成長できるマインドへと変化しています。その意味で、外国人だけでなく日本人も含め、あらゆる人材が「グローバル人材」になり得る土壌が整いつつあるとも言えるでしょう。
そして、こうした人材の活用には、企業自体が変化していくことも不可欠です。評価制度や育成方針、海外拠点との連携体制、組織風土――それらすべてを「グローバル時代にふさわしい形」に再設計することが、企業にとって持続的成長の礎となります。
今後、ヒト・モノ・カネ・情報がよりダイナミックに動くグローバル経済の中で、企業が生き残る鍵は「どんな人材と、どう未来を描いていくか」にあります。グローバル人材は単なる“人手”ではなく、“企業の未来そのもの”をつくる存在です。この本質に目を向け、いま一度、自社の人材戦略を見直すことが求められています。
なお、海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima~出島~」の運営する「開国エンジン~縁人~」のようなグローバル人材マッチング支援サービスを活用することで、自社に最適な人材やエージェントと出会うことが可能です。是非、お気軽にご相談ください。
本記事を参考に、自社に最適なグローバル人材の採用戦略を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談