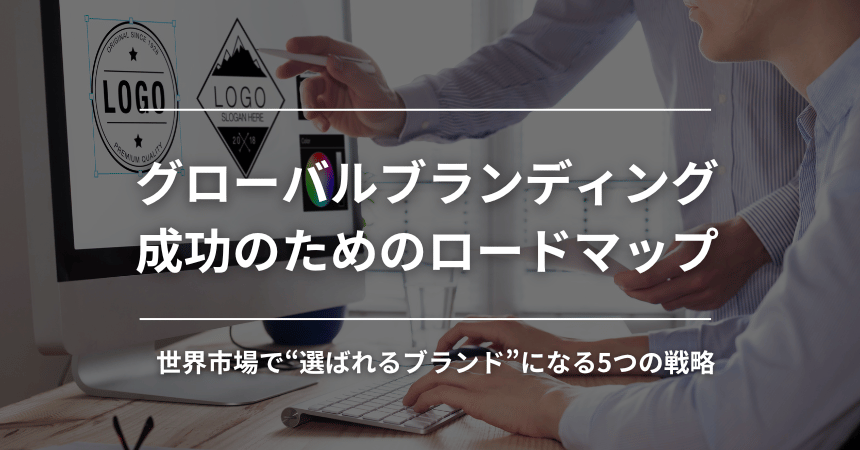訪日観光客の心をつかむ!インバウンド向けSNS戦略ガイド|成功事例と最新トレンドを紹介
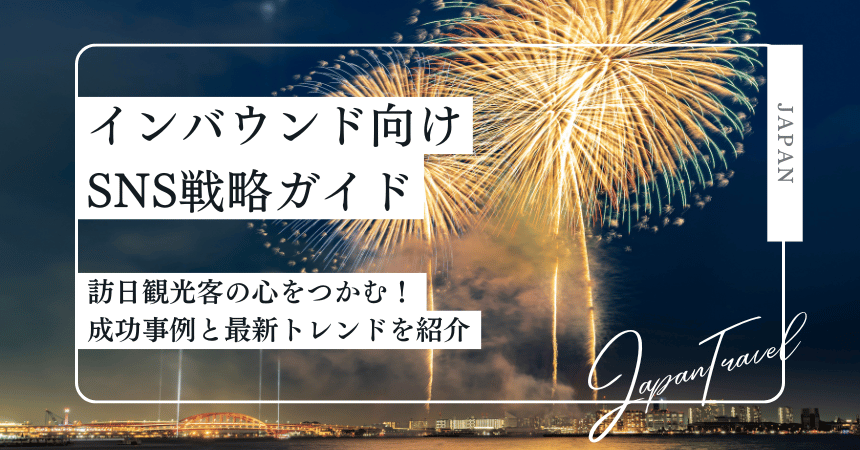
インバウンド市場が再び活況を呈する中、訪日外国人観光客の“行動の起点”としてSNSの存在感が急速に高まっています。情報収集から目的地の選定、飲食店・宿泊施設の選び方に至るまで、SNSが意思決定の重要なタッチポイントとなりつつあります。特にInstagramやTikTokをはじめとしたビジュアル系SNSの影響力は絶大で、訪日中に“映える”体験を求める傾向も顕著です。
しかしながら、闇雲にSNSを使って発信すれば効果が出るわけではありません。国や地域ごとのSNS利用傾向を理解し、自社の商品・サービスに合ったチャネルを選定し、ターゲットの共感を得る表現やストーリー性のある投稿を重ねていくことが重要です。さらに、継続的な運用体制やデータに基づいた改善も不可欠です。
本記事では、訪日外国人観光客向けビジネスにおけるSNSの活用法を体系的に解説します。SNSごとの特徴、集客成功事例、運用時のポイントまで網羅し、観光・小売・飲食など幅広い業種の方に役立つ“実践的なSNS戦略”をご紹介します。是非、参考にしてください。
▼ 訪日観光客の心をつかむ!インバウンド向けSNS戦略ガイド|成功事例と最新トレンドを紹介
1. インバウンド市場におけるSNSの重要性
訪日観光客の「検索」はSNSから始まる
近年、訪日外国人観光客の情報収集のスタート地点として、従来の検索エンジンではなくSNSを活用するケースが増えています。特に若年層の旅行者は、InstagramやTikTokといった視覚的に訴求できるSNSを通じて、観光地や飲食店、アクティビティの選定を行っています。これにより、「Googleで検索する前にInstagramで調べる」といった行動が当たり前となり、SNS上での“見え方”が集客成否を分ける大きな要素となっています。観光・飲食・小売といったリアル体験を伴う業態にとって、SNSは単なる広報手段ではなく、重要な“顧客接点”なのです。
SNS上の「口コミ」が意思決定を左右する
訪日外国人がSNSを活用する目的は単なる情報収集にとどまりません。他の観光客のリアルな体験や口コミが、そのまま訪問動機につながることも多く、いわば「信頼できる第三者の声」として大きな影響力を持ちます。
特に、現地の言語で発信されている投稿や、実際にその場所を訪れた人物のレビューは、同じ国や地域から来る他の観光客にとって強い説得力を持ちます。そのため、観光事業者が意識的にインフルエンサーや一般ユーザーによる投稿を促す工夫をすることが、SNS戦略の鍵となってきています。
コロナ禍以降、デジタルでの接触が主流に
パンデミックを経て、観光客の情報接触は紙媒体からデジタルへ、さらにWebからSNSへと急速に移行しました。現地到着後も、リアルタイムでSNSを活用して行き先を決める傾向があり、例えば「#tokyofood」や「#japantravel」などのハッシュタグを使って、目に留まった投稿から訪問先を決定するケースも多く見られます。こうした変化に対応するには、リアルタイム性・視覚訴求力・共感性を備えたSNS活用が不可欠であり、観光・小売・飲食などの各業界にとって、SNS運用は単なるオプションではなく“必須戦略”となりつつあります。
2. SNSごとの特徴と、インバウンドにおける使い分け方
Instagram:視覚訴求で“行きたくなる”を生み出す
Instagramは、写真や動画を中心としたプラットフォームであり、「映える」ビジュアルによって訪日観光客の関心を強く惹きつけます。特に飲食店、観光地、宿泊施設など、視覚的な魅力を持つビジネスにとっては極めて相性の良いSNSです。投稿内容としては、美しい風景や料理の写真だけでなく、店舗の雰囲気や体験の一瞬を切り取ったリール動画などが効果的です。
また、ハッシュタグの活用によって検索されやすくなるため、訪日客が多く使う英語や中国語、韓国語のタグを意識することが、グローバルな露出に直結します。
TikTok:体験ベースでバズを狙うなら最適
短尺動画を中心としたTikTokは、瞬発力のあるバズ効果が期待できるSNSです。飲食店のメニュー紹介や、観光地でのユニークな体験シーン、現地の文化や祭りなどを紹介するコンテンツは、多くの訪日観光客にとって新鮮で魅力的に映ります。若年層の外国人観光客をターゲットにする場合、TikTokは欠かせない媒体であり、日本の「日常にある非日常」を発信することで、興味喚起と共有の連鎖を生み出すことができます。近年では、旅行前にTikTokで現地の動画を検索し、訪問計画を立てるケースも増えているため、情報発信の即時性と動画編集の工夫が成功の鍵を握ります。
Facebook・YouTube:中華圏や中高年層には依然有効
Facebookは台湾・香港・タイなど、中華圏や東南アジアを中心に依然として利用者が多く、特に中高年層の訪日観光客への訴求力があります。イベント情報や新商品情報など、テキストと画像を組み合わせて伝えるコンテンツとの相性が良く、コミュニティ形成にもつながる特徴があります。
また、YouTubeは長尺動画による詳細な紹介が可能であり、旅の全体像を伝えるには非常に有効な媒体です。旅程紹介や観光地のガイド動画、文化体験の記録など、ブランド価値を深く伝えたい場合に適しており、信頼性のある情報源としての活用が期待できます。
3. 成功するSNS運用のポイントと最新事例
コンテンツは“情報”より“体験”を届ける発想で
インバウンド向けのSNS運用では、単に商品や施設の情報を発信するのではなく、「その場にいるような体験」を届けることが重要です。訪日観光客は、日本文化や風景に対して強い憧れや関心を持っており、その雰囲気や体感をSNSを通じて事前に味わうことで、「行ってみたい」という感情が喚起されます。例えば、スタッフが紹介する和菓子作り体験の様子や、裏通りの居酒屋でのローカルな食体験など、臨場感あふれる投稿は、観光客の想像力を刺激します。結果として、現地での「体験予約」や「来店」につながりやすくなるのです。
現地語・英語・多言語対応で“届く投稿”に
どれほど魅力的な投稿をしても、ターゲットに届かなければ意味がありません。そこで重要なのが、多言語での発信です。インバウンド市場では、英語はもちろん、中国語(繁体字・簡体字)や韓国語での情報提供も求められます。Instagramの投稿に多言語キャプションを付けたり、YouTube動画に多言語字幕をつけたりすることは、訪日意欲のある外国人に情報を“届ける”ための基本です。また、SNS広告やリスティング広告のターゲティング機能を活用すれば、特定の国・地域からのユーザーに絞って訴求することも可能です。
最新事例:旅前×SNSで予約につなげた成功パターン
たとえば、ある京都の着物レンタル店では、Instagramを通じて台湾人インフルエンサーとのコラボレーション投稿を行い、短期間で台湾からの予約が倍増したという事例があります。動画では、着物選びから着付け、観光地での撮影までをドキュメント形式で紹介し、“自分も同じ体験ができる”という疑似体験が強い反響を呼びました。また、沖縄のダイビングショップでは、TikTokでの体験動画投稿からLINE予約への導線を工夫することで、訪日前の予約件数が2倍に伸びたといいます。このように、SNSからの導線設計を意識した運用が、インバウンド市場では大きな成果をもたらしています。
4. インバウンド集客にSNSを活用する際の注意点
文化的背景の違いを理解した発信を心がける
インバウンド向けにSNSを運用する際、日本人向けと同じ感覚で発信してしまうと、意図しない誤解やネガティブな反応を招くことがあります。たとえば、宗教的な価値観やタブーに対する無理解から、不適切な表現を含む投稿をしてしまうことも少なくありません。特に飲食やファッション、宗教施設などを扱う場合には、対象となる国や地域の文化的背景や慣習をきちんと理解したうえで、コンテンツを設計する必要があります。また、現地スタッフやネイティブパートナーの意見を取り入れることで、より精度の高い情報発信が可能になります。
継続的な運用とレスポンス体制の構築
SNSは単発の発信で終わるものではなく、継続的な運用と顧客との双方向のコミュニケーションが求められます。特に訪日前の観光客からは、SNSを通じた質問や予約問い合わせが寄せられることも多く、タイムリーな返信体制を整えておくことが重要です。InstagramのDMやFacebook Messenger、LINE公式アカウントなど、複数チャネルを適切に管理し、対応の迅速さや丁寧さを心がけることで、顧客満足度や信頼感が高まります。また、問い合わせ内容からニーズを読み取ることで、今後のSNSコンテンツや商品改善に活かすヒントも得られるでしょう。
効果測定とPDCAサイクルの継続
SNS施策の成果を最大化するには、数値的な効果測定と改善のサイクルが不可欠です。どの投稿が多くの「保存」や「シェア」を生んだのか、どの国からのユーザーが反応しているのかといった分析を通じて、次回以降のコンテンツ内容や発信タイミングを最適化していきます。インバウンド向けの投稿であれば、日本時間だけでなく、現地時間に合わせた投稿タイミングの調整も効果的です。SNS運用は“発信して終わり”ではなく、“改善し続ける”ことが鍵となります。
5. 訪日観光客向けSNS活用で成果を上げる企業の特徴
明確なターゲットと訴求軸を持っている
訪日観光客向けにSNSを活用して成果を上げている企業の多くは、ターゲットと訴求軸が明確です。たとえば、「台湾の20代女性に“かわいい”日本文化を発信したい」「タイの富裕層ファミリーに“安心・高品質な日本の体験”を伝えたい」といったように、誰に・何を伝えたいのかがはっきりしていることで、投稿の内容やトーンがブレることなく、一貫性のあるブランドイメージが形成されます。漠然と「外国人観光客に向けて発信する」のではなく、ターゲットの国籍・年齢・関心領域を定め、そこに響く情報設計を行うことが成果に直結します。
SNSを“接点”だけでなく“導線”として捉えている
SNSは情報発信の場であると同時に、顧客との接点を実際の来店・購買につなげるための「導線」として活用する視点が重要です。成果を上げている企業は、Instagram投稿から多言語予約ページやGoogleマップへのリンクを丁寧に設計し、スムーズな来店・来場体験へとつなげています。また、ストーリーズでメニューを紹介し、ハイライトでアクセス方法をまとめるなど、ユーザー目線での「使いやすさ」を意識している点も共通しています。SNSで興味を喚起したら、いかに迷わせずに行動してもらうか、その“最後のひと押し”がコンバージョンの鍵となります。
現地インフルエンサーやパートナーを積極的に活用
言語や文化的背景の壁を乗り越えるには、現地に影響力を持つインフルエンサーやパートナー企業との連携が大きな力になります。成果を出している事例では、日本国内での発信だけでなく、台湾・タイ・アメリカなど現地のSNSアカウントと連携したキャンペーン展開が見られます。信頼できる第三者が紹介することで、SNS上での認知と信頼の獲得が飛躍的に高まり、結果として実際の訪問や購買に結びつくケースが多く報告されています。現地ネットワークをどう構築し、パートナーと共にブランディングしていくかは、グローバルSNS戦略において欠かせない視点です。
6. インバウンド向けSNS戦略の設計と今後の展望
顧客導線を設計する「ストーリー思考」の重要性
インバウンド向けにSNSを活用する際には、単に写真や動画を投稿するだけでなく、「誰に、どんな価値を届け、どこへ導くのか」というストーリー設計が鍵となります。たとえば「SNSで日本の文化に興味を持った→店舗の場所を調べた→訪問して体験した→満足して投稿した」という一連の流れが、自然かつスムーズにつながっている状態が理想です。特に観光客は言語や交通手段に不安を抱えていることも多いため、SNS上で“次のアクション”を迷わせない導線づくりが求められます。情報の断片をつなぐ「体験設計」が、投稿の効果を最大限に引き出すポイントです。
プラットフォームの選定と地域ごとの最適化
SNS戦略を成功させるためには、投稿内容だけでなく「どのプラットフォームを使うか」の選定も重要です。国によって人気のSNSは異なり、たとえば中国ではInstagramやFacebookではなく小紅書(RED)やWeChatが主流です。一方、台湾・タイ・アメリカではInstagramやTikTokの活用が効果的です。また、同じInstagramでも言語や文化に合わせたアプローチが必要となるため、投稿言語、ビジュアルのトーン、ハッシュタグの選定なども地域特性に最適化する必要があります。グローバル視点とローカル視点の両立が、成果を引き出すSNS運用のポイントです。
インバウンド市場の多様化と“体験価値”の重視
コロナ禍以降、訪日観光の目的は「モノの購入」から「コトの体験」へと大きくシフトしています。SNSでもその傾向は顕著で、商品の紹介よりも「旅先で得られる感動体験」や「そこでしかできない文化との出会い」がシェアの対象となっています。そのため、SNS活用においても“買える商品”の情報だけでなく、“その商品にまつわるストーリー”や“体験できるシーン”を丁寧に伝えることが重視されます。単なる情報発信を超え、訪日客の“思い出の一部”となるようなコンテンツづくりが、これからのインバウンドSNSの鍵となるでしょう。
7. まとめ|SNSを軸に、インバウンド戦略を再設計しよう
訪日観光が回復し、再び世界中の旅行者が日本を訪れるようになった今、インバウンドビジネスにおけるSNSの役割はますます大きくなっています。かつてのようにガイドブック頼りではなく、旅行者自身がスマートフォンを片手にリアルタイムで情報収集をし、SNSで見たスポットや商品を目的に訪日する時代が到来しています。つまり、SNSは単なる宣伝ツールではなく、「旅の入口」として機能しているのです。
その一方で、ただ目立つ投稿を発信するだけでは、継続的な集客や購買にはつながりません。国・地域ごとの文化的背景を理解し、適切な言語・トーン・ビジュアルで、ターゲットに合わせた丁寧なコミュニケーションを行う必要があります。さらに、SNSで得た関心をいかに来店や購買、再訪につなげるかという導線設計も欠かせません。ここに“ストーリー”や“体験価値”といった要素が求められる理由があります。
インバウンド市場は今後ますます多様化し、個人旅行客や富裕層、Z世代など、セグメントごとにニーズも異なっていくでしょう。だからこそ、SNSは一律のマーケティングではなく、よりパーソナルで文化的文脈に即した発信が必要となるのです。自社のターゲットが誰なのかを見極め、その人たちの旅の起点として、SNSを戦略的に活用すること。それこそが、これからのインバウンドビジネスの競争力となるはずです。
訪日客との新たな関係を築くために、SNSを単なる販促手段としてではなく、「共感と共創の場」として位置づけ、インバウンド戦略全体を再設計する。その視点こそが、アフターコロナ時代の成功を左右する鍵になるでしょう。
なお、「Digima~出島~」には、インバウンド対策の専門家が多数登録されています。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
本記事が、インバウンド対策ならびに海外展開を検討される日本企業の皆様にとって、実務の一助となれば幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談