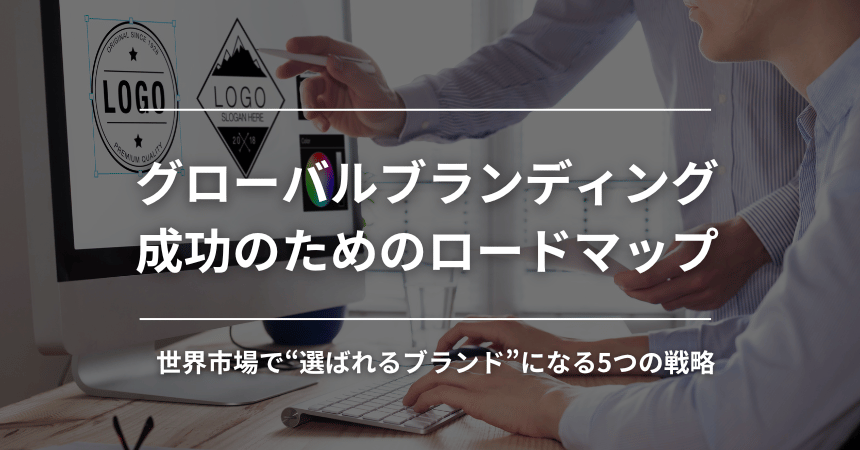「廃プラスチック問題」の商機とは? | 日本企業による環境ビジネスの海外展開

国境を超える「廃プラスチック問題」を、中国→東南アジアへと進む「廃プラの輸入規制」の詳細と併せて解説します。さらに「廃プラ」に付随する「国際的な環境ビジネスの商機」についても「日本企業が取り組む海外ビジネスの事例」を挙げて、「日本の廃プラ輸出量」と併せて考察していきます。
「廃プラスチック(廃プラ)とは、使用後に廃棄されたプラスチックを主成分とする廃棄物の総称です。これまで日本はその「廃プラ」の約5割を中国へ〝輸出〟していました。しかし、2017年末に中国が廃プラスチックの輸入を禁止。溢れ出た廃プラは世界を〝漂流〟し、東南アジアへと漂着しました。
しかし、2019年5月10日に採択された、有害廃棄物の国際的な移動を規制する「バーゼル条約」の改正案を受けて、東南アジア各国でも廃プラの輸入規制が加速。日本やアメリカを含む大量のプラスチック消費国が、自国の資源ゴミを東南アジア諸国へと輸出することが困難になりつつあるのが現状なのです…。
本テキストでは「廃プラスチック問題」を巡る世界の状況と、中国→東南アジアへと〝漂流〟を続ける「廃プラ」を巡って、日本企業が取り組んでいる新たな「国際的な環境ビジネス」の商機について解説します。
▼ 「廃プラスチック問題」の商機とは? | 日本企業による環境ビジネスの海外展開
- 1. 廃プラスチックとは?
- 2. 廃プラスチック問題の概要
- 3. 2017年末に中国が「廃プラ輸入」を禁止したことが発端
- 4. 「日本の廃プラ輸出量」(2017年版)
- 5. 東南アジア・南西アジア諸国の「廃プラ輸入規制」について
- 6. 「SDGs」を商機とする「廃プラ環境ビジネス」
- 7. 日本企業による廃プラ規制を商機とする「国際的な環境ビジネス」
▼アナタの海外ビジネスを成功させるために
1. 廃プラスチックとは?
廃プラスチックを資源として再活用するのは世界全体の命題
そもそも「プラスチック」とは、熱や圧力を加えることで成形加工ができる高分子物質の総称です。その原料は原油などの有償の資源となっており、使い終わったプラスチックである「廃プラスチック」を資源として再活用するのは、先進国および後進国も含めて世界全体の命題とされています。
そして「廃プラスチック(※廃プラ)とは、使用後に廃棄されたプラスチック製品および、その製造過程で発生したプラスチックのかすや、廃タイヤ・合成ゴムくず・合成繊維くず・ビニールシートくずなど、プラスチックを主成分とする廃棄物の総称です。
さらに「廃プラスチック」は、一般廃棄物・産業系廃棄物とに分けられますが、仮に同じ廃棄物であっても、処理する自治体によって、産業廃棄物とするケースもあれば、一般廃棄物として取り扱うケースもあります。
2. 廃プラスチック問題の概要
G20大阪サミットで導入された〝廃プラ〟「50年ゼロ」目標
2019年5月に開催された「G20大阪サミット(20ヵ国・地域首脳会議)」では、その主要議題として、世界経済・貿易などと並んで「海洋プラスチック(廃プラスチック)問題」についても討議され、世界中で問題となっている〝廃プラ〟を2050年までにゼロにする、いわゆる「50年ゼロ」目標を導入することで各国が合意しました。
ただ、その〝50年ゼロ〟という数値目標についても、科学的なデータに基づいた上で算出したものではなく、そもそも世界の海岸を汚染している海洋プラスチック(廃プラスチック)自体がどこから流出しているのかといった詳しい汚染状況の調査も満足に進行していません。また、その具体的な対策も各国の自主的な取り組みに一任されているという、いまだ問題が山積みの状況でもあるのです。
3. 2017年末に中国が「廃プラ輸入」を禁止したことが発端
日本の廃プラスチック輸出の約5割が中国だった
先述したように「G20サミット」で取り上げられるほど、世界における喫緊の課題となっている「廃プラスチック問題」。
そもそもの発端は、2017年末に中国が廃プラスチックの輸入を禁止したことでした。
2017年7月27日、国務院により「海洋ごみの輸入禁止と固形廃棄物輸入管理制度改革の実施計画」が発表。同年12月31日より施行されました。この「計画」によって、中国では〝環境に悪影響を与える廃プラを含む資源ゴミの輸入〟が禁止されたのです。
困ったのは日本を含む先進国でした。先述の「計画」が発表される前年である2016年の中国の貿易統計によると、同年の中国の廃プラスチックの輸入量は734万7,200トンとなっており、内訳としては、その約1割となる約28万4,310トンが日本からであり、香港に次ぐ輸入先となっていました。
また日本の貿易統計では、2016年における廃プラスチック輸出の約5割が中国でした。そもそも日本およびアメリカの廃プラスチックの最大の輸出先は中国でしたが、「計画」発表後は、両国とも中国への廃プラ輸出量は減少しています。
具体的には2017年8月の時点で86,000トンだった日本の対中国への廃プラ輸出量は、「計画」施行後の2018年1月にはわずか2,000トンにまで激減したのです。
もちろんそのわずかな期間で日本の廃プラ産出量が激減することはあり得ません。中国へ輸出できなくなった廃プラを含む世界の資源ゴミは、新たな輸出先へと向かいました。結論から言えば、その代替地として、タイヤベトナムやマレーシアといった東南アジア諸国の国々へと、廃プラは〝漂流〟していったのです。
4. 「日本の廃プラ輸出量」(2017年版)
廃プラは中国から東南アジア各国へと〝漂流〟
中国から拒否される形で、行き場を失った先進国の〝廃プラ〟は東南アジアへと漂流していきました。
事実、東南アジア各国では、日本を含む先進国からの廃プラスチックを含む資源ゴミの輸入量が急増していきました。
■2017年における日本の廃プラ輸出量
・ベトナム: 12万6,219トン / 前年比92.4%増
・マレーシア:7万5,435トン / 前年比2.3倍
・タイ:5万8,160トン / 前年比2.3倍
・インドネシア:2,700トン / 前年比6.6倍
・フィリピン:2,139トン / 前年比3.7倍
・シンガポール: 2,113トン / 前年比3.2倍
上記のように、「東南アジアの廃プラ輸入規制」が実施されるまで、日本による東南アジア各国への輸出が軒並み増加していったのです。
※南アジアであるインドへの輸出も2.1倍の7,526トンと大幅に増加していた
「バーゼル条約」の改正案が「東南アジアの廃プラ輸入規制」を加速
しかし2019年現在、日本やアメリカを含む大量のプラスチック消費国が、自国の資源ゴミを東南アジア諸国へと輸出することが困難になりつつあります。
その大きな要因に、2019年5月10日に採択された、有害廃棄物の国際的な移動を規制する「バーゼル条約」の改正案があります。
「バーゼル条約」は国連環境計画が1989年にスイス・バーゼルで採択。92年に発効されました。具体的には、有害廃棄物は国内での処理を原則としており、輸出時には相手国の同意が必要などと定めています。
先述の改正案では「汚れた廃プラスチック」の輸出入を規制する条約が改正。他のゴミが混じった廃プラスチックを規制対象に加えるというもので、180を超す国が合意したのです。
今回の条約改正により、汚染されていたり他のゴミと混じったりしてリサイクル不可能な廃プラを輸出するには、事前に相手国政府の同意を得なければならなくなりました。
改正された条約は、2021年1月1日から施行予定となっています。
5. 東南アジア・南西アジア諸国の廃プラ輸入規制について
2018年以降、アジア各国で廃プラの輸入規制・利用規制が厳格化
中国という巨大な受け入れ先を失った〝世界の廃プラ〟は、先述のように東南アジア各国へと〝漂流〟していきました。しかし東南アジアのいわゆる途上国には、有害廃棄物を適切に処理する施設も技術も限界がありました。事実、たくさんの資源ゴミが放置されたり、大雨などでそれらが海に流出、あるいは投機される事案が相次いでいたのです。
そのような背景もあって、先述の「バーゼル条約」の改正以前から、アジア各国で廃プラスチックの輸入・利用規制の必要性が叫ばれるようになり、2018年以降、アジア各国で廃プラの輸入規制・利用規制は厳格化していきました。
下記の表は、そんな東南アジア・南西アジア諸国の廃プラ輸入規制についてまとめたものになります(下記のJETROのリンクより抜粋)。

参照:「東南アジア諸国が廃プラスチック輸入規制を強化、日本の輸出量は減少」JETRO
結論から言えば、もはや「廃プラスチック」を巡る問題は、世界中で「脱プラスチック」へと向かっています。
タイやインドやフィリピンなどでは、投棄されたビニール袋が排水溝にたまることで引き起こされる洪水被害が問題視されています。
また、工場や施設の処理能力を超えた「廃プラスチック」は海へと流れ込みます。なかでも、近年、海洋中に離散したマイクロプラスチック(※サイズが5mm以下の微細なプラスチックごみ)は、そこに含有・付着する化学物質が食物連鎖に取り込まれることで、地球全体の生態系に及ぼす悪影響が世界中で懸念されています。
6. 「SDGs」を商機とする「廃プラ環境ビジネス」
「SDGs」のゴール14として掲げられた「海洋・海洋資源の保全」
先述したように、2019年5月に開催された「G20大阪サミット」にて、討議された「海洋プラスチック(廃プラスチック)問題」は、近年注目されている「SDGs(エスディージーズ=Sustainable Development Goals)」でも取り上げられています。
SDGs(エスディージーズ)とは、「持続可能な開発目標」の略語で、平和かつ豊かで持続可能なグローバル社会を構築するための国際目標を指します。
2015年に国連で定められたSDGsには、「持続可能な社会」を実現するための17ゴール(目標)が定められていますが、そのゴール14として「海洋・海洋資源の保全」があります。
具体的には、2025年までに〝あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する〟。2020年までに〝海洋および沿岸の生態系の回復のための取組を行う〟…といった旨の目標が掲げられているのです。
7. 日本企業による廃プラ規制を商機とする「国際的な環境ビジネス」
廃プラ規制を商機とした、日本企業による「環境ビジネス」の海外展開
国際目標であるSDGsですが、そもそも21世紀の営利企業にとって、「SDGs」とは、未来を指向した「イノベーションの機会」であり、「資金調達における投資へのアピール」であり、「新たなビジネスチャンスの創出」でもあります。つまり、そこで掲げられている目標=グローバルマーケットにて自社の商品・サービスを展開することで、そこに商機が生まれるのです。
最後のセクションでは、今回のテーマである廃プラ規制を商機とした、日本企業による「環境ビジネス」の海外展開について解説します。
「三菱製紙」「王子ホールディングス」「日本製紙」
「三菱製紙」はプラスチックを代替する食品包装紙を、2019年9月より日本およびアジアで販売することを発表。従来のプラスチックではなく、生分解性を持つ紙材だけを使用することで、廃棄の際の環境負荷を軽減します。
また「王子ホールディングス」も、新開発の環境に配慮した紙素材「シルビオ バリア」のサンプル提供を開始。
「日本製紙」は2019年3月にマレーシアの包装材メーカー・TSプラスティックスを買収。グローバル市場を見据えた、素材から包装材までの一貫生産体制を構築するべく、パッケージ事業のバリューチェーン拡大を推進しています、
「パナソニック」「ユニクロ」
「パナソニック」もプラスチック素材の代替品として活用できる植物性新素材を開発。プラスチック部品を多用している自社の家電製品に採用していくとのことです。
さらにファーストリテイリング傘下の「ユニクロ」も、日本を含む世界2,000店舗で使用するレジ袋や商品の包装材を、生分解性プラスチックや紙素材からなる新たな素材からなるものに大幅刷新する旨をアナウンスしています。
「日立造船」がタイでゴミ焼却プラントを設置
「日立造船」はタイのラヨーン県で建設されるゴミ焼却プラントの設備工事を受注したと発表。
紙くず、繊維くず、廃プラスチックなどをフィルム状に破砕して燃料化した「フラフ」と呼ばれる燃料の製造プラントに隣接して建設されるプラントは、そのフラフを燃料として焼却発電を行うとされています。
タイのみならず、中国やインドでも、埋立処理以外の廃棄物処理が望まれていることから、ごみ焼却発電プラントの需要が高まっています。今回のごみ焼却発電プラントは、先述のフラフ燃料を活用したEfW(Energy from Waste)プラントとして各方面から注目が集まっています。
「市川環境エンジニアリング」がベトナムで廃棄物処理事業
千葉県市川市に本社を置く「市川環境エンジニアリング」はベトナムにて廃棄物処理やリサイクル事業を展開。
ベトナムにある製紙工場など、石炭を熱源としている施設において、廃プラスチックを主材料としたフラフ燃料の製造・販売事業を進めています。
株式会社西原商事(福岡市)は、外務省の「中小企業等の海外展開支援事業(ODAを活用した中小企業等の海外展開支援のための委託調査業務)」に採択され、「フィリピンのスラバヤ市におけるリサイクル型廃棄物中間処理施設パイロット事業」を実施しています。
2013年にスラバヤ市にリサイクル工場を建設。市内で発生した一般ゴミの収集および分別事業を行い、事業終了後は施設をスラバヤ市に譲渡しています。
8. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
今回は、国境を超える「廃プラスチック問題」と銘打って、中国→東南アジアへと〝漂流〟を続ける「廃プラ」に潜む、国際的な環境ビジネスの商機について、日本企業が取り組む海外ビジネスの事例と併せて解説しました。
先述したように、近年の「SDGs」を背景とする新しいビジネスに注目が集まっています。当然今回ご紹介した「廃プラ問題」を商機とする新たな国際的な環境ビジネスにもチャンスがあることは言うまでもありません。
『Digima〜出島〜』には、厳選な審査を通過した優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。当然、複数の企業の比較検討も可能です。
「海外展開したいがどうすればいいのかわからない」「戦略立案から拠点設立、販路開拓までサポートしてほしい」「海外事業の戦略についてアドバイスしてほしい」…といった、多岐に渡る海外ビジネスに関するご質問・ご相談を承っています。
ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、御社にピッタリの海外進出を支援するサポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。
(参照文献)
・「プラスチックを取り巻く国内外の状況」環境省
・「プラスチックはもういらない!?(東南アジア・南西アジア)」JETRO
・「東南アジア諸国が廃プラスチック輸入規制を強化、日本の輸出量は減少」JETRO
・「東南アジアでも廃プラスチックの輸入禁止へ」JETRO
・「インドネシアも廃プラ輸入禁止へ 中国禁輸で「殺到」」朝日新聞 DIGITAL
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談