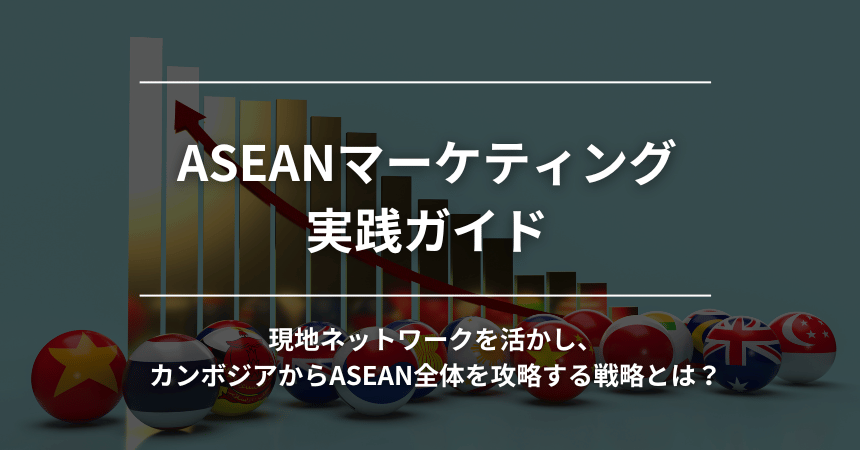【国際労務の基礎知識】海外勤務の就業規則や給与規定、海外赴任者規程など海外労務管理のポイントを解説

本テキストでは、国際(海外)労務とは何か、といった基礎知識から、国際労務で注意すべき3つのポイント、海外勤務の形態や就業規則、国際労務に関する各規定、さらには海外勤務規定の重要性と、それに記載すべき事項…などについて解説します。
海外進出している日本の企業の数は年々増えており、2020年の外務省による調査「海外進出日系企業拠点数調査」によると、海外における日系企業の拠点数は80,373拠点となっています。これは2019年の調査時における74,072拠点より、6,301拠点も数が増えていることとなります。
グローバル時代において、海外へと挑戦する日本企業は増加していますが、企業が海外進出を考える際には、例えば事業立ち上げなどさまざまな段階で自社の社員を海外に派遣する必要性が出てきます。
海外勤務に従事する社員がいる場合の労務管理はどのようにすればよいのでしょうか?
国際労務・海外労務と言うと一般的に、日本から海外に派遣される海外勤務者に対する労務管理と、日本企業で勤務する外国人労働者への労務管理の2種類がありますが、本テキストでは前者について解説します。
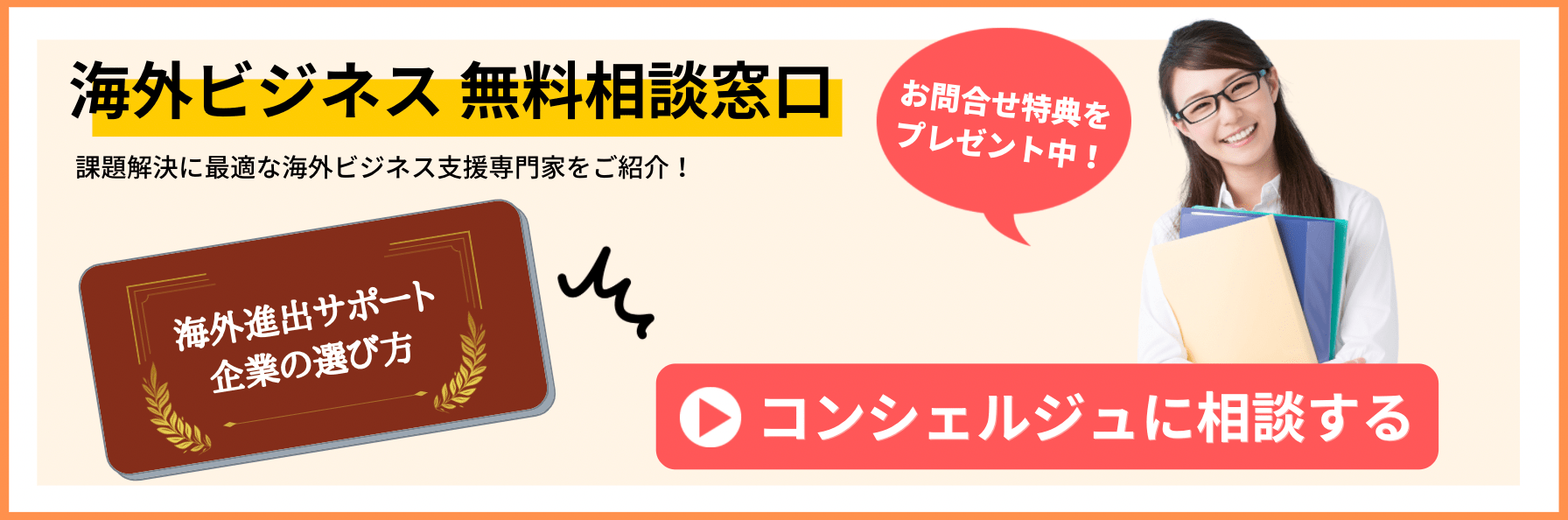
▼国際(海外)労務の基礎知識 | 国際労務で注意すべきポイント、海外勤務規定に記載すべき事項とは?
- 1. 国際(海外)労務とは?
- 2. 国際(海外)労務で注意すべき3つのポイント
- 3. 海外勤務にはおもに3つの種類がある
- 4. 海外勤務者に適用される就業規則について
- 5. 海外勤務規定の重要性とその記載事項について
- 6. 海外勤務における給与の規定について
- 7. 海外勤務における税金と保険料の規定について
- 8. 海外勤務における勤務条件・休日の規定について
- 9. 海外勤務における赴任者の家族の規定について
▼アナタの海外ビジネスを成功させるために
1. 国際(海外)労務とは?
海外勤務者に対しては、さまざまな労務管理が必要となります。この項では、海外進出を考えるなら必ずおさえておきたい国際労務における労務管理について解説します。
海外進出において必要な労務管理とは?
海外進出する多くの企業が本社から現地へと日本人社員を派遣しています。海外事業の立ち上げ時の管理や、経営のテコ入れなど、日本人社員が必要なケースは少なくありません。
海外勤務者に対しては、現地の労働法に基づいた労務管理が求められます。法的には日本の労働法は全く関係なくなるのですが、もともと日本で勤務していた社員に対して日本の労働法を一切無視した無茶な労働はさせられません。
海外勤務者に対しての労務管理は、現地の国や地域における労働法規をしっかり理解しておくことが必須です。
日本と海外では法で定められる会社の義務範囲が異なることが多く、労務に関する慣行も異なるからです。
2. 国際(海外)労務で注意すべき3つのポイント
日本と海外では労務に関する慣行が異なる。それを前提に、このセクションでは、国際(海外)労務で注意すべき3つのポイントについて簡潔に解説します。
ポイント① 国によって異なる労働法の傾向を知っておくことが必要
たとえば、シンガポールでは理由なく懲戒解雇が可能ですが、インドネシアでは懲戒解雇でも退職金の支払いが義務付けられているなど、懲戒解雇についてだけでも国によって違いがあります。シンガポールの労働法は会社に対して有利になるよう設計されているのに対して、インドネシアの労働法は労働者に対して有利となっています。
労働者の権利を守ることを重視しているのか、会社の意向を尊重しているのか、国や地域によって異なる労働法の傾向をしっかりおさえておくことが重要です。
ポイント② 母国人と外国人の雇用人数に注意
国や地域によって異なる、現地における外国人、つまり日本人の雇用人数の割合についても理解しておくことが重要です。労働者に対して有利な労働法を定めているインドネシアでは、外国人を1人雇用するためにはインドネシア人を10人雇わなくてはいけません。
ポイント③ 就業規則の作成義務にも国や地域で違いがある
就業規則の作成はフィリピンやマレーシアでは義務化されていません。その他にも、就業規則と個別契約にある記載が矛盾していた場合の優先順位についても国によって違いがあります。
※就業規則については、後ほど詳しく解説します
このように、さまざまな点で日本と異なる海外での勤務は国際労務が非常に重要なのです。
3. 海外勤務にはおもに3つの種類がある
国によって労働法がかなり異なるため、海外進出において労務管理が非常に重要であることがおわかりいただけたでしょうか。この項では、国際労務を考える上で理解しておくべき「海外勤務」について解説します。
海外勤務にはおもに3種類あり、勤務形態によって適用すべき労務が変わってきます。
海外勤務の3つの種類「出張」「出向」「転籍」について
国際労務の管理対象となる海外勤務者には「出張」「出向」「転籍」という3種類の勤務形態があります。それぞれの違いをおさえておきましょう。
① 出張
一時的な海外勤務であり、指揮命令に関わる業務が日本の企業に所属。責任の所在も日本にあり、かつ日本の企業に指揮命令者がいる、という勤務形態が「出張」です。
② 出向
出張と異なり、指揮命令者が現地の企業にいるのが出向です。日本の企業に従業員として在籍している状態で現地の指揮命令者の下で勤務するもので、日本企業とも現地の企業とも労働契約を交わしている、という勤務形態になります。
③ 転籍
現地の企業で労働契約を結ぶのは出向と同じなのですが、その際に日本の企業を形式上退職する、という勤務形態が「転籍」です。
日本企業の多くが「出向」という形態で海外進出をしている
前述した3種類の海外勤務形態「出張」「出向」「転籍」のうち、日本企業の多くが2つめの勤務形態である「出向」の形で社員を海外赴任させています。
「出向」は日本にも現地にも在籍している勤務形態ですが、現地の労働法が優先適用されることが多く、基本的には日本の労働法は適用されません。これを「属地主義の原則」と言いますが、次の項で解説します。
海外赴任者に適用される「属地主義の原則」とは?
「属地主義の原則」とは、「勤務にあたる国や地域が定める法令の適用を受けることが原則である」ということです。そのため、日本の労働法は海外の事業所へ出向や転籍する社員には適用されません。
出張の場合は日本の労働法が適用されますが、出張であるかの判断には指揮命令や労働管理などの実態が重視されるため、出向とみなされた場合は適用されません。
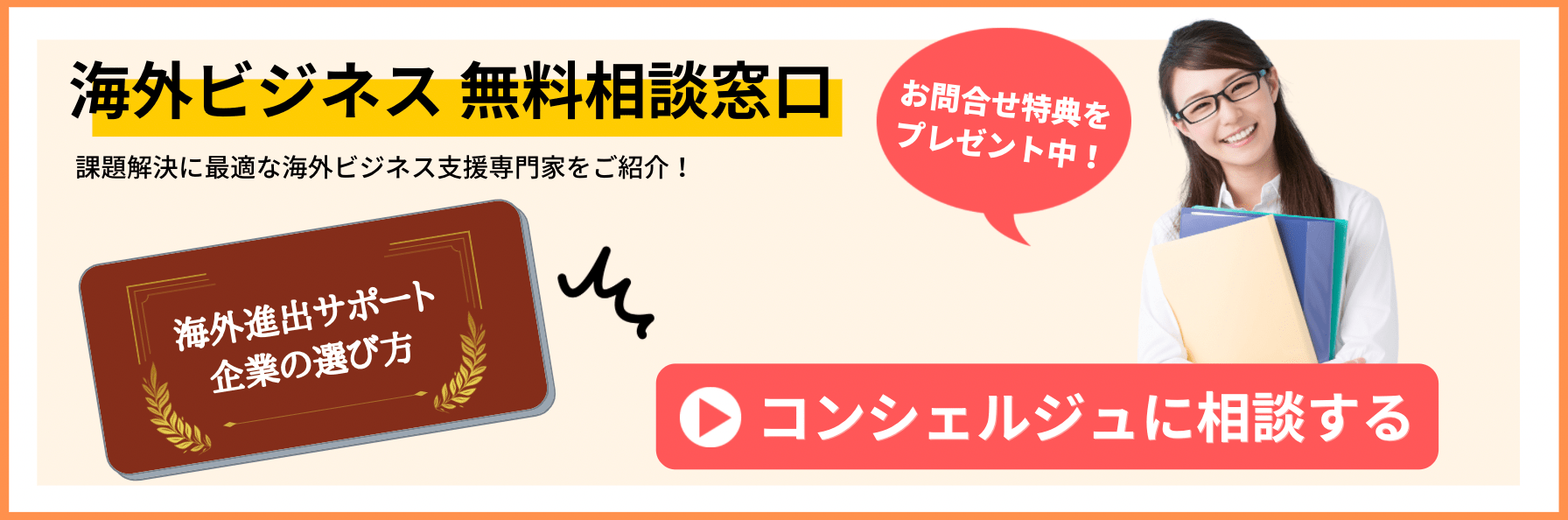
4. 海外勤務者に適用される就業規則について
国や地域によって就業規則の作成が義務化されている場合とそうでない場合があることはすでに解説したとおりです。この項では、そもそも就業規則とはどういったものなのか、海外事業を検討している企業が事前にその旨を記載すべきなのかを解説します。
就業規則とは?
就業規則とは、労働者の労働条件や職場において守るべきルールを定めたものであり、日本においては常時10人以上の労働者を雇用している企業に対して就業規則を作成することと、労働基準監督署への届出が義務づけられています。
海外事業を検討している企業は、事前に就業規則などにその旨を明記しておくべき
先に述べた通り、海外勤務者は「属地主義の原則」によって現地で定められている法令の適用を受けるため、出張以外のケースでは日本の労働基準法を基にした就業規則は適用されません。
就業規則や契約書に海外勤務の可能性があることを明記せずに労働者を海外で勤務させることはできません。そのため、海外勤務の可能性がある場合は、就業規則などに必ず明記する必要があります。
5. 海外勤務規定の重要性とその記載事項について
海外勤務を命じるためには就業規則への明記が必要ということを理解したところで、この項では海外勤務規定の重要性とその記載事項について解説します。
海外勤務規定の重要性について
海外では日本とさまざまな点で労働環境が異なります。規定が定まっていないと、海外勤務者は保険や医療、給与についてなど、多くの心配を抱えることになります。海外で勤務する際にも日本にいた時と同等の生活水準を保障するため、海外勤務における規定を定めておく必要があります。
海外勤務規定を作成する際には国内の給与や福利厚生とのバランスも考慮しなければいけませんし、勤務者によって待遇や処遇がバラバラということもトラブルのもとですから、一貫性を持った処遇を規定しておくべきです。
近年、国際源泉所得税の課税漏れによる追徴課税において、海外給与の労務に関するものが増えています。相当額を超える海外給与を本社で負担すると寄付金として課税されることがあるため注意が必要ですが、こういったトラブルを避けるためにも、海外給与について規定した海外勤務規定が必要なのです。
海外勤務規定の記載事項について
「海外勤務規定」「海外赴任規定」「海外駐在規定」といったワードで検索すると、多くのサンプルが見つかります。業種や職種などによっても記載事項は変わってきますが、一般的には下記の事項は必ず記載しておく必要があります。
・海外における勤務の期間
・労働条件
・休日
・給与
・税金
・保険
・旅費
・福利厚生
・家族への対応
上記のそれぞれを次の項で解説します。
6. 海外勤務における給与の規定について
この項では、前項でご紹介した海外勤務規定の一般的な記載事項の中から、多くの企業が記載している重要な事項をピックアップして解説します。
給与の規定は掘り下げると非常に細かくなるため、全て解説するのは難しいので、ここでは海外給与の規定の大原則と、海外給与設定について理解を深めておきましょう。
給与の規定 | 海外給与規定の大原則「No Loss,No Gain(ノーロス・ノーゲイン)の原則」とは?
海外給与の規定には、多くの企業が「No Loss,No Gain(ノーロス・ノーゲイン)の原則」を取り入れています。
「No Loss,No Gain(ノーロス・ノーゲイン)の原則」とは海外勤務者も国内勤務者もどちらも損も得もしない、という考え方であり、例としては海外勤務の間の現地でかかる所得税を会社が負担し、勤務者に対しては日本での所得税と同額を控除するという「みなし所得税による調整」が挙げられます。
海外給与の支払い方法
海外給与の支払い方法はおもに3種類。それぞれ「購買力補償方式」「別建て方式」とそれを併用する「併用方式」があります。
① 購買力補償方式
現在、この「購買力補償方式」が多くの企業で採用されており、海外給与の支払い方法の主流と言える方式です。国内での購買力と同等の購買力が現地で補償されるというものであり、日本での生活費相当額に為替のレートや生計費指数などを掛けて、現地での適正給与を計算します。
② 別建て方式
別立て方式はかつて多く採用されていた方式です。現地での賃金表を作成し、それに従って給与が支給される方式であり、日本国内の給与体系とは整合性がなく、現地の給与体系に精通していないと賃金表を構築することが難しいため、近年はあまり使われていないようです。
③ 併用方式
「購買力補償方式」「別建て方式」を併用する考え方ですが、別立て方式のようにわざわざ賃金表を作るというよりは、現地法人に金額を提示してもらい、差額を日本企業が調整するなどの方法が取られることも多いようです。
7. 海外勤務における税金と保険料の規定について
この項では、前項と同じく海外勤務規定の一般的な記載事項の中から、多くの企業が記載している重要な事項のうち「税金と保険料の規定について」ピックアップして解説します。
税金と保険料の規定
海外勤務者の給与に課税される税金は、「183日ルール」により短期(滞在期間183日以下)の海外勤務の場合は日本で課税対象となりますが、長期の滞在の場合は現地で課税されます。役員は海外勤務したとしても、日本で税金を支払うことになります。
労災保険は基本的には日本で勤務している従業員に適用されるものですが、労災保険の特別加入制度によって海外勤務でも日本と同じ労災補償を受けることができます。
健康保険は、給付は受けられますが、現地では日本の保険証は使えません。医療費は全額負担したのちに払い戻すという手間が発生します。厚生年金保険の場合は、5年以上の海外勤務の場合は現地の年金制度に加入する必要があります。
雇用保険は転籍の場合は資格を喪失してしまうので注意が必要です。また、介護保険は40歳以上65歳未満の被保険者の場合は「介護保険適用除外該当届」を提出することで海外勤務期間は保険料を支払う必要がなくなります。
8. 海外勤務における勤務条件・休日の規定について
この項では、前項と同じく海外勤務規定の一般的な記載事項の中から、多くの企業が記載している重要な事項のうち「勤務条件・休日の規定」を解説します。
勤務条件・休日の規定
国や地域によっては休日や時間外の労働賃金が非常に高くなることもあるため、現地の労働法をしっかりおさえておきましょう。また、休日は企業によっては課外勤務者にも日本の規定を準用しているケースもあるため、休日をどういった取り扱いにするかを明記しておく必要があります。
また、日本では退職時の有休の買い上げは認められませんが、中国やベトナムでは買い上げる義務があり、特に中国は買い上げ率が通常の賃金の3倍となっています。
9. 海外勤務における赴任者の家族の規定について
海外勤務においては、勤務者の家族についても規定しておくことが必要です。この項では「赴任者の家族の規定」について解説します。
赴任者の家族の規定
海外勤務者が家族を伴って海外で勤務する場合と、家族を日本に残して海外勤務する場合、以下の2つのケースが考えられます。
家族を伴って海外で勤務する場合
家族と共に海外勤務となる場合は、家族がうつになるケースも多いため、本人だけでなく家族のメンタルもケアする対策を講じなければなりません。また、子供がいる場合は現地で学校に通う必要があるので、そのための語学研修などに補助を出すのか、といったこともしっかり決めておきましょう。
日本での住宅ローンの控除や、住宅の維持、老父母の介護など、さまざまなことに対して、どこまで会社が負担するかを検討する必要があります。
家族を日本に残して海外勤務する場合
この場合は単身赴任となるため、環境がかなり変わることで不安定になる精神面を考慮したメンタルヘルス対策を講じる必要があります。また、日本での家族の生計費が維持できる給与を設定しなければなりませんし、一時帰国の回数も増やす必要があるかもしれません。
10. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
海外進出を考える上で、現地に派遣する日本人社員の役割は非常に重要です。日本とは勝手が違う現地でもストレスなく勤務してもらうためには、国際労務が必要不可欠。海外勤務者の労務管理にはさまざまな規定が必要であり、現地の法にも熟知しておく必要があります。
「Digima〜出島〜」には、厳正な審査を通過した優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。当然、複数の企業の比較検討も可能です。
「海外進出の際の労務について知りたい」「海外駐在員に関する労務業務をサポートしてほしい」「海外ビジネスの事業計画立案のアドバイスをしてもらいたい」「海外に進出したいが何から始めていいのかわからない」…といった、多岐に渡る海外進出におけるご質問・ご相談を承っています。
ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
もっと企業を見る