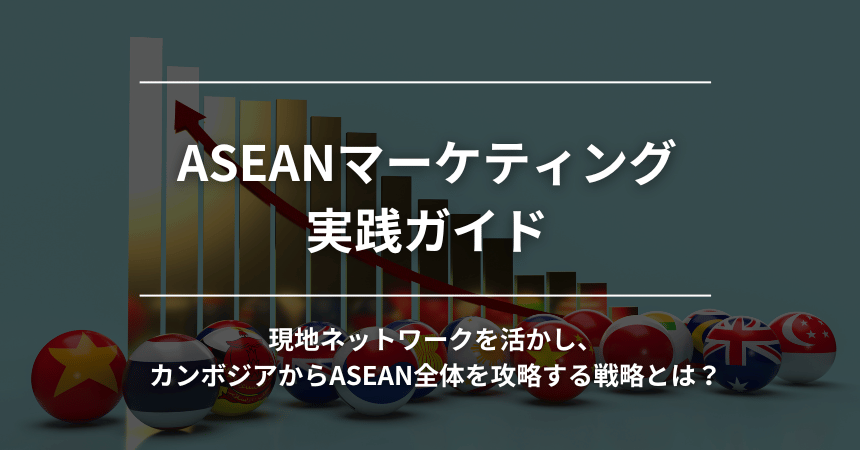激変するASEANへのアメリカ関税|ベトナム・タイ拠点も直撃? トランプ政権の相互関税が日本企業に迫るサプライチェーン再構築

2025年4月、アメリカのトランプ大統領が発表した「相互関税」政策が、世界経済に新たな緊張をもたらしています。従来の関税水準に加え、貿易相手国の関税や非関税障壁を踏まえた報復的な関税を上乗せするというこの政策は、日本には24%、ベトナムには45%、タイには36%と、主要な貿易相手国に対して極めて高い関税を科す内容となりました。
これにより、アメリカ向けに製品を供給してきた日系企業のサプライチェーンは大きな見直しを迫られています。とりわけ、中国以外の生産拠点として注目されてきたASEAN諸国にも、直接的な影響が波及し始めています。本記事では、「ASEAN 関税」「ベトナム 関税」といった視点から、今回の政策が日本企業の海外展開戦略に与える実質的な影響を整理し、今後の対応策を考察します。是非、参考にしてください。
▼ 激変するASEANへのアメリカ関税|ベトナム・タイ拠点も直撃? トランプ政権の相互関税が日本企業に迫るサプライチェーン再構築
トランプ政権「相互関税」の全体像とは?
アメリカが打ち出した「一律10%+国別関税」の仕組み
2025年4月、トランプ政権が発表した「相互関税」政策は、従来の関税制度を根本から揺るがすものとなりました。その中核となるのが、「すべての貿易相手国に対して一律10%の関税を課す」というベースの関税に加え、相手国ごとの“実質的な障壁水準”に応じて個別に追加関税を上乗せするという仕組みです。アメリカ政府は、関税だけでなく、非関税障壁や為替政策、補助金制度なども含めた総合的な観点から、「米国にとって不利である」と見なす国に高い関税を課す方針を示しました。
この制度は、いわば「相互性の回復」を掲げたものとされていますが、その実態は、アメリカが独自に評価・判断した“障壁”に対して一方的な関税措置を取るものであり、国際貿易の透明性や公平性という観点から大きな議論を呼んでいます。すべての国に最低10%が適用される時点で、アメリカへの輸出が前提となっている企業にとっては、追加コストの発生が避けられず、価格競争力を大きく損なう恐れが出ています。
日本は24%、ベトナムはなんと45%、タイ36%…
今回の発表でとりわけ注目を集めているのが、国別に示された関税率の水準です。日本には24%、中国には34%、EUには20%、インドには26%が課されるなど、アメリカが長年貿易赤字を抱えてきた相手国に対して、軒並み高い関税率が設定されています。そして、近年日系企業の進出が活発なASEAN主要国にも、大きな負担がのしかかります。ベトナムには45%、タイには36%、インドネシアには32%、マレーシアにも24%と、いずれも米国向け輸出には極めて不利な水準です。
特にベトナムは、ここ数年で中国からの生産シフト先として注目され、日本企業の製造拠点も数多く設けられてきました。そのベトナムからアメリカに輸出する製品に45%もの関税が課されるとなれば、もはや「チャイナ・プラス・ワン」としての機能が大きく損なわれることになります。ASEAN地域全体が持つ“輸出拠点としての優位性”に対して、今回の関税措置は大きな転換点をもたらしているのです。
自動車に25%の追加関税も(完成車、部品)
さらに今回の政策では、自動車に対して一律25%の追加関税が発動されることも明らかにされています。この措置は、相互関税とは別枠で実施され、完成車のみならず、自動車部品の一部にも適用される可能性が指摘されています。日本からアメリカへの輸出において、自動車は最も重要な品目のひとつであり、現時点で約6兆円以上の輸出額を誇っています。そこに25%という高い関税が加わることで、価格競争力は大幅に低下し、日系メーカーの米国販売台数や利益への影響は避けられないと見られています。
加えて、アメリカ国内では「日本車の販売が多すぎる」といった批判も根強く、非関税障壁という観点からも、日本市場に対する不満が表明されています。そうした政治的背景を踏まえると、今回の関税措置は短期的な経済政策にとどまらず、米国の産業政策全体に直結した構造的な問題とも言えるでしょう。次項では、このような動きがASEAN各国の現地拠点にどのような影響を及ぼしているのか、より具体的に掘り下げていきます。
ASEAN拠点への影響:ベトナム・タイ・インドネシアが直撃
高関税により「チャイナ・プラス・ワン」戦略が機能不全に
これまで多くの日本企業が中国からの生産分散先として選んできたのが、ASEAN諸国でした。中でもベトナムやタイ、インドネシアといった国々は、賃金水準が比較的安定しており、インフラや人材の整備も進んでいることから、「チャイナ・プラス・ワン」の有力な選択肢として注目を集めてきました。しかし、今回の相互関税政策により、こうした戦略の前提が大きく揺らぎ始めています。
ベトナムに対しては45%、タイには36%、インドネシアには32%という関税が設定され、米国市場に向けた製造・輸出拠点としての優位性は一気に後退しました。これまでは、中国からASEANに生産を移すことで関税リスクを回避しつつ、アメリカ市場を維持するというスキームが多くの企業で機能していましたが、今後はその“迂回ルート”自体が関税の網にかかることになります。これにより、ASEAN拠点が抱えるコスト競争力の優位性は大きく損なわれる可能性があります。
ベトナムからの輸出は「採算割れ」も現実に
特にベトナムは、この数年で急速に日本企業の進出が進んだ国のひとつです。衣料・繊維、電子機器、精密部品といった幅広い業種で製造拠点が設けられ、米国市場向けの供給拠点として期待されてきました。しかし、45%という異例の高関税が課されれば、多くの製品は米国市場での価格競争力を完全に失ってしまいます。仮に価格転嫁ができたとしても、販売数量は確実に落ち込み、採算割れとなるケースも出てくるでしょう。
また、ベトナムは労働集約型の産業に加え、近年ではハイテク分野にも進出を強めていました。日系企業が部品の最終組み立てをベトナムで行い、アメリカに輸出するというモデルは、まさにその典型です。しかし、こうしたスキームが関税によって封じられた場合、生産工程の再編や生産地の再移転といった抜本的な対応が必要となり、企業にとっては時間的・資金的な大きな負担がのしかかります。
タイ・インドネシアの「日系製造拠点」も例外ではない
同様の影響は、タイやインドネシアといったASEANの他国にも広がります。タイには日系自動車メーカーや部品サプライヤーが多く拠点を構え、「アジアのデトロイト」とも称されるほど、製造業の集積が進んでいます。これまで、タイで生産された自動車部品を米国に輸出するモデルは有効に機能していましたが、36%という高関税が加われば、採算性は大きく揺らぐことになります。
インドネシアもまた、家電や電機、日用品などの組み立て拠点として活用されてきました。関税率は32%とやや抑えられてはいるものの、それでも企業にとっては大きな追加コストとなることに変わりはありません。現地での生産を見直す動きが広がれば、雇用や経済にも波及し、ASEAN域内の政治的・社会的な安定性にまで影響を及ぼす可能性もあります。
このように、今回の関税政策は、単に“米国との貿易”という一面にとどまらず、ASEAN全体の経済構造や、そこに展開する日系企業の事業戦略を大きく揺るがすインパクトを持っているのです。次項では、こうした状況を受けて、日本企業がどのような対策を講じていくべきか、実際に取りうる対応戦略について詳しく見ていきます。
日本企業が取りうる3つの対応戦略
1. 米国現地生産のさらなる強化で関税回避を図る
高関税という新たな障壁が設けられた今、日本企業がまず検討すべきは、米国市場における「現地生産」の強化です。とりわけ自動車業界では、すでに多くのメーカーがアメリカ国内に組立工場を構えていますが、今回の相互関税政策により、これまで以上に“現地で作って、現地で売る”体制へのシフトが急務となっています。メキシコやカナダなど、USMCA圏内における供給体制も含め、より広域的な現地化戦略が必要になるでしょう。
また、部品メーカーやサプライヤーにとっても、完成品メーカーの現地シフトに合わせた供給体制の再構築が求められます。これには、現地法人の増設やM&Aを通じた現地企業との連携強化、または製造設備の一部移設といった具体的な動きが含まれます。もちろん、アメリカ国内の人件費や土地コストの高さといった課題もありますが、関税負担によるコスト増との比較を経て、より安定した収益構造を築くための中長期的な投資判断が問われています。
2. ASEAN拠点は「脱・米国市場型」に再設計すべき局面へ
一方で、ASEANに展開する製造拠点は、必ずしも米国市場への供給にこだわる必要はありません。今後は「米国向け」と「その他地域向け」の製品や生産体制を明確に分けることで、関税リスクを分散させる戦略が重要になります。たとえば、タイの工場では欧州・中東向け、ベトナムではアジア域内市場や日本国内向けといった具合に、地域別に役割を最適化する動きが加速すると考えられます。
実際、ASEAN域内の内需は年々拡大しており、RCEPやASEAN自由貿易地域(AFTA)などの地域協定も発効済みです。これらの制度を活かすことで、米国市場に依存せずとも、ASEANを中心とした新興国市場へのアクセスを確保することができます。米国を起点とするグローバル供給網が揺らぐ中、ASEANは“独立した市場”として、今後より重要な役割を担っていくことになるでしょう。
3. 調達・物流ネットワークの多元化とFTA活用がカギ
サプライチェーン全体の再構築という意味では、製造拠点だけでなく、調達・物流体制の多様化も重要な要素です。特定の国や地域への依存を避け、複数の調達先を持つことによって、関税や輸送リスクを分散させることができます。また、各国との自由貿易協定(FTA)を最大限に活用し、関税の軽減や原産地規則をクリアする形でのサプライチェーン設計も求められます。
例えば、日本と東南アジア諸国、または日英EPA、日EU・EPAなどを活用すれば、一定の条件下で輸出入時の関税負担を大きく削減できる可能性があります。近年では、サプライチェーン管理や原産地証明書のデジタル化も進んでおり、これを機に貿易管理体制の高度化を図る企業も増えてくるでしょう。
このように、現在の通商環境の変化に対しては、単なる「回避」ではなく、むしろ“戦略的に関税を見据えた体制構築”が不可欠となっています。次章では、関税リスクが顕在化する一方で、なおも成長が期待されるASEAN地域の「ポジティブな側面」にも目を向けていきます。
それでもASEANは「チャンスの地」であり続ける
米国依存からの転換で見えるASEANの新たな可能性
トランプ政権の相互関税政策は、確かにASEAN拠点の米国向け輸出モデルに深刻な打撃を与えています。しかしながら、それが直ちに「ASEAN離れ」につながるわけではありません。むしろ、今こそASEAN各国の本来の潜在力に目を向けるべき局面に来ているといえるでしょう。
まず注目すべきは、ASEAN地域の“市場としての成長性”です。ベトナムやインドネシア、フィリピンといった国々では、中間層の拡大とともに内需市場が急速に拡大しており、現地消費を狙った製品・サービス展開の機会が広がっています。従来のように「安価な製造拠点」としてのみ捉えるのではなく、「現地で作り、現地で売る」モデルへの転換は、今後のビジネスを持続的に展開していく上で大きな鍵となるでしょう。
加えて、ASEAN各国は地域内の経済連携強化にも注力しています。2022年に発効したRCEP(地域的な包括的経済連携協定)は、日本や中国、韓国、オーストラリアなどを含む巨大な経済圏を構成しており、域内貿易のさらなる活性化が期待されています。このような多国間の貿易枠組みをうまく活用することで、関税コストを抑えながら、地域間輸出を加速させる道も十分に開かれているのです。
脱炭素・デジタル・医療など新領域への進出余地も
さらに、ASEAN諸国は従来型の製造業にとどまらず、脱炭素・デジタル化・医療といった成長産業への政策的投資も進めています。たとえば、タイは“バイオ・サーキュラー・グリーン(BCG)経済”を掲げ、クリーンエネルギーや循環型製造の推進に注力しており、日系企業にとっても協業や技術提供のチャンスが広がっています。
また、ベトナムではEC市場やフィンテックの成長が著しく、デジタルサービス分野での市場参入を図る企業が増加しています。インドネシアでは医療アクセスの拡大が政策課題となっており、日本の医療機器やヘルスケアサービスへのニーズも高まりつつあります。こうした新たな分野においては、米国との貿易摩擦の影響を受けにくく、むしろ現地需要を起点とした展開が可能です。
このように、ASEANは単なる“生産コストの安い製造拠点”という見方を超え、成長市場・戦略拠点としてのポテンシャルを内包しています。今後の日本企業には、米国リスクから目をそらすのではなく、それを契機としてASEANとの関係性をより戦略的に深めることが求められているのではないでしょうか。
次項では、このような激動の環境下において、日本企業が進むべき方向性を改めて整理し、具体的な戦略転換のあり方について考察していきます。
世界の分断を超えて、日本企業が進むべき道とは
変化に適応する柔軟性が、海外展開の生命線に
相互関税の導入という米国発の大きな通商転換は、日本企業にとって厳しい外的環境の変化であることは間違いありません。しかし、こうした状況だからこそ問われているのは、単なる“防御”ではなく、将来を見据えた“再構築”の力です。過去数十年にわたり、日本企業はグローバル展開の中で数々の外的ショックを経験してきましたが、それを乗り越えてきたのは、常に変化に柔軟に対応する姿勢と、現地に根差した戦略の実行力でした。
今回も同様に、従来の米国中心の供給モデルにこだわるのではなく、多極化する世界経済の構造に合わせて、地域ごとに最適な形で事業を再編成していくことが求められています。ASEAN拠点は、米国への輸出基地としてだけでなく、アジア全体へのゲートウェイとして再定義されつつあります。そして米国市場についても、現地生産やメキシコ・カナダを活用した体制を築くことで、関税リスクを織り込んだ安定的なビジネスの構築が可能になります。
海外展開に「第3の選択肢」を持つことの重要性
今後の海外展開戦略においては、従来の「中国依存」から脱却し、さらに「米国依存」にも偏らない、新たな“第3の軸”を見出すことが肝要です。ASEANをその一つとすることはもちろん、インドや中東、アフリカといった新興市場にも中長期的な視点で目を向ける必要があります。地政学リスク、通商政策、為替、ロジスティクス……さまざまな不確実性が交錯する中においては、一国や一地域に経営資源を集中させること自体が、大きな経営リスクとなり得るのです。
また、こうした新興国展開には、現地の制度や文化、商習慣に即した「現地適応力」も不可欠です。その意味でも、海外展開においては、信頼できる現地パートナーの存在や、情報の正確な把握、法制度への対応力など、周辺の支援体制の整備がこれまで以上に重要になります。自社単独では読みきれない変化の波を、パートナーシップやネットワークの力で乗り越えていく――。そのような視点が、今後の企業成長の分水嶺となるでしょう。
まとめ
トランプ政権による「相互関税」は、日本企業にとって大きな通商リスクであると同時に、これまでの海外展開戦略を見直す契機ともなり得る動きです。ASEAN各国の拠点を軸とした「チャイナ・プラス・ワン」モデルが再考を迫られる一方で、ASEAN自身が持つ成長性、そして地域間経済連携の進展は、引き続き大きなビジネス機会を内包しています。
重要なのは、変化を恐れるのではなく、それに適応し、自社にとって最適なサプライチェーンや市場戦略を再構築する姿勢です。米国市場の関税リスクを冷静に受け止めたうえで、ASEANを“米国の代替地”としてだけでなく、“自立した成長市場”として見直すことが、今後の持続的な海外展開につながるはずです。
「Digima~出島~」では、こうした環境変化に対応するための現地情報や専門家とのネットワークを活用し、貴社の次なる一手をご支援いたします。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
ASEANをめぐる環境が大きく動く今こそ、戦略の再設計に向けた第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談