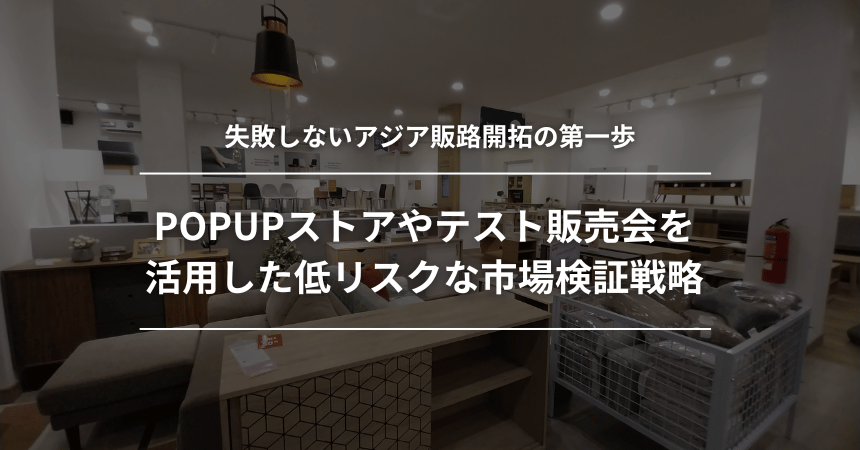VAT(付加価値税)とは?海外進出する日本企業が知っておきたい仕組み・国別税率・実務対応のポイント
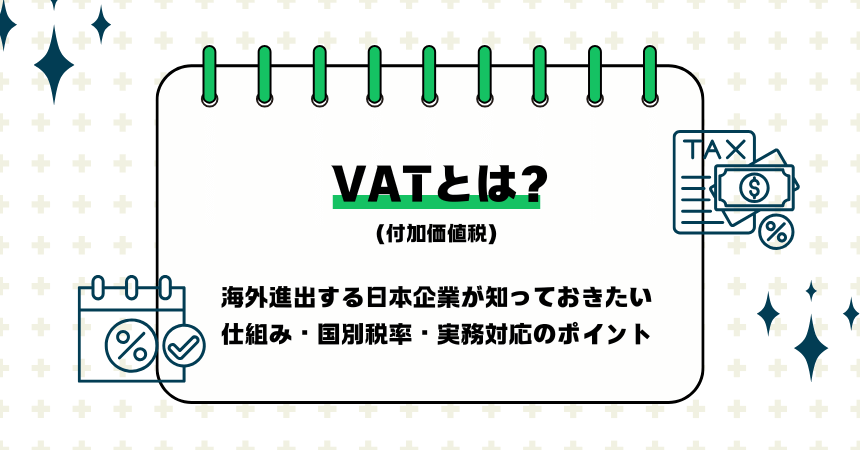
海外展開を進める日本企業にとって、製品やサービスの品質、物流の最適化、現地パートナーの選定などは長年のテーマとして重視されてきました。しかし、もう一つ見落とせないのが「VAT(付加価値税)」に関する対応です。VATは、EUや英国をはじめとする多くの国々で導入されている間接税制度であり、越境ECや現地法人の運営に関わる企業にとって“避けては通れない制度”となっています。
特に近年では、AmazonやShopifyなどを通じた越境ECの拡大に伴い、VAT登録義務が新たに課されるケースが急増しています。「税率はいくらか」「どのタイミングで登録が必要か」「現地での請求書や納税はどうすべきか」といった実務的な課題に対応できていないと、通関の遅延やペナルティ、最悪の場合は販売停止といった深刻なリスクを招きかねません。
本記事では、VATの基本概念から日本の消費税との違い、国・地域別の制度特徴、そして日本企業が取るべき具体的な実務対応までをわかりやすく解説します。複雑に見えるVAT制度も、適切に理解し、整理することで、海外展開の強固な土台を築くことが可能です。ぜひ本記事を通じて、VAT対応の第一歩を踏み出してください。
▼ VAT(付加価値税)とは?海外進出する日本企業が知っておきたい仕組み・国別税率・実務対応のポイント
VATとは?仕組みと日本の消費税との違い
VAT(付加価値税)の基本的な考え方
VAT(Value Added Tax/付加価値税)は、商品やサービスの取引に対して課される間接税であり、各国の政府によって導入・管理されています。VATの最大の特徴は、「付加価値」に対して段階的に課税され、最終的な負担者は消費者であること」です。
たとえば、メーカーが部品を仕入れ、製品を組み立て、小売業者に販売し、それが消費者の手に渡るまでの各取引段階で、それぞれの「付加価値(=利益部分)」に税が課されます。このとき、各企業は仕入れ時に支払ったVATを控除し、差額のみを納税します。これにより、二重課税を回避しつつ、取引の透明性を高める構造が実現されています。
VATはヨーロッパ諸国で広く採用されており、現在では約160か国が同様の制度を導入しています。制度名や税率、控除ルールは国によって異なりますが、基本的な考え方は共通しており、国際取引においても重要な税務対応の要素となっています。
消費税との違い|仕入控除・課税の透明性
日本の消費税もVATと類似した「間接税」ではありますが、両者にはいくつかの重要な違いがあります。特に実務上大きな差となるのが、仕入税額控除の運用と帳簿管理の厳格さです。
日本の消費税制度では、仕入れ時に支払った消費税を「仕入税額控除」として差し引くことができますが、VATの制度では、この控除のために請求書の様式、発行方法、登録番号の記載などが法的に厳格に規定されています。適切なVATインボイスがなければ、仕入れ控除が認められないという厳しい運用が多くの国で採用されているため、事務処理の正確性がより一層求められます。
また、日本では“内税”が一般的で、価格表示に消費税が含まれているのに対し、VAT制度を採用する国では“外税”表示が基本であり、請求書には明確に「本体価格」と「VAT額」が分けて記載されます。価格表示・取引書類のルールが異なる点は、日本企業が海外で販売・請求を行う際の注意点となります。
VATが導入されている主な国と税率の傾向
VATは現在、EU加盟国をはじめとする欧州各国、イギリス、オーストラリア、カナダ、中国、タイ、インドネシアなど、約160か国で導入されている国際標準の間接税制度となっています。日本、アメリカ、香港など一部の国を除き、ほとんどの先進・新興国が何らかの形でVATまたは類似の税制(例:GST=Goods and Services Tax)を持っています。
税率は国によって異なりますが、EU圏では標準税率20〜25%前後が一般的です(例:フランス20%、ドイツ19%、スウェーデン25%など)。一方、発展途上国や新興国では10〜15%台の設定が多く、生活必需品や教育・医療関連サービスなどには軽減税率や非課税措置が設けられているケースもあります。
また、近年では電子商取引の拡大に伴い、デジタルサービスに対してもVATが課されるようになっており、物理的に商品を輸出していなくても税務対応が必要になるケースが増えています。これらの変化を踏まえ、企業側には国ごとの制度を適切に理解し、販売スキームに応じたVAT対応を行う体制構築が求められています。
VATが日本企業に関係するのはどんなとき?
越境ECで商品をEU・UKに販売する場合
日本国内に拠点を置きつつ、EUやイギリスの消費者向けに商品を販売する「越境EC」モデルが拡大しています。こうした取引において、VATの対応が必要となるケースが非常に多く、無登録や誤認識が原因で、販売停止や罰金といったリスクに直結する事例も少なくありません。
たとえば、EUでは2021年7月に制度改正があり、「OSS(One Stop Shop)」というVAT一括申告制度が導入されました。これにより、EU域内向けに年間10,000ユーロを超える越境販売を行う場合、販売者はEU内でVAT登録が必要となり、対象国ごとの税率でVATを課す義務が発生します。
また、イギリスではBrexit後の制度変更により、150ポンド以下の貨物には現地消費者への販売者がVATを徴収・納税する義務があります。日本国内から直送する場合でも「非居住者のVAT登録」が求められるケースがあり、事前準備を怠ると通関拒否や遅延の原因となります。
つまり、日本企業が「国内から発送しているからVATは関係ない」と思っていても、取引相手が個人である以上、VATは販売者側の責任として発生するという点を理解する必要があります。
現地法人や倉庫を設けるとVAT義務が発生するケース
日本企業が海外展開を進める際、現地法人を設立したり、3PL倉庫を活用して商品を現地に保管・発送したりするケースが増えています。このような「現地に物理的拠点や在庫を持つビジネスモデル」では、VAT登録義務がほぼ確実に発生します。
たとえば、EUやイギリスにおいて現地倉庫から商品を配送する場合、たとえ日本本社が在庫の所有者であっても、「現地で商品を販売している」と見なされ、VAT登録と納税義務が課されます。また、現地法人を通じてサービス提供を行う場合にも、その取引が課税対象である限り、VAT対応が必須となります。
このような「販売・物流の現地化」が進めば進むほど、VATの申告・納税は複雑化し、企業側には継続的な税務管理体制と、制度改正に対するアンテナの高さが求められます。現地会計士や税務代理人との連携体制を早期に構築することが、安定した海外展開の前提条件となるのです。
デジタルコンテンツ・電子サービス提供も課税対象に?
物理的なモノの取引に限らず、電子書籍、音楽、動画、ソフトウェア、クラウドサービス、eラーニングなどの「無形のデジタルサービス」もVATの課税対象となるケースがあります。これは「電子サービスへのVAT課税(いわゆるDST=デジタルサービス税)」の世界的な動きに連動した流れです。
たとえば、EUでは非居住者が域内の消費者に対して電子サービスを提供する場合、その国ごとにVATを課し、申告・納税する義務があります。特にB2C取引では、提供者側がVATを徴収しなければならず、取引量が少なくても義務が発生するため、要注意です。
日本企業が自社のプラットフォームを通じて動画講座を配信したり、ソフトウェアをダウンロード販売するような場合も、対象国によってはVAT登録・納税が必要になることがあります。国ごとに課税範囲が異なるため、サービスの内容と販売国を正しく照合し、税務リスクを最小化するための確認体制を整えることが重要です。
国・地域別VATの特徴と注意点
EU加盟国|共通ルールと国別VAT登録の違い
EUはVAT制度を共通の枠組みで運用しており、加盟国すべてがVATを導入しています。そのため制度上の大枠(仕組みや用語)は共通していますが、実務上は国ごとに税率・申告頻度・登録基準・帳簿要件などが異なり、単一のルールで完結できるわけではありません。
たとえば、ドイツでは標準税率が19%、フランスは20%、スウェーデンは25%といったように国ごとにVAT率が異なり、軽減税率の適用範囲も個別に設定されています。また、販売先の国ごとに一定の売上閾値(しきい値)を超えると、その国でVAT登録が求められるというルールも存在していましたが、2021年の制度改正によりEU全体で共通しきい値10,000ユーロが設定され、越境EC事業者には「OSS(One Stop Shop)」による一括申告制度が用意されました。
ただし、OSSを利用せず各国で独自に登録する選択肢もあるため、事業モデルや物流ルートに応じて、どの国で登録すべきかを正確に判断する必要があります。複数国への販売が見込まれる場合は、VAT登録・申告体制の整備が欠かせません。
イギリス(UK)|Brexit後のVAT制度はどう変わったか?
イギリスはEU離脱(Brexit)により、2021年1月以降はEUのVAT共通制度から完全に離脱し、独自のVAT制度が運用されています。そのため、EU向けとUK向けの取引では、税務対応を分けて考える必要があります。
特に注目すべき点は、150ポンド以下の低額商品に対する「販売者課税」への移行です。これにより、イギリス国内の個人消費者に商品を販売する場合、日本の事業者であっても英国税務当局(HMRC)へのVAT登録が必要となり、VATを徴収・申告しなければなりません。日本から直送する越境ECでもVAT登録が必須となるケースがあるため、事前の制度確認は不可欠です。
また、eBayやAmazon UKなどのECプラットフォームを利用する場合は、プラットフォームがVAT徴収代行を行うケースもありますが、それでも登録義務や帳簿保管義務は事業者に残ることが多く、免責されるわけではありません。Brexit以降のUKは制度変更のスピードが速く、継続的なアップデートの確認と、信頼できる現地パートナーとの連携が重要になります。
ASEAN・中国などアジア諸国のVAT・GST制度の違い
アジア圏においても、多くの国でVATまたは類似の間接税制度(GST=Goods and Services Tax)が導入されています。たとえば、中国では「増値税」と呼ばれるVAT制度が運用されており、企業規模や業種によって異なる税率(一般納税人は13%など)が適用されます。
東南アジアでは、タイ(7%)、インドネシア(11%)、マレーシア(8%)、シンガポール(9%)など、比較的安定した税率が維持されていますが、国ごとにVAT登録の基準や電子帳簿の義務、非課税取引の範囲が大きく異なります。また、B2C向けの電子サービス提供に対しても課税対象とする国が増えており、デジタル領域での展開が活発な企業ほど注意が必要です。
さらに、アジアでは「VAT還付制度」の運用が比較的複雑なため、還付を見込んだ価格設計やキャッシュフロー計画が重要になります。現地に輸出・製造拠点を持つ企業はもちろん、ECを通じた直接販売であっても、各国の法令に合わせた適正な対応が必要です。
VAT登録・納税・帳簿管理の実務対応
VAT番号の取得と登録判断のプロセス
VATへの対応を始めるうえで最初に直面するのが、対象国におけるVAT番号の取得です。これは、VAT課税取引を行う事業者として正式に登録されることで得られる番号であり、販売・仕入・納税などあらゆるVAT取引に必要となる企業の識別情報です。国によって申請様式や必要書類は異なるものの、基本的には法人登記情報、取引内容、納税計画などを当局に提出し、審査を経て付与されます。
登録義務が発生するかどうかは、販売先の国籍、販売形態、倉庫の所在などによって決まります。たとえば、EU加盟国において、消費者向けの越境販売が年間一定金額を超えた場合や、現地に在庫を保管している場合には、登録が必須となるケースがほとんどです。こうした判断は制度改正によって変動するため、販売戦略を立てる段階で制度との整合性を確認することが重要です。
VAT登録を怠れば、税務上のトラブルだけでなく、通関や販売許可の問題に発展する可能性があります。したがって、各国の登録要件を正しく把握し、自社の事業形態に適したタイミングで登録申請を行うことが、円滑な海外展開の第一歩となります。
請求書・帳票管理に求められる水準
VAT制度の運用において欠かせないのが、適切な請求書の発行と帳簿の整備です。多くの国では、課税取引ごとにVATインボイスと呼ばれる請求書の発行が義務付けられており、その内容には細かな要件があります。具体的には、取引当事者の名称と住所、VAT番号、取引日、商品やサービスの詳細、価格と税額の区分などが明記されていなければなりません。
これらの要件を満たしていない請求書は、税務当局によって無効と判断され、仕入税額控除が認められないといった不利益につながります。また、電子請求書の活用が義務化または推奨されている国も増えており、特にイタリアやフランス、ポーランドなどでは、リアルタイムで税務当局に請求書データを送信するシステムが導入されています。
企業としては、こうした国ごとの要件に対応できるよう、帳票のテンプレートや発行システムの仕様を整える必要があります。海外販売の拡大とともに請求業務が複雑化するなか、VAT対応に適した会計ソフトやERPとの連携も視野に入れながら、正確かつ効率的な帳票管理体制を整備することが求められます。
外部支援を活用した安定的なVAT運用
VATの登録や申告、帳票管理においては、制度や言語、時差などの壁が大きな負担になることがあります。そのため、多くの企業が現地の税務代理人やコンサルタントと提携し、実務対応を外部支援のもとで行っています。これはコンプライアンスを確保するうえでも、非常に有効な手段です。
信頼できる税務代理人は、現地制度に関する最新情報を提供してくれるだけでなく、登録手続きの代行、申告書の作成、税務調査への対応など、実務全般をサポートしてくれます。また、複数国でVAT登録が必要な場合には、国ごとに窓口を持つグローバル型の支援会社を活用することで、情報管理や対応フローの一元化が図れます。
ただし、支援を受ける場合でも、社内で最低限の制度理解と管理責任を持つ体制が必要です。外部に依存するだけでは、制度変更への即時対応が難しくなるほか、組織としての透明性や内部統制が損なわれる可能性もあります。したがって、専門家の知見を活用しつつも、最終的には社内で制度に対応できる持続的な体制を築くことが、グローバル税務対応の理想的な形と言えるでしょう。
日本企業がVATに対応するための戦略的アプローチ
販売国別にVAT義務を正しく整理することが第一歩
日本企業がVAT対応を進める上で最初に行うべきことは、自社の販売対象国と取引形態に照らして、どの国でどのような税務義務が発生するのかを明確にすることです。VATは国ごとに制度設計や登録義務の基準が異なるため、ひとつのテンプレートで全対応を済ませようとすると、かえってリスクが高くなります。たとえば、EUとイギリスでは制度の根幹こそ似ていても、申告の様式や免税範囲、電子帳票に関する要件は大きく異なります。また、物販とデジタルコンテンツでは課税対象や計算方式が異なるため、販売チャネルや物流形態も加味して制度を整理しなければなりません。
この作業を正確に行うことで、VATの申告漏れや過剰な登録・過少納付といったトラブルを未然に防ぐことができます。重要なのは、税務の問題を事後的に処理するのではなく、戦略的に把握し、前向きに制度対応を設計するという視点を持つことです。
現地ECモールや物流モデルに応じた税務設計を
VAT対応は、単に税率や帳簿管理の問題ではなく、ECや物流戦略とも密接に関連します。たとえば、AmazonやeBayなどの欧州モールを活用する場合、プラットフォーム側がVATの徴収を代行する制度が整備されている国もありますが、それによって販売者の税務義務が免除されるわけではありません。むしろ、販売実績や支払明細の確認、VATインボイスの発行義務など、販売者が担うべき責任は残り続けます。
また、Fulfillment by Amazon(FBA)などの現地倉庫を活用する物流モデルでは、現地に在庫がある時点でその国でのVAT登録義務が生じます。どこから誰に届けるか、誰が在庫を保有しているか、そしてどのプラットフォームを通じて販売しているかによって、課税国や納税者の特定が変わってくるのです。
そのため、ECや物流の戦略を練る際には、同時に税務上の影響を精査し、制度と整合の取れたオペレーション設計を行う必要があります。販売拡大と税務対応は両立すべき課題であり、事業の成長を支える基盤として計画的に考えることが求められます。
長期的にはタックスリスク管理と内部体制整備がカギ
VATへの対応を一過性の課題として捉えるのではなく、長期的な税務リスク管理の一環として組織的に取り組むことが重要です。制度改正や税務当局の調査リスクに継続的に備えるには、社内の経理・法務・事業部門の連携が欠かせません。たとえば、販売対象国の変更や価格戦略の見直しを行う際にも、税務的な影響を含めた意思決定が求められます。
また、税務処理を担当する社員の知識レベルや、使用している会計システムの対応状況も、リスクの大きさに直結します。社内に十分な知見がない場合は、税務顧問や現地代理人と継続的な関係を築き、制度変更への対応力を高めていく必要があります。特に電子インボイスの義務化やリアルタイム申告のような制度進化に対しては、事前の準備がなければ追いつくことができません。
企業がグローバル展開を進めるうえで、VATは単なるコストや規制ではなく、コンプライアンスと信頼の基盤でもあります。これを適切にマネジメントできるかどうかが、持続的な海外事業の成否を分ける鍵になるのです。
まとめ:VAT対応は「販売力」と「信頼」の土台となる
VATは、単に税務的な義務として処理すべきものではなく、グローバルビジネスを展開する企業にとって、販売力と取引信頼を支える基盤となる制度です。適切な登録、納税、帳簿管理を実現できていない企業は、現地での販売機会を失うだけでなく、パートナーや顧客からの信用も損ねる可能性があります。逆に言えば、制度への対応を戦略的に行うことで、競合他社との差別化要素にもなり得ます。
越境ECやデジタルサービス、現地法人による展開など、ビジネスモデルが多様化するなかで、VATへの対応はますます複雑になっています。しかし、制度を正しく理解し、社内外で対応体制を整えれば、リスクを抑えつつスムーズに国際展開を進めることが可能です。税制は企業の足かせではなく、整備された制度の中で事業をスケールさせるための“ルール”であり、信頼の証でもあります。
日本企業がグローバル市場で選ばれる存在となるためには、こうしたルールを味方につけ、確かな税務基盤の上に事業を築く姿勢が求められます。VAT対応はその第一歩であり、単なる法令順守を超えた経営資源のひとつとして位置づけることが、これからの海外展開における大きな差となるはずです。
なお、「Digima~出島~」には、優良な各国ビジネスの専門家が多数登録されています。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
本記事が、海外進出を検討される日本企業の皆様にとって、実務の一助となれば幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談