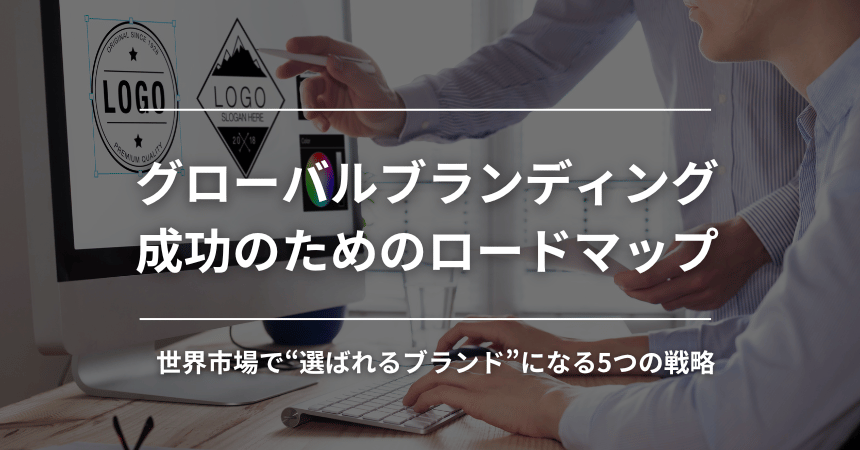AI時代こそ現地で動け|海外ビジネスにおけるフィールドリサーチの重要性と実践ノウハウ

AIの進化により、かつて人の手で行われていた情報収集や分析が、飛躍的なスピードと精度で自動化される時代が到来しています。グローバル市場に関する情報も、オンライン上のデータや生成AIによるリサーチによって、ある程度の傾向やインサイトを把握することが可能になりました。しかし、こうした便利さが進む一方で、あらためて見直されているのが「フィールドリサーチ」、すなわち現地に足を運んで行う調査の重要性です。
実際の空気感、人の表情、文化的背景、生活者のリアルな声——これらは、どれだけAIが高度化しても、オンラインでは捉えきれない情報です。とくに海外ビジネスにおいては、現地特有のニーズや感覚を正しく把握することが、戦略の成否を左右します。データだけでは見えてこない「肌感覚」こそが、意思決定に深みと精度をもたらすのです。
本記事では、フィールドリサーチとはそもそも何かという基本から、AI時代におけるその再評価の背景、そして海外ビジネスでの活用方法と実践ノウハウまでを詳しく解説します。AIが発達した今だからこそ、現地で得られる一次情報の価値を見つめ直すことが、これからの海外展開成功の鍵となるでしょう。
▼ AI時代こそ現地で動け|海外ビジネスにおけるフィールドリサーチの重要性と実践ノウハウ
そもそもフィールドリサーチとは何か
定義と特徴:他のリサーチとの違い
フィールドリサーチとは、実際に調査対象となる現場に赴き、観察やインタビューなどを通じて得られる「一次情報」を収集する調査手法を指します。これは、インターネットやデータベースなどを用いたデスクリサーチ(机上調査)とは大きく異なり、現地に存在する“生の声”や“肌感覚”を重視する点が特徴です。
例えば、消費者へのアンケートを通じて数字上の傾向を把握するのではなく、店舗での購買行動を観察したり、生活者に直接ヒアリングを行ったりすることで、言葉や数字では捉えきれない背景や感情を読み取ることが可能になります。こうした接触型の調査は、文化や価値観が異なる海外市場では特に価値を発揮します。
さらに、フィールドリサーチは「仮説を検証するための調査」というより、「仮説を発見するための調査」として位置づけられることも多く、予測不能なインサイトを得ることに長けています。そのため、新規市場への参入時や、ユーザー理解を深めたい局面で重要な役割を果たします。
フィールドリサーチが活用される典型的な場面
海外ビジネスにおいてフィールドリサーチが効果を発揮する場面は多岐にわたります。たとえば、新たな国や地域に進出を検討する際、その市場の文化的背景や消費者の行動パターンを理解するために現地での観察やインタビューが行われます。どのような商品が好まれているのか、競合はどのようなサービスを提供しているのかといった情報は、実際の街や店舗を歩いてみてこそ見えてくるものです。
また、プロダクトテストやプロトタイプの受容性を評価する目的でも、フィールドでの調査は有効です。現地の生活者に実際に使ってもらい、使い勝手や反応を確認することで、文化的なギャップや改良点を早期に把握することができます。
このように、フィールドリサーチは意思決定の“直前”ではなく、“前提”として実施されるべき活動です。戦略や製品に手を加える前段階での生きた情報収集として、現地の声に耳を傾けることが求められるのです。
リサーチに“足で稼ぐ”価値がある理由
フィールドリサーチの本質的な価値は、「現地でしか得られない情報」にあります。数字では表現しきれない人々の表情、ちょっとした会話、街の雰囲気、商品棚の並びや広告の視覚的訴求など、すべてがビジネスインサイトの源になります。特に文化や価値観が異なる海外市場においては、日本国内の常識や感覚が通用しないことも少なくありません。
例えば、アンケートの結果では好意的に見える商品でも、実際に店頭での動きを観察すると、手に取られては棚に戻されるという行動が繰り返されているかもしれません。その背景には、価格設定、パッケージデザイン、陳列場所、店員の説明など、複合的な要素が絡んでいます。このような「現場の違和感」に気づけるのは、実際に現地で五感を働かせた者だけです。
「足で稼ぐ」リサーチは、数字や文章では把握できない生の情報を拾い上げるための手段です。そしてその情報は、単なる事実ではなく、戦略や施策の“納得感”と“説得力”を高める根拠となるのです。
AIでは代替できない“現地感覚”の価値
データでは掴めない行動と感情
AIによって膨大なデータを瞬時に処理し、消費者の行動傾向や市場動向を可視化することが可能となった現代。しかし、こうした定量的データだけでは捉えきれない「違和感」や「揺らぎ」こそが、実際の現場には存在します。人々が言葉にはしないが確かに抱えている不安や違和感、そして現地の空気や生活リズムに根ざした感情的な反応は、AIが学習するデータの外側にあるものです。
たとえば、ある製品に対して「満足している」と回答した消費者が、実際の使用時には迷いながら操作していたり、購入直後に使用をやめてしまったりすることがあります。こうした行動は、数値には現れづらく、むしろ観察や対話といった人間的な関与によって初めて浮かび上がってきます。
つまり、フィールドリサーチは「数字の裏にある物語」を読み解くための手段です。どれだけAIが進化しても、文化や感情のニュアンスまで完全に読み解くことは困難であり、そこに人の目と足が果たす役割があるのです。
AIでの事前分析×フィールドリサーチの組み合わせが最強
AIが得意とするのは、過去データに基づいたパターンの抽出や予測、仮説立案といった分析業務です。一方で、フィールドリサーチはその仮説を現場で検証し、補正する役割を担います。この2つをうまく組み合わせることで、より実効性の高い戦略が生まれます。
たとえば、AIによる分析で「中東地域では高機能な美容家電への関心が高まっている」という傾向が出てきたとします。しかし、実際に現地で話を聞いてみると、「高機能」とは具体的にどういう意味なのか、「信頼できるブランドとは何か」など、文化や生活背景によって解釈が大きく異なることが明らかになります。
このように、AIが描いた地図を持って現地を歩くことで、仮説のズレを調整し、より深く現地のリアルに迫ることが可能となります。AIは「広さ」をカバーし、フィールドリサーチは「深さ」を補う——その両輪が、グローバル市場での意思決定を支えるのです。
「ユーザー目線」ではなく「現地生活者目線」が重要に
グローバルマーケティングにおいては、「ユーザー目線」の重要性が繰り返し語られますが、こと海外市場に関しては、それ以上に「現地生活者目線」を持つことが求められます。これは、単に製品やサービスの使い勝手を評価するのではなく、生活者としての背景や価値観、日々の選択の文脈まで理解するという姿勢です。
たとえば、ある食品が「健康に良い」という理由で日本では支持されているとしても、その価値観がそのまま別の国に通用するとは限りません。健康に対する考え方、味覚、食文化、宗教的背景などが複雑に絡み合っており、そこに合わせた提案をするには、現地での観察と対話が欠かせません。
フィールドリサーチでは、単なるユーザーアンケートでは得られない深層のインサイト、すなわち「なぜその選択をしたのか」という理由の核心に迫ることが可能です。それはまさに、現地生活者としての視点に身を置き、その立場から市場を見るという姿勢から生まれる情報であり、グローバル戦略にとって決定的な差となり得ます。
海外ビジネスでフィールドリサーチを導入すべき理由
「売れるかどうか」の判断には現場が欠かせない
海外市場に商品やサービスを投入する際、最も重要な判断基準のひとつが「現地で本当に売れるのかどうか」です。カタログ上のスペックや価格、過去の成功体験だけでは、この問いに答えることはできません。なぜなら「売れる」には、その土地の文化や消費者の価値観、購買導線、競合環境といった多様な要素が絡み合っているからです。
例えば、日本では当たり前のパッケージデザインが、現地では全く受け入れられないケースがあります。あるいは、日本製品の品質や機能は高く評価されても、購入場所や支払い方法が合わないために実際には売れないということもあります。こうした現実は、現地で実際に売ってみたり、見せてみたりすることでしか見えてきません。
フィールドリサーチによって、市場の受容性を事前に見極めることで、大きな戦略的ミスを避けることができます。実験的に商品を流通させたり、モニター調査を行ったりすることは、短期的なコスト以上に、長期的な成果に直結するリスク管理の一環なのです。
顧客インサイトと競合との差別化の鍵
海外市場での成功には、単に“良いもの”を届けるだけでなく、“その市場ならではの視点で再定義された価値”を提供することが求められます。そのためには、現地の顧客が何を大切にしているのか、どのような場面で商品・サービスを利用し、どのように評価しているのかを理解する必要があります。こうした「顧客インサイト」は、表面的なアンケートや数値データでは捉えきれない領域です。
フィールドリサーチでは、実際に消費者と会話し、生活の様子を観察し、そこから本質的な価値観や期待、さらには潜在的な不満や未充足ニーズを探ることができます。これらの気づきは、競合にはない独自の打ち出し方、つまり「差別化」の源泉となります。
現地で収集した生の声や行動観察は、商品開発だけでなく、プロモーションのメッセージ、チャネル選定、価格戦略に至るまで、あらゆる意思決定の精度を高めます。顧客理解の深さが、競合と一線を画すブランド体験を創り出す鍵となるのです。
信頼関係とネットワーク構築の起点にもなる
フィールドリサーチのもう一つの大きな意義は、「調査」でありながら同時に「関係構築」の場でもあることです。現地の企業や生活者と直接顔を合わせ、対話を重ねる中で、単なる情報提供者ではなく、信頼できるビジネスパートナーとしての認識が築かれていきます。
とくに海外ビジネスにおいては、「誰と組むか」「誰に紹介されるか」が成功の可否を大きく左右します。その点、現地に足を運び、自らの言葉で熱意やビジョンを語ることは、単なる調査活動を超えた意味を持ちます。現場でのやり取りを通じて得た縁が、のちのアライアンスや販路開拓のきっかけになることも少なくありません。
また、現地でのフィールドリサーチを通じて関係者との信頼を深めることは、情報の質と深さにも直結します。最初は断片的だった情報が、繰り返しの接点や誠意ある姿勢によって、より本質的かつ戦略的に活用できる知見へと昇華していくのです。
効果的なフィールドリサーチを行うための実践ノウハウ
調査設計のポイントと準備段階での注意点
フィールドリサーチを成功に導くためには、現地入りする前の「調査設計」が極めて重要です。目的があいまいなまま現地に赴いても、有意義な情報を得ることはできません。まずは調査の目的を明確にし、「何を知りたいのか」「なぜそれを知る必要があるのか」を言語化することから始めましょう。
次に、仮説を立て、それを検証するための観察項目や質問内容を設定します。たとえば、「Aという商品が現地で支持されている背景には、Bという文化的価値観があるのではないか」といった仮説があれば、それを確かめる行動観察やインタビューの準備が必要です。
また、調査対象となるエリアや時間帯、対象者の属性も綿密に検討する必要があります。マーケットが広大で多様な場合は、どのエリアにフォーカスするかを事前に絞り込むことも有効です。さらに、現地の言語や文化に配慮したコミュニケーション計画を立てておくことで、円滑なヒアリングや信頼関係の構築につながります。
ツールと人材:誰が行うか・どう記録するか
フィールドリサーチの質は、「誰が行うか」と「どのように記録し、分析するか」によって大きく左右されます。調査を担当する人材には、観察力だけでなく、相手の話を引き出す力、場の空気を読む力が求められます。できれば現地の文化や言語に精通したパートナーやローカルスタッフと協働することが望ましいでしょう。
言語の壁がある場合は、単なる通訳ではなく「現地の価値観に精通した翻訳者」の存在が重要です。文化的なニュアンスを含んだやり取りを正確に伝えることは、インサイトの深度に直結します。
また、得られた情報の記録にも工夫が必要です。音声録音や映像記録、フィールドノート、写真など、複数の手段を併用することで、後から分析する際の精度が高まります。加えて、調査後の初期メモや感想も貴重な一次資料となるため、その場での記録を徹底する体制づくりが求められます。
成果を事業にどう活かすか
フィールドリサーチの成果は、調査そのものに価値があるのではなく、「いかに事業に反映できるか」が本質です。得られた情報をどう分析し、どのようなアクションにつなげるかが、フィールドリサーチの真価を決定づけます。
まず、調査内容はチーム内で共有され、意思決定者を含む関係者がその背景と意味を正しく理解することが大切です。そのためには、単なる報告書ではなく、ビジュアルやエピソードを交えたストーリーテリング形式での発信も有効です。現地で見た「驚き」や「発見」をそのまま伝えることで、組織全体の視座を引き上げることができます。
次に、得られたインサイトをもとに仮説を再構築し、新たな戦略や商品設計へとつなげていきます。フィールドリサーチは一度きりのイベントではなく、意思決定のたびに継続的に活用すべきプロセスです。また、現場で得た知見を社内に蓄積し、ナレッジとして共有することが、組織の「現地感覚」を底上げする鍵となります。
まとめ
AIがもたらす情報収集や分析の効率化は、ビジネスに大きな恩恵を与えています。しかし、どれだけデータの網羅性や分析精度が向上しても、現地の空気を吸い、生活者と対話し、五感で体験することで得られる情報には、替えがききません。とくに海外ビジネスのように、文化や価値観が異なるフィールドでは、机上のデータでは掴みきれない“肌感覚”こそが、戦略の質を左右します。
フィールドリサーチは、商品やサービスが「本当に受け入れられるかどうか」を見極めるだけでなく、顧客インサイトの発見や差別化のヒント、さらには現地との信頼関係づくりにもつながる多面的な取り組みです。AIを最大限に活用しつつも、それに依存しすぎず、人が現地で見て、感じて、考えることによって、初めて「実感ある戦略」が生まれます。
これからの時代に求められるのは、“AIを使いこなす力”と“現地で動く力”の両方を持ち合わせた柔軟な姿勢です。変化の激しいグローバル市場において、成功をつかむためには、データと感性を融合させたアプローチこそが最も有効な武器となるでしょう。フィールドリサーチを、単なる調査手法ではなく、海外ビジネスの必須スキルとして捉え直すことが、次の飛躍につながる第一歩です。
なお、「Digima~出島~」には、海外フィールドリサーチの専門家が多数登録されています。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
本記事が、海外展開を検討される日本企業の皆様にとって、実務の一助となれば幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談