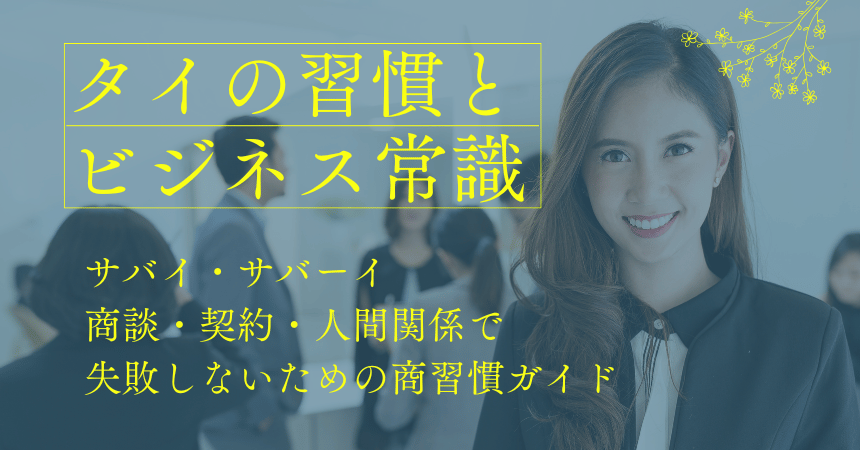タイ製造業レポート~相互関税時代の戦略拠点として再注目される理由と日系企業の進出動向~

東南アジア諸国の中でも、タイは長年にわたり日系製造業の重要な拠点として発展してきました。とりわけ自動車、電機、食品加工分野では高度な産業集積が進んでおり、多くの日本企業が現地法人や合弁会社を通じてグローバルなサプライチェーンの一角を担っています。加えて、インフラや税制優遇制度(BOI制度)、現地調達率の高さなど、他のASEAN諸国と比較してもバランスの取れた事業環境が整備されています。
一方、2025年にトランプ政権が再び導入した「相互関税」政策は、日本企業の国際展開戦略に新たな転機をもたらしています。この新政策により、中国やベトナムからの対米輸出には高い関税が課され、従来の「チャイナ・プラスワン」戦略の再評価が進む中で、タイの持つ安定的かつ中立的な立場が改めて注目を集めているのです。
本記事では、タイの製造業の現状を整理しながら、相互関税下における地政学的・経済的優位性、実際に進出している日系企業の事例、さらには今後の戦略的活用方法について、多角的に解説していきます。ASEANにおける次の一手を見極めたい企業の皆様にとって、具体的な検討材料となることを目指します。
▼ タイ製造業レポート~相互関税時代の戦略拠点として再注目される理由と日系企業の進出動向~
タイ製造業の全体像と主要分野
製造業が占める経済比率と産業構造
タイはASEAN諸国の中でも「工業化」が進んだ国として位置づけられており、製造業は同国のGDPにおいて約3割を占める中核的な産業です。農業大国という印象を持たれることもありますが、実際にはタイ経済の成長を支えてきたのは、輸出主導型の製造業です。特に輸出額の過半数を工業製品が占めており、2020年代以降は自動車、電子部品、食品加工、化学製品といった分野が好調を維持しています。
製造業の拠点はバンコク近郊を中心とした中部地域や、東部経済回廊(EEC)と呼ばれる地域に集積しており、工業団地や輸出専用港などのインフラが計画的に整備されています。また、外資企業の受け入れにも積極的で、日系企業だけでなく欧米・中国の製造業も数多く進出しており、地域としての国際競争力が高いのが特徴です。
自動車、電子機器、食品加工などの主要産業
タイ製造業の中心を成すのは、まず自動車産業です。トヨタ、ホンダ、いすゞなどの日系メーカーが組立工場を構えており、タイは「東南アジアのデトロイト」とも呼ばれる自動車輸出拠点として機能しています。年間200万台を超える自動車生産のうち、半分以上が輸出に回されており、日系企業の部品サプライヤーも多数存在しています。
続いて、電子機器・電気部品の分野も重要です。NECやオムロン、富士電機などが生産拠点を構えており、近年は半導体や精密機器の組立、電池関連の部品製造などへも進出が広がっています。コロナ禍以降、在宅需要によるIT・家電製品の増加とともに、タイ拠点の存在感はむしろ増しています。
また、食品加工分野もタイの強みの一つです。味の素やニチレイ、キユーピーなどが現地生産を通じてASEAN域内への輸出を行っており、タイ産原材料と日本の製造技術を組み合わせた「現地化モデル」が浸透しています。食品・飲料分野ではイスラム市場を意識したハラール対応商品も展開されており、ムスリム人口の多いASEAN各国へのゲートウェイとしての役割も期待されています。
相互関税政策の影響とチャイナ・プラスワンの再加速
2025年トランプ政権の相互関税政策と製造業への影響
2025年4月に発表されたトランプ政権による「相互関税政策」は、グローバルな製造業戦略に大きな波紋を広げています。この政策では、すべての国からの輸入品に最低10%の関税を課すとともに、国ごとに「不公平な貿易障壁」の水準に応じて追加関税が適用されるという仕組みです。日本製品には合計24%の関税が課され、中国製品は実質54%、ベトナム製品には45%、そしてタイ製品には36%の関税が適用される見通しとなっています。
こうした関税の急激な引き上げは、従来の「安価で競争力のある製品をアジアから輸出する」というモデルに大きな修正を迫るものであり、とりわけ米国市場への依存度が高い日本企業には深刻な影響をもたらす可能性があります。完成車や電子機器、建設機械などを米国に供給している企業は、今後、価格競争力の維持やコスト構造の見直しを余儀なくされるでしょう。
中国・ベトナム製造拠点と比べてのタイ製造拠点の相対的優位性
また、このトランプ政権による相互関税政策は、製造拠点の再編を迫る大きな契機となっています。とくに中国やベトナムはこれまで「チャイナ・プラスワン」戦略の中核として注目されてきましたが、中国は関税総額54%、ベトナムは45%と非常に高い関税が設定されたことで、米国向けの輸出拠点としての競争力に陰りが見え始めています。これに対し、タイは36%の関税水準にとどまり、日系企業との取引実績や現地サプライチェーンの成熟度、インフラ整備度などを総合的に勘案すれば、再評価に値するポジションにあるといえます。
とはいえ、タイが常に最適解とは限りません。たとえば米国との地理的・政治的関係を考えれば、近年注目されているメキシコ(USMCA域内)やインド(人口とコスト面の優位性)といった選択肢も現実味を帯びています。特にメキシコは米国市場への即時アクセスが可能で、関税回避の観点ではタイを凌ぐ利点があります。またインドは将来の内需拡大と製造能力向上が期待されており、中長期的な成長見通しではアジアの中でも存在感を増しています。
そのような中で、タイは“安定性と信頼性を重視する製造拠点”として再評価すべき国です。東南アジアの中では依然として制度整備やビジネス環境のバランスが取れており、とくにすでに日系企業が一定のネットワークを構築している分野では、移行・拡張がスムーズに進めやすいという実利的な魅力があります。多極化する製造戦略の中で、タイは“現実的な選択肢”として引き続き検討に値する国であることは間違いありません。
日系製造業にとってのタイ進出メリット
BOI制度による税制優遇と外資サポート体制
タイ政府は、外国企業の誘致を国家戦略の一環と位置づけ、Board of Investment(BOI:タイ投資委員会)を通じて多様な優遇制度を整備しています。BOI認可を取得することで、法人税の一定期間免除、輸入関税の免除、外国人の就労ビザや労働許可の簡素化など、進出初期のコストと手間を大きく軽減することが可能です。特に、電気電子、医療機器、自動車(とくにEV関連)など、戦略産業分野への投資に対しては積極的な支援が講じられており、成長産業を重視する企業にとっては大きな魅力といえます。
また、BOIは単なる優遇制度の提供だけでなく、ワンストップサービスセンターを通じた法的支援、許認可手続きの代行・助言、現地パートナーの紹介など、進出に伴う実務面の支援にも注力しています。日系企業にとって、現地制度の不透明さを払拭できるこれらの支援体制は、初期リスクを抑えつつ事業をスタートさせる上で非常に有効です。
インフラの整備と現地調達率の高さ
タイは東南アジアの中でも特にインフラ整備が進んでいる国の一つです。とくに首都バンコクから東部のチョンブリ、ラヨーン、チャチューンサオにかけての「東部経済回廊(EEC)」は、製造・物流の中核地帯として急速に発展しており、港湾、空港、高速道路、工業団地が戦略的に配置されています。日本企業の多くもこのEEC地域に進出しており、ジャストインタイムの生産や輸出入業務を効率的に行う基盤が整っています。
加えて、現地の部品メーカーや原材料供給業者が豊富に存在しており、製造業にとっては高い現地調達率を実現しやすい環境です。これはコスト競争力の維持や為替リスクの抑制に大きく寄与します。日本からの一部部材を補完的に輸入しながら、現地で完結するサプライチェーンを構築することで、柔軟かつ堅実な生産体制を整えることができます。製品の最終組立から出荷までをタイ国内で完結できる仕組みは、日系企業にとって大きな運営メリットとなっています。
タイ人材の質と日本企業との親和性の高さ
タイの人材は勤勉で手先が器用、加えて日本企業の社風や生産管理手法に対しても高い適応力を示す傾向にあります。とくに製造業においては、長年にわたる日系企業との関係性の中で、カイゼン活動や5Sといった日本流の現場改善文化が根付きつつあります。現地大学や専門学校との連携によって技術者の育成も進んでおり、中間管理職層を含めた人材の質は、ASEAN諸国の中でも比較的安定しています。
また、日本語人材の確保や通訳手配も容易で、商習慣や職場文化への理解度が高い点も安心材料です。タイ国内には日系人材紹介会社や通訳派遣会社も多く、初期の立ち上げ段階から日本側との橋渡し役を担える人材の確保がしやすくなっています。これらの点から、タイは「文化的な相性」と「長期的な雇用関係の構築」がしやすい国といえるでしょう。
リスクと課題|進出判断のうえで留意すべき点
政治的安定性の脆弱さと法制度の変動リスク
タイは他のASEAN諸国と比べても産業インフラや経済制度が整備されている一方で、政治的な安定性においては一定のリスクを抱えています。過去20年間にわたり、軍政と民政の交代が繰り返され、選挙結果や政権交代に伴って投資政策や労働法、税制などの見直しが突如行われるケースも見られました。現在は比較的安定していますが、政局の変動がビジネス環境に直接影響を及ぼす可能性は否定できません。
また、法制度に関しても、外国企業向けの規制緩和や優遇制度がある一方で、解釈の曖昧さや行政判断のばらつきが課題とされています。たとえばBOI認可における条件の変更、輸出入関連の許認可の取得難易度など、事前の制度理解と、進出後の法的フォロー体制をしっかりと整えておくことが求められます。現地法律事務所や日系コンサルタントとの連携によるリスク対策は、長期的な安定運営に不可欠といえるでしょう。
労務コスト上昇と中間層の労働力確保競争
タイは、東南アジアの中でもすでに一定水準の経済発展を遂げており、特に都市部では労務コストの上昇が顕著になっています。最低賃金は年々引き上げられており、バンコク周辺では月額400ドル前後と、ベトナムやカンボジアと比較すると明確なコスト差があります。さらに、インフレや為替変動の影響も加わることで、人件費は今後も緩やかに上昇していくと予測されています。
加えて、熟練工や中間管理職層の人材確保も競争が激化しています。優良な人材は既に多くの外資系企業が囲い込んでおり、給与や福利厚生の条件を含めた魅力的な労働環境を整えなければ、採用・定着が難しい現実があります。このため、単なるコスト面での優位性に期待するのではなく、人材投資や教育体制、社内キャリア形成を重視した中長期的な雇用戦略が必要になります。
ローカルパートナー・人材との関係構築の難しさ
タイは親日的な国であるとはいえ、ビジネス文化や意思決定スタイルは日本とは異なる点も多く、現地パートナー企業や従業員との関係構築には丁寧な対応が求められます。とくに「和を重んじる」タイの国民性においては、強いトップダウンよりも、信頼関係と尊重を重んじたコミュニケーションが重視される傾向があります。
また、ローカル企業との取引においては契約書よりも人間関係を重視する文化が色濃く残っており、誤解や期待値の不一致が長期的なトラブルにつながるケースもあります。そのため、事前の文化理解や、信頼できる現地マネージャーや通訳者の配置が、進出後の安定した運営を支える鍵となります。タイとの協働は「人を大切にする姿勢」が何よりも重要であり、日系企業が得意とする「現場力」を発揮するうえでも、現地との融合が不可欠といえるでしょう。
他のASEAN製造国との比較で見るタイの立ち位置
ベトナムとの比較:人件費とインフラ成熟度のバランス
ここ数年、ベトナムは「チャイナ・プラスワン」戦略の代表的な移転先として注目を集めてきました。特に人件費の安さと若年労働力の豊富さに魅力を感じ、製造業の進出が相次いでいます。ただし、物流インフラや部材の現地調達体制などにおいては、まだ発展途上の側面もあり、製造業の高度化や多国籍展開を志向する企業にとっては、リスクも見過ごせません。
その点、タイは人件費こそベトナムより高めですが、港湾・道路・電力網といったインフラの整備度合いや、長年にわたり培ってきた現地調達網、行政機関との手続きの安定性において、ベトナムを上回る点が多くあります。ベトナムが「成長途上の新興国」であるのに対し、タイは「成熟した中進国」としての安定感を備えており、初期投資の回収性を重視する企業にとっては信頼性の高い選択肢といえるでしょう。
インドネシア・マレーシアとの比較:制度・言語・雇用市場の違い
インドネシアやマレーシアも、製造業の進出先として近年注目されています。インドネシアは人口規模が大きく、内需市場の魅力はタイを凌ぐものがありますが、外資規制や許認可における不透明性、都市間インフラの未整備といった課題を抱えており、特に製造業における「効率性」を重視する企業にとっては慎重な検討が必要です。
一方、マレーシアは英語が公用語であるためビジネス上のコミュニケーションが取りやすく、金融制度や知的財産権保護の面でも整備が進んでいます。ただし、民族構成に基づく優遇政策(ブミプトラ政策)など、企業運営に一定の制約が加わることもあり、外資系企業にとっては柔軟性に欠ける場面もあります。
それに比して、タイは公用語こそタイ語ですが、日本語教育の普及や通訳人材の確保がしやすいこと、また外資に対して特定民族優遇などの政策がなく、運営面での平等性・安定性が高い点で優位性があります。加えて、日系企業が多く進出していることで、商習慣に慣れたサプライヤーや人材が多いことも実務上のアドバンテージといえるでしょう。
物流と地域展開での中心的役割
ASEAN全体を俯瞰したとき、タイの地理的優位性は際立っています。インドシナ半島の中心に位置することで、ミャンマー、ラオス、カンボジア、ベトナムと陸続きにあり、将来的なメコン地域経済圏のハブとしての役割が期待されています。特に、南部の深海港レムチャバン港や、東部経済回廊(EEC)を軸にした物流インフラ整備は、域内輸送と越境物流の両方をカバーできる仕組みを形成しています。
また、タイからシンガポール、マレーシアへの陸路輸送、あるいはバングラデシュやインド東岸へ向けた海上輸送にも適しており、ASEAN+インド市場を見据えた製造・物流拠点としてのポテンシャルを有しています。これは、単一国で完結しない多国間展開を志向する企業にとって、極めて大きな戦略的価値をもつものです。単に「タイ国内で製造する」だけでなく、「タイを起点にASEAN全体へ展開する」という視点が、今後の製造拠点戦略では重要になるでしょう。
タイ製造業の未来と日本企業の展望
「タイランド4.0」による産業高度化と戦略分野の育成
タイ政府は、従来の労働集約型産業から脱却し、付加価値の高い産業構造への転換を目指す国家戦略「タイランド4.0」を推進しています。この政策は、スマート製造、ロボティクス、バイオテクノロジー、次世代自動車(EV・電動二輪など)、デジタル経済などを重点分野に据え、製造業の高度化と革新を強く後押しするものです。
とりわけ自動車分野では、EV関連の部品製造や電池関連技術の誘致が進んでおり、トヨタやホンダをはじめとする日系メーカーも、EV生産・輸出のアジア拠点としての活用を模索し始めています。また、医療・バイオ分野では、高齢化やヘルスケアニーズの高まりに対応する技術導入が求められており、日本の医療機器・精密機器メーカーにとっても、付加価値型製造拠点としての可能性が広がりつつあります。
既存日系企業の取り組み事例に見る展開の方向性
すでに多くの日本企業が、タイ製造拠点の高度化と多機能化を進めています。たとえば、トヨタはタイを東南アジアにおけるEV戦略の中心と位置づけ、政府と連携しながらEVモデルの現地生産体制を構築中です。日系部品メーカーもこれに呼応し、現地での電動化対応部品の生産拡大を進めています。
また、食品業界では、味の素がタイ国内に高度な生産拠点を構えつつ、そこからASEAN各国へ製品を展開する「地域統合型モデル」を採用しています。同社は物流・品質管理・商品開発の機能を現地に統合することで、単なる生産拠点から“ハブ機能”を備えた地域戦略拠点へと進化させているのが特徴です。
こうした動きから見えてくるのは、タイにおける日系製造業の立ち位置が「コスト競争力」だけでなく、「技術展開」や「市場アクセス」「拠点集約」へとシフトしているということです。タイは、単なる“安価な製造国”ではなく、“戦略的に再定義されつつある拠点”へと変貌を遂げつつあります。
中長期で見た戦略的拠点としての可能性
グローバルな貿易環境が揺らぎ、サプライチェーンの分断リスクが顕在化する中で、タイのように制度が整い、インフラが発展し、政治的にも中立性を維持している国の価値は、むしろ増しています。加えて、ASEANという巨大市場への中継拠点、そしてインド・中東方面への物流接続点という側面も含めれば、タイは日本企業にとって中長期的に“リスクを抑えつつ成長を追求できる製造拠点”であるといえるでしょう。
さらに、すでに進出している日系企業が多く、現地ネットワークやノウハウが蓄積されていることも大きな強みです。拠点拡張や機能集約、周辺国向けの輸出体制の構築など、既存の地盤を活かした展開が図れる点で、初期リスクが比較的少なく、実行可能性の高い戦略が描ける国であることも見逃せません。
今後、日本企業は「低コスト×規模拡大」から、「レジリエンス×多極化戦略」への転換を迫られる中で、タイが果たす役割はより重要になっていくと予測されます。
まとめ|相互関税時代の“安定型”拠点としてのタイを再評価する
2025年のトランプ政権による相互関税政策は、グローバル製造業にとって大きな転換点となっています。とりわけ中国やベトナムといった主要製造拠点が高関税の対象となった今、タイの相対的な安定性と信頼性が改めて注目されています。税制優遇措置や物流インフラの整備、現地調達率の高さ、日系企業との親和性のある人材といった要素は、他国と比較してもバランスが取れており、製造戦略において“安定型拠点”としての魅力を放っています。
もちろん、政治的変動や人件費上昇などの課題もある一方で、すでに多くの日本企業が進出し、ノウハウとネットワークを積み重ねてきた実績は、今後の拠点拡張や再配置の際にも有利に働くでしょう。また、「タイランド4.0」による産業の高度化が進む中で、従来の組立加工型の製造拠点から、付加価値型・地域統合型へと進化する可能性も大いにあります。
変化の激しい国際情勢において、タイは“低リスク・中期待値”の現実的な選択肢として、日本企業が改めて検討すべき戦略拠点といえるのではないでしょうか。チャイナ・プラスワンのその先を見据える今だからこそ、タイ製造業の再評価が求められています。
なお、「Digima~出島~」には、優良なタイビジネスの専門家が多数登録されています。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
本記事が、タイ進出・現地展開を検討される日本企業の皆様にとって、実務の一助となれば幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
オススメの海外進出サポート企業
-
YCP
グローバル22拠点✕800名体制で、現地に根付いたメンバーによる伴走型ハンズオン支援
<概要>
・アジアを中心とする世界21拠点、コンサルタント800名体制を有する、日系独立系では最大級のコンサルティングファーム(東証上場)
<サービス特長>
・現地に根付いたローカルメンバーと日本人メンバーが協働した伴走型ハンズオン支援、顧客ニーズに応じた柔軟な現地対応が可能
・マッキンゼー/ボストンコンサルティンググループ/ゴールドマンサックス/P&G/Google出身者が、グローバルノウハウを提供
・コンサルティング事業と併行して、当社グループで展開する自社事業群(パーソナルケア/飲食業/ヘルスケア/卸売/教育など)の海外展開実績に基づく、実践的なアドバイスを提供
<支援スコープ>
・調査/戦略から、現地パートナー発掘、現地拠点/オペレーション構築、M&A、海外営業/顧客獲得、現地事業マネジメントまで、一気通貫で支援
・グローバル企業から中堅/中小/スタートアップ企業まで、企業規模を問わずに多様な海外進出ニーズに応じたソリューションを提供
・B2B領域(商社/卸売/製造/自動車/物流/化学/建設/テクノロジー)、B2C領域(小売/パーソナルケア/ヘルスケア/食品/店舗サービス/エンターテイメントなど)で、3,000件以上の豊富なプロジェクト実績を有する
<主要サービスメニュー>
① 初期投資を抑えつつ、海外取引拡大を通した円安メリットの最大化を目的とする、デジタルマーケティングを活用した海外潜在顧客発掘、および、海外販路開拓支援
② 現地市場で不足する機能を補完し、海外事業の立ち上げ&立て直しを伴走型で支援するプロフェッショナル人材派遣
③ アジア圏での「デジタル」ビジネス事業機会の抽出&評価、戦略構築から事業立ち上げまでの海外事業デジタルトランスフォーメーションに係るトータルサポート
④ 市場環境変動に即した手触り感あるインサイトを抽出する海外市場調査&参入戦略構築
⑤ アジア特有の中小案件M&A案件発掘から交渉/実行/PMIまでをカバーする海外M&A一気通貫支援
⑥ 既存サプライチェーン体制の分析/評価/最適化、および、直接材&間接材の調達コスト削減 -
株式会社ダズ・インターナショナル
東南アジア・東アジア・欧米進出の伴走&現地メンバーでの支援が強み
私たちは企業の海外挑戦を設計→実行→着地まで伴走支援いたします。
これまでの企業支援数は1,500以上です。
私たちは『どの国が最適か?』から始まる海外進出のゼロ→イチから、
海外進出後のマーケティング課題も現地にて一貫支援いたします。
※支援主要各国現地にメンバーを配置し、海外進出後も支援できる体制
------------------------------------
■サポート対象国(グループ別)
↳アジア①(タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・インドネシア・フィリピン・ラオス)
↳アジア②(日本・香港・シンガポール・台湾・韓国)
↳アジア③(ドバイ・サウジアラビア・インドバングラデシュ・モンゴル・ミャンマー)
↳欧米(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)
※サポート内容により、対応の可否や得意・不得意な分野はあります。
------------------------------------
■対応施策ラインナップ
①"市場把握"サポート
目的は"海外現地を理解し、事業の成功可能性を上げる"こと。
(以下、含まれる施策)
↳市場概況・規制調査
↳競合調査
↳企業信用調査
↳現地視察企画・アテンド
②"集客活動"サポート
目的は"海外現地で売れるためのマーケティング活動を確立"すること。
↳多言語サイト制作
↳EC運用
↳SNS運用
↳広告運用(Google/Metaなど)
↳インフルエンサー施策
↳画像・動画コンテンツ制作
③"販路構築"サポート
目的は"海外現地で最適な海外パートナーとの取引を創出"すること。
↳商談向け資料制作
↳企業リストアップ
↳アポイント取得
↳商談創出・交渉サポート
↳契約サポート
④"体制構築"サポート
目的は"海外現地で活動するために必要な土台"をつくること。
↳会社設立(登記・銀行口座)
↳ビザ申請サポート
↳不動産探索(オフィス・倉庫・店舗・住居)
↳店舗開業パッケージ(許認可・内装・採用・集客)
↳人材採用支援(現地スタッフ採用支援)
------------------------------------ -
合同会社サウスポイント
世界と日本をつなぐ架け橋「沖縄」から海外展開を支援しています
2017年7月日本・沖縄と海外の万国津梁の架け橋を目指して、企業の海外展開支援を目的として沖縄・那覇で設立。アジア・欧州を中心に沖縄県内・沖縄県外企業の海外進出・国際展開のサポートを実施しています。2022年7月には観光産業の伸びの著しい石垣市に八重山事務所を開設しております。
沖縄をハブに、台湾・中国・香港・ベトナム・タイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・オーストラリア・ニュージーランド・イギリス・ドイツ・ブラジル各国にパートナーエージェントを配置し、アメリカ合衆国・インドは提携先を設けていますので、現地でも情報収集、視察等も直接支援可能、幅広く皆様の海外展開とインバウンド事業をサポートしております。 -
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。
実績:
東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)
東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)
南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)
北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)
中東(トルコ、サウジアラビア等)
ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)
アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等) -
株式会社東京コンサルティングファーム
【26ヵ国39拠点】各国日本人駐在員が現地にてサポートいたします。
弊社は、会計事務所を母体とした26ヵ国39拠点に展開するグローバルコンサルティングファームです。
2007年に日本の会計事務所として初めてインドに進出し、翌年ASEAN一帯、中南米等にも進出しました。歴が長く、実績・ノウハウも豊富にございます。
海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など国際ビジネスをトータルにサポートしています。
当社のサービスは、“ワンストップ”での サービスを提供できる環境を各国で整えており、特に会計・税務・法務・労務・人事の専門家を各国で有し、お客様のお困りごとに寄り添ったサービスを提供いたします。
<主要サービス>
・海外進出支援
進出相談から登記等の各種代行、進出後の継続サポートも行っています。月額8万円~の進出支援(GEO)もご用意しています。また、撤退時のサポートも行っています。
・クロスボーダーM&A(海外M&A)
海外企業の買収・売却による進出・撤退を支援しています。
・国際税務、監査、労務等
各国の税務・会計、監査や労務まで進出時に必要な業務を幅広く行っています。
・現地企業マッチングサポート
海外販路拡大、提携先のリストアップ、代理店のリストアップ、合弁パートナー探し等を行うことができます。TCGは現地に拠点・駐在員がいるため現地企業とのコネクションがあり、スピーディーに提携先のリストアップなどを行うことができます。