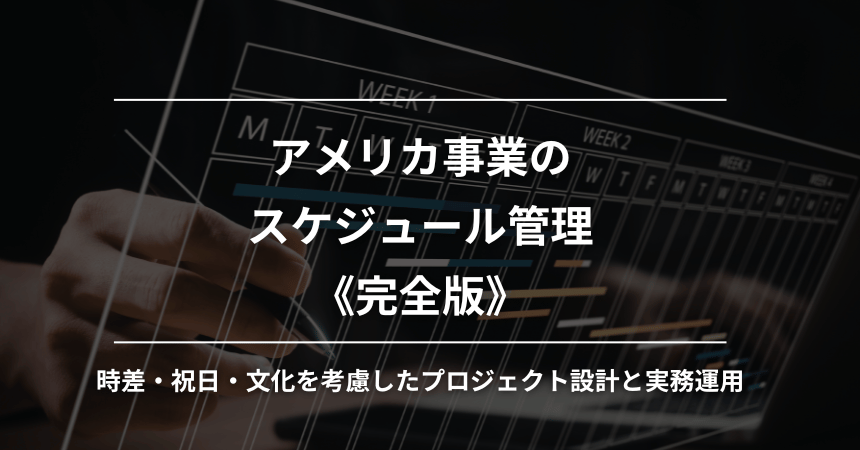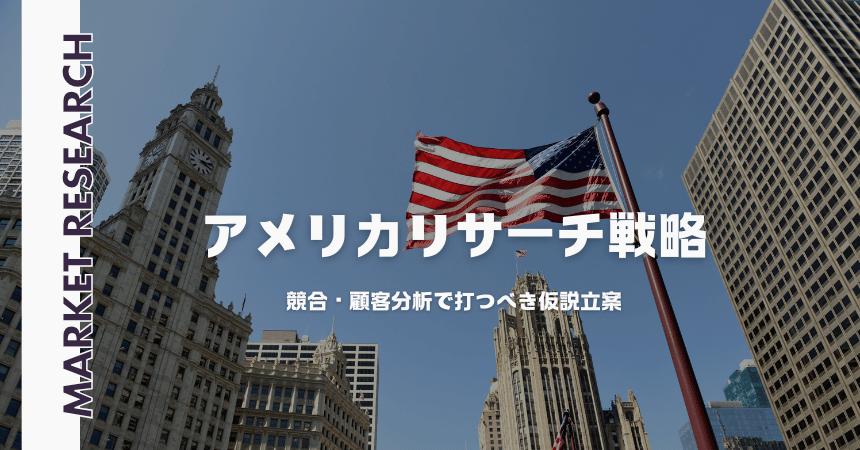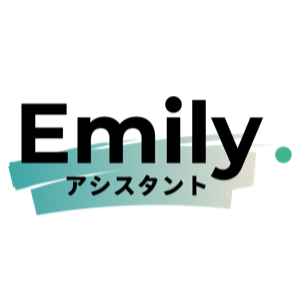アメリカのZ世代とは?|価値観・消費行動・マーケティング戦略を徹底解説
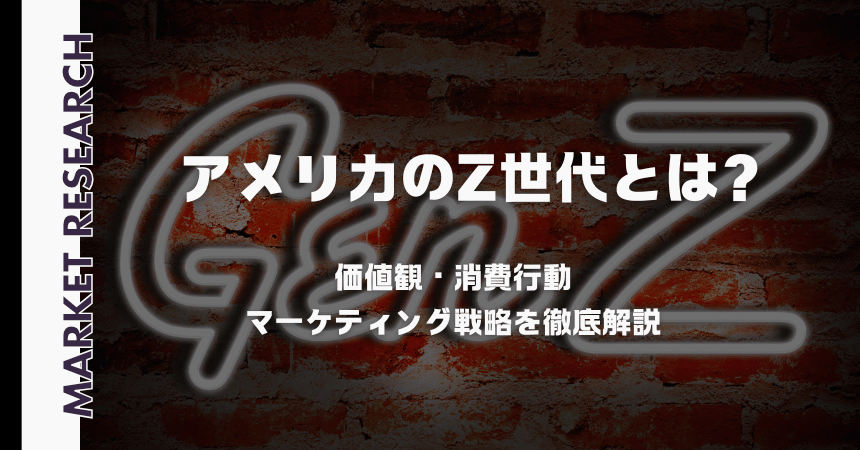
スマートフォンとSNSが当たり前に存在する世界に生まれ育ち、リアルとデジタルの境界を軽々と越えるZ世代。
多様性やサステナビリティへの関心が高く、共感や体験価値を重視するこの新しい世代は、すでにアメリカの経済・文化・社会に大きな影響を与えはじめています。
本記事では、Z世代の基本的な定義から価値観、ライフスタイル、消費行動、そして彼らに響くマーケティング戦略までを包括的に解説します。
これからの時代をリードするZ世代を正しく理解し、未来のビジネスチャンスを掴みましょう。
▼ アメリカのZ世代とは?|価値観・消費行動・マーケティング戦略を徹底解説
1. アメリカのZ世代とは?基本的な定義と特徴
ミレニアル世代との違い
Z世代は、一般的に1997年から2012年頃に生まれた世代を指します。Z世代のひとつ前の世代であるミレニアル世代は1981年から1996年生まれで、Z世代とは育った環境が大きく異なります。
Z世代に関しての特徴や主な違いに関しては下記の通りです。
【デジタルネイティブとしての特性】
Z世代は生まれたときからスマートフォン、SNSといったデジタル環境が整っていた「真のデジタルネイティブ世代」です。一方でミレニアル世代は、アナログからデジタルへの移行期を経験した「デジタル移行世代」です。
【情報感度とアクセススピード】
Z世代はミレニアム世代と比較して、膨大な情報に即時アクセスできる環境に慣れているため、短くてビジュアル中心のコンテンツを好み、情報選別力も高い傾向にあります。
【価値観・生活スタイル】
多様性や社会的公正を重視する傾向が強く、ブランドや商品にも透明性や倫理性を求める傾向があります。また、自己表現の場としてSNSを活用し、リアルとオンラインの境界が曖昧となる世代です。
【購買行動の変化】
インフルエンサーやレビュー、体験型コンテンツを重視しています。EコマースやSNS上での買い物も当たり前で「体験」や「共感」を重視する消費傾向が特徴的となります。
人口規模・経済的影響力の大きさ
アメリカのZ世代は、約6,800万人以上とされており、ミレニアル世代を上回るペースで成長しています。2025年には、全米の人口の約20%以上を占めると見込まれており、すでにその影響力は無視できない段階に入っています。
【家族内での購買決定への影響】
Z世代は自らの購買だけでなく、親世代(主にX世代・ミレニアル世代)に対する影響力も大きいのが特徴です。
Z世代の66%以上が、家庭の買い物に何らかの意思決定をしているとされ、食品、テクノロジー製品、旅行先など幅広いジャンルに意見しています。
【経済的影響と今後の市場価値】
Z世代の年間購買力は、すでに1,500億ドル(約22兆円)超に達しており、さらに拡大中です。
家族や友人などへの間接的な影響力を含めると、その経済影響力は3,000億ドル以上と評価されています。
今後10年以内には、労働市場の中核層として定着し、投資・貯蓄・不動産購入など長期的な経済活動にも関わるようになります。
【就労・投資・発信】
Z世代は現在、学生や新社会人という立場にありながら、SNSを通じてブランドを拡散したり、エシカル消費を広めたりと「発信力」そのものが経済価値を持つ世代でもあります。
また、近年は早期からの株式投資や暗号資産運用にも積極的で、従来の若年層よりも金融リテラシーが高いという報告も増えています。
デジタル・ソーシャルネイティブ
Z世代は、物心ついたときからスマートフォンやSNSが身近に存在する環境で育った、いわば「デジタル・ソーシャルネイティブ」です。
テレビよりもYouTube、検索エンジンよりもTikTokやInstagramといったSNSが情報源の中心であり、コンテンツの消費・発信の両方を日常的にこなしています。
情報収集の変化「検索エンジンよりSNS」
従来の世代がGoogleで調べていたのに対し、Z世代は「まずSNSで検索する」という傾向が顕著です。TikTok、Instagram、Redditなどのプラットフォームで「リアルな声」や「共感できる体験」を求めており、特にZ世代の約40%はGoogleの代わりに、TikTokやInstagramで情報収集を行っています。
マーケティングへの影響「広告より共感・口コミ」
Z世代にとって信頼できる情報源は、企業が発信する広告ではなく、インフルエンサーや友人・家族のリアルなレビューや体験談となります。共感性が非常に重視されており「自分らしさ」や「社会的価値観」と結びついたブランドに反応を示しています。
つまりZ世代は、従来のマス広告やSEO中心のアプローチだけでは届きにくい層であり「体験を軸にした共感型マーケティング」や「SNS上での自然な話題化」が重要となる世代なのです。
2. アメリカZ世代の価値観とライフスタイル
多様性・包括性への意識
アメリカのZ世代は、歴代のどの世代よりも「多様性(Diversity)」と「包括性(Inclusion)」に対する感度が高い世代とされています。
人種、ジェンダー、LGBTQ+、宗教、身体的・精神的な障がいなど、あらゆる違いを尊重し「誰もが尊重され、排除されない社会」を理想とする価値観が強く根づいています。
この世代は、SNSを通じて日常的に社会問題に触れており、差別的・排他的な発言や行動に対して非常に敏感です。
一度でも不適切と判断されれば、企業や有名人に対しても即座にSNS上で批判が集中する、いわゆるキャンセルカルチャーの担い手でもあります。
例えば、2020年以降に企業が「BLM(Black Lives Matter)」への立場を明確にしなかったことや、トランスジェンダーへの対応に問題があった事例で、複数のブランドが不買運動や炎上に発展しました。
Z世代にとっての商品やサービスは「質」だけでなく、それを提供する企業の価値観・社会的姿勢も購買判断の大きな基準となります。単に「多様性と包括性に配慮している」だけでなく、どれだけ真摯に取り組んでいるか、行動で示しているかを常に観察しています。
Z世代にとって「多様性」と「包括性」は単なる理想論ではなく、日常の行動基準であり、企業の存在意義を問う物差しとなっています。
環境・社会問題への関心、サステナビリティ重視
Z世代は、地球温暖化やプラスチック汚染、生物多様性の喪失などの環境危機とともに育ってきた世代です。
ニュースやSNSを通じて、日常的に気候変動や貧困、労働搾取といった社会問題に触れているため、企業の環境配慮や社会的責任に対して、非常に鋭い目を持っています。
商品選択の基準として「安い・早い・便利」といった従来の購買基準に加え、Z世代は「この製品は環境に負荷をかけていないか?」「動物実験や児童労働など倫理的に問題はないか?」「このブランドは社会貢献に積極的か?」などの問いを無意識に投げかけています。
例えば、脱プラスチック包装や再生素材の使用、カーボンオフセットの導入、動物実験を行わないコスメ(cruelty-free)の人気は、Z世代の価値観を象徴していると言えるでしょう。
「A:安いけれど環境破壊につながる商品」と「B:やや高くてもサステナブルな商品」の場合、Z世代は後者のBを選ぶでしょう。これらの判断基準は、Z世代では当たり前でごく自然なものです。
近年では、Z世代の購買行動の中で「企業の価値観」がブランド選びの差別化要素になっています。単なる「エコ風」ではなく、透明性のある実行とコミュニケーションを企業側に求めています。
Z世代にとってサステナビリティは「あれば嬉しい」付加価値ではなく「買う」「買わない」を決める大前提の条件となっています。
自己表現・リアル重視
Z世代にとって「何を持っているか」より「何を表現しているか」が重要であると言えます。ブランド名や価格、社会的ステータスで自己を飾る時代ではなく、自分らしさや価値観にフィットするかが選択の決め手になっています。
「ブランド=自分の一部」になる時代で、モノやサービスを通じて自分の価値観・スタイル・信念を表現しようとします。Z世代はブランドに次のような要素を求めています。
・リアルなストーリー:創業背景やビジョンに共感できるか。
・世界観・空気感:自分のライフスタイルや美意識に合うか。
・社会性・姿勢:社会課題への関心や取り組みに納得感があるか。
これにより、従来の「大手・有名=正義」の公式が通用しにくくなっています。むしろ、知る人ぞ知るD2Cブランドや、無名でもメッセージ性の強い商品の方がZ世代に支持される傾向にあると言えるでしょう。
過剰に演出された広告や、有名人による一方的なアピールより、日常の中にある「リアルな価値」を伝える方が効果的です。Z世代は企業のマーケティングメッセージに敏感で「見せかけの多様性」や「ウワベの社会貢献」を見抜く力を持っています。
重要なのは、企業が何を言うかではなく「誰が・どんな文脈で伝えるか」だと言うことで、SNSやコミュニティベースの発信が重要なカギとなっています。
Z世代は「共感できるかどうか」を最優先に商品やサービスを選んでいます。彼らに響くのは「流行っているから」や「有名だから」ではなく「そこに自分が投影できるか」なのです。
3. Z世代の消費行動とメディア接触傾向
SNS(TikTok、YouTube、Instagramなど)の役割
Z世代の情報収集・購買行動において、SNSは単なる「娯楽」ではなく、検索エンジン・口コミの場であり「購買の入口」となります。
特にTikTok、YouTube、Instagramは、Z世代にとって日常的な情報インフラとなっており、従来のGoogle検索を超える存在になりつつあります。
Z世代にとって、TikTokは新たな検索エンジンになっており、Z世代の多くがレストランや商品の情報を探す際にGoogleよりもTikTokやInstagramを利用しているようです。
これは「視覚的でわかりやすい」「リアルな体験が見られる」「テンポが早くて飽きない」というSNS特有の特長が、Z世代の情報感度とマッチしているためだと言えるでしょう。
短尺・視覚的コンテンツで瞬時に判断するZ世代にとって、冗長な情報や文章に対してストレスを感じやすく、数秒で魅力を伝える短尺コンテンツが求められています。TikTokやInstagramリール、YouTubeショートといった縦型・ビジュアル中心の動画は、商品の魅力や使用感をダイレクトに伝え、そのまま購買へとつながる導線を構築することができます。
ブランドロイヤルティもSNSで形成されており、単なる商品の宣伝ではなく「なぜこのブランドを好きになったのか」「使ってどう感じたか」というユーザーの共感・ストーリーが可視化されています。
SNS上でバズった商品が即完売になる現象も日常的に起きており、購買意欲→認知→ロイヤルティがSNS内で完結するケースが年々増加しています。
Z世代にとってSNSは「ただの広告プラットフォーム」ではなく、生活の一部としてブランドと出会い、共感し、選択する場として確固たる地位を確立しています。企業はこれらを踏まえ、SNSを単なる集客手段として捉えるのではなく、体験価値・共感・透明性を軸にしたコミュニケーション戦略を考える必要があります。
価格よりも「体験価値」や「ストーリー」に反応
Z世代は単に「安さ」や「機能性」では心を動かされにくい世代となります。彼らが求めているのは「その商品を買うことで、どんな気持ちや体験が得られるか」という感情的な価値であると言えます。
Z世代の消費は下記のような傾向にシフトしています。
・誰と買い物をしたか
・どんな気持ちでその商品を選んだか
・その体験を誰と共有したか(SNS投稿、ストーリー共有)
・そのブランドや商品が自分の人生・価値観とどう繋がるか
たとえば、同じTシャツでも「どこで買ったか」や「誰が作ったのか」あるいは「その収益がどんな社会貢献に使われるか」など、背景にあるストーリーやつながりにこそ価値を感じるのがZ世代です。
Z世代の購買行動では「価格が安いか」より「自分らしくいられるか」「共感できるか」が重視され、ブランドに対する愛着や発信行動にも直結します。
使い捨ての安価な商品よりも「長く使いたいと思える」ストーリー性ある製品を選ぶ傾向にあります。
この傾向は、ファッション・コスメ・飲食・体験・サービスなど、あらゆる業種に広がっており、企業側も「商品スペック」ではなく「物語・世界観・顧客体験の設計」を意識した戦略が求められています。
つまりZ世代にとって「なにを買うか」ではなく「なぜそれを選んだか」が重要であると言えるでしょう。企業やブランドが共感される存在であるかどうかが、消費の意思決定に直結する時代となっています。
レビュー・UGC・コミュニティの影響力
YouTubeのレビュー動画やTikTokでの「開封動画(#unboxing)」Instagramでの「使用感のレポート」など、第三者による等身大のレビューがZ世代の購買意欲を大きく左右させます。
・実際の使用感が見える
・想像しやすく、納得感がある
・SNSで拡散されている=「みんなが良いと言っている」という信頼感
上記のような条件を踏まえ、企業が大量広告で商品やサービスを押し出すよりも、ユーザーのよりリアルな声を引き出し、可視化することが重要であると言えます。
さらにZ世代は「コミュニティ(自分と似た価値観を持つ人たちが集まる場)」に強い魅力を感じる傾向があります。レビューを読むだけでなく、投稿して他のユーザーと繋がることにも価値を見出しているのです。
Z世代に響くのは「企業が自分に語りかける広告」ではなく「信頼できる誰かのリアルな声」となります。
その声が多く集まるSNS・レビュー・コミュニティの場こそが、Z世代の購買の現場であり、ブランドの信頼構築の土台でもあると言えるでしょう。
4. アメリカZ世代に響くマーケティング戦略とは?
インフルエンサー選定とブランドの距離感
Z世代への影響力を与えるのは「大物セレブ」や「フォロワー数の多いインフルエンサー」だけではありません。
むしろ彼らが信頼するのは、ナノインフルエンサー(フォロワー数1,000〜10,000)やマイクロインフルエンサー(〜50,000)といった、リアルさと距離の近さを感じさせる存在です。
「広告っぽさ」は逆効果となります。「過度に美化・演出された映像や写真」「ステルスマーケティングと捉えられそうな曖昧なPR表記」のような投稿は、不信感や離脱の原因に陥りやすくなります。
代わりに「使ってみたら意外と良かった」「友達におすすめしたい」といった、生活者視点のカジュアルな発信の方がZ世代の心を動かします。
「ナノマイクロインフルエンサー」と言われているインフルエンサーは、フォロワーとの距離が近く、推薦する商品への信頼性が高くなる傾向にあります。
そのため、コメントやリアクションの熱量が強く、UGCや拡散にも繋がりやすく、ブランドにとってもコスト効率がよく、ナノマイクロインフルエンサーの起用は「量より質」のアプローチが可能となります。
Z世代に届くインフルエンサー戦略は、知名度 < 共感度・演出 < 等身大のリアル、であると言うことを忘れないようにしましょう。
ストーリーテリング・リアルな共感の重要性
Z世代は商品自体よりも「そのブランドが何者なのか」「なぜ存在するのか」に価値を見出します。彼らは機能やスペックではなく、背景にあるストーリーや社会的意義、企業の姿勢に共感したとき、初めて「買いたい」「応援したい」と感じます。
「何を売るか」ではなく「なぜそれを売るか」が、Z世代の心を動かし、単なる「商品説明」ではなく、以下のような理由を購入の判断材料とします。
・このブランドはどんな課題を解決しようとしているのか?
・誰のために、どんな未来を目指しているのか?
・企業の行動や製品に一貫した価値観があるか?
企業・ブランドのストーリーに共感したZ世代は「そのブランドのファンになる」「自らのSNSでその想いを発信する」「自分の価値観と重なるものとして、仲間のように応援する」というような行動に出ます。
これにより企業やブランドは、価格競争に巻き込まれずに長期的なロイヤルティを築くことが可能となるのです。
Z世代が企業側に求める姿勢とは「ストーリーを押しつけず、生活者の感情に自然に届く形で伝えること」「企業の顔や声として、創業者・社員・顧客のリアルな言葉を活用すること」です。
たとえば、創業のきっかけや壁を乗り越えた話、ユーザーの声に耳を傾けた変化など、人間らしさと真摯さが感じられる内容が好まれると言えます。
マイクロコミュニティを活かした施策設計
Z世代においては「大多数に向けたメッセージ」よりも、価値観や関心を共有する「マイクロコミュニティ(小さな集団)」へのアプローチが、深い共感と高い反応を得る鍵となります。
Z世代は多様で分散的なコミュニティ形成を行なっています。以前の世代までのように「若者全体に刺さるメッセージ」は一切存在しません。
代わりに彼らは、次のような細分化された属性を軸に動いています。
・ヴィーガンやサステナビリティ重視層
・アニメ・K-POPなどのオタクカルチャー系クラスタ
・LGBTQ+やジェンダーフリーを重視する人たち
・ローカル・インディペンデント志向のファン層
・DIY/クラフト・スローライフ重視派 など
それぞれのマイクロコミュニティに特化することで「自分たちのことを理解してくれている」という認識が生まれ、ブランドへの共感・信頼が確固たるものになります。
「広く浅く」より「狭く深く」がZ世代に刺さる条件であると言えるでしょう。
マイクロコミュニティに響くポイントは下記の通りです。
・ターゲティング精度が高いため、メッセージの受け取り方が的確
・ニッチな文脈や言葉を使える=「わかってる感」が伝わる
・彼ら自身が発信者となり、UGC・バイラル効果が高まる
マイクロコミュニティを活かす施策例として、DiscordやRedditなどでコミュニティ運営・参加したり、UGCキャンペーンを小規模クラスタごとに展開したり、ナノマイクロインフルエンサーをコミュニティの中心人物として起用すると良いでしょう。
5. 日本企業がアメリカZ世代を攻略するには?
日本発ブランドの成功事例
Z世代にとって「日本=クールで本物感のあるカルチャー」という印象が根強く、特にデザイン性・ミニマリズム・ポップカルチャー・ヘルシー志向といった軸で、日本ブランドが高評価を得ています。
① 無印良品(MUJI)
【評価ポイント】
・ミニマルでサステナブルな世界観
・買い手に考えさせる余白があるデザイン
・商品にロゴがなく、自己表現に干渉しない「自由な美学」
Z世代は「過剰なブランド主張」を敬遠する傾向にあるので、MUJIの「無主張」がむしろ共感を呼んでいます。また、環境配慮や詰替え文化など、サステナブルな姿勢もアメリカのZ世代に好印象を与えています。
② ユニクロ(UNIQLO)
【評価ポイント】
・シンプルで高品質なベーシックウェア
・「ファッションは自己表現の手段」と考えるZ世代にとって、無地で自由に着回せることが好都合
・Jil SanderやJW ANDERSONなどのハイブランドとのコラボがトレンド感を演出
ブランド名やブランド力での成功というよりは、自分のスタイルを確立するブランドとして機能しています。さらに、TikTokでは「UNIQLO haul」や「minimalist fits」などの動画がZ世代に人気となっています。
③ アニメ・マンガ文化
【評価ポイント】
・ストーリーの奥行き・キャラへの共感
・LGBTQ+や異文化受容を扱うストーリーも多く、Z世代の価値観と親和性が高い
・コスプレやファンアートなど、UGCを生む参加型カルチャーの形成
アニメはZ世代にとって「個性を表現する手段」でもあり、単なる趣味を超えてライフスタイルの一部になっています。また現在アメリカでは、アニメTシャツやコラボグッズがストリートファッションとして浸透しています。
④ 日本食・寿司チェーン
【評価ポイント】
・ヘルシー・クリーン・エシカルな食スタイルとして注目
・ヴィーガン寿司やプラントベースのメニュー展開も進んでおり、Z世代の食志向と合致
・回転寿司や自動注文など「体験として面白い」仕組みがSNS映えする
SushiはZ世代にとって「クールな選択肢」で高カロリーなファストフードより「健康的でスマート」という印象を持っています。TikTokでは「Sushiロール作ってみた」「日本食モッパン」なども人気ジャンルとなっています。
日本企業が陥りがちな失敗と改善ポイント
①広告感が強すぎる/企業色が前面に出すぎる
【失敗例】
・一方的なプロモーション動画を大量に出す
・ブランドの「実績」や「日本での人気」ばかりを強調
・SNS投稿がすべて宣伝的で、共感より押し付け感が強い
【改善策】
Z世代との共創・リアルな声を活用したUGC型施策にシフトすると良いでしょう。たとえば「Z世代の実体験紹介」や「現地ユーザーのインタビュー動画」を作成し、宣伝よりも「共感ベースのストーリーテリング」を軸にするようにします。
TikTokやInstagramでは、あえて広告っぽくないコンテンツ(生活に溶け込むVlog風など)が好まれる傾向にあります。
②ターゲット像が曖昧で「若者」と一括りにしてしまう
【失敗例】
・「若者向けにSNSやっとけばいいでしょ!」と雑な広報設計
・性別・文化的背景・価値観が多様なZ世代を一様に扱い、刺さらないメッセージにする
・日本でのヒット実績をそのまま輸出する感覚
【改善策】
実際にアメリカ現地のZ世代をテストグループ・コンテンツ制作に巻き込み、リアリティと共感度を高めるようにします。Z世代の中のマイクロコミュニティ単位で設計し、SNSトレンド、インタビューや対話に基づいたペルソナを設計すると良いでしょう。
③日本基準での製品設計/顧客体験がアメリカ現地に合わない
【失敗例】
・メニューや接客が日本国内のスタンダードをそのまま再現
・英語訳が直訳すぎて違和感、UXが現地基準で考えられていない
・サービスのスピード感や返品対応が日本式の美徳に寄りすぎる
【改善策】
アメリカ現地のZ世代と一緒に商品・UX設計を行い「共同開発」します。また、現地SNSやReddit、Discordなどからリアルな声を継続的に収集・分析することで、日本的な「丁寧すぎる品質」よりも、スピード・簡潔・自由さが評価されるというアメリカの商文化への最適化を図りましょう。
ローカライズと世界観の「翻訳力」
日本発ブランドがアメリカZ世代に響くためには「ローカライズ=単なる言語翻訳」ではなく、価値観と世界観の正しい翻訳が鍵となります。
日本語を単に英語へと直訳するだけでは、そのメッセージはZ世代には刺さりません。商品やサービスの品質が高くても、その背景にある文脈(文化・価値観・美意識)が、日本でのプロモーション活動と同等では伝わらない場合が多くなります。
たとえば「丁寧な手仕事」「和の美意識」「控えめなデザイン」など、日本ではポジティブな意味でも、アメリカZ世代には「地味」「何を主張しているのか分からない」と映る可能性もあります。
ローカライズ成功のポイントとして、アメリカ英語のネイティブによる自然なストーリーテリングを行い、プロダクトデザイン、ロゴ、色彩などをアメリカのZ世代が好むようなものにしましょう。
またプロモーション活動では、SNSや動画コンテンツ、インフルエンサー、UGCなどを活用し、体験ベースで消費者に伝えるようにします。「現地に合わせる」だけでなく、「現地の文化と混ぜ合わせて、新しい価値になる」ということが、日本企業にとって最も理想的であると言えるでしょう。
まとめ
Z世代を理解することがアメリカ市場の扉を開く
Z世代は倫理性や多様性といった価値観を重視し、価格や機能よりもブランドの姿勢に共感して消費を選びます。
彼らと信頼関係を築くには、一方通行の広告ではなく、共感や対話を重視したマーケティングが欠かせません。
Z世代を単なる「顧客」ではなく「共創者」と捉える視点が、これからのブランド戦略に求められています。
アメリカ進出なら「Emily.アシスタント」にお任せください
今回は「アメリカのZ世代とは?|価値観・消費行動・マーケティング戦略を徹底解説」について解説しました。
私たち「COEL, Inc.」は〝アシスト〟というアプローチで、日本企業のアメリカ進出をサポートしています。
「COEL, Inc.」が提供する、アメリカ市場に特化した日本語・英語対応のオンラインアシスタントサービス「Emily.アシスタント」では、アメリカ在住の日米バイリンガルのアシスタントが所属しており、アメリカでビジネスを営む日本企業のサポートを行っております。
アメリカ進出のサポートから、実際に現地でビジネス運営を行う企業のサポートなど、様々な日本企業のアメリカでのビジネスパートナーとして活動しています。
アメリカ進出をご検討の方はぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
オススメの海外進出サポート企業
-
YCP
グローバル22拠点✕800名体制で、現地に根付いたメンバーによる伴走型ハンズオン支援
<概要>
・アジアを中心とする世界21拠点、コンサルタント800名体制を有する、日系独立系では最大級のコンサルティングファーム(東証上場)
<サービス特長>
・現地に根付いたローカルメンバーと日本人メンバーが協働した伴走型ハンズオン支援、顧客ニーズに応じた柔軟な現地対応が可能
・マッキンゼー/ボストンコンサルティンググループ/ゴールドマンサックス/P&G/Google出身者が、グローバルノウハウを提供
・コンサルティング事業と併行して、当社グループで展開する自社事業群(パーソナルケア/飲食業/ヘルスケア/卸売/教育など)の海外展開実績に基づく、実践的なアドバイスを提供
<支援スコープ>
・調査/戦略から、現地パートナー発掘、現地拠点/オペレーション構築、M&A、海外営業/顧客獲得、現地事業マネジメントまで、一気通貫で支援
・グローバル企業から中堅/中小/スタートアップ企業まで、企業規模を問わずに多様な海外進出ニーズに応じたソリューションを提供
・B2B領域(商社/卸売/製造/自動車/物流/化学/建設/テクノロジー)、B2C領域(小売/パーソナルケア/ヘルスケア/食品/店舗サービス/エンターテイメントなど)で、3,000件以上の豊富なプロジェクト実績を有する
<主要サービスメニュー>
① 初期投資を抑えつつ、海外取引拡大を通した円安メリットの最大化を目的とする、デジタルマーケティングを活用した海外潜在顧客発掘、および、海外販路開拓支援
② 現地市場で不足する機能を補完し、海外事業の立ち上げ&立て直しを伴走型で支援するプロフェッショナル人材派遣
③ アジア圏での「デジタル」ビジネス事業機会の抽出&評価、戦略構築から事業立ち上げまでの海外事業デジタルトランスフォーメーションに係るトータルサポート
④ 市場環境変動に即した手触り感あるインサイトを抽出する海外市場調査&参入戦略構築
⑤ アジア特有の中小案件M&A案件発掘から交渉/実行/PMIまでをカバーする海外M&A一気通貫支援
⑥ 既存サプライチェーン体制の分析/評価/最適化、および、直接材&間接材の調達コスト削減 -
株式会社ダズ・インターナショナル
東南アジア・東アジア・欧米進出の伴走&現地メンバーでの支援が強み
私たちは企業の海外挑戦を設計→実行→着地まで伴走支援いたします。
これまでの企業支援数は1,500以上です。
私たちは『どの国が最適か?』から始まる海外進出のゼロ→イチから、
海外進出後のマーケティング課題も現地にて一貫支援いたします。
※支援主要各国現地にメンバーを配置し、海外進出後も支援できる体制
------------------------------------
■サポート対象国(グループ別)
↳アジア①(タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・インドネシア・フィリピン・ラオス)
↳アジア②(日本・香港・シンガポール・台湾・韓国)
↳アジア③(ドバイ・サウジアラビア・インドバングラデシュ・モンゴル・ミャンマー)
↳欧米(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)
※サポート内容により、対応の可否や得意・不得意な分野はあります。
------------------------------------
■対応施策ラインナップ
①"市場把握"サポート
目的は"海外現地を理解し、事業の成功可能性を上げる"こと。
(以下、含まれる施策)
↳市場概況・規制調査
↳競合調査
↳企業信用調査
↳現地視察企画・アテンド
②"集客活動"サポート
目的は"海外現地で売れるためのマーケティング活動を確立"すること。
↳多言語サイト制作
↳EC運用
↳SNS運用
↳広告運用(Google/Metaなど)
↳インフルエンサー施策
↳画像・動画コンテンツ制作
③"販路構築"サポート
目的は"海外現地で最適な海外パートナーとの取引を創出"すること。
↳商談向け資料制作
↳企業リストアップ
↳アポイント取得
↳商談創出・交渉サポート
↳契約サポート
④"体制構築"サポート
目的は"海外現地で活動するために必要な土台"をつくること。
↳会社設立(登記・銀行口座)
↳ビザ申請サポート
↳不動産探索(オフィス・倉庫・店舗・住居)
↳店舗開業パッケージ(許認可・内装・採用・集客)
↳人材採用支援(現地スタッフ採用支援)
------------------------------------ -
合同会社サウスポイント
世界と日本をつなぐ架け橋「沖縄」から海外展開を支援しています
2017年7月日本・沖縄と海外の万国津梁の架け橋を目指して、企業の海外展開支援を目的として沖縄・那覇で設立。アジア・欧州を中心に沖縄県内・沖縄県外企業の海外進出・国際展開のサポートを実施しています。2022年7月には観光産業の伸びの著しい石垣市に八重山事務所を開設しております。
沖縄をハブに、台湾・中国・香港・ベトナム・タイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・オーストラリア・ニュージーランド・イギリス・ドイツ・ブラジル各国にパートナーエージェントを配置し、アメリカ合衆国・インドは提携先を設けていますので、現地でも情報収集、視察等も直接支援可能、幅広く皆様の海外展開とインバウンド事業をサポートしております。 -
COEL, Inc.
アメリカで欠かせない優秀なEmily.アシスタント
私たちCOEL, Inc.は“アシスト”というアプローチで、日本企業が挑戦するアメリカ市場において、欠かせない存在になることを追求しています。
アメリカ市場に特化した日本語・英語 対応のオンラインアシスタントサービスを提供しており、日常業務から専門分野まで幅広い業務をこなしている忙しいあなたの代わりに各種業務のサポートを担います。
アメリカでビジネスを始める企業や、すでに事業展開しているけれども様々なリソース課題を抱えている日本企業に向けて、弊社アシスタントが貴社と同じチームメンバーのように伴走させて頂き、アシスタント業務以外にも「EコマースやMarketing、カスタマーサポート、会計など」に精通したメンバーが業務のサポート致します。 -
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。
実績:
東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)
東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)
南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)
北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)
中東(トルコ、サウジアラビア等)
ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)
アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等)