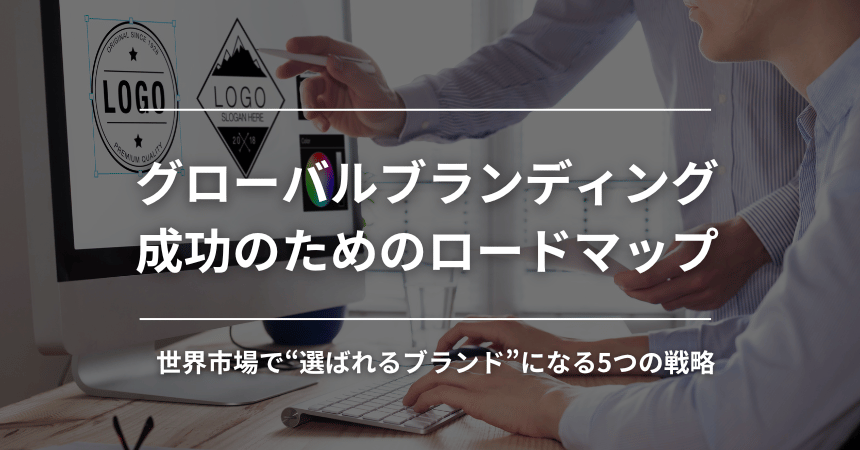【2022年版】IMD世界競争力ランキング-日本の国際競争力はなぜ低下してしまったのか?

「IMD世界(国際)競争力ランキング」について解説します。併せて「日本の国際競争力の低下とその2つの要因」についても考察していきます。
「IMD国際競争力」とは、MBAプログラムが高い評価を受けているスイスのビジネススクール「IMD( International Institute for Management Development / 国際経営開発研究所」が発行する「IMD World Competitiveness Yearbook (WCY):IMD世界競争力年鑑」を指します。これは国家の競争力に関する年次報告書として知られており、さる7月に2022年の調査結果が発表されました。
結果から言うと、世界ランキング1位はデンマーク、アジアトップは3位のシンガポール。日本は(2020年と同じ)過去最低で34位でした。
海外ビジネスに携わり、国際市場を攻略する戦略を立てるにあたって、日本を含めた世界の競争力を知っておくことは非常に有益です。
今回はこの2022年度版IMD世界競争力年鑑の「国際競争力ランキング」をもとに、世界各国の国際競争力について理解を深めていきましょう。
本文後半では、冒頭で述べた、近年問題視されている「日本の国際競争力の低下とその2つの要因」についても詳しく解説していきます。
▼2020年の「IMD世界競争力ランキング」について解説した記事はコチラ
「IMD 世界競争力ランキング」で日本が過去最低の34位 | IMD「世界競争力年鑑」2020年版を分析」
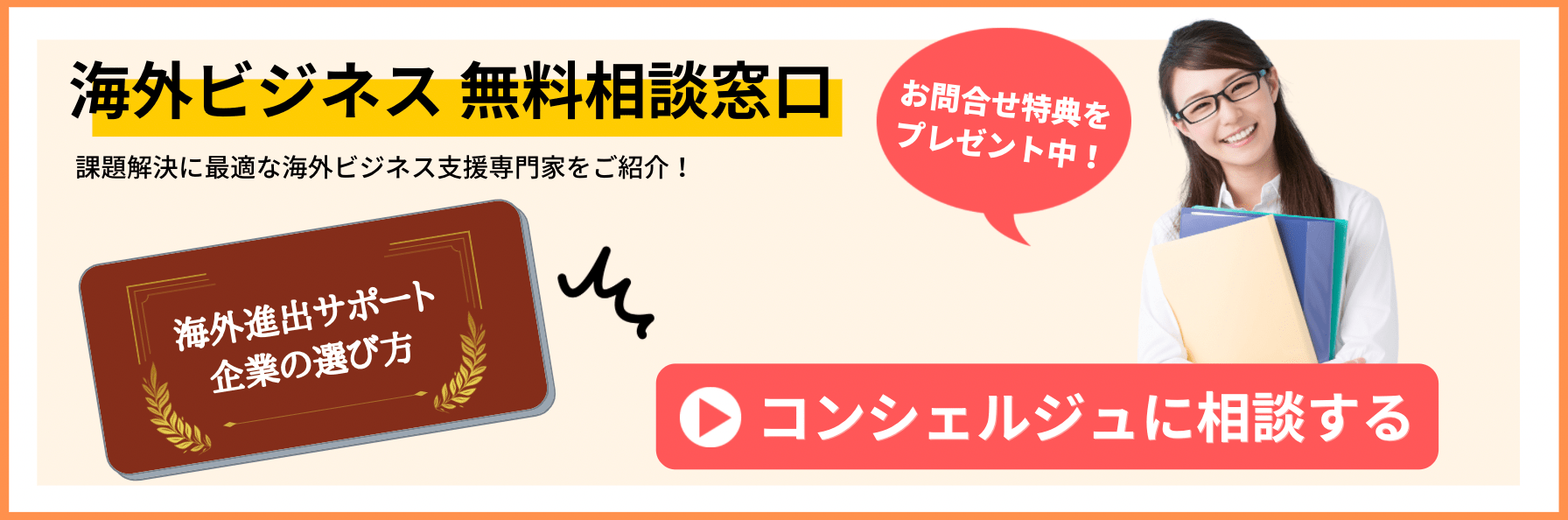
▼【2022年版】IMD世界競争力ランキング-日本の国際競争力はなぜ低下してしまったのか?
- 1. 国際(世界)競争力ランキング2022の結果を解説
- 2. 国際(世界)競争力とは
- 3. 「IMDランキング(世界競争力年鑑)」とは?
- 4. 日本の国際競争力はなぜ低下してしまったのか? 2つの要因を解説
▼アナタの海外ビジネスを成功させるために
1. 国際(世界)競争力ランキング2022の結果を解説
冒頭でも述べましたが、IMDは1989年から毎年「IMD世界競争力年鑑」を発行しており、国際競争力ランキングを発表しています。
調査対象は63の国や地域であり、20項目、333の基準で競争力をスコア化。「経済状況/経済パフォーマンス」「政府の効率性」「ビジネスの効率性」「インフラ」の4つの大項目において順位づけがなされています。
まずは、2022年度のランキングから世界各国の国際競争力を見ていきましょう。
デンマークが初の1位
■世界競争力ランキング 2022(2021)
競争力ランキング-2.png)
2022年の国際競争力ランキングでは、北欧で初めてデンマークが首位を獲得しました。環境意識の高いデンマークはSDGsに積極的であり、国際投資の改善など、さまざまな要因から今回1位を獲得することとなりました。
デンマークは2020年の同ランキングでは2位、2021年には3位にランクインしており、今回が初の1位となっています。
昨年の1位はスイスで、2020年の1位はシンガポールでした。
3位のシンガポールがアジアトップ
世界各国に続いては、アジアに絞って見ていきましょう。
2020年には国際競争力ランキング首位を獲得したシンガポールですが、2021年には5位と順位を下げ、2022年は3位にランクイン。アジア・太平洋地域における首位をキープし続けています。
シンガポールは「国内経済」「国際貿易」の小項目では1位となっており、コロナ禍において経済を解放しつつ感染を抑えたことが高く評価されたようです。
日本は2020年と同じ過去最低の34位
続いては気になる日本の順位です。
調査開始時の1989年から1992年までは首位を獲得していた日本ですが、1997年からは大きく順位を落とし、近年の結果はかなり残念なものとなっています。
2022年の結果は2020年の順位と同じ34位となっており、2020年から3位上昇した2021年の31位から3つランクを落としました。
34位はこれまでの日本の順位の中で過去最低であり、2022年の日本は、2020年に続いてまたもや過去最低ランクを獲得してしまったということです。
2. 国際(世界)競争力とは
国際(世界)競争力ランキング2022の順位について理解できたところで、国際競争力とはそもそも何か、ということも知っておきましょう。この項では国際競争力の定義と重要性について解説します。
国際競争力の定義
「国際競争力」とは国際経済取引における産業や企業の競争力のことです。大きく分けて価格競争力と非価格競争力の2つから成るもので、価格競争力の要素には競合より安価であることや使用価値などが挙げられます。
非価格競争力の要素には品質やアフターサポートなどの付加サービスなどが挙げられます。「世界競争力」も同じ意味で使われているようです。
国際競争力の重要性
では、なぜ国際競争力が重要なのでしょうか。簡単に言えば国際競争力が高ければ高いほど世界で売れる、ということであり、国際競争力の高い国の輸出は増加することとなります。
人口減少の影響を受け、日本の経済が縮小していくことはすでに多くの専門家が予測しており、これから国内市場がシュリンクしていく日本は、海外に市場を求めることを余儀なくされます。
海外に市場を求めるこれからの日本には国際競争力が必要不可欠なものとなるのです。
国際競争力を高める上では、他国がどういったカテゴリーにおいて競争力が強いのか、どの国がランキング上位にいるのかなどを常に把握し、国際市場を攻略する戦略を立てることが重要です。
このように、グローバル化が進む今、国際競争力は非常に重要な存在だと言えます。
3. 「IMDランキング(世界競争力年鑑)」とは?
前項では国際競争力の定義と重要性について解説しました。
冒頭で少し触れた通り、「IMD World Competitiveness Yearbook (WCY):IMD世界競争力年鑑」はMBAプログラムが世界的に高い評価を受けているスイスのビジネススクール「国際経営開発研究所(IMD)」が発行する年次報告書のことであり、「IMDランキング」とも呼ばれています。
この項では「IMDランキング」に加えて、それとは異なる指標で競争力を読み解く「WEFランキング」についても解説していきます。
「IMDランキング」は企業の競争力を「WEFランキング」は国の生産性を評価
「IMDランキング」はここまで解説してきたとおり、国際経営開発研究所(IMD)が発行している「IMD World Competitiveness Yearbook (WCY):IMD世界競争力年鑑」のことであり、こちらは主に企業にとって好ましい環境が整っているかどうかを評価するものです。
国際競争力を読み解く指標として、もう一つ参考になるランキングがあります。スイスの非営利の民間団体である世界経済フォーラム(World Economic Forum)が発表する「世界競争力報告(Global Competitiveness Report)」であり、こちらは「WEFランキング」とも呼ばれています。
「WEFランキング」は国の生産力や収益力を指標に順位を決定するものであり、制度やインフラ、教育などの要素を国際競争力と定義づけています。「WEFランキング」の対象国・地域は2013年の時点で148。同年の「IMDランキング」の対象国・地域が60であることからも、同じ国際競争力を扱う調査でも全く別のものであることがわかりますね。
「WEFランキング」と「IMDランキング」とは異なるものであることを把握しておけば、これらの分析結果をより有効に活用することができるでしょう。
「IMDランキング(世界競争力年鑑)」は、各種統計データと経営者層へのアンケート調査の結果から順位を決定
すでに述べましたが、「IMD World Competitiveness Yearbook (WCY):IMD世界競争力年鑑」は20項目・333の基準で競争力をスコア化しており、「経済状況/経済パフォーマンス」「政府の効率性」「ビジネスの効率性」「インフラ」の4つの大項目において評価がなされます。
「IMDランキング」も「WEFランキング」も、さまざまな統計データと経営者層へのアンケート調査の結果から導き出されていますが、アンケートについては主観が入ることもあるため、調査結果を読み解く際には注意が必要です。
4. 日本の国際競争力はなぜ低下してしまったのか? 2つの要因を解説
日本の国際力が低下した要因は「ビジネスの効率性の低下」とアジア新興国の台頭」の2つ
国際競争力を知る指標となる「IMDランキング」と「WEFランキング」について理解が深まったところで、日本の国際競争力の低下がなぜ起きてしまったのかということについても考えておきましょう。
1989年には首位だった日本の国際競争力は、2022年には過去最低の34位と、近年はかなり不本意な結果となっています。国際競争力の指標は時代によって異なるため、日本という国が時代の変化について行けていないというのが現状です。
日本の国際競争力の低下にはさまざまな要因がありますが、「ビジネスの効率性の低下」と「アジア新興国の台頭」が大きな要因として挙げられます。
以下よりひとつずつ見ていきましょう。
理由①「ビジネスの効率性の低下」(内部要因)とは?
日本のビジネスにおいてまだFAXが現役であることは、海外のビジネスパーソンから見るとかなり奇異に映るようです。
日本のDX化は世界的に遅れており、日本はデジタルの面でも国際競争力で後れをとっていると言われていますが、DXに限らず、変化に対応する力がなく、ビジネスの効率性が低下していることが日本の国際競争力を低下させている大きな要因のひとつです。
日本の研究開発費は、アメリカや中国に比べるとかなり少ないものの、それでも世界3位の投資額となっています。実は日本の研究開発力は今も世界的に高い水準であるにもかかわらず、問題は企業の意思決定が遅いことや、管理職に国際経験がないことなど、研究開発の結果を活かしきれていないことにあると言われているのです。
日本独自の閉鎖的な企業風土などが悪影響を及ぼしているとも考えられており、今、大きな意識改革が求められています。
理由②「アジア新興国の台頭」(外部要因)とは?
かつて日本はその高い技術力で圧倒的な国際競争力を誇っていましたが、近年、市場環境は大きく変化しました。日本の製品の品質は今も高く評価されていますが、高品質だからといって必ずしも売れるわけではないのが現代の国際市場の特徴のひとつです。
アジア新興国が台頭し、これまで日本でしか作れなかった製品が大量に生産され、安価で売られるようになった時代においては、作る力よりも売る力が求められるようになりました。低価格でそれなりの品質であれば売れるのであれば、日本の持つ高い技術力は国際市場において力を失います。
解決策としては品質を国際基準に合わせるか、または高い技術力をどう売るか、さまざまな方向性が考えられますが、どの方向性を選択するかがこれからは問われていくでしょう。
5. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
かつてトップクラスを誇っていた日本の国際競争力は1997年を境に大きく順位を下げ、2022年の調査では34位まで落ちてしまいました。
とはいえ、日本の技術力や研究開発力はいまも高いレベルを保っており、問題は古い企業風土など、企業がそれらを活かしきれていないことにあります。
国際競争力を高めていくためには、企業が自ら新陳代謝を高める意識改革を行う必要があるでしょう。
日本の企業が研究開発力を活かしきれていない理由の一つに「管理職に国際経験がないこと」が挙げられます。世界の市場を知らないのに、世界で戦っていくのはかなり無謀なことと言えるのではないでしょうか。
海外進出を考える上では、現地の市場について最新情報を得た上で適切な戦略を練ることはもはや常識となっており、多くの企業が海外事情に詳しい専門家にサポートを依頼しています。
海外進出についてお悩みやお困りごと、各種ご要望などあれば、ぜひ海外ビジネスコンシェルジュによる無料相談サービスをご利用ください。コンシェルジュがご要望をうかがい、御社にぴったりの海外ビジネスの専門家をご紹介いたします。
『Digima〜出島〜』には、厳正な審査を通過した優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。当然、複数の企業の比較検討も可能です。
「海外へ進出したいが何から始めていいのかわからない」「自社商品・サービスが海外現地でニーズがあるかどうか調査したい」「海外進出の戦略立案から拠点設立、販路開拓までサポートしてほしい」「海外ビジネスの事業計画を一緒に立てて欲しい」
ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、御社にピッタリの海外進出サポートサポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。
(参照文献)
・「World Competitiveness Ranking」(IMD)
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
もっと企業を見る