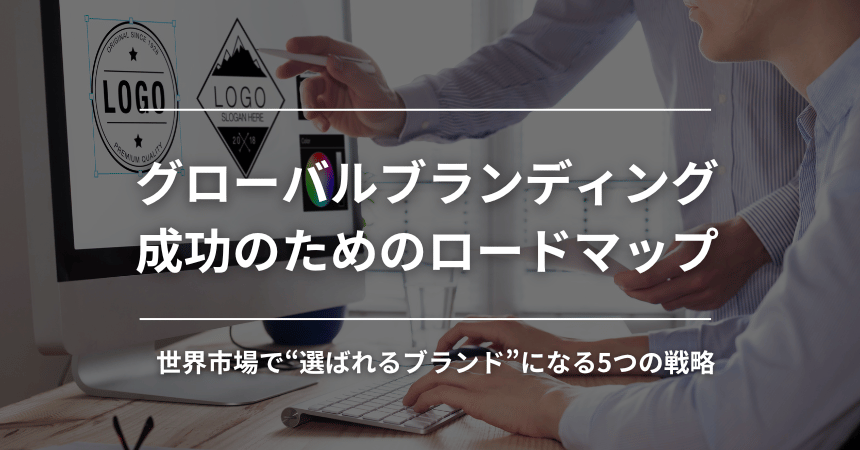越境ECで関税はどう扱われる?トランプ関税でピンチかチャンスか?日本企業が取るべき戦略とは

グローバル市場を視野に入れたビジネス戦略が一般化するなか、越境EC(Cross-border E-Commerce)は、日本企業にとって海外展開の有効な選択肢となりつつあります。特に中小企業やD2Cブランドにとっては、大きな初期投資を伴わずに海外顧客へ直接アプローチできる点で、大きな魅力があります。しかし、越境ECの運用において避けて通れないのが「関税」の問題です。
各国の税制・通関手続きは複雑で、輸出入の都度発生する関税は、単なるコストとしてだけでなく、顧客体験や購買判断に直結する重要なファクターとなります。さらに、2025年4月に米トランプ政権が発表した「相互関税政策」により、日系企業にとって輸出コストの上昇が現実のものとなりつつあり、従来の越境EC戦略の見直しが急務となっています。
本記事では、越境ECにおける関税の基礎から最新の国際動向、特にトランプ関税が与える影響を解説し、日本企業にとって「今がチャンスか、あるいはピンチか」を見極める視点と実践的な対応策をお伝えします。海外市場を取りに行くうえで、確実に押さえておきたい“関税のリアル”を、ぜひご一読ください。
▼ 越境ECで関税はどう扱われる?トランプ関税でピンチかチャンスか?日本企業が取るべき戦略とは
越境ECにおける「関税」とは何か?
関税の基本:誰が・どこで・どんなタイミングで課税される?
関税とは、商品が国境を越えて輸出入される際に、輸入国の税関によって課される税金のことを指します。一般的には、商品の種類(HSコード)と価格、そして原産国によって税率が決まります。越境ECにおいて関税が問題となるのは、多くの場合「誰が払うのか」「いつ発生するのか」が明確でないまま取引が行われるケースが多いためです。
通常、関税は商品の到着時に輸入国側で課税され、受取人(エンドユーザーまたはバイヤー)が負担する仕組みになっています。ただし、販売者側が事前に送料・関税込み価格で商品を提供している場合には、販売者がそのコストを肩代わりしている場合もあります。いずれにしても、関税は“後から請求される”ことが多く、消費者の印象を損ねる原因となりかねません。越境ECを成功させるには、関税の負担がどのタイミングで誰に降りかかるのかを、あらかじめ設計しておくことが不可欠です。
インコタームズとデリバリーモデル(DDPとDAP)の違い
越境取引で関税を誰が負担するかを明確にする際、国際的な物流ルールとして重要なのが「インコタームズ(Incoterms)」です。特に越境ECでは、「DDP(Delivered Duty Paid)」と「DAP(Delivered at Place)」の2つの条件がよく使われます。
DDPは「関税・輸入手数料すべてを販売者が負担し、買い手に商品を届ける」モデルで、消費者にとっては追加費用がかからず安心感がある反面、販売者側のコストや業務負担は増加します。一方、DAPは「関税等の輸入コストは買い手負担」とするもので、販売者側の負担は軽減されるものの、エンドユーザーが商品受取時に予期せぬ請求を受けるリスクがあります。
どちらを採用するかはターゲット市場やビジネスモデルによりますが、いずれの場合も「配送条件を明確に記載し、顧客に誤解を与えないこと」が極めて重要です。
EC事業者が知っておくべき「関税=購買体験に直結するコスト」
関税は単なる“物流上のコスト”ではなく、越境ECにおいては購買体験そのものを左右する要因です。たとえば、商品購入時に表示されていなかった関税が後から加算された場合、顧客満足度は大きく損なわれ、リピーター獲得やブランドの信頼構築に悪影響を及ぼします。
さらに、関税は価格競争力にも直結します。たとえ商品自体が魅力的であっても、通関後に発生する追加料金が高額であれば、消費者は購入を躊躇してしまいます。特に価格に敏感な新興国市場では、関税の扱いが販売成否を分ける重要なファクターになるのです。
そのため、EC事業者は関税を「自社が負担するコスト」か「消費者に見えるコスト」として捉え直し、どちらのアプローチが市場に適しているかを戦略的に設計する必要があります。関税を制することが、越境ECで勝ち抜く鍵のひとつと言えるでしょう。
世界の関税制度と免税ラインの基礎知識
各国で異なる関税・消費税ルール
越境ECに取り組む上で、最大の障壁のひとつとなるのが「国ごとに異なる関税制度や消費税ルール」です。たとえば米国では、800ドル以下の個人輸入に対して関税が免除される「de minimis(デミニマス)」制度があり、ECにおける商品の流通を大きく後押ししています。一方で、EU圏では2021年以降、22ユーロ以下の輸入品に対するVAT(付加価値税)免除が撤廃され、すべての輸入品に対してVATが課されるようになりました。
さらに、ASEAN各国や中東諸国では、関税そのものは低くても、付加価値税や物品税が加算されるケースもあり、最終的な総コストは輸出国側の想定を超えることも少なくありません。これらの制度差を正確に把握せずに販売を行うと、「安いと思ったら高くついた」という顧客の不満を招く結果になりかねません。
BtoCとBtoBで異なる扱い:越境ECと輸出取引の違い
関税制度は、BtoC(一般消費者向け取引)とBtoB(法人間取引)でも大きく異なります。越境ECは主にBtoC取引が中心となるため、申告や納税の簡易化制度が設けられている国もあります。たとえば、EUではIOSS(Import One-Stop Shop)という制度を導入しており、販売事業者がVATを商品代金に含めて徴収・納付することで、スムーズな通関を実現できる仕組みが整えられています。
一方、BtoB取引では、原則として輸入者(現地法人)が税関手続きや関税納付を担うため、仕向国との契約や貿易条件に応じた柔軟な対応が求められます。ECといっても、卸売型やD2B(Direct to Business)型の販売モデルを取る場合には、BtoBとしての扱いになる可能性があるため、分類や契約条件を慎重に検討する必要があります。
関税が“見える化”された今、透明な価格表示が信頼構築の鍵に
各国での規制強化に伴い、「関税や税金を含めた総支払額を事前に明示する」ことが、顧客満足度と信頼の構築において不可欠となっています。とくに欧州・北米市場では、決済前に最終的な支払額が明示されていないとカート離脱率が大幅に上昇するというデータもあり、価格の透明性が競争力を左右する時代に入っています。
そのため、越境ECを展開する企業は、現地通貨での税込み価格表示、関税・送料込み(DDP)の価格設計、関税シュミレーターの設置など、ユーザーにとって分かりやすく安心できる情報提供が求められます。また、物流パートナーや通関代行業者と連携して、正確な課税情報をリアルタイムで取得・反映する体制づくりも重要です。
トランプ政権の「相互関税政策」は越境ECにどう影響するか?
2025年4月の発表内容:一律10%+国別上乗せ関税とは?
2025年4月、米国のトランプ政権が発表した「相互関税政策(Reciprocal Tariffs)」は、多くの越境ビジネスにとって重要な転換点となりました。この政策では、すべての輸入品に対して最低10%の関税を課すとともに、輸出相手国の対米関税水準に応じて、さらに追加課税がなされる仕組みが導入されています。たとえば日本から米国に輸出される商品には、10%の基本関税に加えて14%、計24%の関税が課される見込みです。
この動きは、既存の自由貿易協定やWTOの原則とは対立するものであり、グローバルなサプライチェーンの再構築を促す可能性があります。特に米国市場を主要ターゲットとする越境EC事業者にとっては、価格競争力や利益率への影響が避けられない状況となりつつあります。
中国・ベトナム製品への大打撃と、“日本製”の新たな価値
今回の関税強化は、中国やベトナムなど、これまで製造・供給拠点として多用されていた国々にとって大きな打撃となります。中国製品に対しては最大54%、ベトナム製品には45%の高率関税が課される見通しであり、価格競争力が急激に低下します。この動きを受けて、米国の消費者や企業が「中国以外」「アジア以外」の製品に目を向ける傾向が高まることが予測されます。
ここで再注目されているのが、“Made in Japan”の信頼性です。品質、安全性、デザイン力といった日本製品の持つブランド価値が、多少の価格差を上回る要素として再評価される可能性があります。とくに、食品・美容・生活雑貨などのジャンルでは、日本製であること自体が差別化要因になり得ます。
輸出入ビジネスと越境ECの分水嶺:通関経由の再設計が必要に?
新たな関税体系の導入により、これまでスムーズに運用されていた「低関税・簡易通関」の前提が崩れる場面も出てきています。たとえば、アメリカ向けの小口出荷でも、複数の国から部品を仕入れて組み立てた商品や、複数倉庫経由の商品などは、原産地証明や構成部品の情報提出を求められるケースが増えています。
この変化は、越境ECにとっても例外ではありません。たとえ小規模事業者であっても、通関に関する知識やパートナーとの連携強化が求められるようになります。今後は、「製造地・原材料・物流経路」を戦略的に見直し、必要に応じて配送ルートを変更するなど、越境ECの構造そのものをアップデートしていく必要があります。
越境EC事業者にとってピンチかチャンスか?
関税負担の増加は“価格競争力の低下”を招く
まず否応なく直面するのは、商品価格に対する関税の上乗せによるコスト増です。とくにトランプ政権下の相互関税制度では、日本を含む多くの国に対して20~40%超の高率関税が課せられ、これまで価格優位性を持っていた商品が相対的に割高になるリスクが高まっています。
また、関税負担を消費者に転嫁する場合、購買行動にブレーキがかかる可能性があり、特に価格に敏感な市場ではカート離脱や返品のリスクが増加します。さらに、関税の計算ミスや説明不足がトラブルにつながることもあり、単なるコスト問題ではなく、顧客満足度や信頼構築にも影響を及ぼす問題として捉える必要があります。
日本企業ならではの「品質」「ブランド価値」で戦うチャンス
しかし、全体が“ピンチ”かというと、そうとも言い切れません。むしろ今の局面は、日本企業にとっての差別化チャンスでもあります。なぜなら、関税により価格差が縮まることで、「低価格一辺倒」だった競争から「品質・信頼性重視」の市場へと転換が起こりやすくなるからです。
たとえば、安全基準が高く、丁寧なつくりで知られる日本製の食品、化粧品、生活雑貨などは、関税を含めても十分に選ばれる可能性があります。特に米国や欧州では、サステナブル、エシカル、トレーサビリティといった価値観に対応した商品に関心が高まっており、日本企業がもつ“真面目な製品づくり”は確実に評価されます。
越境EC=ロングテール戦略。ニッチ市場ではむしろ追い風
加えて、越境ECならではの「ロングテール戦略」にも注目です。大量販売・低価格ではなく、「特定の国・人・価値観」に刺さる商品を、適切なチャネルで届けることで、少数でも高単価なビジネスを実現できます。たとえば、特定の食習慣やアレルギー対応、文化的背景に基づく限定商品など、日本ならではの企画力を活かした商品は、価格より“共感”で売れる可能性があります。
その意味で、関税が高くなる状況は、一層「誰に売るか」「どのようにストーリーを伝えるか」が問われるフェーズへ移行したとも言えます。従来の“安く売って量で稼ぐ”モデルから脱却し、「価値を伝えて選ばれる」越境ECへと舵を切るタイミングなのです。
越境ECで関税対応を戦略化するための実務ポイント
DDP(関税込み配送)を使うべきか?それともDAP(関税別)か?
越境ECにおける関税対応を戦略的に考える際、最初に検討すべきは「DDP(Delivered Duty Paid)」と「DAP(Delivered at Place)」のどちらを採用するかという点です。DDPは関税や輸入関連費用をすべて販売者側が負担し、最終価格にそれらを組み込んだうえで商品を提供するモデルです。一方DAPは、関税の負担を購入者に任せ、配送時に関税が請求される方式です。
DDPは顧客体験の向上につながる反面、販売者側には通関手続きや関税予測のコスト・負担がかかります。逆にDAPは運用がシンプルですが、関税に驚いた購入者からの苦情や返品リスクを高める要素にもなります。どちらを選ぶかは、販売する国の慣習、取り扱う商品の価格帯、ユーザー層の関税理解度などを踏まえて検討することが必要です。
プラットフォーム・物流パートナーとの連携が鍵
越境ECの現場では、自社だけで関税管理や通関手続きを行うのは困難なケースが多く、現地の物流パートナーや販売プラットフォームとの連携が欠かせません。たとえばShopifyやWooCommerceなどのECプラットフォームでは、関税・消費税を購入時に計算・表示するプラグインが活用できますし、DHLやFedExといった国際物流企業では、関税の見積もりやDDP配送の代行サービスも提供されています。
また、通関業務の知識をもつ代行業者や越境EC支援企業と連携することで、各国での規制対応やラベル表示のミスを未然に防ぐことができます。価格だけでなく「手間」も大きなコストになる越境ビジネスでは、信頼できるパートナー選びが成果の鍵を握ります。
国別関税シミュレーションと価格設計の見直し
販売国ごとに異なる関税・消費税を事前に把握し、想定される最終価格を反映した価格設計を行うことが、クレームや返品の削減に大きく寄与します。商品ごとのHSコードに基づいて、国別の関税率を調査し、販売価格を設定することで、販売者・購入者双方の不満を未然に防ぐことができます。
また、場合によっては、関税が軽減されるよう原材料やパッケージ構成を変更したり、第三国経由で物流を最適化するケースもあります。これらの対応は一朝一夕には難しいですが、「価格を下げる」のではなく「価格を納得してもらう」ための仕組み作りとして、今後ますます重要になる分野です。
まとめ|越境ECの成功は“関税リスク”の先読みから
越境ECの拡大にともない、関税は単なるコスト要因ではなく、顧客体験や利益構造に直結する重要な戦略要素となっています。特に2025年のトランプ政権による相互関税政策のような不確実性の高い国際情勢では、「何がいつどこで課税されるか」を先回りして把握し、価格設計や配送設計に組み込むことが、成功する越境ECに求められる基本姿勢です。
「関税リスク」を的確に捉え、現地ユーザーにストレスなく商品を届けるためには、正しい制度理解と、物流・通関の信頼できるパートナーとの連携が不可欠です。逆にいえば、これらを丁寧に整えた企業は、価格以外の“価値”で選ばれる強いブランドになれるでしょう。
越境ECは、グローバルなチャンスに満ちた市場です。だからこそ、制度と顧客心理の両方に目を配り、「買いやすさ」と「信頼」を両立させることが、次なる成長のカギとなります。
なお、「Digima~出島~」には、優良な越境ECの専門家が多数登録されています。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談