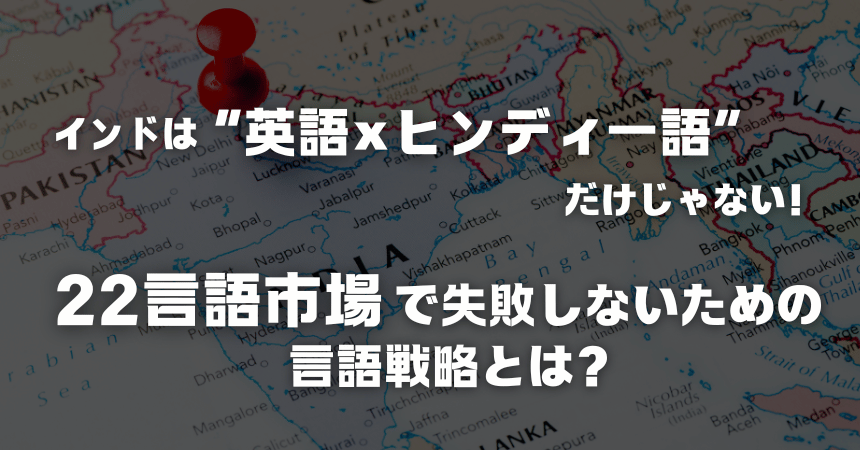インドのBIS認証とは?対象製品・申請手順・日本企業が知るべきポイントを解説|インド標準規格局(BIS)制度ガイド

近年、急速な経済成長を続けるインド市場は、日本企業にとっても魅力的な輸出先・進出先として注目されています。しかし、その市場に製品を投入するには、インド独自の品質・安全規格への対応が避けて通れません。その中でも重要な制度の一つが、BIS認証(Bureau of Indian Standards)です。
BIS認証は、インド標準規格局によって運用されている製品規格制度であり、電気・電子機器、化学品、鉄鋼製品など幅広い製品カテゴリーにおいて、インド国内での製造・輸入・販売を行うための“事前条件”とされています。BIS認証がなければ輸入通関ができず、市場へのアクセス自体が閉ざされる可能性もあるため、制度への正確な理解と的確な対応が求められます。
本記事では、BIS制度の概要から認証の対象となる製品範囲、取得手続き、実務対応時の注意点、そして日本企業が制度対応を進めるうえでの戦略的アドバイスまでを、体系的かつ実務に即したかたちで解説します。インド市場での事業展開を検討するすべての企業にとって、信頼ある製品流通の第一歩として、是非ご活用ください。
▼ インドのBIS認証とは?対象製品・申請手順・日本企業が知るべきポイントを解説|インド標準規格局(BIS)制度ガイド
BISとは何か?インド標準規格局の役割と制度の背景
BIS(Bureau of Indian Standards)とは?制度の概要
BIS(Bureau of Indian Standards/インド標準規格局)は、インドにおける国家規格の制定および製品の品質・安全性を保証する認証制度を管轄する公的機関です。1947年に設立されたISI(Indian Standards Institution)を前身とし、1986年にBIS法に基づく組織として改編されました。その後、2016年には現行のBIS法が施行され、規制範囲の拡大と制度の強化が図られています。
BISの認証制度は、インド国内で流通する製品が一定の品質基準と安全性を満たしているかどうかを審査・証明するものです。電気製品や建材、化学品など、インド政府が「特定の製品にはBIS認証を義務付ける」と指定したカテゴリに属する製品は、輸入・販売・製造に際して必ずBISの認証マーク(ISIマークまたはCRSマーク)を取得する必要があります。この制度により、消費者保護と国内産業の健全な発展が促進されています。
BISの目的と制度の歴史:品質・安全・消費者保護の観点から
BIS制度が目指す最も基本的な目的は、インド国内に流通する製品の品質と安全性を確保し、消費者の利益を守ることです。とくにインドでは、経済成長とともに輸入製品の流通量が増加しており、それに伴って粗悪品や模倣品による事故や健康被害への懸念も高まっていました。こうした背景のなかで、国家基準に基づいた認証制度の必要性が強まり、BIS法の整備・強化が進められてきました。
制度の歴史をたどると、当初は自主的な認証制度として運用されていたBISも、2010年代以降は対象製品の義務化が進み、特に電気・電子機器分野ではCRS(Compulsory Registration Scheme)による強制認証制度が導入されています。また、ISO規格との整合も意識されるようになり、国際基準への準拠が進められている点も特徴です。BIS認証はインド市場の“入場券”であると同時に、製品の信頼性を証明する「品質の証」として広く認知されています。
なぜBIS認証が必要なのか?法令・貿易制度との関係性
BIS認証が求められるのは、単なる業界自主基準ではなく、インド政府によって法律で義務化されているからです。現在、特定製品の輸入・製造・販売にあたっては、事前にBIS認証を取得していなければ、通関で差し止められる可能性が高く、販売行為自体が違法とみなされるリスクもあります。この点は、日本企業が考える「任意の認証」や「国際規格への準拠」とは大きく異なり、BISが法的拘束力を持つ制度であることを理解しておく必要があります。
また、WTOのTBT協定(技術的貿易障害の防止)との整合性を取りつつも、インドは自国の安全・健康・環境を守る目的で、一定の輸入規制や認証制度を設けることが可能とされています。結果として、BIS認証はインドに製品を輸出する際の「非関税障壁」の一つとなり得ますが、それをクリアすることで市場参入の扉が開かれるという側面もあります。インド政府が推進する「Make in India」政策とのバランスを取りながら、日本企業は制度理解と柔軟な対応が求められます。
BIS認証の対象製品と規制の範囲
認証義務のある製品カテゴリ(強制対象品目)
BIS認証には、対象製品が「強制認証制度」の下にあるかどうかという明確な区分があります。現在、BIS認証が法的に義務付けられている製品は、インド政府が通達・告示によって定めており、その範囲は年々拡大しています。2024年時点での代表的な強制認証対象には、電気・電子機器、化学品、建材、鉄鋼製品、ガラス製品、食品包装材などが含まれています。
とくに注目されているのが、電気・電子機器に対するCRS(Compulsory Registration Scheme)です。これはスマートフォン、ノートパソコン、テレビ、電源アダプター、LED照明など、消費者向け製品に幅広く適用されており、BISに登録された工場で製造されたものでなければインドでの流通は認められません。また、近年では医療機器や玩具なども対象に加えられるなど、規制強化の流れが継続しています。対象か否かを判断するには、BISの公式ウェブサイトやインド政府の公報を確認する必要があります。
電気・電子機器、鉄鋼、化学品など業界別の動向
業界別に見ると、BIS認証の必要性は各分野で異なるアプローチを取っています。電気・電子分野では、前述のCRS制度に基づく規制が中心であり、PSE認証やCEマークなどに慣れている日本企業にとっても、それとは異なる独自要件への対応が求められます。例えば製造工場の登録義務や、インド国内へのサンプル提出、日本国内での試験結果が無効とされるケースなど、細かな規制差異に注意が必要です。
一方、鉄鋼製品や化学品においても、インドは自国産業の保護と消費者の安全確保の観点から、BIS認証を義務付ける動きを強めています。とくに鉄筋や鋼管などの建材分野では、一定の規格に適合していなければ建築用途に使用できず、輸入が禁じられる可能性もあります。化学品においては、危険物や農薬原料などのカテゴリにおいて、新たにBIS認証が導入されるケースもあり、今後も対象拡大の可能性は高いと言えるでしょう。
BIS認証が求められる場面:輸入・販売・製造時の注意点
BIS認証の義務は、「いつ」「誰に」適用されるのかという点でも注意が必要です。認証が必要となるのは、製品をインド国内で輸入・製造・販売するいずれの局面でも適用されるため、日本国内で製品を製造してインドに輸出する企業であっても、責任の所在からは逃れられません。つまり、インド市場に製品を投入する限り、製造元または輸入者のいずれかがBIS認証を取得している必要があります。
また、認証を取得した後も、認証マークの表示、製造拠点の維持管理、年次更新、仕様変更時の再申請など、運用面での継続的な対応が求められます。これらを怠ると、たとえ過去に認証を取得していたとしても、通関で差し止めを受けるリスクがあります。とくに、OEMや委託製造などの形態で複数の関係者が関わる場合は、誰が責任を持つのかを明確にし、契約上の役割分担を整理しておくことが重要です。
BIS認証の取得手順と必要書類
BIS認証取得の基本的な流れ:申請〜発行までのステップ
BIS認証を取得するためには、インド標準規格局が定める手順に従って申請を進める必要があります。認証の形式には、ISIマーク認証(主に工業製品)とCRS認証(主に電子機器)がありますが、基本的な流れは共通しています。まず最初に、自社製品がBISの強制認証対象に該当するかを確認し、該当する場合は申請準備に入ります。
申請手続きは、BISのオンラインポータルを通じて行われます。必要事項を入力し、試験機関による製品テストを依頼したうえで、その結果とともに申請書類一式を提出します。特にISIマーク認証の場合には、インドにおける工場審査(Factory Audit)が含まれるため、現地での準備と調整が不可欠です。CRS認証では工場審査は省略されますが、その分試験報告書や技術文書の正確性が重視されます。
申請が受理された後、審査結果をもとにBISが認証の可否を判断し、承認された場合はBIS登録証明書が発行されます。この証明書があれば、該当製品にBISマークを付けてインド市場に出荷できるようになります。
必要な書類・申請情報の具体例と準備のポイント
BIS認証を申請する際には、多数の書類と詳細な製品情報の提出が求められます。たとえば、製品仕様書、図面、材質構成表、安全試験結果、使用部品のリスト、製造工程表、品質管理体制の概要などがその一部です。これに加えて、申請者の会社登記書類、製造者の拠点情報、工場の組織図や責任体制に関する説明も求められるケースがあります。
電子機器などCRS認証が適用される製品では、BISが認可するインド国内の試験所でのテスト報告書が必須となります。つまり、日本国内の試験成績書だけでは認められず、試料をインドに送り、所定の試験を実施する手続きが必要になります。この点は、日本の電気用品安全法(PSE)などと大きく異なる点であり、事前に試験所の予約や通関準備を進めておくことが重要です。
書類提出時の形式や記載ミスも不備とみなされることがあるため、専門知識のあるコンサルタントや現地パートナーの協力を得て、申請全体を正確に管理することが望まれます。
認証取得にかかる期間とコストの目安とは?
BIS認証の取得にかかる期間は、製品カテゴリや認証タイプ、申請書類の正確さ、試験の進捗状況などによって異なりますが、一般的にはCRS認証で2〜3か月、ISI認証で4〜6か月以上が一つの目安とされています。特にISIマーク認証では、工場審査の調整や書類のやり取りに時間を要することが多く、スケジュールには余裕を持って対応することが重要です。
コスト面では、試験費用・申請手数料・代理人手数料・通関費用・翻訳対応費などが発生します。申請の難易度や製品の特性によって幅はありますが、総額で数十万円から100万円超に及ぶケースもあります。また、現地代理人との契約費用や、長期的な維持管理にかかる費用も考慮する必要があります。
加えて、BIS認証は「一度取得して終わり」ではなく、有効期間内の年次更新や製品仕様変更時の再申請など、継続的な費用と対応が発生します。そのため、単なるコストと捉えるのではなく、インド市場への本格的な参入に向けた“事業インフラへの投資”と捉え、計画的に準備を進めることが望まれます。
BIS取得時に注意すべき実務ポイント
工場審査(Factory Inspection)の重要性と対策
BIS認証のうち、ISIマーク認証ではインド標準規格局(BIS)による工場審査が義務づけられている点に注意が必要です。これは、申請された製品がBISの定める規格に適合するかどうかを確認するだけでなく、製造拠点が一定の品質管理体制を有しているかを評価するプロセスです。審査はBISの担当官が日本や第三国の工場を実際に訪問して実施されるため、言語・スケジュール調整・現場対応などを含めた十分な事前準備が必要です。
審査では、製造工程・試験設備・原材料の保管状況・品質記録・トレーサビリティの体制など、ISOの仕組みに近い視点でチェックが行われます。ただしBIS特有の項目や記載様式があるため、過去にISO認証を取得している企業であっても、追加の対応が求められることがあります。審査の不備や準備不足による申請却下を避けるためにも、BIS対応に実績のある専門家のアドバイスを受けながら進めることが安全です。
現地代理人の選定と役割:インドに拠点がない企業の対応
インドに現地法人や拠点を持たない日本企業がBIS認証を取得する場合、BISに対する連絡窓口となる「現地代理人(Authorized Indian Representative)」の選定が必須となります。この代理人は、製品申請時から認証後の維持管理、更新申請、緊急時の当局対応まで、多岐にわたる役割を担う存在です。形式的な名義人というよりは、実質的な申請代理業務を遂行する信頼できるパートナーとして位置付けるべきでしょう。
代理人はインド国内に法人格を持ち、BISに登録された製品の品質に責任を負う立場にあるため、選定を誤ると、申請の遅延やトラブル、更新手続きの不備といったリスクにつながります。代理人選定の際には、過去のBIS対応実績、業界知識、契約条件、費用体系などを慎重に比較検討し、可能であれば日系企業の実績紹介やJETRO等のネットワークを活用するのも有効です。信頼関係のある代理人を確保することが、スムーズな認証取得と将来的な運用安定化のカギとなります。
申請不備・規格改定・更新漏れなどで起こり得るトラブルと回避法
BIS認証の運用では、認証取得後にも多くの管理対応が求められます。まず注意すべきは、BISの規格は随時見直される可能性があり、製品が従来の基準を満たしていても、新基準への適合を求められることがあります。規格の改定が発表された場合、一定期間内に再試験・追加書類の提出が求められるため、インド側の情報を定期的にチェックする仕組みを社内に設ける必要があります。
また、認証の有効期間が満了する前には、更新手続きを行う必要があります。うっかり更新期限を逃してしまうと、再申請が必要となり、製品の輸入や販売が一時的に停止される事態に陥ることもあります。これを防ぐためには、認証番号ごとに期限・責任者・提出スケジュールを明確に管理することが欠かせません。
さらに、初期申請時の書類不備や記載ミスも多くのトラブル原因となっています。審査官による指摘事項があいまいなまま放置されるケースもあるため、言語・制度への理解が不十分なまま自己判断で進めるのではなく、専門の支援機関や実務経験者と連携して対応することで、こうしたリスクを最小限に抑えることができます。
日本企業がBIS対応する際の戦略と実践アドバイス
自社製品が対象かどうかを見極める判断プロセス
インドへの輸出を検討するにあたり、まず最初に行うべきは、自社の製品がBIS認証の「強制対象品目」に該当するかどうかの確認です。BIS認証の対象品目は、インド政府が随時告示によって追加・変更しており、その一覧はBISの公式サイトや関連省庁の通達にて確認できます。日本語の情報が限られているため、英語による原文確認や専門機関からの情報取得が実務上有効です。
製品の型式、構成部品、使用目的によっては、同じカテゴリでも認証が必要なケースと不要なケースに分かれることがあります。そのため、自社製品の仕様を詳細に分析し、対象製品リストの中での該当性を慎重に評価する必要があります。また、販売方法(B2BかB2Cか)、最終使用者、現地での製造有無といった流通形態によっても、認証の有無が左右されることがあります。不明な点がある場合は、早い段階でインドの認証支援機関や日系コンサルタントに照会し、明確な判断基準を持つことが、安全な対応につながります。
BIS取得済みの競合他社や認証支援サービスの活用方法
制度対応を進めるうえで有効なのが、すでにBIS認証を取得している他社の事例を参考にすることです。とくに同業他社や類似製品の認証実績がある場合、どのような申請書類を用意し、どの試験所を利用したのか、どの代理人を選んだのかといった情報は、初めて取り組む企業にとって大きなヒントとなります。BISの認証製品データベースでは、過去に登録された製品の情報も検索できるため、自社製品に近い事例の確認をおすすめします。
また、BIS認証の取得には制度理解だけでなく、英語での申請書類作成や現地手続きの調整など、専門的な知識と実務対応が求められます。そのため、申請を外部に委託する企業も増えており、特に初めてインドに製品を出荷する企業にとっては、認証支援サービスを活用することで申請エラーや手戻りを防ぐことができます。日本語での対応が可能な業者も存在するため、コストと信頼性を見極めたうえで、戦略的に外部パートナーを活用することが成功の近道です。
第三者機関との連携で進める制度対応のすすめ
BIS認証のような海外制度に対応する際、日本国内で得られる支援を最大限に活用することも重要です。商工会議所や業界団体の中には、会員向けにBIS制度やインド輸出関連のセミナー・個別相談を実施している団体もあります。こうした機関を通じて、制度の全体像を把握し、法令解釈や申請実務に関する情報を収集することは、社内でのリスク管理やプロジェクト推進にも大きく寄与します。
もちろん、本サービス「Digima~出島~」にも、優良なインドビジネスの専門家が多数登録されています。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
一企業で対応しきれない情報の壁や制度の複雑さを、外部リソースの力を借りて越えていく姿勢が、制度対応を“負担”ではなく“競争優位”につなげる鍵となるのです。
まとめ:インド市場参入に不可欠な“信頼の証明”としてのBIS
BIS認証は、単なる製品検査や形式的な許可を意味するものではなく、インド市場で製品を展開するうえでの「信頼の証明」と言える制度です。製品の品質・安全性を国家基準に基づいて証明することで、インド政府のみならず、現地の流通業者や最終消費者からの信頼を得る基盤となります。とくに電気・電子機器や建材、化学品といった分野では、BIS認証を取得していない限り、そもそもインド市場にアクセスすることができない構造になっており、事業継続の前提条件ともなっています。
本記事では、BIS制度の概要から対象製品、申請手順、注意点、そして日本企業が対応する際の実務ポイントまでを幅広くご紹介しました。制度対応には一定のコストやリードタイムを要するものの、それは将来のインド市場での安定的なビジネス展開を見据えた戦略的投資とも位置づけられます。
今後、インド政府による規制の拡大や制度変更の可能性もある中で、企業としては「後手」ではなく「先手」の姿勢で制度に対応し、市場の信頼を確保する体制を整えていくことが重要です。BIS認証は、インド市場での競争力を高めるための出発点にほかならず、それを的確に活用することで、日本企業のプレゼンスはより確かなものとなるでしょう。
本記事が、インド進出を検討される日本企業の皆様にとって、実務の一助となれば幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
オススメの海外進出サポート企業
-
YCP
グローバル22拠点✕800名体制で、現地に根付いたメンバーによる伴走型ハンズオン支援
<概要>
・アジアを中心とする世界21拠点、コンサルタント800名体制を有する、日系独立系では最大級のコンサルティングファーム(東証上場)
<サービス特長>
・現地に根付いたローカルメンバーと日本人メンバーが協働した伴走型ハンズオン支援、顧客ニーズに応じた柔軟な現地対応が可能
・マッキンゼー/ボストンコンサルティンググループ/ゴールドマンサックス/P&G/Google出身者が、グローバルノウハウを提供
・コンサルティング事業と併行して、当社グループで展開する自社事業群(パーソナルケア/飲食業/ヘルスケア/卸売/教育など)の海外展開実績に基づく、実践的なアドバイスを提供
<支援スコープ>
・調査/戦略から、現地パートナー発掘、現地拠点/オペレーション構築、M&A、海外営業/顧客獲得、現地事業マネジメントまで、一気通貫で支援
・グローバル企業から中堅/中小/スタートアップ企業まで、企業規模を問わずに多様な海外進出ニーズに応じたソリューションを提供
・B2B領域(商社/卸売/製造/自動車/物流/化学/建設/テクノロジー)、B2C領域(小売/パーソナルケア/ヘルスケア/食品/店舗サービス/エンターテイメントなど)で、3,000件以上の豊富なプロジェクト実績を有する
<主要サービスメニュー>
① 初期投資を抑えつつ、海外取引拡大を通した円安メリットの最大化を目的とする、デジタルマーケティングを活用した海外潜在顧客発掘、および、海外販路開拓支援
② 現地市場で不足する機能を補完し、海外事業の立ち上げ&立て直しを伴走型で支援するプロフェッショナル人材派遣
③ アジア圏での「デジタル」ビジネス事業機会の抽出&評価、戦略構築から事業立ち上げまでの海外事業デジタルトランスフォーメーションに係るトータルサポート
④ 市場環境変動に即した手触り感あるインサイトを抽出する海外市場調査&参入戦略構築
⑤ アジア特有の中小案件M&A案件発掘から交渉/実行/PMIまでをカバーする海外M&A一気通貫支援
⑥ 既存サプライチェーン体制の分析/評価/最適化、および、直接材&間接材の調達コスト削減 -
株式会社ダズ・インターナショナル
東南アジア・東アジア・欧米進出の伴走&現地メンバーでの支援が強み
私たちは企業の海外挑戦を設計→実行→着地まで伴走支援いたします。
これまでの企業支援数は1,500以上です。
私たちは『どの国が最適か?』から始まる海外進出のゼロ→イチから、
海外進出後のマーケティング課題も現地にて一貫支援いたします。
※支援主要各国現地にメンバーを配置し、海外進出後も支援できる体制
------------------------------------
■サポート対象国(グループ別)
↳アジア①(タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・インドネシア・フィリピン・ラオス)
↳アジア②(日本・香港・シンガポール・台湾・韓国)
↳アジア③(ドバイ・サウジアラビア・インドバングラデシュ・モンゴル・ミャンマー)
↳欧米(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)
※サポート内容により、対応の可否や得意・不得意な分野はあります。
------------------------------------
■対応施策ラインナップ
①"市場把握"サポート
目的は"海外現地を理解し、事業の成功可能性を上げる"こと。
(以下、含まれる施策)
↳市場概況・規制調査
↳競合調査
↳企業信用調査
↳現地視察企画・アテンド
②"集客活動"サポート
目的は"海外現地で売れるためのマーケティング活動を確立"すること。
↳多言語サイト制作
↳EC運用
↳SNS運用
↳広告運用(Google/Metaなど)
↳インフルエンサー施策
↳画像・動画コンテンツ制作
③"販路構築"サポート
目的は"海外現地で最適な海外パートナーとの取引を創出"すること。
↳商談向け資料制作
↳企業リストアップ
↳アポイント取得
↳商談創出・交渉サポート
↳契約サポート
④"体制構築"サポート
目的は"海外現地で活動するために必要な土台"をつくること。
↳会社設立(登記・銀行口座)
↳ビザ申請サポート
↳不動産探索(オフィス・倉庫・店舗・住居)
↳店舗開業パッケージ(許認可・内装・採用・集客)
↳人材採用支援(現地スタッフ採用支援)
------------------------------------ -
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。
実績:
東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)
東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)
南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)
北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)
中東(トルコ、サウジアラビア等)
ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)
アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等) -
株式会社東京コンサルティングファーム
【26ヵ国39拠点】各国日本人駐在員が現地にてサポートいたします。
弊社は、会計事務所を母体とした26ヵ国39拠点に展開するグローバルコンサルティングファームです。
2007年に日本の会計事務所として初めてインドに進出し、翌年ASEAN一帯、中南米等にも進出しました。歴が長く、実績・ノウハウも豊富にございます。
海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など国際ビジネスをトータルにサポートしています。
当社のサービスは、“ワンストップ”での サービスを提供できる環境を各国で整えており、特に会計・税務・法務・労務・人事の専門家を各国で有し、お客様のお困りごとに寄り添ったサービスを提供いたします。
<主要サービス>
・海外進出支援
進出相談から登記等の各種代行、進出後の継続サポートも行っています。月額8万円~の進出支援(GEO)もご用意しています。また、撤退時のサポートも行っています。
・クロスボーダーM&A(海外M&A)
海外企業の買収・売却による進出・撤退を支援しています。
・国際税務、監査、労務等
各国の税務・会計、監査や労務まで進出時に必要な業務を幅広く行っています。
・現地企業マッチングサポート
海外販路拡大、提携先のリストアップ、代理店のリストアップ、合弁パートナー探し等を行うことができます。TCGは現地に拠点・駐在員がいるため現地企業とのコネクションがあり、スピーディーに提携先のリストアップなどを行うことができます。 -
株式会社コンパスポイント
Amazonを使った日本企業の海外進出をサポートします。
弊社コンパスポイントでは、越境EC、各国Amazon特有のノウハウに加え、
貿易に関する知識と数多くの企業様への支援実績に基づいて
Amazonを中心とした国内外EC全般のサポートとコンサルティングを提供させて頂いております。
また、中小機構開のEC・IT活用支援パートナー、及び販路開拓支援アドバイザー、
JICAマッチング相談窓口コンサルタント、
複数の銀行の専門家として企業様のご支援をさせて頂いており、
また、中小機構、銀行、地方自治体、出島 等が主催する各種セミナーでの登壇も行っております。
日本Amazonはもちろん、北米、欧州、インド、オーストラリア、サウジ、UAE、
トルコ、シンガポールAmazonなどへの進出サポートを行っており、
中小企業から大手まで、またAmazonに出品可能なあらゆる商品に対応致します。
企業様が海外Amazonへ進出される際にハードルとなる、
Amazon販売アカウントの開設、翻訳、商品画像・動画撮影、商品登録、国際配送、
多言語カスタマーサポート、国際送金サポート、PL保険、Amazon内広告を含む集客、
テクニカルサポート、アカウント運用代行、著作権・FDA・税務対応・GDPR対応サポート、
市場調査、コンサルティング、SNSマーケティング、メディアバイイング、現地スタッフの手配
等について、弊社パートナーと共に対応させて頂きます。
また、国内Amazonの場合、並行して楽天、ヤフー、自社サイト、SNS、メディアサイト、広告なども含めたデジタルマーケティングのトータルサポートも実施しております。