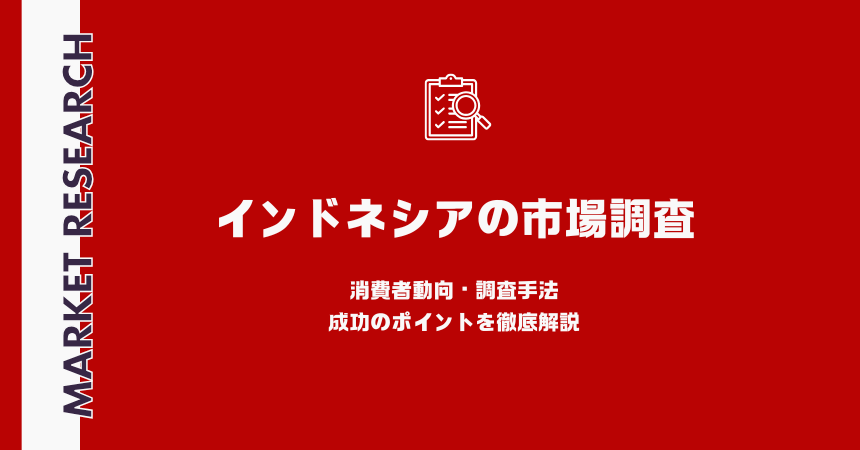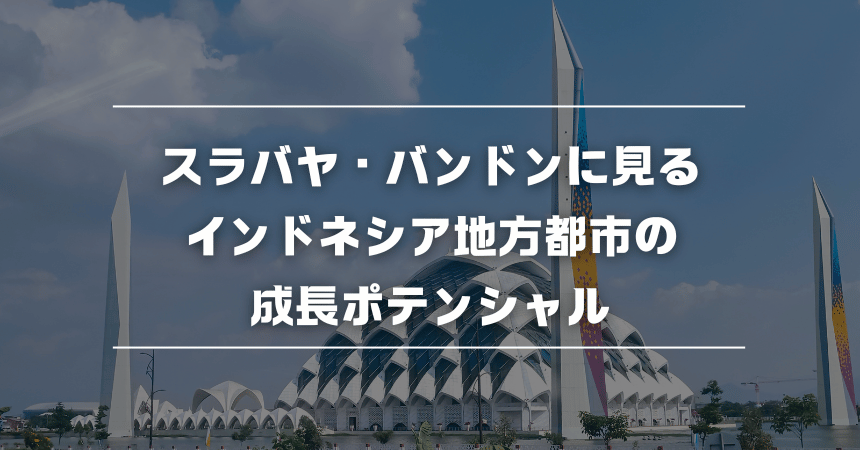インドネシア製造業レポート|主要産業・進出日系企業・トランプ相互関税の影響を解説

ASEAN最大の人口を誇るインドネシアは、消費市場としての潜在力だけでなく、生産拠点としても注目度が高まっている国の一つです。近年では、自動車や電子機器、食品などの製造業を中心に外資の進出が加速しており、なかでも日系企業は早くからインドネシア市場への参入を進めてきました。
特に2025年4月に発表されたトランプ政権による新たな相互関税政策では、ASEAN各国から米国への輸出が高関税の対象となり、サプライチェーンの再構築が世界的に進んでいます。こうした動きの中で、日本企業はインドネシアの製造拠点としてのポジションを改めて見直す必要に迫られています。
本記事では、インドネシア製造業の概況や注目セクター、進出日系企業の動向から、他ASEAN諸国との比較、そして新関税政策の影響までを網羅的に解説します。現地の課題や成功のヒントも含め、インドネシアでの製造拠点確保・拡大を検討する企業に向けた実務的な情報をお届けします。是非、参考にしてください。
▼ インドネシア製造業レポート|主要産業・進出日系企業・トランプ相互関税の影響を解説
インドネシア製造業の概況と注目される理由
人口2.7億人の巨大市場と労働力供給
インドネシアはASEAN最大の人口を有する国であり、2024年時点で2億7,000万人を超える市場規模を誇ります。さらに、その約半数を若年層が占める点は、長期的な労働力供給の安定性と消費成長の両面において、大きなポテンシャルを秘めています。実際に近年では、インドネシア国内での中間層の増加が進み、自動車や家電製品、加工食品といった消費財の内需が年々拡大しています。
加えて、製造業の現場を担う熟練労働者の育成も進められており、低コストかつ一定の技能レベルを持つ人材を確保できる環境が整ってきました。ジャカルタ首都圏では最低賃金の上昇が見られるものの、地方工業団地においては依然としてベトナムやタイよりも人件費が抑えられるエリアも存在します。製造業にとって、インドネシアは「市場」としての魅力と「供給地」としての機能を兼ね備えた、バランスの取れた進出先といえるでしょう。
政府の製造業振興策(産業マスタープラン、工業団地整備など)
インドネシア政府は、製造業を国家成長の柱と位置付け、長期的な産業振興戦略を打ち出しています。その中核となっているのが「インドネシア産業4.0(Making Indonesia 4.0)」構想であり、食品・繊維・電子機器・自動車などの主要分野を重点的に高度化・デジタル化する政策が推進されています。これにより、生産性向上だけでなく、外資企業の誘致や産業集積の形成にも力を入れているのが特徴です。
また、政府主導での工業団地整備も活発に行われており、ジャワ島を中心に東西へと広がる形で数多くの工業団地が整備・拡張されています。特にチカンペック、カラワン、バンテン州などは日本企業の進出が多い地域で、インフラの整備状況やサポート体制も相対的に整っています。こうした政策面の後押しは、製造業の立地選定において非常に重要な要素となっており、インドネシアの投資環境整備は今後も注目されるポイントです。
近年の外資誘致政策と日系企業への期待
インドネシア政府は近年、外資誘致に一層積極的な姿勢を示しています。従来は一部産業で厳格だった外資規制も緩和され、2021年に施行された「雇用創出オムニバス法」により、外国企業が進出しやすい制度環境が整備されつつあります。これにより、製造業を含む幅広い業種で外資比率の制限が撤廃または緩和され、外資系企業にとっての参入障壁が大幅に低下しました。
また、税制優遇措置の強化も見逃せない要素です。特定業種・地域での投資に対して法人税の減免が認められるほか、新たな機械導入や技術移転を伴うプロジェクトには追加的な減税インセンティブが与えられる場合もあります。こうした措置は、日本を含む先進国の企業にとって、投資判断の後押しとなっています。
主な製造業セクターと市場規模
自動車・二輪車関連:ASEAN随一の生産・販売規模
インドネシアの自動車産業は、ASEAN域内でもトップクラスの規模を誇っています。2023年の四輪車生産台数は140万台を超え、その多くが国内市場で消費されるとともに、一部は東南アジア各国や中東への輸出にも回っています。さらに二輪車においては、年間生産・販売台数ともに世界上位に位置し、ホンダ、ヤマハといった日系メーカーが圧倒的なシェアを維持しています。
こうした背景には、人口の増加と所得水準の上昇に伴うモータリゼーションの進展があり、中間層の拡大が着実に需要を押し上げてきました。また、インドネシア政府はEV(電気自動車)分野への投資を積極的に誘致しており、日系・韓国系の大手自動車メーカーによる電池工場やEV生産拠点の整備も進められています。今後は「内需×輸出×EV移行」という3つの成長軸が、自動車セクター全体の市場拡大をけん引していくと見られています。
食品・飲料加工、日用品:旺盛な内需と輸出ポテンシャル
食品・飲料・日用品といった生活消費財の製造分野も、インドネシアでは極めて重要な位置を占めています。中間層の増加と都市化の進行により、パッケージ食品、清涼飲料、スキンケア製品などの消費量は年々拡大しており、国内企業だけでなく日系・欧米系の大手メーカーも積極的に現地生産を展開しています。
例えば、味の素やライオン、花王といった日本企業は、現地ニーズに合わせた製品開発や販売戦略を行い、広くブランドを浸透させています。また、インドネシア政府はハラール認証制度の整備を進めており、イスラム市場への輸出拠点としての役割にも注目が集まっています。食品安全基準の強化や物流インフラの改善も進んでおり、今後は「製造+輸出」型の展開がより一般化していくことが予想されます。
電子機器・化学品・繊維などの注目分野
近年、インドネシアでは自動車・食品以外の製造分野においても多様な成長が見られます。電子機器では、国内のIT機器需要拡大に加えて、東南アジア域内への部品供給や組立拠点としての役割が高まっており、スマートフォン関連部品やテレビ、冷蔵庫といった家電製造の誘致も進められています。台湾・韓国企業による投資の活発化に加え、日本の部品・素材メーカーも拠点拡大を検討する動きが広がっています。
また、石油化学や日用品原料を含む化学品分野では、豊富な天然資源を活かした国内生産体制が構築されつつあります。タイやマレーシアと並ぶ化学コンビナートの形成が注目される中、インドネシアは低コスト・安定供給の利点を生かし、原料から加工品までの一貫供給体制の構築が期待されています。
繊維分野では、縫製や染色加工などの中間工程が活発であり、特に日本や韓国、欧州向けの輸出用生産地として注目を集めています。環境対応型工場の増加やエシカル生産への転換も進んでおり、サステナブル志向の強い企業にとっては魅力的な生産パートナーとなりつつあります。
インドネシアに進出している主要日系企業
トヨタ・ホンダ・ヤマハなど自動車関連の大手
インドネシアにおける日系企業の進出は、自動車産業がその先陣を切ってきました。トヨタ自動車は現地法人である「トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・インドネシア(TMMIN)」を通じて、エンジンや車両の現地生産を行っており、既に50年以上にわたる事業実績を有しています。ホンダやスズキ、ダイハツも現地での製造・販売体制を構築しており、二輪分野ではヤマハが広く普及しています。
これらの企業は単に完成車を輸出するだけでなく、現地調達率の向上や部品サプライヤーとの連携強化を進めており、裾野産業の形成にも大きく貢献しています。政府が推進する電動化政策に呼応し、EV向けバッテリー製造やハイブリッド車の現地組立計画なども本格化しつつあります。こうした取組みにより、日系自動車メーカーは今後もインドネシア市場での競争優位性を維持・強化していく見通しです。
花王・味の素・ライオンなど消費財メーカー
日系の消費財メーカーもまた、インドネシアにおいて長年にわたりブランドを築いてきた存在です。花王は1990年代から現地での製品製造・販売を展開し、洗剤やスキンケア商品が家庭向け市場に広く浸透しています。味の素は調味料や冷凍食品を軸に事業展開しており、家庭用から業務用まで幅広いニーズに応える製品群を展開。現地の食文化に合わせた商品開発にも力を入れています。
また、ライオンは歯みがき・石けん・シャンプーなどの製造拠点を持ち、インドネシア全土に販売網を張り巡らせています。これらの企業に共通するのは、現地生産によるコスト競争力の確保とともに、マーケティングや物流を含む一貫したオペレーション体制の構築です。単なる輸出ビジネスから、インドネシアを中核とする現地完結型のビジネスモデルへとシフトし、収益基盤を強固にしています。
地場企業との合弁・現地化の事例も紹介
日系企業の中には、単独進出ではなく、地場企業との合弁を通じて事業展開を進めるケースも少なくありません。たとえば、自動車部品や電機関連分野では、現地企業と技術提携を行いながら現地生産と販売を行うスタイルが一般化しています。これは、現地のビジネス慣行や規制環境に柔軟に対応するための戦略的な選択といえます。
また、近年では販売・マーケティング領域でも現地パートナーとの連携が進んでおり、ローカルな消費者ニーズに適応するための重要な足がかりとなっています。インドネシアでは宗教や文化に配慮した商品設計が求められることも多く、現地人材の意見を反映させた製品・サービス開発が成功の鍵を握ります。現地化とパートナーシップのバランスをどう取るかは、日系企業の進出戦略において今後ますます重要な論点となるでしょう。
他ASEAN諸国との比較にみるインドネシアの位置付け
タイ、ベトナム、マレーシアとの製造コスト比較
ASEAN諸国の中で製造業の集積地として注目されるタイ、ベトナム、マレーシアと比較した場合、インドネシアは人件費・土地代ともに一定のコスト競争力を保っている一方で、都市圏と地方との格差も大きく、その選定には注意が必要です。例えば、ジャカルタ周辺は近年の最低賃金引き上げにより、ベトナムのハノイやホーチミンと同程度かやや高めの水準に近づいていますが、ジャワ島東部などの地方都市では、依然としてコストメリットが維持されています。
一方で、マレーシアはインフラの整備や英語人材の確保に優れている反面、全体的に人件費は高め。タイは日系企業の進出数が多く、部材調達やサプライヤー網の成熟度が高いものの、同様に賃金・土地代は上昇基調にあります。ベトナムは製造業誘致の最有力国として台頭していますが、用地不足や労働需給の逼迫も課題になり始めています。これらと比べ、インドネシアは今後の産業集積とインフラ拡張余地が大きく、中長期的な成長を重視する企業には魅力的な選択肢となり得ます。
労働市場、インフラ、政情の安定性から見る魅力とリスク
インドネシアの労働市場は、量的にはASEAN最大級の規模を誇り、人口構成の若さからも長期的な供給安定が期待されます。実際、多くの産業において地元の労働力を確保することが可能であり、日本のような高齢化リスクとは対照的な構造を持っています。ただし、職種によっては技能不足や定着率の課題が指摘されており、現地での教育・訓練が必要となる場合もあります。
また、インフラ面では近年の改善が著しく、ジャカルタと周辺都市をつなぐ高速道路や工業団地へのアクセス道路、港湾施設の近代化が進んでいます。ただし、雨季の洪水対策や地方都市の電力供給体制など、まだ課題の残る地域も少なくありません。政情については、民主主義体制の下で比較的安定した政治運営が続いており、外資企業にとってリスクの少ない市場としての安心感も一定の評価を得ています。
インドネシア拠点をどう活用するかの視点
インドネシアを製造拠点として活用する上では、「コストだけで選ぶ」時代はすでに終わりつつあり、「市場としての成長力」と「中長期的な供給安定性」を重視した戦略が求められています。すでに成熟したタイ、インフラ優位のマレーシア、コスト重視のベトナムと比較し、インドネシアは“拠点と市場のバランスが取れた存在”といえるでしょう。
特に中間層の拡大が著しい現在のインドネシアでは、製造した製品を国内で消費する「地産地消」型のビジネスモデルが機能しやすく、マーケティングやブランド戦略と組み合わせた展開が有効です。また、東ジャワやスラウェシなど、今後注目される新興工業地域を視野に入れた拠点分散も、企業の成長戦略において重要な判断材料になるでしょう。インドネシアでの成功には、単なる生産拠点という位置づけにとどまらず、「長期的な事業基盤」としての捉え方が鍵となります。
トランプ政権の相互関税政策がもたらすインパクト
インドネシアから米国への輸出品が32%関税対象に
2025年4月にトランプ政権が発表した「相互関税政策」は、世界中のサプライチェーンに多大な影響を与え始めています。インドネシアも例外ではなく、同国から米国への輸出品に対して、基礎関税10%に加え、インドネシアに対する追加関税22%が上乗せされ、合計で32%の関税が適用される見通しとなっています。
この関税は、完成品だけでなく中間財や部品にも広く適用される可能性があり、繊維製品や電子部品、家具など、米国向け輸出比率の高い業種にとってはコスト構造を根本から見直す必要に迫られる事態です。とりわけ、インドネシアに生産拠点を持つ日系企業にとっては、関税増により価格競争力が大幅に損なわれ、現地生産品の米国輸出にブレーキがかかることは避けられません。
日本企業のサプライチェーン戦略への影響
これまで、インドネシアを含むASEAN諸国は「チャイナ+1」戦略の受け皿として注目されてきました。実際、米中貿易摩擦を受けて中国からインドネシアに生産を移す動きが加速していましたが、今回の関税措置により、インドネシア経由での米国向け輸出にも高い関税が課されることで、その選択肢にも再考を迫られています。
特に自動車部品、電子デバイス、アパレルなど、インドネシアから米国に輸出されている品目の中には、現地調達と輸出を組み合わせてサプライチェーンを構築している日本企業も多く存在します。そのため、今回の相互関税措置は、単なる販売価格の問題にとどまらず、部材調達先や最終組立地の見直し、ひいてはサプライチェーン全体の再設計を求められる転換点となっています。
ASEAN各国における再評価とポジショニング見直しの動き
米国による相互関税政策の導入は、ASEAN全体に波及効果を及ぼしています。たとえば、ベトナムは対米関税45%、タイは36%と、インドネシアよりもさらに高い水準で課税される予定であり、ASEAN全体としては「代替生産拠点」の役割を見直さざるを得ない状況です。中国からの移転先として期待されていたASEAN諸国が、今度は関税リスクを抱える地域へと変貌しつつあるのです。
こうした中で、インドネシアは32%という比較的中間的な関税水準に位置づけられており、米国市場以外の輸出拠点としての役割に再び注目が集まっています。特にアジア・中東・アフリカ市場に対する地理的優位性やFTA(自由貿易協定)の活用可能性を視野に入れた再ポジショニングが、日本企業の中でも検討され始めています。つまり、インドネシアは“米国以外”への供給網の要として、今後新たな役割を担う可能性があるということです。
インドネシア製造業における課題と乗り越え方
法制度の複雑さ、通関・物流の課題
インドネシアにおける製造業の展開では、現地の法制度や通関手続きの複雑さが大きな課題として挙げられます。特に、各省庁間での手続きの重複、法律改正の頻度、また地方自治体ごとの運用の違いなどが、外資企業にとって事業スピードや透明性を損なう要因になっています。また、税制やライセンス取得の運用が地域差や担当官の裁量によって左右されるケースもあり、進出初期には信頼できる現地パートナーやコンサルタントの支援が不可欠です。
物流面では、インフラ整備が進んでいるとはいえ、依然として港湾の混雑や通関遅延、地方への輸送にかかる時間とコストが事業運営の障害となる場合があります。とくに工業団地外での物流拠点を持つ企業にとっては、こうした遅延やコスト増がサプライチェーン全体の効率性に影響を及ぼすこともあります。そのため、立地選定の段階で物流網へのアクセスや港湾との距離、通関経験のある人材の確保といった要素を入念に検討する必要があります。
労働慣行と現地マネジメントの難しさ
インドネシアの労働市場は豊富な人材供給力を有していますが、その一方で、現地の労働文化やマネジメントスタイルの違いに起因する問題も散見されます。たとえば、集団意識や上下関係を重視する文化背景から、現場の自主性が育ちにくい傾向があり、日本式の改善活動や現場主導の問題解決には時間を要することがあります。また、労働組合の影響力が比較的強く、労使交渉やストライキへの対応など、企業側には慎重な姿勢と信頼構築が求められます。
マネジメント面では、日本本社との意思疎通や指示系統の構築に課題があることも多く、現地の幹部人材の育成と権限移譲が進まない場合には、組織運営に大きなボトルネックとなります。このため、日系企業においては初期段階から中間管理職層の研修やローカライズ対応に力を入れることが、現地拠点の自立性と持続的な成長に繋がっていきます。
日本企業の成功事例にみる解決アプローチ
こうした課題を乗り越え、インドネシアで安定した事業展開を実現している日系企業は少なくありません。たとえば、ある自動車部品メーカーでは、現地での技能訓練施設を独自に設け、人材育成を通じて品質管理と生産性向上を図っています。また、食品メーカーでは、現地市場の嗜好や宗教的価値観に対応した商品開発と販売チャネルの構築を行うことで、高いブランド定着率を実現しています。
さらに、物流や制度面での課題に対しては、工業団地内に拠点を設けることでインフラアクセスと行政対応の円滑化を図る企業もあります。加えて、現地スタッフとの定期的な対話の機会を設け、職場内の信頼関係を醸成することで、定着率の向上やリスク管理に繋げているケースもあります。このように、課題を前提とした対応策の積み重ねが、インドネシアでの持続的成長を支える鍵となります。
まとめ|インドネシア製造業は“現地完結型”でこそ活きる
インドネシアは、ASEAN最大の人口規模と豊富な労働力、成長する内需市場を背景に、製造業にとって依然として高いポテンシャルを持つ国です。自動車、食品、日用品など、広範な業種で日系企業が既に拠点を構えており、現地での生産から販売、さらには第三国への輸出まで、幅広い展開が進んでいます。
一方で、制度の不透明さや物流インフラの課題、労務管理の難しさなど、進出・運営における注意点も少なくありません。特に、2025年の米国・トランプ政権による相互関税政策の影響により、インドネシアから米国市場への輸出に制限がかかる中で、今後は“米国依存型”の戦略から、“アジア・中東・アフリカ”といった他市場への多角化が重要になるでしょう。
そうした環境変化の中、インドネシアで成功している日系企業の多くは、単なる生産拠点としての活用にとどまらず、「現地完結型」の事業体制を構築しています。つまり、現地ニーズに合わせた製品開発、地場人材の育成、信頼されるブランド構築などを組み合わせて、長期的な経営基盤を築いているのです。
インドネシアでの製造業展開を検討する際には、目先のコストや税制だけでなく、現地社会との接点づくりや、地域全体の成長にどう貢献できるかという視点も欠かせません。グローバルサプライチェーンの再編が進む中で、日本企業にとってインドネシアは、単なる“安価な生産地”ではなく、“アジア戦略の中核を担うパートナー”としての可能性を持つ市場といえるでしょう。
インドネシア政府は特に日系企業への信頼を厚く持っており、自動車・電子機器・化学などの分野では、すでに多数の日本企業が安定操業を続けている実績があります。ジャカルタ日本人商工会議所(JJC)との連携を通じた政策対話も行われており、日系企業にとっては「既に信頼と経験のある市場」として、今後の事業展開の拠点候補となりうるでしょう。
なお、当社では工場・パートナー開拓はもちろん、市場調査、EC出品や代理店開拓などの販路開拓、プロモーション代行、求人代行など、インドネシア進出をワンストップでサポートしております。是非、お気軽にご相談ください。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
オススメの海外進出サポート企業
-
YCP
グローバル22拠点✕800名体制で、現地に根付いたメンバーによる伴走型ハンズオン支援
<概要>
・アジアを中心とする世界21拠点、コンサルタント800名体制を有する、日系独立系では最大級のコンサルティングファーム(東証上場)
<サービス特長>
・現地に根付いたローカルメンバーと日本人メンバーが協働した伴走型ハンズオン支援、顧客ニーズに応じた柔軟な現地対応が可能
・マッキンゼー/ボストンコンサルティンググループ/ゴールドマンサックス/P&G/Google出身者が、グローバルノウハウを提供
・コンサルティング事業と併行して、当社グループで展開する自社事業群(パーソナルケア/飲食業/ヘルスケア/卸売/教育など)の海外展開実績に基づく、実践的なアドバイスを提供
<支援スコープ>
・調査/戦略から、現地パートナー発掘、現地拠点/オペレーション構築、M&A、海外営業/顧客獲得、現地事業マネジメントまで、一気通貫で支援
・グローバル企業から中堅/中小/スタートアップ企業まで、企業規模を問わずに多様な海外進出ニーズに応じたソリューションを提供
・B2B領域(商社/卸売/製造/自動車/物流/化学/建設/テクノロジー)、B2C領域(小売/パーソナルケア/ヘルスケア/食品/店舗サービス/エンターテイメントなど)で、3,000件以上の豊富なプロジェクト実績を有する
<主要サービスメニュー>
① 初期投資を抑えつつ、海外取引拡大を通した円安メリットの最大化を目的とする、デジタルマーケティングを活用した海外潜在顧客発掘、および、海外販路開拓支援
② 現地市場で不足する機能を補完し、海外事業の立ち上げ&立て直しを伴走型で支援するプロフェッショナル人材派遣
③ アジア圏での「デジタル」ビジネス事業機会の抽出&評価、戦略構築から事業立ち上げまでの海外事業デジタルトランスフォーメーションに係るトータルサポート
④ 市場環境変動に即した手触り感あるインサイトを抽出する海外市場調査&参入戦略構築
⑤ アジア特有の中小案件M&A案件発掘から交渉/実行/PMIまでをカバーする海外M&A一気通貫支援
⑥ 既存サプライチェーン体制の分析/評価/最適化、および、直接材&間接材の調達コスト削減 -
株式会社ダズ・インターナショナル
東南アジア・東アジア・欧米進出の伴走&現地メンバーでの支援が強み
私たちは企業の海外挑戦を設計→実行→着地まで伴走支援いたします。
これまでの企業支援数は1,500以上です。
私たちは『どの国が最適か?』から始まる海外進出のゼロ→イチから、
海外進出後のマーケティング課題も現地にて一貫支援いたします。
※支援主要各国現地にメンバーを配置し、海外進出後も支援できる体制
------------------------------------
■サポート対象国(グループ別)
↳アジア①(タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・インドネシア・フィリピン・ラオス)
↳アジア②(日本・香港・シンガポール・台湾・韓国)
↳アジア③(ドバイ・サウジアラビア・インドバングラデシュ・モンゴル・ミャンマー)
↳欧米(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)
※サポート内容により、対応の可否や得意・不得意な分野はあります。
------------------------------------
■対応施策ラインナップ
①"市場把握"サポート
目的は"海外現地を理解し、事業の成功可能性を上げる"こと。
(以下、含まれる施策)
↳市場概況・規制調査
↳競合調査
↳企業信用調査
↳現地視察企画・アテンド
②"集客活動"サポート
目的は"海外現地で売れるためのマーケティング活動を確立"すること。
↳多言語サイト制作
↳EC運用
↳SNS運用
↳広告運用(Google/Metaなど)
↳インフルエンサー施策
↳画像・動画コンテンツ制作
③"販路構築"サポート
目的は"海外現地で最適な海外パートナーとの取引を創出"すること。
↳商談向け資料制作
↳企業リストアップ
↳アポイント取得
↳商談創出・交渉サポート
↳契約サポート
④"体制構築"サポート
目的は"海外現地で活動するために必要な土台"をつくること。
↳会社設立(登記・銀行口座)
↳ビザ申請サポート
↳不動産探索(オフィス・倉庫・店舗・住居)
↳店舗開業パッケージ(許認可・内装・採用・集客)
↳人材採用支援(現地スタッフ採用支援)
------------------------------------ -
合同会社サウスポイント
世界と日本をつなぐ架け橋「沖縄」から海外展開を支援しています
2017年7月日本・沖縄と海外の万国津梁の架け橋を目指して、企業の海外展開支援を目的として沖縄・那覇で設立。アジア・欧州を中心に沖縄県内・沖縄県外企業の海外進出・国際展開のサポートを実施しています。2022年7月には観光産業の伸びの著しい石垣市に八重山事務所を開設しております。
沖縄をハブに、台湾・中国・香港・ベトナム・タイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・オーストラリア・ニュージーランド・イギリス・ドイツ・ブラジル各国にパートナーエージェントを配置し、アメリカ合衆国・インドは提携先を設けていますので、現地でも情報収集、視察等も直接支援可能、幅広く皆様の海外展開とインバウンド事業をサポートしております。 -
ワールド・モード・ホールディングス株式会社
国内外1,500社以上の実績!ファッション・ビューティー業界特化の支援
私たちワールド・モード・ホールディングスは、日本で唯一のファッション・ビューティー業界に特化したソリューション・グループです。
業界に精通したプロフェッショナルが集結し、従来の枠を超えたトータルサポートを実現。戦略企画、マーケティング、プロモーション、店舗運営、人材採用・育成など、多角的な視点から実践的なソリューションを提供しています。
近年では、カフェ・飲食、小売以外の業態や海外市場にも対応領域を拡大。エリア・業種を問わず、クライアントの課題に寄り添った柔軟な支援を行っています。
今後も、「顧客に寄り添い、目標を共有するパートナー」として、そして「ワンストップで価値を届けるプロフェッショナル集団」として、進化を続けてまいります。
<グループ会社>
株式会社iDA、株式会社AIAD、株式会社フォー・アンビション、株式会社BRUSH、VISUAL MERCHANDISING STUDIO株式会社、株式会社AIAD LAB、株式会社 双葉通信社、WORLD MODE ASIA PACIFIC -
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。
実績:
東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)
東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)
南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)
北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)
中東(トルコ、サウジアラビア等)
ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)
アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等)