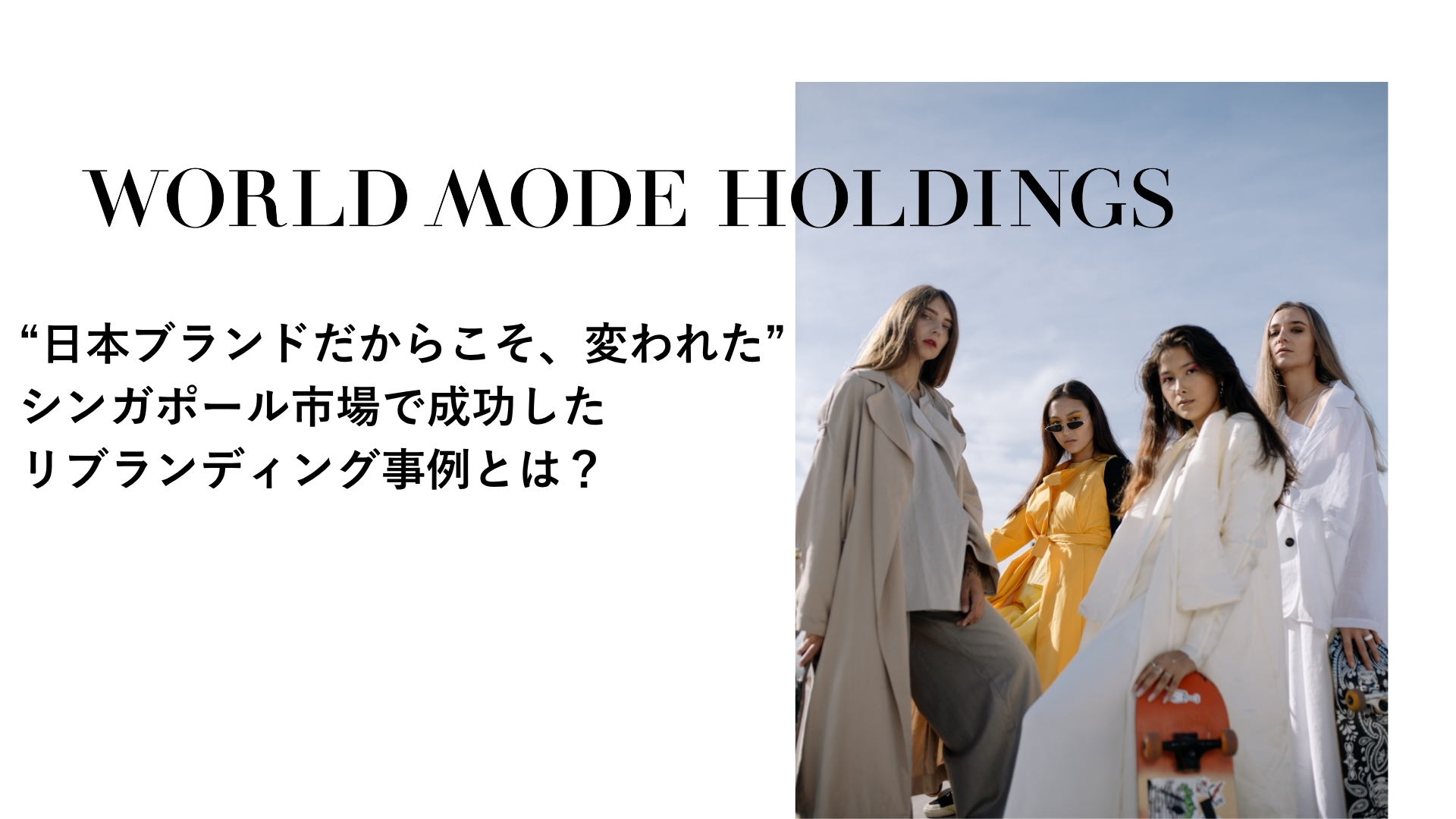トランプ政権“相互関税”の今こそ狙う、シンガポール市場の再定義|成功のカギは“戦略の立て方”にある

いま、海外展開の前提が大きく揺らぎ始めています。2025年4月、米国トランプ政権が打ち出した「相互関税政策」により、日本やASEAN各国からの輸出品に対して高関税が課されることが発表されました。日本企業にとっては、対米ビジネスの収益性が大きく損なわれるリスクが高まり、サプライチェーンの見直しや販路の再構築が急務となっています。
こうした中で注目されているのが、ASEANの中心に位置するシンガポールです。相互関税を受けてブロック経済へと移行していきそうな現在の世界情勢を踏まえ、シンガポールの“ハブとしての役割”は増していく可能性があります。ただ、高い経済的自由度と、外資に開かれた制度環境により、すでに数多くの日本企業が進出を果たしている“成熟市場”ですが、その一方で、「後発参入の難しさ」や「コストの高さ」に苦戦する声も少なくありません。「日本ブランド」だけで勝てる時代は終わり、今や“戦略”の有無が成功を分ける局面に入っています。
しかし、だからこそ、適切なタイミングで的確な戦略を立てられれば、シンガポール市場にはまだ大きなチャンスが眠っています。本記事では、米国の新たな通商政策とグローバル環境の変化をふまえたうえで、Traverse Asiaの視点から見た“これからのシンガポール進出”の考え方と、現地で成果を出すための実践的なヒントをご紹介していきます。是非、参考にしてください。
▼ トランプ政権“相互関税”の今こそ狙う、シンガポール市場の再定義|成功のカギは“戦略の立て方”にある
米国の相互関税政策が変える、日本企業の進出戦略
米国の「相互関税」政策とは何か?
2025年4月、トランプ大統領による新たな通商政策「相互関税政策」が正式に発表されました。この政策では、すべての輸入品に対して最低10%の関税を課すことに加え、各国の対米関税・非関税障壁の水準に応じて追加関税を上乗せするという、非常に強硬な保護主義的措置が採られています。日本に対しては、24%という高水準の関税が設定されており、さらに自動車など一部品目には25%の追加関税も課される予定です。これにより、実質的な関税負担が一気に数倍に跳ね上がることとなり、対米輸出を前提とした日本企業の多くが、ビジネスモデルの見直しを迫られています。
輸出依存からの転換が求められる時代へ
これまで多くの日本企業は、米国市場を収益の柱としてきました。特に自動車や電子部品、産業機械などの分野では、米国向け輸出に大きく依存する構造が長く続いてきたのが実情です。しかし今回の相互関税政策により、輸出コストは著しく上昇し、競争力の低下は避けられません。加えて、為替や地政学的リスクも複雑化する中で、もはや「一国依存」は大きな経営リスクとなっています。こうした状況を受け、今、サプライチェーンの多極化と市場ポートフォリオの見直しが、企業経営における喫緊の課題となっているのです。
東南アジアへの注目と、その中のシンガポール
こうしたグローバルな環境変化の中で、東南アジアは新たな製造・販売拠点として再評価されています。特にベトナムやタイ、インドネシアといった国々は、低コストの生産拠点として近年多くの企業が進出を進めてきました。ただし、今回の相互関税ではこれらASEAN主要国にも高率の関税が適用されるため、「中国の代替地」という従来の戦略だけでは限界があることも明らかになっています。こうした中で、比較的関税負担が軽微であり、国際的な取引やサービスビジネスの拠点として優位性を持つ国、それがシンガポールです。単なる“逃げ道”ではなく、次なる戦略的拠点として、シンガポールをどう活用するかが問われるフェーズに入っています。つまり、相互関税を受けてブロック経済へと移行していきそうな現在の世界情勢を踏まえ、シンガポールの“ハブとしての役割”は増していく可能性があるということです。
シンガポール市場の現状と“見落とされがちな本質”
外資を歓迎する“オープン市場”という顔
シンガポールは、ASEANの中でも特にビジネス環境の整備が進んだ国として知られています。法人設立の容易さや税制の透明性、英語が共通語として通用する社会環境など、外資にとって参入しやすい要素が揃っています。実際、世界銀行の「ビジネスのしやすさランキング」でも常に上位に位置づけられており、日本企業にとっても心理的なハードルが低い市場の一つです。日系飲食店や商社、製造業の地域統括会社なども多く、すでに一定のプレゼンスを築いています。こうした背景から、「まずはシンガポールに」という動きは今なお根強く残っています。
“入りやすい”がゆえに見落とされる本質的な難しさ
しかし、シンガポール市場の本質は「外資に開かれている」ことだけでは語れません。むしろ、その開かれた環境ゆえに、世界中から企業がひしめく“超競争市場”となっているのが現実です。消費者やバイヤーの目も非常に肥えており、「日本から来た」「品質が良い」といった理由だけで受け入れられることは、もはや期待できません。たとえユニークな商品やサービスであっても、現地ニーズとのずれや価格設定の甘さがあれば、瞬く間に淘汰されてしまいます。
また、参入コストも高く、飲食業などでは家賃や人件費が他のASEAN諸国の数倍になることも珍しくありません。戦略が不十分なまま「日本でうまくいったから」と安易に進出すると、費用だけがかさみ、成果が得られないまま撤退に追い込まれるケースも見受けられます。つまり、シンガポールは「簡単に入れるが、簡単には成功できない市場」であることを、まず認識する必要があるのです。
日本ブランドの限界と、問われる“中身”の勝負
かつては「日本製」「日本発」というだけで一定の信頼を得られた時代がありました。実際、今でも“ジャパンブランド”はシンガポールで一定の価値を持っています。しかし、その価値は年々“希釈”されており、ただの看板やイメージだけでは差別化にならなくなっています。今のシンガポール市場では、消費者が商品の本質やストーリー、価格と品質のバランスを厳しく評価しています。日本ブランドが通用しないわけではありませんが、それは「中身が伴っていること」が前提です。
つまり、「どう見せるか」ではなく「何を届けるか」「なぜそれがシンガポール市場に必要なのか」といった、より本質的な問いに応えられる戦略設計が不可欠です。その意味で、シンガポール市場は“ブランド先行型”ではなく“戦略実行型”の市場だといえるでしょう。
シンガポール進出のよくある失敗パターン
「日本で成功したから」という思い込みによる横展開
日本で実績のある商品やサービスを、そのままの形でシンガポールに持ち込む――このアプローチは、多くの企業が陥る落とし穴のひとつです。確かにシンガポールは、法制度やインフラが整っており、ロジックだけで見るとビジネスをスムーズに始められる印象があります。しかし、現地市場のニーズや文化、競合環境は日本とは大きく異なります。例えば、味覚やパッケージデザインの感覚、広告やSNSの使い方ひとつとっても、現地の消費者の感性に合わなければ選ばれることはありません。
この「現地化」の視点を持たず、成功体験の焼き直しで展開してしまうと、初期の期待に反して反応が乏しく、マーケティングコストだけが膨らむ結果となるのです。シンガポール進出を検討する際には、まず「日本モデルのどこが活かせて、どこが通用しないのか」を冷静に見極めることが重要です。
現地パートナー任せによる“戦略不在”の展開
もうひとつ典型的な失敗パターンが、シンガポール現地の代理店や取引先に事業展開を“丸投げ”してしまうケースです。たしかに、現地のビジネス慣習やネットワークに精通したパートナーとの連携は、進出初期には非常に有効です。しかし、全体の戦略設計を自社で描かず、「とりあえず現地に任せてみよう」としてしまうと、ブランドの方向性がぶれたり、結果の責任の所在が曖昧になったりするリスクが生じます。
加えて、現地パートナーは複数ブランドを扱っていたり、日系企業の価値を完全に理解しきれていない場合もあるため、自社の商品やサービスの「本来の強み」が伝わらず、期待した成果に結びつかないこともあります。シンガポールで成功している企業の多くは、現地パートナーと連携しつつも、戦略の軸を自社でしっかりと持っているという共通点があります。
試行錯誤にかかる“コストの高さ”を軽視する
ASEAN各国と比べて、シンガポールは圧倒的に事業コストが高い国です。たとえば、飲食業の場合、都心部で店舗を借りれば月額数十万円から百万円単位の賃料がかかり、人件費も東南アジア随一の水準にあります。加えて、マーケティング活動も単価が高く、ひとつのプロモーションに対して求められる精度も高いため、いわゆる「トライ&エラー」が許されにくい環境です。
そのため、明確な戦略なしで試行錯誤を繰り返すと、短期間で予算が尽きてしまい、撤退を余儀なくされるケースもあります。こうしたコスト構造を正しく理解し、「限られた予算で最大限の成果を上げるにはどうすべきか」を事前に検討することが不可欠です。特に中小企業にとっては、初期の一手を誤ることが致命的な結果につながりかねません。
それでも、Traverse Asiaがシンガポールでチャンスを感じる理由
小さな市場だからこそ、トレンドが一気に広がる土壌がある
シンガポールの人口はおよそ600万人。市場規模としては決して大きくはありません。しかし、ここには東南アジア全域や世界のビジネスリーダーが集まり、トレンドの発信力が極めて強い特徴があります。つまり、シンガポールでヒットすれば、そこからASEAN諸国、さらには中華圏に波及する可能性があるのです。
その中で特に注目すべきなのが、「ヘルス」「サステナブル」「日本的な丁寧さ」といった価値観が浸透しつつある点です。たとえば、健康志向の高まりのなかで、日本の抹茶商品やグルテンフリーフードがトレンドとして広がりを見せています。このような“新しい生活様式”にフィットする商材であれば、きちんとしたアプローチを通じて認知を得ることは十分に可能です。市場が成熟しているからこそ、商品力と戦略がかみ合えば、短期間でも成果を上げられるポテンシャルを秘めています。
実例:ゼロから始めて2年で4,000個を販売したToC商品
Traverse Asiaでは、シンガポールの消費者に向けたToC(対個人)ビジネスにも積極的に取り組んでいます。たとえば、ある日本発のウェルネス系商材を用いたプロジェクトでは、立ち上げ当初は認知ゼロという状態からのスタートでした。しかし、現地消費者の関心や嗜好に合わせてブランド設計を行い、SNS広告やイベント販促を組み合わせて丁寧に認知を拡大。その結果、わずか2年で累計4,000個以上を販売するまでに成長しました。
この事例からも分かるように、たとえリソースが限られていたとしても、現地市場のニーズを読み取り、それに合わせて設計・実行された戦略は確かな成果につながります。重要なのは、“当てずっぽう”のプロモーションではなく、現地の生活者や企業目線に立ったアプローチを取ることです。Traverse Asiaはこうした仮説検証型の進出スタイルを通じて、数々の成果を積み重ねてきました。
「チャンスはある」──ただし、戦略が前提条件
競争が激しい、参入コストが高い、日本ブランドだけでは通用しない──これらはすべて事実です。しかしその一方で、これらのハードルを冷静に見据えたうえで、適切な準備を重ねた企業には確実に“入り込む余地”があります。むしろ、多くの企業が安易に挑んで失敗しているからこそ、「本気で考えている企業」が光る市場なのです。
Traverse Asiaでは、シンガポール市場に精通した現地チームと連携し、進出戦略の立案からマーケティング設計、実行支援まで一貫してサポートしています。成功には偶然ではなく、明確な根拠と計画が求められる──その原則が通用するのが、シンガポールという市場です。「ここに勝機がある」と確信しているからこそ、私たちはシンガポール進出を希望する日本企業に対して、慎重かつ前向きなチャレンジを推奨しています。
成功の鍵は、“戦略の立て方”にある
自社の強み・弱みを改めて見直す「ゼロベースの市場理解」
シンガポール進出を検討する際、多くの企業が最初に見落としがちなのが、「そもそも自社の何が現地で通用するのか」を掘り下げていないという点です。日本国内での強みが、必ずしも現地市場でも価値を持つとは限りません。一方で、自社が気づいていなかった“当たり前”が、シンガポールでは差別化要素になることもあります。したがって、進出に際してはまず、自社の商品やサービスを現地の目線で評価し直し、「どこに勝機があるのか」「どこを補完する必要があるのか」をゼロベースで整理することが出発点となります。
このプロセスを経て初めて、現地との接点が明確になり、ブランディングや価格設定、コミュニケーション設計の方向性が見えてくるのです。Traverse Asiaでは、こうした“自己理解と市場理解の接点”を明らかにするための市場リサーチや競合分析、仮説構築といった戦略立案支援を重視しています。
商品設計・価格・チャネル選定まで一貫した設計が不可欠
シンガポール市場で成功を収めるためには、単に「売る場所」を探すだけでは不十分です。商品パッケージ、使用シーン、価格帯、プロモーション手法など、すべてが市場に適合している必要があります。たとえば、日本ではシンプルで洗練されたデザインが好まれる商品であっても、シンガポールでは“機能を明確に伝える”パッケージでなければ消費者に響かないといった文化的な違いが存在します。
また、販売チャネルの選定も重要です。シンガポールではEC化が進んでいるとはいえ、体験型イベントやリアル店舗での“接触”が購買に強く影響する傾向があります。高価格帯の商品であれば、ターゲット層が集まる百貨店やポップアップイベントを通じて“ブランド体験”を促すことも有効です。このように、商品そのものから販路までを一貫して設計し、細部に至るまで現地ニーズに最適化することが、成功への近道といえるでしょう。
Traverse Asiaが提供する“戦略から実行まで”の伴走支援
Traverse Asiaは、単なる調査や進出支援にとどまらず、戦略立案から販売・展開までを一貫して支援できることを強みとしています。たとえば、現地消費者のインサイトをもとにした商品パッケージの調整、テスト販売の実施、SNS運用やインフルエンサーマーケティングの導入まで、実務レベルでの実行支援を行うことで、戦略が“絵に描いた餅”で終わらないようサポートしています。
さらに、進出後も販売データや顧客の声をもとにしたPDCAを回すことで、継続的に戦略のアップデートを図ります。進出直後の“反応の差”を冷静に受け止め、改善しながら着実に浸透を図っていく──それが、Traverse Asiaの考える“現実的な成功”の形です。戦略は描くだけではなく、「どう実現するか」まで設計されて初めて意味を持つ。だからこそ、私たちは常に“実行の現場”とともに動いています。
まとめ|“なんとなく進出”はもう終わり。今こそシンガポールに再定義を
シンガポールは、日本企業にとって最も参入しやすいASEAN市場のひとつです。しかし、それは同時に「競争が激しく、見極めなしでは成果が出にくい市場」であることも意味しています。かつてのように、“日本ブランド”の看板だけで売れる時代はすでに終わりを迎えており、いま求められているのは、明確な戦略と現地最適化された実行力です。
さらに、米国による相互関税政策の影響で、グローバルに製販体制を見直す動きが加速する今、シンガポールは単なるマーケット以上に、東南アジア全体のゲートウェイとしての重要性を高めています。だからこそ、今このタイミングで“なぜシンガポールに進出するのか”“どう勝ち筋をつくるのか”を徹底的に考えることが、将来の成果を分けることになります。
Traverse Asiaでは、こうした問いに向き合う企業とともに、戦略構築から現地での実行、拡販までを一気通貫で支援しています。安易な進出ではなく、「本気の戦略」でシンガポール市場に挑む企業にこそ、次の成長のチャンスが開かれると私たちは信じています。
なお、私たちが最も注力しているのは、市場の構造と生活者の価値観を踏まえた“戦略の立て方”そのものです。誰に、何を、どう届けるのか。その設計次第で、海外展開の成果は大きく変わります。ご関心のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
オススメの海外進出サポート企業
-
YCP
グローバル22拠点✕800名体制で、現地に根付いたメンバーによる伴走型ハンズオン支援
<概要>
・アジアを中心とする世界21拠点、コンサルタント800名体制を有する、日系独立系では最大級のコンサルティングファーム(東証上場)
<サービス特長>
・現地に根付いたローカルメンバーと日本人メンバーが協働した伴走型ハンズオン支援、顧客ニーズに応じた柔軟な現地対応が可能
・マッキンゼー/ボストンコンサルティンググループ/ゴールドマンサックス/P&G/Google出身者が、グローバルノウハウを提供
・コンサルティング事業と併行して、当社グループで展開する自社事業群(パーソナルケア/飲食業/ヘルスケア/卸売/教育など)の海外展開実績に基づく、実践的なアドバイスを提供
<支援スコープ>
・調査/戦略から、現地パートナー発掘、現地拠点/オペレーション構築、M&A、海外営業/顧客獲得、現地事業マネジメントまで、一気通貫で支援
・グローバル企業から中堅/中小/スタートアップ企業まで、企業規模を問わずに多様な海外進出ニーズに応じたソリューションを提供
・B2B領域(商社/卸売/製造/自動車/物流/化学/建設/テクノロジー)、B2C領域(小売/パーソナルケア/ヘルスケア/食品/店舗サービス/エンターテイメントなど)で、3,000件以上の豊富なプロジェクト実績を有する
<主要サービスメニュー>
① 初期投資を抑えつつ、海外取引拡大を通した円安メリットの最大化を目的とする、デジタルマーケティングを活用した海外潜在顧客発掘、および、海外販路開拓支援
② 現地市場で不足する機能を補完し、海外事業の立ち上げ&立て直しを伴走型で支援するプロフェッショナル人材派遣
③ アジア圏での「デジタル」ビジネス事業機会の抽出&評価、戦略構築から事業立ち上げまでの海外事業デジタルトランスフォーメーションに係るトータルサポート
④ 市場環境変動に即した手触り感あるインサイトを抽出する海外市場調査&参入戦略構築
⑤ アジア特有の中小案件M&A案件発掘から交渉/実行/PMIまでをカバーする海外M&A一気通貫支援
⑥ 既存サプライチェーン体制の分析/評価/最適化、および、直接材&間接材の調達コスト削減 -
株式会社ダズ・インターナショナル
東南アジア・東アジア・欧米進出の伴走&現地メンバーでの支援が強み
私たちは企業の海外挑戦を設計→実行→着地まで伴走支援いたします。
これまでの企業支援数は1,500以上です。
私たちは『どの国が最適か?』から始まる海外進出のゼロ→イチから、
海外進出後のマーケティング課題も現地にて一貫支援いたします。
※支援主要各国現地にメンバーを配置し、海外進出後も支援できる体制
------------------------------------
■サポート対象国(グループ別)
↳アジア①(タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・インドネシア・フィリピン・ラオス)
↳アジア②(日本・香港・シンガポール・台湾・韓国)
↳アジア③(ドバイ・サウジアラビア・インドバングラデシュ・モンゴル・ミャンマー)
↳欧米(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)
※サポート内容により、対応の可否や得意・不得意な分野はあります。
------------------------------------
■対応施策ラインナップ
①"市場把握"サポート
目的は"海外現地を理解し、事業の成功可能性を上げる"こと。
(以下、含まれる施策)
↳市場概況・規制調査
↳競合調査
↳企業信用調査
↳現地視察企画・アテンド
②"集客活動"サポート
目的は"海外現地で売れるためのマーケティング活動を確立"すること。
↳多言語サイト制作
↳EC運用
↳SNS運用
↳広告運用(Google/Metaなど)
↳インフルエンサー施策
↳画像・動画コンテンツ制作
③"販路構築"サポート
目的は"海外現地で最適な海外パートナーとの取引を創出"すること。
↳商談向け資料制作
↳企業リストアップ
↳アポイント取得
↳商談創出・交渉サポート
↳契約サポート
④"体制構築"サポート
目的は"海外現地で活動するために必要な土台"をつくること。
↳会社設立(登記・銀行口座)
↳ビザ申請サポート
↳不動産探索(オフィス・倉庫・店舗・住居)
↳店舗開業パッケージ(許認可・内装・採用・集客)
↳人材採用支援(現地スタッフ採用支援)
------------------------------------ -
合同会社サウスポイント
世界と日本をつなぐ架け橋「沖縄」から海外展開を支援しています
2017年7月日本・沖縄と海外の万国津梁の架け橋を目指して、企業の海外展開支援を目的として沖縄・那覇で設立。アジア・欧州を中心に沖縄県内・沖縄県外企業の海外進出・国際展開のサポートを実施しています。2022年7月には観光産業の伸びの著しい石垣市に八重山事務所を開設しております。
沖縄をハブに、台湾・中国・香港・ベトナム・タイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・オーストラリア・ニュージーランド・イギリス・ドイツ・ブラジル各国にパートナーエージェントを配置し、アメリカ合衆国・インドは提携先を設けていますので、現地でも情報収集、視察等も直接支援可能、幅広く皆様の海外展開とインバウンド事業をサポートしております。 -
ワールド・モード・ホールディングス株式会社
国内外1,500社以上の実績!ファッション・ビューティー業界特化の支援
私たちワールド・モード・ホールディングスは、日本で唯一のファッション・ビューティー業界に特化したソリューション・グループです。
業界に精通したプロフェッショナルが集結し、従来の枠を超えたトータルサポートを実現。戦略企画、マーケティング、プロモーション、店舗運営、人材採用・育成など、多角的な視点から実践的なソリューションを提供しています。
近年では、カフェ・飲食、小売以外の業態や海外市場にも対応領域を拡大。エリア・業種を問わず、クライアントの課題に寄り添った柔軟な支援を行っています。
今後も、「顧客に寄り添い、目標を共有するパートナー」として、そして「ワンストップで価値を届けるプロフェッショナル集団」として、進化を続けてまいります。
<グループ会社>
株式会社iDA、株式会社AIAD、株式会社フォー・アンビション、株式会社BRUSH、VISUAL MERCHANDISING STUDIO株式会社、株式会社AIAD LAB、株式会社 双葉通信社、WORLD MODE ASIA PACIFIC -
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。
実績:
東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)
東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)
南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)
北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)
中東(トルコ、サウジアラビア等)
ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)
アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等)