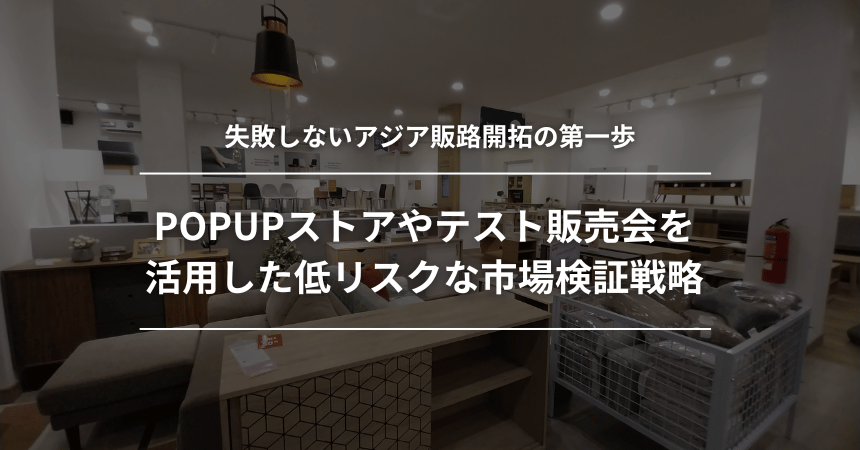HSコードとは?一覧表・調べ方・種類・必要性まで徹底解説

「HSコード」とは、HS条約という「商品の名称及び分類についての統一システム(Harmonized Commodity Description and Coding System)に関する国際条約」に基づいて定められたコード番号です。
HSコードとは、輸出入の際に、それらの商品を分類する番号であり、その番号から、その商品の関税率や、原産地規則(貨物の原産地(国籍)を決定するためのルール)を調べることができます。
つまり、HSコードとは、国際貿易における世界共通の分類番号であり、輸出入されるさまざまな物品に固有の分類番号をつけることで、その物品がどのような物なのか理解できるようにした〝世界共通の番号(コード)〟なのです。
HSコードは、国際貿易において非常に重要で、関税に深く関わるものです。TPPやEPAといった自由貿易協定が活性化することで、今後、輸出入において「原産地証明書」などを用意する必要性がさらに高まります。
とは言え、HSコードは膨大な数となっており、それら全てを覚えることは決して容易なことではありません。しかし、おおまかにHSコードの概要だけでも知ることで、国際貿易における輸出入業務の理解はさらに深まります。
本テキストで「HSコードの基礎知識」について学びましょう。
▼ HSコードとは?一覧表・調べ方・種類・必要性まで徹底解説
- 1. HSコードとは
- 2. なぜHSコードが必要なのか?
- 3. HSコードは「EPA」に必要な「原産地証明書」に記載しなければならない
- 4. HSコードの決まり方
- 5. HSコードの調べ方/検索方法
- 6. HSコードの種類 / HSコード一覧
- 7. 日本企業の「輸出入・貿易・通関」に関する最新トレンド
▼アナタの海外ビジネスを成功させるために
1. HSコードとは
HSコードとは国際貿易における世界共通の分類番号
HSコード(Harmonized System Code)は、国際貿易における物品の分類を統一するために使用される国際的な標準コードです。このコードは、輸出入されるあらゆる物品に固有の番号を付与することで、その物品がどのようなものであるかを世界共通で理解できるようにしています。
HSコードの目的は、各国の通関手続きにおいて統一的な物品の分類を行うことで、貿易を円滑にし、国際貿易統計の一貫性を確保することです。このコードを使用することで、特定の物品に対する関税率の決定や、原産地規則(特定の物品の原産地を判定するためのルール)の適用を容易にします。つまり、HSコードは、貿易に関わる関税手続きや国際的な規制の適用に不可欠な役割を果たします。
HSコードは世界税関機構(WCO)が管理している
「HSコード」という名称は、「商品の名称及び分類についての統一システム(Harmonized Commodity Description and Coding System)に関する国際条約(HS条約)」に基づいて定められたものであり、世界税関機構(WCO)が管理しています。HSコードは「HS番号」「輸出入統計品目番号」「関税番号」「税番」などの異なる名称でも呼ばれることがあります。
HSコードは、6桁の基本コードから成り立ち、国際的に統一されていますが、各国はその基本コードに基づいて独自の細分化を行い、さらなる桁数を追加することがあります。この統一されたシステムにより、世界中の税関が共通の分類基準に従って商品を評価し、取り扱うことが可能になります。
HS条約とは
HS条約(Harmonized Commodity Description and Coding Systemに関する国際条約)は、物品の国際貿易における名称および分類を統一するための国際的な基準を定めた条約です。この条約は、関税及び貿易の管理を容易にし、貿易統計の整合性を確保するために、世界税関機構(WCO:World Customs Organization)が管理しています。
1988年に発効されたHS条約の目的は、貿易に使用される物品の分類の統一を図り、国際貿易をより円滑にすることです。これにより、各国の税関は統一された基準に基づいて物品を分類し、関税や輸出入管理を行うことができるようになっています。HS条約に基づくコード、すなわちHSコードは、輸出入手続きにおける共通の言語として機能し、貿易の透明性と効率性を向上させます。
現状の最新版はHS2022
2024年現在、HS条約には日本を含む158の締約国が加盟しており、実際には200以上の国と地域がHSコードを使用しています。HSコードは5年ごとに改訂され、最新のバージョンは2022年1月に発効したHS2022です。
HS2022には、環境問題や新しい製品カテゴリの認識など、現在の貿易や国際的な懸念事項に対応するため、351件の改訂が含まれています。例えば、電子廃棄物(e-waste)、新しいタバコやニコチン製品、ドローン、特定の化学物質(化学兵器禁止条約やロッテルダム条約などで規制されているもの)に関する新しい分類規定が追加されました。また、感染症の迅速診断キットや臨床試験用キットの分類も簡素化されました。
次の改訂版である「HS2027」の準備が現在進行中であり、2024年末までに最終的な議論と修正が行われる予定です。
2. なぜHSコードが必要なのか?
HSコードで関税率や原産地規則を迅速かつ正確に調べることができる
では、そもそもなぜHSコードは必要なのでしょうか?
同じ物品であるにもかかわらず、名称が異なっていたり、そもそも製品名だけではどのような物品なのかわかりづらかったりすると困ってしまいます…。そういった際に、世界共通のHSコードが役に立つのです。
商品を輸出入する際、各物品はいずれかの品目コードに分類され、コードからは関税率、原産地規則を調べることができます。固有の番号によって物品がどういったものなのかを示すHSコードは、関税を決めたり、規制品や制限品を見分けるために使われたりする、輸出入申告に必要不可欠なものです。
さらに、HSコードは各国政府が輸出入の統計データを収集・分析するためにも利用されており、国際貿易の透明性と効率性を高める重要なツールとなっています。
3. HSコードは「EPA」に必要な「原産地証明書」に記載しなければならない
EPAで関税の優遇処置を受けるにはHSコードを知っておく必要がある
HSコードは、国際貿易において非常に重要で、関税に深く関わるものです。TPPやEPAといったFTA(自由貿易協定)が活性化しつつある現在、輸出入において「原産地証明書」などを用意する必要性がさらに高まります。
そもそも「EPA(※1)」とは、経済連携協定(Economic Partnership Agreement)の略称で、特定の国や地域間の貿易や投資を促進するための条約です。日本企業がEPAを活用すれば、国や商品によっては輸出入時の関税が削減されるケースが多々あるので、貿易事業者はEPAを知っておく必要があります。
そしてEPAを活用するには「原産地証明書」が必要です。原産地証明書とは、輸出入の際の貨物の国籍を証明する書類を指しますが、EPAに基づく原産資格を満たしていることを、原産地証明書で証明することで、通常の関税率よりも低い関税率の適用を受けることができます。
整理すると…
「EPA」を活用する際に「原産地証明書」が必要であり、さらに原産地証明書に「HSコード」を記載する必要があるのです。つまり、EPAを活用して関税の優遇処置を受けるには、HSコードを知っておくと理解も深まる
…ということになります。
EPAについての詳細は…
『EPAの基礎知識 |貿易におけるEPAの活用メリット&EPAの利用方法を解説』
…で解説しています。
原産地証明書についての詳細は…
『「原産地証明書」の基礎知識 | 〈 証明書の種類→認定基準→取得方法〉の3ステップで解説』
…をぜひご覧ください。
※1
EPA:
経済連携協定(Economic Partnership Agreement)が正式名称。特定の国や地域間の貿易や投資を促進するための条約
※2
原産地証明書:
貨物の原産地を証明する書類のこと。英語では「Certificate of Origin」
「HTSコード」「NCMコード」とは?
200以上の国や地域で使われているHSコードですが、HSコードを使わない国もあります。例えばアメリカとブラジルはそれぞれ独自のコードである「HTSコード」「NCMコード」を使用しています。下記よりそれぞれ見ていきましょう。
■HTSコード
HTSコードはアメリカのHSコードです。HTSとは「Harmonized Tariff Schedule」の略。国際的に統一されている関税システムを米国に適用する為につくられたもので、互換性のないコードです。
基本品目分類番号が6桁であるHSコードに対し、HTSコードは基本品目分類番号が4桁となっており、4桁の末尾に2桁と4桁の拡張コードをつけ、品目の確定が行われます。
■NCMコード
ブラジルなど、南米の貿易圏である「メルコスール(南米南部共同市場)」の加盟国では、MCMコードを使用しています。NCMは「Nomenclature Comum do MERCOSUL」の頭文字をとったものです。合計8桁のコードですが、6桁まではHSコードと同じです。
4. HSコードの決まり方
HSコードは誰がどのようにして決める?
HSコードが国際貿易になくてはならないコード番号であることはご理解いただけたと思います。では、HSコードとは誰がどのように決めるのでしょうか?
輸出入する品目のHSコードは、輸出者が、つまりは輸出する本人が決めます。実行関税率表や輸出統計品目表などを確認し、品目の特徴を照らし合わせて最も適当なHSコードを選ぶ必要がありますが、慣れていないと決して容易ではない作業です。そこで、税関の事前教示制度を活用したり、専門の業者に任せたり…というケースが多々あります。
HSコードを決めるための世界共通のルールとは?
国際貿易で必要不可欠なHSコードには当然世界共通のルールが存在します。
各国の関税率表は、HS条約の品目表(HS)に基づいて作成されており、一般に、関税率表の6桁の号までを「HSコード」と呼んでいます。
HSコードは「部」「類」「項」「号」で構成されており、HSコードは輸出と輸入ではコードが微妙に異なります。また、HS条約に基づいた世界共通の番号は6桁までとなっています。6桁以降は各国が任意の桁数を付け足して活用しています。
アップライトピアノのHSコードの構造
では、この「部」「類」「項」「号」について、HSコードが920110のアップライトピアノを例に見ていきましょう。

まず、6桁の上2桁である「92」の部分を「類」と言います。この例で言うと、類「92」は「楽器並びにその部分品及び付属品」となります。
続く2桁の「01」は「ピアノ(自動ピアノを含む)、ハープシコードその他鍵盤のある楽器」となり、「類」を含む上4桁の「9201」の部分を「項」と言います。
さらに2桁の「10」が加わり「類」と「項」含めた6桁の「号」である「920110」が「アップライトピアノ」となります。(※ちなみに、ピアノはアップライトと、グランドピアノとで6桁のコードが変わり、グランドピアノは「920120」となります)
7桁以降は国ごとに定められた細分方法が使われており、日本では上6桁の号に「統計細分=下3桁」を加えた番号「000」からなる9桁である「920110000」がアップライトピアノとして定められています。
そして「部」ですが、これは全ての貿易対象品目を21に分けた大分類を指します。こちら「部」については後ほど詳しく説明します。
順番として「部」→「類」→「項」→「号」の順に、分類が細かくなっていきます。
5. HSコードの調べ方/検索方法
HSコードの検索の仕方とは?
このセクションではHSコードの調べ方について解説します。
HSコードは、輸出と輸入、さらに国などによって変わります。したがってHSコードを調べるには以下の3つのポイントに注意しなければなりません。
① 日本のHSコードを調べる:輸入するとき
② 日本からのHSコードを調べる:輸出するとき
③ 取り引きする国の輸出入のHSコードをを調べる:取り引きする国の関税やEPAの原産地規則の確認
HSコードは日本関税協会のWebタリフ
でも調べることができますが、分類の見方などに慣れていないと探すのはなかなか大変です。
そこで、税関の事前教示制度を利用することをおすすめします。事前教示制度とは、輸入の前に税関に対して、貨物の関税分類(税番)や関税率などについての照会を文書で行い、文書によって回答を受けることができる制度です。
Eメールでも事前教示制度を受けることができますが、口頭による事前教示と同じ扱いとなり、輸入申告時の税関の審査において尊重されるものではないことに注意が必要です。ただし、この場合でも特定の手続きを踏むことで、文書による事前教示と同等の申請にすることができます。
また、製法、成分割合など、機密事項がある場合にはセキュリティの問題がありますので、Eメールによる照会はできません。
さらに詳しく知りたい場合は…税関サイト「輸出入通関手続きの便利な制度」
必要な文書は…税関のHP 関税法関係[C様式]
などがあります。
ただ、いずれにせよ、HSコードを自分で調べて書類に記入したとして、それが誤ったHSコードであった場合、本来の関税額と異なってしまうので、輸入者に確認してもらったり、あるいは通関業者に依頼する方法がベターかもしれません。
6. HSコードの種類 / HSコード一覧
HSコードは「部・類・項・号」で構成される
最後にHSコードの種類と一覧について解説します。
HSコードの大分類である「部」は21種類。その中に97の類があり、部の中に項や号があります。
このセクションでは、前項で詳しく解説できなかった、21種類の「部」について見ていきましょう。
第1部 動物(生きているものに限る)及び動物性生産品
第2部 植物性生産品
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
第5部 鉱物性生産品
第6部 化学工業(類似の工業を含む)の生産物
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
第11部 紡織用繊維及びその製品
第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれら
第15部 卑金属及びその製品
第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機
第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第20部 雑品
第21部 美術品、収集品及びこっとう
HSコードの分類要素
すでにご説明したとおり、HSコードは「部」「類」「項」「号」からなっており、大分類である「部」から「類」「項」「号」と品目を細分化して示す構造となっています。
HSコードの一覧表
最後にHSコードの一覧表についてですが、税関サイトにある、輸出統計品目表、輸入統計品目表に記載がありますので、詳しくはこちらをご参照ください。
7. 日本企業の「輸出入・貿易・通関」に関する最新トレンド
「輸出入・貿易・通関」に関する相談が急増
最後に「HSコードの基礎知識」の補足情報として、「日本企業の輸出入・貿易・通関に関する最新トレンド」をご紹介します。
毎年、海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima~出島~」では1年間の進出相談と海外進出企業ならびに、海外進出支援企業を対象に実施したアンケートをもとに「海外進出白書」を作成しています。
下記は「Digima〜出島〜」に寄せられた、海外進出を検討する企業の「輸出入・貿易・通関」に関する相談の「国別割合」「業種別割合」「企業規模別割合」内訳になります。

まず、国別割合では「アメリカ・中国」の2大国の割合が急増しています。その他、「ヨーロッパ」の順位も上がっており、市場規模との連動が見られそうです。また、4番手も「タイ」となっており、すでに進出済みの企業が多い国の割合が大きくなっていることがわかります。
業種別割合では「卸売・小売」の割合が大きく増加しています。
また、最も注目すべきは規模別割合です。「50名以下」の割合が非常に大きくなっており、8割を超えています。
この点から、「小規模事業者が小ロットで海外に製品を送る」という際に、「輸出入・貿易・通関」が大きな課題となっていることが明らかになります。
そもそも、海外にモノを運ぶための方法は主に2つに分けることができます。それは「航空貨物輸送」と「海上貨物輸送」です。その名の通り「航空貨物輸送」は飛行機で貨物を運ぶ方法、「海上貨物輸送」とは船で貨物を運ぶ方法となります。航空貨物輸送のメリットは、飛行機で運ぶため「早い」ことが挙げられます。1日〜1週間で世界中にモノを送ることができます。
ただし、運べるものの大きさや重量は制限され、かつ運賃が高くなっています。海上貨物輸送のメリットは、船で運ぶため、大量に運ぶことができ、安いことです。また、航空貨物輸送と比べ、運べるものの大きさや重量が制限されないことが挙げられます。一方でデメリットは、時間がかかることです。日本―ヨーロッパ間であれば、1カ月程度は必要となります。
また、大量に運ぶことができる反面、コンテナ単位での輸送が軸となっているため、少量を運ぼうとしても輸送会社から断られたり、割高になってしまうことがあります。それこそが、「小規模事業者が小ロットで海外に製品を送る」際の相談が増えていることの要因となっているでしょう。
そのため、輸送会社とのネットワーク提供や交渉を代行してくれる輸出入コンサルといったサービスなども出てきています。しかし、相談件数や内容を鑑みるに、まだまだ大きな課題として残っていると言えます。
…上記の内容をさらに深掘りした日本企業の海外進出動向を「海外進出白書」にて解説しています。
日本企業の海外進出動向の情報以外にも、「海外進出企業の実態アンケート調査」「海外ビジネスの専門家の意識調査」など、全95Pに渡って、日本企業の海外進出に関する最新情報が掲載されている『海外進出白書(2023-2024年版)』。
今なら無料でダウンロードが可能となっております。ぜひ貴社の海外ビジネスにお役立てください!

8. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
貴社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
今回は「HSコードの基礎知識」として、HSコードの種類やルール、実際に輸出入を行う際のHSコードの調べ方や検索方法…などについて解説しました。
グローバル化が進む現代において、貿易をスムーズに進めるために必要不可欠なHSコード。輸出入を考えている製品のHSコードを調べるのは決して容易ではありませんが、税関の事前教示制度など、便利なシステムを活用することで、自分で調べることができます。
とは言え、書類に記入したHSコードが誤りの場合思わぬトラブルが発生する可能性もあります。また輸出入に必要な業務はそれだけではないため、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
「Digima〜出島〜」には厳正な審査を通過した様々な支援を行う優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。
「海外に自社商品を輸出したい」「海外から商材を輸入したい」「通関や輸出入許可の申請をサポートしてほしい」……といった海外ビジネスにおける様々なご質問・ご相談を承っています。
ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、御社にピッタリの海外進出サポートサポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
もっと企業を見る

海外進出・海外ビジネスで
課題を抱えていませんか?
Digima~出島~では海外ビジネス進出サポート企業の無料紹介・
視察アレンジ等の進出支援サービスの提供・
海外ビジネス情報の提供により御社の海外進出を徹底サポート致します。
0120-979-938
海外からのお電話:+81-3-6451-2718
電話相談窓口:平日10:00-18:00
海外進出相談数
22,000件
突破