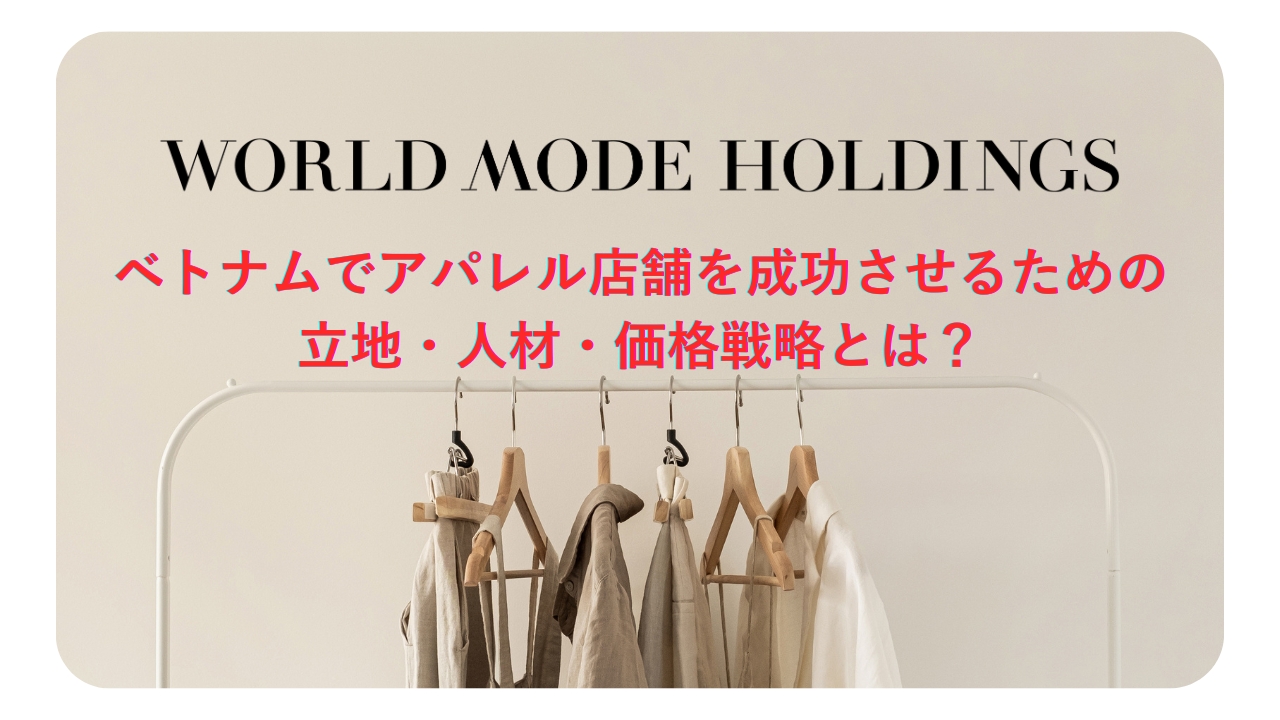ベトナム製造業レポート~成長力・人件費・相互関税リスクを踏まえた拠点戦略の考え方~

ここ数年、東南アジアの中でも製造拠点としての存在感を急速に高めているのがベトナムです。アパレルや家具、電気・電子機器といった労働集約型産業を中心に外資系企業の進出が進み、特に中国の人件費高騰や地政学リスクを背景とした「チャイナ・プラスワン」の移転先として、多くの注目を集めてきました。加えて、若年層人口の多さや労働コストの安さといった要素も、製造業にとっての魅力となっています。
しかしながら、2025年に発表された米国の「相互関税政策」により、ベトナム製造業の立ち位置にも変化の兆しが見られます。対米輸出に対して最大45%の関税が課されることとなり、従来の輸出志向型のビジネスモデルに依存する日系企業にとっては、見直しが必要な局面に差しかかっています。
本記事では、ベトナム製造業の基礎的な状況から、日系企業が見込むメリットと直面するリスク、相互関税による影響、そして他国との比較を通じての再評価ポイントまで、網羅的に解説します。今後のアジア製造拠点戦略を考えるうえで、ベトナムをどう活用するべきか――、その判断材料をお届けします。是非、参考にしてください。
▼ ベトナム製造業レポート~成長力・人件費・相互関税リスクを踏まえた拠点戦略の考え方~
ベトナム製造業の現状と経済的背景
製造業が支えるベトナム経済の基盤
ベトナムは1986年以降のドイモイ政策(刷新政策)によって急速に市場経済化が進み、現在ではGDPの約3割を製造業が占める「ものづくり大国」としての顔を持つまでに成長しています。外資企業による直接投資(FDI)が年間で数百億ドル規模にのぼり、特に製造業への投資が全体の半数以上を占めている点は、同国の成長モデルを象徴しています。
加えて、工業団地の開発や港湾インフラの整備、労働力育成への政策的な後押しも相まって、製造業が安定的な雇用と輸出収入の源となっています。2023年時点での輸出額は約3,700億ドルとされ、そのうち6割以上が製造業製品であり、繊維製品、スマートフォン、PC部品、家具などが主要品目に挙げられます。特にサムスンなど韓国系大手の進出により、電子機器分野が急成長を遂げています。
こうした流れに乗り、日系企業の製造拠点としてもベトナムは確固たる地位を築いていますが、今後は「単なる低コスト拠点」からの脱却と、持続可能な産業基盤への転換が問われるフェーズに入っています。
外資主導の産業構造と韓国・中国の影響力
ベトナム製造業の特徴のひとつは、外資主導型の産業構造にあります。政府は積極的な外資誘致政策を打ち出しており、外資企業には法人税の免除や土地利用の優遇措置が提供されるケースが多く、こうした政策の恩恵を受けて韓国、中国、日本などの企業が製造拠点を多数設立しています。特にサムスンは、北部バクニン省やタイグエン省に大規模なスマートフォン工場を構えており、ベトナムの輸出の2割近くを1社で担うまでになっています。
中国企業も、米中貿易摩擦を契機にベトナムへ生産をシフトさせる動きを強めており、繊維・家具・電子部品などの分野でプレゼンスを拡大しています。このような構造の中で、ベトナム経済は一定の成長を維持してきた一方、国内企業の競争力強化や技術移転が思うように進んでいないという課題も抱えています。
また、外資系企業が集中する北部・中部と、地場産業が多い南部との間では、インフラ整備や労働力の質に差が生じており、地域間の産業格差も見られるようになっています。日本企業が進出する際には、これら外資環境の現状と、地域ごとの産業特性を丁寧に見極めることが必要となるでしょう。
日系企業にとっての魅力と進出動向
人件費の安さと若年労働力の供給力
ベトナムが製造業の進出先として高い注目を集める最大の理由のひとつは、依然としてコスト競争力のある人件費水準です。2024年時点の最低賃金は地域差はあるものの月額約200ドル前後であり、バンコク周辺で月400ドルを超えるタイと比べても、圧倒的な差があります。また、ベトナムは総人口の約6割が35歳未満という非常に若い労働人口構成を持ち、今後数十年にわたり安定的な労働力供給が期待できる点も大きな魅力です。
とくに電子機器やアパレル、靴、家具といった労働集約型産業では、こうしたコスト面と供給面のバランスが企業の競争力に直結します。実際、日系企業の多くは、ベトナムのこうした人材環境を評価し、製造工程の一部、あるいは中核的な生産を同国に委ねる体制を構築しています。工場スタッフの勤勉さや職場定着率の高さも、日本企業の品質管理文化に適応しやすいとされており、現地教育との連携も進みつつあります。
経済特区制度と日系企業の進出傾向
ベトナム政府は外資誘致の一環として、北部や中部、南部に多数の工業団地や経済特区(Economic Zones)を整備しています。これらのエリアでは、法人税の一定期間免除、輸入機械の関税優遇、外資100%出資の許可といったインセンティブが提供されており、日系企業もこれを活用して進出を加速させてきました。
たとえば北部のハイフォン市にあるディンブー経済区には、キヤノンやブリヂストンなどの大手製造企業が工場を構えており、ベトナム北部は日本企業の一大集積地となっています。また、南部ではホーチミン郊外のビンズオン省やドンナイ省に進出する企業が多く、アパレル・食品・日用品などの製造拠点として機能しています。近年では、半導体関連の中核部品製造や高精度部品の加工分野にも日系企業の動きが見られ、単なるローコスト生産ではなく、技術展開型の投資も増えています。
このように、ベトナムは制度面と地理的条件を活かし、日本企業にとって多様な業種・フェーズでの活用が可能な製造拠点へと進化しつつあるといえるでしょう。
ベトナム製造業の課題とリスク
インフラの未整備と物流ボトルネック
近年の外資流入と製造業の拡大により、ベトナムのインフラ整備は急ピッチで進められているものの、依然として物流やエネルギー供給面での課題は残されています。たとえば、主要港湾であるハイフォン港やカトライ港は取扱量が増加しており、輸出入のピーク時には混雑が常態化し、コンテナの遅延や通関処理の停滞が発生することも珍しくありません。これにより、リードタイムの予測が難しくなり、サプライチェーン全体に不確実性が生じる可能性があります。
また、高速道路や鉄道といった国内輸送インフラについても、北部から南部までを貫く物流ネットワークが十分に整備されておらず、工場から港までの輸送に時間とコストがかかるケースが散見されます。さらに、製造拠点の多くが集中している北部・南部では、電力の供給能力を上回る需要が見られる季節もあり、電力制限や計画停電が生産活動に影響を与えるリスクも無視できません。
労働争議・賃金上昇・熟練人材の不足
低コスト労働力の確保がベトナム進出の大きな利点である一方で、近年は労働争議や賃上げ要求が増加しています。特に多くの外国企業が進出する工業団地では、ストライキの発生や待遇改善を求める動きが顕著になっており、人事面での安定運営に一定の工夫が求められるようになっています。
さらに、最低賃金は年率5~7%のペースで引き上げられており、今後数年で東南アジア内でも競争力が相対的に低下する可能性もあります。これに加えて、製造業の高度化が進む中で、必要とされる熟練労働者や中間技術者の人材層が追いついていない現状も課題です。エンジニアや品質管理人材などの採用は、現地の教育水準や人材流動性の問題から、他国と比べてもやや難易度が高いとされています。
このように、労働力の“量”には強みがあるものの、“質”の面では発展途上であり、企業としては教育体制や人材定着戦略をしっかりと構築する必要があります。
行政対応の煩雑さと制度運用の不透明性
ベトナムにおいては、企業運営に関わる許認可手続きが煩雑であることも、外資系企業にとっての課題のひとつです。進出時の法人登記、工場設置、環境認可などは、それぞれの地域行政によって対応に差がある場合があり、同じ制度であっても申請から承認までのスピードや解釈が異なることがあります。
また、税務調査や労働監査に関しても、制度の透明性が十分に確保されていないという声が多く、突然の行政指導や修正申告を求められるケースも報告されています。特に日系企業はコンプライアンス意識が高いため、こうした予測不能な行政対応は大きな経営リスクとなります。
これらの状況を踏まえ、現地での事業運営には、信頼できるローカルパートナーや日系コンサルティング会社との連携、現地法律事務所の活用など、制度面の“読み違え”を防ぐ体制づくりが不可欠です。制度そのものではなく、“運用”に潜むリスクを見逃さない姿勢が求められます。
2025年トランプ政権の相互関税政策とベトナム拠点の影響
ベトナムからの対米輸出に課される45%関税の衝撃
2025年4月、米国トランプ政権が発表した「相互関税政策」は、世界の製造業に激震を走らせました。すべての国に最低10%の関税を課すとともに、各国の対米障壁の度合いに応じて関税率を引き上げるという方針のもと、ベトナム製品には実に45%という高率の関税が課されるとされました。この数字は、中国(54%)に次ぐ高水準であり、ベトナムがこれまで築いてきた“米国輸出の代替拠点”としての立場を大きく揺るがすものとなっています。
ベトナムはスマートフォン、家具、衣料品など、米国向け輸出依存度の高い産業を多く抱えており、関税による価格上昇は現地製品の競争力を大きく損ないます。とりわけ、これまで中国から生産を移転してきた日系・韓国系・台湾系企業にとって、同様の関税網に巻き込まれたことは“避難先”としてのベトナムの意味合いを弱める結果となりました。
チャイナ・プラスワンの再定義とリスク分散の加速
今回の関税政策は、日系企業にとってチャイナ・プラスワン戦略の“再定義”を迫るものです。中国に加えてベトナムまでもが高関税の対象となったことで、米国市場向けの製造戦略は根本的な見直しが必要となっています。これまでは「中国リスクを避けてベトナムへ」というシンプルな選択肢が通用していましたが、今後は「米国向けは米国内または関税率の低い国で」、「ベトナムはそれ以外の市場向けに活用」というような、より高度な拠点分担が求められるでしょう。
また、米国以外の輸出市場への比重を高める動きも活発化しています。たとえば、EUとの自由貿易協定(EVFTA)を活かした欧州向け輸出、あるいは日本・韓国とのEPAを活用した地域内流通への転換など、ベトナムを「グローバル対応型製造拠点」へと柔軟に再設計する必要性が増しています。関税リスクを最小限に抑えながら、製造・販売の地理的多様化を図ることが、中長期的な競争力維持のカギとなるでしょう。
他国との比較とベトナムの立ち位置
タイ・インドネシアとの比較:インフラと制度の成熟度
ベトナムと並んで東南アジアの製造拠点候補としてよく比較されるのが、タイやインドネシアです。タイは東部経済回廊(EEC)などを中心としたインフラ整備が進んでおり、港湾、電力、工業団地の質においてはベトナムを上回ります。行政手続きの透明性や投資制度の安定性にも定評があり、製造拠点としての“完成度の高さ”という点では依然優位にあります。
一方、インドネシアは人口が約2.7億人とASEAN最大であり、今後の内需拡大を見据えた製造展開を視野に入れる企業にとっては魅力的です。しかし、労働法の複雑さや賃上げ圧力、港湾の混雑などインフラ面の制約が大きく、特に中小企業にとっては進出ハードルが高い傾向にあります。
これに対してベトナムは、制度やインフラはまだ発展途上ながら、コストとスピードのバランスが取れた国として位置づけられます。行政制度の不安定さや物流の課題はあるものの、投資環境の改善に向けた政府の姿勢は強く、迅速な対応力と外資企業の受け入れ意欲は評価に値します。
インド・バングラデシュとの比較:将来性と実行力の差
中国からの生産移転先として、近年注目度が増しているのがインドやバングラデシュです。特にインドは豊富な労働力と巨大市場を併せ持つ国として、電子機器・自動車産業を中心に進出の動きが広がっています。ただし、インフラの地域差が大きく、行政手続きの複雑さや土地取得の難しさなど、実行フェーズでの困難さが大きな課題となっています。
バングラデシュは繊維製品の世界的生産拠点として知られており、アパレル企業を中心に進出が進んでいますが、政治的・制度的な不安定性は依然として高く、ベトナムに比べると安定的な運用には注意が必要です。
これらと比べた際のベトナムの強みは、実行スピードの早さと外資企業との相性の良さにあります。外資依存度の高さは裏を返せば、外資との協調姿勢の表れであり、言語・文化面での柔軟性や現場レベルの対応力は、日系企業にとって取り組みやすい環境といえるでしょう。将来性ではインドに劣るかもしれませんが、「実行可能性」と「即戦力」という観点では、依然ベトナムに一日の長があるといえます。
ベトナム製造業の将来性と日系企業の展望
内需拡大と“ローカル向け製造”へのシフト可能性
従来、ベトナムの製造業は輸出志向型モデルに強く依存していましたが、近年は現地の経済成長に伴い、内需をターゲットとした製造戦略の重要性が増しています。中間層の拡大、都市化の進展、生活水準の向上により、家電、自動車、食品、医薬品など、多様な製品への現地ニーズが高まっているのが現状です。
日系企業にとっても、単に「ベトナムで作って海外に売る」という枠を超え、「ベトナムで作り、ベトナムで売る」視点が必要になりつつあります。現地パートナーとの合弁、販路開拓、物流網の整備などを通じて、内需対応型ビジネスへのシフトを検討する企業が増えており、特に生活密着型製品ではすでに成功事例が見られます。これにより、輸出リスクの分散や為替変動の影響軽減も期待できるでしょう。
技術移転と産業構造転換のカギを握る分野
ベトナム政府は、労働集約型から技術集約型への産業転換を明確に掲げており、ハイテク製造分野の育成に力を注いでいます。特に半導体部品、精密加工、電気自動車(EV)関連の分野は、次世代の成長ドライバーとして注目されています。これらの分野では、先進国企業の技術移転が大きな成長の起点となるため、日本の技術力を活かした進出に大きな期待が寄せられています。
たとえば、ある日系電子部品メーカーは、品質管理手法を現地工場に導入することで、ローカル人材の育成と同時に製造品質の底上げに成功しました。このように、技術移転と現地化のバランスが取れたモデルは、日系企業にとって長期的な競争優位の構築につながります。
さらに、グリーンエネルギーやカーボンニュートラル関連の分野でも、日本の環境技術を活用したベトナムでの事業展開は、政策的な支援を受けやすい領域となりつつあります。ベトナム政府の支援策や国際協力スキームを活用しながら、こうした分野でのプレゼンスを高めていくことも、今後の重要な戦略のひとつといえるでしょう。
まとめ|成長国・ベトナムをどう活用するか再定義を
ベトナムは、労働コストの安さや若年労働力の豊富さを背景に、これまで「チャイナ・プラスワン」の代表的な製造拠点として評価されてきました。実際、外資企業による進出は加速し、製造業は同国の経済を牽引する主要産業となっています。しかし、インフラの課題や行政制度の不透明さ、そして2025年に発表された米国の相互関税政策による輸出環境の変化など、従来の成功モデルに陰りが見え始めているのも事実です。
こうした環境変化の中で、ベトナム製造業の活用法も再定義が求められています。今後は、単に「安価に作って輸出する」だけではなく、内需市場の拡大を捉えた販売戦略や、ハイテク分野・グリーン分野への参入による付加価値の創出が鍵となります。ベトナムを“柔軟性のある製造拠点”と位置づけ、地域別・市場別に製品・機能を分担させるような戦略が有効です。
日本企業が持つ技術力や品質管理力は、現地の産業高度化と親和性が高く、共創的なパートナーシップを築ける素地があります。成長国・ベトナムとの関係を見直し、リスクと機会を見極めながら、次なる戦略拠点として再活用する視点が、これからの国際競争力の維持には不可欠です。
なお、「Digima~出島~」には、優良なベトナムビジネスの専門家が多数登録されています。「海外進出無料相談窓口」では、専門のコンシェルジュが御社の課題をヒアリングし、最適な専門家をご紹介いたします。是非お気軽にご相談ください。
本記事が、ベトナム進出・現地展開を検討される日本企業の皆様にとって、実務の一助となれば幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
27000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
オススメの海外進出サポート企業
-
YCP
グローバル22拠点✕800名体制で、現地に根付いたメンバーによる伴走型ハンズオン支援
<概要>
・アジアを中心とする世界21拠点、コンサルタント800名体制を有する、日系独立系では最大級のコンサルティングファーム(東証上場)
<サービス特長>
・現地に根付いたローカルメンバーと日本人メンバーが協働した伴走型ハンズオン支援、顧客ニーズに応じた柔軟な現地対応が可能
・マッキンゼー/ボストンコンサルティンググループ/ゴールドマンサックス/P&G/Google出身者が、グローバルノウハウを提供
・コンサルティング事業と併行して、当社グループで展開する自社事業群(パーソナルケア/飲食業/ヘルスケア/卸売/教育など)の海外展開実績に基づく、実践的なアドバイスを提供
<支援スコープ>
・調査/戦略から、現地パートナー発掘、現地拠点/オペレーション構築、M&A、海外営業/顧客獲得、現地事業マネジメントまで、一気通貫で支援
・グローバル企業から中堅/中小/スタートアップ企業まで、企業規模を問わずに多様な海外進出ニーズに応じたソリューションを提供
・B2B領域(商社/卸売/製造/自動車/物流/化学/建設/テクノロジー)、B2C領域(小売/パーソナルケア/ヘルスケア/食品/店舗サービス/エンターテイメントなど)で、3,000件以上の豊富なプロジェクト実績を有する
<主要サービスメニュー>
① 初期投資を抑えつつ、海外取引拡大を通した円安メリットの最大化を目的とする、デジタルマーケティングを活用した海外潜在顧客発掘、および、海外販路開拓支援
② 現地市場で不足する機能を補完し、海外事業の立ち上げ&立て直しを伴走型で支援するプロフェッショナル人材派遣
③ アジア圏での「デジタル」ビジネス事業機会の抽出&評価、戦略構築から事業立ち上げまでの海外事業デジタルトランスフォーメーションに係るトータルサポート
④ 市場環境変動に即した手触り感あるインサイトを抽出する海外市場調査&参入戦略構築
⑤ アジア特有の中小案件M&A案件発掘から交渉/実行/PMIまでをカバーする海外M&A一気通貫支援
⑥ 既存サプライチェーン体制の分析/評価/最適化、および、直接材&間接材の調達コスト削減 -
株式会社ダズ・インターナショナル
東南アジア・東アジア・欧米進出の伴走&現地メンバーでの支援が強み
私たちは企業の海外挑戦を設計→実行→着地まで伴走支援いたします。
これまでの企業支援数は1,500以上です。
私たちは『どの国が最適か?』から始まる海外進出のゼロ→イチから、
海外進出後のマーケティング課題も現地にて一貫支援いたします。
※支援主要各国現地にメンバーを配置し、海外進出後も支援できる体制
------------------------------------
■サポート対象国(グループ別)
↳アジア①(タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・インドネシア・フィリピン・ラオス)
↳アジア②(日本・香港・シンガポール・台湾・韓国)
↳アジア③(ドバイ・サウジアラビア・インドバングラデシュ・モンゴル・ミャンマー)
↳欧米(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)
※サポート内容により、対応の可否や得意・不得意な分野はあります。
------------------------------------
■対応施策ラインナップ
①"市場把握"サポート
目的は"海外現地を理解し、事業の成功可能性を上げる"こと。
(以下、含まれる施策)
↳市場概況・規制調査
↳競合調査
↳企業信用調査
↳現地視察企画・アテンド
②"集客活動"サポート
目的は"海外現地で売れるためのマーケティング活動を確立"すること。
↳多言語サイト制作
↳EC運用
↳SNS運用
↳広告運用(Google/Metaなど)
↳インフルエンサー施策
↳画像・動画コンテンツ制作
③"販路構築"サポート
目的は"海外現地で最適な海外パートナーとの取引を創出"すること。
↳商談向け資料制作
↳企業リストアップ
↳アポイント取得
↳商談創出・交渉サポート
↳契約サポート
④"体制構築"サポート
目的は"海外現地で活動するために必要な土台"をつくること。
↳会社設立(登記・銀行口座)
↳ビザ申請サポート
↳不動産探索(オフィス・倉庫・店舗・住居)
↳店舗開業パッケージ(許認可・内装・採用・集客)
↳人材採用支援(現地スタッフ採用支援)
------------------------------------ -
合同会社サウスポイント
世界と日本をつなぐ架け橋「沖縄」から海外展開を支援しています
2017年7月日本・沖縄と海外の万国津梁の架け橋を目指して、企業の海外展開支援を目的として沖縄・那覇で設立。アジア・欧州を中心に沖縄県内・沖縄県外企業の海外進出・国際展開のサポートを実施しています。2022年7月には観光産業の伸びの著しい石垣市に八重山事務所を開設しております。
沖縄をハブに、台湾・中国・香港・ベトナム・タイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・オーストラリア・ニュージーランド・イギリス・ドイツ・ブラジル各国にパートナーエージェントを配置し、アメリカ合衆国・インドは提携先を設けていますので、現地でも情報収集、視察等も直接支援可能、幅広く皆様の海外展開とインバウンド事業をサポートしております。 -
ワールド・モード・ホールディングス株式会社
国内外1,500社以上の実績!ファッション・ビューティー業界特化の支援
私たちワールド・モード・ホールディングスは、日本で唯一のファッション・ビューティー業界に特化したソリューション・グループです。
業界に精通したプロフェッショナルが集結し、従来の枠を超えたトータルサポートを実現。戦略企画、マーケティング、プロモーション、店舗運営、人材採用・育成など、多角的な視点から実践的なソリューションを提供しています。
近年では、カフェ・飲食、小売以外の業態や海外市場にも対応領域を拡大。エリア・業種を問わず、クライアントの課題に寄り添った柔軟な支援を行っています。
今後も、「顧客に寄り添い、目標を共有するパートナー」として、そして「ワンストップで価値を届けるプロフェッショナル集団」として、進化を続けてまいります。
<グループ会社>
株式会社iDA、株式会社AIAD、株式会社フォー・アンビション、株式会社BRUSH、VISUAL MERCHANDISING STUDIO株式会社、株式会社AIAD LAB、株式会社 双葉通信社、WORLD MODE ASIA PACIFIC -
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。
実績:
東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)
東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)
南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)
北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)
中東(トルコ、サウジアラビア等)
ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)
アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等)